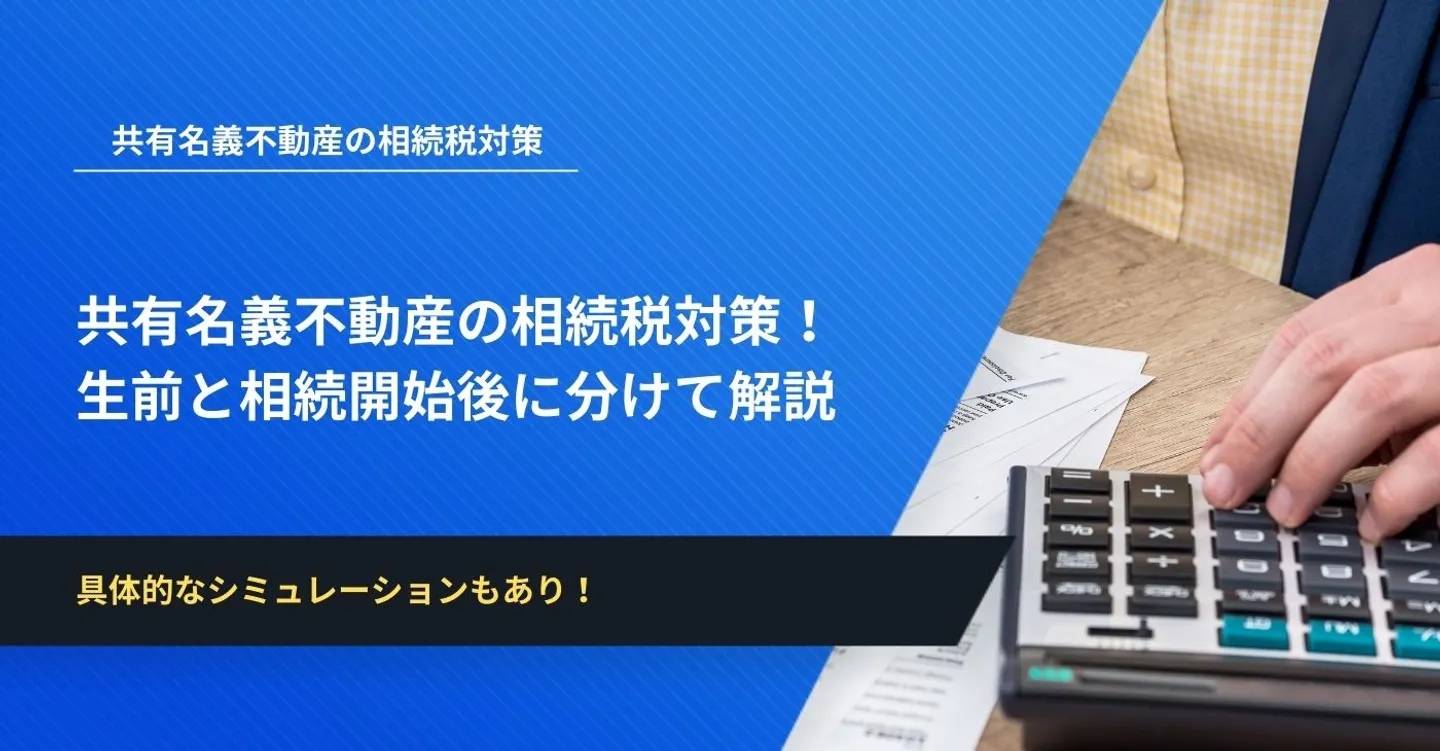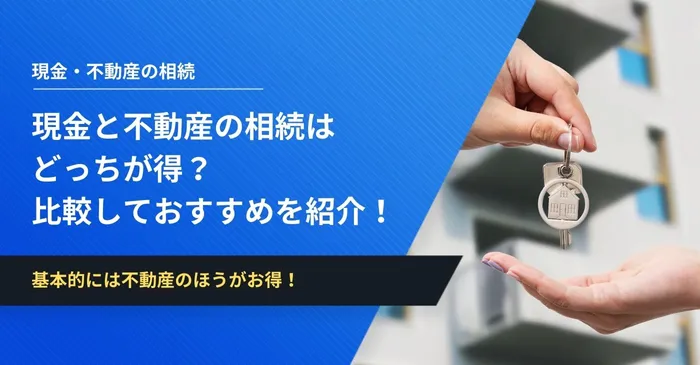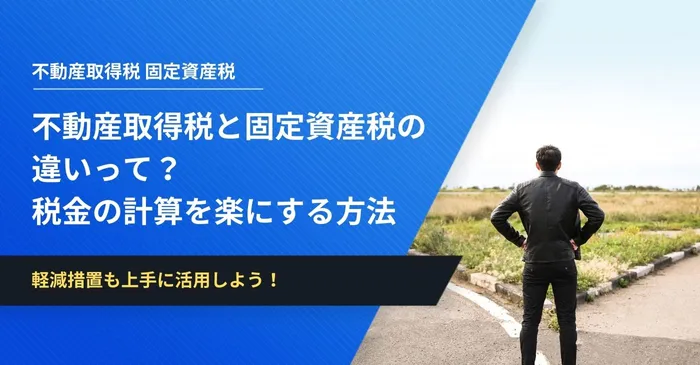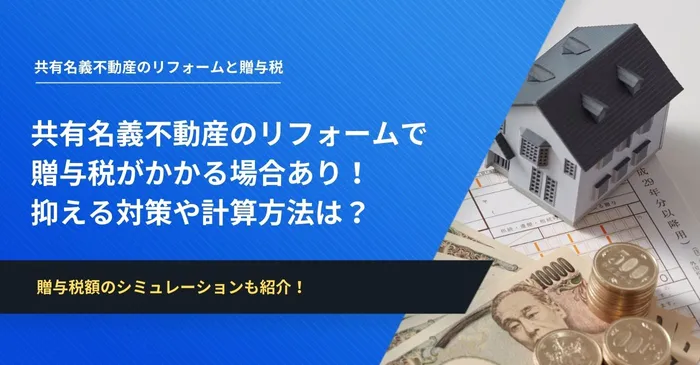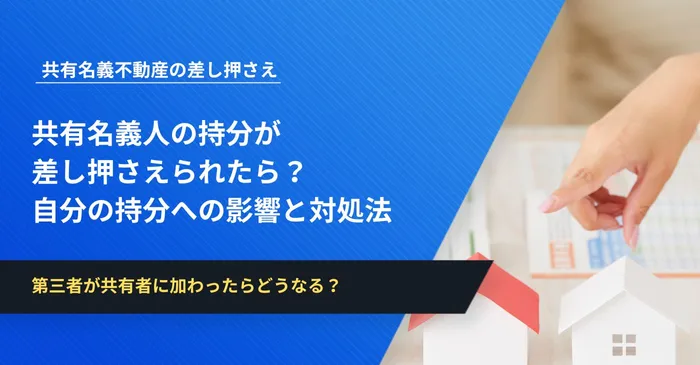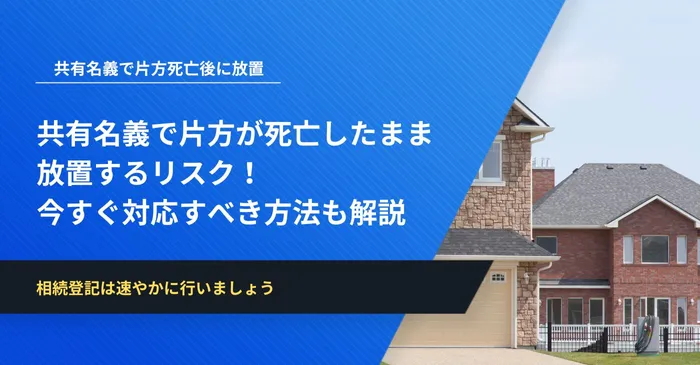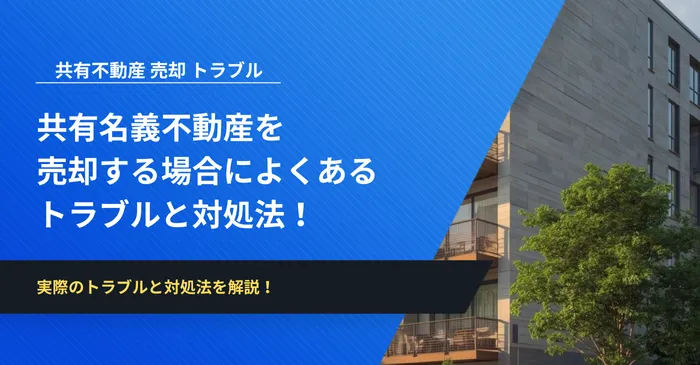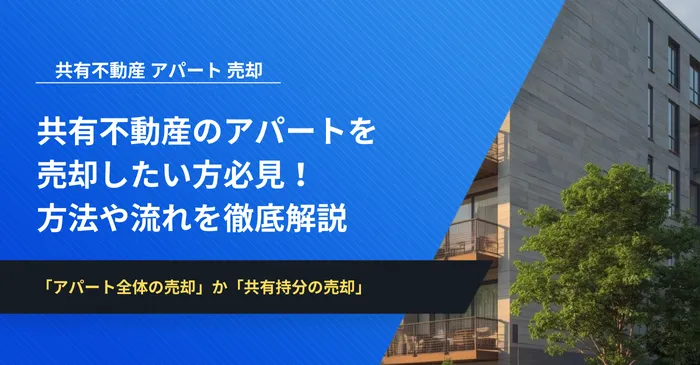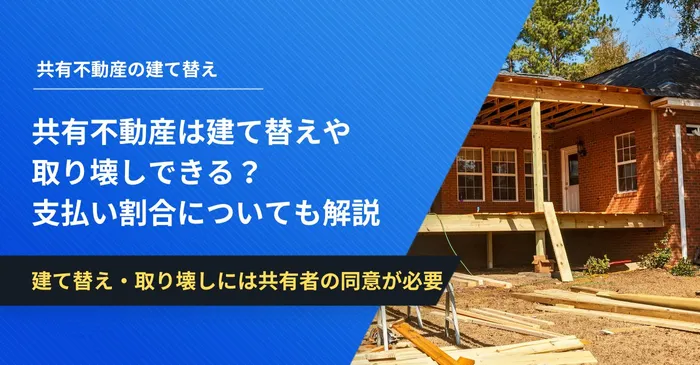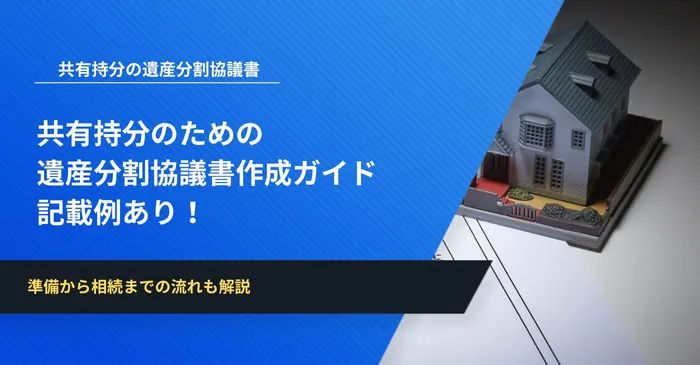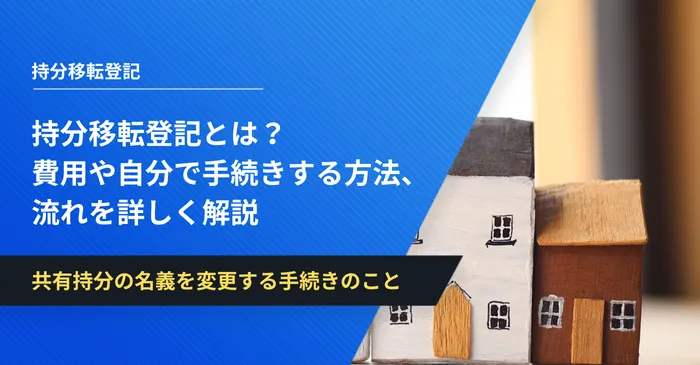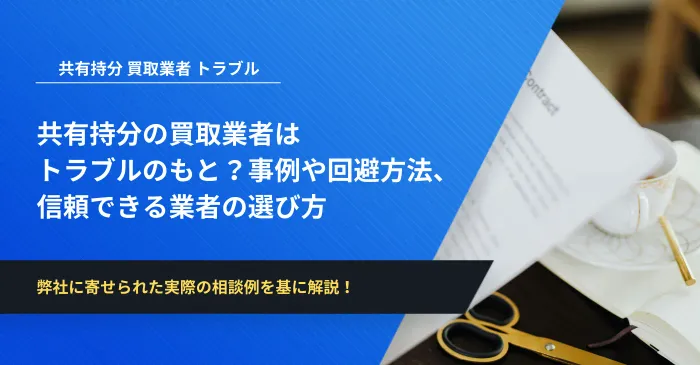不動産を共有名義にすることで相続税対策になると言われる理由とは?
不動産を共有名義にすることが相続税対策になると言われる理由は、主に2つあります。
一つ目は、相続財産を複数人で分散させることで、基礎控除や各種特例を有効活用できるためです。相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除があり、この金額を超えなければ相続税はかかりません。また、小規模宅地等の特例を適用すれば、居住用の土地は330平方メートルまで評価額を80%減額できます。これらの制度を考慮すると、多くの場合は相続税が発生しないか、発生しても少額で済むケースが多いです。
二つ目は、共有持分のみを相続する場合、評価額が下がる傾向があることです。不動産の持分だけを所有していても、他の共有者の同意なしには自由に売却や活用ができません。そのため「利用価値に乏しい」と判断され、不動産全体の評価額よりも持分の評価額は低くなりやすいのです。
ただし、共有名義には将来的なリスクも伴うため、安易に共有名義にすることはおすすめできません。共有者間での意見の対立、不動産の売却や活用の制約、共有者が増え続けることによる管理の複雑化など、相続税の節税効果以上のデメリットが生じる可能性もあります。
【生前】共有名義の相続税対策:生前贈与で持分を一方の共有者に移転しておく
共有名義不動産の相続税対策として、生前贈与により片方の共有者の持分をもう一方の共有者に移転しておくことで、相続財産を減らせる可能性があります。
たとえば、夫婦で共有している不動産について、夫の持分を生前に妻へ贈与しておけば、夫が亡くなった際の相続財産が減り、相続税の負担を軽減できます。
生前贈与の方法には、「暦年贈与」と「相続時精算課税」の2種類があります。それぞれ異なる特徴があるため、贈与する財産の額や状況に応じて使い分けることが重要です。
暦年贈与は年間110万円までの基礎控除を活用する方法で、長期的な計画が必要です。一方、相続時精算課税は2,500万円までの特別控除を一度に使える制度ですが、相続時に贈与財産が加算される点に注意が必要です。
どちらの方法を選ぶかは、贈与する持分の評価額、贈与者の年齢、将来的な相続税の見込みなどを総合的に判断して決めることが大切です。
暦年贈与:基礎控除110万円の範囲内なら贈与税がかからない
暦年贈与とは、年間110万円までの贈与であれば贈与税がかからない制度です。この基礎控除を活用することで、贈与税を負担することなく財産を移転できます。
共有持分の評価額が110万円以下であれば、贈与税を負担せずに持分を移転できます。また、評価額が110万円を超える場合でも、毎年110万円以内で少しずつ持分を贈与していくことで、計画的に相続財産を減らせます。
なお、贈与税の基礎控除は「贈与を受ける人」1人あたり年間110万円です。つまり、同じ人が複数の人から贈与を受けた場合でも、合計で110万円を超えると贈与税がかかります。一方、贈与する側から見れば、複数の人に110万円ずつ贈与しても、それぞれの受贈者が基礎控除の範囲内であれば贈与税は発生しません。
ただし、暦年贈与を活用する際にはいくつかの注意点があるため、計画的に進めることが重要です。
【注意①】相続開始前の7年以内に贈与された財産は相続税の課税対象となる
令和6年1月1日以降に行われた暦年贈与は、相続開始前の7年以内に贈与された財産が相続税の課税対象となります。従来は3年以内だったのですが、令和5年度の税制改正により7年以内に延長されました。
これは、亡くなる直前に駆け込みで贈与を行うことで相続税を回避することを防ぐためのルールです。たとえば、父が亡くなる5年前に子どもへ110万円を贈与していた場合、その110万円は相続財産に加算されて相続税が計算されます。
ただし、7年以内の贈与すべてが加算されるわけではなく、合計100万円までは加算されません。また、贈与時に贈与税を支払っていた場合は、相続税から控除されるため二重課税にはなりません。
早めに生前贈与を開始することで、相続税の課税対象となるリスクを減らせるため、長期的な計画が重要です。
【注意②】定期贈与とみなされると贈与税が課される可能性がある
毎年同じ金額を同じ時期に贈与すると、定期贈与とみなされ、初年度に一括で贈与税が課される可能性があります。定期贈与とは「最初から一定期間にわたって一定額を贈与することを約束していた贈与」のことです。
たとえば、「10年間にわたって毎年110万円ずつ贈与する」という約束をしていた場合、合計1,100万円の贈与を初年度に受けたとみなされ、初年度に多額の贈与税が課される可能性があるのです。
定期贈与とみなされないためには、以下のような工夫が必要です。
- 毎年の贈与時期や金額を変える
- 贈与のたびに贈与契約書を作成する
- あえて基礎控除を超える金額を贈与して贈与税の申告を行う
毎回贈与契約書を作成し、その都度贈与を行っていることを証明することが有効です。贈与契約書には、贈与の日付、贈与する財産の内容、贈与者と受贈者の署名捺印などを記載しておきましょう。
相続時精算課税:毎年110万円の基礎控除と2,500万円の特別控除が利用できる
相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円までの特別控除が受けられます。さらに令和6年以降は、年間110万円の基礎控除も新設され、この基礎控除分については相続財産への加算が不要となりました。
この制度は、直系尊属(父母や祖父母)から18歳以上の子や孫への贈与に適用されます。「基礎控除額110万円+特別控除額2,500万円」を超える部分に対しては、一律で20%の贈与税が課されます。
相続時には、贈与時の価額で相続財産に加算され相続税が計算される点に注意が必要です。つまり、贈与税は軽減されますが、最終的には相続税として清算される仕組みです。
この制度は、将来値上がりが見込まれる財産の贈与に有利ですが、一度選択すると暦年課税に戻せないため慎重な判断が必要です。
【注意1】相続時精算課税制度を利用するには申請が必要
相続時精算課税制度を利用するには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに確定申告が必要です。確定申告の際に、「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
「相続時精算課税選択届出書」の提出時には、以下の書類を添付します。
- 受贈者の戸籍謄本(または抄本)
- 贈与者の住民票の写しまたは戸籍の附票の写し
- その他必要に応じた一定の書類
申請を忘れると制度を利用できず、通常の贈与税が課されるため注意が必要です。
【注意2】同じ贈与者からの贈与は暦年課税へ切り替えられない
一度、相続時精算課税制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与はすべて相続時精算課税制度が適用され、暦年課税への切り替えはできません。
たとえば、父からの贈与について相続時精算課税制度を選択した場合、その後の父からの贈与はすべて相続時精算課税制度が適用されます。ただし、母からの贈与については別途選択できるため、父と母で異なる制度を利用することは可能です。
夫婦間贈与なら最高2,000万円の配偶者控除を活用できる
夫婦間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与する場合、最高2,000万円の配偶者控除が受けられます。暦年贈与の基礎控除110万円と併用できるため、最大2,110万円まで非課税で贈与できます。
この配偶者控除を受けるための要件は以下の通りです。
- 婚姻期間が20年以上であること
- 居住用不動産またはその取得資金の贈与であること
- 贈与を受けた翌年3月15日までに居住開始し、引き続き居住する見込みであること
配偶者控除を利用するには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに確定申告が必要です。
以下に、配偶者控除を受けるための贈与税の申告手続きの流れをまとめました。
| 手続きの段階 |
内容 |
期限 |
| 贈与の実行 |
居住用不動産またはその取得資金を配偶者へ贈与する |
- |
| 居住開始 |
贈与を受けた翌年3月15日までに居住を開始する |
贈与を受けた翌年3月15日まで |
| 確定申告 |
贈与税の申告書と必要書類を税務署に提出する |
贈与を受けた翌年2月1日~3月15日 |
| 添付書類 |
戸籍謄本、居住用不動産の登記事項証明書など |
確定申告時に提出 |
【補足】共有持分を贈与する場合は「不動産取得税」もかかる
共有持分を贈与する場合、贈与税とは別に不動産取得税が課されます。不動産取得税は、土地や建物を取得したときに都道府県が課す税金で、贈与によって不動産を取得した場合も対象となります。
不動産取得税の税率は、以下の通りです。
| 不動産の種類 |
税率 |
| 土地 |
3% |
| 住宅(居住用建物) |
3% |
| 住宅以外の建物 |
4% |
(出典:不動産取得税|愛知県)
税率は不動産の固定資産税評価額に対して適用されます。たとえば、固定資産税評価額が2,000万円の土地の持分50%(評価額1,000万円)を贈与された場合、不動産取得税は「1,000万円×3%=30万円」となります。
なお、不動産取得税は贈与を受けた人が負担します。贈与税とあわせて、受贈者の負担が大きくなる可能性があるため、事前に税額を試算しておくことが重要です。
【相続開始後】共有名義の相続税対策:「小規模宅地等の特例」を利用する
小規模宅地等の特例を利用すれば、相続税評価額を最大80%減額できます。共有名義不動産でも要件を満たせば適用可能なため、相続税の負担を大幅に軽減できる非常に効果的な制度です。
この特例の対象となる宅地は、特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等・特定居住用宅地等・貸付事業用宅地等の4種類があり、それぞれ対象者と適用要件が異なります。詳しい適用対象者と適用要件については、国税庁のホームページで確認できます。
居住用の宅地の場合は、配偶者は同居していなくても適用されますが、そのほか親族は基本的に同居している必要があります。同居していなくても適用されるケースはありますが、適用要件が厳しくなる点に注意が必要です。
共有名義不動産の場合、取得者ごとに要件を満たすかどうか判定する必要があるため、事前に専門家に相談することをおすすめします。
被相続人の「共有持分」に対して最大80%の減額が適用される
特定居住用宅地等の場合、330㎡まで80%減額されます。たとえば、評価額5,000万円の土地(面積200㎡)を相続した場合、特例を適用すれば評価額は1,000万円となり、4,000万円分の評価額が減額されます。
この特例の適用要件として、主に以下の点が求められます。
- 被相続人の配偶者または同居親族が相続すること
- 相続税の申告期限まで居住し続けること
- 相続税の申告期限まで所有し続けること
共有名義不動産の場合、被相続人の共有持分のみが特例の対象となります。つまり、被相続人が50%の持分を所有していた場合、その50%の持分に対してのみ80%の減額が適用されるということです。
複数の相続人がいる場合は「取得者ごと」に適用可否を判定する必要がある
複数の相続人が共有持分を相続する場合、取得者ごとに特例の適用要件を満たすかどうか判定する必要があります。
たとえば、配偶者と子が共有持分を相続する際に、配偶者は要件を満たすが子は同居していない場合は、「配偶者の持分のみ」特例が適用されます。
具体的には、以下のような計算になります。
| 相続人 |
取得持分 |
特例適用の可否 |
理由 |
| 配偶者 |
50% |
適用可能 |
配偶者は同居要件が不要 |
| 子 |
50% |
適用不可 |
同居していない |
一方、取得者全員が要件を満たせば、それぞれの持分に対して特例が適用されます。複数の相続人で持分を相続する場合は、誰が相続するかによって税負担が大きく変わる可能性があるため、慎重に検討しましょう。
持分割合と利用状況が異なる場合は「用途ごとの按分計算」が必要
共有名義不動産が居住用と事業用で利用されている場合など、用途が複数ある場合は、用途ごとに按分計算が必要です。
たとえば、1階が店舗、2階が居住用の建物の場合、居住用部分のみが特定居住用宅地等として特例の対象となります。この場合、建物全体の面積に対する居住用部分の面積割合を計算し、その割合に応じて特例を適用します。
按分計算の例を以下にまとめました。
| 用途 |
面積 |
面積割合 |
特例適用 |
| 1階(店舗) |
100㎡ |
50% |
対象外 |
| 2階(居住用) |
100㎡ |
50% |
適用可能 |
複雑なケースが多く、専門的な知識が必要なため、税理士に相談することをおすすめします。誤った計算をすると、本来受けられる特例が受けられなくなったり、過少申告となったりする可能性があるため注意が必要です。
共有名義にすることで変わる相続税のシミュレーション
共有名義不動産全体の相続税評価額は、「土地」と「建物」それぞれの相続税評価額を計算し、最後に合算します。評価額が算出できれば、そこから相続税額を計算できます。
ただし、実際の相続税計算では不動産だけでなく、預貯金や株式など相続財産全体を考慮する必要があります。本項では、共有名義不動産の相続税評価と税額がどのように変わるかを理解するため、不動産部分のみに焦点を当ててシミュレーションします。
また、共有名義にすることで「持分のみ」の評価となり、単独所有よりも評価額が下がる傾向があります。持分だけでは自由に売却や活用ができないため、利用価値が低いと判断されるためです。この点も含めて、以下で具体的なシミュレーションを見ていきましょう。
あくまでも不動産の相続税だけの計算であり、実際の相続税額を算出する際は不動産以外の全財産を考慮しないといけない点にご注意ください。
共有する土地の相続税のシミュレーション
土地の相続税評価額は、原則として路線価方式で算出します。路線価方式は、路線価(1㎡あたりの土地の価格)に土地の面積を乗じて計算する方法です。
共有名義の場合は、算出した評価額に持分割合を乗じることで被相続人の持分の評価額が算出されます。計算式は以下の通りです。
<計算式>
土地の評価額=路線価×土地面積×持分割合
具体的なシミュレーションを見てみましょう。
| 項目 |
内容 |
| 路線価 |
30万円/㎡ |
| 土地面積 |
200㎡ |
| 被相続人の持分 |
1/2(50%) |
| 土地の評価額 |
30万円×200㎡×1/2=3,000万円 |
ただし、実際の評価は持分にすることで下がります。共有持分のみでは自由に売却や活用ができず、利用価値が低いと判断されるためです。実務上、共有持分の評価額は5~30%程度減額されることがあります。
上記の例で、仮に20%減額されるとすると、評価額は「3,000万円×(1-0.2)=2,400万円」となります。
なお、路線価が定められていない地域では、倍率方式を用います。計算式は以下の通りです。
<計算式>
固定資産税評価額×倍率×持分割合
路線価と倍率は、国税庁の路線価図・評価倍率表のページで確認できます。
共有する建物の相続税のシミュレーション
建物の相続税評価額は、固定資産税評価額と同じです。共有名義の場合は、固定資産税評価額に持分割合を乗じることで被相続人の持分の評価額が算出されます。
<計算式>
建物の評価額=固定資産税評価額×持分割合
具体的なシミュレーションを見てみましょう。
| 項目 |
内容 |
| 固定資産税評価額 |
1,500万円 |
| 被相続人の持分 |
1/2(50%) |
| 建物の評価額 |
1,500万円×1/2=750万円 |
土地と同様に、実際の評価は持分にすることで下がります。建物の共有持分も単独では利用しにくいため、評価額が減額される可能性があります。
上記の例で、仮に20%減額されるとすると、評価額は「750万円×(1-0.2)=600万円」となります。固定資産税評価額は、固定資産税の「納税通知書」または「固定資産評価証明書」で確認できます。
【土地と建物を合算した相続税のシミュレーション】
先ほどの土地と建物の評価額を合算し、相続税額を計算してみましょう。
| ケース |
土地の評価額 |
建物の評価額 |
合計評価額 |
| 持分割合のみで計算 |
3,000万円 |
750万円 |
3,750万円 |
| 共有持分による減額を考慮(20%減) |
2,400万円 |
600万円 |
3,000万円 |
相続人が配偶者と子1人の場合、基礎控除額は「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」です。
- 持分割合のみで計算した場合:3,750万円<4,200万円→相続税はかからない
- 共有持分による減額を考慮した場合:3,000万円<4,200万円→相続税はかからない
このケースでは、どちらも基礎控除の範囲内に収まるため相続税は発生しません。ただし、不動産の評価額がより高額な場合や、ほかの相続財産がある場合は、共有持分による減額効果が相続税の軽減に大きく影響します。
相続税や納税資金の確保のため共有を選択することが現実的な場合もある
原則として、不動産を共有名義にすることはおすすめしません。共有名義には将来的な不動産活用の制約や共有者間のトラブルリスクがあり、「節税になるからとりあえず共有にしたほうが良い」という安易な判断は避けるべきです。
ただし、相続税の納税資金の確保や遺産分割の現実的な制約により、例外的に共有名義が選択される場面も存在します。
以下では、そのような典型的なケースについて解説します。
【納税資金の準備が難しく、売却までの時間的余裕がないケース】
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期限までに不動産を売却して現金化できない場合、一時的に共有で相続し、後に売却して精算するという方法が取られることがあります。
たとえば、以下のような状況が該当します。
- 相続財産のほとんどが不動産で、現金・預貯金が少ない
- 不動産の買い手が見つからず、申告期限までに売却が完了しない
- 相続人全員が納税資金を用意できない
このようなケースでは、「ひとまず共有で相続→売却後に精算」という段階的な対応が現実的な選択肢となります。ただし、これは相続税対策というよりも、納税までの猶予措置として共有を利用する形です。売却後は、持分割合に応じて売却代金を分配し、それぞれが納税資金に充てることになります。
【代償金の支払いが困難で、遺産分割として共有にせざるを得ないケース】
不動産の評価額が遺産の大部分を占め、相続人全員が現金で代償金を支払うだけの資力を持たない場合には、結果として共有とせざるを得ないことがあります。特に都市部の自宅不動産など、評価額が高く流動性が低い資産では典型的に生じる状況です。
たとえば、以下のような実務対応が見られます。
| 対応パターン |
内容 |
| (A)共有で承継→将来売却して換価→分配 |
共有で相続した後、売却可能なタイミングで不動産を売却し、持分割合に応じて売却代金を分配する |
| (B)共有で承継→後に一方が買い取る |
まず共有で相続し、その後、資金が準備できた相続人が他の相続人の持分を買い取る |
この場合も「節税目的で共有を選択した」というよりは、分割の現実的制約により共有にならざるを得ない消極的選択である点を明確にする必要があります。あくまでも「積極的な相続税対策」としての共有ではなく、「やむを得ない事情による消極的選択」として共有が選ばれる状況である点を理解しておくことが重要です。
代償金の支払いが可能であれば、一人の相続人が不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払う方が、将来的なトラブルを避けられるため望ましい方法です。
共有名義化による相続税対策はメリットばかりではない
共有名義で相続することには、一定のメリットも存在します。持分割合に応じて相続税を支払うことになるため、相続人一人あたりの相続税の支払い額は抑えられます。
たとえば、評価額5,000万円の不動産を兄弟2人で半分ずつ相続すれば、それぞれ2,500万円分の評価額に対して相続税を計算することになり、一人で全額を相続するよりも各人の税負担は軽くなります。
しかし、共有名義で相続することでこのようなメリットもありますが、相続後のリスクの方が大きいといえます。共有名義不動産は、将来的な活用や処分に大きな制約が生じ、共有者間のトラブルにつながる可能性が高いためです。
目先の相続税負担の軽減だけを考えて共有名義を選択すると、後々取り返しのつかない問題に発展する恐れがあります。以下では、共有名義で相続した場合の具体的なリスクについて解説します。
共有名義不動産全体の活用や処分が自由に行えなくなる
共有名義不動産は、共有者全員の同意または持分価格の過半数の同意がないと、自由に活用や処分ができません。自分の持分だけを所有していても、不動産全体を自由に使うことはできないのです。
不動産の活用や処分を行う際には、その行為の内容によって必要な同意の範囲が異なります。大きな変更を伴う行為ほど、より多くの共有者の同意が求められる仕組みになっています。
共有名義不動産全体の売却・建て替え・増改築には「共有者全員の同意」が必要
不動産の売却・建て替え・増改築などの「変更行為」を行う際は、共有者全員の同意が必要となります。たとえ持分の大部分を所有していても、他の共有者が一人でも反対すれば、これらの行為は実行できません。
たとえば、以下のような行為は変更行為に該当します。
- 不動産全体の売却
- 建物の建て替え
- 建物の大規模な増改築
- 土地の用途変更
共有者の人数が多いほど全員の同意を得ることが難しくなり、活用の自由度は落ちます。将来的に不動産を売却したい場合や活用したい場合に、大きな障害となるリスクがあります。
共有名義不動産全体のリフォーム・賃貸には「共有者の持分価格の過半数」の同意が必要
共有名義不動産の改造に至らない程度の軽微なリフォームや賃貸などは「管理行為」にあたり、共有者の持分価格の過半数の同意が必要です。ここで重要なのは、「共有者の過半数」ではなく「持分価格の過半数」である点です。
たとえば、3人の共有者がいて、持分割合がA:50%、B:30%、C:20%の場合を考えてみましょう。
| 共有者 |
持分割合 |
人数での割合 |
| A |
50% |
1/3 |
| B |
30% |
1/3 |
| C |
20% |
1/3 |
この場合、Aだけで持分価格の過半数(50%以上)を満たすため、Aの同意があれば管理行為を実行できます。人数では3人中1人(33%)でも、持分価格では過半数となるのです。
具体的には、3年以内の期間で建物を賃貸(短期賃貸借)する場合は、共有者の持分価格の過半数の同意が必要です。この制約により、不動産を有効活用したくても、他の共有者の同意が得られずに活用できないケースが発生します。
利用していなくても固定資産税等の管理費が発生する
共有不動産は、共有者が持分割合に応じて管理費用を負担しなければならないと、民法第253条で定められています。
原則として、共有不動産の利用状況に関わらず負担する責任を負い、固定資産税や都市計画税などの維持費が発生します。たとえば、自分が共有不動産に住んでいなくても、持分割合に応じた税金の支払い義務があるのです。
また、持分割合に応じて負担するのが原則ですが、共有者の1人が支払わない場合は、ほかの共有者が代わりに支払う必要があります(連帯納税義務)。これは、固定資産税などが共有者全員で連帯して納付する義務を負う税金であるためです。
結果として、他の共有者が税金を滞納した場合、自分の持分に対する税金だけでなく、滞納者の分まで支払わなければならない可能性があります。このような負担が、共有者間のトラブルにつながることも少なくありません。
相続が繰り返されると将来的に権利関係が複雑化する
相続登記を放置すると、相続が発生するたびに共有者の人数が増え、権利関係が複雑化します。
たとえば、当初は兄弟2人の共有だったものが、それぞれの相続が発生することで、その子どもたち、さらにその孫たちへと共有者が増えていきます。
世代を経るごとに共有者同士の関係が疎遠になり、遺産分割協議も困難になります。面識のない遠い親戚と不動産を共有している状態になれば、売却や活用の合意を得ることはほぼ不可能です。
さらに、行方不明者や未成年、認知症の相続人が現れた場合には、代理人の選任が必要になる場合があります。
| 状況 |
必要な手続き |
| 行方不明者がいる場合 |
不在者財産管理人の選任が必要 |
| 未成年者がいる場合 |
法定代理人または特別代理人の選任が必要 |
| 認知症の相続人がいる場合 |
成年後見人の選任が必要 |
これらの代理人選任には、家庭裁判所への申立てが必要となり、時間と費用がかかります。共有者が増えれば増えるほど、このような複雑な手続きが必要になる可能性が高まるのです。
共有名義で相続したなら共有状態から抜け出すことも選択肢の一つ
共有名義で相続した不動産は、将来的なトラブルや活用の制約を避けるため、早めに共有状態を解消することも選択肢の一つです。共有状態を解消する方法はいくつかあり、それぞれにメリットと注意点があります。
以下の表に、共有状態を解消する主な方法をまとめました。ご自身の状況に合った方法を検討してください。
| 方法 |
内容 |
| 共有名義不動産全体を売却する |
共有者全員で不動産全体を売却し、売却代金を持分割合に応じて分配する。共有者1人につき3,000万円の特別控除が受けられる。ただし、共有者全員の同意が必要。 |
| 共有持分を共有者間で売買する |
ほかの共有者の持分を買い取り単独名義にする。単独名義になれば自由に活用・処分できるが、買い取るための十分な資金があることが前提。 |
| 自分の持分のみを売却する |
自分の持分のみを買取業者に売却する。共有持分のみなら、ほかの共有者の同意なく売却可能だが、市場価格より安くなる可能性が高い。 |
| 土地の場合は分筆する |
土地を分筆し、それぞれの共有者が単独で所有する。各自が自由に土地を活用できるようになるが、分筆後の土地が最低敷地面積を下回ると建物を建築できなくなる。 |
| 共有持分を放棄する |
自分の持分を放棄し、ほかの共有者に帰属させる。固定資産税などの負担から解放されるが、対価は得られない。 |
| 共有物分割請求訴訟を起こす |
裁判所に共有物の分割を請求する。強制的に共有状態を解消できるが、時間と費用がかかる。 |
共有状態を放置すると、相続が繰り返されて権利関係がさらに複雑化し、解消が困難になります。共有名義で相続した場合は、早めに専門家に相談し、最適な解消方法を検討することをおすすめします。
共有名義の相続税対策はまず税理士に相談する
共有名義不動産の相続税対策は、複雑で専門的な知識が必要です。生前贈与の方法、小規模宅地等の特例の適用要件、共有持分の評価方法など、判断が難しい項目が多く、誤った対策を行うと、かえって税負担が増えたり、将来的なトラブルにつながったりする可能性があります。
税理士に相談することで、適切な相続税対策を提案してもらえます。ご自身の財産状況や家族構成、将来的な不動産の活用方法などを総合的に考慮したうえで、最適な対策を提案してもらえるでしょう。
また、相続税の計算や申告手続きも税理士に依頼できます。相続税の計算は複雑で、特に不動産の評価は専門的な知識が必要です。税理士に依頼すれば、正確な計算と適切な申告が可能となり、税務調査のリスクも軽減できます。
小規模宅地等の特例などの適用要件を満たすかどうかの判断も、税理士に相談するのが安心です。特例の適用要件は細かく定められており、わずかな判断の誤りで数百万円単位の税負担の差が生じることもあります。相続税に詳しい税理士に相談し、確実に特例を活用することをおすすめします。
まとめ
本記事では、共有名義不動産の相続税対策について詳しく解説してきました。
共有名義不動産は、適切な対策を講じることで相続税の負担を軽減できる可能性があります。生前贈与による暦年贈与や相続時精算課税制度、夫婦間贈与の配偶者控除などを活用すれば、計画的に財産を移転できます。また、相続開始後でも、小規模宅地等の特例を適用することで、相続税評価額を最大80%減額できます。
ただし、共有名義には将来的な不動産活用の制約や共有者間のトラブルリスクがあるため、安易に共有名義を選択することはおすすめできません。不動産の売却や賃貸には共有者の同意が必要となり、相続が繰り返されると権利関係が複雑化していきます。
相続税対策として共有名義を選択する際は、目先の節税効果だけでなく、長期的な視点での判断が重要です。納税資金の確保や代償金の支払いが困難な場合など、やむを得ない事情で共有を選択するケースもありますが、可能であれば単独所有や早期の共有解消を検討すべきです。
共有名義不動産の相続税対策は複雑で専門的な知識が必要なため、まずは相続税に詳しい税理士に相談することをおすすめします。適切な対策を講じることで、相続税の負担を抑えつつ、将来的なトラブルも回避できるでしょう。