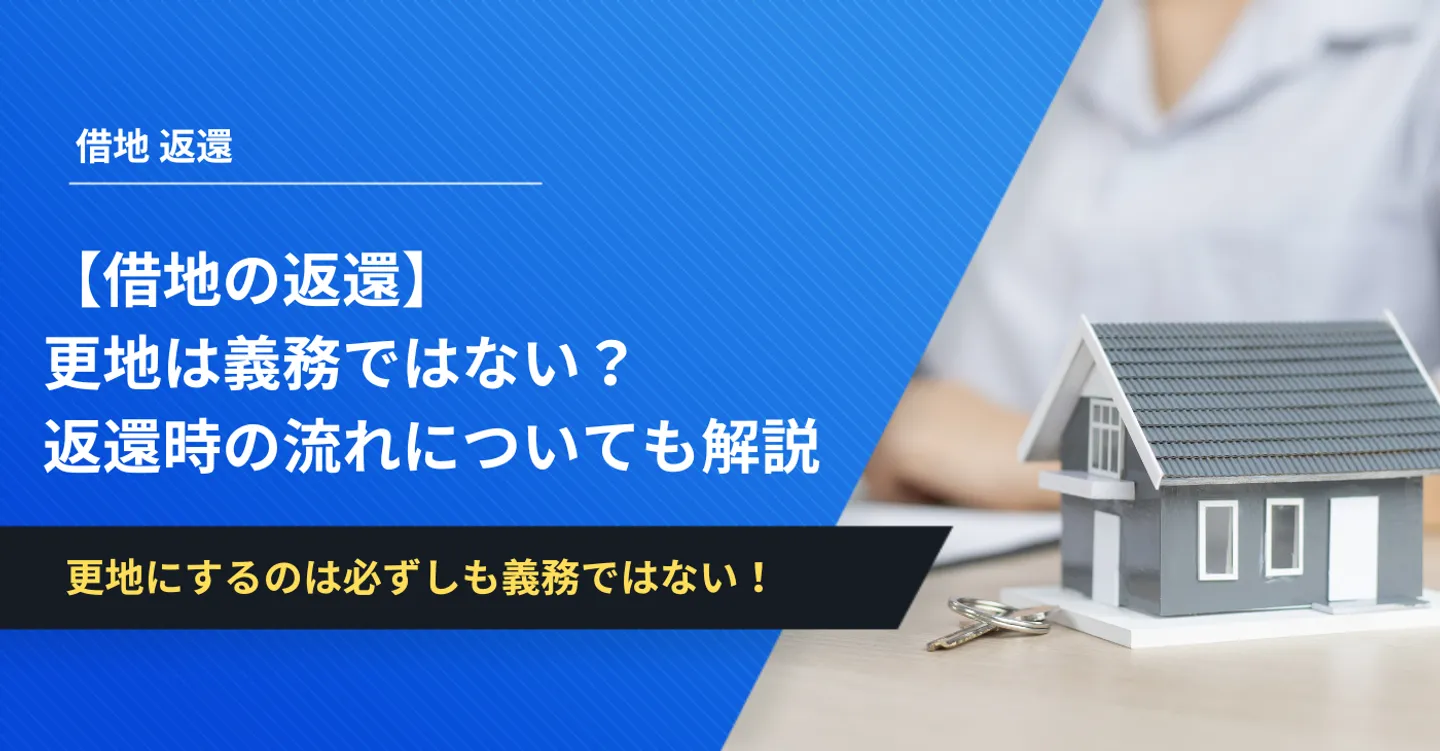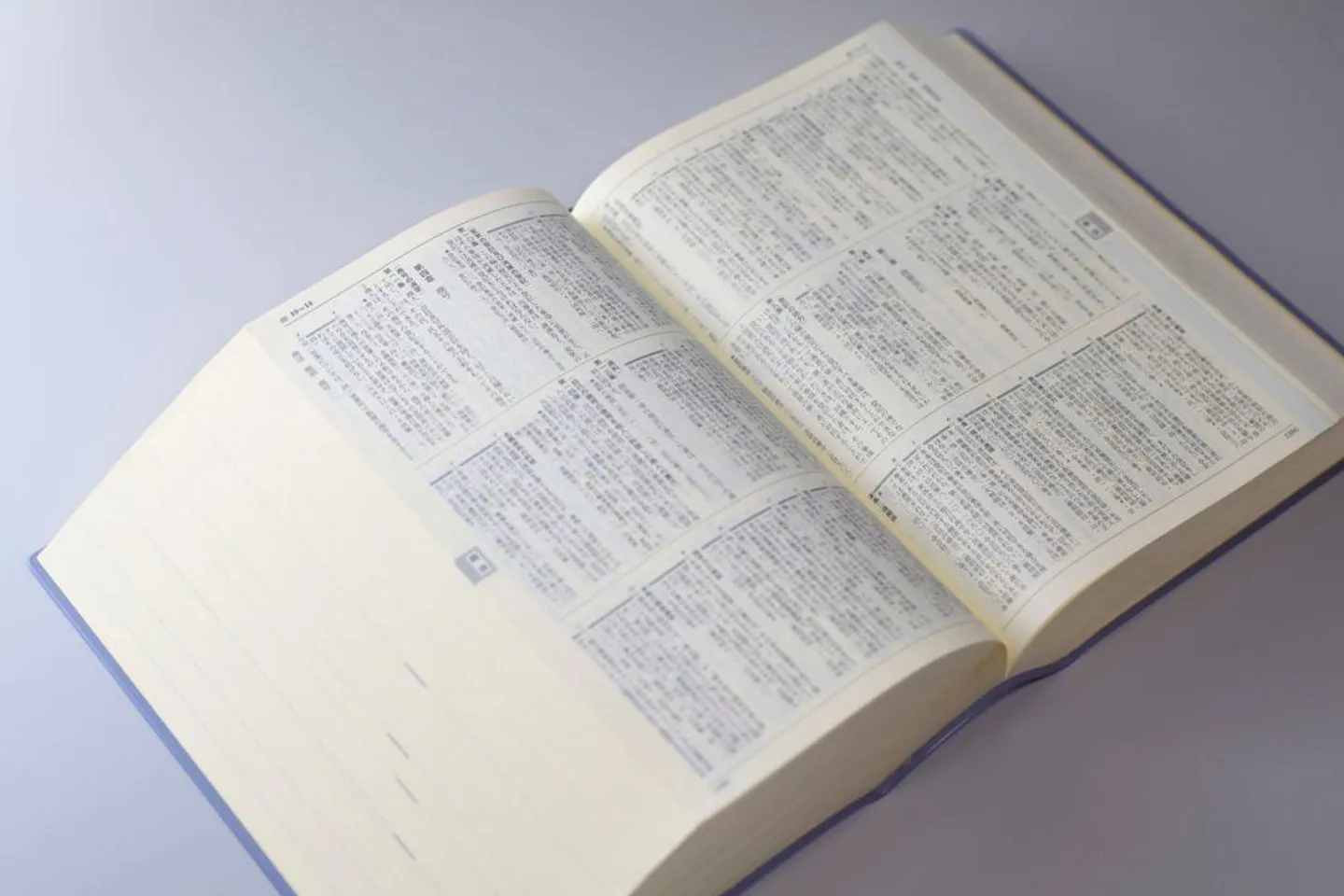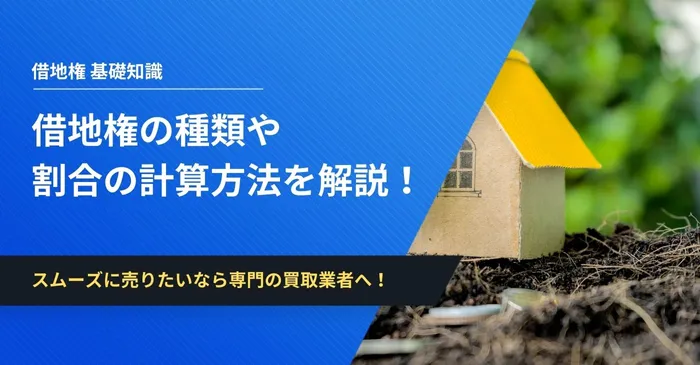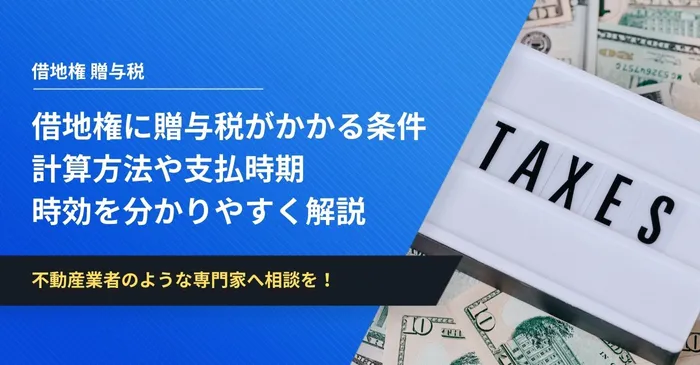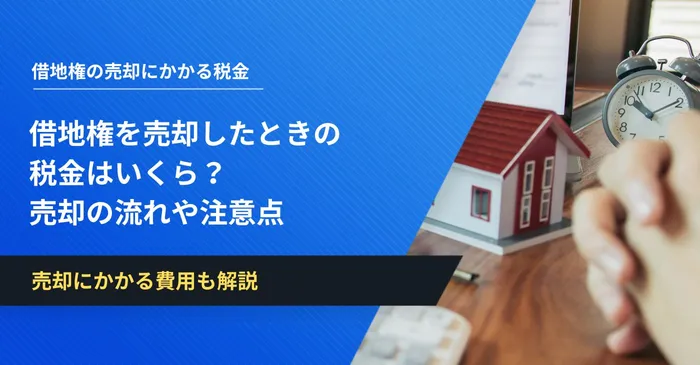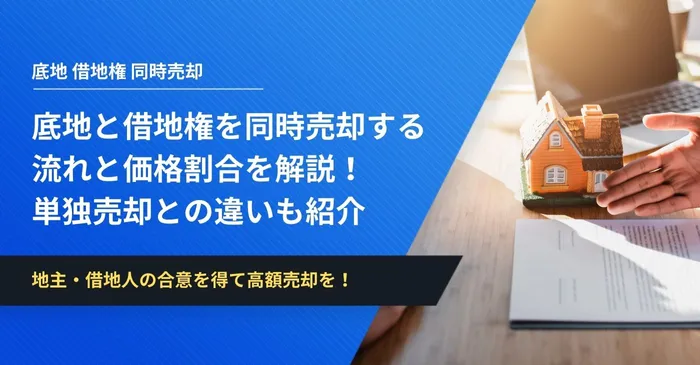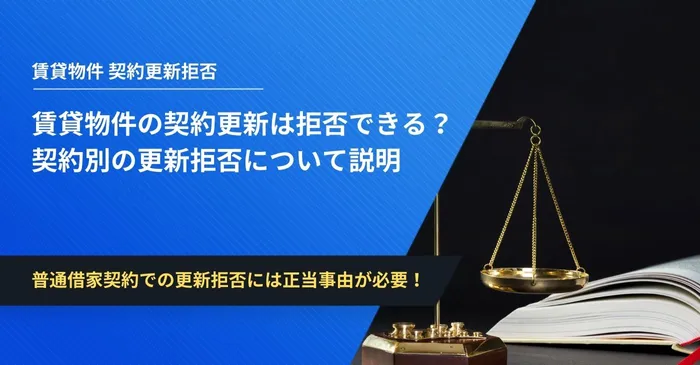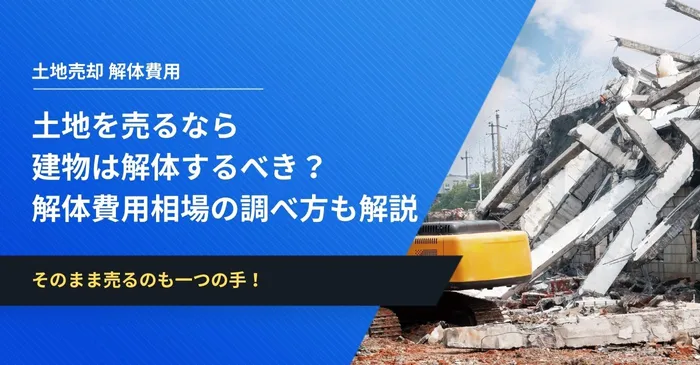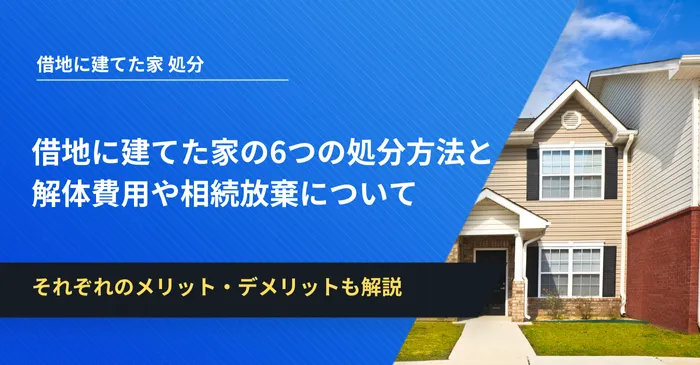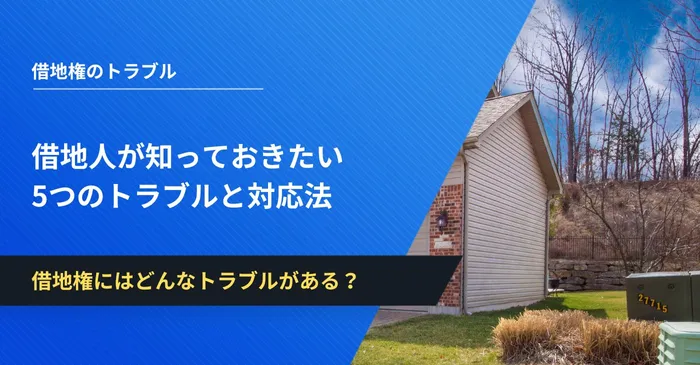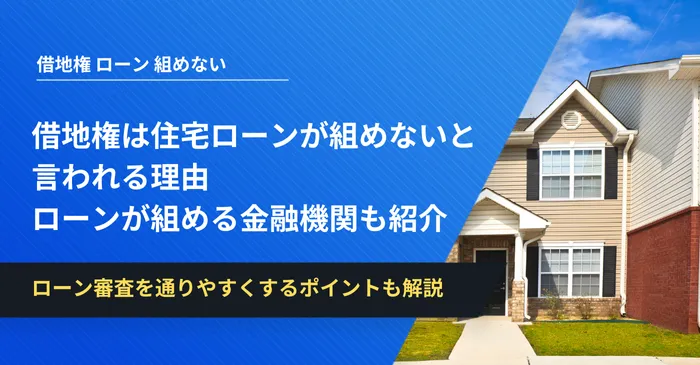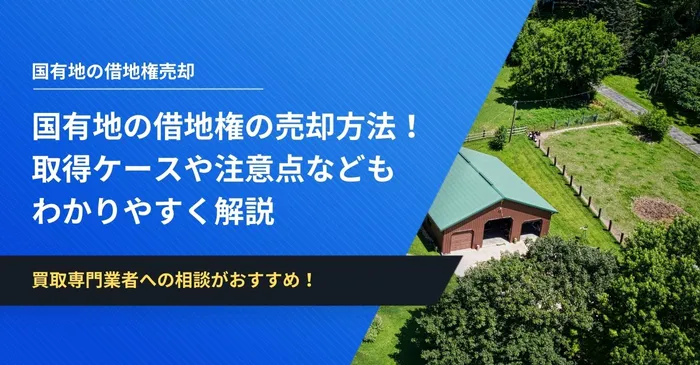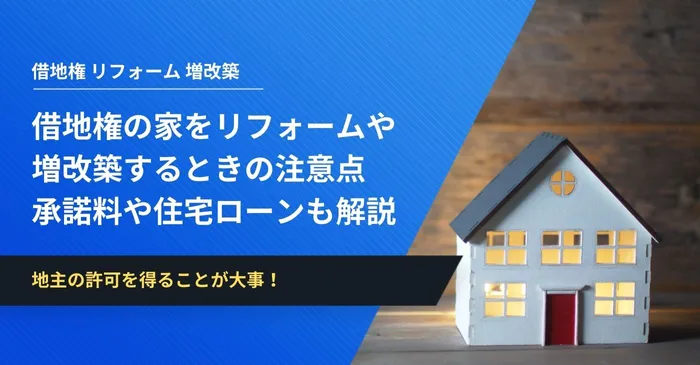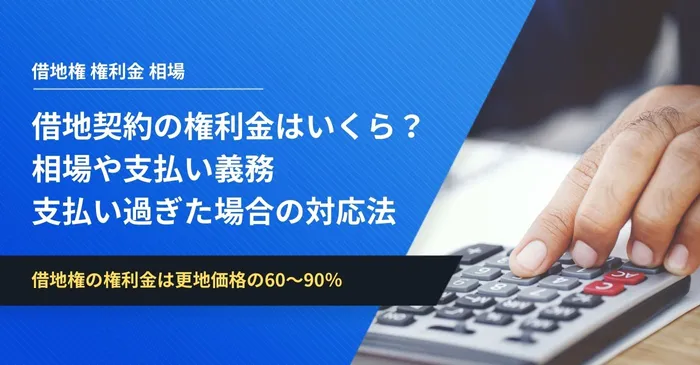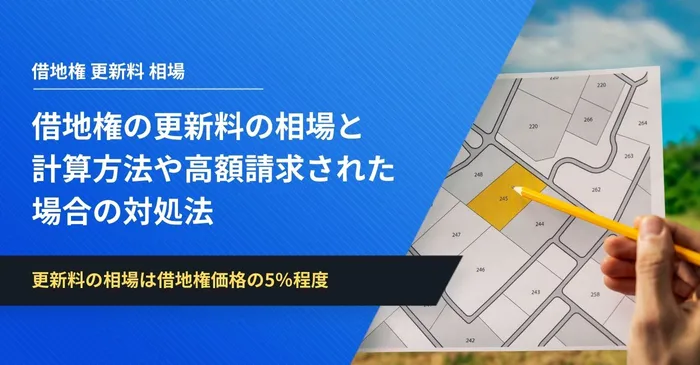借地権とは
借地とは、地主から借りた土地のことを指しています。また、建物を所有するために土地を借りる権利のことを「借地権」、借地権を有する者は「借地人」といいます。
両者の公平を保つためにさまざまな法律で基準を定めており、その中に、借地権の更新を定めた「借地法(旧法)」と「借地借家法(新法)」があります。
なお、旧法と新法では以下3種類の借地権が定められています。
| 適用される法律 |
賃貸契約時期 |
借地権 |
| 借地法(旧法) |
平成4年7月31日以前に契約 |
旧法借地権 |
| 借地借家法(新法) |
平成4年8月1日以降に契約 |
普通借地権 |
| 定期借地権 |
旧借地権と普通借地権では、基本的に借地人が希望すれば更新が可能です。地主側の都合により契約を解除する場合は、地主側による下記のような正当な理由の主張が必要になります。
・地主が土地の使用を必要とする場合
・借地に関するこれまでの経過
・宅地などの土地の利用状況
・立退料の支払いなど
一方で定期借地権とは、当初定められた期間で契約が終了する借地権のことです。
期間が満了すると、借地人は契約を更新できないため、契約期間が終了すると借地の返還義務が生じるのが大きな特徴です。
借地権について詳しく知りたい方は以下の記事を参照ください。
借地を返還するのに更地は義務ではない
借地人が地主に返還する際、借りたときの状態に戻して返還しなければならないという原状回復義務を負います。そのため、借地人は原則として建物を解体して更地に戻してから返還する必要があります。
建物を解体する際にかかる費用も、借地人が負担しなければなりません。ただし、借地契約の種類や借地権の売却方法によっては、更地にしなくても借地権を返還できる場合があります。
旧法借地権や普通借地権で契約している場合は、地主に対して借地上の建物を買い取ってもらうように請求できる建物買取請求権が認められているため、返還時に自費で建物を解体する必要がないうえ、建物の売却代金を得ることも可能です。
建物買取請求権を行使できない場合でも、地主と交渉して借地権を買い取ってもらう方法や第三者に売却する方法であれば、更地にせずに借地権を返還できます。
ただし、定期借地権で契約していた場合はいかなる理由があっても返還義務が生じるため、契約期間が満了になったら更地にする必要があります。そのため、借地権返還を求められた際は契約の種類について必ず確認しましょう。
借地と借地権の返還方法
借地権の返還には大きく分けて次の4つの方法があります。
- 更地にして地主に返還する
- 地主に買取請求をして建物を買い取ってもらう
- 地主に借地権を買い取ってもらう
- 借地権を第三者に売却する
ここからは、それぞれの方法について詳しく解説していきます。
更地にして地主に返還する
特別な条件がない場合、借地の上に存在する建物は借地人が取り壊し、更地にしてから地主に返還する必要があります。
その際、解体業者などに依頼して、借地の返還前に建物を取り壊すことになります。解体費用も借地人が全額負担するのが原則となっていて、資金を用意しなければなりません。
業者の選定から建物の解体が完了するためには数カ月かかることもあるため、借地や借地権を地主に無償で返還する場合、計画的に準備を進めておきましょう。
認定課税を受けないことを届け出る特例
通常の借地権は、借主側が土地価格の6%程度の金額を地代として支払うものとして設定されます。地代の支払いがなく無償で貸し出す場合、贈与税として借主は借地権の認定課税を支払わなければなりません。
しかし、社長などの個人が自分で経営している法人に、無償で土地を貸しているというケースのように、同じ人物が所有しているが用途が違うことで書面上の所有者が異なる場合にも適用されてしまいます。
そこで、借主側が無償で返還する契約であれば、借地権の認定課税は免除される特例が定められています。その際、「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出しなければなりません。
そのため、土地の無償返還に関する届出書が手元にある場合は、必ず無償で返還することになります。
地主に買取請求をして建物を買い取ってもらう
前述の通り、借地人が借地を返還する場合は原則その上にある建物を取り壊す必要があります。
しかし、旧借地権や普通借地権(新法)で契約した場合、契約期間満了などの一定の要件に当てはまれば「建物買取請求権」の行使が認められています。
建物買取請求権とは、借地人側は地主に対して借地の上に存在する建物を買取するように請求できる権利のことです。
つまり、借地人が建物の解体費用を負担するところを、逆に建物を売却してお金が入ってくることになります。
借地人にとって有利な権利ですが、次の要件すべてを満たす必要があります。
- 借地契約の期間が満了したこと
- 借地契約の更新がないこと
- 借地に建物があること
なお、建物買取請求権を行使できるのは、原則契約の解除や地主が土地の継続利用を拒んでいる場面です。
過去の裁判所の判例などから、通常の合意解約の場合は、建物買取請求権の行使は認められない可能性が高くなります。また、賃貸借契約書に建物買取請求権の拒否をするといった記載があったとしても、その記載は無効です。
ただし、借地人に地代の未払いや遅滞、重大な契約違反などの理由がある場合、地主側は建物買取請求権を拒否できます。
地主に借地権や借地の上に存在する建物の買取を求める場合、普段から地主と良好な関係を築いておき、事前に建物買取請求権などに詳しい弁護士などの専門家へ相談しておくことをおすすめします。
地主に借地権を買い取ってもらう
借地権には土地の価格の数10%相当もの価値があり、売買や親から子への相続なども可能です。
そのため、借地権の返還は無償ではなく、地主に借地権を買い取ってもらうケースも多いです。
ただし、建物買取請求権が適用されている場合は借地権の買い取りを請求できないことも頭に入れておきましょう。
借地権を第三者に売却する
借地権には価値があるため、地主だけでなく第三者にも売却可能です。このケースでは、地主に経済的負担をかけることなく、適正な価格で借地権を売却できます。
借地権の第三者への売却は、不動産会社を通して買主を探したり、借地権の買取専門業者に買取を依頼したりする方法で行います。
ただし、借地権の第三者への売却には、原則として地主の承諾が必要です。そのため、普段から地主と良好な関係を築いておきましょう。
底地と建物をセットで売却する
第三者に売却する際は、底地と建物をセットで売却すれば建物を解体しなくても売却可能です。底地とは、借地権が発生している土地のことで、権利者は地主になります。
借地権のみを売却する場合だと、同一の不動産に地主と借地人の2人の権利者がいるため、買い手からは避けられやすく、相場よりも安い価格でなければ売却が困難です。
ですが、底地と建物をセットにすれば、土地の所有権も建物の所有権も同時に購入することになるため、完全所有権の不動産として売却できます。そのため、それぞれ単体で売却するよりも買い手が見つかりやすく、高値で売却可能です。
>>【無料相談】底地の買取窓口はこちら
借地を返還する手続きの流れ
ここからは、借地を返還する手続きの流れを見ていきましょう。
一般的な手続きの流れは次のようになります。
- 契約書の記載事項を確認する
- 貸主への報告・交渉
- 解体業者の選定と解体工事
- 更地の返還と建物滅失登記
それぞれの流れを1つずつ確認していきます。
1. 契約書の記載事項を確認する
借地を返還する場合は、まず土地賃貸借契約書の記載事項を確認しましょう。土地賃貸借契約書には、借地権の種類や存続期間、賃料や支払い方法、借地上の建物の処分方法などが記載されています。特に重要なのが、借地権の種類と存続期間です。
借地権は原則として、途中で解約はできません。借地権の存続期間は、旧法と新法のどちらで契約しているか、新法の場合は普通借地権と定期借地権のどちらで契約しているかによって変わってきます。
まずは、存続期間がいつまでなのか、建物の処分方法はどうなっているのか確認してみましょう。
2.貸主への報告・交渉
契約書の記載事項を確認したら、貸主への報告や交渉が必要です。貸主に何も報告せずに解体工事などを行うと、トラブルや裁判になる可能性があります。
そのため、賃貸契約は継続するのか、借地権や建物の買取はできるのか、解体工事が必要かなどの交渉を行いましょう。
更地にする必要がある場合は、いつまでに更地にして返還するのかなどの交渉を行います。トラブルをなくすため、貸主への報告や交渉は、最初はもちろん、返還までの間、随時行った方が良いでしょう。
3.解体業者の選定と解体工事
貸主との交渉がまとまったら、次に解体業者を選びます。解体業者によって解体費用が異なったり、業者の中には悪徳業者が存在したりするので、必ず複数の業者に査定の依頼や相談を行いましょう。
解体業者が決まったら、解体工事の開始です。近所への挨拶なども忘れずに行いましょう(解体業者が代わりに行う場合もあります)。
4.更地の返還と建物滅失登記
解体工事が完了すると、更地を貸主に返還します。ただし、これで手続きが完了したわけではありません。
解体後は、建物が無くなったことを法務局に登記する必要があります。これを「建物滅失登記」といいます。
不動産登記法では、建物を解体してから1カ月以内に建物滅失登記を行うよう定められています。
建物滅失登記を行わないと、その土地の売却や貸付ができなかったり、無くなった建物に固定資産税などの税金が課されたりする可能性があるので、忘れずに建物滅失登記をしましょう。
借地を更地にするための解体費用
以下のような場合、借地を更地にして返還する必要があります。
- 地主に無償で借地権を返還する場合
- 有償で借地権を返還する際に建物買取請求権を行使できない場合
借地を更地にするための解体費用がどれぐらいかかるのか、見ていきましょう。
解体費用は建物の構造によって異なる
解体工事は、足場の建設などの仮設工事や重機による解体、屋根の解体や内装の解体、樹木等の撤去など、建物がどのような構造になっているのかによって、大きくその内容が異なります。
また、作業内容によって作業員の人数なども決まるため、人件費や諸経費なども大きく異なります。よって、一概に相場というものはありません。
一般的には、木造の場合坪あたり3万~4万円、鉄骨造(S造)の場合坪あたり4万~5万円、鉄筋コンクリート造(RC造)の場合坪あたり5万~6万円程度が目安といわれています。
建物の構造によって大きく異なるため、一概にはいえませんが、解体業者を選ぶ際に法外な見積もりになっていないかどうかを確認する目安として、上記の額を頭に入れておくとよいでしょう。
解体費用は業者によって大きく異なる場合がある
解体費用は、建物の構造だけでなく業者によってもその金額が異なります。場合によっては、数十万円単位で異なるケースもあるため、解体業者を選ぶ場合は必ず複数の業者に査定をしてもらうようにしましょう。
ただし、なかには安い価格を提示して、不法投棄などの違法行為を行う業者もいます。解体業者を選ぶ場合には、価格ももちろんですが、信頼できる業者を選ぶことにも注意が必要です。
解体費用を抑えるには?
解体費用を安くするには、以下の方法を試してみるのがおすすめです。
- 自分で処分できるものは自分で行う
- 自治体の助成金が出る場合もある
- 複数社で見積もりしてもらう
ここでは、解体費用を安くする方法について見ていきましょう。
1.自分で処分できるものは自分で行う
建物の解体を業者に依頼する場合、現状のまま物の解体を依頼するケースも多いです。しかし建物の中には、家具や電化製品など自分で処分できるものが多く残っています。
これらを自分で処分することで、業者の手間を抑えられるため解体費用を低くできる可能性が高いです。
価値のあるものは、リサイクルショップやインターネットでなどで売却すれば、お金を得られる可能性もあります。粗大ごみなどは、各自治体に頼んで処分することで、費用を安くできるでしょう。
2.自治体の助成金が出る場合もある
解体する建物が古い場合など、自治体によっては助成金が出るケースもあります。助成金の金額は一律だったり、解体費の一部(上限あり)だったりと自治体によってさまざまです。
解体を行う必要がある場合は、助成金の有無や、助成金がある場合は条件や手続き方法などの詳細について、事前に各自治体に問い合わせましょう。
3.複数社で見積もりしてもらう
前述の通り、解体費用は業者によって異なるため、依頼する業者によっては数十万円以上の金額差が生じる場合もあります。
その際、複数の業者から見積もりをとればある程度の相場感がつかめてくるので、適正価格の業者の中から自身に合った業者に解体を依頼できます。
また、他社の見積もり金額を値引き交渉の材料として活用できるため、当初提示してもらった見積もり金額よりも安く抑えられる可能性もあります。
まとめ
借地を返還する場合、原則として借地の上にある建物を解体し、更地として返還する必要があります。
しかし、場合によっては借地権を有償で返還できるケースや建物買取請求権を行使できるケースもあります。
さらに、建物を解体する際には、解体業者の選定にも十分に注意する必要がありますが、自分ひとりですべてを判断することは簡単ではありません。
そのため、まずは信頼のおける不動産業者に相談することをおすすめします。
借地を返還する際のよくある質問
借地と借地権を返還するには、どうすればよいですか?
地主に無償で借地権を返還する方法と、地主に有償で借地権を買取してもらう方法の2種類があります。
借地権にはどの程度の価値がありますか?
借地権には土地の価格の数10%相当もの価値があります。地主または買取業者に売却することが可能です。
【借地権の買取窓口】無料相談はこちら
借地を更地にするための解体費用はどの程度ですか?
解体費用は建物の構造・依頼する解体業者によって異なります。一般的には、木造の場合3万~4万円/坪、鉄骨造(S造)の場合4万~5万円/坪、鉄筋コンクリート造(RC造)の場合5万~6万円/坪が目安とされています。
借地に返還義務はありますか?
適用される借地権によって異なります。定期借地権では契約の更新が認められていないため、当初定めた契約期間の満了に伴って借地の返還義務が生じます。
一方、旧法や普通借地権で契約した場合は、借主が契約の更新を望む限り、原則として契約が更新され続けます。
地主は正当な事由がなければ更新の拒絶ができないため、正当な事由があって契約の更新を拒絶された場合や自ら契約更新を拒絶した場合を除き、借地の返還義務は生じません。
訳あり不動産の売却でお悩みなら
今すぐご連絡ください
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-