生活保護を受給する場合、基本的には不動産をはじめとする資産は処分する必要があります。
例外として、生活維持に必要な不動産は、売却しなくても生活保護の受給が認められます。
マイホームに住み続けながら生活保護を受給したい場合、一度売却した家を賃貸契約で借りる「リースバック」という方法もおすすめです。
また、なるべく高く不動産を売却するためには、複数の不動産会社を比較することも大切です。
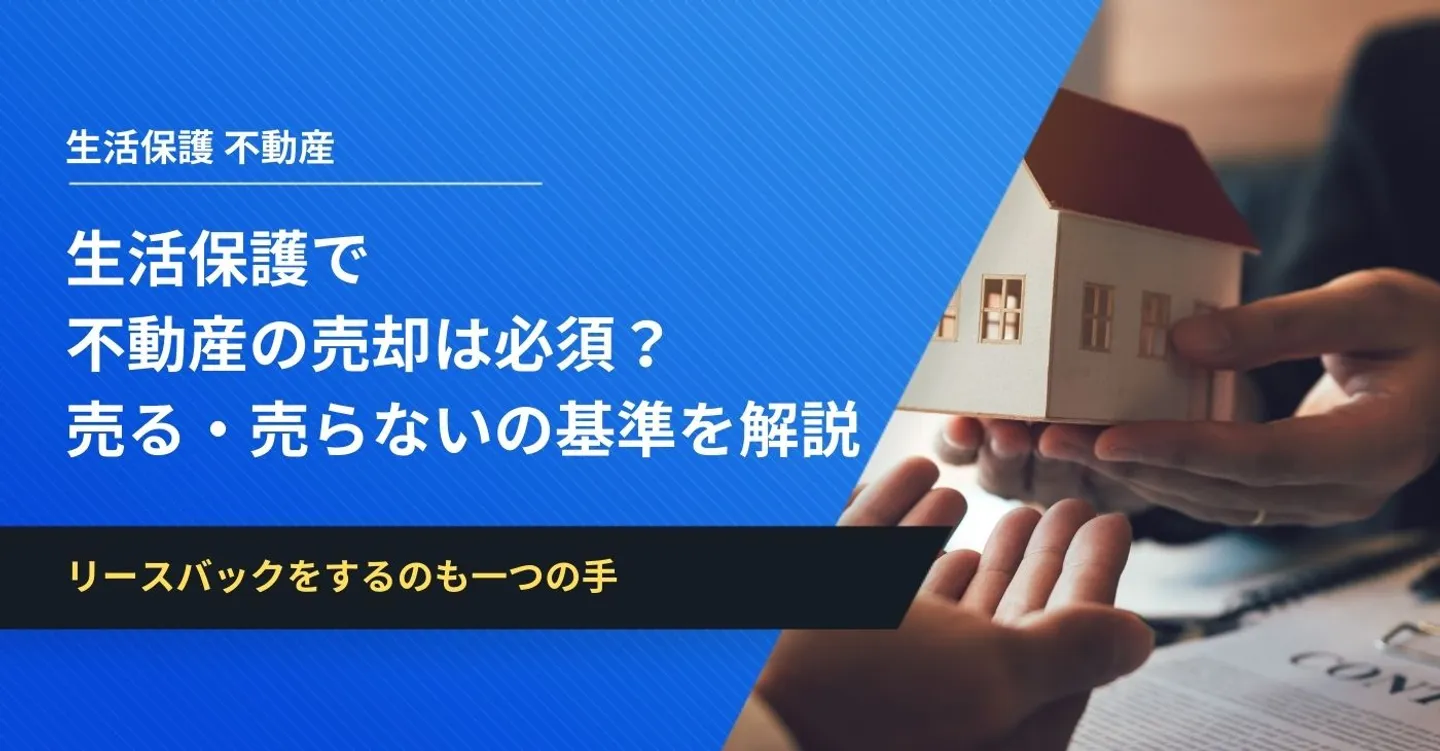
生活保護を受給する場合、基本的には不動産をはじめとする資産は処分する必要があります。
例外として、生活維持に必要な不動産は、売却しなくても生活保護の受給が認められます。
マイホームに住み続けながら生活保護を受給したい場合、一度売却した家を賃貸契約で借りる「リースバック」という方法もおすすめです。
また、なるべく高く不動産を売却するためには、複数の不動産会社を比較することも大切です。
「生活保護」とは、憲法に記載されている「健康で文化的な最低限度の生活」を保証するための公的支援で、最低限の生活費を国から受給できます。
日本国憲法 第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
生活が困窮するほど余裕がない人を対象としているので、換価できる資産があると、原則として生活保護は受けられません。
しかし、不動産については、生活保護を受けながら所有を続けられる場合があります。
ここでは、生活保護の基本的な要件と、不動産を所有できるケースについて解説します。
生活保護を受給するためには、以下の要件を満たす必要があります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
第一に、収入が一定以下である必要があります。地域ごとに定められた「最低生活費」があり、これを超える収入の人は受給できません。
最低生活費は住所地や家族構成によって異なりますが、地方の県庁所在地に住む親子4人暮らしだと約22万円程度です。
生活最低費から、その人の収入を差し引いた金額が受給額となります。上記の例で言えば、収入が10万円あれば「22万円-10万円=12万円」が支給額です。
資産には不動産の他に預貯金や絵画や貴金属、自動車などさまざまなものがあります。
生活保護を受給するためには、生活が困窮していることが前提となるため、まずはこれらの資産を生活維持のために処分しなければいけません。
ただし現実に最低限の生活を維持するために活用されているのであれば、処分しなくてもよい場合があります。
不動産も処分しなくてよいケースについては、後の項目でくわしく解説します。
働ける能力があるのに、仕事をしない人は能力活用の要件を欠くため、生活保護の対象にはなりません。
なぜなら、この場合は憲法が保障する最低限度の生活を送るための最低生活費を稼ぐ能力があるのに、自ら放棄していると判断されるためです。
ただし、高齢者や病気で働けない人は働く能力がないと判断されるので、能力活用の要件を満たしていると扱われて、生活保護を受けられます。
生活保護法第4条第2項では「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」と規定されています。
民法に定める扶養義務者とは、第877条に規定されている「直系血族及び兄弟姉妹」です。
つまり、両親や兄弟姉妹といった扶養義務者から仕送りなどを受けた場合、その仕送り分は収入と見なされてしまい、その金額だけ保護費が減額されます。
ただし、扶養義務者の扶助は生活保護を受ける必須要件ではなく、扶養義務者が援助の要請を断ったとしても、生活保護申請を拒否することはできません。
前述の通り、生活保護の受給条件には「資産活用の要件」があります。
これは生活保護を受給する前に、預貯金や不動産などの所有している資産を活用して、なるべく自力で必要最低限の生活費をまかなうことを指します。
資産を活用しても必要最低限の生活費がまかなえない場合のみ、国から生活保護を受給できる仕組みです。
つまり、次の項目で解説する「例外」に該当しない場合、所有している不動産を売却しないと生活保護は受給できません。
例外として、生活維持に必要な不動産であれば、売却しなくても生活保護を受給できるケースがあります。
例えば、生活保護を受給するためにマイホームを手放した結果、借りる家も見つからずに住む場所がなくなってしまうと、健康で文化的な最低限度の生活は送れません。
こうした事態を防ぐため、例外として「生活に必要不可欠な不動産である」と認められた場合のみ、不動産を売却しなくても生活保護が受給できます。
健康で文化的な最低限度の生活を送るためには、住む場所はもちろん仕事も必要です。
以下のような不動産であれば、生活保護を受給しながら所有できます。
基本的に「生活に欠かせない不動産」は売却しなくても生活保護の受給が認められます。
それぞれのケースを1つずつ見ていきましょう。
1つ目のケースは、自分で所有して住んでいるマイホームです。
自分が住んでいるマイホームは売ると住む場所を失ってしまうため、売却しなくても生活保護を受給できます。
ただし、豪邸に住んでいる場合など、最低限度の生活を送るには十分すぎる不動産は売却しないと生活保護を受給できません。
2つ目のケースは、収入を得るための事業に必要な不動産です。
例えば、生活保護を受給するために農家から農地を奪ってしまうと、その人は仕事を失ってしまい収入がなくなってしまいます。
ですので、生活費をまかなうための事業に必要な農地や賃貸アパートといった不動産であれば、売却しなくても生活保護の受給が認められます。
3つ目のケースは、売却しても価値の低い不動産です。
売却しても価値の低い不動産は、売却にかかる税金などを差し引くと利益がほとんどない場合もあるため、そのまま所有していても大差ないと判断されるのです。
売却しても価値の低い不動産は「最低限度の生活に支障がない」と判断されるため、所有したままでも生活保護を受給できます。
「資産の活用」のため、所有している不動産を売却しないと生活保護を受給できないケースも少なくありません。
以下のような不動産は売却しないと生活保護を受給できません。
基本的に「最低限度の生活に必要ない」と判断される不動産や「生活費をまかなうために役立たない」ような不動産は売却が命じられると考えましょう。
それぞれのケースについて、1つずつ解説していきます。
1つ目のケースは、現在は居住していない不動産です。
相続などによって、いま住んでいる家とは別に不動産を所有する機会もあります。
原則として、住まいとして利用していない不動産は所有していなくても困らないので、売却しないと生活保護を受給できません。
2つ目のケースは、豪邸などの資産価値が著しく高い不動産です。
このようなケースは、たとえマイホームでも売却しないと生活保護を受給できません。
確かに1億円の家に住んでいたり、6LDKに1人暮らししている状況は明らかに最低限度の生活ではないので、生活保護を受けられないのも当然といえます。
ちなみに厚生労働省では、下記を超える資産価値の不動産は売却すべきとしています。
住んでいる地域によって基準額は異なりますが、だいたい2,000万円を超える不動産を保有していると、生活保護の受給は難しいかもしれません。
3つ目のケースは、家賃収入の少ない賃貸アパートです。
所有している賃貸アパートの賃貸収入を生活費に充てている場合、アパートを手放すと困ってしまう人もいるでしょう。
賃貸アパートは一見すると事業に必要な不動産に思えますが、賃貸収入が少ない場合は所有していても生活費には不十分なので、最終的に生活保護を受給することになります。
そのため、賃貸収入の少ない賃貸アパートは売却しないと生活保護を受給できません。
生活保護を受給する場合、所有・相続する不動産の処分が命じられるケースがあります。
しかし、生活保護を受給するほど生活に困窮している以上、不動産を売るのであれば、なるべく高く売却したいところです。
不動産業者であれば、どこへ売却しても高く売れるわけではなく、安値で買い叩かれてしまったり、取扱いを断られてしまう恐れもあります。
処分が命じられた不動産を高く売りたい場合は「一括査定」を利用して、もっとも査定額の高い不動産業者に売却を依頼しましょう。
本来であれば、わざわざ自分で不動産業者に連絡して、1社ずつ査定を申し込んだ後、それぞれの査定額を比較しなければなりません。
しかし「一括査定サイト」を利用すれば「どの不動産業者が1番高く売れるのか?」がすぐにわかります。
「生活保護を受給したいが、マイホームは手放したくない」という人も多いでしょう。
「リースバック」という方法を使えば、現在の家に住み続けながら生活保護を受給できます。
この項目では、リースバックを利用してマイホームに住み続けながら生活保護を受給する方法を解説していきます。
「リースバック」とは、現在のマイホームを一度不動産会社へ売却して、その不動産会社から賃貸契約で家を借り直すことを指します。
つまり、マイホームの所有権は自分から不動産会社へ移りますが、家を手放さずにそのまま住み続けることが可能です。
また、いったん家を売却することで生活保護の受給条件も満たせるため、家に住み続けながら生活保護も受給できます。
リースバックで家を売ると、いったん不動産会社へ所有権が移ってしまいますが、購入資金さえ貯めれば、将来的にリースバックした家を自分で買い戻すことも可能です。
生活保護を受給しながらコツコツと生活を立て直せば、将来的にお金を貯めて生活保護を抜け出し、リースバックした家も買い戻せるでしょう。
ただし、家賃を2~3か月以上も滞納したり賃貸契約を履行できない場合、リースバックした家を買い戻せる権利である「再売買予約権」を失ってしまう恐れがあります。
また、家を売却する段階で買い戻す予定を伝えておかないと買い戻せないケースもあるため、買い戻し時の価格も含めてリースバックの契約時に定めておきましょう。
リースバック後の賃料が高額だと、生活保護を受給できないケースも稀にあります。
なぜなら豪邸や広すぎる家だと、いくらリースバックで家を売却しても「最低限度の生活を上回る」と判断されてしまうためです。
とはいえ、一般的な生活レベルの家であれば、生活保護の受給が認められないケースは少ないです。
心配であれば、リースバックを扱う不動産会社や最寄りの福祉事務所へ相談して「リースバック後も生活保護を受給できるか?」を確認するとよいでしょう。
ここまで解説したとおり、生活保護はメリットだけでなくデメリットも多いです。
そのため「なるべく生活保護は受給したくない」という人も少なくないでしょう。
また生活保護は必ずしも受給できるわけではなく、受給を申請しても断られてしまうケースも少なくありません。
そうした場合は下記の方法を用いれば、生活保護を受給せずに不動産を利用して生活費をまかなえます。
この項目では、それぞれの方法を1つずつ具体的に解説していきます。
1つ目の方法は「長期生活支援資金貸付制度」を利用して、不動産を担保にお金を借りるというものです。
「長期生活支援資金貸付制度」とは、所得の少ない65歳以上の高齢者世帯を対象として、不動産を担保に生活資金や医療費などの貸付をしている制度です。
| 貸付限度額 | 不動産の評価額の70%程度 |
| 貸付期間 | ・貸付元利金が貸付限度額に達するまで ・借受人が死亡するまで |
| 貸付額 | 毎月30万円以内 |
| 貸付利子 | 年利3%または長期プライムレート(現在2.2%) |
長期プライムレートとは、銀行が1年を超える長期間で大企業向けに融資する際の金利のことで、一部の金融機関が発表しています。
下記の条件をすべて満たす場合、長期生活支援資金貸付制度による貸付が受けられます。
長期生活支援資金貸付制度を利用したい場合、自分の住んでいる市区町村の自立相談支援機関へ相談してみるとよいでしょう。
参照:「生活福祉資金(長期生活支援資金)の概要について」(厚生労働省)
2つ目の方法は、不動産を第三者へ貸し出して賃貸収入を得るというものです。
居住していない家などの生活に必要ない不動産を所有している場合、売却ではなく貸し出すだけであれば、手放さずに済みます。
また生活保護を受給する場合は手放さなければらない豪邸や広い家でも、部屋の一室を貸し出すことで家を手放さずに賃貸収入を生活資金に充てることが可能です。
「自分の不動産にどのような使い道があるのか?」を知りたい人は不動産会社へ相談してみるとよいでしょう。
3つ目の方法は、不動産を任意売却して売却益を受け取るというものです。
任意売却とは、住宅ローンなどの抵当権が行使されて家を差押えられる前に、借入先の金融機関から承諾を得て不動産を売却することです。
住宅ローンの滞納などが原因で家を差押えられて競売にかけられてしまうと、通常の不動産売却よりも売却益が少なくなってしまいます。
生活保護を検討するほど経済的に苦しい場合、任意売却で不動産を手放して高額な売却益を手に入れたほうが損をせずに済みます。
なるべく売却益を高くするにも、複数の不動産会社へ査定を依頼して、もっとも査定額の高い業者へ任意売却を依頼するとよいでしょう。
一定要件を満たしている場合、生活保護受給者であっても不動産の所有が認められます。
しかし、生活保護受給者が死亡した場合、所有していた不動産はどうなるのでしょうか。
最後に、生活保護受給者が死亡した後の不動産の扱いについて解説します。
被相続人が生活保護受給者だからといって、不動産の相続方法が特別異なることはありません。
ただし生活保護受給者の場合、維持管理に費やす費用も限定されているために、住宅の状態は良好とはいえないものが多くあります。
このため、古家付きの物件として売却した場合、市場の相場よりも安くなる可能性があります。
近年、持ち家を保有する高齢者が生活保護の相談に行くと、福祉事務所の担当者がリバースモーゲージ(要保護者向け長期生活支援金)を勧めることがあります。
親が生活保護を受給していると思っていたら、実はリバースモーゲージを利用していたとなると事情が変わってきます。
リバースモーゲージは自宅を担保にした借金なので、契約者が死亡した場合、自宅は速やかに競売にかけられます。
この自宅を取り返そうとすれば、これまでの借入金を一括返済するか、競売にかけられた際に自分で落札するしかありません。
ただし、確実に落札できる保証はないため注意が必要です。
生活保護を受給する場合でも、所有している不動産を売却せずに済むケースもあります。
資産価値の高すぎる不動産でない限り、自分が住んでいるマイホームを所有したままで生活保護は受給できます。
また生活保護を受給しながらマイホームに住み続けられる「リースバック」という方法もあります。
生活保護を受給したくない場合、不動産を担保に貸付を受けたり、不動産を任意売却することで生活費をまかなうことも可能です。
「生活保護を受けるべきか?」や「不動産を売却するべきか?」を検討するためにも、まずは不動産会社や地域を所管する福祉事務所の生活保護担当者へ相談して、アドバイスを受けることをおすすめします。