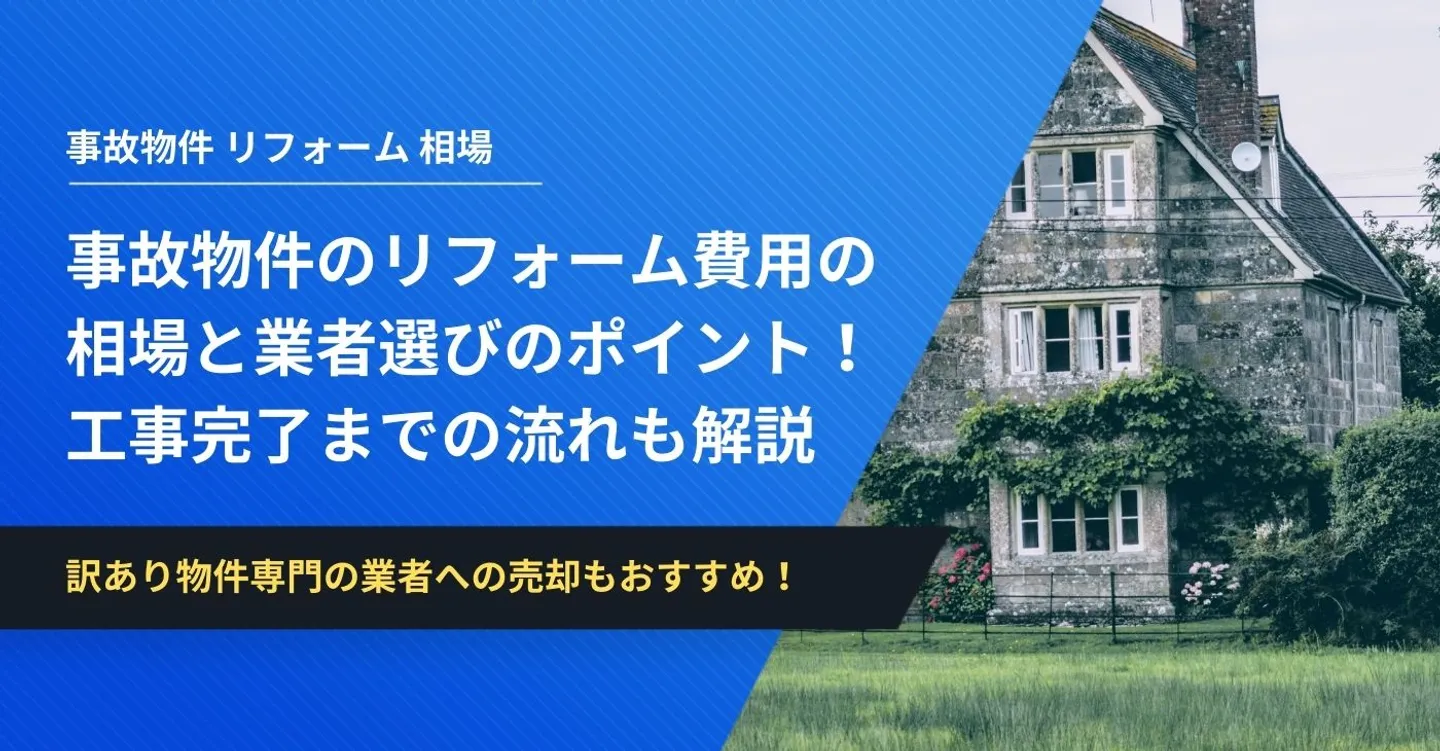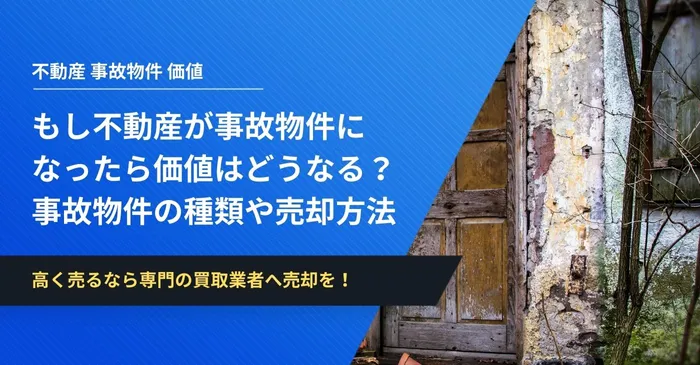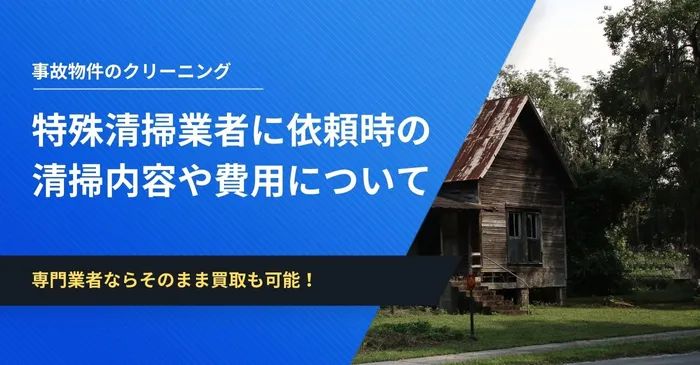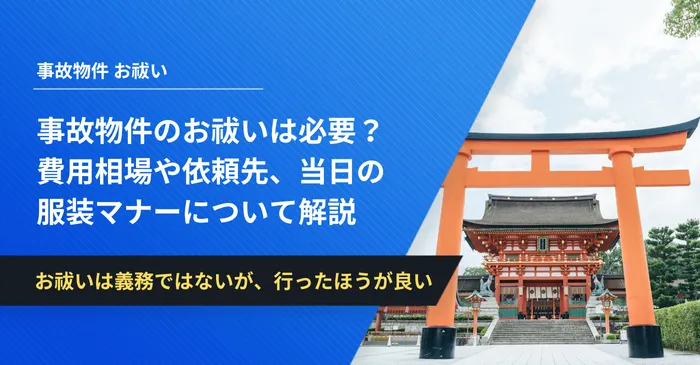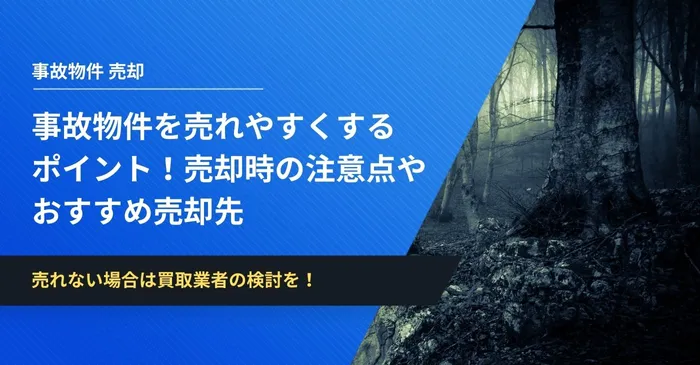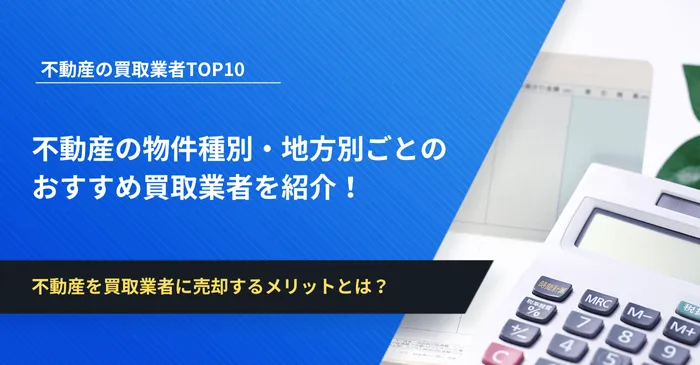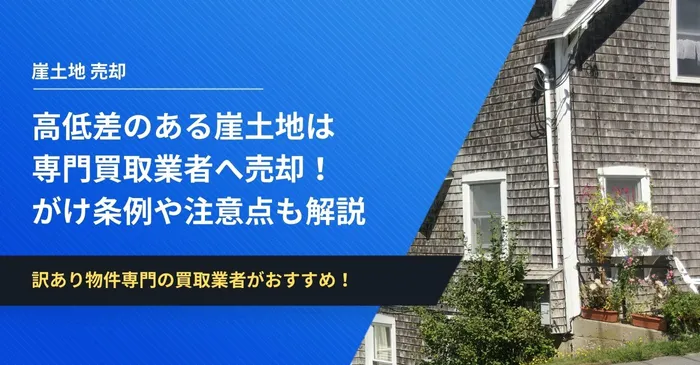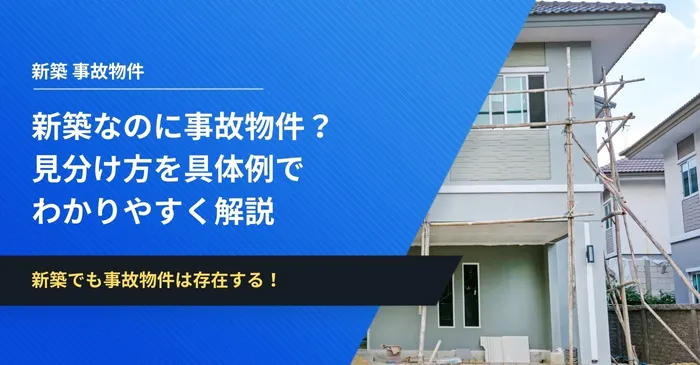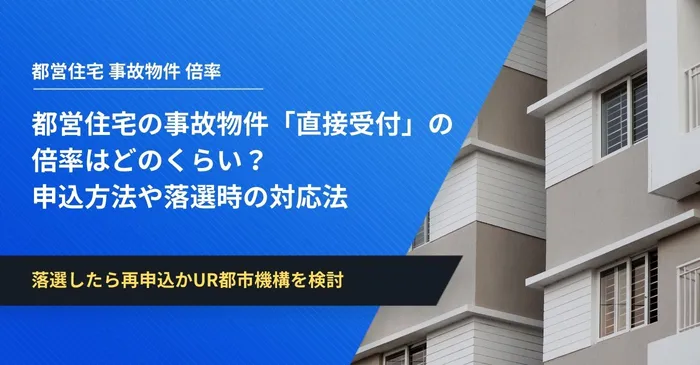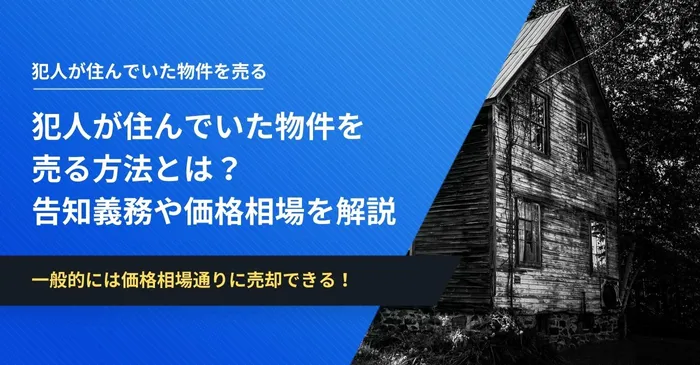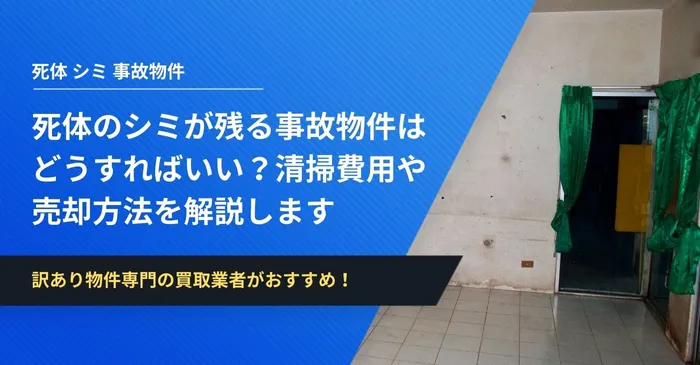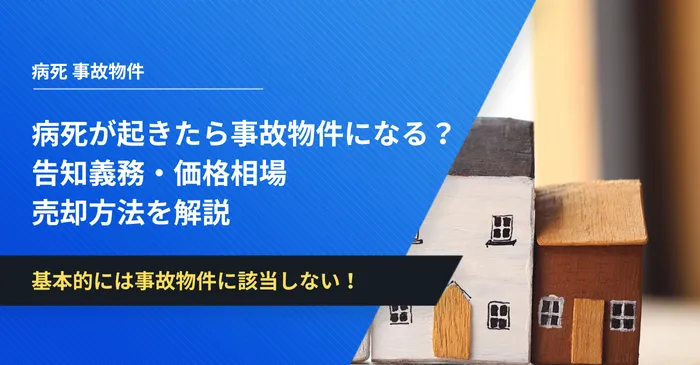事故物件のリフォーム費用の相場
不動産が事故物件となってしまった場合、基本的に大幅なリフォームが必要です。
体液や血液が現場に染み付いたままでは、まず住みたがる人はいません。ウイルス性の感染症が発生する恐れもあります。
外観を維持するためだけではなく、居住者の健康面を守る意味でも大幅なリフォームが必要です。
また壁紙や床だけではなく、キッチンやお風呂などの水回り、エアコンなどの設備も交換しないといけないケースもあります。
それぞれの設備をリフォームする場合の費用を見てみましょう。
壁紙や床の交換費用は約5~7万円
まず、重要なのは内装の交換です。
体液などが染み付いた壁やフローリング、フロアなどは全面的に交換する必要があります。
天井や壁などの壁紙張り替えする場合の一般的な費用相場は、1㎡あたり1,000円前後となっています。
ちなみに、デザイン性を重視した壁紙に張り替える場合、さらに費用は高くなります。
20㎡前後のワンルーム物件の場合、居室部分の壁紙張り替えで3万円から5万円程度が相場です。
また、床部分の張り替え費用の相場は、6畳で2万円前後です。
クッションフロアにすれば、費用を抑えられますが、質の良いフローリングにすると、さらに費用が多くかかります。
20㎡~25㎡の物件で壁紙と床をすべて交換する場合、5~7万円は費用を負担しなければなりません。
設備をすべて交換すると約50万円かかる
事故物件をリフォームする場合、壁紙や床の交換だけでは済まないかもしれません。
遺体が風呂場で発見されるケースもあります。
そのような遺体の発見に時間がかかってしまうと、風呂やトイレが故障したり、体液や血痕などが残る可能性もあります。
設備をリフォームする場合、交換費用は以下のとおりです。
- トイレの交換:トイレユニットそのものの購入費用は、3万~5万円程度
- お風呂の交換:ユニットバスの価格は、10万~15万円前後
- 洗面所の交換:洗面所の価格は、5万円程度
- エアコンの交換:新品のエアコン本体の費用は、3万~5万円程度
これらは設備自体の費用ですので、さらに工事費としてそれぞれ3~5万円程度の費用がかかります。
その他にも、前の設備を廃棄する費用も負担しなければなりません。
例えば、トイレとお風呂を交換する場合、30万円前後かかることが一般的です。エアコンを交換する時も、合計で5万円程度はかかると見積りしておきましょう。
キッチンや風呂、エアコンなど室内全体をリフォームする場合、50万円以上かかるケースもあります。
故人の遺族に原状回復費用を負担してもらえるケースもありますが、遺族と連絡が取れずに負担してもらえないこともあります。
事故物件のリフォーム業者を選ぶ3つのポイント
リフォーム費用の相場を確認したところで、次はリフォーム業者選びのポイントを見ていきましょう。
よいリフォーム業者を選べれば、費用も安く抑えつつリフォームできます。
以下の項目から、事故物件のリフォーム業者を選ぶポイントを順番に紹介していきます。
1.事故物件である事実を伝えても断らない業者
もっとも重要なのは、事故物件である事実をリフォーム業者へ最初に伝えることです。
リフォーム業者の中には、事故物件のリフォームを断る会社もあります。
また、リフォーム前に特殊清掃を実施することも検討しましょう。
ある程度、見た目を改善することで、リフォームを業者に依頼を受けてもらえる可能性が高まります。
2.リフォーム費用の細かい内訳を提示してくれる業者
2つ目のポイントは、見積りを出した時にリフォーム費用の細かい内訳を出してくれる業者を選ぶことです。
見積りの明細を作ることを嫌がり、一括で「リフォーム費用」や「職人人件費」などの曖昧な見積りを出すリフォーム業者もいます。
そういった曖昧な見積りしか提示してこないリフォーム業者は、工事後に費用を上乗せしてくる恐れがあるため注意しましょう。
細かな内訳を出してもらえば「本当に必要な費用なのか?」「ここはリフォームするべきなのか?」といったことが、自分で判断できます。
3.相見積を取ることを了承してくれる業者
リフォームを依頼する時は、複数のリフォーム業者へ相談して、相見積(あいみつ)を取ることも重要です。
相見積を取れば、リフォーム相場を把握しながら値引き交渉などができます。割高な費用で業者へ依頼してしまうことを防げます。
費用を比較することで「A社はトイレが安いけど、B社は壁紙が安い」など、検討できます。
ですので、必ず相見積を了承してくれる業者に依頼すべきです。
また、リフォーム業者に対しては、きちんと相見積を取ることを伝えておきましょう。
リフォーム業者に依頼してから工事完了までの流れ
実際にリフォーム業者に依頼してから、工事が完了するまでの流れは以下のように進みます。
- リフォーム業者に現地で見積してもらう
- 工期を見積りしてもらって工事日時を決定する
- リフォーム工事することを近隣住宅・他の住人へ告知する
- 決定した工期でリフォーム工事を実施する
- 立会いして物件の引渡し確認をする
次の項目から、実際の流れを順番に見ていきましょう。
リフォーム業者に現地で見積してもらう
現地見積の後、精密な見積をもう一度取ってもらいます。
ここで大幅に料金が変わることは少ないですが、初回の見積では確認できなかった欠陥が発覚するかもしれません。
リフォームに慣れている業者ほど、素人では気づけない欠陥まで見つけてくれる可能性が高いです。
工期を見積りしてもらって工事日時を決定する
見積り費用に問題なければ、工期の見積りと工事期間を決定します。工事期間が長くなればなるほど、職人の人件費がかかります。
できるだけ集中して短期間で工事してもらえる日時を選びましょう。
もしも、自分で立ち会いたい場合、立ち会いできる日時を工期に入れてもらいましょう。
また、リフォーム会社の忙しさによって、工事可能な日程が変わることもあります。
業者の都合にあわせて工期を調整できれば、リフォーム費用を割引してもらえるケースもあります。
リフォーム工事することを近隣住宅・他の住人へ告知する
工事が決まったら、必ず他の住人や近隣住宅へ告知しましょう。
リフォーム工事が開始されると、どうしても騒音が発生してしまいます。
基本的には平日の日中に工事しますが、日中に在宅している住人もいるでしょう。
リフォーム業者が近隣住民へ説明してくれることも多いですが、施主である自分も挨拶に伺った方がトラブルを避けられるでしょう。
決定した工期でリフォーム工事を実施する
他の住人や近隣住民への説明が済んだら、決定した工期でリフォーム工事が実施されます。
1部屋だけのリフォーム工事であれば、数日程度で終わるでしょう。
ただし「壁紙と床の交換はA社、キッチンやバスの交換はB社」など、複数の業者へ依頼する場合、リフォーム工事が1週間程度かかることもあります。
事前にリフォーム会社へ確認をとっておきましょう。
立会いして物件の引渡し確認をする
リフォーム工事の完了の知らせを受けたら、必ず立会いして物件の引渡しをおこないます。
「この部分をこのようにリフォームしました」という報告を受けたら、工事の内訳を見ながら、ひとつずつ細かくチェックしていきましょう。
少しでも疑問に思う点があれば、必ずこの場で解決しておきましょう。
そして、リフォームにかかった工事費用の最終確認をします。
リフォーム後の事故物件を貸し出す・売却するときは「告知義務」に注意!
事故物件のリフォームが完了すれば、物件が賃貸運営・売却できる状態になります。
しかし、事故物件となった以上、そのまま売り出す・貸し出すことはできません。
事故物件となった物件を賃貸運営・売却する場合「告知義務」に注意しましょう。
告知義務とは・・・告知義務とは、不動産売買を平等に進めるため、物件について知り得る情報を売主から買主へ告知しなければならない義務のこと
事故物件を賃貸運営・売却する際は「事故物件であること」を必ず告知しなくてはなりません。
告知義務を怠ると損害賠償請求される恐れもある
物件の取引する際は、告知義務を果たさなくてはなりません。
「事故物件であることを伝えると、売れないかも・・・」と考えるかもしれませんが、事故物件であることを隠すことは絶対にやめましょう。
契約後に事故物件であることが判明すると、契約不適合責任によって損害賠償請求される恐れもあります。
そのため、事故物件を売買・賃貸する際は、リフォームしたとしても、事故物件であることを告知しましょう。
事故物件を売るなら「訳あり物件専門の買取業者」がおすすめ
ここまで説明した通り、事故物件を取引する際は告知義務があります。
そのため、事故物件を賃貸運営・売却しようとしても、なかなか居住希望者は現れません。
そこで、おすすめしたいのが「訳あり物件専門の買取業者」への売却です。
業者が直接買い取ってくれるため、事故物件であっても売れ残りません。
また、事故物件をリフォームせず、そのままの状態で売ることもできます。まずは以下のフォームから、無料査定を受けてみて下さい。
事故物件がリフォーム前でも買取可能です!まずは、お気軽にお問い合わせください。
最短48時間のスピード買取で
不動産を現金化
「高く・早く・トラブルなく」
売却したいなら
訳あり物件買取専門の
当社にお任せください!
まとめ
自分の物件が事故物件となってしまうと、賃貸運営・売却時に大きなリスクを抱えます。
再び利用できる状態にするには、特殊清掃とリフォームを施さなければいけません。
事故物件をリフォームするときは、建物や設備の状況によって大きく値段が変動します。50万円程度かかるケースもあるため、事前に査定を受けることが大切です。
なお「訳あり不動産専門の買取業者」になら、リフォームが済んでいない物件でも売却できるのでおすすめです。
>>【無料相談】事故物件・訳あり物件の高値買取窓口はこちら
事故物件のリフォームでよくある質問
そもそも、事故物件はどんな物件なの?
一般的には「死人がでた物件」を事故物件といいますが、法律や条例で定義されているわけではありません。
事故物件のリフォーム費用相場は?
壁紙や床の交換費用は約5~7万円です。もしも、トイレやキッチンなど設備の交換が必要であれば、約50万円の費用が必要になります。
事故物件のリフォーム業者はどう選ぶ?
「事故物件である事実を伝えても断らない業者」「リフォーム費用の細かい内訳を提示してくれる業者」「相見積を取ることを了承してくれる業者」といった3つのポイントを意識するとよいです。
リフォームした事故物件はいくらで貸し出せる?
事故物件だからといって、明確な家賃の相場はありません。ただし、多くの入居者を募るために、事故内容に応じて家賃を値引きする必要があります。
リフォーム後の事故物件を貸し出すときの注意点は?
心理的瑕疵物件であることを借主へ必ず告知するよう気を付けましょう。もしも、事故物件であることを隠して貸し出すと、損害賠償請求に発展する恐れがあります。
訳あり不動産の売却でお悩みなら
今すぐご連絡ください
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-