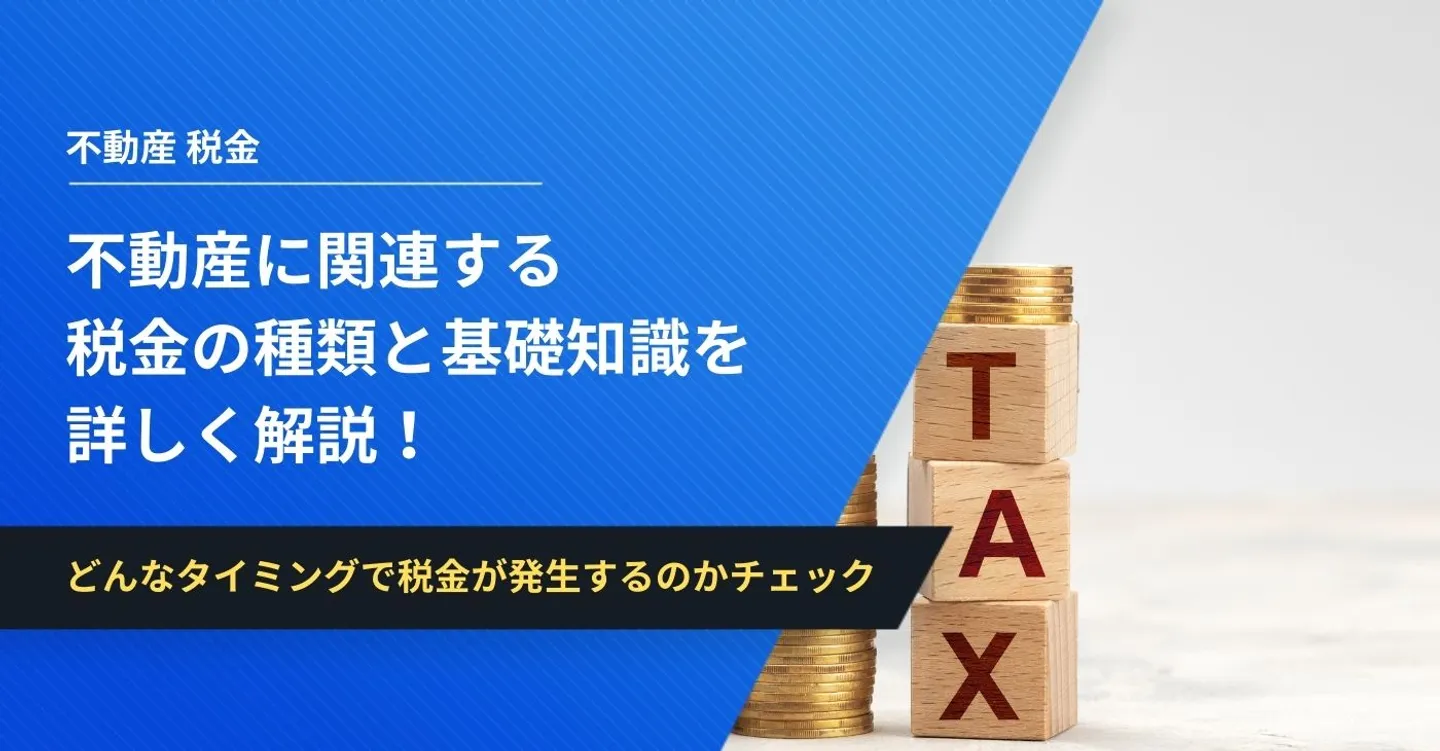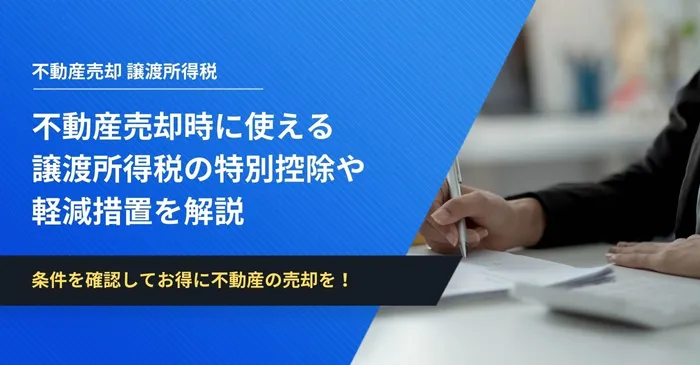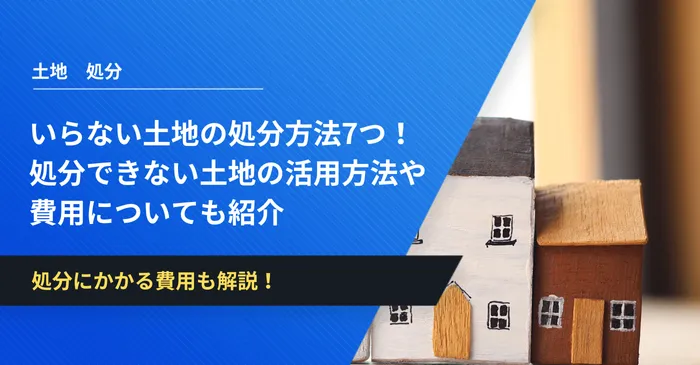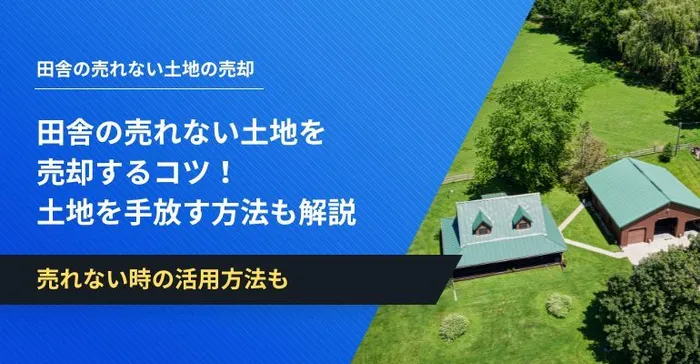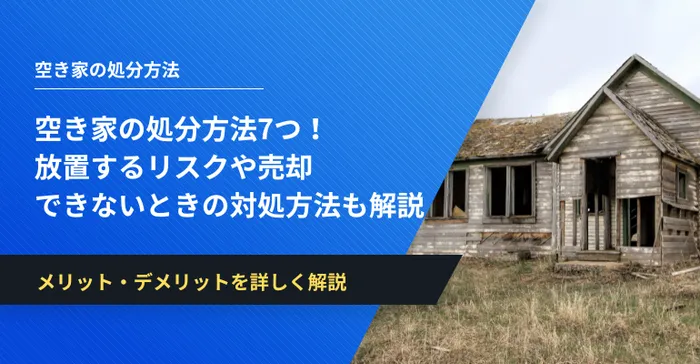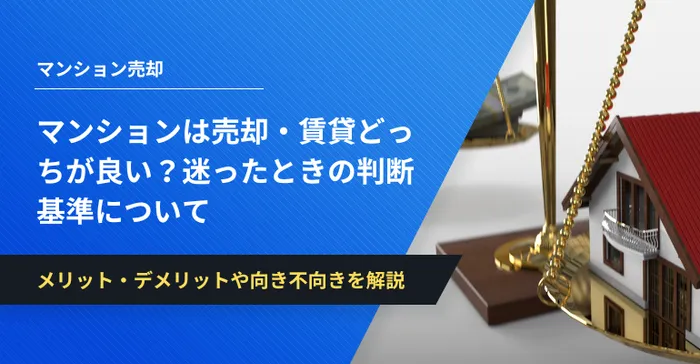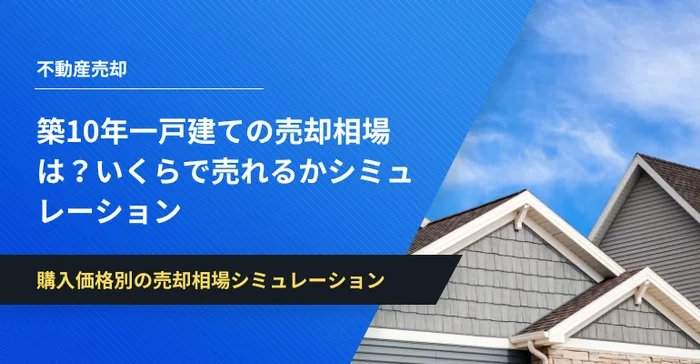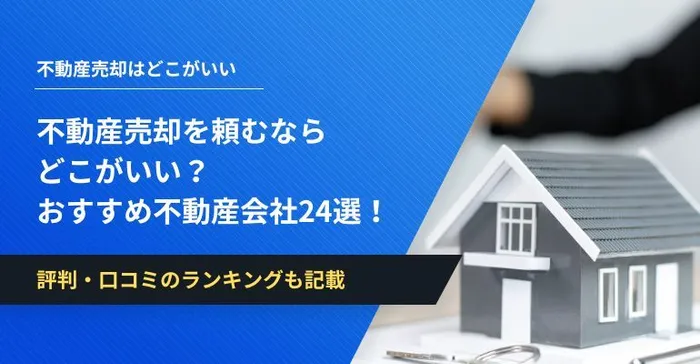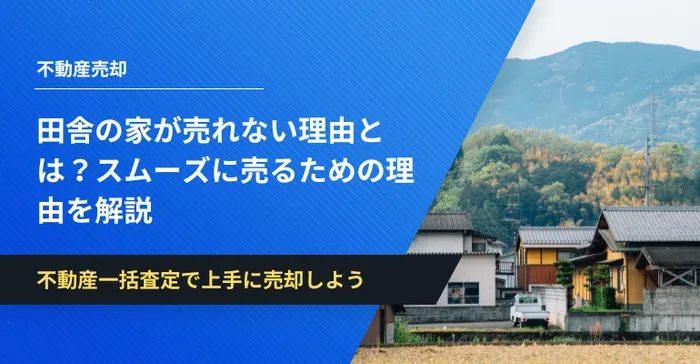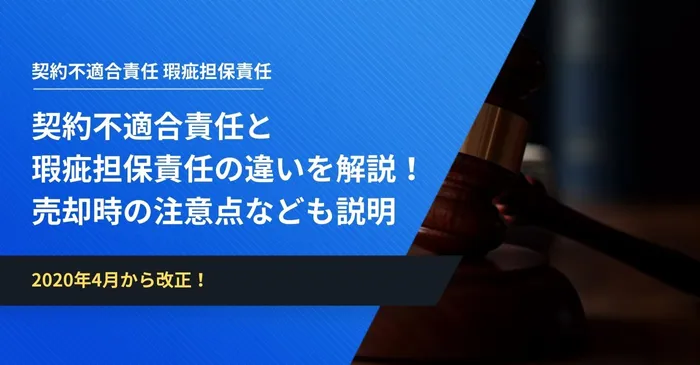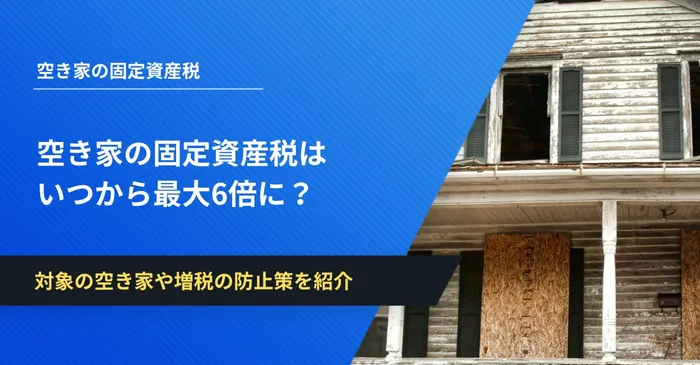不動産を取得した時にかかる税金
不動産を取得した時に課される税金は、主に下記の4つです。
どの税金も、不動産の課税標準(課税の基準となる金額)に、税率を乗じて計算します。
不動産は高額な資産なため、上記の税金も数十万~数百万円にのぼる可能性があるので注意しましょう。
不動産取得税
土地や建物といった不動産を取得するとき、不動産取得税が発生します。不動産の所有権を取得した人に対して、都道府県が課す税金です。
固定資産税評価額を基準に、税率を乗じて算出します。不動産取得税の標準税率は4%ですが、軽減措置などによって税率が下がる場合もあります。
不動産を取得すれば、登記の有無に関わらず課税されます。しかし、相続など一部の取得原因によっては非課税です。
| 課税される取得原因 |
・売買
・交換
・贈与(死因贈与を含む)
・新築
・増改築 |
| 課税されない取得原因 |
・相続
・遺贈(包括遺贈および相続人への特定遺贈を含む)
・遺言信託
・譲渡担保
・土地区画整理事業の換地など |
また、次に紹介する「免税点」未満の金額で行われた不動産取得であれば、課税されません。
| 取得の区分 |
免税点となる金額 |
| 土地の取得 |
10万円未満 |
| 建物の取得(建築にかかるもの) |
1戸につき23万円未満 |
| 建物の取得(建築以外のもの) |
1戸につき12万円未満 |
免税点の課税標準額に関しては、固定資産税評価額に特別控除などを適用して求めます。
他にも、取得した不動産が公共用の道路など公益のために使用される場合も、不動産取得税は非課税になります。
参照:東京都主税局「不動産取得税」
登録免許税
不動産を取得して、所有権移転登記や保存登記などを申請する際「登録免許税」がかかります。
登録免許税は「登記の種類」と「登記する不動産の種類」によって税額が変わるので注意しましょう。
課税標準に、下記の税率を乗じます。登録免許税の課税標準は「固定資産税評価額もしくは法務局が地域ごとに定める価格」です(抵当権設定登記は債権金額または極度金額)。
土地の所有権の移転登記
| 登記の種類 |
税率 |
| 土地の売買 |
2%
※軽減税率により1.5%(2021年現在)
|
| 建物の売買 |
2%
※軽減税率により住宅用家屋は0.1~0.3%(2021年現在)
|
| 建物の所有権保存 |
0.4%
※軽減税率により住宅用家屋は0.1~0.15%(2021年現在)
|
| 相続 |
0.4% |
| 贈与・遺贈 |
2% |
| 抵当権の設定 |
0.4%
※軽減税率により住宅ローンは0.1%(2021年現在) |
参考:国税庁「登録免許税の税額表」
印紙税
印紙税とは、契約書や領収書など特定の書類に対して課される税金です。対象の書類に、印紙税を貼りつけることで納税します。
税額は、書類の種類と記載された金額(契約金額や領収金額)によって変わります。
下記は、印紙税における書類の種類と税額を、一部抜粋したものです。
| 書類種別 |
契約金額および印紙税額 |
・不動産の譲渡に関する契約書
・地上権または土地の貸借権の設定や譲渡に関する契約書
・消費貸借に関する契約書(住宅ローンの契約書など)
・運送に関する契約書 |
10万円以下のもの・・・200円 |
| 10万円を超え50万円以下・・・400円 |
| 50万円を超え100万円以下・・・1,000円 |
| 100万円を超え500万円以下・・・2,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下・・・1万円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下・・・2万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下・・・6万円 |
| 1億円を超え5億円以下・・・10万円 |
| 5億円を超え10億円以下・・・20万円 |
| 10億円を超え50億円以下・・・40万円 |
| 50億円を超えるもの・・・60万円 |
契約金額の記載のない契約書・・・200円
(契約金額1万円未満の契約書は非課税) |
・請負に関する契約書
(建築工事、設計、不動産鑑定、会計・税務の契約書など) |
100万円以下・・・200円 |
| 100万円を超え200万円以下・・・400円 |
| 200万円を超え300万円以下・・・1,000円 |
| 300万円を超え500万円以下・・・2,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下・・・1万円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下・・・2万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下・・・6万円 |
| 1億円を超え5億円以下・・・10万円 |
| 5億円を超え10億円以下・・・20万円 |
| 10億円を超え50億円以下・・・40万円 |
| 50億円を超えるもの・・・60万円 |
契約金額の記載のない契約書1通 200円
(契約金額1万円未満の契約書は非課税) |
| ・債務の保証に関する契約書 |
1通につき200円
(身元保証に関する契約書は非課税) |
| ・売上代金にかかる金銭または有価証券の受取書 |
100万円以下・・・200円 |
| 100万円を超え200万円以下・・・400円 |
| 200万円を超え300万円以下・・・600円 |
| 300万円を超え500万円以下・・・1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下・・・2,000円 |
| 1,000万円を超え2,000万円以下・・・4,000円 |
| 2,000万円を超え3,000万円以下・・・6,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下・・・1万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下・・・2万円 |
| 1億円を超え2億円以下・・・4万円 |
| 2億円を超え3億円以下・・・6万円 |
| 3億円を超え5億円以下・・・10万円 |
| 5億円を超え10億円以下・・・15万円 |
| 10億円を超えるもの・・・20万円 |
| ・売上代金にかかる金銭または有価証券の受取書以外の受取書 |
1通につき200円
(記載された受け取り金額が3万円未満のもの、および営業によらないものは非課税) |
ただし、不動産売買契約書には軽減措置があるため、実際の税率は上記より低くなります。
参照:国税庁「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
参照:国税庁「印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」
不動産売買契約書の印紙税の軽減措置について
不動産売買契約書に貼る印紙については、印紙税の軽減措置が適用されます。
先に紹介した金額ではなく、下記の金額を納めます。
| 書類 |
契約金額および軽減後の印紙税額 |
| 軽減措置の対象となる不動産の譲渡に関する契約書 |
10万円を超え50万円以下・・・200円 |
| 50万円を超え100万円以下・・・500円 |
| 100万円を超え500万円以下・・・1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下・・・5,000円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下・・・1万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下・・・3万円 |
| 1億円を超え5億円以下・・・6万円 |
| 5億円を超え10億円以下・・・16万円 |
| 10億円を超え50億円以下・・・32万円 |
| 50億円を超えるもの・・・48万円 |
参照:国税庁「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」
印紙税は「消費税の書き方」によって税額が変わる
印紙税を計算するための基準となる契約金額には、消費税が含まれる場合と含まれない場合があります。
例えば、次のように「消費税に相当する金額がいくらなのか」が明記されていれば、契約金額は税抜金額で考えることができます。
例1:建物代金1,000万円 消費税額 100万円
例2:建物代金1,000万円 うち消費税額 100万円
どちらの場合も契約金額は1,000万円となるので、譲渡契約書の印紙税額は1万円で済みます。
しかし、次のような記載では消費税額が実際にいくらなのかが記載されていないため、税込金額が契約金額とされてしまいます。
例1:建物代金 1,100万円(消費税額10%を含む)
例2:建物代金 1,100万円(税込)
上記の場合は契約金額が1,100万円となるため、譲渡契約書の印紙税額は2万円になってしまいます。
消費税
建物を購入したり、新築したりする場合には、実際に取引された金額に対して消費税がかかります。建物の仲介に利用した不動産会社へ支払う仲介手数料も、その全額に対して消費税が課税されます。
消費税額=建物の購入代金など×消費税率10%
消費税率の10%のうち7.8%が国税となり、2.2%は地方税となります。
ただし、取得した不動産が土地の場合や、売主が個人や免税事業者である建物の場合、消費税は課税されません。
不動産を保有している間にかかる税金
不動産を保有している間に発生するのは「固定資産税」と「都市計画税」の2つです。
どちらもの市区町村が管轄する地方税であり、2つは一緒に課税されます。
不動産を保有し続ける限り課税されるので、不要な不動産があれば早めに処分したほうがよいでしょう。
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物、償却資産などの不動産を所有している人に対し、市町村(東京23区は都)が課す税金です。
固定資産税の計算は、次の式で求められます。
固定資産税=固定資産税評価額×1.4%
1.4%は、固定資産税の標準税率となります。固定資産税の税率は最高で2.1%と定められていますが、ほとんどの市区町村が標準税率の1.4%を採用しています。
固定資産税評価額は、3年に1度「評価替え」によって見直されます。評価替えによって、現状に見合う適正な評価額にもとづいて課税されるのです。
評価替えが実施される年度は「基準年度」と呼ばれます。基準年度の翌年、翌々年の固定資産税は、基準年度の評価で計算するのが原則です。
ただし、新築・増改築等のあった建物や、分筆・合筆のあった土地など、基準年度の評価が適当ではない状況の場合、基準年度と関係なく新たに評価されます。
参照:e-Govポータル「地方税法第341条、第409条」
都市計画税
都市計画税とは、市町村(東京23区は都)が、市街化区域内に所在する土地や建物の所有者に対して課税するものです。
都市計画税の計算は、次の式で求められます。
都市計画税=固定資産税評価額 × 0.3%
0.3%という税率は、都市計画税の最高限度の税率となっています。
都市計画税の課税自体が市区町村の任意によるものであるため、0.3%までの範囲内で各市区町村が自由に税率を定めています。
都市計画税の課税対象にならない不動産もある
都市計画税が課税されるのは、市街化区域に所在している不動産のみです。
そのため、市街化調整区域や無指定区域の不動産には原則として課税されません。
ただし、特定の開発区域内で都市計画事業が行われる場合には、都市計画税が課税されることもあります。
不動産を売却した時にかかる税金
不動産の売却で課税されるのは「譲渡所得税」と「住民税」の2つです。
譲渡所得税は国税、住民税は都道府県が課す地方税ですが、申告は一緒におこないます。
不動産の売却価格から各種経費を差し引き、税率を乗じることで課税額を算出します。
譲渡所得税・住民税
譲渡所得税と住民税の課税対象となるのは、不動産を売却したことで得られた利益です。不動産売却で得た利益は「譲渡所得」と呼ばれます。
譲渡所得税と住民税は分離課税となり、給与所得や事業所得など他の所得とは分離して課税されます。なお、譲渡所得がマイナスになった場合には課税されません。
譲渡所得税と住民税を計算するためには、譲渡所得がいくらだったのかを計算する必要があります。計算式は、次のとおりです。
譲渡所得=不動産の売却価格-(取得費+譲渡費用)
譲渡所得税と住民税の税率は「所有期間」で変わる
譲渡所得税と住民税における税率は、不動産を売却した年の1月1日時点における、当該不動産の保有年数で変わります。
保有期間が5年超の不動産は「長期譲渡所得」とされ、所得税が15.315%、住民税が5%となります。合計で20.315%の税率です。
保有期間が5年以下の不動産は「短期譲渡所得」とされ、所得税が30.63%、住民税9%となります。合計で39.63%の税率です。
※上記の所得税率には、2037年まで課税される「復興特別所得税」が上乗せされています。
譲渡所得を計算するときの「取得費」にはなにが含まれる?
譲渡所得を計算するときは、売却不動産の取得費を算出しなければいけません。
取得費は、下記にあげる「不動産取得時の支出」を合算します。
1.不動産の購入代金
当該不動産を取得するために支払った費用は、当然取得費に含まれます。売買契約書に記載されている金額から、減価償却費を差し引いて算出するのが基本です。
減価償却費の計算は、不動産の種類や構造、用途によって異なります。税理士などの専門家に問い合わせるか、国税庁などが公表している一覧表を確認して正確に計算しましょう。
2.仲介手数料
当該不動産を取得するために不動産会社へ支払った仲介手数料も、取得費の一部です。仲介手数料の領収書などで金額を確認しましょう。
領収書が見つからなければ、見積書などで代用できる場合もあります。
3.印紙税
不動産を事業目的ではなく、住居などとして利用していた場合は、購入時に支払った印紙税も取得費に含めることができます。
4.登録免許税
登記申請のときに支払う登録免許税は、取得費の一部となります。
5.不動産取得税
当該不動産が事業用ではない場合には、不動産取得税は取得費に含めて計算できます。
6.建物の撤去費用
古い建物がある土地を購入し、その建物をすぐに取り壊して新しい建物を建てる場合、取り壊しに要した費用も取得費に含めることができます。
7.立ち退き費用
取得したい不動産に住んでいた人に対し、取得に先立って立ち退いてもらうために金銭を支払っているなら、立ち退き費用として取得費に含めることができます。
取得費が不明もしくは少額のときは「売却価格の5%」で計算する
不動産の取得時期が古かったり、先祖伝来の土地であったりすると、取得費がわからないというケースがあります。
取得費がわからない場合、不動産を売却した価格の5%を取得費とすることが可能です。
また、取得費が判明している場合でも、ごく少額であった場合は同じように5%相当額まで修正できます。
つまり、譲渡所得を算出するときは、最低でも「売却価格の5%」が取得費になるということです。
まとめ
不動産にまつわる税金はたくさんの種類がありますが、一定要件を満たすことで軽減や繰り延べをできる特例もあります。
しかし、要件や期限が細かく設定されており、適用には複雑な手続きが必要です。
個々の状況によって最適な節税方法も異なるため、税金の専門家である税理士に相談してみるとよいでしょう。
不動産の税金についてよくある質問
不動産を取得するときに発生する税金とはどんなものですか?
不動産を取得したことに対する「不動産取得税」や、登記申請時に支払う「登録免許税」などがあります。
不動産を保有しているときに発生する税金とはどんなものですか?
「固定資産税」と「都市計画税」があげられます。どちらも市町村が課税するもので、毎年1月1日時点の不動産所有者に課されます。
不動産を売却するときに発生する税金とはどんなものですか?
「譲渡所得税」と「住民税」があげられます。譲渡所得税は国税、住民税は地方税ですが、どちらも一緒に課税されます。
税金を抑える制度はありますか?
どの税金にも、税額の軽減や納税の繰り延べなどをできる特例があります。一律で適用されるものもあれば、別途申告が必要な制度もあるので、税理士や税務署などに確認しましょう。
税金に関する疑問や質問は、どこに相談すべきですか?
税金の専門家である、税理士に相談しましょう。税理士なら、個々の状況にあわせて最適な節税方法を提案できます。
訳あり不動産の売却でお悩みなら
今すぐご連絡ください
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-