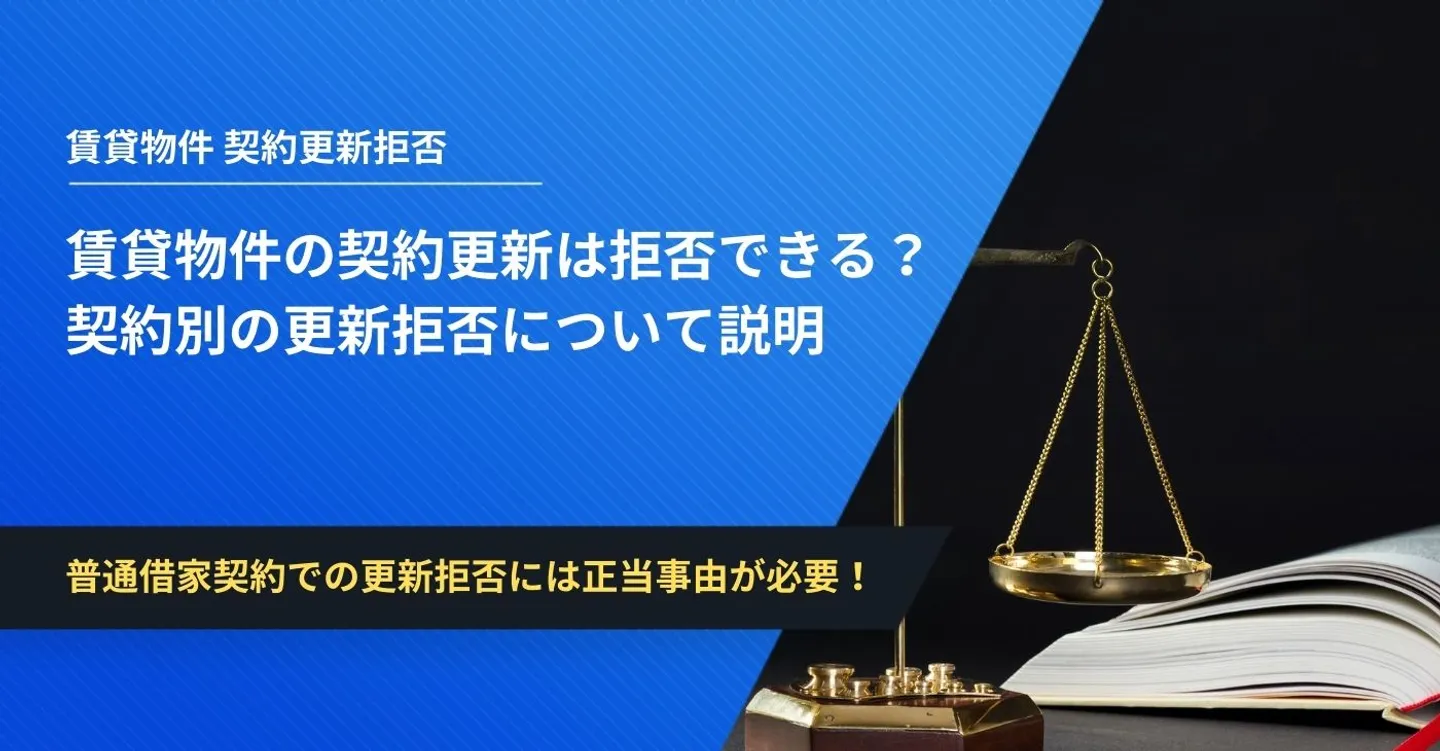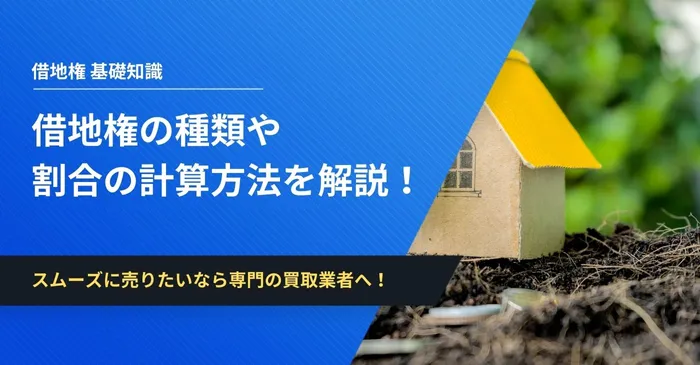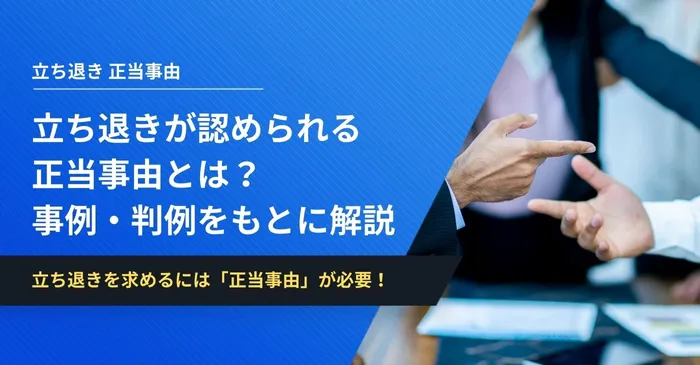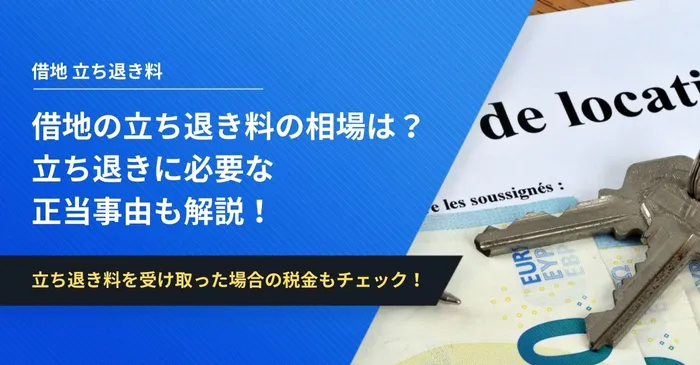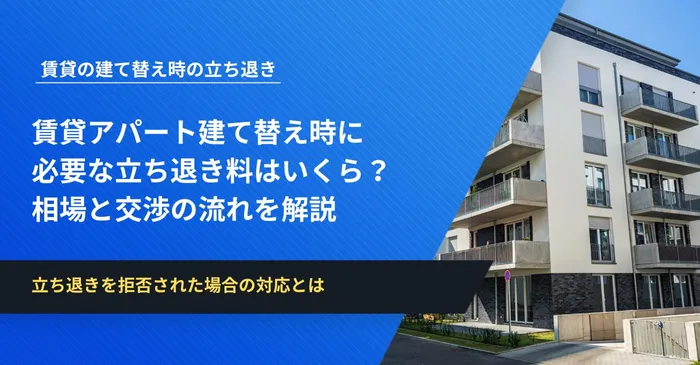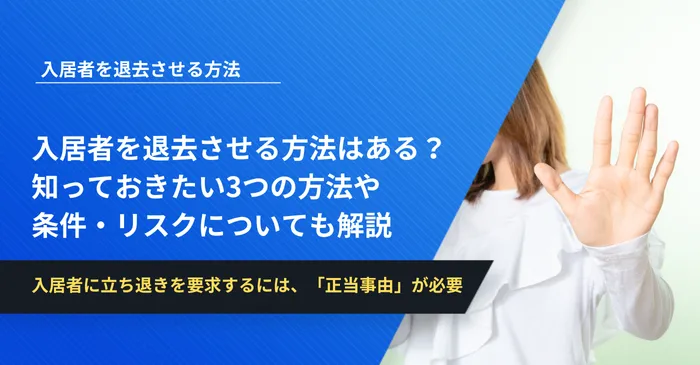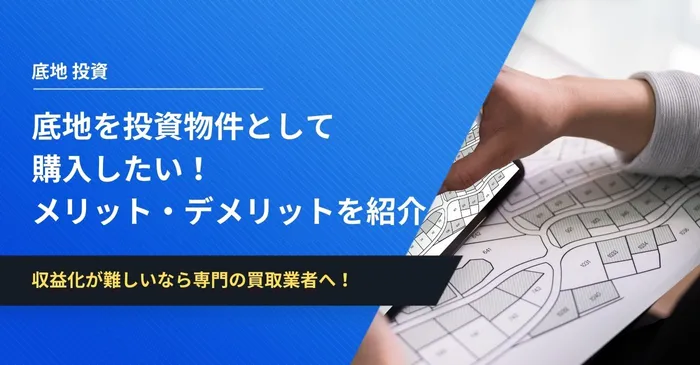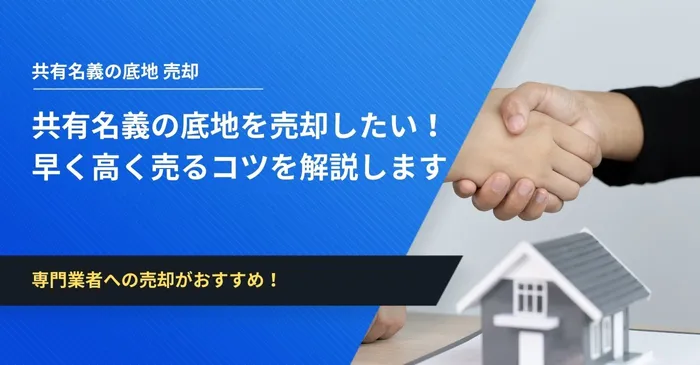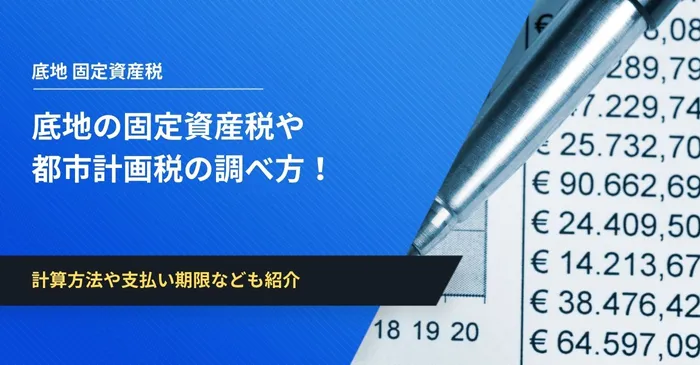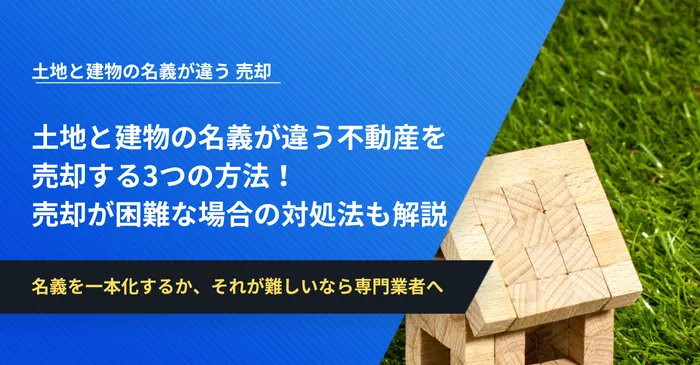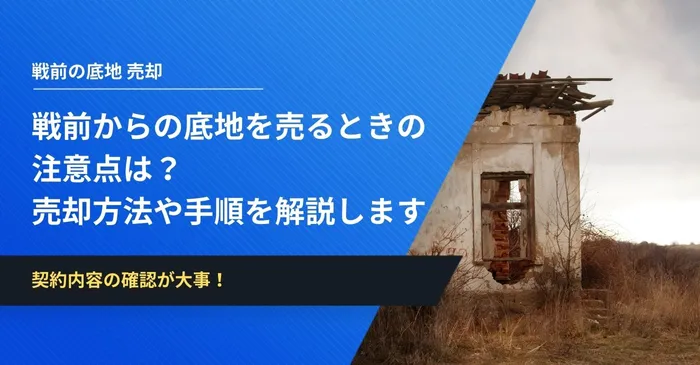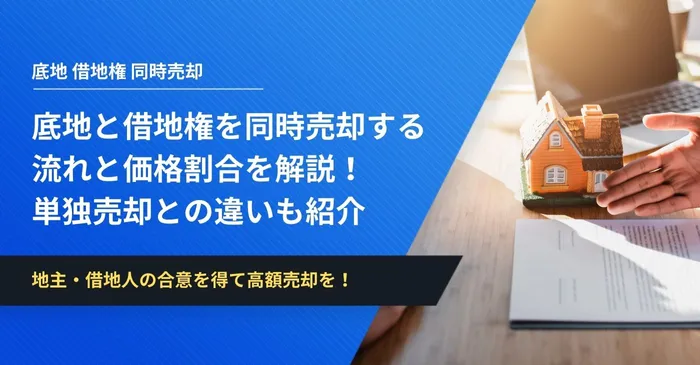「定期借家契約」の場合は契約更新の必要が無い
契約更新を拒否したい相手との契約が「定期借家契約」なら、期間満了時になれば問題なく更新拒否できます。
言い換えると、そもそも定期借家契約には、契約の更新がありません。定期借家契約とは、原則として契約を更新することがなく、一定の期間に達した時点で終了する賃貸借契約のことを指しています。
例えば「定期借家2年」という条件付きの物件に入居した人は、入居後2年が経過すれば賃貸借契約は終了するので退去しなければなりません。
定期借家契約を結びたい場合は、普通借家契約に一定の要件をプラスした内容で契約します。
例えば、賃貸借契約書に「期間満了後の更新は無い」ことをはっきり記載したり、賃貸借契約書とは別に定期借家に関する書類を用意し、契約締結時に借主に交付して内容を説明するなどの手続きが必要です。
なお、定期借家の契約書は、公正証書によって作成するのがベストです。
定期借家契約は、一般のアパートやマンションなど居住用の物件だけでなく、店舗や倉庫などの事業用物件にも適用可能です。
定期借家契約に決められた期間はない
定期借家契約の期間には、最低期間や最長期間などの制限はありません。貸主と借主の間で自由に設定できます。
ただし、特約がない限り賃料の随時改定ができないため、不必要に契約期間を長くすることは避けるべきです。
定期借家契約は、期間が満了すると同時に終了します。期間満了後に、借主が契約の更新を求めることはできません。
貸主の同意があれば再契約できますので、その場合は再び契約書を取り交わすことで再契約できます。定期借家契約の場合、期間満了と同時に当初交わされた契約は終了しているため、契約の「更新」ではなく「再契約」扱いとなります。
ちなみに、契約期間が1年以上に設定されている定期借家については、契約期間の満了について貸主が借主へ事前通知することが義務付けられています。
「普通借家契約」の場合は契約更新の拒否が困難
最も一般的な賃貸借契約の「普通借家契約」では、契約更新を拒否することは非常に難しくなります。
入居の期限が定められることはなく、原則として契約は更新されていくことになります。
借主側が中途解約を申し出た場合は、契約内容に従った手続きを踏むことで解約が可能になります。
一方、貸主側の都合で契約更新を拒否したい場合は「正当事由」が必要になります。
契約更新を拒否するには「正当事由」が必要
「正当事由」とは、更新拒否が妥当であると言える事情、もしくは事実のことを意味しています。
そして、正当事由とされるものには以下のようなものがあります。
- 十分な立退料を支払うこと
- 貸主の状況の変化
- 物件の劣化
- 借主の債務不履行による信頼関係の破壊
それぞれ、具体的に見ていきましょう。
1.十分な立退料を支払うこと
立退料とは、貸主の都合で借主に退去を求める場合、貸主から借主に支払われる金銭のことを指します。
具体的には「借主が新しい家を見つけて契約するための費用」「そこへ引っ越すための費用に相当する額」「店舗として使用されていた物件であれば営業補償」などを考慮して、立退料の金額が決まります。
賃貸物件の場合は居住年数が長ければ長いほど、借主はその地域の環境や習慣、気候に順応し、愛着を抱いている可能性が高いものです。
近隣の人々との親しい人間関係も、借主が長年生活する中で培ってきたひとつの財産です。
店舗などの事業用物件であれば、その地域で築いてきた評判や顧客との信頼関係は事業を継続する上で非常に重要な資産であり、別の場所に移転することで被る損害は軽視できません。
立退料の算定にあたっては、借主が長年生活の本拠地としてきた地域を去ることの重大さと損失を、十分考慮しなければなりません。
2.貸主の状況の変化
貸主の側に、やむを得ない事情が発生することもあります。
例えば、貸主の居住している建物が経年劣化や災害、事故などでひどいダメージを受け、引き続き居住することが困難になるかもしれません。
修繕して何とかなる状態ではないのなら、借主に借している建物を取り戻し、自分の生活の場とする他ない場合もあります。
どのようなケースが正当事由に該当するかどうかは、貸主の家が被ったダメージがどれほどのものか、代わりに居住できる建物を他に持っていないか、などの要素に左右されます。
貸主の個人的な事情が正当事由と判断されるためには、事情の深刻さが重要になります。
3.物件の劣化
契約中の賃貸物件が老朽化したり、地震や台風などの被害を受けることで、居住に適さない状態になることもあります。
このケースは借主側の身体の安全に直接関係することなので、正当事由と認められやすくなるでしょう。
それでも、軽微な地震などで倒壊のおそれがあるほどに危険が切迫しているのか、それとも修繕の見込みがあるのかによって、正当事由としての重みが変わってきます。
4.借主の債務不履行による信頼関係の破壊
借主が、賃貸借契約を誠実に履行しないために、貸主との信頼関係が損なわれた場合は、契約を解除できます。
信頼関係の破壊による契約解除は、契約期間満了後の更新拒否とは制度自体が違うため、契約更新を待たずに着手できます。
借主の債務不履行に該当するのは、下記のような行為です。
- 賃料を支払わない
- 物件を契約内容と異なる目的で使用している
- 物件の利用状況が著しく不適切である
債務不履行に加え、信頼関係の破壊があって初めて、貸主の側から一方的に契約解除することが可能になります。
また、支払いの約束をしたにもかかわらず、繰り返し約束を反故にした場合も信頼関係の破壊がなされたことになるでしょう。
しかし「信頼関係が破壊された」かどうかは、簡単に判断できません。
実際に契約更新を拒否したいなら、まずは不動産問題に詳しい弁護士へ相談してみましょう。
正当事由は必ず認められるわけではないので注意
正当事由として認められてきた4点をご紹介しました。
4番目の債務不履行については、正当事由云々という問題を超えた事態でもあるので、更新時期がやってくる前に契約解除することも検討しましょう。
ただし「上記のいずれか1点に該当していれば、それで正当事由が成立する」わけではありません。
正当事由を争った過去の裁判においては「契約拒否に至った貸主の事情と借主の事情」「借主との契約期間の長さや物件の状態」など、複合的な要素を客観的に考慮した上で判決が下されています。
正当事由が認められるかどうかは、ケースバイケースとなります。
契約更新に関するトラブルが起きたら弁護士に相談!
正当事由に基づく契約更新拒否を提示して、借主がすんなりと受け入れてくれれば何の問題もありません。
しかし実際には、借主に何かの落ち度や問題点があるため、更新拒否をして出て行ってもらいたいと考えている貸主も多いでしょう。
契約更新拒否に応じてくれない場合などは、両者の意見は対立しているのでトラブルに発展してしまいます。
当事者だけでトラブルを解決することはほぼ不可能です。
借主との話し合いでは解決できそうにない場合は、問題が大きくなる前に弁護士に相談しましょう。
まとめ
「定期借家契約」の場合は、契約更新の必要が無いといえます。
しかし「普通借家契約」の場合は、契約更新の拒否が困難になってしまいます。
正当事由が認められるには、さまざまな要素が関係するからです。
もしも、契約更新を拒否したい場合は、弁護士への相談を早めにすることで、解決までの時間も短くなり、かかる費用も抑えられるでしょう。
賃貸物件の契約更新に関するよくある質問
賃貸物件の契約更新は貸主から拒否できますか?
「定期借家契約」であれば、期間満了時に問題なく更新拒否できます。「普通借家契約」の場合でも、貸主側に正当事由があれば賃貸借契約を更新拒否できます。
普通借家契約ではどのような場合に更新拒否が認められますか?
十分な立退料を支払った場合や貸主の状況が変化した場合、また物件が劣化している場合や借主が債務不履行を起こした場合であれば、普通借家契約でも契約拒否が認められます。
正当事由にはどのようなものがありますか?
「十分な立退料を支払うこと」「貸主の状況の変化」「物件の劣化」「借主の債務不履行による信頼関係の破壊」といったものが正当事由として認められます。
正当事由があれば、普通借家契約の契約拒否は必ず認められますか?
過去の裁判においては、正当自由だけでなくさまざまな要素を考慮した上で判決が下されるため、必ずしも普通借家契約の契約拒否が認められるとは限りません。
契約更新に関するトラブルはどこへ相談できますか?
契約を更新拒否する旨を示しても、借主が拒否する場合、話し合いでは解決できないようであれば、弁護士へ相談しましょう。
訳あり不動産の売却でお悩みなら
今すぐご連絡ください
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-