譲渡所得税とは、不動産を売却したときに課される税金です。売却で得られた利益に対して課税されます。
不動産は高額な資産なので、課税額も高くなるのが一般的です。
しかし、控除や軽減措置の特例を活用すれば、大幅に節税することも可能です。
確定申告の際は、控除や軽減措置の適用を忘れず申請しましょう。
ただし、税制度や各種計算は非常に複雑です。手続きに不安があれば、税金の専門家である税理士に相談することをおすすめします。
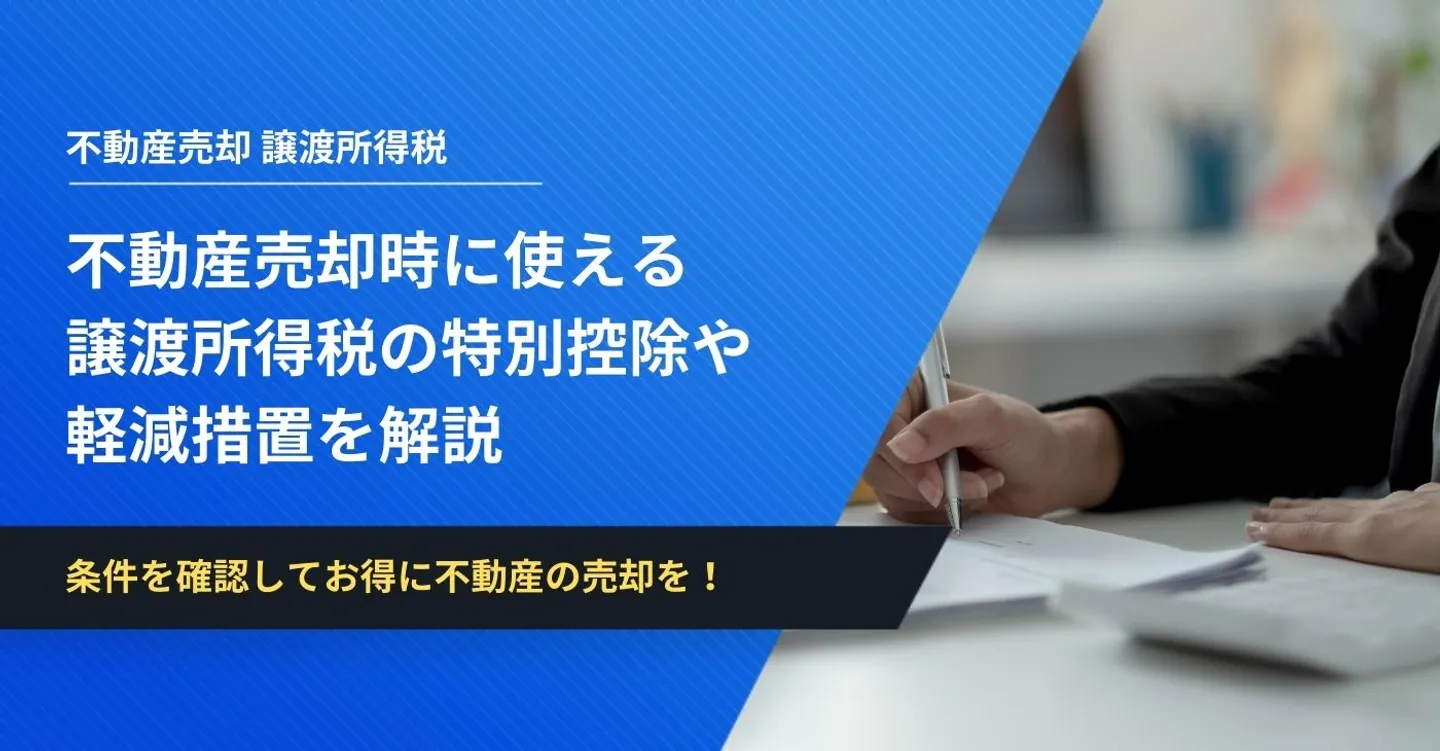
譲渡所得税とは、不動産を売却したときに課される税金です。売却で得られた利益に対して課税されます。
不動産は高額な資産なので、課税額も高くなるのが一般的です。
しかし、控除や軽減措置の特例を活用すれば、大幅に節税することも可能です。
確定申告の際は、控除や軽減措置の適用を忘れず申請しましょう。
ただし、税制度や各種計算は非常に複雑です。手続きに不安があれば、税金の専門家である税理士に相談することをおすすめします。

譲渡所得税という、不動産を売却するときにかかる税金があります。
所得とは、収入から経費などを差し引いたものです。給与所得や事業所得などいくつかの種類があります。
それらの所得は合計し総所得金額を求め、まとめて課税(総合課税)するのが原則です。総合課税は、利益と損失を相殺できる「損益通算」ができます。
しかし、不動産の売却に伴って生じる譲渡所得は、他の所得とは合算せず個別に計算する「分離課税」になります。
譲渡とは、権利・財産・地位などを他人に譲り渡すことです。不動産における譲渡とは、所有している不動産(土地や建物)を売却することをいいます。
譲渡所得とは、譲渡によって得た所得のことです。土地や建物などの所有資産を売却し、そこから得られた利益に課されます。
また、所得を自分で申告する必要がある「申告分離課税」でもあります。申告を忘れて納税せず放置していると、税務署から無申告税などのペナルティが課されるので注意しましょう。
ちなみに、不動産の売却以外で申告分離税にあてはまる所得には、株式の譲渡所得や先物取引による雑所得などがあげられます。詳しくは、税務署や税理士に聞いてみましょう。
不動産の譲渡所得税を計算するには、まず譲渡所得を計算しましょう。譲渡所得は、下記の計算式で算出します。
収入金額は、実際に買主から受け取る売却代金のことです。固定資産税や都市計画税の精算金も含まれます。
上記で算出した譲渡所得に、税率を乗じれば譲渡所得税の課税額がわかります。税率は、譲渡した年の1月1日時点における所有期間で変わります。
| 種別 | 所有期間 | 税率 |
|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 物件を譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が5年以下 | 39%(所得税30%+住民税9%) |
| 長期譲渡所得 | 物件を譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が5年超 | 20%(所得税15%+住民税5%) |
不動産の譲渡所得による住民税は、譲渡所得税と一緒に申告をおこないます(納付は別)。そのため、上記の表でも税率を併記しています。
譲渡所得を算出するときは、収入金額から取得費を差し引きます。取得費とは、文字どおり売却不動産を取得したときにかかった費用のことです。
取得費は、大きく分けて2つあります。
取得代金とは、購入や建築にかかった代金です。増改築などの改良費や設備費も、取得代金に含まれます。
建物の場合は、取得代金から減価償却相当額を差し引き、経年劣化による資産価値の低下を反映させます。
取得諸費用とは、取得時に発生した代金以外の費用です。購入時の仲介手数料や印紙税などの各種税金、取得から使用するまでの借入金の利子、測量費などが該当します。
上記の取得代金や取得諸費用が不明な場合、もしくはごく少額の場合、収入金額の5%を取得費とすることも可能です。
譲渡費用は、不動産を売却するためにかかった費用のことです。具体的には、以下のものが該当します。

譲渡所得税を申告するとき、要件を満たせば下記7つの特別控除を譲渡所得から差し引けます。
1から7の順番で適用され、年間で最大5,000万円まで控除されます。譲渡所得が控除額を下回る場合、課税されません。
公共事業による収用で不動産を売却した場合、5,000万円の控除を受けられます。
詳しい要件は、下記のとおりです。
この控除を受ける場合、確定申告のときには、公共事業の施行者から受けた公共事業用資産の買取に関する証明書などを提出する必要があります。
7つの特別控除のなかでも、とくに利用されるのが「マイホームを売却したときの3,000万円特別控除」です。
3,000万円の特別控除を受けるための要件は、下記のとおりです。
3,000万円の特別控除を受けるためには、確定申告時に下記の書類を提出します。
区画整理や再開発の事業において土地を売却した場合、2,000万円の控除を受けられます。
要件として、事業をおこなう施行者が下記にあてはまることが必要です。
また、譲渡が2年以上にまたがった場合、最初に売却した年以外は控除の対象にはなりません。
下記の施行者がおこなう宅地開発に伴って土地を売却した場合、1,500万円の控除を受けられます。
また、区画整理事業による控除と同様、売却が2年以上にまたがった場合、最初に譲渡した年しか対象にはなりません。
平成21年1月1日から平成22年12月31日までに取得した土地を売却した場合、1,000万円の控除を受けられます。
控除を受けるための要件は下記のとおりです。
確定申告時には、譲渡所得の内訳書や、売却した土地の取得年度がわかる書類の提出が必要です。
参照:国税庁「平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除」
一定の要件にあてはまる農地の売却では、800万円の控除を受けられます。
農用地利用集積計画にもとづく農地売却などで適用されます。
対象となる農地の要件は細かいものが多いので、税理士などに相談してみましょう。
都市計画区域内にある低未利用土地(土地がまったく使われていない、もしくは近隣と比べて利用の程度が低い土地)を売却した場合、100万円の控除を受けられます。
要件として、下記のものがあります。
確定申告時には、譲渡所得の内訳書や、上記要件を満たしているとわかる書類を提出する必要があります。
参照:国税庁「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」
ここまで譲渡所得税の特別控除について紹介しましたが、控除以外にも税額の軽減や課税繰越の特例がいくつかあります。
上記3つの特例について、詳しく見ていきましょう。
居住用の不動産を売却して利益が出た場合、一定の要件に当てはまれば、譲渡所得税(所得税・住民税)の税率が軽減される特例です。
具体的には、下記の税率が適用されます。
| 譲渡所得のうち6,000万円まで | 10% |
|---|---|
| 譲渡所得のうち6,000万円を超えた部分 | 15%+600万円 |
この特例を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
この特例は「3,000万円の特別控除の特例」と併用できます。
重複して適用できるため、長年住んでいた住宅を売却する場合や、譲渡所得税を多く支払う人にとっては、さらにメリットとなります。
この特例は、一般的に「課税の繰り延べ」といわれています。マイホーム買い換えに伴って売却した物件の課税を、新しく買った不動産を売却するときまで先延ばしにできる特例です。
この特例を受けるための要件は「売却した物件の要件」「新しい物件の要件」「その他の要件」の3種類にわけられます。
また、この特例と買い替え先の住宅ローン控除は同時に使えないため、注意が必要です。
物件を売却することによって、損失を出してしまうことも考えられます。
しかし、不動産の売却は分離課税であるため、基本的には他の所得と損益通算できません。
ただし、一定の要件を満たして申告をすれば、給与所得など他の所得との損益通算が可能になります。
マイホームを買い換えたとき、売却した物件について損が出た場合に使用できる特例です。
物件売却の損失額を、その年の他の所得から控除できます。また、その年の所得では控除しきれなかった場合、以後3年間まで繰り越して控除が可能です。
参照:国税庁「マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき」
住宅ローンが残っている物件を売却して譲渡損失が出たとき、ほかの所得との通算(損益通算)ができる特例です。
さらに、翌年以降3年間は、損失を繰り越して控除することもできます。
居住用財産の買い換えに関する損益通算・繰越控除とは異なり、新しく不動産を購入する必要がありません。
物件を売却後、アパートやマンションなど賃貸物件や実家に住む場合に利用できます。
参照:国税庁「住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき」
不動産の譲渡所得税には、さまざまな特例があります。控除の特例をうまく活用すれば、課税を0円にすることも可能です。
確定申告の際は、適用できる特例を忘れず申告しましょう。
また、税金や確定申告で不安があれば、税金の専門家である税理士に相談しましょう。個々の状況にあわせて、最適な節税方法を提案してくれます。