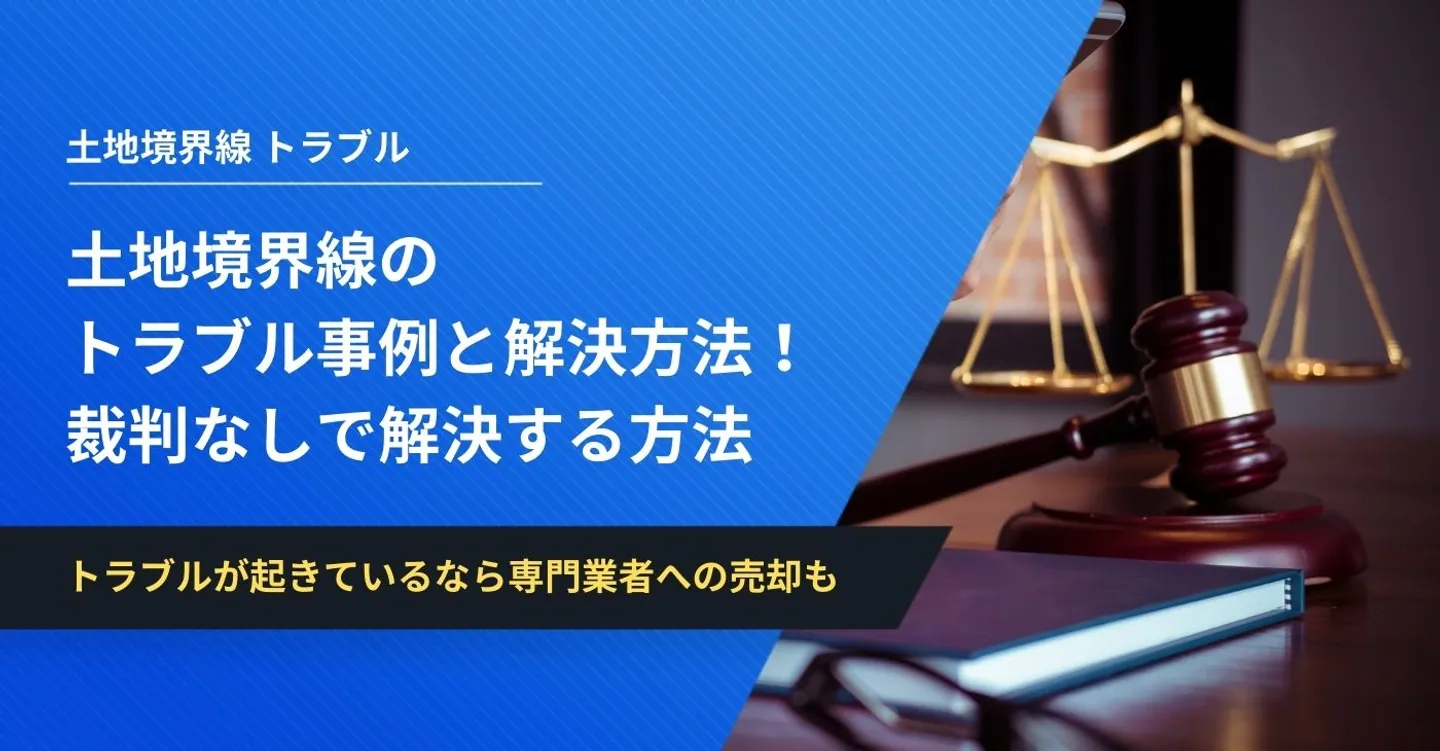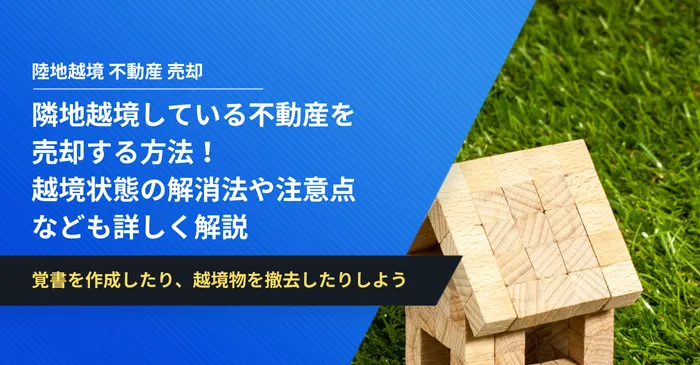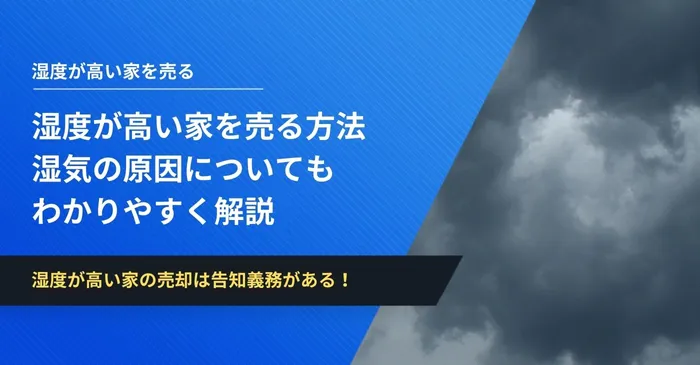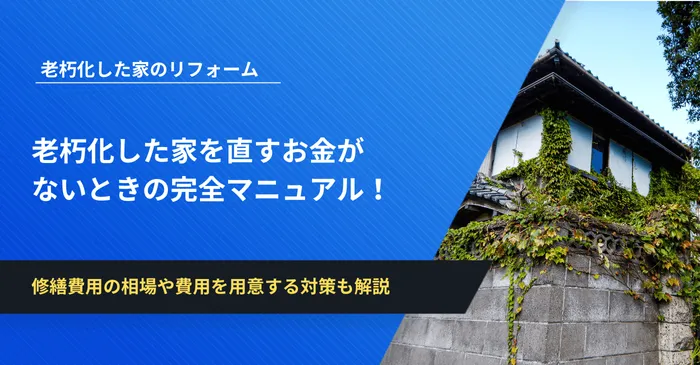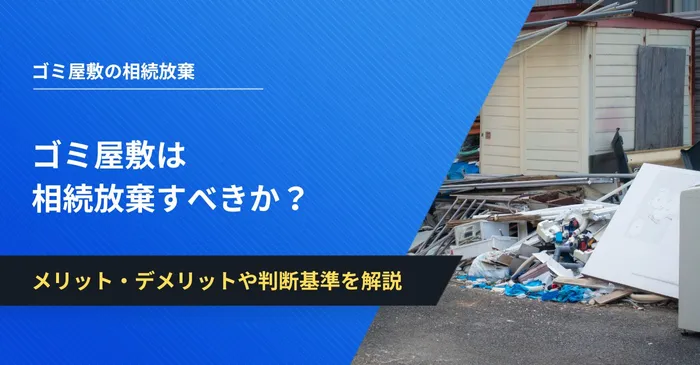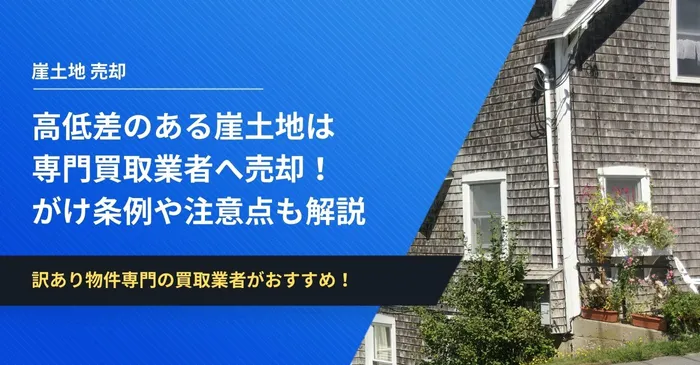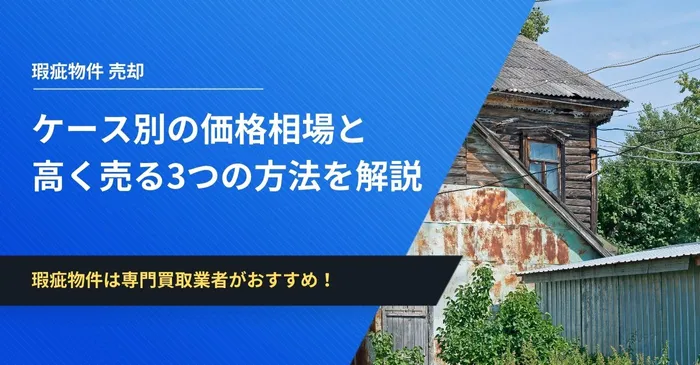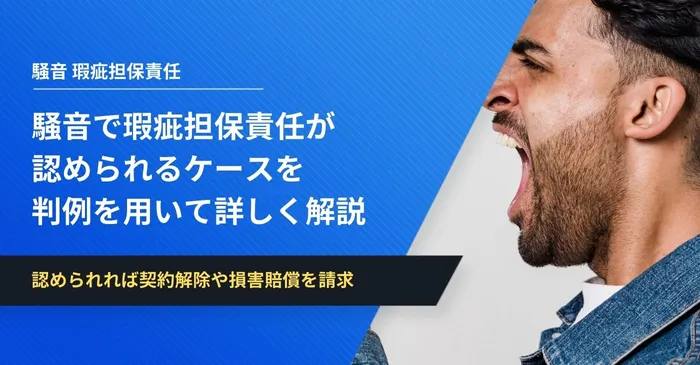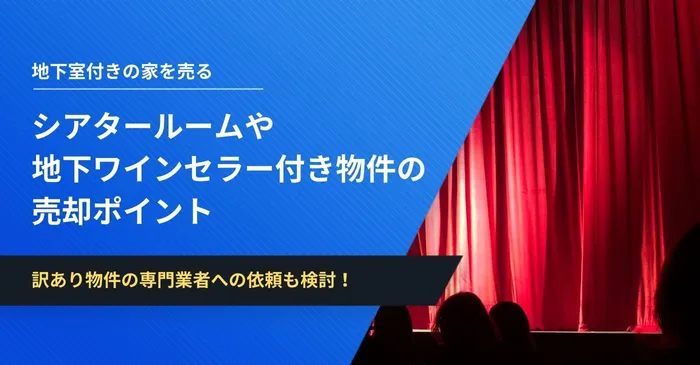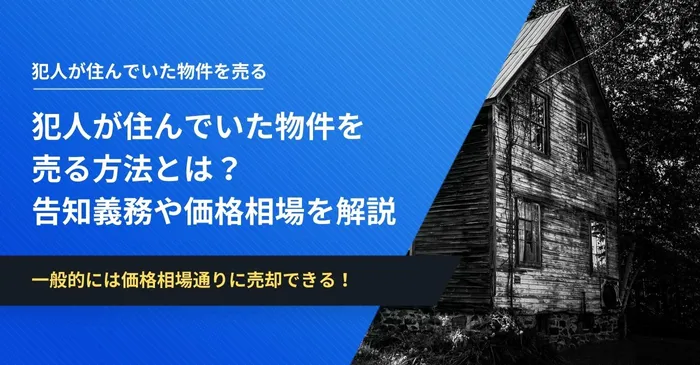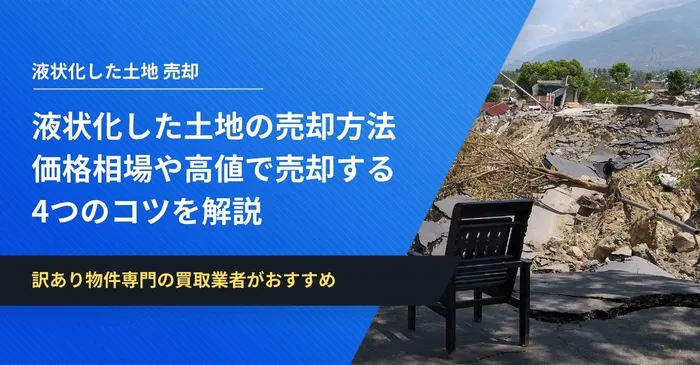土地や敷地の境界線トラブルと対処法
土地や敷地の境界線トラブルは、近隣住民との話し合いで解決できれば良いですが、難しい場合は別途対処が必要となります。
対処はトラブルの内容によって異なり、木の枝などの越境物を撤去して解決できるものもあれば、当人同士では解決できず裁判にまで発展することもあります。
土地や敷地の境界線の主なトラブルと対処法は下記のとおりです。
| トラブルの内容 |
対処法 |
| 木の枝や構造物の越境によるトラブル |
・木の枝などの越境物があるならすぐに撤去する
・越境している物を移動・撤去する
・構造物の越境であれば覚書を作成する
|
| 筆界と所有権界の認識の相違によるトラブル |
・土地家屋調査士に依頼して境界線を測定し直してもらう
・法務局の筆界特定制度を利用する
・ADR機関へあっせんや調停を申立てる
・裁判所へ境界確定訴訟を提起する
|
| 境界標のズレや紛失によるトラブル |
・家屋調査士に依頼して境界標を設置し直す |
| 隣人との不仲によるトラブル |
・筆界特定制度・ADR機関の利用などを検討する |
それぞれのトラブルと対処法について詳しく解説していきます。
木の枝や構造物の越境によるトラブル
隣地に木の枝や構造物が越境している場合、隣人から苦情が入り、トラブルに発展することがあります。具体的に越境とされるのは下記のようなケースです。
- 境界付近に生えた木の枝が、隣地に侵入している
- 屋根や軒、雨どいなどの構造物の一部が、隣地に入っている
- 設置した物置やエアコンの室外機、アンテナの一部が、隣地に入っている
- 経年劣化したブロック塀が傾き、隣地に飛び出している
隣地との境界があいまいである場合、越境によるトラブルが起きやすいです。続いて、越境によるトラブルの対処法をみていきましょう。
対処法|木の枝などの越境物があるならすぐに撤去する
木の生えている場所が自分の敷地内であっても、枝が境界からはみ出ていると越境とみなされます。
その際は、すぐに枝を切るなどして撤去するとよいでしょう。
隣人の敷地に生えている木の枝が自分の敷地内に侵入してきているのなら、伐採を求めることができます。
第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。出典:e-Govポータル「民法第233条1」
自分の敷地内だからと、勝手に伐採してしまうと不法行為となる恐れがあるので必ず所有者に伐採を依頼しましょう。
はみ出しているのが根であれば、所有者に許可を取らずに除去することが認められています。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。出典:e-Govポータル「民法第233条2」
ただし、勝手に除去するとのちにトラブルとなる恐れもあるので、所有者に了承を得てから除去することをおすすめします。
対処法|越境している物を移動・撤去する
物置やエアコンの室外機、アンテナなどが越境している場合は、設置を依頼した業者に相談して、移動もしくは撤去しましょう。
軽微な越境であれば、隣人と話し合いで移動・撤去をしないで済む場合もあります。
しかし、数年後に「越境を許した覚えはない」とトラブルになるおそれもあるため、越境に同意したことを示す書面などを残しておくと安心です。書面作成後は、菓子折りなどのお礼の品を渡しておくと丁寧でしょう。
対処法|構造物の越境であれば覚書を作成する
屋根や軒、雨どい、ブロック塀などの構造物の移動や撤去は、多額の費用が発生するため、すぐに対処できないことも考えられます。
その場合は、越境についての覚書を作成すると良いでしょう。覚書は「将来、建物の建て替えの際に越境状態を解消します」といった内容です。
なお、覚書を作成する際は、隣地との境界を明確にする必要があるため、土地家屋調査士に測量図の作成、越境物調査を依頼する必要があります。土地家屋調査士に越境物調査を依頼すると、覚書の作成も依頼できるケースがほとんどです。
筆界と所有権界の認識の相違によるトラブル
土地の境界線における考え方は「筆界」と「所有権界」の2つです。筆界は、土地が初めて登記された時に定められた境界を指します。一方、所有権界は土地の所有者の権利が及ぶ、私法上の境界を意味します。
「土地の譲渡、不動産の相続」などによって筆界と所有権界が不一致になるとトラブルが起きやすくなります。具体的には、下記のような内容のトラブルが考えられます。
- 古い時代に隣地と所有権界についての取り決めをしたが、土地を相続した親族に取り決めが引き継がれず、境界線で揉める
- 境界線となるブロック塀を設置した側が、ブロック塀の外側までが敷地だと主張して揉める
- 隣地と境界線を移動することを話したが、一方がその取り決めを忘れており揉める
境界線があいまいで、双方の認識にズレが生じている場合は、境界線を明確にする必要があります。具体的な方法について詳しくみていきましょう。
対処法|土地家屋調査士に依頼して境界線を測定し直してもらう
古くからの土地で境界線があいまいである場合などは、土地家屋調査士に依頼して境界線を測定し直してもらうとよいでしょう。
土地家屋調査士は、土地の境界を明らかにする業務の専門家です。
土地家屋調査士は、土地の境界を明らかにするだけでなく以下のような依頼もこなしてくれます。
- 登記
- 境界標の復元・設置
- 境界確認書の作成
- 境界トラブルの相談
土地の境界線を確定したら、のちのトラブルを防ぐためにも登記が必要ですが、土地家屋調査士は登記手続きまでおこなってくれます。
土地の境界線を確定する詳しい手順は、以下の記事で解説していますので参考にしてください。
土地家屋調査士への依頼費用をどうするかあらかじめ話し合う
土地家屋調査士へは、平均で7~10万円程度の費用がかかります。
土地の広さや依頼内容によっては、それ以上かかる可能性もあります。
費用をどのように負担するのか、あらかじめ決めておきましょう。
測量を依頼する土地の住民同士で折半とするのが一般的ですが、どちらかの売却にともなう測量の場合など、片方が負担することもあります。
また、双方の立会いが必要な場合もありますので、日程に関してもあらかじめ話し合っておくとよいでしょう。
対処法|法務局の筆界特定制度を利用する
筆界特定制度とは、土地所有者の申請に基づき、筆界特定登記官が筆界調査委員の意見を踏まえて土地の境界線を特定する制度です。
筆界特定制度を利用するメリットは、主に以下の3つです。
- 裁判に比べて費用が安い
- 裁判よりも短期間で境界が確定できる
- 専門家の意見による判断のため信用性が高い
筆界特定制度を利用するには、特定したい筆界がある土地の固定資産税評価額を合計した金額を基準として算出した申請手数料が必要です。
対象土地の合計額の
1/2に5%を乗じた額 |
手数料 |
| 100万円までの部分 |
10万円までごとに
800円 |
100万円を超え
500万円までの部分 |
20万円までごとに
800円 |
500万円を超え
1,000万円までの部分 |
50万円までごとに
1,600円 |
1,000万円を超え
10億円までの部分 |
100万円までごとに
2,400円 |
10億円を超え
50億円までの部分 |
500万円までごとに
8,000円 |
| 50億円を超える部分 |
1,000万円までごとに
8,000円 |
参照:法務局「筆界特定制度に関する“よくある質問”」
測量が必要な場合は、別途で測量費がかかります。
筆界特定制度とは、元々ある境界線を明らかにする制度であり、新たに境界線を決められるものではありません。
筆界特定制度の申請書式は、以下の法務局のページよりダウンロードができます。
参照:法務局「筆界特定制度」
対処法|ADR機関へあっせんや調停を申立てる
ADRとは、訴訟手続きによらない紛争解決方法のことで「あっせん」「調停」「仲裁」の主に3つの方法があります。
あっせんと調停は、あっせん人や調停人が間に入って話し合いを進めます。あくまでも当人同士での話し合いにおける解決を目指す制度で、話し合いを拒否することも可能です。
仲裁は、当事者同士が仲裁を受けることに同意している場合に限り、仲裁人が解決内容を判断するものです。
この際の判断は「仲裁判断」といわれ、裁判の判決と同じ効力があります。当事者は判断結果を拒否することができず、控訴や上告といった制度もありません。
また、仲裁判断がくだされると、同じ案件で裁判を起こすことができなくなります。
そのため、穏便に解決するにはなるべく、あっせんや調停の段階での解決を目指すとよいでしょう。
土地の境界線におけるトラブルは、境界問題相談センターが管轄しています。
ADR認定土地家屋調査士がサポートし、専門的な立場から問題解決に向けた助言をしてくれます。
以下のページから、最寄りの境界問題相談センターを検索できるので参考にしてください。
参照:日本土地家屋調査士会連合会「ADR境界問題相談センター」
対処法|裁判所へ境界確定訴訟を提起する
話し合いでの解決が難しい場合は、裁判所へ「境界確定訴訟」を提起できます。
境界確定訴訟は、通常の訴訟とは違い「勝訴」「敗訴」といった勝ち負けを決める訴訟ではありません。
境界確定訴訟を提起すると、裁判所が独自に境界を判断します。そして、境界確定訴訟で確定された境界については、異議を唱えることはできません。
境界標や筆界確認書といった客観的証拠が1つもない場合でも棄却はされず、裁判所の判断で新たな筆界が確定されます。
境界確定訴訟の判決が出るまでは約2年かかります。また、費用に関しても数十万円がかかることが通常です。
裁判にまで発展すると、隣人との関係修復も難しいケースが多いため、なるべく話し合いでの解決を目指した方がよいでしょう。
また、所有権や時効取得について明らかにしたい場合は、所有権確定訴訟を提起する必要があります。
境界確定訴訟や所有権確定訴訟を提起するのであれば、不動産問題に詳しい弁護士へ依頼するのがおすすめです。
境界標のズレや紛失によるトラブル
境界標とは、土地の境界点を示す目印や標識を指します。御影石やコンクリート、プラスッチックなどの材質の杭、金属プレート、金属鋲に十字や矢印が書かれており、境界点を明らかにします。
建物の建て替えやブロック塀の積み替え、下水道工事、外構工事などを行う際は、この境界標を移動させることがあります。本来は移動前に境界標の位置を記録し、工事後に復元させるものですが、境界標の位置がズレてしまったり、古い時代で紛失してしまったりといったトラブルもあります。
境界標は設置義務のあるものではありませんが、ズレや紛失によって境界線があいまいになり、トラブルの火種となることがあります。
対処法|家屋調査士に依頼して境界標を設置し直す
境界標が紛失したり、ズレてしまったりした場合は、家屋調査士に依頼して設置し直しましょう。専門家でない者が勝手に境界標を設置し直すと、大きなトラブルに発展するおそれがあります。
そのため、家屋調査士の測量のもと、隣人に境界点を確認してもらい、境界標の設置をすることが重要です。
隣人との不仲によるトラブル
土地の売却や活用を検討している場合、境界線を明確にするために家屋調査士に依頼することがあります。しかし、隣人と不仲である場合は、筆界確認に協力してもらえない可能性があります。
筆界確認とは文字通り、土地の所有者同士が境界線を確認することです。筆界確認が行えないと境界を確定できず、土地の売却や建物の建築などに支障をきたします。
対処法|筆界特定制度・ADR機関の利用などを検討する
筆界確認に協力してもらえず、境界線の確定が難しい場合は、先述した筆界特定制度やADR機関の利用、訴訟などを行うこととなります。隣人との話し合いで解決できるのが一番ですが、どうしても難しい場合は検討してみてください。
なお、隣地越境の不動産売却については下記の記事を参考にしてみてください。
土地や敷地の境界線におけるトラブルを防ぐためにするべきこと
土地の境界線に関するトラブルは、近隣住民との間に発生するケースがほとんどです。
前の項目でお伝えしたように、話し合いで解決できず裁判までもつれるケースも少なくありません。
しかし、できれば近隣住民とのトラブルは避けたいですよね。
そこでこの項目では、土地の境界線におけるトラブルを防ぐためにするべきことをお伝えします。
筆界確認書を作成してお互いに署名押印する
土地家屋調査士に測量を依頼すると、筆界確認書を作成してくれます。
分筆登記や地積更正登記を提出する際には、署名押印された筆界確認書も一緒に提出しなければなりません。署名押印された筆界確認書がないと、土地の売買に支障をきたす恐れがあります。
また、筆界確認書への署名押印は、お互いが筆界確認書に記載された内容に同意していることの証拠となります。
そのため、将来的なトラブルを防ぐためにも隣人の土地との境界線があいまいであるなら、早めに境界線の確定を土地家屋調査士へ依頼するとよいでしょう。
永続性のある境界標を立てる
土地の境界線を確定させる手段として、境界標を立てるのは有効な手段です。
しかし、木製の境界標だと朽ちたり動いてしまう恐れがあります。
そのため、境界石やコンクリート標などの永続性がある境界標を埋設するのがよいでしょう。
地中に境界標を埋設できない場合は、金属鋲をブロック塀やコンクリートに直接打ち込むこともできます。
隣人とトラブルとなる前に境界標を設置しておけば、土地の境界線をめぐって隣人と争うことを避けられます。
境界標の設置も、最終的には登記に結びつくので土地家屋調査士に依頼するとよいでしょう。
日頃から近隣住民とコミュニケーションをとる
そもそも土地の境界線におけるトラブルは、近隣住民とのコミュニケーション不足が原因であることが多いです。
- 木がはみ出ているのが前から気になっていた
- 面識のあまりない住民から、急に境界線確定の立会いを要求されて困惑している
- 土地を売却したいから測量したいのに、隣人が協力してくれない
このようなトラブルは、日ごろから近隣住民と良好な関係を築いていれば起きにくいといえます。
誰でも、あまり面識のない住民からいきなり境界線について指摘されたり、木がはみ出ているのに知らん顔をされていたら、気持ちがよくないですよね。
土地の境界線は、近隣住民との面識がなくても訴訟で解決できます。
しかし、訴訟にはお金も時間もたくさんかかってしまいます。
そのため、のちのトラブルを防ぐためにも、日頃から近隣住民とコミュニケーションをとるとよいでしょう。
土地や敷地の境界線についてのトラブル事例と解決方法
ここまで、土地の境界線におけるトラブルの対処法や防止策についてお伝えしました。
それでは、実際にどのようなトラブル事例があるのでしょうか。
この項目では、土地の境界線におけるトラブルの事例と、そのトラブルをどのように解決したのかを解説します。
隣の土地を売り出し中の不動産業者から屋根の境界越境を指摘された事例
Aさんが住む家の隣は長い間空き地となっていましたが、あるとき不動産業者が売り出すために測量を始めました。
Aさんも測量に立ち会ったところ、Aさん宅の屋根が越境していることが判明。
20年以上前に建てた家であるため、Aさんは取得時効を主張しましたが、不動産業者は認めません。
訴訟までは持ち込みたくなかったAさんは、不動産問題に詳しい弁護士に相談することにしました。
越境している分の土地を不動産業者から買取って解決
弁護士に相談したところ、越境している部分の土地はわずかであるため裁判で争うよりも買取った方が安く、また早く解決できると助言されました。
Aさんが不動産業者へ買取りを持ちかけたところ、交渉は成立。
相場よりも若干低い値段で取引することで、双方納得のいく結果となりました。
土地の売却をしたいのに隣人が境界の確定に協力してくれない事例
Bさんは海外へ長期転勤となったため、親から相続した自宅を土地ごと売却することにしました。
しかし、古い自宅だったため境界確認書などは見つからず、改めて測量を依頼することに。
土地家屋調査士に測量を依頼したところ、隣人が建てたブロック塀の位置がBさんの境界内に侵入しているとのことでした。
そのため、隣人に新たな境界線の確定とブロック塀の撤去を求めたところ、拒否されてしまいました。
取り付く島もない隣人に困ったBさんは、インターネットで見つけた「訳あり物件も買取可能」な不動産業者へ相談することにしました。
訳あり物件専門の業者へ売却して解決
Bさんが相談をしたのは、弁護士と提携している訳あり物件専門の買取業者でした。
状況を説明すると、隣人が取得時効の条件を満たしている可能性が高いとのことでした。
Bさんは転勤まで時間もなかったので、Bさんのブロック塀部分に関して取得時効を認めることに同意。
取得時効の援用手続きも含めて、訳あり物件専門の業者へ委託し解決しました。
境界線のトラブルが起きている土地でも、積極的に買取しています!
最短48時間のスピード買取で
不動産を現金化
「高く・早く・トラブルなく」
売却したいなら
訳あり物件買取専門の
当社にお任せください!
まとめ
土地や敷地の境界線トラブルは、越境物の撤去などで済む内容であれば良いですが、当人同士で解決できないようなトラブルに発展する場合もあります。
まずは隣人との話し合いを試みて、難しい場合はトラブルの内容に合わせて、家屋調査士への依頼や筆界特定制度の利用などで対処していきましょう。
また、土地の境界線においてトラブルが発生している不動産を売却したい場合は、訳あり物件専門の買取業者へ依頼するのがおすすめです。
当社クランピーリアルエステートでは、境界線トラブルが発生しているといった訳あり物件でも積極的に買取をしています。
無料での査定や相談もおこなっていますので、お気軽にお問い合わせください。
訳あり不動産の売却でお悩みなら
今すぐご連絡ください
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-