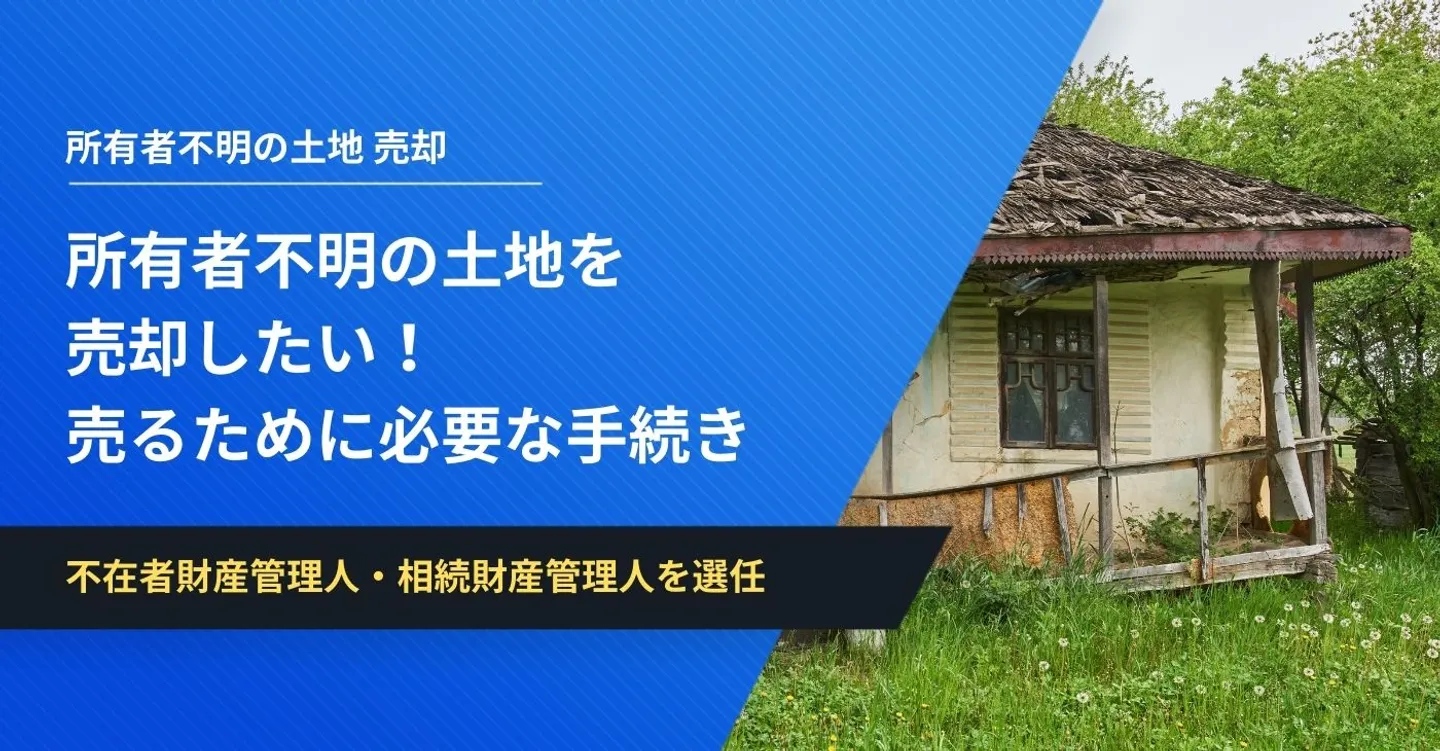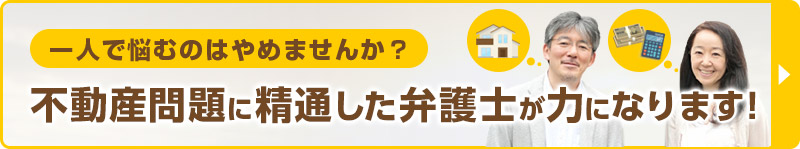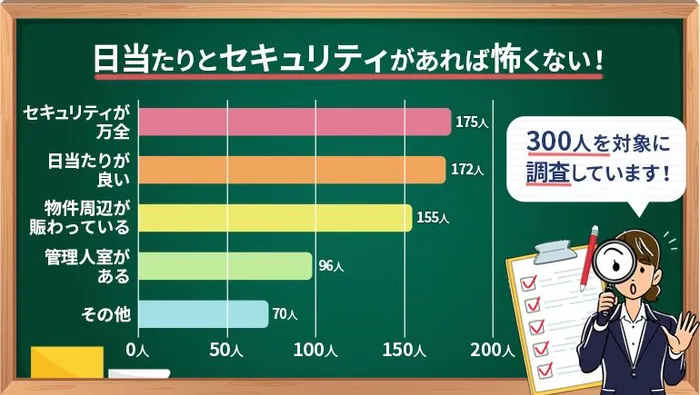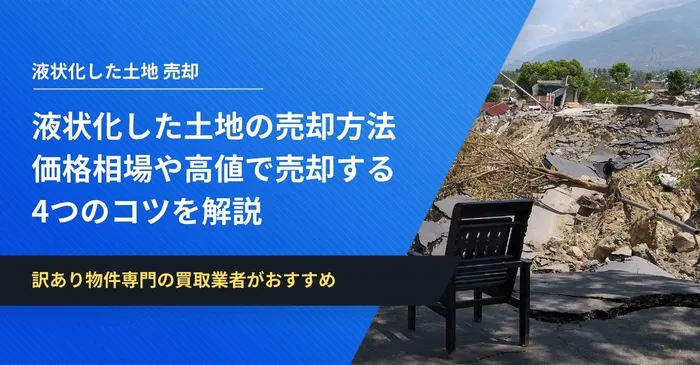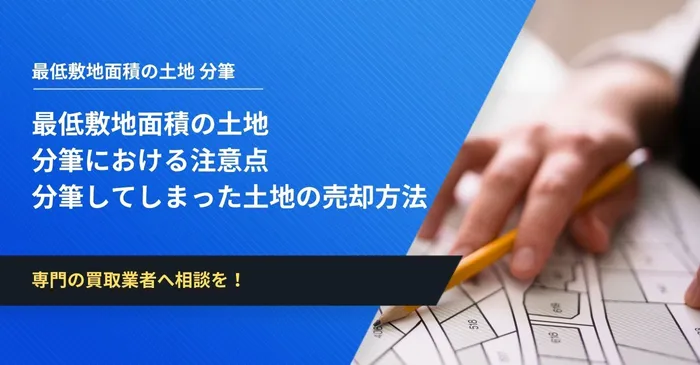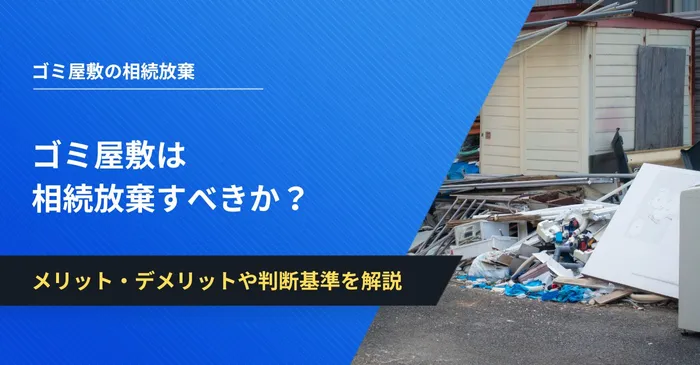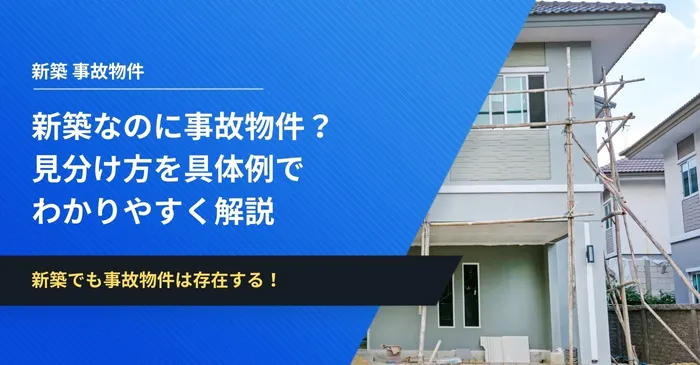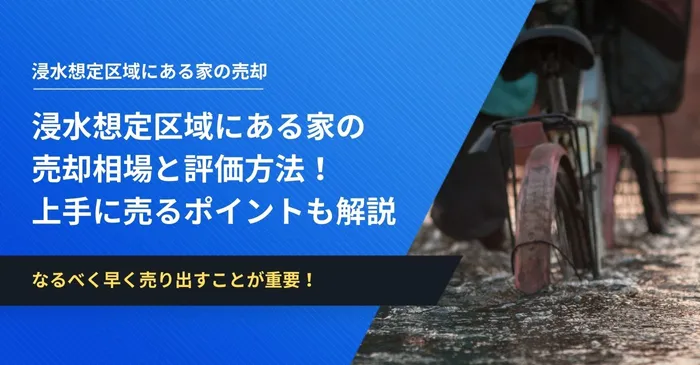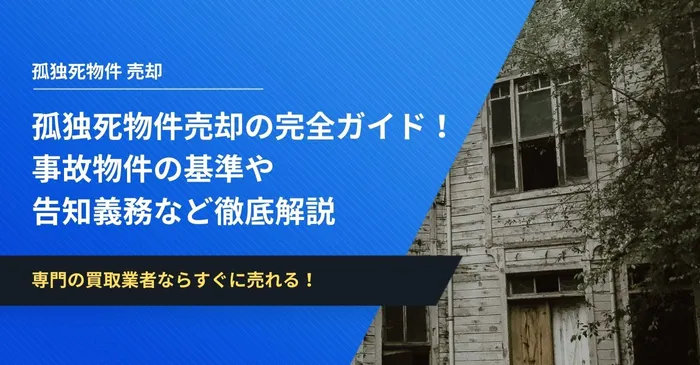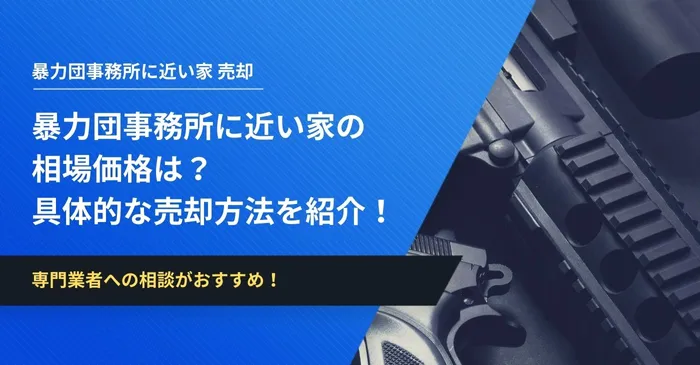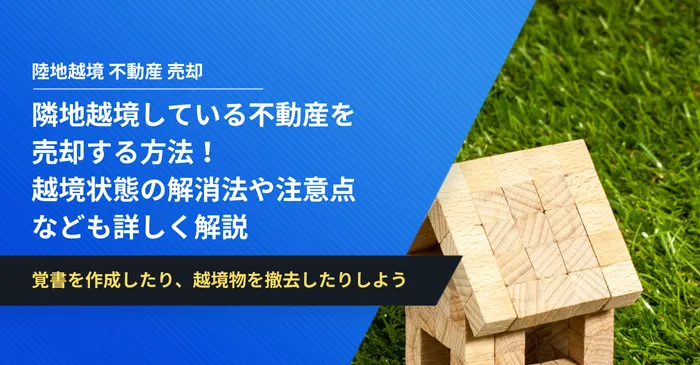所有者不明の土地はなぜ生まれるのか?
まずは「所有者不明の土地とは、どのような土地か?」という法律上の定義を確認しましょう。
国土交通省によると、所有者不明の土地とは次のような土地のことです。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第2条
この法律において「所有者不明土地」とは、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地をいう。
引用:e-Govポータル「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第2条」
わかりやすくいうと、登記簿において表題部の所有者の氏名・住所が正常に登記されていない「変則型登記の土地」が所有者不明の土地となります。
原則として土地を取得する際、所有者の権利を証明するために法務局の登記簿へ、以下の2つの登記記録を登記をします。
- 表題部(土地や建物の状況が記載した情報)
- 権利部(土地や建物の権利関係を記載した情報)
しかし、この表題部に所有者の情報が登記されていない土地は「変則型登記の土地」いわゆる「所有者不明の土地」となります。
所有者不明の土地が生まれる原因
所有者不明の土地が生まれる原因として、次のケースが挙げられます。
- 土地の相続人を確認できない
- 土地の相続人が登記していない
それぞれのケースと具体例を順番に見ていきましょう。
1.土地の相続人を確認できない
1つ目は、土地の相続人を確認できないため、所有者不明の土地になるケースです。
- 子供や親族などの相続人がいない場合
- 相続人はいても消息がつかめない場合など
近年では少子高齢化が進んだことで相続人がわからなくなるケースが増えており、所有者不明の土地が増加しています。
また土地の所有権が相続されていても、次のように相続した所有者の所在が把握できずに所有者不明の土地となるケースも多いです。
- 所有者の転居先がわからないため連絡が取れない
- 登記簿の所有者に「山田太郎 外10名」としか記載されていない
2.土地の相続人が登記していない
2つ目は、土地の相続人が登記していないせいで、所有者不明の土地となるケースです。
次のような場合、土地の相続登記がおこなわれずに所有者がわからなくなってしまいます。
- 相続人が決まらず、不動産登記をせずに放置された
- 相続人は決まったが、土地の名義変更を忘れていた
さらに登記されていない状態が長期化するほど、相続人の数が増えてしまい、余計に土地の所有者を把握しづらくなります。
相続登記が放置される所有者不明の土地の傾向として、次のような価値の低い土地「死に地」であることが多いです。
- そのまま土地を放置しておけば、固定資産税を払わずに済むから
- 相続登記する手間をかけるほど、土地を取得する利点がないから
所有者不明の土地による機会損失を行政も問題視している
所有者不明の土地によるデメリットを問題視した政府によって「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が2019年6月1日に全面施行されました。
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」を要約すると、次のような内容となります。
- 所有者不明の土地を公共事業へ利用するための審理手続きを省略できる。
- 所有者不明の土地を地域福利増進事業に利用する権利を設定できる。
- 所有者不明の土地の所有者の探索するために、公的情報を行政機関が利用できる。
- 所有者不明の土地について、特定登記未了土地である旨を登記官が登記できる。
- 所有者不明の土地について、地方公共団体が相続財産管理人の選任を請求できる。
行政機関側で土地の所有者を探したり、土地を管理できる代理人を選任できるなど、所有者不明の土地を処分しやすくなったため、その減少が期待されています。
最短48時間のスピード買取で
不動産を現金化
「高く・早く・トラブルなく」
売却したいなら
訳あり物件買取専門の
当社にお任せください!
所有者不明の土地でも一定条件を満たせば売却可能
所有者不明の土地でも一定条件を満たせば売却できます。
行政も所有者不明の土地を自由に扱えないことによる機会損失を問題視しており、近年では所有者不明の土地を管理・売却できるように法整備が進んでいます。
以下の要件を満たして「所有者不明の土地」であると法的に認められることで、本来の所有者以外の第三者でも売却できるようになります。
登記簿や戸籍謄本などで所有者や相続人を探しても見つからなければ売却できる
国土交通省では「政令で定める方法により探索しても所有者が見つからない土地」を「所有者不明の土地」としています。
具体的には、以下の方法で所有者を探しても見つからない場合「所有者不明の土地」として法的に認められます。
- 登記簿に記載されている所有者を参照する
- 登記された所有者および相続人の安否を戸籍謄本で確認する
現時点で登記簿上の所有者が死亡しており、相続人も見つからない場合は「所有者不明の土地」となります。
また登記人や相続人が存命でも、引越しなどにより現住所が特定できない場合は「所有者不明の土地」と見なされるケースがあります。
上記のように登記簿や戸籍謄本で所有者が見つからない場合、然るべき手続きを踏めば「所有者不明の土地」を売却できるのです。
最短48時間のスピード買取で
不動産を現金化
「高く・早く・トラブルなく」
売却したいなら
訳あり物件買取専門の
当社にお任せください!
所有者不明の土地を売却する方法
所有者不明の土地を売却する方法は、大きく分けて2種類あります。
- 所有者不明の土地を管理できる人物を探す
- 所有者不明の土地を取得時効して売却する
ただし土地の取得時効には10〜20年もかかるため、土地を管理できる人物を探したり、新しい管理人を選任して売却するパターンが一般的です。
それぞれの売却方法について、順番に見ていきましょう。
所有者不明の土地を管理できる人物を探す
まずは所有者不明の土地を管理できる人物を探して、売却に協力してもらう方法です。
具体的には、次の3ステップで進行します。
- 登記簿で土地の所有者を確認する
- 土地の所有者の相続人を探す
- 不在者財産管理人もしくは相続財産管理人を選任する
まずは所有者不明の土地を管理できる人物を探して、見つからない場合のみ新しく土地の管理人を選任して売却する形になります。
それぞれのステップについて、1つずつ解説していきます。
1.登記簿で土地の所有者を確認する
まずは所有者不明の土地を管轄する法務局へ行き、登記簿を閲覧しましょう。
登記簿を閲覧する際には、以下の点を確認しましょう。
- 所有者不明の土地の所有者の住所
- 所有者不明の土地の所有者の氏名
- 所有者不明の土地の抵当権
これらの情報を確認することで、過去の所有者の登記理由や登記時期、土地所有権の共有者などがわかります。
登記簿を確認しても所有者がわからない場合、その土地は「所有者不明の土地」とみなされます。
もし土地の所有者が存在している場合、その土地は「所有者不明の土地」ではないため、売却するには所有者の協力が必要になります。
2.戸籍謄本から土地の所有者の相続人を探す
つづいて所有者不明の土地の所有していた人物の本籍のある市区町村役場へ行き、戸籍謄本を閲覧しましょう。
戸籍謄本を閲覧することで、法律において被相続人から土地の相続が認められている「法定相続人」が確認できます。
すでに土地の所有者が死亡しており、相続人も見つからない場合、この時点で「所有者不明の土地」と見なされます。
また所有者や相続人が存命であっても、現住所が特定できない場合や安否が7年間わからない場合は「所有者不明の土地」と認められるケースがあります。
もし土地の相続人が存在する場合、その土地は「所有者不明の土地」ではないので、相続人の協力がないと売却できません。
3.不在者財産管理人もしくは相続財産管理人を選任する
土地の所有者と相続人を探して「所有者不明の土地」であることを確認したら、不在者財産管理人または相続財産管理人を選任しましょう。
ただし不在者財産管理人または相続財産管理人の選任には、裁判所への申立てが必要です。
「どちらの財産管理人を選任するか?」の違いは、以下のとおりです。
| 種類 |
選任するケース |
| 不在者財産管理人 |
登記簿における所有者の1人が不明の場合 |
| 相続財産管理人 |
亡くなった被相続人に相続人がいるか不明な場合もしくは相続放棄によって相続人がいない場合 |
それぞれの財産管理人の違いと、選任方法を1つずつ見ていきましょう。
不在者財産管理人を選任する方法
登記簿を確認した結果、所有者不明の土地の所有者が1人ではない場合「不在者財産管理人」を選任して、残りの共有者と協力して売却しましょう。
土地の所有者が1人ではない場合、その土地は個人の所有物ではなく共有者の共有物と扱われるため、共有者全員の同意がないと売却できません。
そこで行方不明の共有者に代わる「不在者財産管理人」を選任して、その人物の同意を含めて共有者全員が合意することで土地を売却できるようになります。
不在者財産管理人を選任する方法は、次の5ステップです。
- 不在者財産管理人の選任申立書を作成する
- 家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申し立てる
- 家庭裁判所に不在者財産管理人選任を審理する
- 家庭裁判所から不在者財産管理人選任の審判が下りる
- 申立人の元に審判書が送付されて選任が公告される
ただし「不在者財産管理人」を選任したとしても、共有者全員の同意が得られないと土地を売却できないので、確実な方法とはいえません。
相続財産管理人を選任する方法
登記簿と戸籍謄本を確認した結果、所有者不明の土地の所有者および相続人が見つからない場合「相続者財産管理人」を選任して、その人物に売却してもらいましょう。
相続財産は基本的に相続人が管理しますが、相続人がいないと財産や負債がそのまま放置されてしまうため、相続者財産管理人が管理することになります。
相続財産管理人を選任する方法は次のとおりです。
- 相続財産管理人の選任申立書を作成する
- 家庭裁判所に相続財産管理人選任を申し立てる
- 家庭裁判所に相続財産管理人選任を審理する
- 家庭裁判所から相続財産管理人選任の審判が下りる
- 申立人の元に審判書が送付されて選任が公告される
ただし「相続財産管理人」を選任しても、与えられている権限が限られるため、土地を売却する場合は家庭裁判所の許可が必要になります。
民法第28条
管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
引用:e-Govポータル「民法第28条」
民法第103条
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
引用:e-Govポータル「民法第103条」
所有者不明の土地を時効取得して売却する
土地の所有権には時効が認められており、所有者不明の土地を10〜20年以上も占有していた場合、自分の土地とすることができます。
つまり所有者不明の土地を10〜20年以上も占有していた場合、時効援用の手続きをして自分の土地とすることで自由に売却できます。
しかし、このように所有者不明の土地を占有しているケースは少なく、これから時効取得するにも10年以上かかるため、あまり現実的な方法とはいえません。
次の項目では、土地の取得時効が認められる条件を確認していきましょう。
10〜20年間占有すれば土地の所有権を時効取得できる
民法では、他人の所有物でも10年または20年以上占有していた場合、占有者が所有権を取得できるように認める「取得時効」という制度を認めています。
民法第162条
1. 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2. 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
引用:e-Govポータル「民法第162条」
取得時効が認められるまでの期間は「所有者不明の土地が他人の所有物であると知っていたか?」によって異なります。
| 時効成立までの期間 |
条件 |
| 10年 |
自分の土地であると勘違いしていた場合 |
| 20年 |
他人の土地であることを知っていた場合 |
ただし取得時効にはさまざまな条件があり、すでに時効が成立していても土地を取得するには時効援用という手続きが必要となります。
そのため、所有者不明の土地を時効取得したい場合、いちど弁護士に相談してから時効援用の手続きをしてもらうことをおすすめします。
まとめ
この記事では、所有者不明の土地を売却する方法を解説しました。
たとえ所有者不明の土地であっても、所有者および相続人以外の第三者が勝手に売却することはできません。
登記簿・住民票・戸籍謄本などを確認した結果、土地の所有者および相続人が存在しなければ、その土地は「所有者不明の土地」として法的に認められます。
法的に認められた「所有者不明の土地」であれば、不在者財産管理人または相続財産管理人を選任することで、新たな管理人の下で売却することが可能です。
また所有者不明の土地を10年または20年以上占有していた場合、所有権を取得して売却することもできますが、時効援用などの手続きが必要になります。
所有者不明の土地を売却したい場合、自分1人では売却がむずかしいので、不動産業者や弁護士に協力してもらうのがベストでしょう。
最短48時間のスピード買取で
不動産を現金化
「高く・早く・トラブルなく」
売却したいなら
訳あり物件買取専門の
当社にお任せください!
所有者不明の土地についてよくある質問
所有者不明の土地でも売却できますか?
所有者以外が勝手に売却することはできません。ただし、所有者や相続人が見つからない場合、不在者財産管理人や相続財産管理人を選任することで売却できるケースもあります。
不在者財産管理人はどのように選任しますか?
登記簿や戸籍謄本を調査して「所有者不明の土地」であることを確認した後、家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申し立て、家庭裁判所から不在者財産管理人選任の審判が下りれば選任されます。
相続財産管理人はどのように選任しますか?
登記簿と戸籍謄本を調査して「所有者および相続人が不明」であることを確認した後、家庭裁判所に相続財産管理人選任を申し立て、家庭裁判所から相続財産管理人選任の審判が下りれば選任されます。
不在者財産管理人や相続財産管理人になる人は、任意に選べますか?
裁判所の判断によって選任されるので、任意では選べません。原則として、第三者の弁護士など資産に関する利害関係のない人が選ばれます。
長期間、土地を占有していれば所有権を得られると聞きましたが、どんな条件がありますか?
確かに、土地の占有期間が長く続けば時効による所有権の取得が可能です。土地を占有している期間が、自分の土地であると勘違いしていた場合は10年、他人の土地であることを知っていた場合は20年続くと、時効取得が認められます。
訳あり不動産の売却でお悩みなら
今すぐご連絡ください
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-