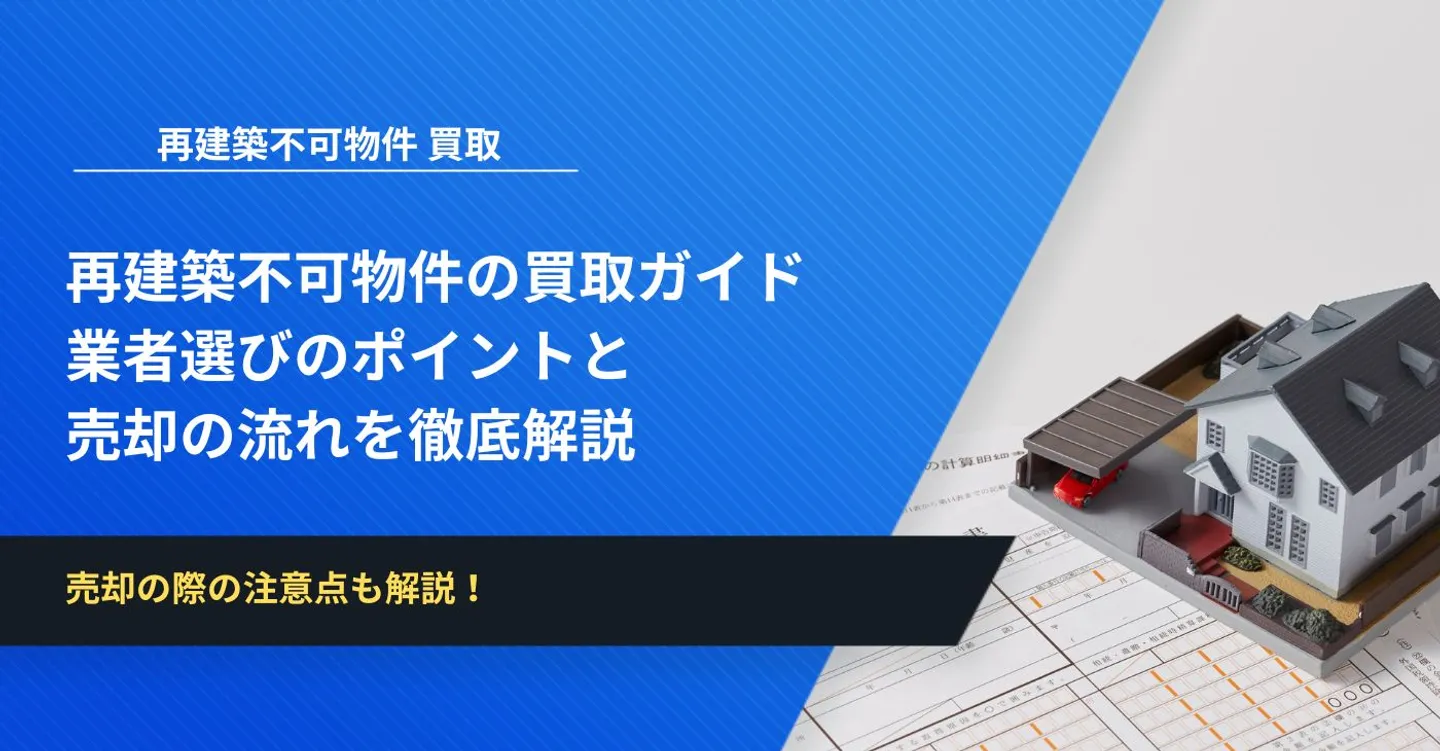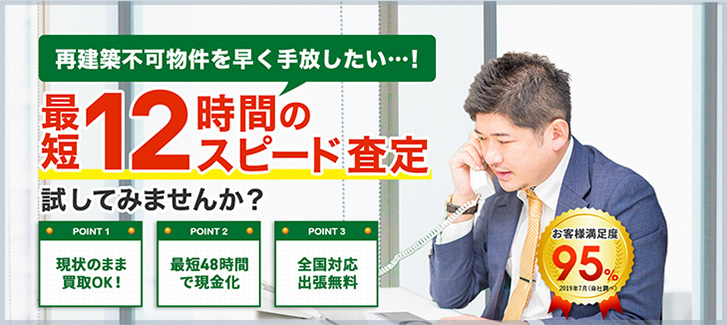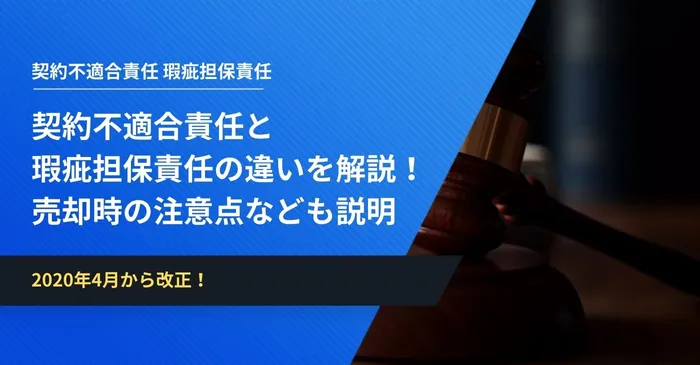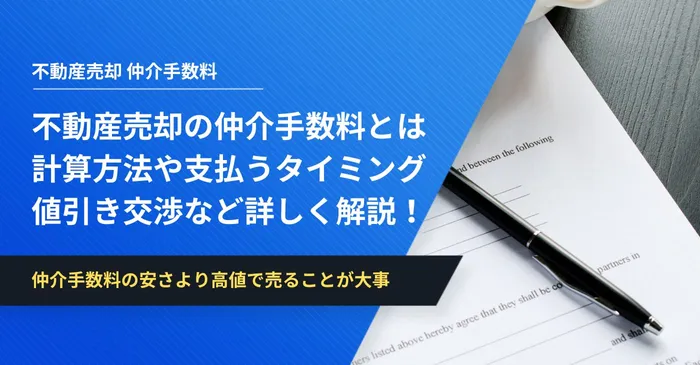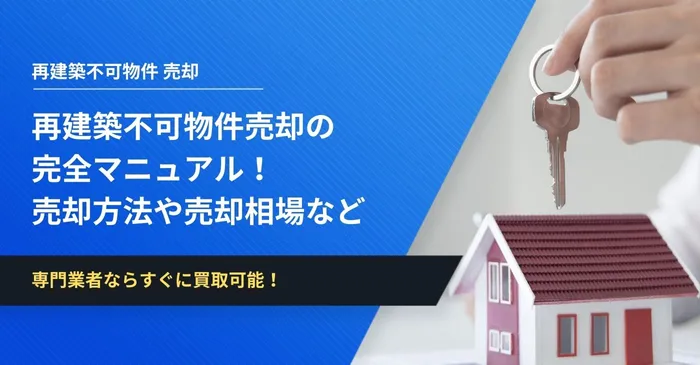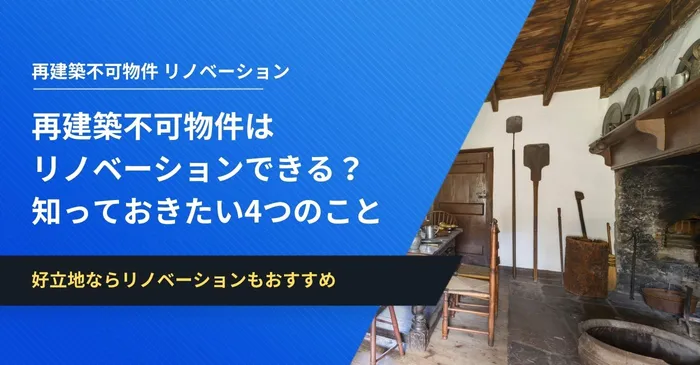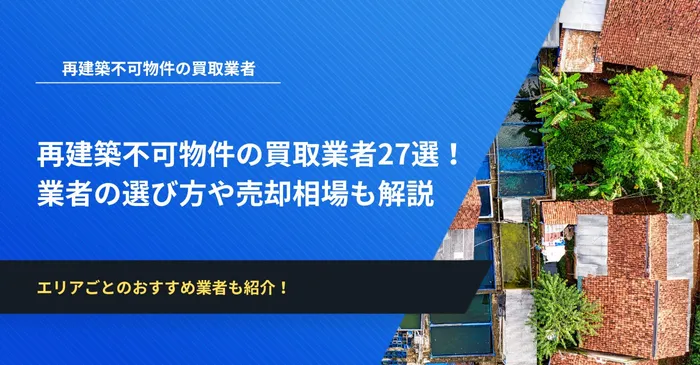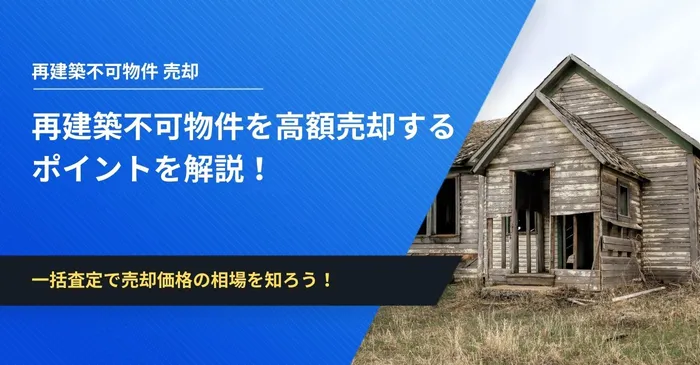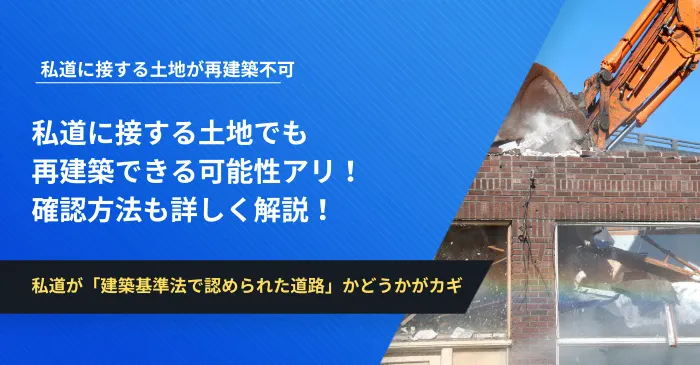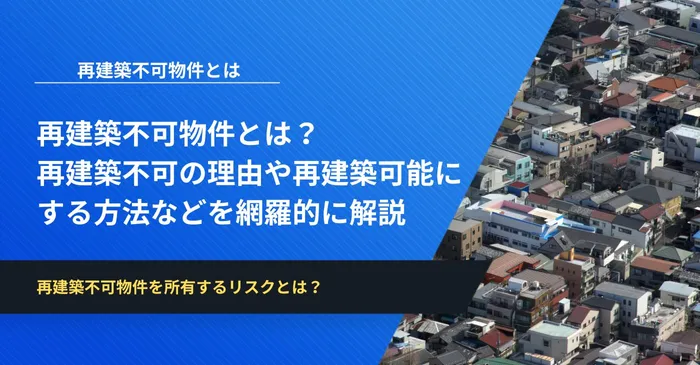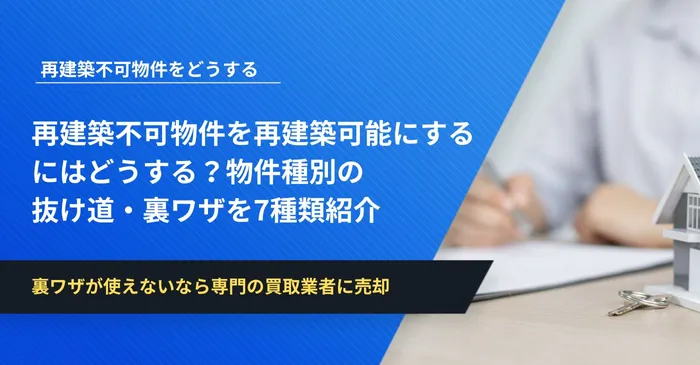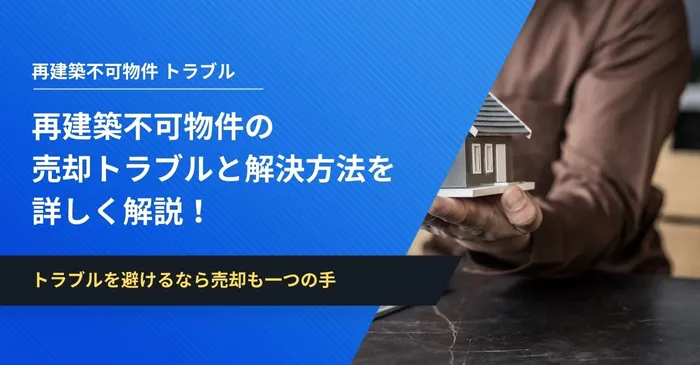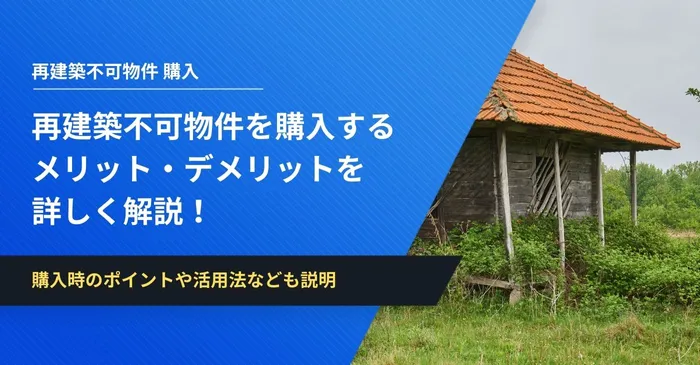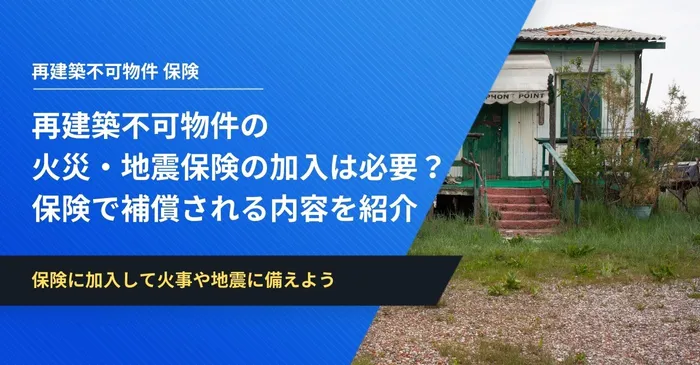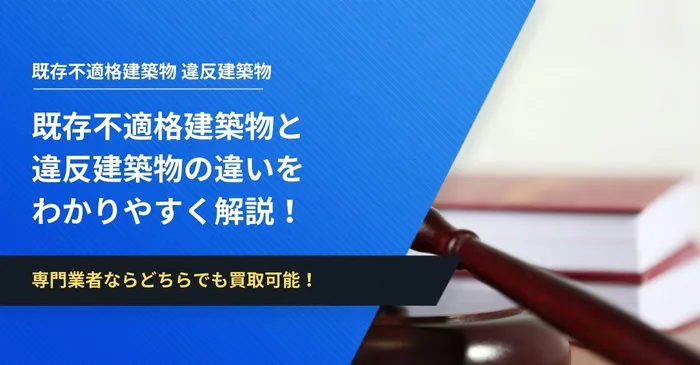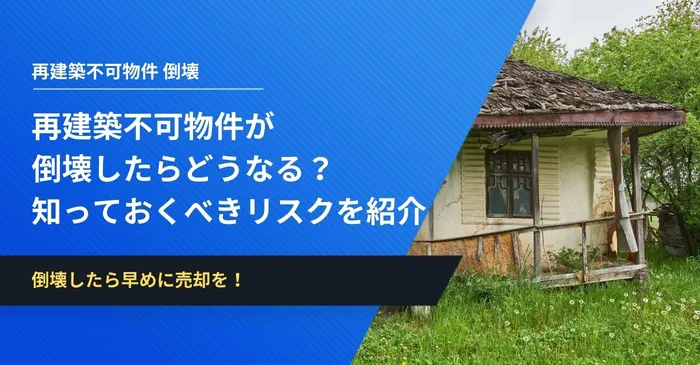再建築不可物件の売却を検討しているものの「どのように進めればよいのかわからない」「買取業者に依頼しても適正な価格で売却できるのか不安」と感じる方は少なくありません。
再建築不可物件とは、建築基準法に定められた「接道要件(敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないという規定)」を満たしていないことを主な理由として、原則として建て替えができず、大規模なリフォームにも制限がかかる特殊な不動産を指します。
さらに、都市計画法による区域区分や用途地域の制限などが重なり、結果として再建築が認められないケースもあります。このような制約があるため、住宅ローンの利用が難しく購入希望者も限られることから、仲介による売却では買い手が見つかるまでに長期間を要する、あるいは売却自体が困難となる場合も少なくありません。
こうした事情から、再建築不可物件の売却では専門の買取業者に直接売却する方法が有力な選択肢となります。
再建築不可物件を買取で売却するメリットには下記のようなものがあります。
再建築不可物件を買取で売却するメリット
| メリット |
具体的な説明 |
| 現況のまま売却可能 |
リフォームや解体を行わずにそのまま引き取ってもらえるため、工事車両の進入が難しい物件や老朽化が著しい物件でも売却しやすい。 |
| 早期の資金化 |
契約から現金化までが短期間で進み、最短で数日から数週間程度で資金化できる。 |
| 契約不適合責任の免除 |
築古物件に多い設備不良や構造上の問題について、免除特約が付されるケースが多く、売却後の修補・損害賠償リスクを回避できる。 |
| 仲介手数料が不要 |
仲介を介さずに売却できるため、売却額から仲介手数料を差し引かれる心配がない。 |
| プライバシーの確保 |
一般公開の売却活動を行わないため、売却を近隣や知人に知られにくい。 |
上記のようなメリットがある一方で、買取には注意すべき点もあります。
一般的に買取価格は市場相場の7割前後にとどまることが多く、仲介に比べて手取り額が下がりやすい傾向にあります。これは、買取業者が修繕費用や解体費用、保有期間中の維持費や税金、さらには再販・運用時のリスクを見込んで価格を提示するためです。特に再建築不可物件は活用方法が限られるため、業者が保守的な見積もりをする場合には大幅に価格が下がることもあります。
このように、再建築不可物件の売却では買取による迅速性や確実性という大きなメリットがある一方、価格面でのデメリットも存在します。また、同じ物件であっても業者ごとのノウハウや出口戦略によって提示価格は大きく異なり、隣地の買い増しやリノベーションなど柔軟な活用方法を持つ業者であれば比較的高い価格を提示する可能性がありますが、経験の少ない業者では低い査定額となることが少なくありません。
適正価格での売却を目指すのであれば、複数の業者に査定を依頼して比較検討し、再建築不可物件に関する実績や専門知識を十分に持つ業者を選ぶことが重要です。
本記事では、買取業者の具体的な選び方や査定時のチェックポイント、実際の売却事例まで実務的な観点から解説していきます。再建築不可物件の売却でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
再建築不可物件を買取に出すメリット
再建築不可物件の売却を検討する際、不動産仲介による売却と買取専門業者への売却という2つの選択肢があります。仲介での売却は市場価格に近い金額での売却が期待できる一方、買取は売却価格が市場価格より低くなる傾向がありますが、その分多くのメリットを得られます。
特に、再建築不可物件は一般の購入希望者にとって敬遠されがちな物件であり、仲介での売却には長期間を要したり、売却自体が困難になったりするケースも少なくありません。そのため、確実性とスピードを重視するなら、買取専門業者への売却が有効な選択肢となります。
以下では、買取と仲介の違いを踏まえながら、買取のメリットを詳しく解説します。
リフォームや解体せずに買い取ってもらえる
仲介で再建築不可物件を売却する場合、購入希望者を見つけるために建物の修繕やリフォームが必要になることが多々あります。しかし、再建築不可物件ではさまざまな制約があります。
まず、リフォーム可能な範囲が限定されます。建築確認申請が必要な大規模リフォーム(主要構造部の2分の1以上の修繕や10㎡以上の増築など)は、接道要件を満たしていないため申請が通らず実施できません。小規模なリフォーム(内装の張り替えや設備交換など)は可能ですが、建物全体の価値向上には限界があります。
さらに、小規模なリフォームでも物理的制約があります。接道要件を満たしていないため、工事車両の進入が困難で足場の設置ができないなど、リフォーム工事自体が制約を受けるケースが頻繁にあります。このような物理的な制約により、リフォーム会社から工事を断られたり、通常よりも高額な工事費用を請求されたりする可能性があります。
また、老朽化が著しい場合は建物を解体することも検討されますが、解体しても再建築ができないため、更地にしても土地のみの価値となり、かえって資産価値が下がってしまう可能性があります。費用をかけてリフォームや解体を行っても、再建築不可という根本的な制約により購入希望者が現れない可能性も否定できません。
一方、買取専門業者は再建築不可物件の取り扱いに精通しており、物件の現状をそのまま評価して買取を行うため、売主側でのリフォームや解体工事は一切不要です。これにより、工事費用の負担やリスクを回避しながら、迅速な売却が実現できます。
早期現金化が可能(最短数日〜数週間)
仲介による売却では、売主は買主に対して契約不適合責任を負うのが一般的です。契約不適合責任とは、引き渡した物件に契約内容との不適合(欠陥や不具合など)があった場合、売主が買主に対して修補や代金減額、損害賠償などの責任を負う制度です。
再建築不可物件は築年数が古い物件が多くなっています。これは、昭和25年(1950年)の建築基準法制定により、建物の敷地は幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接する必要があるという接道義務が定められたためです。この法改正以前に建築された物件や、当時の基準では適法だった物件が、現在の基準では再建築不可となっているケースが多く、築70年以上の古い物件が大半を占めています。
そのため、給排水設備の不具合や建物構造の問題など、予期しない不適合が発見される可能性があります。仲介での売却では、物件引渡し後に買主が不適合を知った時から1年以内であれば、売主に対して各種請求が可能となっています。
しかし、買取専門業者への売却では、多くの場合で契約不適合責任が免責となる特約が設けられます。これは、買取業者が物件の状況を専門的に評価したうえで買取価格を決定しており、将来的なリスクも織り込み済みであるためです。この免責により、売却後の予期しない出費や法的トラブルのリスクが大幅に軽減されます。
契約不適合責任を免れるケースが多い
仲介による売却では、売主は買主に対して契約不適合責任を負うのが一般的です。契約不適合責任とは、引き渡した物件に契約内容との不適合(欠陥や不具合など)があった場合、売主が買主に対して修補や代金減額、損害賠償などの責任を負う制度です。
再建築不可物件は築年数が古い物件が多く、給排水設備の不具合や建物構造の問題など、予期しない不適合が発見される可能性があります。仲介での売却では、物件引渡し後に買主が不適合を知った時から1年以内であれば、売主に対して各種請求が可能となっています。
しかし、買取専門業者への売却では、多くの場合で契約不適合責任が免責となる特約が設けられます。これは、買取業者が物件の状況を専門的に評価したうえで買取価格を決定しており、将来的なリスクも織り込み済みであるためです。この免責により、売却後の予期しない出費や法的トラブルのリスクを大幅に軽減できます。
仲介手数料がかからない
仲介による売却では、成約時に不動産会社に対して仲介手数料の支払いが必要になります。仲介手数料は「売却価格×3%+6万円(税別)」が上限として法律で定められています。たとえば、1,000万円で売却した場合、約36万円の仲介手数料が発生します。
一方、買取の場合は、買取業者が直接物件を購入するため仲介は発生せず、仲介手数料の支払いは不要です。この仲介手数料の節約分を考慮すると、買取価格が仲介価格より多少低くても、実質的な手取り額にそれほど大きな差が生じない場合もあります。
再建築不可物件を買取業者に売却する際の費用
買取業者への売却時に必要となる主な費用は以下の通りです。
再建築不可物件の買取売却時にかかる費用
| 費用項目 |
金額目安 |
備考 |
| 印紙税 |
1,000円〜6万円 |
売買契約書の契約金額により変動 |
| 抵当権抹消費用 |
1〜3万円程度 |
抵当権設定がある場合のみ |
| 譲渡所得税 |
利益の約20〜39% |
売却益が出た場合のみ |
なお、譲渡所得税の詳細については売却後の確定申告と税金の納付で詳しく解説しています。
買取の場合、通常は以下の費用が不要になります:
- 仲介手数料(売却価格の3%+6万円が上限)
- リフォーム・解体費用(現況のまま買取のため)
- 測量費用(業者によっては不要。ただし境界が不明確な場合は依頼される可能性あり)
- 広告費用(買取業者が直接購入するため不要)
物件を売りに出していることが世間に知られない
仲介による売却では、購入希望者を広く募集するため、不動産ポータルサイトへの掲載や新聞折り込み広告、現地看板の設置などの販売活動が行われます。
これにより、近隣住民や知人に物件を売却していることが知られてしまう可能性があります。相続した実家を売却する場合や、経済的な理由で売却を余儀なくされる場合など、売却の事実を周囲に知られたくない人にはデメリットといえるでしょう。
一方、買取の場合は、買取業者が直接物件を購入するため、広告や宣伝活動を行う必要がなく、売却していることが第三者に知られるリスクを大幅に軽減できます。査定から契約まで、買取業者との間でのみ手続きが完結するため、プライバシーを保護しながら売却を進められるでしょう。
再建築不可物件を買取業者に売却する際の注意点
買取による売却には多くのメリットがある一方で、いくつかの注意点も存在します。特に売却価格や業者選定に関する点は、売却を検討する際に必ず把握しておくべき重要な要素です。こうした意点を事前に理解することで、買取と仲介のどちらが自分の状況に適しているかを適切に判断できるようになります。
注意点については、以下で詳しく解説していきます。
仲介売却より売却価格が下がりやすい
買取による売却では、仲介による売却と比較して売却価格が低くなる傾向があります。一般的に、不動産の売却価格は、仲介の場合で市場相場通り、買取では市場相場の約7割程度になるとされています。たとえば、市場相場が1,000万円の不動産であれば、買取では700万円程度での売却となるのが通常です。
この価格差が生じる理由は、買取業者のビジネスモデルにあります。買取業者は物件を購入した後、商品として再生・活用し、第三者への再販や賃貸運用を行って利益を得ています。この過程で発生するさまざまなコストが買取価格に反映されるためです。
具体的には、以下のようなコストが想定されます。
- 建物の修繕・リフォーム費用
- 解体費用(必要に応じて)
- 保有期間中の税金・維持管理費
- 販売活動費用
- 業者の利益
特に、再建築不可物件の場合、工事の制約により通常よりも高額な修繕費用が見込まれたり、活用方法が限定されたりするリスクがあるため、これらのリスクを見込んだ価格設定となるのが一般的です。
業者によって買取価格に差が出る
同じ再建築不可物件であっても、買取業者によって提示される買取価格には大きな差が生じます。この価格差の要因は、主に各業者の活用ノウハウと出口戦略の違いにあります。
再建築不可物件に精通した業者は、建築基準法の制約の中でも効果的な活用方法を知っており、隣地の買い増しによる再建築可能化や、現行法に適合したリノベーション手法など、多様な出口戦略をもっています。これにより、物件から得られる将来的な収益を高く見積もることができ、結果として高い買取価格を提示できるのです。
一方で、再建築不可物件の取り扱い経験が少ない業者は、リスクを高く見積もったり、限定的な活用方法しか想定できなかったりするため、買取価格が低くなる傾向があります。
商品化コストは買取業者の活用ノウハウに大きく依存するため、業者によっては比較的仲介に近い価格帯での売却が可能な場合もあります。そのため、買取を検討する際は複数の業者から査定を取得し、価格だけでなく各業者の再建築不可物件に対する専門性や実績も含めて総合的に判断することが重要です。
再建築不可物件の買取業者はどこを見る?主な査定ポイント
再建築不可物件の買取査定では、一般的な不動産とは異なる特殊な評価基準が適用されます。買取業者は物件を購入後に収益化する必要があるため、再建築不可という制約の中でどのような活用が可能かを中心に査定を行います。以下の表にて、買取業者が重視する主要な査定ポイントを詳しく解説します。
再建築不可物件の主な査定ポイント
| 査定ポイント |
詳細 |
| 接道条件や立地 |
・買取業者が最も重視する要素
・隣地の買い増しや道路の拡幅により建築基準法の接道要件を満たせる可能性を詳細に検討
・接道幅員が2メートルに近い場合や、隣地所有者との交渉により接道部分の確保が見込める場合は高評価。 |
| 周辺の需要 |
・現在の建物をリフォームして賃貸運用する可能性を評価
・周辺エリアの賃貸需要や家賃相場、入居者層、駅からの距離、商業施設へのアクセス、学校や病院などの生活利便施設の充実度が評価対象 |
| 建物の状態 |
・構造や築年数、維持管理状況が買取価格に直結
・構造的に問題がなく最小限のリフォームで賃貸可能であれば高評価
・大規模修繕が必要な場合は査定価格が大幅に下落
・基礎部分や主要構造部の劣化具合を重点的にチェック |
| その他の瑕疵(かし) |
・事件や事故の発生履歴や近隣の嫌悪施設の存在など心理的瑕疵の有無を調査
・賃貸運用時の入居率や家賃設定に影響するため慎重に評価
・瑕疵の程度によっては買取を断られる場合もあり。 |
| 土地の形状や面積 |
・土地の形状が整形で面積が適切であれば将来的な活用の幅が拡大
・不整形地や極端に狭小な土地は建物の配置や駐車場の確保が困難で査定価格に影響
・高低差がある土地や擁壁の設置が必要な土地は追加工事費用を見込んだ評価 |
これらの査定ポイントを総合的に評価し、買取業者は最終的な買取価格を決定します。
重要なのは、一つの要素ではなく、複数の要素がどのように組み合わさって収益化の可能性を高めるかという観点です。このため、一見不利に思える条件でも、他の要素との組み合わせによって予想以上の査定価格が提示される場合もあります。
再建築不可物件の買取業者を選ぶポイント
再建築不可物件の買取は通常の不動産売却とは事情が大きく異なるため、業者選びでも特有のポイントを押さえる必要があります。
たとえば、一般的な「対応の速さ」「説明の丁寧さ」といった点に加えて、再建築不可物件特有の専門的な観点を確認することが重要です。特に、専門的な内容は素人には判断しにくい部分が多いため、不明な点は必ず質問してレスポンスを比較しましょう。
以下にて、業者選びの際にチェックすべきポイントをさらに詳しく解説していきます。
再建築不可物件の買取実績と活用ノウハウ
再建築不可物件は金融機関の融資がつかず流通も少ないため、買取実績の少ない業者では査定精度が低くなる傾向があります。このため、過去に同種の物件をどのくらい扱ったかを確認することが、適正価格での買取につながります。
専門業者は、再建築不可物件をどのように再販・活用するかの具体策をもっています。隣地と一体利用する方法、借地として活用する方法、リフォームして賃貸に転用する方法など、現場で培った実務ノウハウに基づく戦略です。
こうしたノウハウがある業者であれば、潜在的価値を正確に見極められるため、過剰にリスクを織り込むことなく適正価格で買取してもらえます。
【確認方法】
公式サイトで「再建築不可の買取事例」が掲載されているか、相談時に過去の事例を聞いてみましょう。経験豊富な業者はWebで具体的な取引事例を公開していることもあり、実際の買取価格や売却後の再販方法などが参考になります。
【ポイント】
実績が豊富な業者ほど「再販売」「隣地買収」「投資用活用」など多様な出口戦略を持ち、買取価格にも反映されやすくなります。査定額に反映されるのはもちろん、業者の対応からも専門性の高さを判断できます。
法規制や再建築可能性に関する知見
接道要件の緩和、セットバック、隣地買収など、将来的に「再建築可能」とできる可能性を見極められるかは、買取価格に大きく影響する重要な要素です。建築基準法や都市計画法に関する深い知識をもつ業者なら、現在は再建築不可でも将来的な可能性を含めた適正評価が可能です。
【確認方法】
査定時に「この物件は再建築可能になる可能性はありますか?」と具体的に質問してみましょう。また、接道幅員の測定や隣地との境界確認を行っているかも確認ポイントです。
【ポイント】
知見がある業者なら、接道要件やセットバックの有無、隣地買収の実現可能性などを具体的に説明してくれます。あいまいな返答しかない場合は知識不足の可能性があるため注意が必要です。
弁護士等の士業との連携
相続で取得した再建築不可物件は、相続登記が済んでいないと売却できません。また、共有名義など複雑な権利関係がある場合は、司法書士や税理士と連携している業者を選ぶと手続きがスムーズに進みます。
登記手続きや税務相談に対応できる業者なら、登記から税務申告までまとめてサポート可能です。実務上、こうした体制が整っている業者なら、売却手続きにかかる負担や不安を軽減できます。
【確認方法】
相続関連の手続きサポートがあるか、提携している士業事務所があるかを確認しましょう。
【ポイント】
信頼できる業者は、契約解除条件や補償内容もわかりやすく提示してくれるため、売主に不利な状況を避けられます。
取引条件の柔軟性
引渡し猶予、残置物処分、契約不適合責任免除など、売主に有利な条件を提案できるかも重要なチェックポイントです。
【確認方法】
契約前に「引渡し猶予は可能か」「残置物処分は業者で対応してもらえるか」など具体的に条件を提示して交渉してみましょう。現金化まで即日~数週間で対応できる業者を選べば、期限に合わせてスムーズに手続きを進められます。
【ポイント】
柔軟に対応できる業者は、売主の事情に合わせた売却が可能でストレスが少なくなります。ただし、極端に短期間を謳う業者は査定精度が十分でないこともあるため、現実的なスピードと適正な価格の両立が重要です。
また、査定額の根拠をきちんと説明できる業者は、経験に基づいた信頼できる査定を行っています。「再建築不可だから安い」とだけ説明する業者は避け、プラス要素も含めた透明性のある査定を提供できる業者を選ぶとよいでしょう。
再建築不可物件を業者に買い取ってもらう流れ
再建築不可物件の買取売却は、一般的な仲介売却とは手続きの流れが大きく異なります。買取業者との直接取引となるため、購入希望者を探す期間が不要で、スピーディーな売却が実現できます。
以下では、査定依頼から代金受領まで、具体的な手続きの流れを詳しく解説します。
査定依頼
売却の第一歩は、買取業者への査定依頼です。電話・メール・不動産会社のサイトなどから無料で依頼でき、複数社に依頼して比較することが高値売却のポイントとなります。
再建築不可物件は一般的な物件と異なり、取り扱いできる業者が限られているため、専門業者を中心に依頼することが重要です。査定依頼時には、物件の基本情報(所在地、築年数、構造、接道状況など)のほか、相続物件であるか、急いで売却したいかなどの事情も伝えておくと、より正確な査定が期待できます。
同じ物件でも業者によって査定額に数十万円から数百万円の差が生じることも珍しくないため、必ず複数社に依頼して比較検討を行いましょう。査定は無料で行われるため、売却を決定していない段階でも気軽に相談できます。
現地調査
査定依頼後、業者が物件を訪問し、接道状況・建物の状態・周辺環境を実際に確認します。再建築不可特有のポイントとして、セットバックの可能性、隣地との関係、将来的な再建築可能性なども詳細にチェックされます。
現地調査では、建物の構造や劣化状況、設備の状態、敷地の形状や高低差なども評価対象となります。また、周辺の賃貸需要や交通利便性、商業施設へのアクセスなども査定に影響する要素として調査されます。
この際、残置物の有無や建物の状態について事前に正確に伝えておくと査定がスムーズに進みます。隠し事があると後から査定額の見直しが発生する可能性があるため、現況を正直に開示することが重要です。
査定額の提示・交渉
現地調査完了後、数日で査定額が提示されます。査定書には買取価格だけでなく、その根拠や条件も明記されているため、内容をしっかりと確認しましょう。業者によって数十万円から数百万円の差が出ることがあるため、金額だけでなく条件面も含めて総合的に比較検討することが大切です。
査定額に納得がいかない場合は、価格交渉も可能です。また、引渡し猶予・残置物処分・契約不適合責任免除などの条件交渉も同時に行えます。特に相続物件の場合、遺品整理や引越しに時間が必要なケースが多いため、引渡し時期についても柔軟に相談してみましょう。
査定額だけでなく、業者の対応や専門性、提案内容なども判断材料として重視し、最も信頼できる業者を選定することが成功のカギとなります。
契約・引渡し
売却条件に合意したら売買契約を締結します。仲介と異なり、契約不適合責任を免除できるケースが多く、売却後のトラブルリスクを大幅に軽減できます。契約書には売買代金、引渡し日、残置物処分の取り決めなどが明記されるため、内容をよく確認してから署名・押印を行いましょう。
契約時に必要な書類は、権利証(登記識別情報通知書)、印鑑証明書、住民票、固定資産税納税通知書などです。相続物件の場合は、相続登記が完了していることが前提となるため、事前に手続きを済ませておく必要があります。
契約後は、残置物処理や引越しなど引渡し準備を進めます。多くの買取業者では残置物処分も対応してくれるため、処分費用や手間を軽減できます。引渡し日までに物件を空の状態にし、鍵の引渡しをもって売却手続きが完了します。
入金
契約完了から数日から数週間で代金が入金されます。仲介売却と比べて現金化のスピードが圧倒的に早く、急な資金需要にも対応可能です。入金方法は銀行振込が一般的で、振込手数料は買取業者が負担するケースが多くなっています。
入金前には、登記移転手続きが完了していることを確認します。司法書士が立ち会いのもと所有権移転登記が行われ、新たな所有者への名義変更が完了した後に代金が支払われる流れとなります。
入金確認をもって売却手続きが正式に完了となります。領収書の発行や、今後の税務申告に必要な書類の保管も忘れずに行いましょう。
売却後の確定申告と税金の納付
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、確定申告が必要になります。譲渡所得は「売却価格-(取得費+譲渡費用)」で計算され、プラスになった場合に課税対象となります。
| 所有期間 |
区分 |
税率 |
内訳 |
| 5年以下 |
短期譲渡所得 |
約39% |
所得税30%+住民税9% |
| 5年超 |
長期譲渡所得 |
約20% |
所得税15%+住民税5% |
相続で取得した物件の場合、取得費の計算が複雑になりやすく、被相続人の取得価格や取得時期の確認が必要です。また、相続税を支払っている場合は、一定額を取得費に加算できる特例もあります。
また、譲渡損失が出た場合は確定申告の義務はありませんが、他の所得と損益通算することで節税効果が期待できる場合があります。計算が複雑で不安がある場合は、税理士に相談すると安心して手続きを進められるでしょう。
再建築不可物件の買取事例
再建築不可物件の買取は、物件の状況や売主の事情によってさまざまなケースがあります。実際の買取事例を通じて、どのような物件がどの程度の価格で売却できるのか、具体的なイメージを掴んでいただけます。
以下では、当社が実際に対応した代表的な買取事例をご紹介します。なお、紹介する事例は、当社が実際に対応した案件をもとに、個人情報が特定されないよう配慮し一部内容を編集・加工したものです。
相続した空き家を早期処分したケース
| 項目 |
詳細 |
| 相談者 |
50代女性/地方在住 |
| 物件 |
築45年の木造住宅(接道幅1.5m/再建築不可) |
| 背景 |
相続したものの遠方にあり管理が困難で、維持費負担も重かった |
| 買取価格 |
550万円 |
| 結果 |
残置物処分も含めて当社が引き受け、固定資産税などの負担から解放された |
この事例では、相続により取得した遠方の空き家を早期処分したいというニーズに対応しました。接道幅が狭く再建築不可であったものの、立地条件や建物の状態を総合的に評価し、適正価格での買取を実現しました。残置物の処分から手続きまで一括対応することで、売主様の負担を最小限に抑え、維持管理費用からの解放を実現できました。
住宅ローン返済が困難になり売却したケース
| 項目 |
詳細 |
| 相談者 |
40代男性/会社員 |
| 物件 |
築30年の戸建て(4m未満の私道に接道) |
| 背景 |
転職による収入減でローン返済が難しく、仲介売却は1年以上売れ残っていた |
| 買取価格 |
1,200万円 |
| 結果 |
ローンを完済でき、任意売却を避けることができた |
転職による収入減で住宅ローンの返済が困難になったケースです。仲介では1年以上売却できずにいましたが、買取により迅速な現金化を実現し、任意売却を回避できました。私道に接道する再建築不可物件でしたが、建物の状態や立地を適正に評価することで、ローン完済に十分な価格での買取が可能となりました。
投資用戸建を一括売却したケース
| 項目 |
詳細 |
| 相談者 |
60代男性/不動産投資家 |
| 物件 |
築38年の木造戸建(接道なし) |
| 背景 |
老朽化による空室で採算が合わず、修繕コストも見合わないと判断 |
| 買取価格 |
400万円 |
| 結果 |
早期に売却資金を確保し、別の収益物件へ再投資できた |
投資用として運用していた再建築不可物件の老朽化により、収益性が悪化したケースです。接道なしという厳しい条件でしたが、土地の立地ポテンシャルを評価し、投資家様の資産組み替えニーズに対応しました。早期売却により確保した資金で、より収益性の高い物件への再投資が実現できました。
狭小地を隣地所有者に売却したケース
| 項目 |
詳細 |
| 相談者 |
70代女性/住み替え希望 |
| 物件 |
土地面積50㎡の戸建て(接道2m未満) |
| 背景 |
高齢のため引っ越しを検討していたが、通常の売却は困難 |
| 買取価格 |
800万円 |
| 結果 |
市場相場より高い価格で現金化でき、住み替え資金を確保できた |
狭小地かつ接道条件を満たさない再建築不可物件でしたが、隣地との一体利用の可能性を見出すことで高値での売却を実現しました。通常の市場では売却が困難な物件でも、専門的な知識と豊富なネットワークにより、市場相場を上回る価格での買取が可能となった事例です。
事故物件を含む再建築不可物件を処分したケース
| 項目 |
詳細 |
| 相談者 |
30代女性/相続人 |
| 物件 |
築40年の木造住宅(接道条件NG/過去に孤独死あり) |
| 背景 |
心理的瑕疵により仲介での売却はほぼ不可能 |
| 買取価格 |
180万円 |
| 結果 |
心理的瑕疵を考慮したうえで当社が買取を行い、維持管理の負担から解放された |
再建築不可に加えて心理的瑕疵も重なった、非常に売却困難な物件のケースです。仲介での売却はほぼ不可能な状況でしたが、専門業者として適正に評価し、売主様の精神的・経済的負担の解消を最優先に対応しました。困難な案件でも諦めずに解決策を提案できることが、専門業者の強みといえます。
まとめ
再建築不可物件は仲介よりも買取が現実的な選択肢です。
一般の購入希望者にとって再建築不可物件は敬遠されがちで、住宅ローンの利用も困難なため、仲介での売却には長期間を要したり、売却自体が困難になったりするケースが少なくありません。この点、買取専門業者なら、専門的な知識と豊富な活用ノウハウをもっているため、確実かつスピーディーな売却が期待できます。
ただし、同じ物件でも業者によって数十万円から数百万円の査定額の差が生じる可能性があるため、業者の比較が必須です。必ず複数の業者に査定を依頼し、金額だけでなく条件面も含めて総合的に比較検討しましょう。
また、信頼できる業者を選ぶこともスムーズな売却のカギとなります。再建築不可物件の買取実績、法規制に関する知見、士業との連携体制、取引条件の柔軟性などを総合的に評価し、最も信頼できる業者を選定するのが重要です。
再建築不可物件に関するよくある質問
再建築不可から再建築可能になるケースにはどのようなものがありますか?
再建築不可から再建築可能にするケース(方法)は次の通りです。
| 再建築可能にする方法 |
内容 |
| セットバック |
前面道路の幅員が4メートル未満の場合、道路中心線から2メートル後退することで接道要件を満たす方法 |
| 隣地買収 |
隣地を買収して接道幅員を2メートル以上確保し、再建築可能とする方法 |
| 道路の拡幅・新設 |
行政による道路拡幅工事や都市計画道路の整備により接道要件を満たすケース |
| 建築基準法の緩和措置 |
一定の条件下で適用される法的緩和措置 |
ただし、これらの方法が適用できるかは物件ごとに異なるため、専門家による詳細な調査が必要です。
相続で引き継いだ再建築不可物件を処分する場合に何か注意点はありますか?
相続で引き継いだ再建築不可物件を処理する際の注意点は次の通りです。
| 注意点 |
詳細 |
| 相続登記の完了させておく |
2024年4月から義務化。相続開始から3年以内に手続きを行わないと過料が科される可能性 |
| 取得費を算定しておく |
被相続人の取得価格が不明な場合は売却価格の5%を取得費とする |
| 相続税の取得費加算特例を把握しておく |
相続税を支払った場合、一定額を取得費に加算して譲渡所得税を軽減可能 |
| 共有名義を把握しておく |
売却には原則として共有者全員の同意が必要 |
再建築不可物件をそのまま保有し続けるリスクはどのようなものがありますか?
再建築不可物件をそのまま保有し続ける場合のリスクは次の通りです。
| リスク項目 |
内容 |
| 税負担の継続 |
固定資産税・都市計画税が毎年課税。「特定空家等」指定で軽減措置解除の可能性 |
| 維持管理費用 |
修繕費、草刈り・清掃費、管理会社への委託費用などが継続的に発生 |
| 資産価値の下落 |
建物の老朽化により価値が下落し続ける。取り壊すと土地のみの価値に |
| 損害賠償リスク |
建物倒壊や屋根材飛散で近隣に被害を与えた場合の賠償責任 |