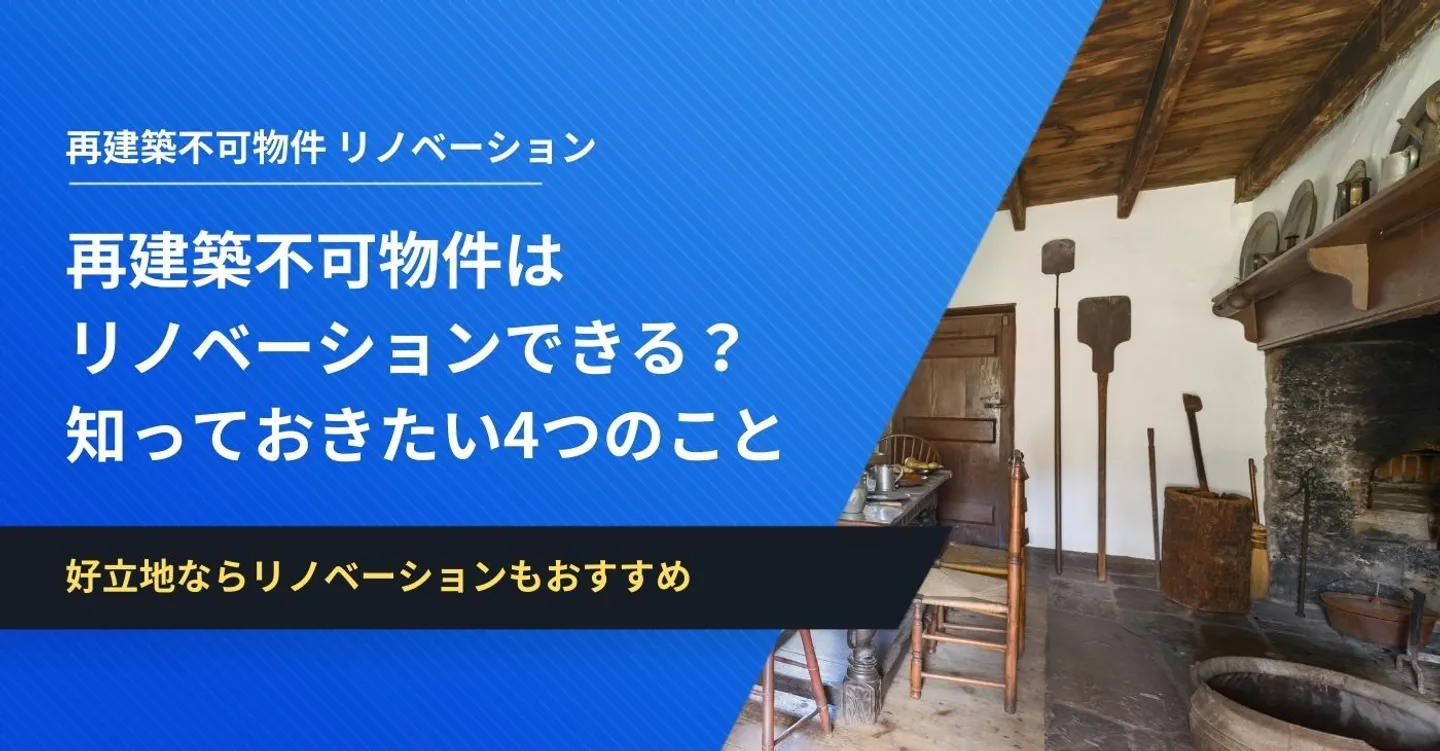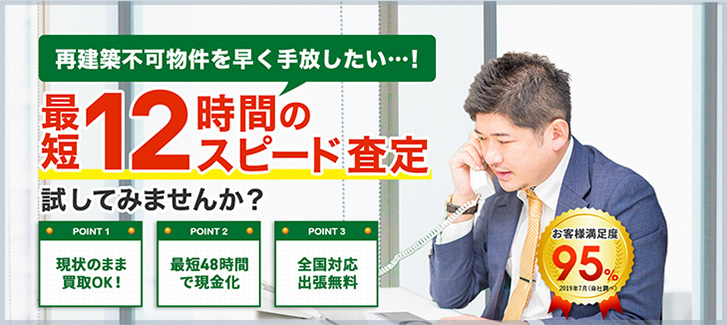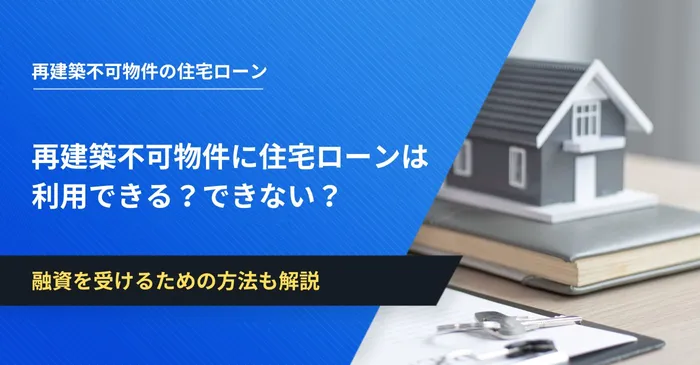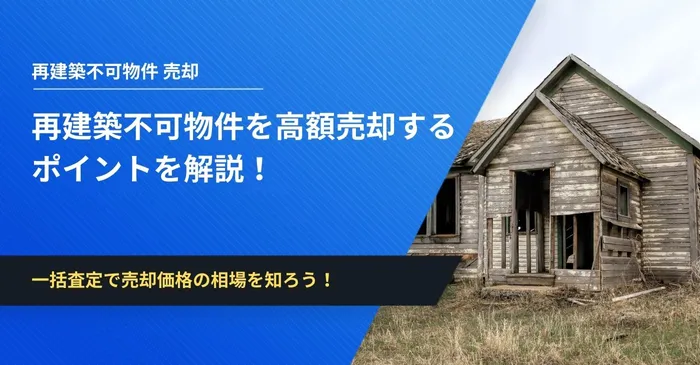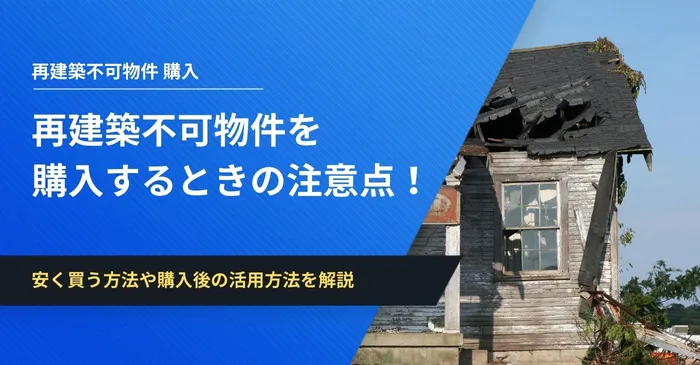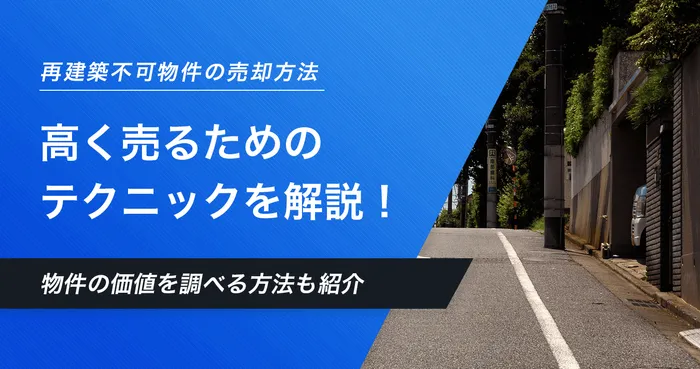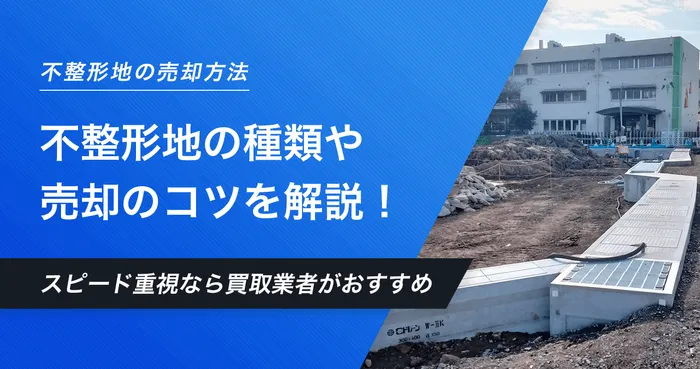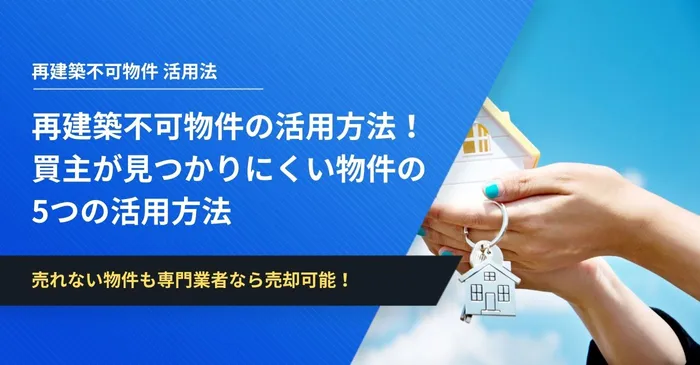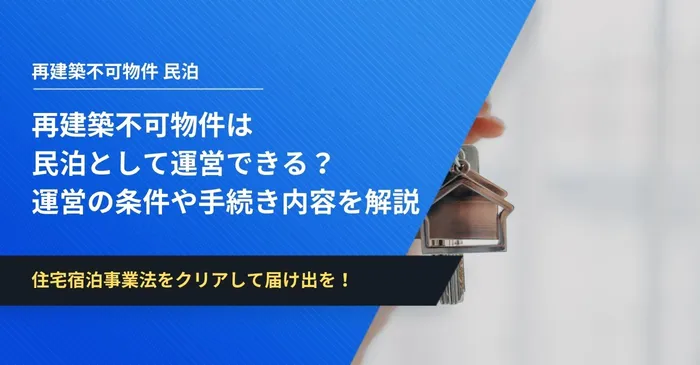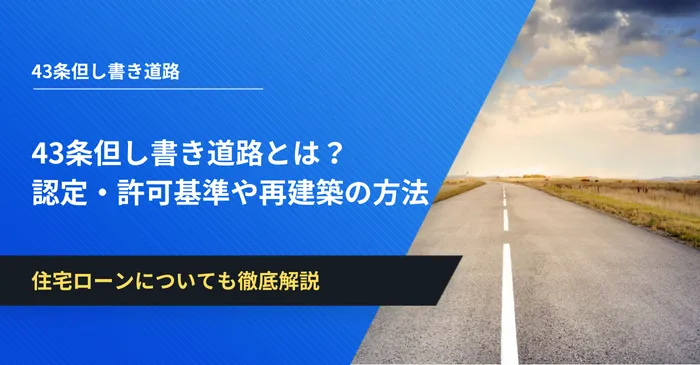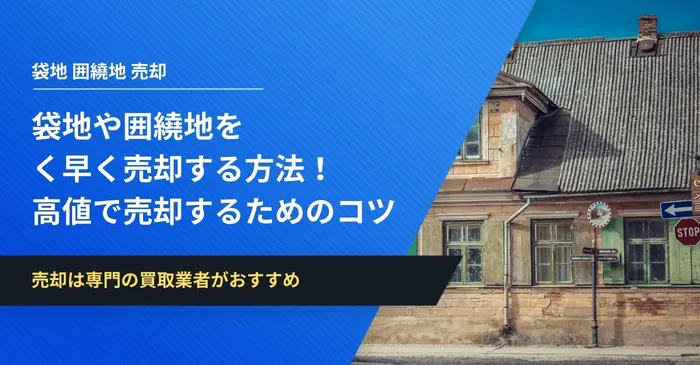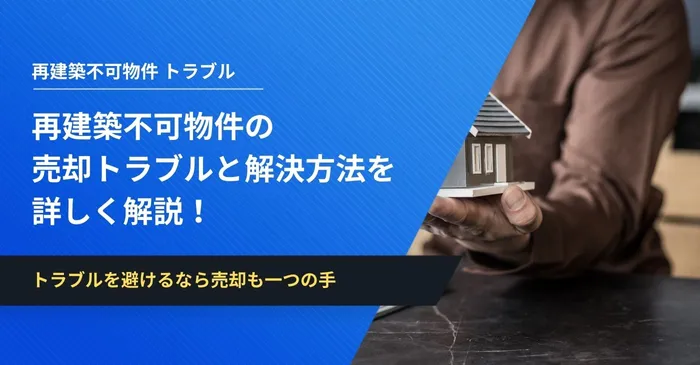再建築不可物件でもリノベーションはできる
一口にリノベーションといっても、原状回復や模様替えから建て替えに近いものまで、様々な規模のものが考えられます。
再建築不可物件は増築や改築が禁止されているため、構造部分や外壁に手を入れる場合は注意が必要です。
特に、建築確認を受ける必要があるかどうかによって、リノベーションの可否も決まります。
リノベーションができるかどうかは「建築確認の有無」による
建築確認とは、建物の建築や大規模修繕をおこなうときに必要な手続きです。
建築確認では、これから施工する工事が、建築基準法に違反していないかどうかを地方自治体が確認します。
建築確認を受けずに施工することは禁止されているため、建築確認は建築・大規模修繕の必須条件です。
建築確認の必要性は、建築基準法上の「4号建築物(建築基準法第6条の4に該当する建物)」であるかどうかで決まります。
地域によって判断が異なるため、リノベーションを検討している場合には、地方自治体や不動産会社に建築確認の有無を相談するとよいでしょう。
参照:e-Govポータル「建築基準法第6条の4」
「4号建築物」における修繕や模様替えに建築確認は不要
4号建築物とは、建築基準法第6条1項に定められている1号~3号以外の建築物です。
4号建築物では、大規模修繕や模様替えといったリノベーションによる建築確認は不要です。
4号建築物とは、簡単にいうと個人が住宅として利用したり、小規模な店舗や病院・学校として利用したりするような建物を指します。
具体的には、下記のように「一般建築」と「特殊建築物」に分けられます。
一般建築物(戸建住宅・事務所など)
<木造の場合>
2階建て以下
かつ延べ面積500㎡以下
かつ高さ13m・軒高9m以下
<非木造の場合>
平屋
かつ延べ面積200㎡以下
特殊建築物(学校、病院、店舗、共同住宅など)
<木造の場合>
2階建て以下
かつ延べ面積100㎡以下
かつ高さ13m・軒高9m以下
<非木造の場合>
平屋
かつ延べ面積100㎡以下
4号建築物でも建築基準法の諸規定は遵守しなければいけませんが、行政からの事前審査はありません。
4号建築物に該当する再建築不可物件では、リノベーションが問題になるケースはほとんどないでしょう。
参考:国土交通省「建築関係法の概要 建築基準法について」
参考:埼玉県「4号建築物」
4号建築物に該当しない建築物でも小規模なリノベーションは可能
4号建築物に該当しない再建築不可物件の場合、建築確認申請はまず通りません。
ただし「主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段)のうち1つ以上で1/2を超える修繕」にあてはまらない場合、建築確認はいりません。
要するに、小規模な工事なら建築確認を申請しなくても施工できるとうことです。
したがって、工事を複数にわけ、1つの工事が1/2を超えないようにすれば、建物全体の修繕や模様替えが可能です。
しかし、工事が大規模なのか小規模なのかを判断するにあたり、明確な基準はありません。そのため、リフォーム会社などに相談し、どのように工事を進めるとよいかアドバイスをもらいましょう。
再建築不可物件でリノベーションすべき状況
再建築不可物件のうち、リノベーションに向いている物件は、大きくわけて2種類あります。
1つは、今後も長く住む予定の住居である場合です。リノベーションをおこなうことで建物の安全性が上がり、今後も長く住めるようになります。
むしろ、今後も長く住みたいのであれば、老朽化した建物はなるべく早くリノベーションすべきです。
もう1つは、立地がよい物件を賃貸向けにリノベーションする場合です。リノベーションで賃貸需要を高められるでしょう。
主要な電車の沿線や駅の近くなど、利便性の高いエリアに立地している場合は、ぜひ検討してみましょう。
再建築不可物件をリノベーションする際の注意点
再建築不可物件をリノベーションするにあたり問題となるのは、建築確認だけではありません。
コストや賃貸物件としての需要など、事前にしっかり調査する必要があります。
特に、再建築不可物件を新たに購入してリノベーションする計画を立てている場合は、入念に対応を練っておきましょう。
他の物件と比較してリノベーションのコストが高い恐れがある
再建築不可物件をリノベーションする際は、リノベーションにかかるコストに注意しましょう。
再建築不可物件は道路への接道義務を果たしておらず、工事車両が物件の近くに接近できない場合や、接道していても幅員が狭くて通り抜けられない場合があります。
また、建物の周囲に足場を組んだり、資材を置いたりするスペースがないことが多く、そもそも工事ができないケースもあります。
築年数の古い物件である場合、いざ着工したら想定以上に状態が悪く、コストが上乗せされるケースもあるでしょう。
新たに再建築不可物件の購入を検討している場合は、売主に物件の詳しい状態を確認しておくことをおすすめします。
賃貸する場合には築年数に注意
再建築不可物件をリノベーションし、アパートのような形で賃貸しようと考えている場合には、築年数に注意しましょう。
築古のアパートは入居希望者から敬遠されがちです。特に、再建築不可物件は築古物件が多く、リノベーションでは築年数を刷新できません。
いくら全体的にリノベーションをしていても、事情を知らない人が「築60年」という表示を目にしたら、それだけで入居を避ける場合があります。
対策としては、物件情報サイトに登録する画像が重要です。ひと目見ただけで大規模なリノベーションをしたことがわかるようなものにしましょう。
物件資料に、リノベーション済みであると明記することも大切です。
再建築不可物件のリノベーションでローンの利用は難しい
再建築不可物件をリノベーションするにあたり、ローンの利用を検討する人も多いでしょう。しかし、再建築不可物件のリノベーションに対して、金融機関のローン審査を通過するのは難しいといえます。
再建築不可は、担保価値が低く査定されてしまいます。
また、金融機関は原則として、建物の耐用年数の期間内でしか融資をおこないません。
建物を賃貸用にリノベーションするのであれば、その収益率によってはローンを受けることも可能ですが、条件は厳しいものとなるでしょう。
ましてや、自身の居住用にリノベーションする場合には、その物件から収益があがるわけではありませんので、なおさらローンを受けにくいといえます。
日本政策金融公庫の利用を検討しよう
事業用に再建築不可物件をリノベーションするなら、日本政策金融公庫の利用を検討しましょう。日本政策金融公庫は通称「公庫」と呼ばれる、政府系金融機関です。
公庫は担保価値よりも事業計画を重視して融資する傾向があります。事業計画が優れていれば、ローンを組めるケースが少なくありません。
公庫は定期的に事業計画作成の支援イベントを企画しているため、そのようなイベントでアドバイスをもらうとよいでしょう。
ただし、いくら担保価値より事業計画を重視するといっても、担保としての価値がゼロでも問題ないというわけではありません。
担保価値が高いに越したことはありませんので、担保価値と事業計画のどちらにも注意を怠らないようにしましょう。
参考:日本政策金融公庫
まとめ
再建築不可物件のリノベーションを検討する場合は、まずは「そもそもリノベーションするだけの価値があるのかどうか」を冷静に判断しましょう。
また、せっかく多額のコストをかけてリノベーションをしても、物件を充分に利用・活用できなければ意味がありません。
「何のためにリノベーションをするか」をしっかりと検討し、悔いのないリノベーションをおこないましょう。
再建築不可物件のリノベーションに関するよくある質問
再建築不可物件とは何ですか?
接道義務を守れていないなどの理由で建築基準法を満たしておらず、新しい建物の建築ができない物件です。
再建築不可物件はリノベーションできますか?
地方自治体から建築確認が認められれば、再建築不可物件でもリノベーション可能です。また、小規模な工事(柱や梁など主要部分以外の工事)であればそもそも建築確認が不要なので、自由にリノベーションできます。
再建築不可物件をリノベーションする際、注意点はありますか?
他の物件よりもリノベーションにかかる費用が高く、築年数が古いと賃貸に出しても借主が見つかりにくい点に注意しましょう。
再建築不可物件をリノベーションする場合、ローンは利用できますか?
不可能ではありませんが、審査を通過するのは基本的に難しいでしょう。仮に通過できても、金利や返済期間などで不利な条件となるケースがほとんどです。ただし、事業用資産であれば、日本政策金融公庫の融資を受けられる可能性があります。
どのような再建築不可物件ならリノベーションに向いていますか?
立地のよい物件であれば、リノベーションによって資産価値を大幅に向上できる場合があります。また、思い入れのある物件なら何より自分の気持ちが重要なので、今後も長く残していきたいと考えるのであれば、リノベーションをするとよいでしょう。
訳あり不動産の売却でお悩みなら
今すぐご連絡ください
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-