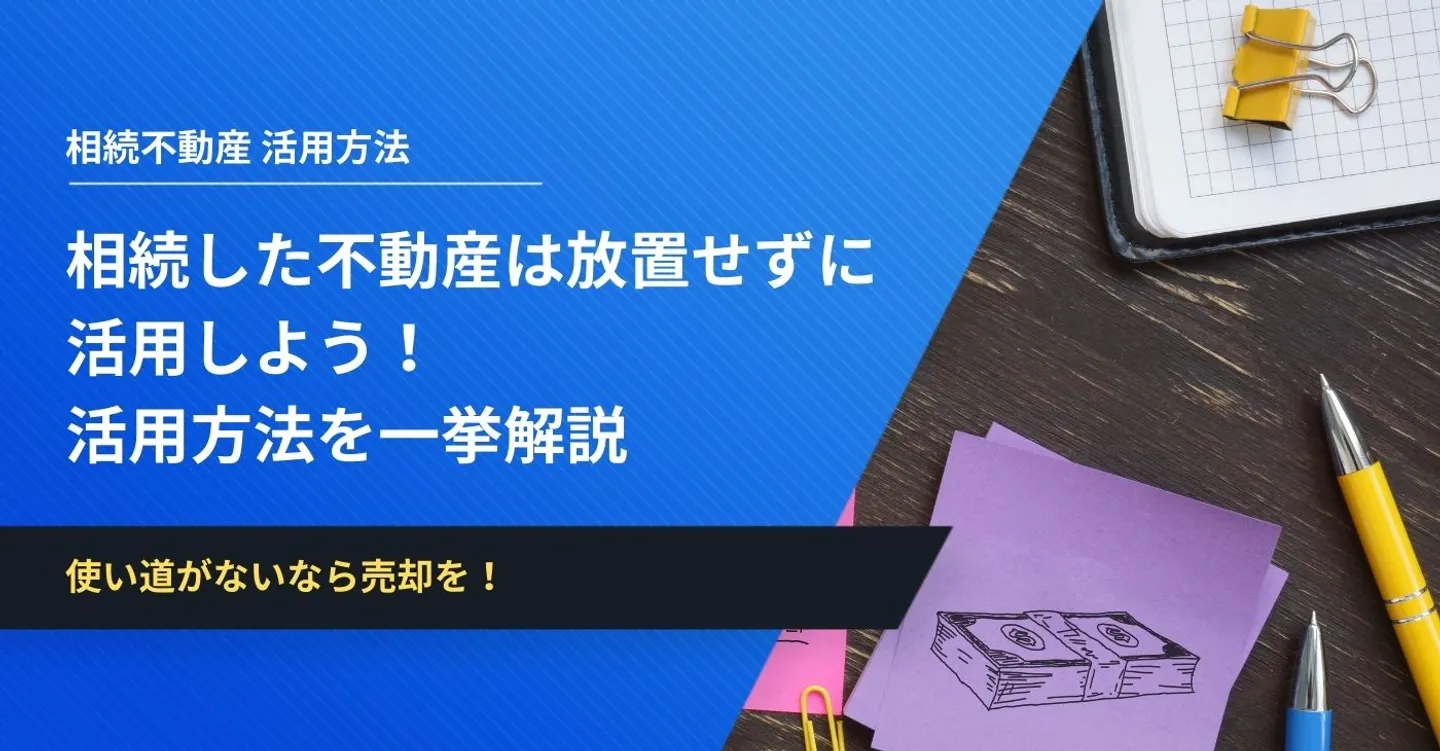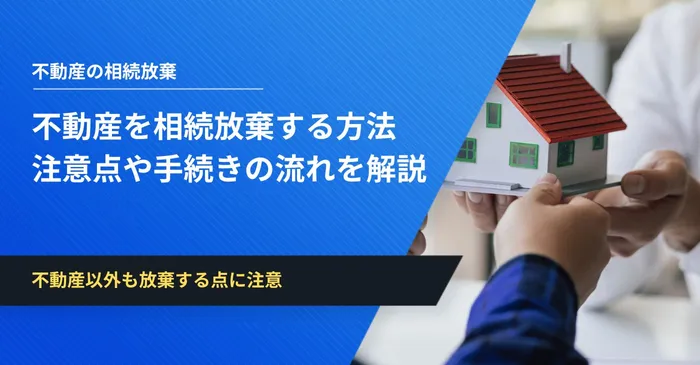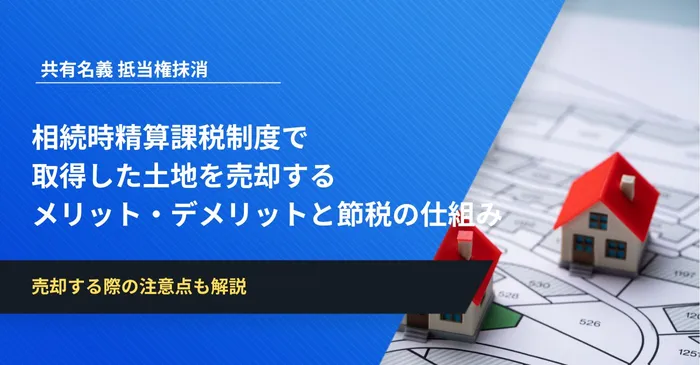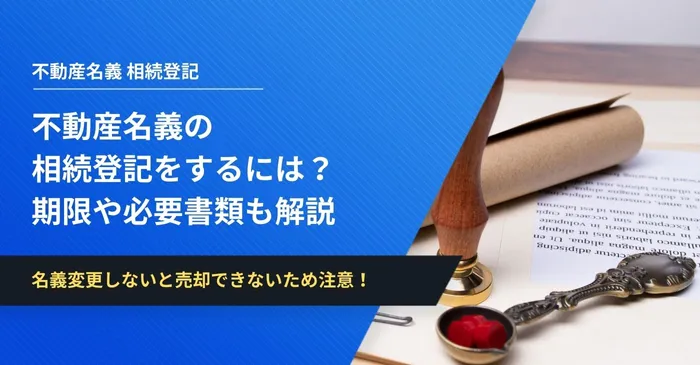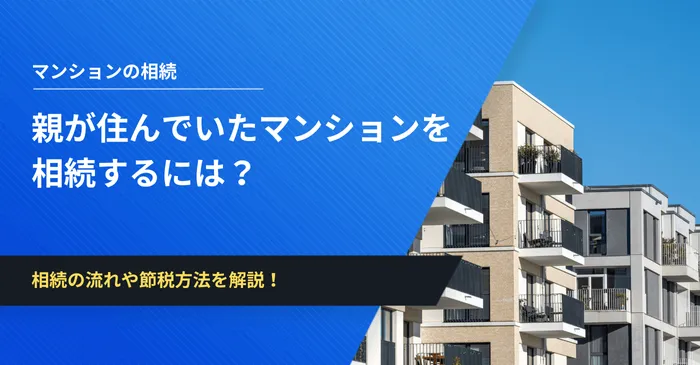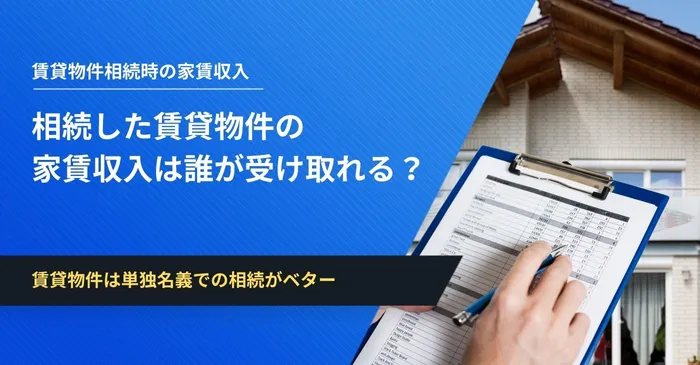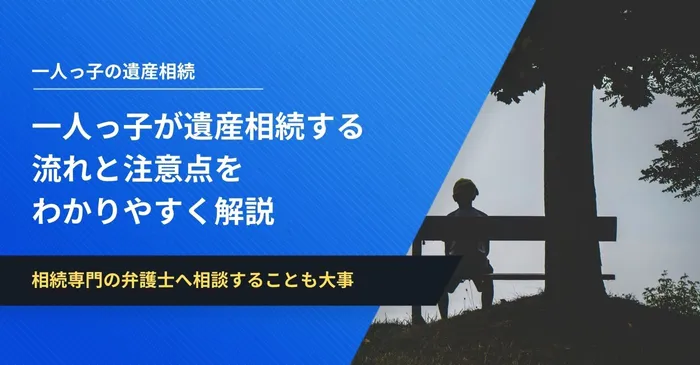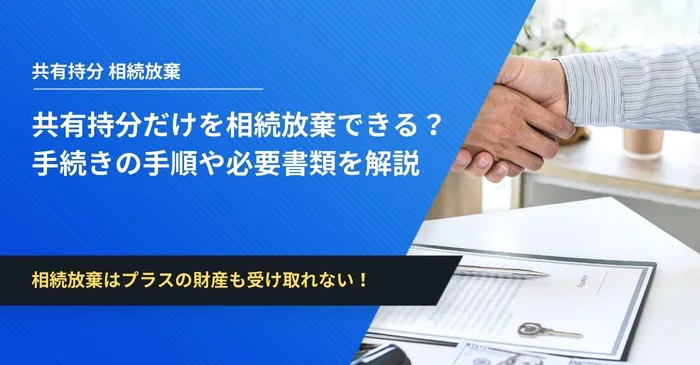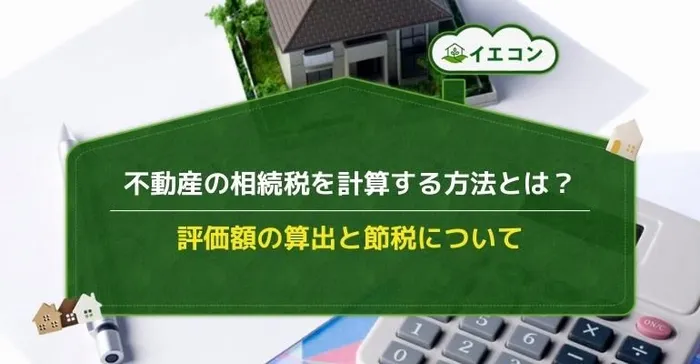相続した不動産をそのまま放置するリスク
まず前提として、相続した不動産をそのまま放置することは絶対に避けましょう。
建物・土地に関わらず、不動産を所有している限り、固定資産税や都市計画税を毎年負担しなければなりません。
そのうえ、建物や土地を活用せずに放置してしまうと、老朽化が進んで建物が倒壊して損害賠償を請求されるリスクや、固定資産税・都市計画税を余計に課税されてしまうのです。
相続した不動産を活用せずに放置すると起こる問題と解決方法を解説します。
固定資産税や都市計画税が毎年かかり続ける
相続した不動産を所有する限り、固定資産税や都市計画税を毎年納税しなければなりません。
固定資産税とは、建物や土地などに対して課税される税金で、毎年1月1日時点に不動産を所有している人物が納税するように定められています。
都市計画税は市街化区域都市に建物や土地を所有している場合に課せられる税金で、 毎年1月1日時点に不動産を所有している人物へ固定資産税とあわせて徴収されます。
固定資産税と都市計画税の納税額は、それぞれ以下のとおりです。
- 固定資産税=固定資産税評価額 × 1.4%
- 都市計画税=固定資産税評価額 × 0.3%
ここでいう固定資産税評価額は、固定資産税を決める際の基準となる金額のことで、土地であれば、時価の約70%程度といわれています。
正確な固定資産税評価額を知りたい場合、固定資産税の納税通知書で確認できます。
建物や土地を第三者へ貸し出した場合も、固定資産税や都市計画税は借主や借地人ではなく所有者自身が納税しなければなりません。
建物や土地を貸し出して家賃収入や地代を得ることができれば、固定資産税や都市計画税を払ってでも相続した不動産を所有し続けるメリットがあります。
しかし、そのまま放置しておいても税金を徴収されるだけでデメリットしかないため、相続した不動産を活用して収益化するか、手放してしまった方がよいでしょう。
【建物の場合】空き家にすると老朽化してしまう
相続した不動産が建物の場合、定期的な掃除やメンテナンスを施さず、空き家のまま放置すると老朽化が進んでしまいます。
なぜなら以下のような理由で、人が利用している建物に比べて、空き家は湿気・カビ・害虫などが沸きやすいためです。
- 空気が換気されない
- 掃除がおこなわれない
- 修繕がされない
そして老朽化した建物が倒壊して周辺住民へ被害を与えてしまうと、損害賠償を請求されてしまう恐れもあります。
老朽化による建物の倒壊を防ぐにも、自分または第三者に利用してもらい、定期的な掃除やメンテナンスをしてもらったほうがよいでしょう。
【土地の場合】固定資産税の負担が大きくなる
相続した不動産が土地の場合、建物がある場合に比べて、固定資産税・都市計画税を多く支払わなければなりません。
土地に建物が建っている場合、固定資産税・都市計画税は土地の面積に応じて、次のような軽減措置を受けられます。
住宅用地が受けられる減税措置
| 面積 |
固定資産税 |
都市計画税 |
| 小規模住宅用地(200㎡まで) |
課税標準額×1/6×1.4% |
課税標準額×1/3×0.3% |
| 一般住宅用地(200㎡以上) |
課税標準額×1/3×1.4% |
課税標準額×2/3×0.3% |
相続した不動産が更地のまま放置すると、これらの軽減措置を受けられないため、固定資産税は最大6倍、都市計画税は最大3倍まで負担が大きくなります。
相続した土地を放置しても、無駄な税金を余計に払うだけですので、土地を活用して収益化することで、固定資産税・都市計画税の負担を相殺しましょう。
不動産が必要なければ買取業者に売却しよう
建物の老朽化や土地の税金を抑えるには、相続した不動産を自分自身で管理・活用していかなればなりません。
とはいえ、自分で利用するにしても、他人へ貸し出して活用するにしても、手間や費用がかかるため、次のように感じる方も多いでしょう。
- 「不動産を相続したけど、必要ないのでいますぐ手放したい!」
- 「相続した不動産でないのでいますぐ手放したい!」
相続した不動産を手間なく処分したい場合、不動産買取業者へ売却することをおすすめします。
当サイトを運営する不動産買取業者「クランピーリアルエステート」では、最短12時間で査定額をお伝えしたのち、最短48時間での現金化も可能です。
「相続した不動産を活用するか、売却するか迷っている・・・」という方も大歓迎ですので、まずはお気軽にご相談ください。
査定や相談だけであれば一切費用はかかりません!疑問や質問をお気軽にお問い合わせください。
最短48時間のスピード買取で
不動産を現金化
「高く・早く・トラブルなく」
売却したいなら
訳あり物件買取専門の
当社にお任せください!
相続した建物の活用方法
「せっかく相続した不動産を無駄なく活用したいけど、どうすればいいか方法がわからない・・・」と頭を悩ませている方も多いでしょう。
一軒家をはじめアパートやマンションなどの建物を相続した場合、活用方法として次のような方法が挙げられます。
- 建物をそのまま貸し出す
- リフォーム・リノベーションしてから貸し出す
- 建物を解体してから土地活用する
建物の活用方法としては、建物を貸し出して賃料を得る「賃貸経営」が基本になりますが、それがむずかしい場合は建物を解体して土地活用へ移るのも方法の1つです。
それぞれの活用方法とメリット・デメリットを解説していきます。
【方法1】建物をそのまま貸し出す
1つ目の活用方法は、建物をそのまま貸し出す方法です。
相続した不動産が建物であれば、そのままの状態で第三者へ貸し出すことも可能です。
とくに都市部の人気の高いエリアの建物なら、そのままでも入居者が集まり、賃貸物件として収益化できる可能性もあります。
また、すでに入居者がいるアパートやマンションを相続した場合、そのままオーナーとなることで安定した家賃収入が得られます。
メリット:初期費用が必要ない
建物をそのまま貸し出すメリットは、初期費用がかからないことです。
建物へリフォームや建て替えをおこなってから貸し出す場合、少なくても100万円以上の初期費用をかけなければなりません。
一方でリフォームや建て替えをせずに建物をそのまま貸し出せば、経済的負担がないだけでなく、時間や手間もかかりません。
とりあえず、最初は現状のままで建物を借りてくれる借主を探して、見つからない場合に別の方法を検討するのもよいでしょう。
デメリット:築年数が古いと空室リスクが高い
建物を相続する場合、築年数の浅い建物を相続するケースよりも、築年数が古い実家などを相続することのほうが多いでしょう。
一般的に築年数が古い物件は需要が少ないため、借主が集まりにくく空室が生まれてしまい、満足いく家賃収入を得られない恐れもあります。
築年数を判断する基準として、一戸建ての場合は「築20年ぐらいで建物価値はゼロになる」といわれることが多いです。
築年数の古い建物の場合、そのまま貸し出すのではなく、リフォーム・リノベーションを施したり、一度解体して建物を建て替えてから貸し出したほうが収益化が見込みやすいです。
【方法2】リフォームしてから貸し出す
そのままの状態では入居者が見つかりそうにない建物であれば、リフォームしてから賃貸に出す方法もあります。
例えばアパートやマンションの場合なら、オートロック設備を付けるだけで女性からの需要が高まるため、入居者が集まりやすくなり賃料も高めに設定できるでしょう。
空き家をリフォーム・リノベーションする場合にかかる費用相場は以下のとおりです。
リフォーム・リノベーション費用の相場
| 方法 |
費用相場 |
| 全面リフォーム |
約150万円~約500万円 |
| リノベーション |
約250万円~約1,200万円 |
建て替えよりも費用をかけずに、建物の価値を高められるため「1000万円単位の高額な費用は出せないが、安定した賃貸経営をしたい」という人におすすめです。
メリット:初期費用が安く抑えられる
建物が少し傷んでいるが手を加えれば利用できる状態であれば、必要最低限のリフォームを施すだけで十分活用できます。
いったん建物を解体してから建て替える場合に比べて、リフォーム・リノベーションであれば、約30%~50%も初期費用を抑えて賃貸経営を始められます。
また建物のリフォームやリノベーションに対して補助金を受け取れる場合もあるため、どのような精度が利用できるか調べて、費用の負担を抑えるとよいでしょう。
デメリット:新築に比べると空室リスクは高い
リフォーム・リノベーションを施すことで建物の景観や設備を魅力的にできますが、やはり新築に比べると見劣りしてしまう点は否めません。
そのため、新築の賃貸物件ほどの入居率は期待できず、ある程度の空室リスクを抱えており、賃料も安く設定せざるを得ないケースが多いです。
せっかく費用をかけてリフォーム・リノベーションしても、その費用に見合う家賃収入を得られなければ赤字になってしまいます。
【方法3】建物を解体してから土地活用する
相続した建物を活かした形での活用が難しい場合、いったん建物を解体してしまうのも1つの方法です。
需要の少ない建物で賃貸経営を続けても、満足いく収益が得られず、固定資産税・都市計画税をはじめ、管理コストも含めると赤字続きになってしまいます。
そうした場合、割り切って現状の建物を解体してしまったほうが、土地として別の用途などに活用しやすいです。
建物の築年数が古い場合、自治体によっては解体費用の助成金も受け取れるため、どのような制度が利用できるか調べておくとよいでしょう。
参照:「補助金等一覧」(東京都住宅政策本部)
メリット:活用方法の選択肢が広がる
建物がなくなって更地になれば、賃貸経営だけでない活用方法にも選択肢が広がります。
詳しくは後述しますが、駐車場として貸し出したり、新しくアパートやマンションを建てて賃貸経営を始めることも可能です。
また相続した不動産を貸し出すのではなく売却する場合も、建物がある土地より更地のほうが買主が集まりやすいです。
デメリット:建物の解体費用がかかる
建物がある土地を更地にするには、解体業者へ依頼して建物を取り壊してもらわなければなりません。
建物を取り壊す際にかかる解体費用の相場は次のとおりです。
建物の解体費用の相場
| 構造 |
解体費用 |
| 木造 |
3万~5万円/坪 |
| 鉄骨造 |
4万~6万円/坪 |
| 鉄筋コンクリート造 |
6万~8万円/坪 |
解体費用をかけてまで更地にするメリットを感じない場合、現状のままで買取してくれる不動産買取業者へ売却しましょう。
当サイトを運営する不動産買取業者「クランピーリアルエステート」では、建物が残っている土地でも現状そのままで買取可能です。
建物や土地の状態をヒアリングして買取価格をお伝えしますので、解体を検討する前にまずは無料査定へお問合せください。
建物の状態によっては更地よりも高額買取できるケースもございます。以下のボタンからお気軽にご相談ください。
最短48時間のスピード買取で
不動産を現金化
「高く・早く・トラブルなく」
売却したいなら
訳あり物件買取専門の
当社にお任せください!
相続した土地の活用方法
つづいて、相続した不動産が土地だった場合や、相続した建物を更地にした後の活用方法を解説します。
相続した土地の活用方法として、次の4種類が挙げられます。
- 借地権を設定して貸し出す
- 駐車場にして貸し出す
- トランクルームを建てて貸し出す
- アパートやマンションを建築して賃貸経営する
借地権を設定したり、駐車場にする場合であれば、土地に手を加えずそのままの状態で第三者へ貸し出すことが可能です。
またコンテナを設置してトランクルームとして貸し出したり、アパートやマンションを建設して賃貸経営をおこなうこともできます。
相続した土地の活用方法について、それぞれのメリット・デメリットをみていきましょう。
1.借地権を設定して貸し出す
1つ目の活用方法は、借地権を設定して土地そのものを貸し出す方法です。
借地権とは、建物の所有を目的に土地を借りる権利のことで、これを設定することで借地人は土地に建物を建築して、居住用や事業用などさまざまな用途で利用できます。
土地の貸主は、借地人から「地代」を受け取ることができるため、地代の金額が固定資産税などを上回っていれば、採算としてはプラスになります。
メリット:一定期間は確実に地代が得られる
借地権を設定して土地を貸し出す場合、最低でも10年以上の契約となります。
例えば定期借地権の地代は、土地の固定資産税評価額の5~8%程度になりますが、こうした地代を契約期間内は確実に得ることができます。
一般的な賃貸借契約と異なり、10年単位での契約が多いため、長期的な地代収入が保証されることがメリットといえます。
デメリット:一定期間は土地を利用できない
ただし、借地権を設定する際は、貸し出した土地を半永久的に取り戻せない恐れもあるため、契約の種類に注意しましょう。
普通借地権の場合、契約期間が終了しても正当事由がない場合、借地人の希望で契約更新できるため、一旦契約してしまうと解約がむずかしく、半永久的に土地を利用できない恐れもあります。
一方で定期借地権であれば、契約期間をもって確実に契約が終了するため、土地を取り戻すことができます。
土地を貸し出す場合は「将来的に土地が必要になるか?」という点まで考慮して、自分にあった種類の借地権を契約しましょう。
2.駐車場にして貸し出す
2つ目の土地活用の方法は、更地にした土地を駐車場として貸し出す方法です。
駐車場経営には「月極駐車場」と「コインパーキング」の2種類がありますが、いずれもローコスト・ローリスクな土地活用の方法といわれています。
月極駐車場であれば、毎月定まった安定収入を得ることができますし、コインパーキングは利用されるほど料金を受け取れるため、月極駐車場より儲かる可能性もあります。
メリット:初期費用を安く抑えられる
駐車場であれば、居住用のような建物を建築するわけではないので、比較的少ない資金で経営できます。
基本的には、更地に砂利を敷いたり、アスファルト舗装を施すだけで駐車場経営を始められます。
駐車場には借地借家法の適用もないので、土地を別の目的で利用したくなったときに対応しやすい点もメリットといえます。
デメリット:利用率が低いと赤字化してしまう
駐車場も低コストで開業できるとはいえ、利用者が少ないと固定資産税・都市計画税に見合う収益を得られずに赤字化してしまいます。
そのため、綿密な市場調査をおこない、どのような形式で駐車場を経営するか慎重に検討しましょう。
例えば相続した土地が住宅地にあれば、家に駐車場がない近隣住民が利用してくれる可能性が高いため、月極駐車場を経営することをおすすめします。
一方、以下のような地域であれば、コインパーキングの利用率が高く収益化が見込みやすいです。
3.トランクルームを設置して貸し出す
3つ目の土地活用の方法は、コンテナを設置してトランクルームとして貸し出す方法です。
トランクルームとは、いわゆる倉庫や物置のことで、自宅に物を置くスペースがない利用者が荷物置き場として借りてくれます。
トランクルームは、コンテナなどを設置して、内部をパーテーションなどによって区切り、利用者ごとのスペースを作るだけで貸し出せます。
メリット:狭い土地でも貸し出し可能
トランクルームであれば、建物を建築したり、駐車場として車を止められないような狭い土地でも活用可能です。
騒音がある場所、狭い土地、陽当たりの悪い場所など、居住用としては難がある土地でも、トランクルームであれば問題なく設置することができます。
また借地借家法の影響を受けないため、トランクルーム経営を取りやめて、他の活用方法へ移行しやすい点もメリットといえます。
デメリット:管理や集客に手間がかかる
トランクルームの場合も手放しで運営できるわけではなく、やはり管理や集客が必要になります。
アパートやマンションに比べれば管理が楽ですが、例えばトランクルームに不具合が発生した場合はすぐに修繕しなければいけません。
また賃貸経営や駐車場経営と同様に集客もおこなわなければならないため、多少なりとも手間がかかることは理解しておきましょう。
4.アパートやマンションを建築して賃貸経営する
4つ目の土地活用の方法は、新築のアパートやマンションを建築して賃貸経営する方法です。
アパートとマンション、それぞれの方法に次のようなメリットがあります。
アパートとマンションの違い
| アパート |
建設費用を抑えて賃貸経営をスタートできる |
| マンション |
堅牢な構造なので長期的な賃貸経営ができる |
いずれの方法でも、築年数の古い賃貸物件に比べて人気が高いため、入居者が集まりやすく、相場より高く家賃を設定しても空室が生まれにくいです。
一方でアパートやマンションを建てるための初期費用が高いため、1つでも空室が生まれてしまうと赤字になりやすいです。
メリット:入居率も高く収益を生みやすい
アパートやマンションで賃貸経営をおこなう場合、部屋の数だけ入居者から家賃を受け取ることが可能です。
1戸あたりの家賃を高く設定しなくても、アパートやマンションの部屋がすべて入居者が集まれば相当な収益になります。
また、一般的な賃貸契約であれば2年は家賃収入が得られますし、入居者によっては再び契約更新をして住み続けてくれるので、安定した家賃収入を得ることができるでしょう。
デメリット:初期費用のせいで赤字化しやすい
アパート・マンションを建設して賃貸経営をおこなう場合、多額の費用をかけて建設した以上、空室リスクには細心の注意を払う必要があります。
アパート・マンションの建設費用の相場は以下のとおりです。
アパート・マンション建設費用の相場
| 構造 |
建設費用 |
| 木造 |
70万円~90万円/坪 |
| 鉄骨造 |
80万円~100万円/坪 |
| 壁式プレキャストコンクリート造 |
90万円~100万円/坪 |
| 鉄筋コンクリート造 |
90万円~120万円/坪 |
空室が生まれると、その分の家賃収入を得られないため、高額な初期費用を回収できずに賃貸経営が赤字となってしまいます。
アパート・マンションに入居者が集まらない場合、賃料を下げることで空室を解消して、可能な限り赤字を抑えましょう。
リスクを抑えるなら相続した不動産を売却するのがベスト
ここまで相続した建物の活用方法とメリット・デメリットを一挙解説してきました。
どの活用方法にもメリットとデメリットがあるため、毎年かかる税金や運用コストに見合う収益が得られないと赤字化してしまうリスクもあります。
こうしたリスクを抑えたい場合、相続した不動産を売却するのがベストな活用方法です。
とはいえ、売却先を誤るとなかなか買主が見つからず、不動産が売れ残ってしまう恐れもあるため注意が必要です。
この項目では、相続した不動産を早く・確実に売却する方法を解説します。
売却できれば確実にまとまったお金が手に入る
ここまで解説した不動産の活用方法は、基本的に「不動産を貸し出す」ものでした。
不動産を貸し出す場合、得られる利益は毎月の家賃収入のように少額ずつしか手に入らず、借主が見つからないとまったく利益を得られないリスクもあります。
また「いつ借主がいなくなるか心配・・・」といった精神的ストレスも大きいです。
一方で不動産を売却する場合、利益を得られる機会は売却時の1度きりですが、まとまったお金が確実に手に入るというメリットがあります。
わかりやすくいうと、数百万円〜数千万円もの大金がすぐ手に入る訳です。
もちろん買主が見つからないと不動産を売却できないので「どうやって買主を見つけるか?」がポイントになります。
仲介業者だと買主が見つからず売れ残る恐れがある
不動産を売却する場合「仲介業者」を介して一般の買主へ売却する方法と「買取業者」に直接買取してもらう方法の2種類があります。
不動産業者の違い
| 仲介業者 |
売主の不動産を購入してくれる第三者を探す |
| 買取業者 |
売主の不動産を自社で買取する |
このうち「仲介業者」を介して売却する場合、買主が見つからずに不動産が売れ残ってしまうリスクがあるため注意しましょう。
買取業者なら自社で買取するので売れ残るリスクは低い
買主が見つからずに売れ残ってしまうリスクを避けたい場合、相続した不動産を買取業者に買取してもらいましょう。
買取業者であれば自社で買取するので、わざわざ一般の買主を探す必要がないため、手間や時間がかからない上に売れ残るリスクも低いです。
そのため、買取業者の査定を受けて価格や条件に納得すれば、最短数日で不動産をまとまったお金に変えることができます。
訳あり物件も扱う当社であれば他社で断られた物件も買取可能!
買取業者の査定を受けた結果、必ずしも買取してもらえるとは限りません。
大手不動産業者などの場合、次のような「訳あり物件」は法律的な扱いがむずかしいため、買取拒否されたり安く買い叩かれてしまうケースも多いです。
- 道路に面していない家などの「再建築不可物件」
- 建物内で両親が衰弱死した場合などの「孤独死物件」
- 兄弟など複数人で不動産を相続した際の「共有持分」
弁護士と提携している「訳あり物件専門の買取業者」なら、上記のように他社で買取拒否された物件も買取可能です。
当サイトを運営する「クランピーリアルエステート」も弁護士と提携した買取業者として、相続後の使い道に困った不動産を数多く買取してきた実績がございます。
「まだ不動産を手放すか迷っている」という人も、とりあえず話を聞いてみる感覚でお気軽にご相談ください。
売却を迷っている不動産や相続前の不動産でもご相談ください!
最短48時間のスピード買取で
不動産を現金化
「高く・早く・トラブルなく」
売却したいなら
訳あり物件買取専門の
当社にお任せください!
まとめ
この記事では、相続した不動産の活用方法とメリット・デメリットを解説しました。
どの活用方法にもメリットとデメリットがあり、毎年かかる税金や運用コストに見合う収益が得られず赤字化してしまうリスクもあります。
継続的に運用していくリスクを避けたい場合、相続した不動産の売却をおすすめします。
ただし、建物が老朽化していたり立地が悪いと需要が少ないため、不動産を売りに出しても買主が見つからずにいつまでも売れ残ってしまうリスクもあります。
無駄な税金を払わず、すぐ確実に不動産を活用したい場合、相続した不動産を不動産買取業者に買い取ってもらいましょう。
相続した不動産に関するよくある質問
相続した不動産をそのままにしてはダメですか?
固定資産税を支払わなければならず、空き家に指定されて行政指導を受ける恐れもあるため、相続した不動産は放置しないほうがよいでしょう。
相続した不動産を放置するリスクは何ですか?
固定資産税や都市計画税が毎年かかり続ける上、建物の場合は空き家にすると老朽化が進んでしまい、土地の場合は固定資産税の負担が大きくなるといったリスクがあります。
相続した建物はどのように活用できますか?
建物をそのまま貸し出したり、リフォーム・リノベーションを施してから貸し出す、建物を解体して更地にしてから土地活用するといった方法があります。
相続した土地はどのように活用できますか?
借地権を設定して貸し出したり、駐車場・トランクルームをして貸し出す、アパートやマンションを建築して賃貸経営するといった方法があります。
相続した不動産を活用できない場合、どうすればよいですか?
相続した不動産を買取業者に売却すれば、すぐにまとまったお金に変えることができます。
訳あり不動産の売却でお悩みなら
今すぐご連絡ください
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-