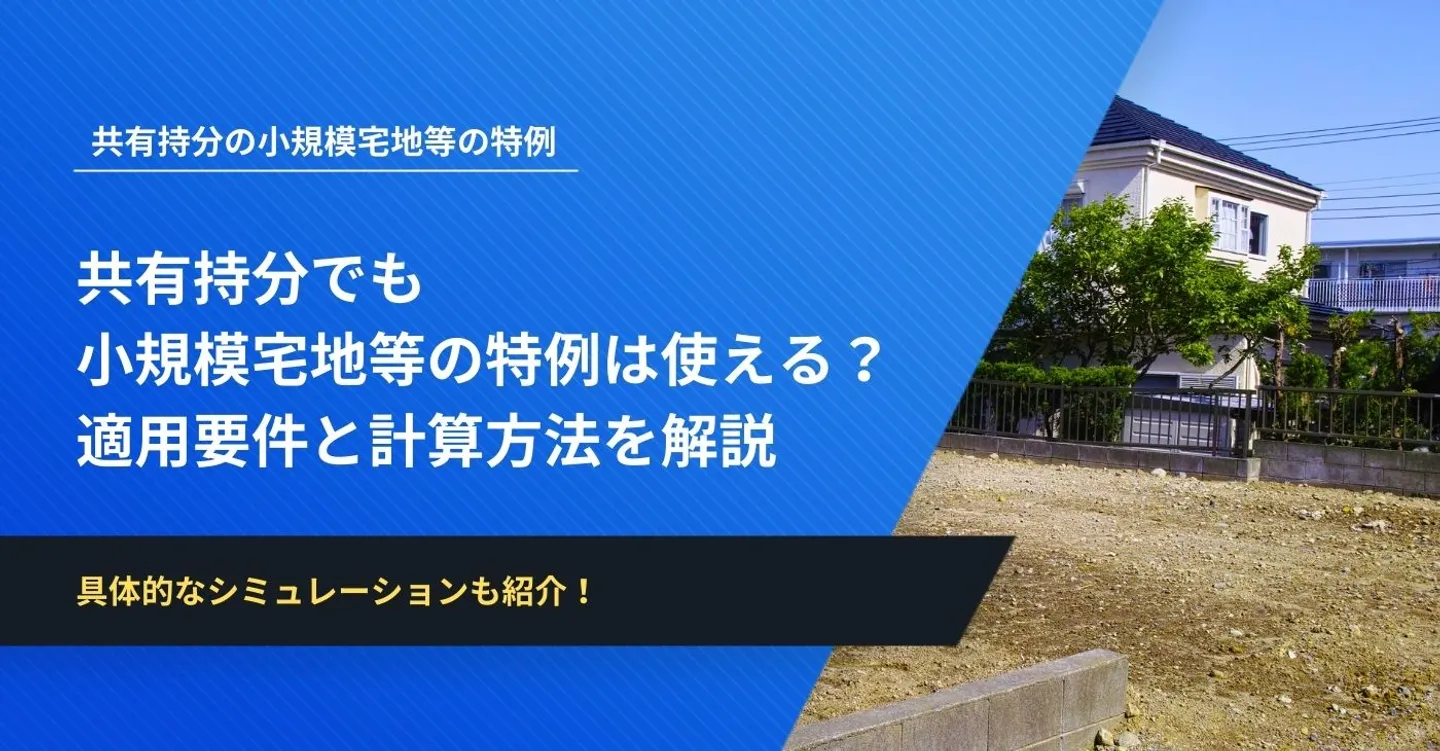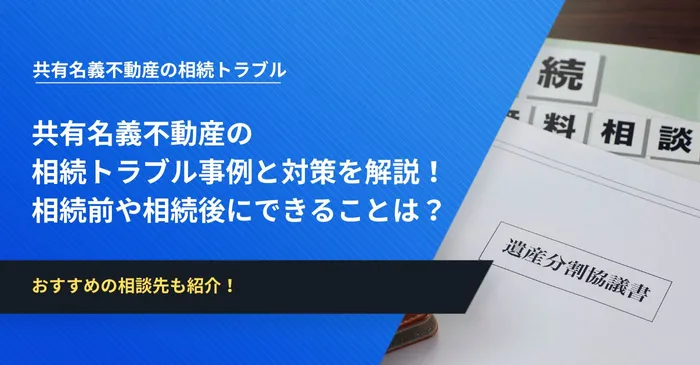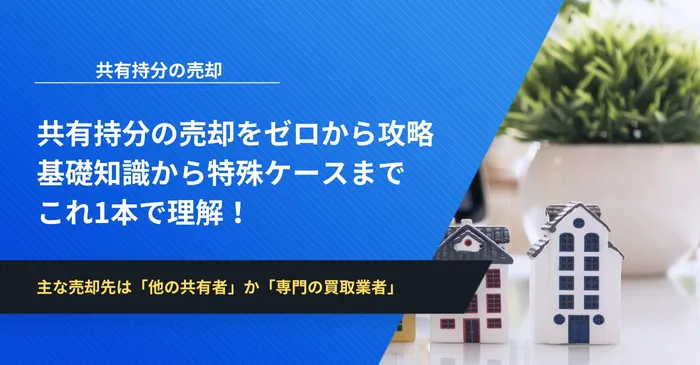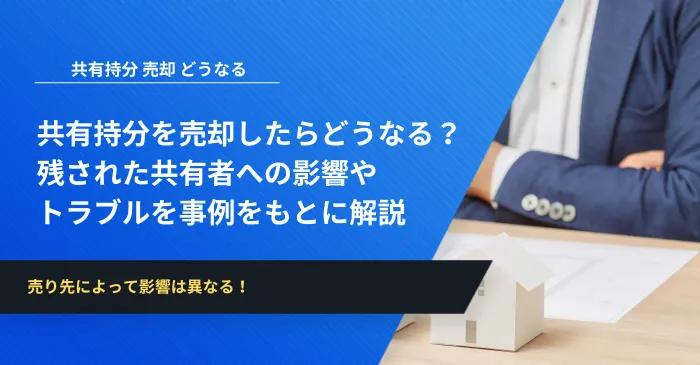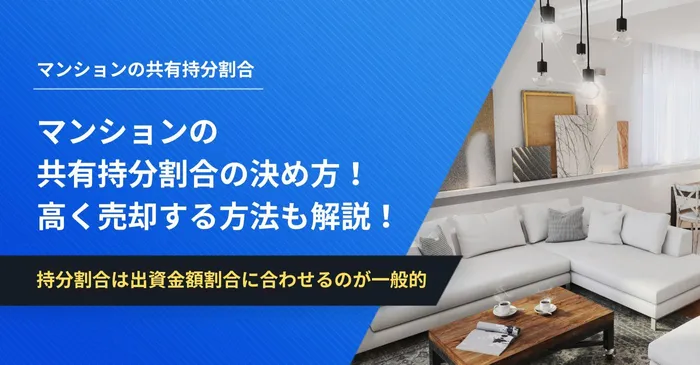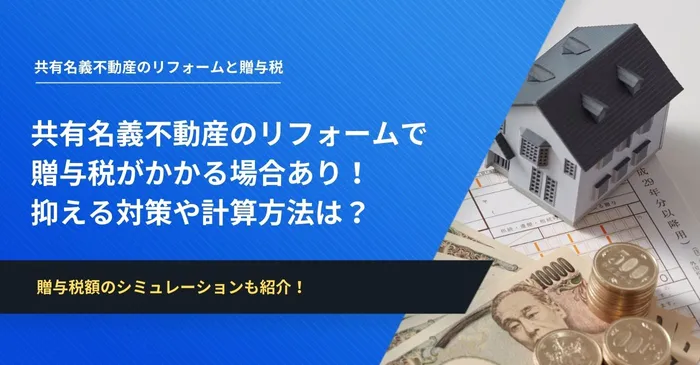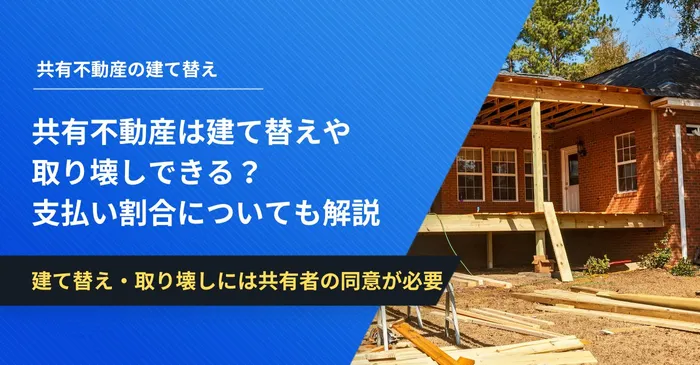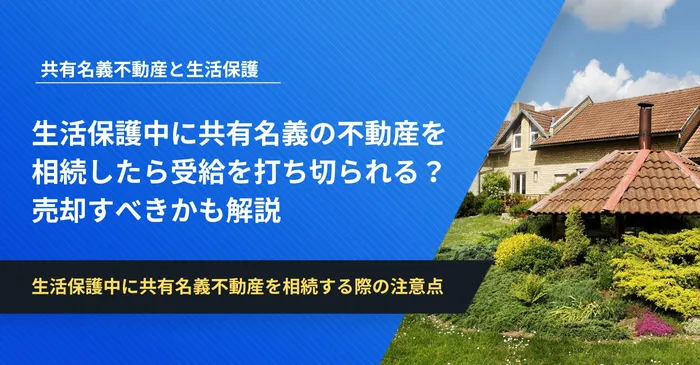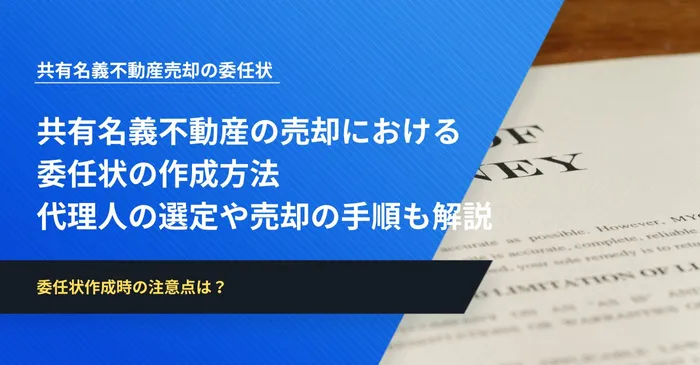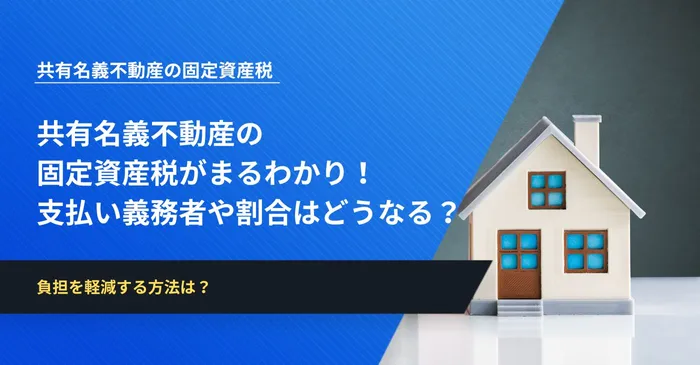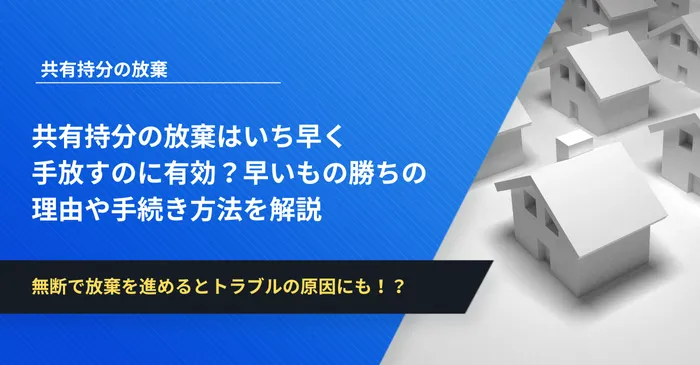共有持分の土地でも「小規模宅地等の特例」は適用要件を満たせば利用できる
共有持分の土地であっても、要件さえ満たせば、「小規模宅地等の特例」の適用を受けられます。
小規模宅地等の特例とは、相続した土地の相続税評価額を一定割合で減額し、相続人の相続税負担を軽くする制度です。敷地権を含む「土地」が対象であり、建物そのものの評価額は減額の対象になりません。
対象者は、土地を相続または遺贈で取得した人ですが、取得した人であれば誰でも使える制度ではなく、取得者が用途区分ごとに定められた要件を満たすことが適用を受ける前提です。配偶者は対象となりやすい一方、配偶者以外の親族が対象となるには、下記の条件を満たす必要があります。
- 相続開始直前に、被相続人と同居していたこと
- 相続開始後、相続税の申告期限まで当該宅地等に居住し続けること
- 相続で取得した当該宅地等(土地の持分)を、相続税の申告期限まで引き続き保有すること
なお、被相続人と同居していなかった親族でも、一定の条件を満たせば、例外としていわゆる「家なき子」の要件により特例の対象となることがあります。一定の条件とは、下記の3点です。
- 相続開始前3年以内に本人・配偶者・三親等内の親族などが所有する家屋に居住していないこと
- 相続開始時に居住している家屋を本人が過去に所有したことがないこと
- 取得した宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで引き続き保有していること
対象となる土地は、居住用・事業用・賃貸用の3つの用途区分に分かれており、それぞれ特例を適用できる面積の上限(限度面積)と減額割合が定められています。
|
区分
|
主な対象
|
限度面積
|
減額割合
|
|
特定居住用宅地等
|
被相続人等の居住用
|
330㎡
|
80%
|
|
特定事業用宅地等
|
被相続人等の事業用
|
400㎡
|
80%
|
|
特定同族会社事業用宅地等
|
同族会社の事業用
|
400㎡
|
80%
|
|
貸付事業用宅地等
|
賃貸用
|
200㎡
|
50%
|
参考:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
」
注意したいのが、小規模宅地等の特例は、土地全体に一律で適用される制度ではないという点です。共有名義の土地では、まず土地全体の相続税評価額を路線価方式や倍率方式で算出しますが、特例で減額の対象になるのは、その土地全体ではなく「被相続人が所有していた持分に対応する部分」に限られます。
ただし、共有名義の土地では、被相続人の持分に対応する部分だけを見ても、特例の適用の可否と減額の範囲は確定しません。小規模宅地等の特例は、相続税評価額の算定方法を変更する制度ではなく、算出した相続税評価額に対して、要件を満たす範囲に限って減額を適用する制度です。「誰がその持分を取得したのか」と「その持分部分がどの用途として使われていたのか」によって、適用の可否と減額できる範囲が変わるのです。
以下では、複数の相続人がいる場合に取得者ごとに適用可否を判定するルールと、土地の利用状況が混在している場合に用途ごとに対象となる面積の範囲を決めるルールを、それぞれ分けて解説します。
複数の相続人がいる場合は「取得者ごと」に適用可否を判定する
小規模宅地等の特例は、土地全体に一律で付く制度ではなく、「その土地を取得した相続人が要件を満たしているか」によって、「特例が使えるか使えないか」と「使える場合にどの範囲まで減額できるか」が決まります。そのため、同じ土地を共有で相続した場合でも、相続人全員がそろって特例を使えるとは限りません。要件を満たす相続人の取得分には特例が適用され、要件を満たさない相続人の取得分には特例が適用されない、というように結論が分かれることがあります。
ここでいう「取得分」とは、共有で相続したときに各相続人が取得した持分割合に対応する部分を指します。例えば、配偶者と子が土地を1/2ずつ共有で相続した場合、配偶者の取得分と子の取得分は別々に扱い、配偶者が要件を満たすか、子が要件を満たすかをそれぞれ確認します。
配偶者と子が共有で相続したケースでは、配偶者は原則として特例を適用できる一方、子が特例を使うには、被相続人と同居していたかなど、子に求められる要件を満たす必要があります。子が要件を満たさない場合、子の取得分には特例が適用されません。なお、要件を満たさず、適用を受けられない相続人がいても、要件をみたした相続人には特例が適用されます。
共有者の利用状況が異なる場合は「適用対象となる面積」が制限される
共有名義の土地では、共有者それぞれの利用状況が同じとは限りません。例えば、同じ土地の中でも、被相続人は居住用として使っていた一方で、ほかの共有者は賃貸用や事業用として使っていたというケースも起こり得ます。
小規模宅地等の特例は、土地全体を一括で同じ区分として扱う制度ではありません。土地の利用状況が混在している場合は、居住用・事業用・賃貸用といった用途ごとに、どの面積がどの用途に当たるかを整理したうえで、用途区分ごとに特例を適用します。
結果として、特例の対象となる面積は、単純に被相続人の持分面積だけでは決まらず、利用区分に応じた按分(割合に応じて分けること)が必要になることがあります。
【用途が混在する場合の持分面積の按分の例】
例えば、500㎡の土地を被相続人とほかの共有者が50%ずつ所有していた場合、被相続人の持分に対応する面積は500㎡×50%=250㎡。
この被相続人の持分250㎡の利用状況が「居住用30%:賃貸用70%」だった場合は、下記のように居住用と賃貸用に面積を分けて考えることになる。
居住用の持分面積:250㎡×30%=75㎡
賃貸用の持分面積:250㎡×70%=175㎡
実際に、相続する土地の相続税評価額を算出する場合には、上記のようにまず用途ごとに面積を分けたうえで、それぞれの用途に対応する評価額を算出します。各土地の評価額に対して、居住用は80%減額、賃貸用は50%減額というように、用途区分ごとに定められた減額割合を適用していきます。
なお、複数の用途区分を併用する場合、それぞれの限度面積を単純に合算できるわけではなく、特定の計算式による面積の調整が必要になる点に注意しましょう。
共有名義の土地に小規模宅地等の特例を適用する際の計算方法
それでは、共有名義の土地に小規模宅地等の特例を適用する際の計算方法を見ていきましょう。
計算の流れは大きく3段階です。
①土地全体の地積に被相続人の持分割合を掛けて、特例の適用対象となる面積を出す
②その面積をもとに路線価方式または倍率方式で相続税評価額を算出する
③用途区分に応じた減額割合を評価額に適用して減額金額と課税対象となる評価額を求める。
なお、本章でお伝えする計算方法は、あくまで一般的な計算のイメージとして捉えてください。
小規模宅地等の特例は、相続税申告で特例の適用を記載した申告書を提出し、その申告内容や添付書類にもとづいて税務署が要件充足を確認します。「要件を満たしていない」「根拠資料が不足している」などと判断された場合は、特例の適用が認められず、想定していた減額が受けられないこともあります。
小規模宅地等の特例の計算は複雑で、専門的な知識を必要とするため、相続に強い税理士に相談することをおすすめします。
①特例の適用対象となる土地の面積(㎡):全体の地積×(被相続人の)持分割合
共有名義の土地で小規模宅地等の特例を適用する前提で計算する場合、最初に行うのは「特例の適用対象となる面積」を出す作業です。特例の対象になるのは、土地全体ではなく、被相続人が所有していた持分に対応する面積に限られます。そこで、土地全体の地積(㎡)に被相続人の持分割合を掛けて、適用対象面積を算出します。
【特例の適用対象となる面積の出し方】
適用対象面積=全体の地積(㎡)×被相続人の持分割合
例えば、300㎡の土地を被相続人が3分の2、配偶者が3分の1の持分で共有していた場合。小規模宅地等の特例の適用対象となる面積は、土地全体の地積300㎡に被相続人の持分割合2/3を掛けて算出します。計算すると、300㎡×2/3=200㎡となり、特例の適用対象面積は200㎡です。
②土地の相続税評価額:適用対象となる土地の面積(㎡)×各種補正率×路線価
①の「特例の適用対象となる面積(㎡)」が出たら、次に、その面積に対応する土地の相続税評価額を算出します。土地の相続税評価額は、路線価が設定されている地域であれば、一般に「路線価方式」で計算します。
【路線価方式の計算式】
相続税評価額=適用対象面積(㎡)×路線価×各種補正率(奥行価格補正率など)
実際には、土地の形状や接道状況などに応じて補正率の種類が複数あり、条件によって計算が細かく分かれます。この章では「適用対象面積に、路線価と補正率を掛けて評価額を出す」という全体像を押さえてください。
なお、路線価は国税庁「路線価図」で確認できます。
■路線価と路線価方式は?
路線価とは、相続税や贈与税で土地を評価するために国税庁が定める、道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額。土地の相続税評価額を算定する際の基準となる単価として用いられる。路線価方式は、路線価を用いて土地の相続税評価額を算定する方法。
路線価が設定されていない地域:固定資産税評価額×持分割合×倍率
路線価が設定されていない地域では、路線価方式ではなく「倍率方式」で土地の相続税評価額を算出します。倍率方式は、固定資産税評価額を基準にして評価額を求める方法で、共有名義の土地であれば被相続人の持分割合も掛け合わせて、被相続人持分に対応する評価額を計算することになります。
【倍率方式の計算式】
相続税評価額=固定資産税評価額×持分割合×倍率
倍率は、国税庁「評価倍率表」で確認できます。固定資産税評価額は、市区町村から毎年4〜5月頃に届く「固定資産課税明細書」のほか、市区町村の固定資産税担当窓口で取得できる「固定資産評価証明書」や「固定資産課税台帳」などでも確認できます。
③小規模宅地等の特例による減額金額(特定居住用宅地等に該当する場合):土地の相続税評価額×80%
①で適用対象面積を出し、②でその部分の相続税評価額を算出したら、最後に小規模宅地等の特例による「減額金額」を計算します。
【減額金額の計算式(特定居住用宅地等に該当する場合)】
減額金額=土地の相続税評価額×80%
減額後に課税対象となる評価額は、算出した相続税評価額から減額金額を差し引いて求めます。
【課税対象となる評価額の計算式】
課税対象となる評価額=土地の相続税評価額-減額金額
例えば、土地の相続税評価額が4,000万円の場合、減額金額は「4,000万円×80%=3,200万円」で、「課税対象となる評価額」は4,000万円-3,200万円=800万円となります。
二世帯住宅の共有は「登記の種類」で適用の可否が決まる
二世帯住宅の敷地に小規模宅地等の特例を適用する場合は、同じ家に住んでいたかどうかといった生活実態だけでは、「特例を適用できるか」と「敷地のどこまでが減額の対象になるか」を判断できません。建物が登記上どのように区分されているかによって、「どの部分の敷地を居住用として扱うのか」や「親族を同居親族として扱うのか」の考え方が変わるためです。
実務上、二世帯住宅の登記は「区分所有登記」と「共有登記」の2つに分けて考えると理解しやすく、どちらに当たるかで、特例の対象となり得る敷地の扱いが大きく変わります。
以下では、登記の種類ごとに、特例の扱いがどう違うのかを順に解説します。
「区分所有登記」だと特例が使えない可能性が高い
区分所有登記の二世帯住宅は、小規模宅地等の特例を適用できないケースが多い登記形態です。区分所有登記とは、二世帯住宅の1階・2階などの各世帯部分を、それぞれ独立した区分として登記する方法を指します。
区分所有登記では、土地の権利が建物全体に一括で付くのではなく、各住戸にセットになっているのが一般的です。したがって、小規模宅地等の特例の適用可否を判断する対象になるのは、二世帯住宅が建っている土地全体ではなく、被相続人の住戸にひも付いていた土地の権利の部分に限られます。
また、小規模宅地等の特例は「土地を取得した人が要件を満たすか」で適用の可否が決まるため、取得者が配偶者ではなく子などの場合、同居要件を満たせないことが珍しくありません。区分所有登記の二世帯住宅だと、たとえ実態としては同じ建物で同居していたとしても、登記上は別の住戸に居住していた扱いとなり、同居親族としての判定で不利になりやすいためです。
つまり、区分所有登記の二世帯住宅では、特例の対象が被相続人が持っていた土地の持分に限られることに加え、取得者が配偶者以外だと同居要件を満たせないケースが多いことから、小規模宅地等の特例が適用できない可能性が高いのです。
なお、区分所有登記でも、相続する区分と取得者の要件が噛み合えば、特例が適用される余地があります。
【区分所有登記でも特例が適用できる可能性がある例】
・例1:配偶者が、被相続人が住んでいた住戸と、その住戸にひも付く土地の権利を相続する場合。配偶者が取得者としての要件を満たす限り、特例の対象になり得る
・例2:被相続人と同居していた子が、被相続人が住んでいた住戸と、その住戸にひも付く土地の権利を相続する場合。子が同居親族としての要件を満たす限り、特例の対象になり得る
「共有登記」であれば二世帯住宅でも特例を適用しやすい
共有登記の二世帯住宅は、区分所有登記に比べて小規模宅地等の特例の適用を受けやすい登記形態です。共有登記とは、二世帯住宅全体を法的に一つの住戸として登記し、親子など複数人で所有権の割合(持分)を決めて共有する方法を指します。
共有登記のポイントは、親世帯・子世帯で生活空間が分かれていても、登記上は建物全体が一つの住戸として扱われる点です。たとえ建物内で行き来ができない完全分離の構造であっても、登記上は同じ住戸に居住していたとして扱われるため、相続人が配偶者でも子でも同居親族として判定されやすくなります。
また、共有登記では敷地の権利が住戸ごとに切り分けられていないため、被相続人が居住していた建物の敷地は一体の居住用宅地等として扱われやすく、子世帯の居住部分を含めて敷地全体が小規模宅地等の特例の対象になります。
区分所有登記では、特例の対象が被相続人の住戸にひも付く土地の権利の部分に限られやすい一方、共有登記では敷地を建物全体を居住用宅地として扱いやすく、減額の対象となる範囲が大きくなりやすい点が大きな違いです。
もちろん、小規模宅地等の特例は、登記の形態だけで決まる制度ではなく、取得者が配偶者や同居親族かといった基本的な要件をクリアする必要はあります。ただ、登記上一棟の住居として記録が残る共有登記は、区分所有登記よりも小規模宅地等の特例の適用を受けやすく、より大きい土地で相続税評価額の減額を受けられる可能性があるのです。
【共有登記でも特例が適用されない可能性がある例】
・例1:子が相続するが、相続開始直前に被相続人と同じ建物で同居していない場合。同居親族の要件を満たせず、特例が適用されないことがある。
・例2:同居している相続人が取得するが、相続開始後に当該建物から転居する場合。居住継続要件を満たせず、特例が適用されないことがある。
・例3:敷地の一部を明確に貸付用や事業用として使っている場合。住居用として使っていると認められる土地のみが特例の対象となる。
共有持分に「小規模宅地等の特例」を適用したシミュレーション
相続によって土地の共有持分を取得することを前提に、小規模宅地等の特例を適用した場合、相続税評価額がどの程度なのかをシミュレーションします。各シミュレーションでは、土地の面積や持分割合などの前提条件を明示したうえで、計算過程と評価額の差をまとめます。
以下は、当社が連携している税理士法人の協力を得て作成した「小規模宅地等の特例」に関するシミュレーションです。実際の相談事例をもとにしていますが、個人が特定されないよう、条件や数値を調整したうえで掲載しています。あくまで制度理解を目的としたシミュレーションであり、実際の相続では専門家による個別判断が必要となります。
夫婦で土地を共有していた場合
|
前提条件
|
・土地:被相続人2/3 配偶者1/3の共有
・建物:被相続人と配偶者で1/2ずつ共有
・敷地面積:300㎡
・評価額:6,000万円
・相続人:配偶者(土地の被相続人持分を単独相続)
|
|
計算
|
①特例の判定対象となる面積を確認する
敷地面積:300㎡
②相続で取得する評価額を算出する
6,000万円 × 被相続人の土地持分2/3 = 4,000万円
③限度面積に照らして、特例の対象範囲を確定する
敷地面積300㎡は居住用宅地等の限度面積(330㎡)以内のため、特例の対象は全額
④適用する特例と減額率を確定する
特定居住用宅地等として80%減額
⑤減額額を算出する
4,000万円 × 80% = 3,200万円
⑥特例適用後の評価額を算出する
4,000万円 - 3,200万円 = 800万円
|
本ケースでは、配偶者が相続で取得した土地の被相続人持分について、敷地面積が居住用宅地等の限度面積(330㎡)に収まっているため、80%減額が取得分の評価額にそのまま適用されます。
親子で土地を共有していた場合
|
前提条件
|
・土地:被相続人1/2 長男1/2の共有(生前から共有)
・建物:被相続人単独所有
・敷地面積:400㎡
・評価額:8,000万円
・相続人:長男(被相続人と同居/土地の被相続人持分を相続)
|
|
計算
|
①特例の判定対象となる面積を確認する
400㎡ × 被相続人の土地持分1/2 = 200㎡
②相続で取得する評価額を算出する
8,000万円 × 被相続人の土地持分1/2 = 4,000万円
③限度面積に照らして、特例の対象範囲を確定する
判定対象面積200㎡は居住用宅地等の限度面積(330㎡)以内のため、特例の対象は全額
④適用する特例と減額率を確定する
特定居住用宅地等として80%減額
⑤減額額を算出する
4,000万円 × 80% = 3,200万円
⑥特例適用後の評価額を算出する
4,000万円 - 3,200万円 = 800万円
|
本ケースでは、長男が相続で取得した土地の被相続人持分について、特例の判定対象となる面積が居住用宅地等の限度面積(330㎡)以内に収まっているため、80%減額が取得分の評価額にそのまま適用されます。
配偶者と子で土地を共有相続した場合
|
前提条件
|
・土地:被相続人の単独所有
・敷地面積:300㎡
・評価額:6,000万円
・相続人:配偶者・長男(土地を1/2ずつ相続/長男は被相続人と同居)
|
|
計算
|
①特例の判定対象となる面積を確認する
敷地面積:300㎡
②相続で取得する評価額を算出する
6,000万円 × 配偶者の取得持分1/2 = 3,000万円
6,000万円 × 長男の取得持分1/2 = 3,000万円
③限度面積に照らして、特例の対象範囲を確定する
敷地面積300㎡は居住用宅地等の限度面積(330㎡)以内のため、特例の対象は全額
④適用する特例と減額率を確定する
配偶者:特定居住用宅地等として80%減額
長男:特定居住用宅地等として80%減額
⑤減額額を算出する
配偶者:3,000万円 × 80% = 2,400万円
長男:3,000万円 × 80% = 2,400万円
⑥特例適用後の評価額を算出する
配偶者:3,000万円 - 2,400万円 = 600万円
長男:3,000万円 - 2,400万円 = 600万円
|
本ケースでは、配偶者と長男が相続で取得した土地の各持分について、敷地面積が居住用宅地等の限度面積(330㎡)に収まっているため、80%減額がそれぞれの取得分の評価額にそのまま適用されます。
生前から土地が共有で、さらに相続でも共有取得した場合
|
前提条件
|
・土地:被相続人1/2 配偶者1/2の共有(生前から共有)
・建物:被相続人の単独所有(配偶者がすべて相続)
・敷地面積:280㎡
・評価額:8,400万円
・相続人:配偶者・長女(土地の被相続人持分1/2を各1/4ずつ相続/長女は被相続人と別居・自己所有の持家あり)
|
|
計算
|
①取得者ごとの適用可否を判定する
配偶者:適用可
長女:家なき子要件を満たさず適用不可
②特例の判定対象となる面積を確認する
280㎡ × 被相続人の土地持分1/2 = 140㎡
③相続で取得する評価額を算出する
8,400万円 × 配偶者の取得持分1/4 = 2,100万円
8,400万円 × 長女の取得持分1/4 = 2,100万円
④限度面積に照らして、特例の対象範囲を確定する
判定対象面積140㎡は居住用宅地等の限度面積(330㎡)以内のため、適用できる取得者については特例の対象は全額
⑤適用する特例と減額率を確定する
配偶者:特定居住用宅地等として80%減額
長女:適用なし
⑥減額額を算出する
配偶者:2,100万円 × 80% = 1,680万円
長女:減額なし
⑦特例適用後の評価額を算出する
配偶者:2,100万円 - 1,680万円 = 420万円
長女:2,100万円
|
本ケースでは、同じ土地の被相続人持分を相続していても、配偶者は特例の適用対象となる一方で、長女は家なき子要件を満たさないため特例を適用できません。
居住用と事業用が混在する土地を共有相続した場合
|
前提条件
|
・土地:被相続人の単独所有
・建物:1階:被相続人が営む店舗(特定事業用)/2階:被相続人の居住用
・敷地面積:360㎡(店舗180㎡/居住用180㎡)
・相続人:配偶者・長男(土地・建物を各1/2ずつ共有で相続/長男は被相続人と別居・自宅あり/被相続人の事業は配偶者と長男が共同で承継)
|
|
計算
|
①取得者ごとの適用可否を判定する
配偶者:居住用は適用可、事業用は適用可
長男:事業用は適用可、居住用は家なき子要件を満たさず適用不可
②居住用と事業用の面積と評価額を切り分ける
面積:居住用180㎡、事業用180㎡
評価額:土地全体の評価額を6,000万円とし、面積按分で切り分ける
居住用の土地評価額:6,000万円 × 居住用面積180㎡ ÷ 敷地面積360㎡ = 3,000万円
事業用の土地評価額:6,000万円 × 事業用面積180㎡ ÷ 敷地面積360㎡ = 3,000万円
③特例の判定対象となる面積を確認する
居住用:180㎡
事業用:180㎡
④相続で取得する評価額を算出する
配偶者の居住用取得評価額:3,000万円 × 配偶者の取得持分1/2 = 1,500万円
配偶者の事業用取得評価額:3,000万円 × 配偶者の取得持分1/2 = 1,500万円
長男の居住用取得評価額:3,000万円 × 長男の取得持分1/2 = 1,500万円
長男の事業用取得評価額:3,000万円 × 長男の取得持分1/2 = 1,500万円
⑤限度面積に照らして、特例の対象範囲を確定する
居住用180㎡は居住用宅地等の限度面積(330㎡)以内のため、適用できる取得者については特例の対象は全額
事業用180㎡は事業用宅地等の限度面積の範囲内のため、適用できる取得者については特例の対象は全額
⑥適用する特例と減額率を確定する
配偶者:居住用は特定居住用宅地等として80%減額、事業用は特定事業用宅地等として80%減額
長男:事業用は特定事業用宅地等として80%減額、居住用は適用なし
⑦減額額を算出する
配偶者の居住用:1,500万円 × 80% = 1,200万円
配偶者の事業用:1,500万円 × 80% = 1,200万円
長男の事業用:1,500万円 × 80% = 1,200万円
長男の居住用:減額なし
⑧特例適用後の評価額を算出する
配偶者の居住用:1,500万円 - 1,200万円 = 300万円
配偶者の事業用:1,500万円 - 1,200万円 = 300万円
長男の事業用:1,500万円 - 1,200万円 = 300万円
長男の居住用:1,500万円
|
本ケースでは、居住用と事業用が同じ敷地内にあるため、最初に用途ごとに対象範囲を切り分けたうえで、取得者ごとに適用可否を判定する必要があります。
※本事例は居住用・事業用ともに限度面積の範囲内であるため、それぞれの持分に上限まで特例を適用していますが、面積が上限を超える場合は優先順位を考慮した調整計算が必要です。
配偶者は居住用・事業用の両方で特例を使える一方、長男は事業を承継しているため事業用は対象となりますが、居住用は別居かつ自宅が別にあるため、家なき子の要件を満たさず、特例の対象になりません。
このように相続人ごとに適用要件が異なるため、取得者ごとに判定が必要です。
区分所有登記された二世帯住宅の土地を共有相続した場合
|
前提条件
|
・土地:被相続人の単独所有
・建物:二世帯住宅(1階70㎡:長男家族が居住/2階70㎡:被相続人と配偶者が居住)
・建物の登記:区分所有登記(1階:長男名義/2階:被相続人名義)
・敷地面積:350㎡
・評価額:1億500万円
・相続人:配偶者・長男(土地を各1/2ずつ共有で相続)
|
|
計算
|
①特例の判定対象となる敷地を確定する
被相続人が居住していた2階部分に対応する敷地:175㎡相当
②取得者ごとの適用可否を判定する
配偶者:適用可(被相続人の居住区分に対応する敷地を相続で取得し、配偶者要件を満たす)
長男:適用不可(被相続人の居住区分に対応する敷地の持分は相続で取得するが、区分所有登記では1階居住は被相続人との同居と扱われにくい。さらに、長男は自己の居住区分を有しているため家なき子要件にも該当せず、取得者要件を満たさない)
③特例の判定対象となる面積を確認する
判定対象面積:175㎡
④相続で取得する評価額を算出する
判定対象となる敷地の評価額:1億500万円 × 被相続人居住区分に対応する敷地割合175/350 = 5,250万円
配偶者が相続で取得する評価額:5,250万円 × 配偶者の取得持分1/2 = 2,625万円
長男が相続で取得する評価額:5,250万円 × 長男の取得持分1/2 = 2,625万円
⑤限度面積に照らして、特例の対象範囲を確定する
判定対象面積175㎡は居住用宅地等の限度面積(330㎡)以内のため、適用できる取得者については特例の対象は全額
⑥適用する特例と減額率を確定する
配偶者:特定居住用宅地等として80%減額
長男:適用なし
⑦減額額を算出する
配偶者:2,625万円 × 80% = 2,100万円
長男:減額なし
⑧特例適用後の評価額を算出する
配偶者:2,625万円 - 2,100万円 = 525万円
長男:2,625万円
|
本ケースでは、建物が区分所有登記されているため、土地全体ではなく「被相続人が居住していた区分に対応する敷地」だけが特例の判定対象になります。
長男は被相続人の居住区分に対応する敷地の持分を取得しているものの、区分所有登記では1階居住が同居と扱われにくいうえ、1階部分を自分名義の住戸として所有しているので家なき子要件にも該当しません。結果として、取得者要件を満たさないため、特例を適用できません。
小規模宅地等の特例を使う際の注意点
小規模宅地等の特例を適用するには、相続人による所定の手続きが必要ですが、本来適用できる状況にありながら、対応の不備によって適用できなくなるケースがあります。想定していた減額が受けられないと、相続税額が大幅に変わります。
- 相続税がゼロになる場合でも、特例を使うなら相続税の申告が必要
- 相続税の申告期限(10ヶ月)までに土地を売却すると、特例の適用要件を満たさず、適用外になる
- 相続時精算課税制度で生前贈与を受けた宅地等には、原則として特例は適用されない
- 遺産分割協議が未了だと特例を適用できず、期限内にまとまらない場合は所定の手続きが必要
以下では、小規模宅地等の特例の適用可否が変わるポイントを解説します。
小規模宅地等の特例の利用には相続税の申告が必要
小規模宅地等の特例を適用するためには、相続人が「相続税の申告(相続税の申告書の提出)」を行う必要があります。提出先は、被相続人(亡くなった人)の死亡時の住所地を管轄する税務署です。申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内であり、期限までに申告手続きを完了させなければなりません。
小規模宅地等の特例は、算出した相続税評価額に対して、要件を満たす範囲に限り減額を適用する制度であるため、申告書で「どの土地に」「どの用途区分で」「誰の取得分に」特例を適用するのかを明確にし、税務署が要件に適合しているかを確認できる状態にしておく必要があります。
また、特例を適用した結果、相続税がゼロになる場合でも申告は必要です。相続税が0円になる場合でも、特例を適用する以上、申告手続き自体を省略することはできません。
小規模宅地等の特例の適応を受けたい場合は、相続税の申告が必要になる点を最初に押さえておく必要があります。
相続税の申告期限(10ヶ月)までに売却すると適用外になる
小規模宅地等の特例の適用要件には、「宅地等を相続税の申告期限(10ヶ月)まで保有し続けること」が含まれます。申告期限前に土地を売却すると、特例の適用要件を満たさなくなり、特例を適用できません。結果として、想定していた減額が受けられず、相続税額が想定より増えるおそれがあります。
土地の売却を検討している場合は、申告期限(10ヶ月)後に売却するなど、スケジュールを調整する必要があります。申告期限より前に売却せざるを得ない事情がある場合は、特例を使わない前提で相続税額がどう変わるかを含めて、早い段階で専門家に確認しておくことが重要です。
相続時精算課税制度によって贈与を受けた宅地等には適用されない
相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けた土地には、小規模宅地等の特例は適用されません。そもそも小規模宅地等の特例は、相続や遺贈によって取得した土地が対象であり、取得の経緯が生前贈与である場合は、特例の対象外となります。
しかし、相続時精算課税制度は、生前贈与で取得した財産を、贈与者の死亡時に相続税の計算へ反映させて精算する仕組みです。「贈与された土地の価額が相続税の計算に含まれるなら、小規模宅地等の特例も適用できるのでは?」と勘違いされることがよくあります。
実際には、相続時精算課税制度を使った場合、贈与者が亡くなったときに、贈与を受けた土地(贈与時点の相続税評価額)を相続税の課税価格に加算して、相続税を計算します。ただし、土地の取得はあくまで生前贈与であり、相続や遺贈で取得した土地ではないため、小規模宅地等の特例は適用できません。
生前贈与と相続のどちらが節税になるかは、土地の利用区分・相続人の状況・他の財産などによって変わります。生前贈与時に相続時精算課税を選ぶと、原則として後から変更できないため、将来的な相続と相続税の計算も含めて税理士に相談し、前提条件を確認したうえで判断することが重要です。
遺産分割協議がまとまっていないと特例は使えない
小規模宅地等の特例は、土地を誰が取得するのかが確定していることが前提です。小規模宅地等の特例では取得者ごとに要件が異なるため、遺産分割で誰が土地を取得するか決まっていない段階では、要件を満たすかどうかを判定できません。
相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらない場合は、相続税申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告する方法があります。分割見込書を付けて期限内に申告しておけば、申告期限から3年以内に遺産分割が成立した場合に、後から特例の適用を受けられることがあります。
分割が決まらないまま申告期限を迎えると、特例を使えない前提で相続税を計算することになり、想定より納税額が増えます。納税額が増えると、相続人がすぐに用意できる現金だけでは納付できず、「相続人の誰かが立て替える」「金融機関から借りる」「その他の財産を売却して納税資金を作る」などの対応が必要になることがあります。さらに、立替えをした場合は、後から誰がいくら負担するのか、立替分をいつどう精算するのかが争点になりやすく、遺産分割協議が長引く原因にもなります。
そのため、遺産分割協議が相続税の申告期限(原則10ヶ月)までにまとまらない見込みがある場合は、特例を受ける権利を確保するために、以下の手順で手続きを行う必要があります。
【遺産分割が相続税の申告期限までにまとまらない際の手順】
① 申告期限内に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して、いったん特例の適用なし(未分割の状態)で申告・納税を行う。 この時点では特例が使えないため、特例を適用しないで計算した税額を納付する必要がある。
② 遺産分割が成立した後に、分割が行われた日の翌日から4か月以内に税務署へ「更正の請求」を行い、小規模宅地等の特例を適用して再計算し、納め過ぎた相続税の還付を受ける。
小規模宅地等の特例は、適用要件が非常に複雑かつ、土地を取得する人によって税額が数百万円変わることも珍しくないため、自分たちだけで判断せず専門家の知見を借りることをおすすめします。
まずは税理士に、特例を活用して全員の手取りが最大になる遺産分割案のシミュレーションや、万が一に備えた「分割見込書」の作成を依頼し、手続きの不備や判断ミスを防ぎましょう。
また、当事者だけで話し合うと、相場や法的な落とし穴に気づかないまま不利な条件で合意したり、感情面の対立で協議が止まったりすることがあります。当事者間の協議が進まない場合は、弁護士に交渉の窓口対応や、遺産分割協議書の作成・確認を依頼しましょう。話し合いで解決されない場合は、家庭裁判所の調停・裁判も視野に入れることになります。
相続税が払えない・共有者間のトラブルが心配なら共有持分の売却も選択肢の一つ
相続で土地を共有取得した後、「相続税の納付資金が足りない」または「共有者間の対立で不動産全体の売却や活用方針が決まらない」場合は、各共有者が自分の共有持分を売却して資金化する方法も選択肢になります。不動産全体を売却するには共有者全員の合意が必要ですが、共有持分の売却は「自分の持分」に限って進められるため、全員の同意を前提にしません。
ただし、前提として「誰がどの持分を持つのか」が確定している必要があります。取得者や持分割合が決まっていない段階では、売る対象となる持分自体が確定していないため、共有持分の売却は進められません。
共有持分の売却ができる状態になっても、一般の買主にとって共有持分は利用や処分の自由度が低く、売却先が見つかりにくい傾向があります。共有持分を買っても、購入後も他の共有者と権利を分け合う状態となるため、買主は自分の判断だけで居住したり、不動産全体を売却したりできず、利用や処分には他の共有者との協議が必要になるためです。
結果として、買主は共有者との関係調整や、将来的に共有状態を解消する手続まで見据えたうえで購入を判断しなければならず、一般の買主は手を出しにくくなります。
そこで有力な売却先となるのが、共有関係が残る物件の買取を前提にしている共有持分専門の買取業者です。共有持分専門の買取業者は、不動産の利用や処分に制約があることを前提に、一般の買主が敬遠するリスクや手間を織り込んで買取の可否と取引条件を判断できます。
さらに、買取後に想定される共有者との協議や、共有状態を解消するために必要となり得る手続きも見越して対応方針を立てるため、共有状態がネックになりやすい不動産でもスムーズに買い取ってもらえる可能性があります。
まとめ
共有名義の土地でも、小規模宅地等の特例は要件を満たせば利用できます。
ただし、減額の対象は土地全体ではなく、被相続人の持分に対応する土地に限られ、取得した相続人ごとに同居要件など適用の可否を判定する必要があります。さらに、用途が居住用・事業用・賃貸用で混在する場合は面積と評価額を区分して按分し、路線価方式または倍率方式で評価額を算出したうえで、区分ごとの減額割合を適用します。
小規模宅地等の特例が適用できる事例でも、手続きの期限切れや添付書類の不備によって減額が受けられないこともあり得るため、税務の専門家である税理士に相談して進めると安全です。遺産分割や活用方針の合意が進まない場合は、弁護士に交渉や手続きのサポートを依頼しましょう。
また、共有持分を取得したが相続税を払うお金が足りない場合や、持分を手放したいのに共有者間の対立で不動産全体の売却が難しい場合は、共有持分のみを売却して資金化する選択肢も検討できます。
共有持分専門の買取業者であれば、共有状態の制約があることを前提に買取ができるため、一般の買主では敬遠されるような物件でも早期の現金化が可能です。価格面では共有状態による減価が考慮されるのが一般的ですが、他の共有者の同意を得ずに自身の権利のみを切り離せる点は大きなメリットです。