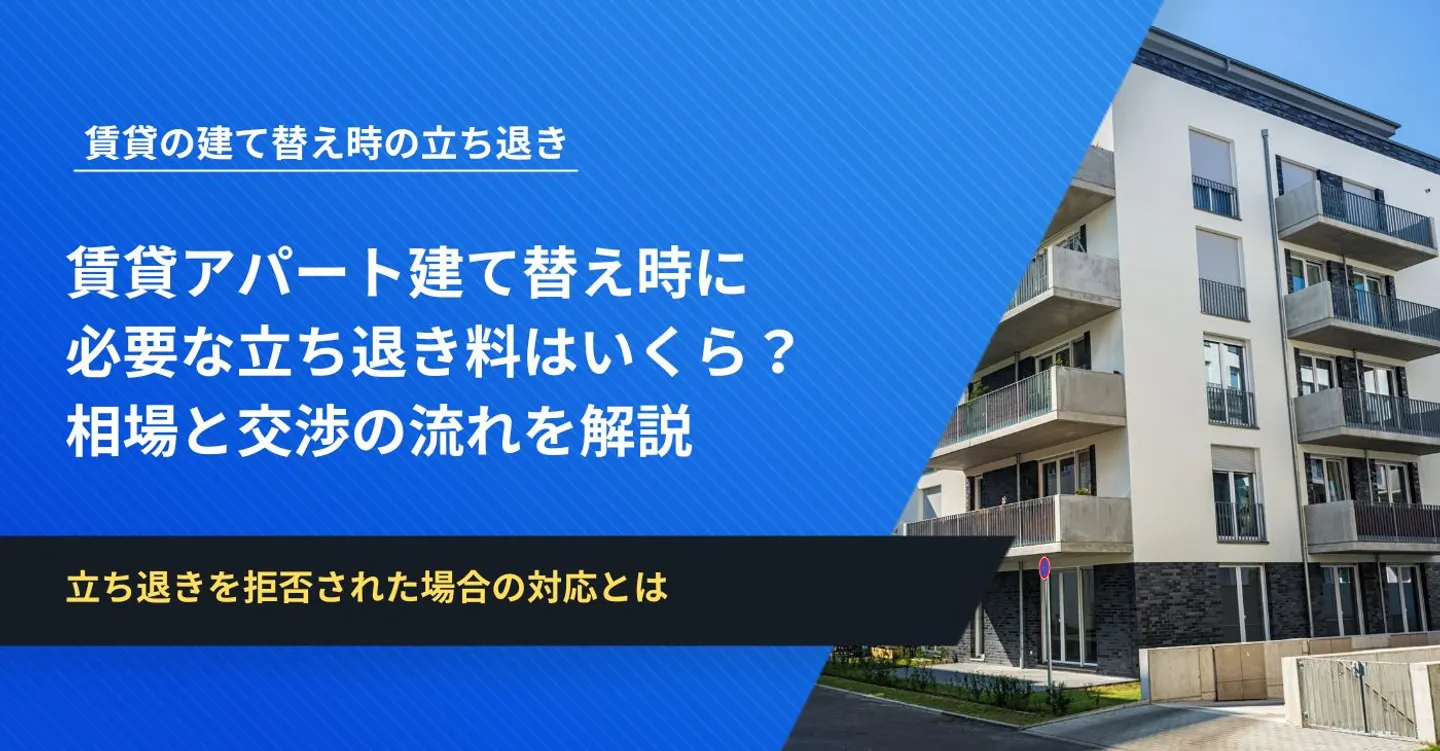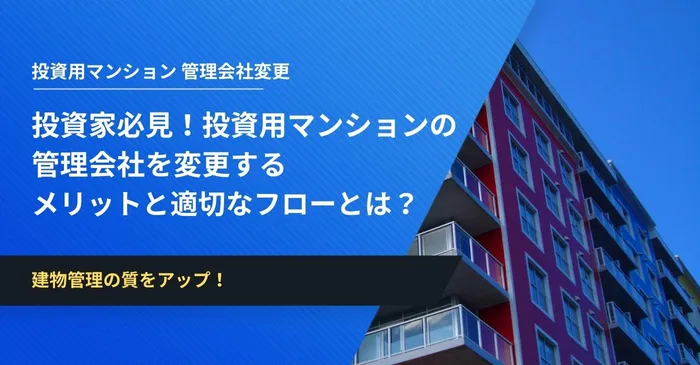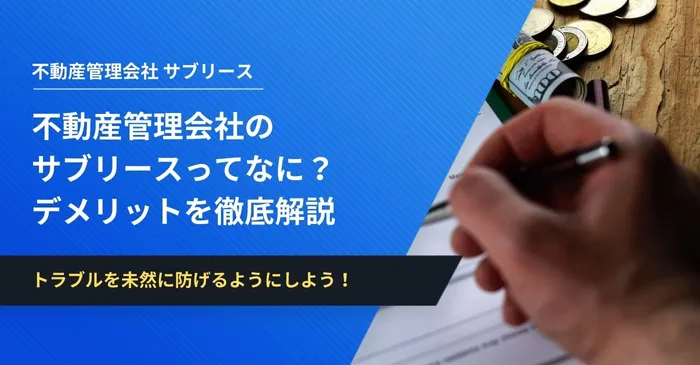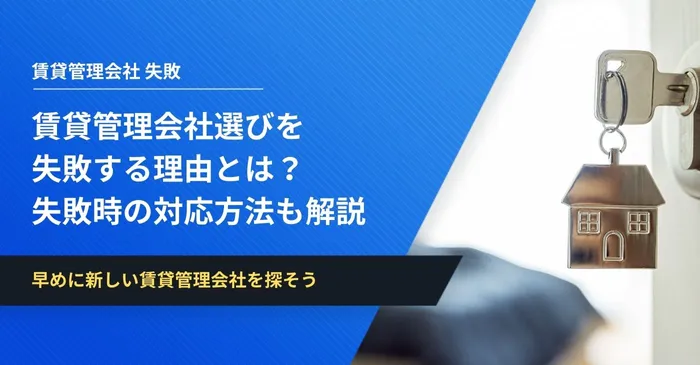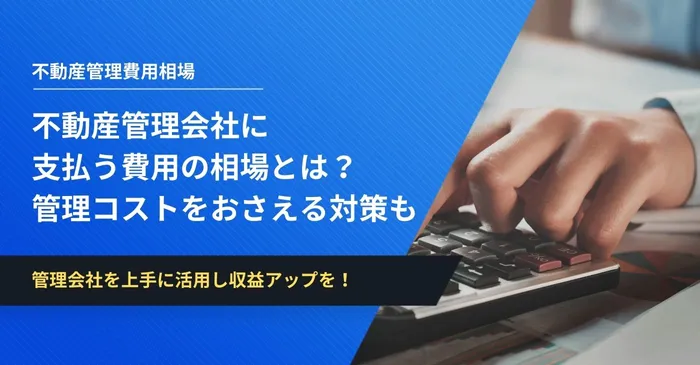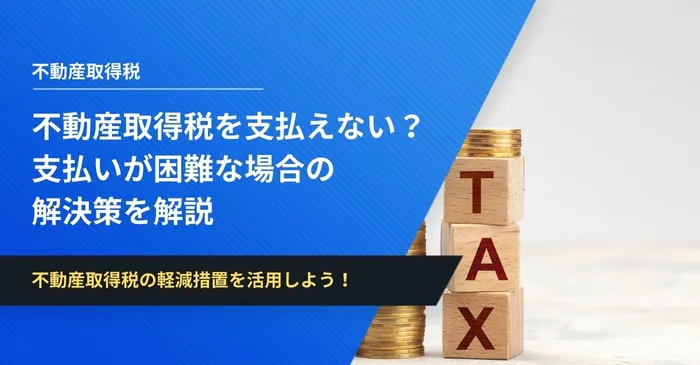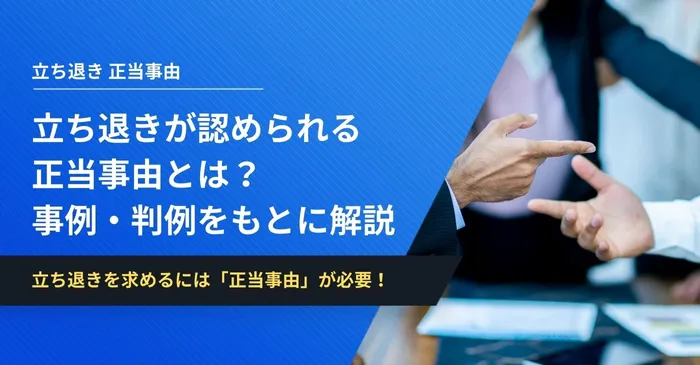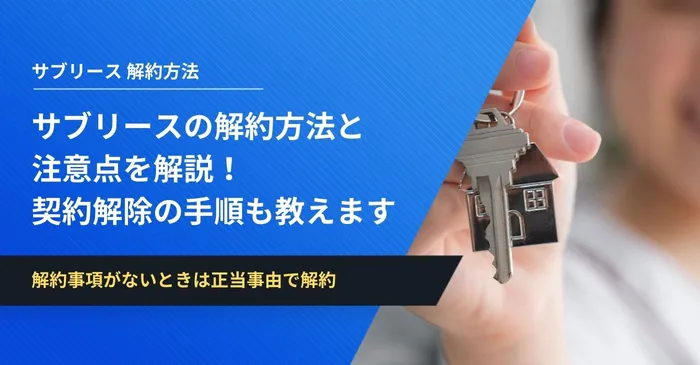賃貸アパートの建て替えにともなう立ち退き料の相場と内訳
賃貸アパートを建て替える際、入居者に退去してもらうためには「立ち退き料」の提示が必要な場合がほとんどです。金額の妥当性や補償の内容によって、入居者が納得して応じてくれるかどうかが変わってきます。
ここでは、一般的な立ち退き料の相場や内訳、支払うのが通例とされる理由について解説します。
立ち退き料の目安|家賃の6〜12ヵ月分が一般的
立ち退き料の金額に明確な法的基準はありませんが、実務では「家賃の6〜12ヵ月分程度」が1つの目安とされています。たとえば、月10万円の家賃であれば60万〜120万円程度が相場の目安です。
この金額は、主に引越費用や新生活の準備にかかる実費を補うことを目的としたもので、入居者の金銭的・精神的負担を軽減するための配慮でもあります。
ただし「契約年数」「家族構成(高齢者・障がいのある方など)」「地域相場」などによって適正な金額は変動します。とくに高齢者の方は、転居にともなう負担が大きくなりやすいため、立ち退き料が高めに設定されるケースもあります。
具体的な補償内容については、次の項で詳しく紹介します。
立ち退き料の内訳に含まれる主な費用
立ち退き料には、単に「立ち退いてもらうための謝礼」だけでなく、退去によって発生する費用や損失を補う性質があります。
以下は、主に含まれる補償内容の例です。
| 費用項目 |
内容 |
| 引越費用 |
荷造りや運搬にかかる実費(引越業者の利用など) |
| 転居先の初期費用 |
敷金・礼金・仲介手数料・前家賃など新居にかかる費用 |
| 喪失利益 |
相場より安い家賃で住んでいた場合の経済的不利益 |
| 精神的損害 |
生活環境の変化に伴うストレスや不便さへの補償 |
これらの補償内容は、交渉のなかで明確に示すことで入居者の理解を得やすくなります。また、住み慣れた場所からの転居に対する不安や負担を軽減するうえでも重要な配慮となります。
立ち退き料の支払いに法的義務はないが実質的に提示がほぼ必須となる傾向にある
立ち退き料の支払いは、法律上の義務ではありません。しかし、実務上は提示しなければ入居者が退去に応じてくれないケースが大半です。このような背景から、アパートの建て替えにあたっては、立ち退き料の提示が事実上必須といえます。
借地借家法は入居者を強く保護しており、貸主の都合だけで契約を終了させることは困難です。建て替えを理由とする場合でも「生活上の支障が出ているかどうか」や「他に手段がないか」といった観点で慎重に判断されます。
オーナーが誠意を示すために立ち退き料を提示することが交渉上有効であり、裁判実務においても重要な判断材料となります。
入居者に不利益のない条件を示すことは、交渉の円滑化に役立つでしょう。なお、法的な退去請求の可否は、次の項で解説する「正当事由」の有無によって判断されます。
賃貸アパートの立ち退きを請求するには正当事由が必要
賃貸借契約において、貸主が一方的に入居者へ退去を請求するには「正当事由」が必要です。正当事由とは、土地や建物の賃貸借契約を終了させる際に、貸主側から契約の更新を拒否したり解約を申し出たりする場合に必要とされる、正当な理由のことです。
とくにアパートの建て替えによる立ち退き交渉では「正当事由」の有無が大きな争点になるケースも少なくありません。
ここでは、正当事由の考え方と、実務でよく問題になる「老朽化」や「立ち退き料の提示」などについて解説します。
老朽化による建て替えでは立ち退きの正当事由として不十分な場合がある
老朽化を理由とするアパートの建て替えは、退去請求の典型例の1つですが、貸主が一方的に入居者へ退去を請求することはできません。借地借家法により、契約を終了させるには「正当事由」が必要です。
「正当事由」には、単なる築年数の経過や老朽化だけでなく「建物の安全性に具体的な問題がある」「現実的な維持管理が困難である」などの事情が求められます。
築40年を超えていても、補修やメンテナンスによって居住継続が可能と判断されれば、退去請求は認められないケースもあるのが実情です。
裁判所では、正当事由の有無を次のような複数の要素をもとに総合的に判断します。
- 貸主側の必要性:建て替えの目的・緊急性・代替手段の有無など
- 入居者側の事情:居住年数・高齢者や障がい者の有無・転居の困難性など
- 補償の内容:立ち退き料の有無・水準・再転居支援の有無など
立ち退き料は、正当事由を補完する要素とされていますが、提示すれば必ず退去請求が認められるわけではありません。建て替えの必要性や入居者の生活実態など、全体を見たうえで判断されます。
正当事由が認められやすいケースとは?
建て替えを理由に退去を請求する場合でも「築年数が古い」といった理由だけでは、正当事由としては不十分とされるケースがあります。
以下のような事情がある場合は、裁判所で立ち退きを認められやすくなる傾向があります。
- 建物が倒壊する恐れがあったり大規模修繕が必要な
- 借主が近隣に迷惑行為を繰り返す
- 貸主やその親族が居住する必要がある
- 都市開発など外的要因により立ち退きが避けられない
- 入居者による長期的な家賃滞納があるなどの契約違反がある
ただし、これらの要素があったからといっても、必ず立ち退きが認められるというわけではなく、状況を総合的に判断されます。
また、家賃滞納がある場合でも、直ちに正当事由が認められるとは限りません。滞納期間が長期にわたり(目安として3か月以上)かつ改善の見込みがないなどの事情があれば、正当事由の判断材料として考慮される場合があります。
なお「収益性を上げたい」「建て替えて自分で住みたい」といった貸主側の事情だけでは、正当事由として認められにくいケースが多いです。
実務では、十分な立ち退き料や転居支援などの条件を提示し、入居者との話し合いによる解決を目指すことが重要とされています。
正当事由についての具体的な裁判例については「老朽化による賃貸アパートの立ち退きに関する判例」で詳しく紹介します。
立ち退き交渉を見据えた下準備
立ち退きをスムーズに進めるには、交渉を始める前の準備が重要です。とくに契約更新や建て替えのタイミングを見据えた計画的な対応ができているかどうかで、その後の話し合いの進みやすさが変わります。
ここでは、立ち退き交渉に入る前に押さえておきたいポイントを解説します。
- 契約更新時に将来の建て替えを見据えた対応をしておく
- 立ち退き理由を明確にしておく
契約更新時に将来の建て替えを見据えた対応をしておく
賃貸借契約の更新時には、将来的にアパートを建て替える可能性があると入居者に伝えておくことが大切です。建て替えが未確定でも「老朽化や設備の限界により将来的に建て替えの可能性がある」といった文言を契約書類や覚書に含めておくと、後の交渉でトラブルを防ぎやすくなります。
とくに定期借家契約は、契約期間満了で確実に終了するため、退去を前提とした計画が立てやすくなります。
一方、普通借家契約の場合は、賃貸人側からの解約には正当事由が必要です。そのため、事前に建て替えの意向を共有しておくことで、信頼関係を築き、将来の退去交渉が円滑に進む可能性が高まります。
また、契約更新書面に「将来的な建て替えの可能性について双方で確認済み」といった文言を加えておくと、交渉の際に「聞いていない」と反発される事態を避けやすくなります。
立ち退き理由を明確にしておく
立ち退き交渉を始める前に、なぜ建て替えを行う必要があるのか、具体的な理由を整理しておくことが重要です。入居者に退去を請求する際には正当事由として「老朽化」や「安全性確保」などが挙げられますが「古くなったから」だけでは納得を得るのは難しいのが実情です。
たとえば、耐震性の不足、雨漏り・配管破損の頻発、修繕コストの限界など、具体的な事情を示すことで説得力が増します。
さらに、現在の建物が抱える安全面の懸念や、近隣への影響などについても丁寧に説明することで、入居者の理解を得やすくなります。
立ち退き理由は、通知書や説明時に明確に伝えるべき重要なポイントです。曖昧な説明は不信感を招き、交渉が難航する原因にもなりかねません。
建て替えの必要性を客観的に裏付ける資料(劣化診断報告書・工事計画書・設計図面など)があると、交渉の場でも説得力のある説明がしやすくなるでしょう。
賃貸アパート建て替え時の立ち退き交渉の流れ
アパートを建て替えるにあたり、入居者に退去してもらうには、丁寧かつ段階的な交渉が必要です。とくに、正当事由の説明や立ち退き料の提示、最終的な合意に至るまでには、時間と配慮が求められます。
感情的なトラブルに発展しないよう、スケジュールを明確にして進めることが重要です。
立ち退き交渉の主な流れは以下の4ステップです。
- 立ち退きの理由と意向を入居者に伝える
- 立ち退き料を含めた交渉を行う
- 退去時期や条件について合意を得る
- 明け渡しと物件確認を行う
それぞれの段階でのポイントや注意点を詳しく解説します。
1.立ち退きの理由と意向を入居者に伝える
建て替えなど貸主の都合で退去を請求する場合は、原則として契約満了の1年前〜6ヵ月前までに通知しなければなりません(借地借家法第26条)。この時期を過ぎてしまうと、契約が更新されたとみなされてしまうため、早めの準備が重要です。
立ち退き交渉の第一歩は「なぜ建て替えをするのか」「なぜ立ち退きが必要なのか」という理由を明確に伝えることです。口頭だけでなく、後のトラブルを避けるためにも書面で通知するのが望ましいです。文面は簡潔かつ丁寧に記載しましょう。
この段階での通知は、借地借家法に基づく契約解除とは異なり、まずは任意での話し合いを求めるための意思表示という位置づけです。
正式に立ち退きを裁判で請求する場合には「契約解除通知」という法的効力のある通知が別途必要になります。
本段階の通知はあくまで交渉のきっかけであり、入居者に状況を理解してもらい、話し合いによって退去の合意を目指すための第一歩と捉えるのが適切です。
書面通知時に入れるべき内容
入居者に立ち退きを請求する際は、まずは口頭ではなく、書面によって正式に通知することが重要です。書面に残すことで、交渉の経緯を記録できるほか、後のトラブル防止にもつながります。
通知書には、立ち退きを求める理由や立ち退き料、退去の期限など、入居者が検討・判断するために必要な情報を漏れなく記載しなければなりません。
具体的には、以下の内容を盛り込むのが望ましいとされています。
- 建て替え予定の理由(老朽化、安全性確保など)
- 退去を求める期限
- 立ち退き料の提示額と内訳(必要に応じて)
- 引越しに関する支援内容(例:費用補助、紹介先の有無)
- 今後の相談窓口(連絡先や担当者)
これらの項目を明記することで、入居者の不安を減らし、誠実な姿勢を示すことができます。交渉を円滑に進めるためにも、通知書の内容は慎重に検討しましょう。
なお、通知後は一方的に進めるのではなく、入居者一人ひとりに対して丁寧な説明を行うことも重要です。事前にアポイントを取ったうえで訪問し、入居者の事情や不安に寄り添った姿勢を示しましょう。
一括説明会などは入居者の反発を招くおそれもあるため、基本的には個別対応が望ましいとされています。
2.立ち退き料を含めた交渉を行う
立ち退きの意思を伝えたあとは、入居者との具体的な交渉が始まります。交渉の中心となるのが、立ち退き料の提示です。
金額の目安は家賃の6〜12ヵ月分が多いですが、交渉によって増減するため、柔軟な対応が求められます。
入居者側は、転居費用や新居の初期費用、引越し準備の手間など、多くの不安を抱えています。そのため、提示する補償内容が納得できるものであるかどうかが、交渉の成否を大きく左右します。
金額だけでなく、支払い時期・方法、追加費用の有無といった条件面も明確にしておくことが重要です。
また、家賃免除や原状回復費用の免除など、金銭以外の条件を組み合わせることで、よりスムーズな合意に至るケースもあります。入居者の事情に応じた柔軟な提案を心がけましょう。
交渉の際は、立ち退き料を単なる一時金とせず、引越し費用・敷金・礼金・新居初期費用などの「実費をベースに補償する」姿勢が入居者との信頼関係構築にもつながります。立ち退き料の妥当性を検討するためには、実際の見積書や請求書を確認し、必要に応じて専門家に相談するのも有効です。
なお、立ち退き料の支払いにあたっては、税務上の誤解を避けるためにも、必ず領収書を発行し「贈与ではなく補償金」であることを明記することが大切です。税務署の判断に不安がある場合は、税理士への相談も検討するとよいでしょう。
3.退去時期や条件について合意を得る
立ち退き料の金額や補償内容がまとまったら、次は退去時期やその他の条件について具体的な取り決めを行います。スケジュールの調整は重要で、入居者の生活事情を考慮しつつ、建て替え工事の着工時期に間に合うよう、計画的に進める必要があります。
取り決めるべき具体的な内容は、以下のとおりです。
- 退去予定日(引越し完了日)
- 立ち退き料の支払日・方法
- 原状回復義務の有無
- 退去後の鍵の返却方法
- 損傷箇所の確認・立会い日程
これらの内容は口頭だけでなく、必ず書面にして記録を残すことが大切です。
また、立ち退きに伴い賃貸借契約を終了させるには、入居者との合意に基づいた「契約解除に関する合意書(または覚書)」を取り交わす必要があります。立ち退き料の支払いタイミングも含め、法的な根拠となるよう必ず文書で残しておきましょう。
なお交渉が難航した場合や、合意後に入居者が退去に応じないケースなど、トラブルが懸念される際は、早めに弁護士に相談することも選択肢の1つです。強制執行などの法的手続きを見据えた対応をすることで、明け渡しまでの見通しが立ちやすくなります。
入居者に立ち退きを拒否された場合については「入居者に立ち退きを拒否された場合の対処法」で詳しく解説します。
4.明け渡しと物件確認を行う
退去の合意が成立したあとは、予定日にあわせて物件の明け渡しを行います。明け渡しの際は、オーナー(または管理会社)と入居者が現地で立ち会い、室内の状態を一緒に確認するのが一般的です。
確認すべき主なポイントは、以下のとおりです。
- 部屋の損傷や汚れの有無
- 設備や備品の不具合の確認
- 鍵の返却状況
- 残置物の有無
立会いの結果、とくに問題がなければその場で鍵を受け取り、明け渡しは完了します。原状回復費用については、事前の取り決め(免除の有無など)に沿って対応しますが、後々のトラブルを防ぐためにも、室内の状況は写真で記録しておくとよいでしょう。
また、立ち退き料の支払いが完了していない場合は、明け渡しと同時に支払うケースもあります。合意書の内容を双方で確認し、円満に手続きを終えるよう心がけましょう。
入居者に立ち退きを拒否された場合の対処法
立ち退き交渉が順調に進めば理想的ですが、現実には入居者が退去を拒み、話し合いが難航するケースも少なくありません。すべての入居者がスムーズに応じることはまれで、建て替えの事情や補償内容に納得できない場合は交渉が長期化するおそれもあります。
このような場合は、法的手続きを視野に入れて対応を検討する必要があります。
具体的には、以下のようなステップで進めていくとよいでしょう。
- 家庭裁判所の調停で第三者を交えた話し合いを行う
- 調停で解決できない場合は裁判で立ち退きを請求する
- 裁判後も退去しない場合は、明渡しの強制執行を申し立てる
それぞれの方法について、詳しく解説します。
調停で第三者を介して話し合う
入居者が任意の立ち退きに応じない場合は、家庭裁判所に「民事調停」を申し立てる方法があります。調停は、話し合いによる解決を目指す手続きです。調停委員が貸主と入居者の間に入り、建て替えの必要性や立ち退き料の内容などについて意見調整を行います。
手続きは裁判よりも簡単で費用も抑えられますが、話し合いによる解決を目指すもののため、入居者が同意しなければ成立しません。
調停を申し立てる際には、以下のような準備が必要です。
- 申立て先:物件所在地を管轄する簡易裁判所(請求額が高額な場合は地方裁判所)
- 申立費用:数千円〜(収入印紙代、郵券代)
- 必要書類:申立書、登記事項証明書、賃貸借契約書の写しなど
交渉段階で合意に至らなかった場合でも、条件の見直しや再提案によって進展するケースもあるため、柔軟に対応しましょう。
調停で解決できない場合は裁判で立ち退きを請求する
話し合いや調停で合意に至らない場合は、訴訟によって立ち退きを請求することになります。なお、立ち退き訴訟では、調停を経る必要はありません。
裁判では、単に建物を建て替えたいという希望だけでは足りず「正当事由」の有無が審査されます(借地借家法第28条)。とくに、老朽化や耐震性の問題など建て替えの必要性に加え、入居者への補償内容(立ち退き料など)の妥当性も含めて総合的に判断されるのが一般的です。
なお、交渉や調停でのやり取り内容は、裁判でも確認される可能性があるため、交渉経過や合意内容は記録として残しておくことが重要です。やり取りの内容や日付を簡単なメモでも残しておけば、後日の証拠として活用できる場合があります。
また、訴訟に進んだ場合は半年〜1年以上かかるケースもあり、請求が認められなければ建て替えスケジュールに大きな影響が出る可能性もあります。事前に弁護士とよく相談し、準備を整えたうえで進めましょう。
裁判における「正当事由」の判断で考慮される主な事情は以下のとおりです。
- 建物の老朽化や著しい劣化による居住困難
- 建て替えの必要性・計画の合理性
- 入居者への補償内容(立ち退き料や代替物件のあっせんなど)
- 貸主・借主双方の使用継続の必要性
これらの条件を客観的資料で裏づけできない場合は「正当事由が認められない」と判断され、請求が退けられる可能性もあります。裁判に移行する場合は、慎重かつ丁寧な準備が求められます。
判決後も退去しない場合は強制執行も可能
裁判で立ち退きが認められた場合でも、入居者が判決に従って退去しないケースがあります。このようなときは、裁判所に「明渡しの強制執行」を申し立てることが可能です。
強制執行では、裁判所の執行官が現地に赴き、法的手続きに基づいて物件の明け渡しを実施します。
ただし、強制執行には追加費用(執行官手数料、動産の搬出費用など)が発生し、原則として貸主側が負担します。準備期間も必要なため、できるだけ話し合いや補償によって解決を図るのが望ましいでしょう。
立ち退き交渉をスムーズに進めるポイント
立ち退き交渉を成功させるには、提示金額だけでなく、交渉のタイミングや入居者への配慮、手続きの進め方までを丁寧に整えておく必要があります。以下のような工夫を意識することで、トラブルを回避し、入居者との交渉が進みやすくなります。
- 少なくとも6ヵ月以上前から交渉を始める
- 空室が増えたタイミングで立ち退きを申し出る
- 入居者の事情や感情にも配慮する
- 交渉内容は必ず書面で記録する
- 難航する場合は弁護士など専門家に相談する
立ち退き交渉は少なくとも6ヵ月以上前に始める
立ち退き交渉は、時間に余裕を持って始めることが重要です。
入居者にとっては、住み慣れた場所を離れる不安や、引越し準備の負担が大きく、急な通告では反発を招きやすくなります。建物の取り壊しを予定する日の6〜12ヵ月以上前から意向を伝えることで、入居者との信頼関係を築きやすくなるでしょう。
交渉が長期化した場合や、法的手続きに発展する可能性も見越して、早めの準備をしておくことが大切です。
空室が増えたタイミングで立ち退きを申し出る
アパート内の空室が目立つタイミングを狙って、立ち退き交渉を始めるのもよいでしょう。空室が多いほど全体の賃貸収入への影響が小さくなるだけでなく「建て替えはやむを得ない」と入居者が納得しやすくなるメリットもあります。
とくに築年数が40年を超え、設備の老朽化や修繕頻度が増えている物件では、タイミングを見計らって交渉を切り出すことで、感情的な対立を避けやすくなります。
入居者の事情や感情にも配慮する
立ち退き交渉では、入居者の立場や生活事情への配慮が欠かせません。とくに高齢者や子育て世帯など、転居が難しい入居者に対しては、単に金銭的な補償を示すだけでは不十分な場合があります。
引っ越し先の地域や生活環境の変化に対する不安を理解し、丁寧な説明やサポート体制の提示を行うことで、相手との信頼関係も築きやすくなります。強引な交渉ではなく、相手の事情に寄り添う姿勢が、結果的に円満な立ち退きにつながるでしょう。
なお、貸主はあくまで「立ち退きをお願いする立場」であることを忘れてはいけません。交渉中に大声を出したり無断で部屋に立ち入ったりする行為は、違法行為として処罰されるおそれもあります。感情的にならずに冷静な対応を心がけましょう。
交渉内容は必ず書面で記録する
立ち退き交渉が進んできたら、口頭だけに頼らず、内容を文書で残すことが重要です。たとえば、立ち退き料の金額や支払い方法、退去期限、原状回復の免除条件などを合意書や覚書の形で明記し、署名・押印をもらっておくとよいでしょう。
文書化が難しい場合でも、交渉日時ややり取りの概要をメモや録音で残しておくだけで、万が一裁判になった際の証拠として活用できる可能性があります。日ごろから継続的に記録を残しておくことが大切です。
交渉が難航する場合は専門家を活用する
入居者との交渉が進まない場合は、不動産に詳しい弁護士や不動産会社などの専門家に相談を検討しましょう。立ち退きの法的根拠や補償額の妥当性など、法律や実務に基づいたアドバイスを受けることで、トラブルの回避につながります。
また、第三者が介入することで交渉の客観性が保たれ、感情的なもつれも起きにくくなります。とくに複数の入居者がいる場合や、過去にトラブルがあったケースでは、早めに専門家の関与を検討するとよいでしょう。
費用面も見越して、立ち退き料だけでなく弁護士費用などを含めた総予算をあらかじめ多めに見積もっておくことが、精神的なゆとりにもつながります。
立ち退き料以外で入居者の納得を得る工夫
立ち退き交渉では、立ち退き料だけでは入居者の理解を得られない場合もあります。
ただし、以下のような配慮や工夫を加えると、補償額を抑えつつも、納得してもらいやすくなるでしょう。
- 退去時の原状回復費用を免除する
- 退去前の家賃を免除する
- 引っ越し先の紹介や建て替え後の再入居を提案する
順番に見ていきましょう。
原状回復費用を免除する
入居者にとって、退去時にかかる原状回復費用は大きな負担となります。とくに、長期入居者の場合はクロスの張り替えや床の補修などで、修繕費が高額になるケースも少なくありません。
そのため、立ち退きの条件として「原状回復費用を免除する」旨を伝えると、心理的・経済的な負担を軽減し、合意を得やすくなる可能性があります。
実務上でも、建て替えを目的とした退去では室内を解体・改装することが前提のため、原状回復を求める合理性は乏しいと言えるでしょう。交渉時には、あらかじめ「原状回復費用の請求は行わない」と書面で明示しておくと、入居者の不安軽減にもつながります。
退去時の家賃を免除する
立ち退きに応じてもらうための工夫として「退去日までの家賃を免除する」といった対応も有効です。
退去が決まった入居者にとっては、引越し準備や転居先の契約などで出費がかさむ時期にあたります。その負担を軽くすることで、交渉がスムーズに進むきっかけにもなるでしょう。
とくに、転居先の初期費用(敷金・礼金・前家賃など)を自己負担する場合、家賃免除は経済的な助けになります。一方で貸主にとっては、家賃免除を立ち退き料の一部として位置づけることで、全体の補償コストを抑える手段にもなり得ます。
なお、家賃免除は1ヵ月分が一般的ですが、2ヵ月以上となると立ち退き料と大差なくなるため、補償とのバランスを見て調整しましょう。
家賃の免除額や期間は、事前に合意したうえで書面に残しておく必要があります。
引っ越し先の提案や再入居の約束をする
立ち退きを請求する際には、入居者の新しい住まいの選択肢を示すことで、安心感を与えることができます。
高齢者や長期入居者は、とくに住み慣れた地域を離れることに不安を感じやすく、新たな住まいの確保が困難なことが、立ち退きに応じない理由になる場合もあります。
そのため、周辺の賃貸物件の候補を複数提示したり、家賃条件が近い物件を紹介したりすることで、入居者の不安を軽減できるでしょう。
また、建て替え後に再入居を希望する入居者に対しては、優先的に契約できる「再入居の約束」をすることも有効です。
ただし、建て替え後は家賃が高くなるケースが一般的なため、建て替え前と同じ条件で再契約できるとは限りません。再入居の可否や家賃の目安については、事前に説明しておく必要があります。
老朽化による賃貸アパートの立ち退きに関する判例
老朽化による建て替えが、立ち退きの「正当事由」として認められるかどうかは、交渉や裁判での主要な争点になります。
ここでは、実際に争われた裁判例を3件紹介し、どのような事情が評価されたのかを確認します。
以下のように、築年数・補償内容・入居者の事情などによって、判断がわかれています。
- 築60年超の長屋で補償なしでも立ち退き請求が認められたケース
- オーナーチェンジ直後の建て替え計画で正当事由が否定されたケース
- 築50年超のビルが家賃6ヵ月分の補償提示で立ち退きが認められたケース
判例①:築60年超の老朽化を理由に補償なしで立ち退きが認められたケース(東京地裁 平成3年11月26日)
この事案では、築60年を超える木造長屋住宅の老朽化を理由に、貸主が立ち退きを求めたものです。入居者は長年居住していたものの、建物の傷みが進んでおり、安全性の面でも不安があったとされています。
裁判所は、老朽化の程度や修繕が困難な状況、建て替えの必要性などを踏まえ、正当事由を認めました。
築年数が極めて長く、安全性や耐用性に問題がある場合、補償がなくても立ち退きが認められる可能性があります。
判例②:オーナーチェンジ直後の建て替え計画で正当事由が否定されたケース(東京地裁 平成30年5月29日)
この事案は、賃貸物件の新しい所有者(オーナー)が取得後すぐに建て替えを計画し、入居者に対して立ち退きを求めたものです。オーナーは老朽化や経済的合理性を理由に立ち退きを求め、補償も提示しましたが、入居者は拒否しました。
裁判所は、建物の築年数や劣化状況を認めつつも「取得直後の立ち退き請求」である点や「入居者が長期間居住していたこと」「新オーナーによる突然の建て替え意向」などを考慮しました。これらを踏まえ、正当事由は認められないと判断されたのです。
この判例からは、補償の有無だけでなく、取得時期や貸主の誠実な対応も判断に影響することがわかります。
判例③:築50年超ビル・家賃6ヵ月の補償で認められたケース(東京地裁 令和3年12月14日)
この事案は、築50年を超える老朽化したビルの建て替えに伴い、貸主が入居者に立ち退きを求めたケースです。
貸主は耐震性や老朽化を理由に、将来的な安全性や維持コストの観点から建て替えを計画し、家賃6ヵ月分の補償を提示しました。
裁判所は、建物の築年数と老朽化の程度、そして入居者に対して一定の補償が行われたことを総合的に判断し、立ち退きの正当事由を認めました。
老朽化の程度に加え、補償内容が具体的かつ妥当であるかどうかも、正当事由の認定において重要な判断要素となっています。
賃貸アパートから立ち退いてもらえない場合の対処法
立ち退き交渉を進めても、入居者が応じてくれないケースは少なくありません。ここでは、立ち退きを拒否された場合の具体的な対処法を紹介します。
主な方法は以下のとおりです。
それぞれの方法を見ていきましょう。
弁護士に相談する
立ち退き交渉がこじれてしまった場合や、入居者から強く拒否されているケースでは、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
とくに賃貸借契約や借地借家法に精通した弁護士であれば、立ち退きの正当性や適切な補償額、交渉の進め方について、専門的なアドバイスを受けることが可能です。
また、弁護士が代理人として入居者と直接やり取りを行うことで、貸主側への不信感を緩和し、交渉が前向きに進展するケースもあります。書面通知や証拠の整理、万が一裁判に発展した際の対応まで、法的リスクに備えた総合的なサポートを受けられます。
地域の弁護士会や法テラスを通じて、無料法律相談を活用できるケースもあるため、費用面に不安がある場合でも、情報収集から始めてみるとよいでしょう。
弁護士費用の目安としては、30分あたり5,000 円程度で相談できるケースが多いです。初回相談は無料の事務所もあるため、気軽に相談してみてください。
不動産会社に間に入ってもらう
賃貸アパートを管理している不動産会社がある場合は、立ち退き交渉を任せるのも有効な手段です。不動産会社は日常的に入居者とやり取りしているため、信頼関係が築かれているケースも多く、貸主が直接話すよりも心理的ハードルが下がる可能性があります。
また、交渉にあたっては、以下のような実務対応にも長けており、誤解や感情的な対立を避けやすくなります。
- 立ち退き理由の説明
- 引っ越し時期の調整や段取りのサポート
- 補償条件(立ち退き料など)の提示タイミングについてのアドバイス
さらに、立ち退き料の相場や過去の対応事例についても、具体的なアドバイスを受けられるでしょう。不動産会社と連携することで、オーナーの意向を反映させつつ、入居者との良好な関係を保ったまま話し合いを進めやすくなります。
ただし、不動産会社が対応できるのは、書類の受け渡しや条件の伝達など実務的な交渉に限られ、法的判断や訴訟対応はできません。強制的な手続きが必要な場合は、弁護士に依頼するとよいでしょう。
まとめ
賃貸アパートを建て替える際の立ち退き料の相場は、一般的に家賃の6〜12ヵ月分程度とされています。これは引越費用や転居先費用、生活環境の変化に対する精神的負担などを含む金額です。
こうした補償を提示することで入居者の納得を得やすくなり、交渉が前向きに進みやすくなる可能性が高まります。
なお、立ち退き料の支払いは法律上の義務ではありませんが、実務上は支払うのが一般的です。
一方で、法的に退去を請求するには「正当事由」が必要です。単なる老朽化だけでは正当事由は認められにくく、補償の内容や入居者の事情などを含めて総合的に判断されます。
交渉は少なくとも6ヵ月以上前から始め、家賃免除や原状回復費用の免除、再入居の提案など柔軟な対応を検討するとよいでしょう。それでも合意が得られない場合には、調停や裁判を視野に入れ、弁護士や不動産会社と相談しながら進めることが大切です。
立ち退き交渉は感情や信頼が絡むデリケートなやり取りです。信頼関係を崩さずに合意を目指すためにも、冷静かつ丁寧に交渉を進めましょう。
訳あり不動産の売却でお悩みなら
今すぐご連絡ください
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-