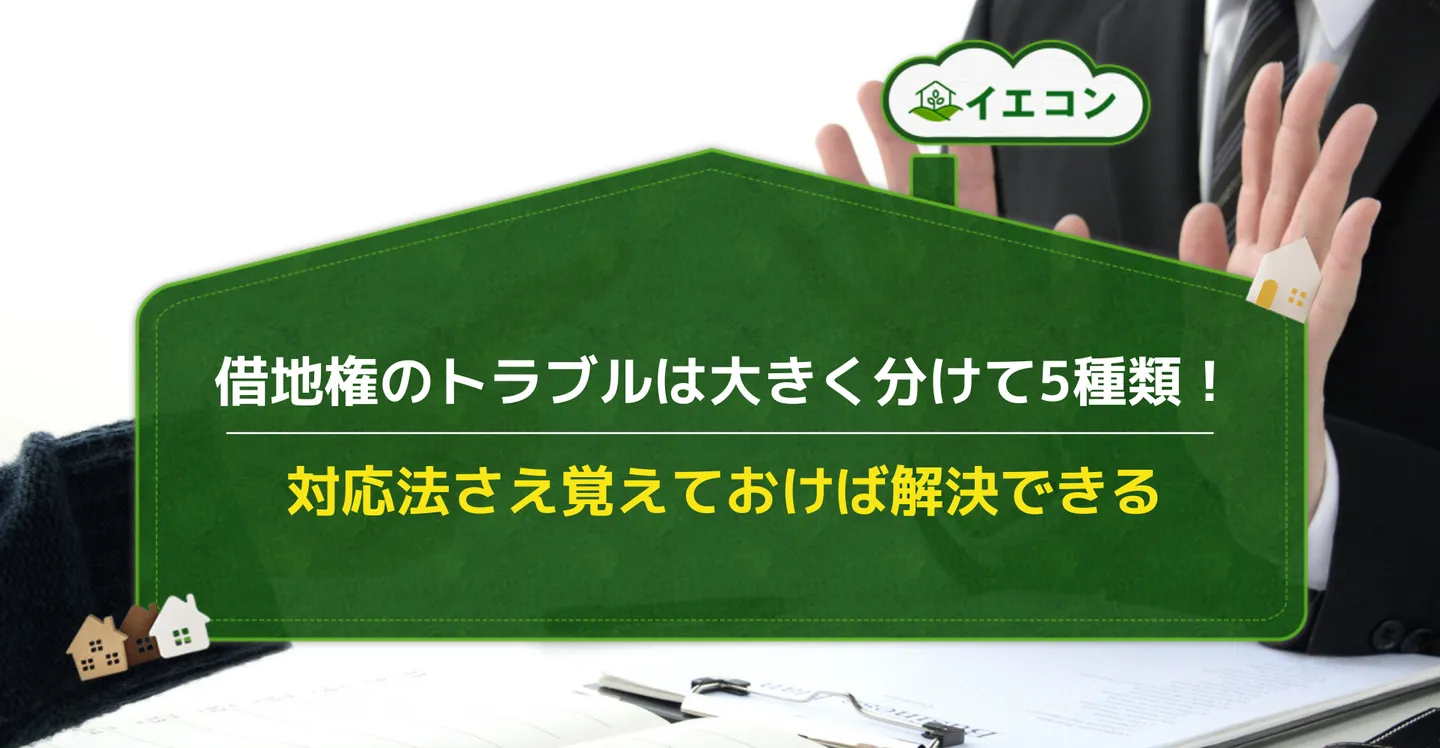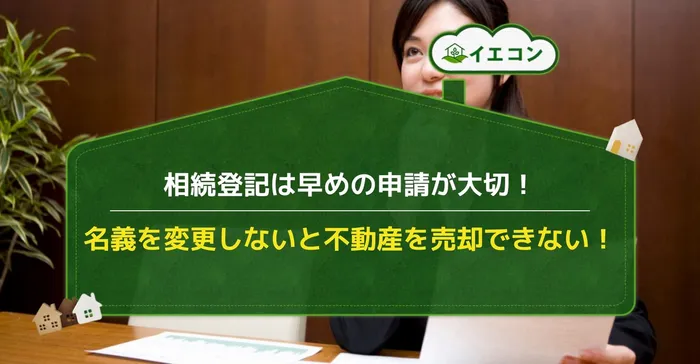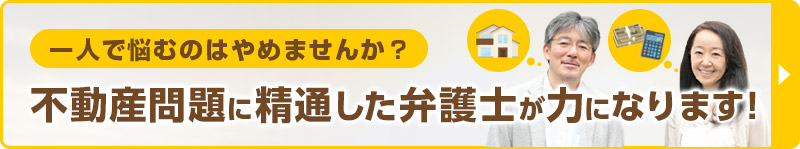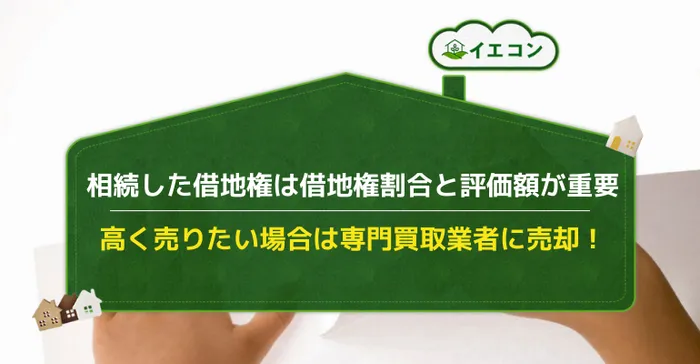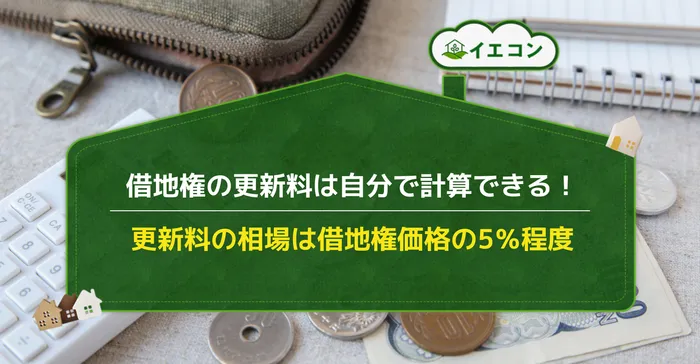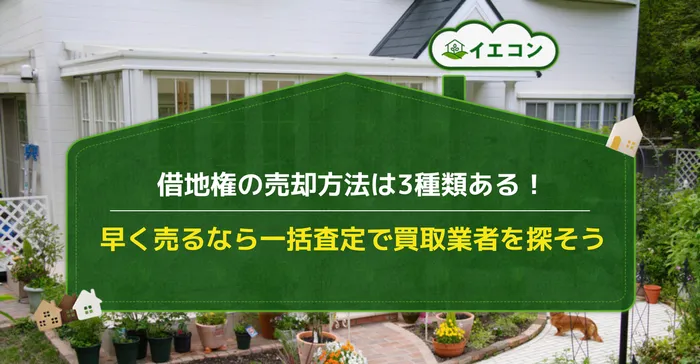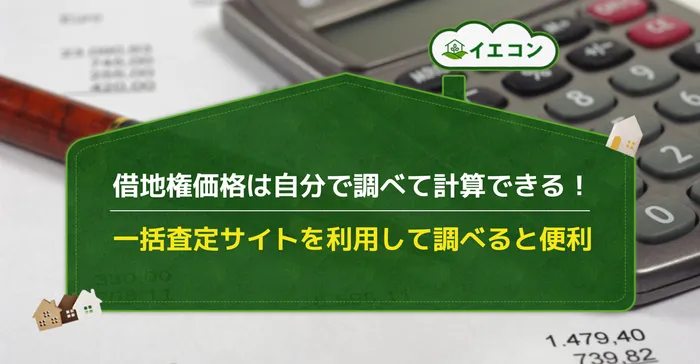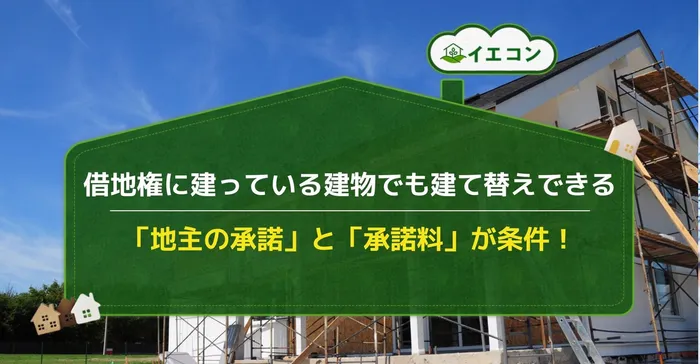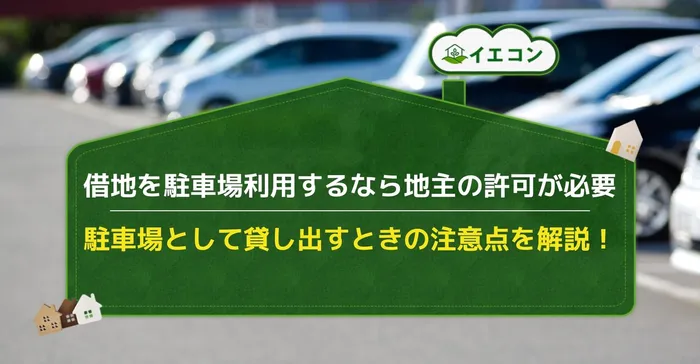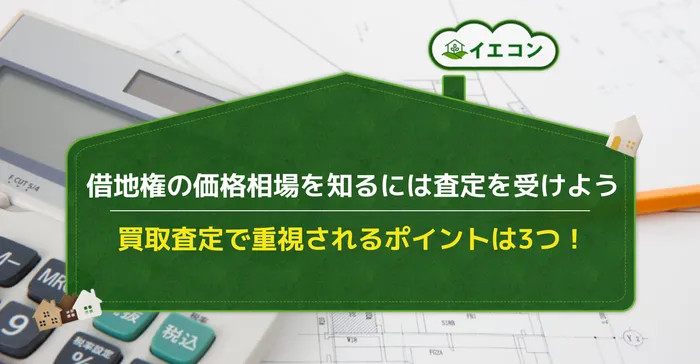借地権とは、借地借家法で定められた「建物を建てるために第三者から土地を借りる権利」を指します。借地権が発生する土地の貸し借りでは、土地を貸す「地主」と、土地を借りる「借地人」の2者が存在するため、どうしてもトラブルが起きやすくなります。
具体的には、下記のようなトラブルが多くみられます。
| 項目 | 具体例 |
|---|---|
| 相続 | ・名義変更料を請求された ・地主から借地の返却を求められた ・共有名義で相続して意見がまとまらない ・借地権に高額な相続税がかかる |
| 更新 | ・契約書に記載のない更新料の支払いを求められた ・更新を拒否された ・契約期間が切れて地主に借地の明け渡しを要求された ・更新後は新法借地権になると言われた |
| 売買 | ・譲渡の承諾を認めてもらえない ・建物への抵当権設定の承諾がもらえない ・売却したいのに借地権の契約書が見つからない ・底地を第三者に売却されてしまう |
| 競売 | ・競売により借地人となったが、地主が借地権の譲受けを認めない |
| その他 | ・地主から地代を上げたいと言われた ・地代を滞納してしまった ・建て替えを許可してくれない ・駐車場としての貸し出しを承諾してくれない |
借地権の制度は非常に複雑で、当事者である地主、借地人も正しく理解できていないケースもみられます。地主、借地人ともに借地権に関するトラブルを把握し、適切な対応ができるように備えておくことが重要です。「借地権のトラブルについて相談したい」「底地の買い取りをしたい」「借地権を売却したい」といった場合は、借地権に詳しい不動産業者や弁護士に相談するのも良いでしょう。
本記事では、借地権のトラブルが起こる主な原因、借地権に関するトラブルと対応策、トラブルの解消法や未然に防ぐ方法を解説します。
不動産を現金化
借地権のトラブルが起こる主な原因
借地権の発生する土地では、土地を貸す「地主」と、土地を借りる「借地人」の2者が存在します。地主と借地人では立場が異なることから、それぞれに下記のような感情や不満をもちやすく、それがトラブルへとつながっていくといえます。
| 立場 | 不満の内容 |
|---|---|
| 地主 | ・自分の土地がなければ、借地人は建物に住めない ・土地を貸しているのだから、地代や更新料を払ってもらいたい ・借地権のせいで土地を自由にできないため、返却してほしい ・借地人に土地を売却するなら、なるべく高額で売りたい |
| 借地人 | ・自分の建物なのに、地主の許可なく売却や建て替えができない ・毎月、地代を支払っているのだから、更新料や増改築の承諾料は払いたくない ・地代や更新料が高すぎる ・土地を買い取りたいけれど、地主が承諾してくれない |
地主は借地権によって地代や更新料などの収入はあるものの、建物を建てて居住したり、賃貸物件にしたりといったことは叶わず、土地を自由に活用できません。また、借地借家法(旧法)は「契約期間が満了しても、建物がある限りは契約が更新される」「地主から承諾が得られなくても、裁判所への申立てによって再建築や譲渡の許可がおりる」など、立場の弱い借地権者を保護する内容も多く、そこが不公平感や不満を生む原因にもなっています。
一方、借地人は建物を所有しているものの、土地は第三者のものなのでどうしても窮屈さを感じやすいといえます。例えば、建て替えや借地権の売却には地主の許可が必要です。裁判所への申立てによって許可がおりることもありますが、手続きには専門知識も必要で現実的には難しい場合もあります。
両者の関係性が上手くいっていればトラブルにならない場合もありますが、長期間の土地の貸し借りでは地主、借地人が代替わりすることもあり、人が変わることでトラブルになる可能性も考えられます。
なお、平成4年以降の借地借家法(新法)では、契約期間満了時には契約を終わらせることが可能となり、さらに更新のない定期借地権も新設されています。旧法から新法の契約に変更したい場合は、地主と借地人の両者の合意が必要となります。
1.借地権の相続に関するトラブルと対応法
借地権も相続財産なので、遺産分割協議の対象です。
そのため、相続人と地主間でのトラブルだけでなく、相続人同士でもトラブルになる恐れがあるので注意しましょう。
| トラブルの内容 | 対応方法 |
|---|---|
| 名義変更料を請求された | 名義変更料の請求は拒否しても問題ありません。ただし、地主との関係悪化を防ぐために、名義変更料を支払った方が良いケースもあります。 |
| 地主から借地の返却を求められた | 借地権の相続に地主の承諾は必要ないため、借地の返却に応じる必要はありません。 |
| 共有名義で相続して意見がまとまらない | 借地権問題に詳しい不動産会社や弁護士に相談しましょう。なお、共有名義は相続が発生するたびに名義人が増えて権利関係が複雑になるため、単独名義に変更するのが望ましいです。 |
| 借地権に高額な相続税がかかる | 小規模宅地等の特例を利用すれば、課税評価額から80%の控除が受けられる可能性があります。利用可能かは所轄の税務署に相談しましょう。 |
それぞれのトラブルについて、解説していきます。
名義変更料を請求された
亡くなった借地人の借地権を相続する場合、名義変更料(名義書換料)を請求されることがあります。
しかし、相続による借地権の取得は譲渡にはあたりません。
そのため、地主の承諾がなくても相続できますし、承諾料や名義変更料を支払う必要もないです。
したがって、借地権を相続する際に地主から名義変更料などを請求されても、拒否しても問題ありません。ただし、支払いの拒否によって地主との関係が悪化するおそれもあり、譲渡や売却の際に承諾を得られないといった可能性も考えられます。そのため、地主との関係を保つために、名義変更料を支払った方が良い場合もあります。
借地契約を結び直す必要はない
そもそも、借地権を相続するときには、借地人が変わったことを地主に伝える義務はありません。
地主との土地賃貸借契約を相続人の名義で結び直す必要もないので、借地上にある建物を相続人名義で登記すれば、借地権を第三者にも主張できます。
しかし、今後の地主との関係性を良好に保つためには、借地権を相続することを地主に伝えて、契約書の名義を書き換えたほうが良いでしょう。
地主が知らないうちに借地権者が変わっていたとなると、法的な義務はなかったとしても不信感を持たれてしまいます。
また契約書の名義を書き換えるのも、いずれ借地権を売却したいと考えた時に取引を滞りなく進めるためです。
地主から借地の返却を求められた
借地権を相続することを地主に伝える場合「相続するなら借地を返してほしい」と言われることがあります。
地主にとって「土地賃貸借契約は亡くなった借地人と結んだので、相続人とは結んでない」という考えからです。
しかし、借地権の相続に地主の承諾は必要ないので、地主から借地の返還を求められても、それに応じる義務はないので安心してください。
共有名義で相続して意見がまとまらない
借地権を相続する場合、次のようなデメリットもあります。
- 地主に地代を支払う必要が生じる
- 借地上の建物を増改築・売却する際に地主の承諾が必要
そのため、遺産分割協議でも「誰が相続するか?」の結論が出ないことが多いです。
その結果、相続人同士の共有名義で相続してしまうと、その後のトラブルが起こりやすいです。
借地権を売却するには相続人全員の同意が必要
まず、共有名義の借地権は、第三者へ売却する際に相続人全員の同意が必要です。
以下のような状況になると、意見を一致させることが困難でしょう。
- 母親は借地上の建物に住みたいのに長男は売却したい
- 自分は建物を賃貸に出して家賃収入を得たい
こうした場合、相続人同士の関係性にヒビが入ることもありえます。
相続人が死亡すると権利関係が複雑になる
相続人が亡くなって再び相続が発生すると、借地権の名義人が増えていくため、どんどん権利関係が複雑になります。
そのため、借地権を含む不動産を相続する際には、なるべく共有名義ではなく単独名義にすることをおすすめします。
また、共有名義の借地権が再び相続されるタイミングで、単独名義に変えるように遺産分割協議を進めましょう。
そうしなければ、トラブルを自分の子や孫にまで引き継いでしまうことになります。
もし相続人同士が意見が合わない場合、借地権に精通している不動産会社や弁護士に相談することをおすすめします。
借地権に高額な相続税がかかる
借地権は相続財産なので、相続税の課税対象でもあります。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
借地権の相続税評価額は所有権の土地の60~70%程度です。
立地の良い都市部や高級住宅地の借地権であれば、相続税は60坪程度で7000万円近くかかります。
しかし、借地と建物が亡くなった方の自己居住用であれば、一定の要件を満たすことで小規模宅地等の特例によって、課税評価額が控除されます。
課税評価額から80%もの控除を受けられる
しかし、被相続人が実際に借地に住んでいない場合、特例の適用を受けられないので、相続税が高額になる可能性が高いです。
例えば「被相続人は施設に入居していて、実際に借地に住んでいたのは相続人だった」といったケースです。
また、小規模宅地等の特例は、被相続人の配偶者でなければ適用要件が複雑なので、特例の適用を受けられるかを所轄の税務署に相談しておくと良いでしょう。
借地権の相続については、下記の記事でも詳しく紹介しています。
2.借地権の更新に関するトラブルと対応法
借地権の存続期間は、最初の契約を交わしてから30年以上です。
旧法借地権においては、非堅固建物で20年以上となっていますが、それでも非常に長い契約といえます。
そのため、存続期間が満了となる前に地主や借地人に相続があったり、当事者間でも更新についてどのような取り決めをしたのか記録に残っていなかったりして、トラブルになることがあります。
更新に関するトラブルの多くが、更新料の支払いと更新拒絶の問題です。
| トラブルの内容 | 対応方法 |
|---|---|
| 契約書に記載のない更新料を請求された | 借地契約に更新料の支払いが定められていない限り、支払う必要はありません。ただし、更新料の支払いに合意したり、過去の更新時に更新料を支払っている場合は、支払う必要があります。 |
| 契約更新を拒否された | 借地上に建物が存在しており、定期借地権でない限り、地主は更新の拒否ができません。ただし、地代の滞納などの正当事由がある場合は、地主が更新を拒否できる可能性があります。 |
| 契約期間が切れて地主に借地の明け渡しを要求された | 借地上に建物が存在し、借地人が居住していれば契約が更新されたとみなされるため、明け渡す必要はありません。 |
| 契約更新後は新法借地権になると言われた | 地主と借地人両者の合意がない限りは、新法借地権への変更は認められないため、要求に応じる必要はありません。 |
それぞれ詳しく解説します。
契約書に記載のない更新料の支払いを求められた
借地権の更新料について、法律で定められてはいません。
そのため、借地契約で更新料の支払いを定めていない限り、地主から更新料を請求されても支払義務はありません。
また、支払わなかったからといって更新拒絶されることもないので安心してください。
ただし、以下の場合は更新料の支払義務が生じるので注意しましょう。
- 契約書に記載はなくても更新料の支払いに合意している
- 過去の契約更新時に更新料を支払った実績がある
借地権の更新料については下記の記事も参考にしてみてください。
更新を拒否された
契約期間満了を理由に、地主から借地の返還を求められることがあります。
しかし、借地上に建物が存在している限り、契約期間を満了しても借地契約は更新されるため、借地を返還する必要はありません。
このことは、以下のように借地借家法でも定められています。
借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。引用:e-Govポータル「借地借家法第5条」
地主に正当な事由がなければ、借地人に事前に通知していたとしても、更新拒否は認められません。
そして更新を拒否できる正当事由は、以下の要素から総合的に判断されます。
- 権利金の支払いがあったか?
- 地代の滞納がなかったか?
- 建物の用途は事業用か居住用か?
- 立退き料は妥当な金額で提供されるか?
もし契約書に「契約更新はしない」と書かれていても、借地権が定期借地権でない限り、借地人に不利な特約として無効になるので安心してください。
契約期間が切れて地主に借地の明け渡しを要求された
以下のような場合、借地権の契約期間が切れていることもあります。
- 口頭によって契約期間の延長を決めていた
- 更新時に新しく契約書を交わさなかった
しかし、後に契約内容を確認したときに、契約期間が切れていることを理由に借地の明け渡しを求められるケースも少なくありません。
こうした場合でも、借地を明け渡す必要はありません。
その根拠として、借地借家法でも以下のように記されています。
借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。引用:e-Govポータル「借地借家法第5条の2」
つまり、契約期間が切れていても、借地上に建物があって借地権者が住み続けていれば、同一条件で契約が更新されたとみなされます。
しかし、このようなトラブルが起きないためにも、なるべく契約更新時には常に新しい契約書を交わすように徹底しましょう。
更新後は新法借地権になると言われた
1992年8月1日に借地法が廃止・改正され、新しく借地借家法が施行されました。
| 新法借地権 | 1992年8月1日以降に契約された借地権 |
|---|---|
| 旧法借地権 | 1992年8月1日以前に契約された借地権 |
新法借地権とは「契約更新がない借地権」のことで、旧法借地権では更新を断るには地主に正当事由が必要でしたが、新法借地権は契約期間満了を理由に契約を終了できます。
「旧法借地権の更新時に新法借地権へ変更できる」と考えている地主もいますが、旧法借地権を更新するときは、更新後も旧法が適用されます。地主と借地人両者の合意がない限りは、新法借地権への変更は認められません。
そのため「新法借地権が適用されるから契約を終了したい」と言われても、その要求に応じる必要はありません。
ただし、地主または不動産会社から具体的な説明があり、納得して変更した場合は新法借地権となります。
逆に具体的な説明ないまま、新法借地権に変更した場合は「借地権者に不利な契約」として無効になる場合もあります。
新法借地権を巡ってトラブルが起きた際は、弁護士などの専門家に相談してください。
3.借地権の売買に関するトラブルと対応法
借地権の売買は通常と手続きが異なるため、トラブルに発展することも多いです。その中でも代表的なトラブルを解説します。
| トラブルの内容 | 対応方法 |
|---|---|
| 譲渡の承諾を認めてもらえない | 地主の代わりに裁判所に許可をもらうことで譲渡が可能です。ただし、裁判所を通した譲渡によって、地主と新しい借地人の不和を生むおそれも考えられます。弁護士に依頼して地主と交渉してもらうのが良いでしょう。 |
| 建物への抵当権設定の承諾がもらえない | 地主との交渉を続けるか、地主の承諾なしでも融資を受けられる金融機関を探す必要があります。 |
| 売却したいのに借地権の契約書が見つからない | 契約書がなくても、金融機関での振込通知書や地主からの領収書などの「地代の支払いを証明できるもの」、固定資産税の納税通知書などの「借地上の建物が借地権者名義の登記であることを示すもの」の2つが揃えば売却可能です。 |
| 底地を第三者に売却されてしまう | 地主が変わることで底地の売買や地代の値上げを交渉されるおそれがあります。あらかじめ地主に底地の買い取りの希望を伝えておく、売却先について相談しておくことでトラブルを防ぎましょう。 |
譲渡の承諾を認めてもらえない
借地権を第三者に譲渡するには、地主の承諾が必要です。
しかし、地主が第三者への譲渡を認めてくれない場合があります。
- 譲渡承諾料の金額が高額で取引が成立しない
- 「なんとなく嫌だ」という地主の感情的な問題
このとき、地主の承諾を得ずに借地権を譲渡すると、借地契約を解除される可能性もあるため、買主と話がまとまっていても絶対に取引を進めてはいけません。
そのときには、裁判所に地主の承諾に代わる許可(代諾許可)を求めることになります。
このことは借地借家法で規定されています。
(土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可)
第19条 借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、賃借権の譲渡若しくは転貸を条件とする借地条件の変更を命じ、又はその許可を財産上の給付に係らしめることができる。引用:e-Govポータル「借地借家法第19条」
地主に代わって裁判所が譲渡許可を与えられる
譲渡を認めても地主が不利にならない場合、裁判所が地主の代わりに譲渡許可を与えることが可能です。
地主にとって不利というのは、地代を支払うことも難しい人や、反社会的勢力の関係者などに譲渡されてしまう場合をいいます。
そのため、一般的な不動産を購入できるような資金力・社会的信用がある買主であれば、不利になるとは認められません。
また、代諾許可を得られる場合は「財産上の給付」にあたる承諾料の支払いを命じられることが多く、承諾料の相場は借地権価格の10%程度です。
ただし、借地非訟事件手続きで認められた譲渡承諾は、売却後の新しい借地人と地主との関係性が良好とはいえないので、今後もトラブルが起こりやすいです。
ですので、なるべく裁判所には頼らず、弁護士などに依頼して、地主との話し合いで解決することをおすすめします。
建物への抵当権設定の承諾がもらえない
借地権の売買では譲渡に関する承諾だけでなく、借地上の建物への抵当権設定の承諾「ローン承諾」も必要です。
多くの金融機関で住宅ローンを組むときには、地主からの承諾を求められます。
承諾をもらえなければ、住宅ローンが利用できず、現金一括で購入するしかないため、大抵の買主は資金を準備できずに購入できません。
そのため、売却価格を一般的な借地権付き建物の価格より低くしなければ、買主が見つかりにくいです。
さらにローン承諾は譲渡承諾と異なり、裁判所に申し入れても認められないことが多いです。
そのため、ローン承諾をもらえない場合、地主と話し合って認めてもらうか、地主の承諾がなしでも融資を受けられる金融機関を探すしかありません。
売却したいのに借地権の契約書が見つからない
借地権を売却しようと思ったときに契約書が見つからないという人も多いです。
そして契約書がなければ、確かに借地権を取得していることが証明できず売却できないのではないかと考えてしまいます。
契約書が見つからなかったとしても、以下の2つの条件を満たしていれば、自分が借地権者であることを証明できるので大丈夫です。
- 地代を払っていること
- 借地上の建物が借地権者名義で登記されていること
地代の支払いの証明は、金融機関での振込通知書や地主からの領収書で十分です。
また、建物の登記については法務局で確認するか、毎年5月ごろに届く固定資産税の納税通知書で確認可能です。
そして、もし建物の登記名義人が借地権者となっていない場合は速やかに登記するようにしてください。
相続で建物を取得時に登記を忘れていることがあり、建物が借地人名義でなければ地主が変わったときに借地権を主張できないからです。
底地を第三者に売却されてしまう
地主が底地を整理するために、不動産業者や投資家に売却するケースもあります。
底地を購入する不動産業者や投資家は再販や地代収入などによって利益を生み出すことを目的としていることが多いです。
そのため、底地の売買や地代の値上げ交渉などを持ちかけられてしまうことも考えられます。
何度断ってもしつこく交渉されたり、相場よりも高い地代や更新料を要求してくるなどのトラブルに発展する可能性もゼロではありません。
もし地主が底地の売却を検討していることに気づいたら、底地の買取を検討したり売却先について相談しておくことでトラブルを防ぐことができるかもしれません。
4.借地権の競売に関するトラブルと対応法
借地権者が建物に抵当権を設定して融資を受けた場合、債務不履行に陥ると抵当権が実行され、建物は競売にかけられます。
借地権の競売でよくあるトラブルは、新しい借地権者となる競落人に地主が借地権の譲受けを承諾しないというものです。
地主から承諾を得られなければ、借地権を買い受けても借地契約が解除になる恐れがあります。
そのような場合、裁判所に地主の承諾に代わる許可「代諾許可」を求めましょう。
競売における代諾許可の申立ては「競(公)売に伴う土地賃借権譲渡譲受許可申立」と呼ばれ、申立期限は建物の代金を支払って2カ月以内です。
また、裁判所から許可を得られなかった場合は「建物買取請求権」を用いて、地主に対して時価で建物を買い取るように請求できます。
建物買取請求権を行使すると地主は拒否できないので、取引は自動で成立することになります。
5.借地権のその他のトラブルと対応法
借地権のトラブルでは、地代に関するトラブルや、建て替え、土地の活用法に関するトラブルも存在します。
| トラブルの内容 | 対応方法 |
|---|---|
| 地主から地代を上げたいと言われた | 適正な地代とするための値上げであり、契約に「地代を増減しない」といった特約がない限りは値上げに応じる必要があります。値上げに納得できない場合は地主との話し合いをし、解決しない場合は調停、訴訟の順で地代を決めることになります。 |
| 地代を滞納してしまった | 滞納による契約解除は、1~2回の支払い遅れであれば認められないケースが多いです。なお、解除通知の前に届く、地代の支払い請求に従ってすみやかに支払えば、契約を継続できます。 |
| 建て替えを許可してくれない | 契約書に増改築特約が含まれている場合は、地主の許可が必要です。地主に承諾料を提示して、交渉してみましょう。建物の老朽化によって建て替えが必要な場合は、裁判所に許可してもらう方法もあります。 |
| 駐車場としての貸し出しを承諾してくれない | 地主の代わりに裁判所に許可を求める方法もありますが、駐車場の貸し出しは転貸に該当するため、認められないケースがほとんどです。地主との交渉がうまくいかない場合、貸し出しは難しいでしょう。 |
上記のトラブルをそれぞれ詳しく解説していきます
地主から地代を上げたいと言われた
契約期間中、地主の事情が変わったり固定資産税が高くなったりといった理由で、地主から「地代を上げたい」と言われることがあります。
このとき、契約で「地代を増減しない」という特約がない限り、適正な地代とするための値上げであれば応じなければなりません。
地代を増減できる条件は、借地借家法で次のように定められています。
(地代等増減請求権)
第11条 地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。引用:e-Govポータル「借地借家法第11条」
3つの条件にあてはまるとき、地主は地代の増額を借地権者に請求できます。
- 土地の固定資産税・都市計画税の増減があったとき
- 地価の上昇または低下があったとき
- 近隣の似た土地における地代と比較して不相当な地代となっているとき
ただし、借地権者が必ずしも言われたとおりの地代を支払わなければならないわけではなく、地主の請求に対して借地権者が承諾することで決定します。
もし地代の値上げ自体や値上げされた金額に納得ができないのであれば、話し合いを実施して、双方の合意点を探すこともできます。
話し合いで結論が出なければ調停、それでも決まらなければ訴訟という順序で最終的な地代が決まります。
また、地主が「値上げした地代でなければ受け取らない」と受取拒否する場合、地代は法務局の供託所に供託することで、債務不履行とはならず借地契約解除を避けられます。
地代を滞納してしまった
地代の支払いは借地権者の義務ですが、地代の未払いは地主とのトラブルでよくあるものです。
そして、何らかの事情で地代を滞納してしまい、契約解除されそうになった場合は、まず契約書の確認をするようにしましょう。
一般的には、契約解除の条項に地代の滞納が含まれているので、どのような場合に契約解除となるのかを確認します。
・地代の支払いの遅延が多く、地主との信頼関係を破壊したとき
1〜2回支払いが遅れてしまったとしても、地主との信頼関係を破壊したことにはならず、契約解除は認められない場合が多いです。
また、地代を滞納して即座に借地契約を解除されることは少なく、解除通知の前に地代を工面する期間として、約1週間を猶予とした地代の支払い請求が届きます。
そのため、この期間内に支払うことで借地契約を継続させることができます。
こうしたトラブルを起こさないためにも、地代を滞納しないように心がけましょう。
建て替えを許可してくれない
契約書に増改築特約が含まれている場合、建て替えや増改築を行う際に地主の許可が必要です。増改築特約は、借地人が建て替えや増改築を行うことにより、土地に不利益が生じるのを防ぐために設けられているもので、ほとんどの契約書にはこの特約が記載されています。
契約書に記載があり、地主が建て替えや増改築を許可してくれない場合は、承諾料などを提示して地主と交渉しなければなりません。
仮に増改築特約の記載がない場合も、建て替えや増改築を行う際には地主に一言伝えておくと、トラブルを防げるでしょう。
なお、建物の老朽化によって早急に建て替えが必要な場合などは、地主の代わりに裁判所の許可を得られれば建て替えが可能です。地主の許可がおりず、交渉も進まない場合は、裁判所への申立ても検討してみてください。
借地権にある建物の建て替えについては、下記の記事を参考にしてください。
駐車場としての貸し出しを承諾してくれない
借地にある建物を居住地として利用し、余ったスペースを駐車場として貸し出したい場合は、借地の転貸に該当するため、地主の承諾が必要です。民法にも定められていますが、地主の承諾を得ないまま貸し出しを行ってしまうと契約解除されるおそれもあります。
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
引用元 e-Govポータル「 民法第612条」
地主の承諾が得られない場合は、裁判所への申し立てによって許可をとる方法もありますが、費用や時間がかかるうえ、許可を得るのは難しいとされています。地主の心証も悪くなるおそれがあるため、交渉しても地主が承諾してくれない場合は諦めた方が良い場合もあります。
借地の一部を駐車場として貸し出す際の注意点については、下記の記事で詳しく紹介しています。
借地権のトラブルを解消する方法
借地権のトラブルが発生した場合、地主と借地権の2者間の話し合いでは解決できない場合もあります。トラブルを解消したい時は、下記のような方法も検討してみてください。
- 不動産会社に相談する
- 弁護士に依頼する
- 地主に借地権を売却する
それぞれの方法について、詳しく解説していきます。
不動産会社に相談する
「底地を買い取りたい」「借地権を売却したい」といった場合は、不動産会社に相談するのがおすすめです。
借地権の取引実績のある不動産会社であれば、底地の買い取りに関する的確なアドバイスをもらえます。買い取りする際は、地主との価格交渉などもありますが、不動産会社であれば底地の査定なども行ってもらえるため、相場を踏まえたうえで交渉が可能です。
借地権を売却する際は、不動産仲介業者に依頼して買主を探してもらう方法と、不動産買取業者に依頼して直接売却する方法があります。ただし、借地権の売却は簡単ではなく、時間を要します。買主側からすると借地権の扱いは面倒で、土地も建物もどちらも手に入れたいと考えるためです。
早めに借地権を売却したい場合は、不動産仲介業者ではなく、借地権に精通している専門の不動産買取業者に依頼する方がスムーズでしょう。借地権の売却は地主の承諾が必要ですが、専門の不動産買取業者であれば、地主との交渉にも慣れているため、心強い味方となってくれます。
不動産を現金化
不動産買取業者の選び方や、売却の流れは下記の記事を参考にしてみてください。
弁護士に依頼する
借地権に関するトラブルが発生し、地主との話し合いが上手くいかない場合は、弁護士に依頼する方法もあります。
借地権にまつわるトラブルは多岐にわたり、地主、借地人双方に専門知識がないことで話がまとまらない場合もあります。その点、借地権を含む不動産に詳しい弁護士に依頼すれば、専門知識をもってスピーディーに解決に導いてくれます。今後起こりうるトラブルへのアドバイスなどももらえ、適切な対処ができます。
また、借地人の代理人として地主と交渉してくれるため、地主と直接やり取りする必要がなくなり、ストレスなどからも解放されるでしょう。
地主に借地権を売却する
相続などで借地権を得て、その土地に居住していない場合は、借地権を手放したいと考える人もいるでしょう。借地権の売却は不動産会社だけではなく、地主に直接売却することも可能です。
地主側からすると、借地権の購入によって完全所有権の土地を入手できることになるため、土地の活用の制限がなくなります。地主が底地を活用したいと考えていそうなら、こちらから売却の交渉を持ちかけることでスムーズに借地権の売却ができることもあります。
ただし、売却時には建物を解体して更地にすることを求められることがほとんどです。解体費用は発生するものと考えておいた方が良いでしょう。
また、価格面での交渉に難儀する可能性も考えられるため、売却相手が地主であっても、借地権に詳しい不動産会社に相談して売却を進めるのがおすすめです。
借地権のトラブルを未然に防ぐ方法
借地の契約は長期にわたるため、地主との信頼関係を築いておくことが重要です。良好な関係であれば、建て替えや借地権の売却などに関する地主の承諾も得やすく、トラブルが発生しにくいといえます。
また、土地を買い取る場合は、底地の相場や土地の境界線などについて事前調査をしておき、計画的に進めることで、トラブルを防いで交渉にあたれるでしょう。
地主と良好な関係を築いておく
借地権のトラブルの多くは、地主と借地人の関係性が良好であれば発生しません。地主の承諾が必要である建て替えや借地権の売却、契約期間満了後の更新なども、地主と信頼関係を築けていれば、スムーズに進む可能性が高いといえます。
借地契約は数十年と長期にわたる契約期間になるため、できるだけ良い関係を築けるように心がけましょう。近隣に地主が住んでいる場合は顔を合わせる機会もあるため、挨拶をしたり、コミュニケーションをとったりしておくとお互いに気持ちの良い関係でいられます。地主が遠方に住んでいる場合は、年賀状や暑中見舞いのハガキを出すなど、ちょっとした工夫でコミュニケーションがとれるでしょう。
なお、土地を買い取りたい気持ちがある場合は、事前に地主に「売却する際は、買い取りも検討するので教えてほしい」と伝えておくのがおすすめです。普段から地主とコミュニケーションをとって良好な関係を築けていれば、地主側から売却話をもちかけてくれる場合もあります。
土地を買い取る場合は事前調査をしておく
地主から土地を買い取る場合は、事前調査や準備が重要です。地主が買い取りを了承したからといって焦って交渉にあたると、地主からの心証を損ねたり、不利な条件になったりするおそれがあります。
まず、土地の価格相場をきちんと調べておきましょう。土地の買い取りでは価格交渉があるため、相場を知っておくことが重要です。高すぎる額を提示すれば地主が不信感をもつ可能性があります。もちろん低すぎる額では損をすることになるでしょう。不動産会社に依頼し、相場を調査したうえで地主に提示するなど、双方が納得できるように交渉を進めると良いでしょう。
また、借地に何軒か建物が建っている場合は土地が1筆になっていて、買い取った際に分筆登記が必要になる場合もあります。境界線が曖昧なまま買い取りすれば、後々トラブルが発生するおそれもあります。こういった土地では土地家屋調査士へ依頼し、地主と借地人で境界を確認するといった作業が発生することを覚えておきましょう。
まとめ
借地権においては地主の立場が強いため、地主の決定には必ず従わなければならないと感じますが、決してそういうわけではありません。建て替えや売却などは地主の承諾が必要になりますが、借地借家法(旧法)は立場の弱い借地人を保護する内容になっているため、地主が無理な立ち退きを迫るなどはできません。
法律上、借地人の権利も認められているので、弁護士を通して地主と交渉したり、裁判所に判断を仰ぐことで不利益を被る事態は避けられます。
「地主が言うからきっとそうなのだろう」と思い込んで、要求を受け入れることで思わぬ損をしてしまうおそれもあります。
借地権のトラブル発生時、自己判断が難しいときや困ったときは、すぐに不動産会社や弁護士に相談しましょう。