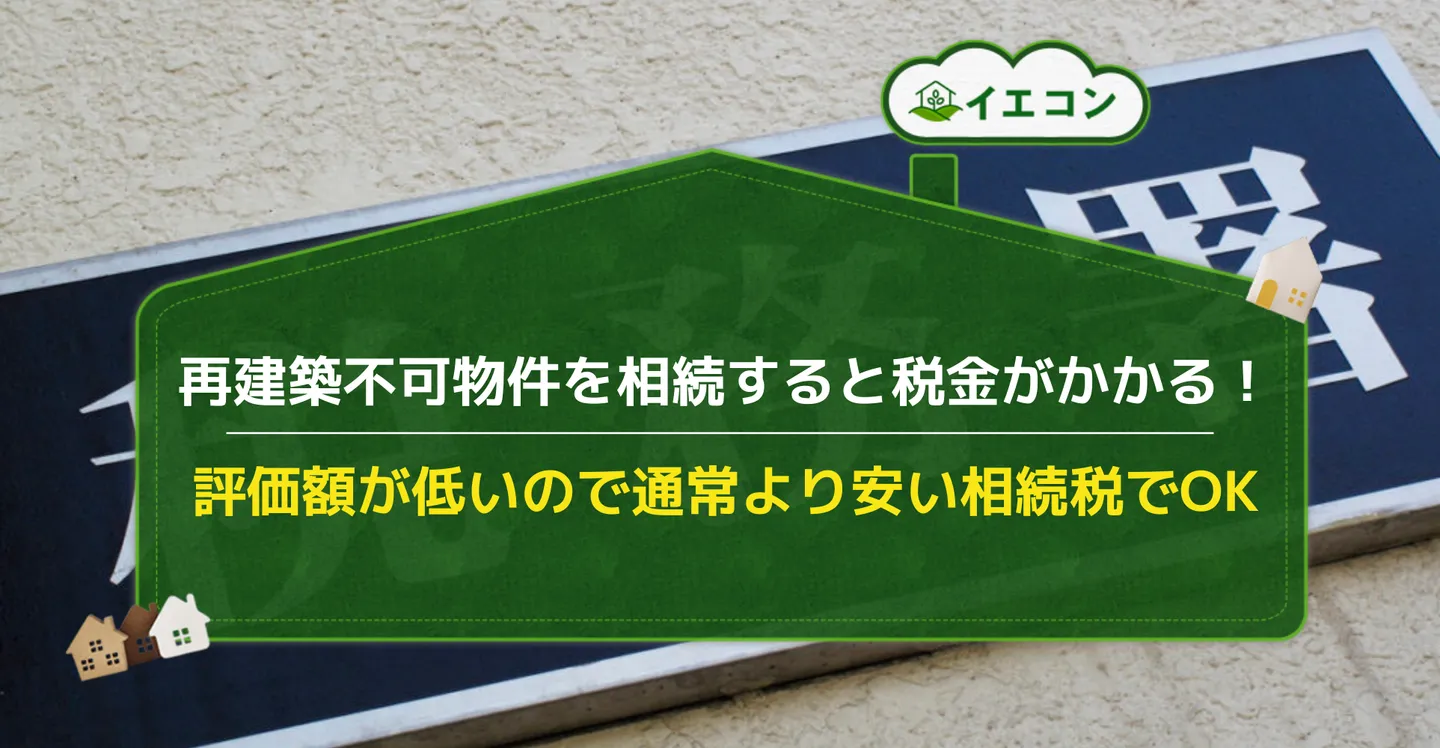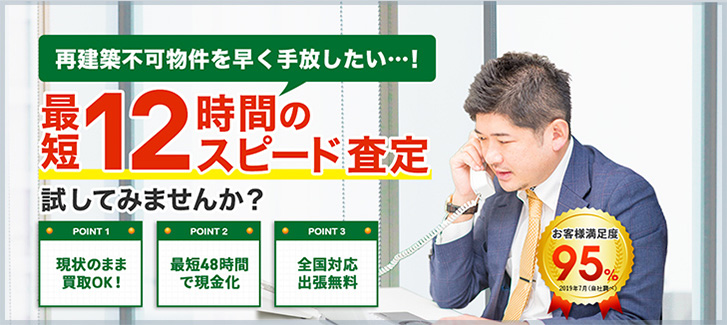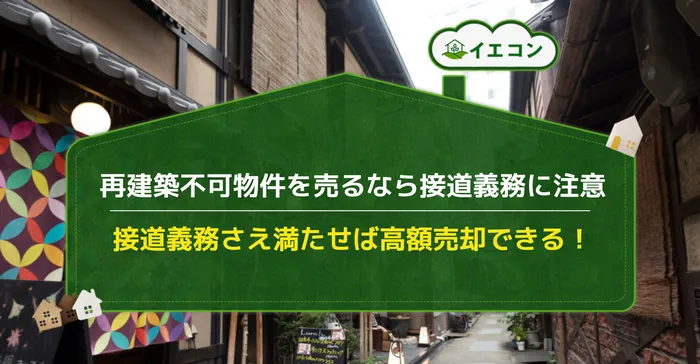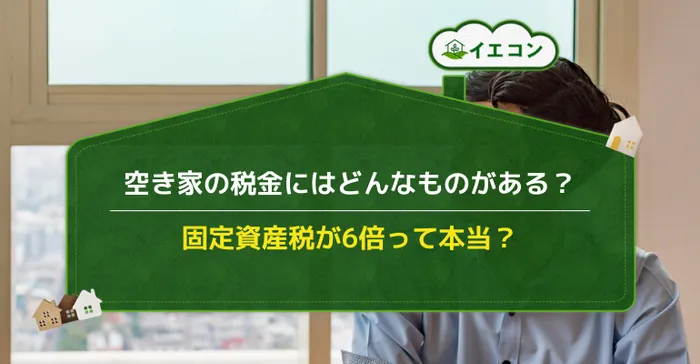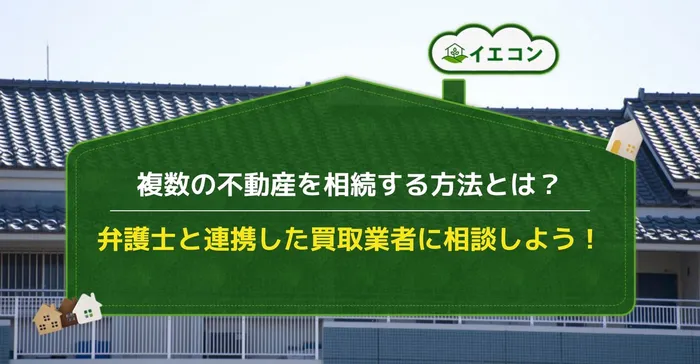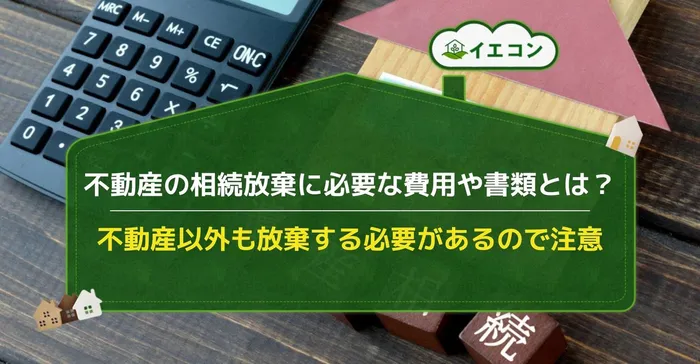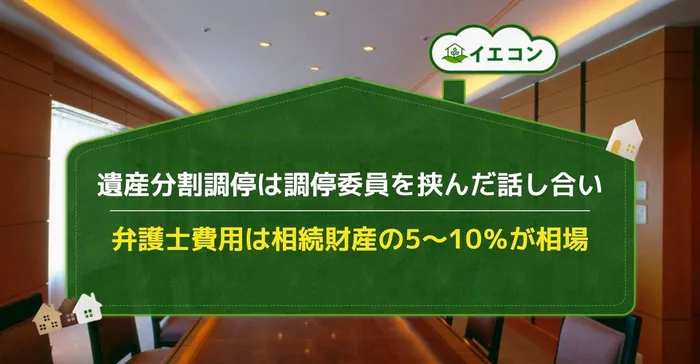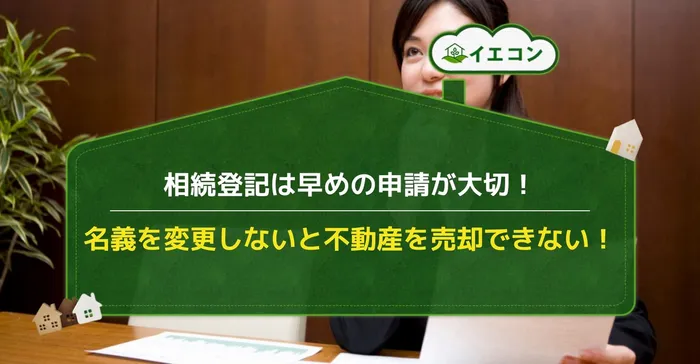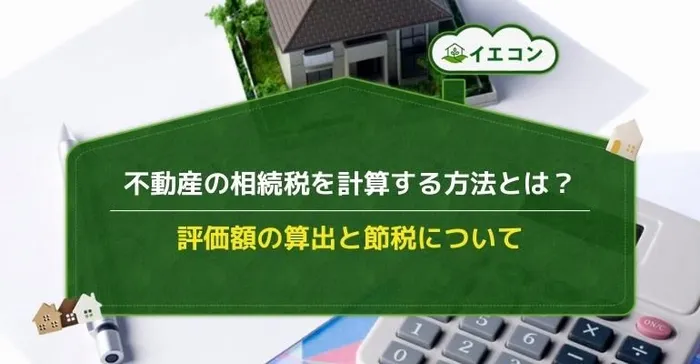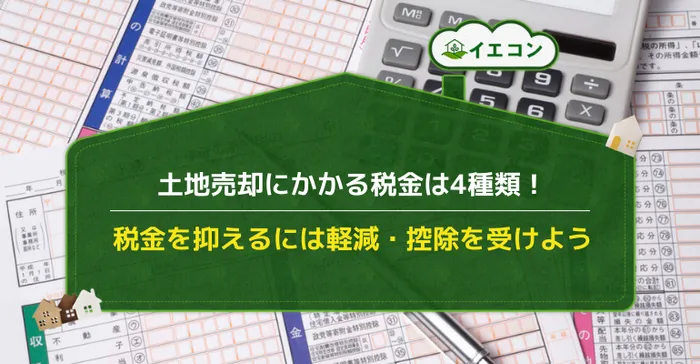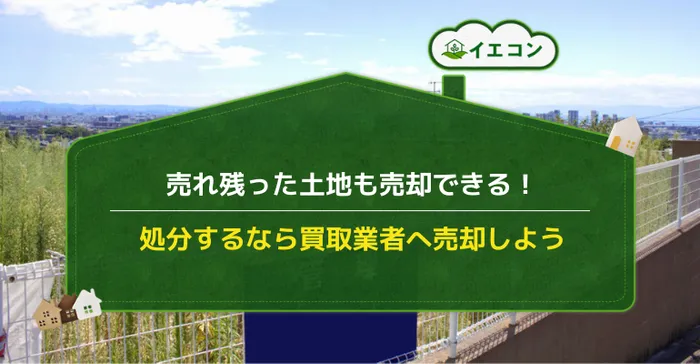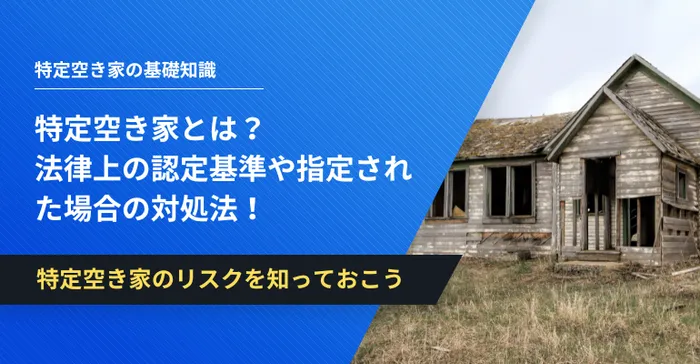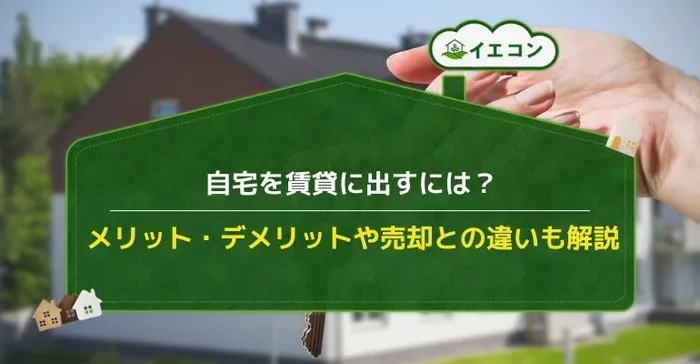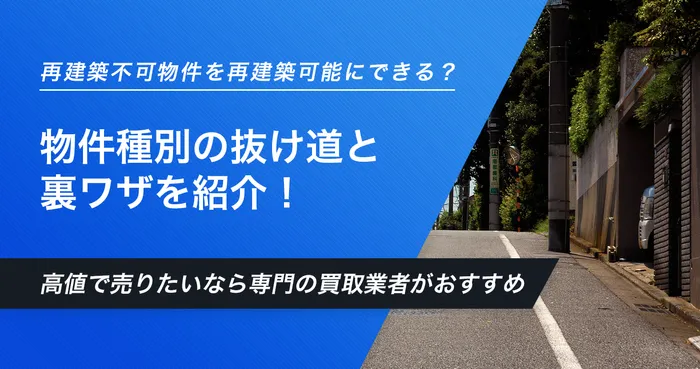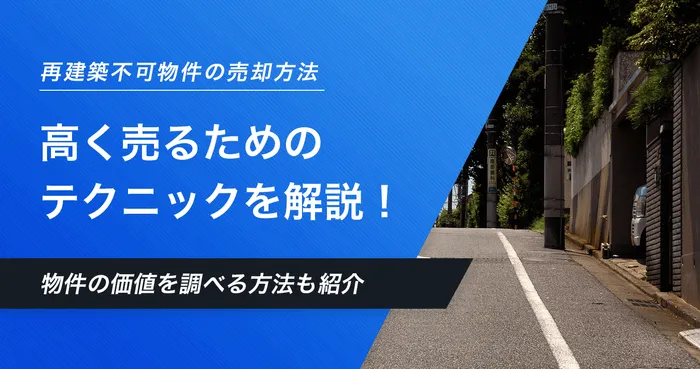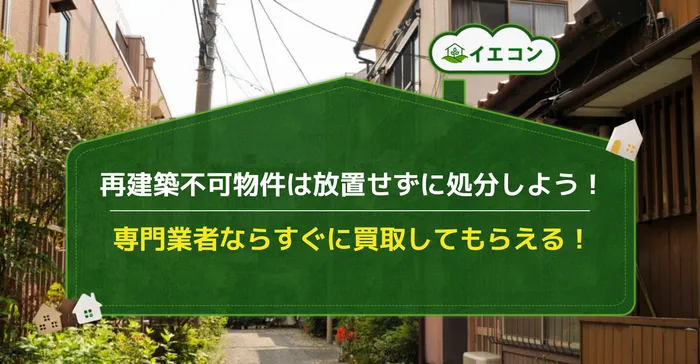再建築不可物件を相続する予定がある場合、「再建築不可物件を相続する予定だけど、相続するべきかわからない」「そもそも相続のために何をすればいいかがわからない」といった不安や悩みがあることでしょう。
再建築不可物件の相続を検討している場合、まずは本当に相続をするべきかどうかを考えるべきです。
再建築不可物件の所有にはさまざまなリスクがあるうえに、「手放したくても手放せない」という状況に陥る可能性もあります。相続放棄以外にも再建築不可物件自体の相続を避ける方法はあるため、リスクを踏まえて相続しない方法をとるのも1つの手です。
「リスクを踏まえてでも相続をしたい」という場合、再建築不可物件などの遺産を相続するためにはさまざまな手続きが必要です。スムーズに相続の手続きを進められるように、相続の流れを事前に把握しておくのがよいでしょう。
当記事では、再建築不可物件を相続するリスクから、相続の流れや物件自体を相続しない対処法まで、再建築不可物件の相続に関わる情報を網羅的に解説していきます。
「再建築不可物件の相続の際に何をすればいいかがわからない」という場合にも参考にしてみてください。
まずは相続する物件が本当に再建築不可物件であるかを確かめておくべき
再建築不可物件の相続を検討している場合、その物件が本当に再建築不可なのかを確かめておきましょう。「実は再建築不可ではなかった」という可能性もゼロではありません。
そもそも、再建築不可物件とは、新たに建物を建てられない土地のことです。再建築不可になる原因は、大まかに「接道義務を満たしていない」「市街化調整区域にある」の2つがあります。
| 原因 | 概要 |
|---|---|
| 接道義務を満たしていない |
幅員4m以上の道路に土地の間口が2m以上接していなければいけないという「接道義務」を満たしていない土地。 具体例 ・土地が道路とまったく接していない ・前面道路(敷地に面した道路)の幅が4m未満 ・道路に接している敷地の幅が2m未満 |
| 市街化調整区域にある | 物件が市街化を抑制する地域である「市街化調整区域」にある場合。物件の状態に関わらず、建物などの開発が制限される。 |
どちらかに該当している物件であれば、再建築不可物件となります。まずは相続予定の物件が再建築不可になる原因に該当していないかを確かめておきましょう。
なお、市街化調整区域については、市区町村の都市計画課に問い合わせることで確認できます。自治体によっては都市計画図をインターネットで公開しているため、「〇〇(自治体名) 都市計画図」などと検索して確かめてみてください。
最寄りの役所の建築課でも確認は可能
「相続予定の物件が再建築不可物件かどうかを確かめられない」という場合、最寄りの役所で確認してみるのもよいでしょう。役所の建築課に出向くことで、相続予定の物件が再建築不可物件であるかを確かめてもらえます。
役所で調べてもらう場合、下記のような書類が必要です。
- 登記事項証明書
- 地積測量図
- 公図
- 相続予定の建物の図面
いずれの書類も、相続予定の物件がある地域の法務局で用意できます。自力で調べるのが難しい場合、これらの書類を用意したうえで、最寄りの役所で確認することも検討してみてください。
再建築不可物件の相続にはさまざまなリスクがある!相続するべきかは慎重に判断するべき
再建築不可物件の所有にはさまざまなリスクがあるため、リスクを加味したうえで相続するべきかを慎重に判断するのが大切です。再建築不可物件を相続するリスクには、下記が挙げられます。
- 物件が古くなっても建て替えや増築、改築などを行えない
- 倒壊などによって近隣住民に悪影響を及ぼす可能性がある
- 仲介での売却が難しい
- 固定資産税が最大6倍に増える可能性がある
簡単にいえば、物件の状態がどれほど悪化しても修繕ができないうえ、手放したくても売却が難しいことが再建築不可物件を相続するリスクといえます。
また、近隣住民に悪影響を及ぼす可能性があることなど、他にもリスクがあるため、再建築不可物件であれば物件自体を相続しないことを考えるのも重要です。
ここからは、再建築不可物件を相続するリスクについて、それぞれ詳しく解説していきます。
再建築不可物件を相続した後に何も対策をせずにいると、現状よりも老朽化が進み、居住すら難しい状態になってしまいます。そのまま所有を続けると、将来的に自分の子どもや孫が再建築不可物件を相続することになる可能性もあります。
その場合、現状よりも活用や売却が難しくなるうえに、固定資産税などの出費負担を子どもや孫にかけさせてしまうリスクがあるのです。
子どもや孫に負の遺産を残さないためにも、活用の予定がない再建築不可物件であれば処分を検討することも手です。
物件が古くなっても建て替えや増築、改築などを行えない
再建築不可物件は、建物の建て替えや増築、改築などを行えない物件です。そのため、「建物が傾いてきた」などと建物の状態が相続後に悪くなったとしても、修繕を行えないデメリットがあります。
仮に老朽化が進んで建物が倒壊してしまった場合、その土地には建物を新たに建てることはできません。
再建築不可物件の多くは、接道義務が制定された1950年以前に建てられた物件であるため、築70年を超えているのが一般的です。すでに築古の物件であると考えられるため、建て替えなどが行えないリスクを踏まえると、長期間の居住には向きません。
長期間住むために再建築不可物件の相続を検討しているのであればおすすめはできないため、本当に相続するべきかを再度検討してみてください。
倒壊などによって近隣住民に悪影響を及ぼす可能性がある
再建築不可物件は建て替えなどができないことから、通常の物件よりも倒壊のリスクが高いといえます。また、老朽化が進んでいることも考えられるため、台風などの災害があった場合には外壁や屋根が剥がれてしまう可能性もあります。
万が一、倒壊などによって近隣住民に被害が出てしまえば、損害賠償を請求される可能性もあります。近隣住民に怪我などの被害を与えてしまう可能性があるうえに、それによって高額な賠償金を支払うリスクもあるため、再建築不可物件の相続は慎重に判断をしましょう。
仲介での売却が難しい
不動産を仲介で売却する場合、買い手が現れなければ売却はできません。つまり、需要が低い物件は、仲介で売却するのが難しいです。
再建築不可物件は建て替えなどが制限されることから、通常の物件よりも需要が低くなるのが一般的です。そのため、仲介で売却するのは難しくなると予測されます。
仲介で物件を売却するのは、不要になった不動産を手放すベストな方法といえます。その方法が取りづらく、場合によっては「手放したくても手放せない」という状態に陥る可能性があるのも、再建築不可物件を相続するリスクといえます。
固定資産税が最大6倍になる可能性がある
再建築不可物件に限らず、不動産を所有している場合、その所有者は毎年土地と建物にかかる固定資産税を支払わなければなりません。
通常の物件であれば、「一般住宅用地の特例」などの特例控除が適用されているため、固定資産税が減税されるのが一般的です。しかし、再建築不可物件を相続した後に建物が倒壊したり、更地にしたりすると一般住宅用地の特例が外れてしまい、固定資産税が最大6倍になってしまいます。
たとえば、評価額500万円の建物の場合、一般住宅用地の特例が適用されていると、「500万円×1/6×1.4%=約1万1000円」と固定資産税を算出できます。この場合で特例が外れてしまうと、固定資産税は「500万円×1.4%=7万円」と増えてしまうのです。
毎年の出費が高額になるリスクもあることを踏まえて、再建築不可物件を相続するかを検討してみてください。
相続前にできる再建築不可物件の対処法
相続前の状態であれば、再建築不可物件自体を相続しないことも可能です。リスクを踏まえて、再建築不可物件の相続をしない判断をしたのであれば、下記のような対策をとってみてください。
| 対処法 | 概要 |
|---|---|
| 代償分割 | 相続人の1人が再建築不可物件を取得する方法。ほかの相続人は代償金を受け取れる。 |
| 換価分割 | 再建築不可物件を売却して得られた売却金額を分割する方法。 |
| 相続放棄 | 遺産を相続する権利を放棄する方法。 |
ここからは、相続前にできる再建築不可物件の対処法をそれぞれ解説していきます。
ほかの相続人が再建築不可物件の所有を希望する場合は「代償分割」
代償分割とは、相続人の1人が再建築不可物件を取得して、ほかの相続人に代償金を支払って遺産を分割する方法です。
たとえば、500万円の価値がある再建築不可物件を2人で代償分割する場合、1人が再建築不可物件を所有し、もう1人には250万円が物件所有者から支払われます。
そのため、相続人のなかに再建築不可物件を所有したい人がいる場合には、代償分割であれば再建築不可物件自体は所有することなく相続が可能です。
ただし、代償分割の場合、再建築不可物件を所有する人に代償金を支払える能力があることが前提となります。代償金を支払えなければ、他の方法で再建築不可物件などの遺産を分割する必要があります。
相続人の全員が再建築不可物件を所有しないのであれば「換価分割」
換価分割とは、再建築不可物件を売却して、その金額を相続人で分配する方法です。たとえば、500万円の価値がある再建築不可物件を2人で換価分割する場合、物件を売却して250万円を2人に分配されます。
物件自体を売却するため、相続人の全員が再建築不可物件を不要とする場合に向いている方法といえます。
なお、前述したように仲介では買い手がつきづらいですが、専門の買取業者であれば再建築不可物件でも売却を期待できます。詳しくは「再建築不可物件を専門とする買取業者に買い取ってもらう」の見出しで解説していくため、換価分割をする場合には参考にしてみてください。
マイナスの財産のほうが多いなら「相続放棄」
相続放棄とは、遺産を相続する権利を放棄することです。相続放棄であれば、ほかの相続人の意向にかかわらず再建築不可物件を相続せずに済みます。
ただし、相続放棄をすると、再建築不可物件以外の遺産も相続できなくなるため、プラスの財産のほうが多い場合には向きません。「再建築不可物件以外にも多額の借金がある」といった場合であれば、相続放棄を検討してみてもよいでしょう。
再建築不可物件を相続する場合は相続の流れを確認しておく
財産を所有している人が亡くなると相続が開始され、相続人は亡くなった人が所有していた預金や不動産などの財産を引き継ぎます。再建築不可物件も相続財産とみなされるため、相続する際は所定の手続きが必要です。
- 財産と相続人を確定する
- 遺言書を確認する
- 遺産の価値を調べ
- 遺産分割協議を実施する
- 相続税の申告と相続登記をおこなう
このように再建築不可物件を相続する場合、さまざまな手続きが必要です。そのため、相続の流れを事前に把握しておくのがよいでしょう。
1. 財産と相続人を確定する
相続が開始されたら、まず所有している財産と相続人を確定する必要があります。被相続人が所有している財産は、すべて相続人で分割する必要があります。
もしも、相続の手続きが終了したあとに遺産の一部が見つかると、再度最初から手続きをし直す必要があります。そこで、まずは所有している財産の確定を行います。
財産の確定は、固定資産税通知書や配当金支払明細書などの郵便物から調査していくのが一般的です。
また、相続人も確定させる必要があります。今まで、親族の誰も存在を知らなかった相続人がいるケースもあるからです。
相続人の確定は、被相続人の戸籍謄本等を新しいものから順に遡って調べます。
2. 遺言書を確認する
相続では、被相続人の意思が重要視されます。そのため、遺言書で誰がどの財産を引き継ぐか記載されている場合は、遺言に従って遺産分割することが原則です。
そこで、遺言書が遺されていないかを確認しておきましょう。
3. 遺産の価値を調べる
遺産を分割するためには、その財産の価値がいくらかを知る必要があります。
事前に遺産の価値を調べておくことで、公平な相続を目指します。
不動産や株式などの財産がある場合は、相続開始時点での価値を評価しておきましょう。
ちなみに、再建築不可物件の価値を調べるためには、不動産の一括査定を受けるのがおすすめです。査定を受けたからといって、必ず売らなければいけないわけでもありません。
4. 遺産分割協議を実施する
遺産の価値が分かれば、それを基に相続人同士でどのように遺産を分割するかを協議し、決定します。
遺産分割は、相続人全員の同意がなければ決定しません。
後でトラブルにならないためにも、相続人全員の同意がなされたら、相続人全員の署名・押印がされた遺産分割協議書を作成します。
もしも、遺産分割協議がうまくまとまらない場合は、不動産問題に詳しい弁護士へ相談し、間に入ってもらうと交渉が進みやすくなります。
5. 相続税の申告と相続登記をおこなう
相続人の間で遺産分割がされたら、相続税の申告と相続登記を行います。
相続が開始されたら、10か月以内に相続人全員の署名・押印がされた申告書を作成し、相続税の申告と納付をする必要があります。
相続税申告書は、被相続人の住所地の所轄税務署に提出します。
相続財産のなかに不動産がある場合は、相続登記をおこないます。相続登記は、必ずしなければならないわけではありませんが、相続登記をしておかなければ、第三者に対して所有権を主張できません。
後の不要なトラブルを防ぐためにも、相続登記は必ずおこなっておくべきです。
再建築不可物件を相続する場合にはさまざまな税金がかかる
再建築不可物件を相続する場合、さまざまな税金がかかります。
- 相続税
- 登録免許税
- 固定資産税・都市計画税
「突然税金の請求がきた」とならないよう、再建築不可物件を相続する場合には支払いが必要な税金について確認しておくとよいでしょう。
相続税:再建築不可物件の評価額などによって決定する
相続税とは、被相続人が所有していた財産を相続した場合にかかる税金です。再建築不可物件だけでなく、現金や自動車、土地などを相続する場合にも原則相続税がかかります。
相続税は、財産総額から借金や葬式費用などを差し引いた金額が一定の金額(基礎控除額)を上回ったときに課せられます。
ただし相続税には、基礎控除という一定の非課税枠が設けられています。
被相続人が所有していた財産の評価額が、基礎控除額を超える場合のみ相続税がかかります。
相続税は、財産の評価額に応じて10~55%の税率がかけられ、評価額が高ければ税率も高くなります。他の税金に比べて納付額が高くなることから、相続の税金といえば相続税が中心となります。
ここからは、相続税の概算額を求めるための基本的な計算方法を解説していくため、再建築不可物件を相続する場合には参考にしてみてください。
相続税の基本的な計算方法
前述したとおり、被相続人が所有していた財産の評価額が基礎控除額を超える場合のみ、相続税を支払う必要があります。基礎控除額は以下の計算式で計算します。
たとえば、相続人が配偶者と子供2人の合計3人の場合の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。
基礎控除額を超える財産がある場合は、次の計算式で相続税を計算します。
たとえば、財産の評価額総額が1億円、相続人が配偶者と子供2人の合計3人、相続税率30%、控除額700万円の場合、相続税の金額は以下のようになります。
相続税率は次の表のとおりです。
| 財産の評価額-基礎控除額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
参照:国税庁「相続税の税率」
※上記の計算はあくまで概算の相続税を計算するためのものです。実際の納付額とは少し異なります。
登録免許税:再建築不可物件の評価額の0.4%
登録免許税とは、再建築不可物件の相続登記をおこなう際に必要な税金です。相続登記をする際に、法務局で印紙を購入する形で納めます。
登録免許税は「固定資産税評価額×税率0.4%」の式で算出でき、税率は評価額にかかわらず一定です。固定資産税評価額は、市区町村などの役所から毎年送付される、固定資産税課税明細書などに記載されています。
ちなみに、相続で取得した再建築不可物件に対して、不動産取得税はかかりません。
固定資産税・都市計画税:再建築不可物件の評価額によって決定する
再建築不可物件を所有すると、毎年、固定資産税と都市計画税がかかります。
固定資産税とは所有している固定資産に課される税金で、都市計画税とは都市計画事業や土地区画整理事業のために課される税金のことです。
1つの納付書で固定資産税と都市計画税の両方を支払うため、一般的には合算したものが固定資産税と考えている人も多いですが、それぞれ税率が異なります。
固定資産税と都市計画税の税金は、それぞれ次のように計算します。
- 固定資産税:固定資産税評価額×税率1.4%(原則)
- 都市計画税:固定資産税評価額×税率0.3%(原則)
税率は、自治体や物件の利用状況などにより異なります。再建築不可物件は、一般の物件に比べて固定資産税評価額が低いため、登録免許税や固定資産税・都市計画税は比較的低くなります。
相続した再建築不可物件を活用するための対策を講じておく
再建築不可物件を相続するのであれば、下記のような方法で物件を活用するのが得策です。
- 相続した再建築不可物件に居住する
- 賃貸物件として貸し出す
- 物件を再建築可能にする
- 再建築不可物件を専門とする買取業者に買い取ってもらう
- 再建築不可物件を寄付する
ここからは、相続した再建築不可物件を活用するための対策を紹介していきます。
なお、再建築不可物件は仲介では売れづらいですが、買取業者であれば売却に期待できます。また、最終的には寄付をする方法もあるため、再建築不可物件の活用が難しい場合には買取や寄付も検討しておくとよいでしょう。
相続した再建築不可物件に居住する
再建築不可だからといって、その物件に住んではいけないわけではありません。そのため、相続した再建築不可物件に居住することも1つの手です。
なお、適切な管理がされていない空き家は「特定空き家」として認定される場合があります。特定空き家に認定されると、固定資産税が最大6倍になるなどのリスクがあります。
しかし、居住している物件であれば特定空き家として原則認定されません。つまり、相続した再建築不可物件に居住することは、特定空き家に認定されないための対策にもなるのです。
賃貸物件として貸し出す
前述のように再建築不可物件の買い手は現れづらいですが、賃貸物件であれば人気が低いとは限りません。
普通に住めるのであれば、その物件が再建築不可物件であることは問題ではありません。むしろ、エリアや家賃設定によっては、すぐに入居希望者が現れる可能性はあります。
そのため、賃貸物件として貸し出せば、再建築不可物件であってもそのままの状態で活用できる可能性はあるのです。
物件を再建築可能にする
再建築不可物件になるのは、再建築不可になる原因があるためです。その原因を改善すれば、再建築不可物件も建て替えや増築などを行えます。
再建築可能になれば、通常の物件として扱われます。そのため、物件を再建築可能にすることも対策の1つです。
物件を再建築可能にする方法には、下記が挙げられます。
| 方法 | 概要 |
|---|---|
| セットバックをする | 再建築不可物件の土地の一部を道路にする工事を行い、道路の幅員を増やして接道義務を満たす方法 |
| 隣地の一部を買い取る | 道路と接する敷地の幅を2m以上になるよう、不足分を隣地の一部から買い取る方法 |
| 隣地の一部を借りる | 道路と接する敷地の幅を2m以上になるよう、不足分を隣地の一部から借りる方法 |
| 所有する土地と隣地の一部を等価交換する | 接道義務の不足分を隣地から借りて、代わりに同等の土地を譲る方法 |
| 43条但し書き申請をする | 周囲の空き地を道路として扱ってもらうための申請をして、接道義務を満たす方法 |
| 位置指定道路を申請する | 都道府県知事や市町村長などから、私道を法上の道路として認めてもらい、接道義務を満たす方法 |
下記の記事では、再建築可能にする方法を詳しく解説しています。相続した物件を再建築可能にしたい場合には参考にしてみてください。
再建築不可物件を専門とする買取業者に買い取ってもらう
買取業者のなかには再建築不可物件を専門とする業者があります。専門の業者であれば、仲介よりも再建築不可物件の売却に期待できます。
状態がよくない物件であっても買取の可能性はあるため、「老朽化が進んで居住が難しくなった」「賃貸に出したけど入居者が現れない」など、再建築不可物件の活用が難しい場合、専門の買取業者に依頼するのが得策といえます。
また、専門業者であれば、仲介よりも早く再建築不可物件を売却できるのが一般的です。あくまで目安ですが、一般的に仲介の場合は3か月〜1年程度の期間がかかるのに対して、買取であれば物件を売却できるまで1週間〜1か月程度となります。
早く確実に再建築不可物件を売却したい場合、専門とする買取業者に依頼することを検討してみてください。
再建築不可物件を寄付する
専門の買取業者であっても、必ず再建築不可物件を売却できるとは言い切れません。場合によっては買取も難しい可能性もあるため、その場合には再建築不可物件を寄付することも検討してみてください。
再建築不可物件の所有にはさまざまなリスクがあるうえに、処分が難しいデメリットもあります。本来は売却が望ましいですが、寄付であっても再建築不可物件を手放せます。
再建築不可物件を寄付する方法には、下記が挙げられます。
| 方法 | 概要 |
|---|---|
| 空き家バンクを利用する | 自治体が窓口になり、空きを利用したい人や購入したい人を紹介してもらえる方法。登録しておくだけで再建築不可物件の貰い手が現れる可能性がある。 |
| 自治体に寄付する | 物件がある自治体に引き取ってもらう方法。稀なケースではあるが、再建築不可物件の条件によっては寄付が認められる場合もある。 |
なお、下記の記事では売れない再建築不可物件を処分する方法を解説しています。「仲介を依頼したけど買い手が現れない」という場合には参考にしてみてください。
まとめ
再建築不可物件の所有には、さまざまなリスクがあります。そのため、使用用途が定まっていないのであれば、代償分割や換価分割といった方法で、そもそも再建築不可物件自体を相続しないことも1つの手です。
また、再建築不可物件を活用する方法も多数あります。「使用用途がないなら手放すべき」とはいえないため、再建築不可物件を相続するのであれば活用するための対策を講じておくことも大切です。
なお、買取業者のなかには、再建築不可物件を専門とする業者もあります。仲介よりも早く高値で買い取ってもらえる可能性があるため、相続後に再建築不可物件を活用するのが難しい場合には、専門業者に依頼することも検討してみてください。