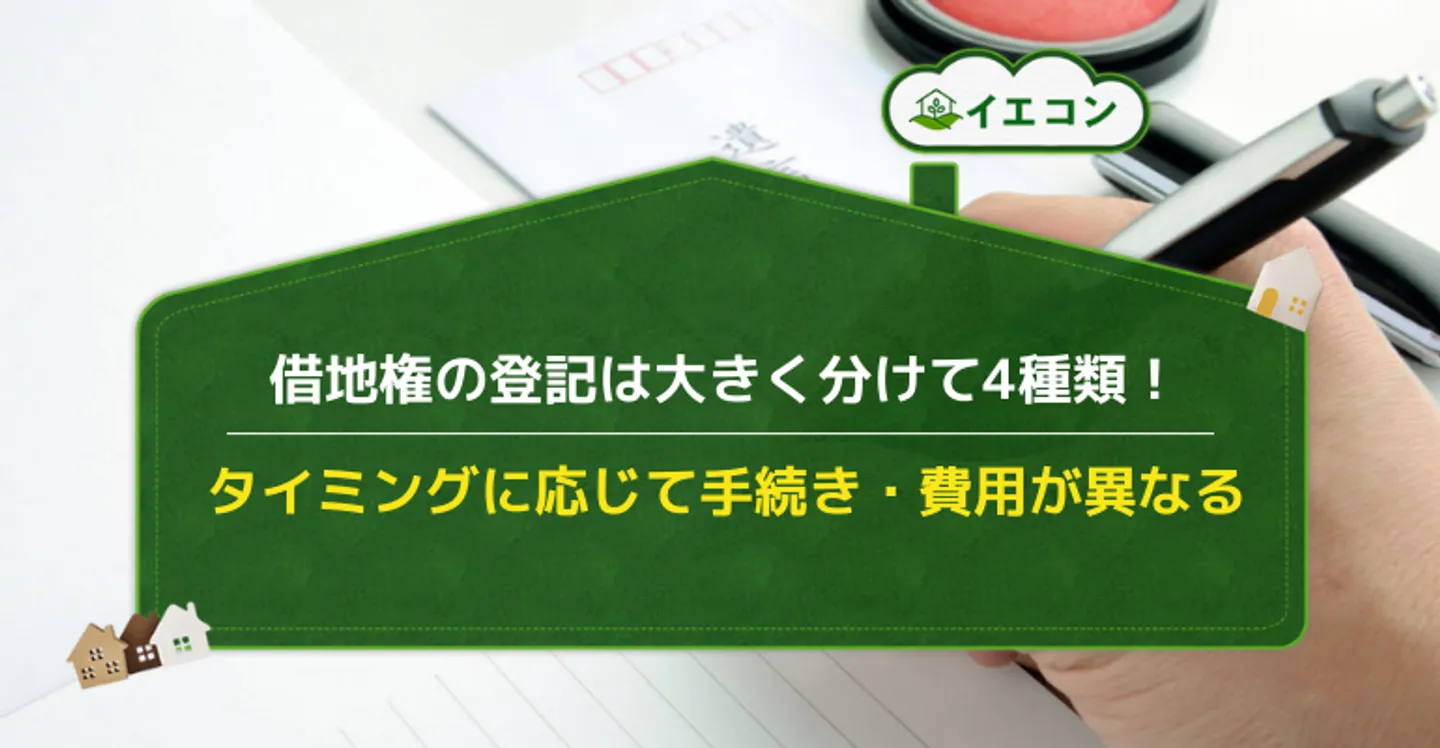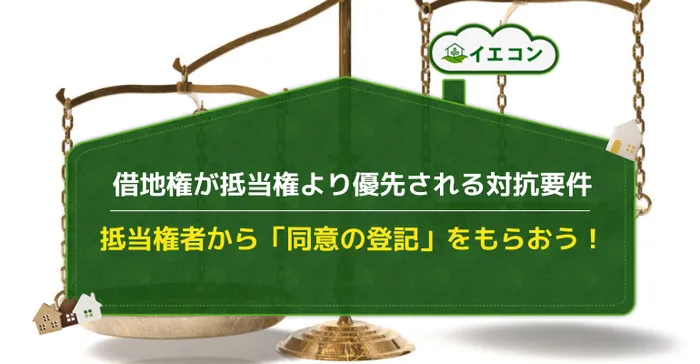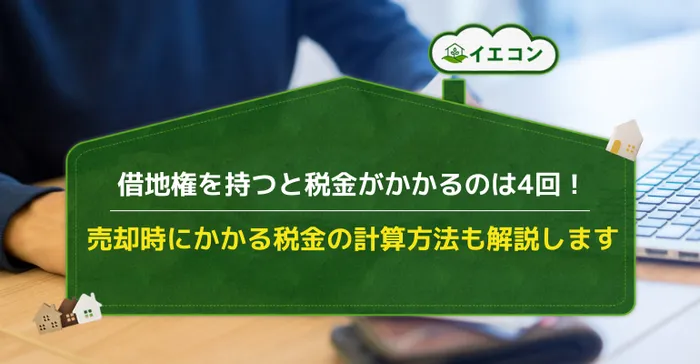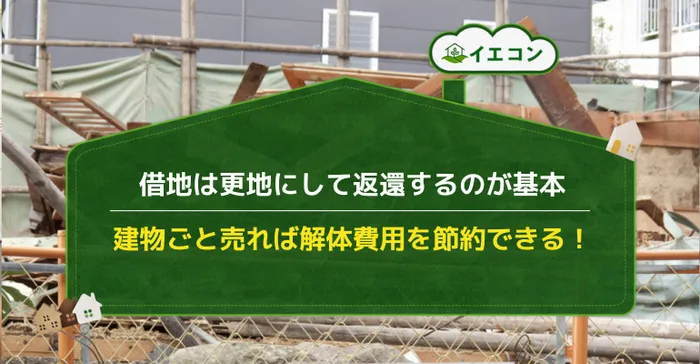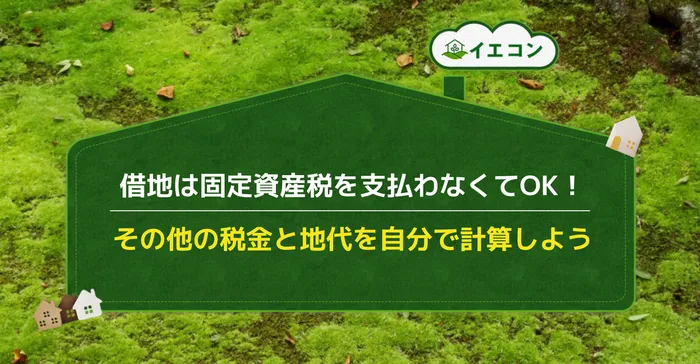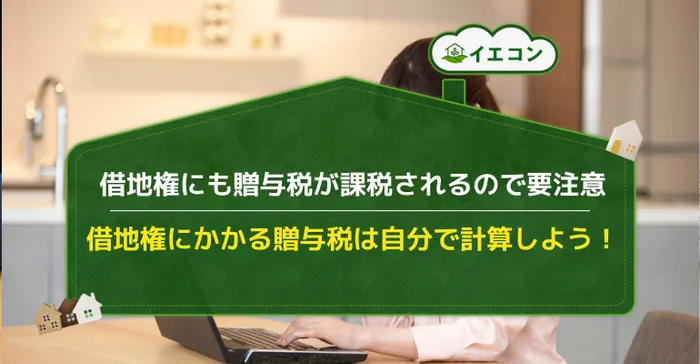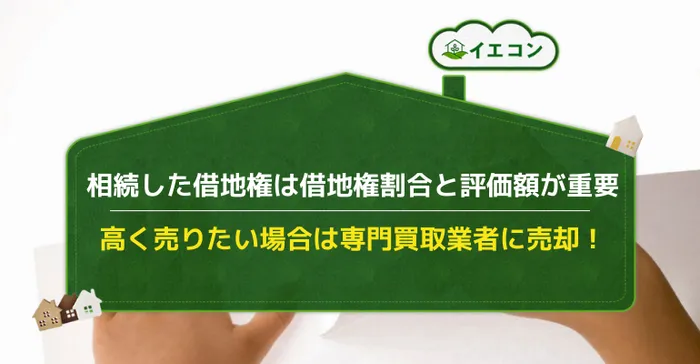土地を借りる権利を「借地権」といいますが、この借地権は法務局で登記することができます。
登記とは、不動産の権利関係を公に証明するための制度です。登記があることで、相続や売買などで権利トラブルが発生するのを防げます。
借地権の登記は、取得するタイミングや、あるいは借地契約を解除して返還するときにおこないます。
この記事では、借地権の登記が必要になるタイミングとや具体的な費用や手続きを具体的に解説します。
借地権の適切な取り扱いを把握して、権利トラブルを未然に防ぎましょう。
借地権は「地上権」と「賃借権」の2種類

借地権は他人の土地を借りて利用するために取得する権利のことです。そして、有償で借りるか、無償で借りるか、また借りる目的によって取得する権利は異なります。
このうち、建物を建てて利用するために取得する借地権は、「地上権」と「賃借権」の2つです。
それぞれの権利の性質や、取得することで発生する権利と義務について詳しく解説します。
1.地上権
地上権とは、他人の土地で竹木や、建物、道路、トンネルや電柱などの工作物を所有するために取得する権利です。
地上権を取得するために交わす契約が、地上権設定契約になります。
地上権は「物権」という種類の権利で、対象の物を直接的に、そして、排他的に支配することができるものです。
つまり、その物に対する権利は自分にのみ所属し、自分の意思で自由に使用できるということです。
そのため、地上権では、土地の所有者である地主を通さずに直接、借地を使うことができます。
地上権の場合は地主の協力のもと登記できる
土地に地上権を設定したときには、借地権者が地上権を登記するための協力義務が地主にはあります。
地主は、借地人から登記の協力を求められると、拒否することはできません。
そして、地上権を登記しておけば、底地権の譲渡や相続などで地主が変わったとしても関係なく、自由に使い続けることができます。
さらに、地上権を他人に貸したり、他人に譲渡したりすることも地主に承諾なく行うことができるのも特徴です。
地上権はこのような非常に強い権利として認められているため、実際には、居住用・事業用にかかわらず、建物所有を目的とした借地権で設定されることはまずありません。
そのため、一般的に「借地権」というと、次に解説する「賃借権」を指します。
2.賃借権
賃借権とは、賃料を払って他人の物を利用する権利です。
借りる対象が土地に限られているわけではなく、建物でもパソコンやカバンなどの不動産以外の「動産」も対象です。
賃貸借契約を締結することで取得でき、借地権の場合は特に、土地賃貸借契約書を地主と交わして設定されます。
賃借権は「債権」という種類の権利で、契約を交わした相手に対して、一定の行為を請求できる権利になります。
つまり、土地の賃借権であれば、契約の相手である地主に対して「土地を使わせてほしい」と請求できるだけです。
また、賃借権は原則、当事者間でのみ有効とされているので、地主が土地を第三者に譲渡したときには、その土地を譲り受けた新しい地主に対して「土地を使わせてほしい」と請求することはできません。
賃借権の登記の場合は地主に協力義務はない
賃借権の登記の場合、地主に協力義務はないため、賃借権が登記されることは稀です。
なぜなら、登記することで借地権の力が強くなることを地主が嫌がるからです。
しかし、借地人に極めて不利な状態となるため、借地借家法では、借地人が借地上の建物を自分名義で登記していれば、賃借権の登記をした場合と同じように、第三者への対抗力を持つと定めました。
建物の登記は借地人単独の意思で行えて、地主の承諾は必要ありません。
ただし、借地人の子ども名義や配偶者名義で登記した場合、借地権の第三者への対抗力は認められないので注意してください。
このように定められているので、建物の登記さえしていれば、地主が変わったとしても安心して借地を利用し続けることができます。
また、賃借権で発生する権利も地上権と違いがあり、地主に無断で賃借権を他人に譲渡したり、転貸したりすることは禁止されています。
違反した場合、借地契約の解除となる可能性もあるので注意してください。
借地権の登記が必要なタイミング
借地権を登記する目的は、その権利を確かに持っていることを第三者に主張するためで、専門的には「対抗要件」といいます。
そもそも、借地権を設定する契約は基本的に当事者間でのみ有効なものです。
そのため、地主が変わるようなことがあると、その新しい地主に借地権を主張できません。
したがって、新しい地主から明け渡しを求められた場合、それを拒否することができなくなります。
このような事態を避けるため、借地権を登記する必要があるというわけです。
そして、登記が必要なタイミングは次の3つです。
- 借地契約を締結したとき
- 借地権の譲渡を受けたとき
- 借地権を相続で取得したとき
- 借地契約を解消して更地で返還するとき
1.借地契約の締結または建物を建てたとき
更地の状態で地主と借地契約を結んだ場合、その借地権が地上権であれば、契約を締結したときに地主へ地上権設定登記の協力を要請します。
一方で、借地権が賃借権だったときには、賃借権を登記せず、その借地上の建物を登記することとなります。
そのため、賃借権の場合は、借地契約を結び、建物の建築が完成したときが、登記のタイミングです。
このときに行う登記を所有権保存登記といいます。登記の期限は原則、新築して1カ月以内です。
2.借地権の譲渡を受けたとき
第三者から借地権や借地権付き建物を購入したり、父親など親族から贈与されたりして借地権を譲り受けたときも、登記を行うタイミングです。
このときに行う登記は、所有権移転登記といいます。
借地権付き建物の売買契約を結び、売主と買主がそれぞれ取引の準備を整え決済・引き渡しを行うときに、併せて登記手続きもすることが一般的です。
また、借地権が賃借権の場合、譲渡するときには地主の承諾が必須です。
建物の名義を変えると、そのつもりがなくても、借地権を譲渡したことになります。
特に、建て替えと合わせて建物の名義を子どもに変更するような場合は、地主の承諾を得て行うように気をつけてください。
3.借地権を相続で取得したとき
相続が発生して、借地権を取得したときにも登記が必要です。この登記は「相続登記」と呼ばれていて、亡くなった方から相続人へ不動産の名義を変更する「所有権移転登記」のことです。
地上権であれば地上権の相続登記を、賃借権であれば建物の相続登記を行います。
このとき、借地契約書の名義変更までは不要で、地主に相続で借地権を取得したことを通知するのみで大丈夫です。
口頭でもよいですが、内容証明などの書面で通知したほうが将来的なトラブルを避けられるでしょう。また、譲渡とは異なり、相続の場合は、借地権の取得に地主の承諾は必要なく、名義書換料なども支払う必要はありません。
4.借地契約を解消して更地で返還するとき
借地上の建物を取り壊して、更地で地主に返還するときにも登記が必要になります。
このときの登記を滅失登記といいます。
借地上に建物が存在しなくなったことを示すことが目的です。
滅失登記を行うことで、その建物の登記簿は閉鎖されます。
滅失登記は、建物が滅失した日から1カ月以内に手続きしなければなりません。
もし、滅失登記の必要があるのに行わなかった場合、10万円以下の過料という厳しい罰則も定められているので注意してください。
ただし実際には、期限を過ぎても過料を支払うことはまずありません。ですが、滅失登記をしないデメリットは多いです。
たとえば、以下のものです。
・土地を担保に融資を受けようとしたときに、金融機関の審査が通らない
・土地を売却しようとしたときに、買主が住宅ローンを借りられない
滅失登記は忘れがちですが、手続きしなければ様々なトラブルになるので、確実に手続きを完了させるようにしましょう。
借地権の登記における費用と手続き

それでは実際に、先ほど紹介したタイミングで借地権を登記するときに必要な費用と手続きについてです。
一般的な借地権である土地賃借権の場合でお伝えします。
土地賃借権を登記することはまずないので、ここでの借地権の登記は、借地上の建物の登記のことです。
借地契約を交わしたときに必要な費用と手続き
借地契約を交わしたときは、建物の引き渡しを受けたときに「所有権保存登記」をおこないます。
このときに必要な書類は、下記のとおりです。
- 住民票の写し
登記申請書
委任状(司法書士に委託する場合)
住民票の写しは、建物の所有者の氏名、住所が一致しているかに使用します。
登記申請書は、所有権保存登記を法務局に申請するための書類です。
法務局のホームページからダウンロードできます。
登記手続きを司法書士に代行してもらう場合は、委任状の作成も必要になります。そのため、ご自身で登記申請を行うときには必要ありません。
また一定の条件を満たしている建物の場合、住宅用家屋証明書も併せて準備することで、登録免許税の軽減措置を受けられます。
住宅用家屋証明書の交付を受けられるかどうかは、その建物の所在地の市区町村役場で確認してください。
登記のタイミングは、建物が完成し、引き渡し・残金決済に合わせて行うことが一般的です。
そして、所有権保存登記に必要な費用は下記になります。
- 住民票の写し、住宅用家屋証明書などの発行手数料
- 登録免許税
- 司法書士報酬
書類の発行手数料は合計で2000円程度です。
登録免許税は、建物の固定資産税評価額の0.4%です。
住宅用家屋証明書の交付を受けられた場合、軽減税率が適用されて、固定資産税評価額の0.15%になります。
住居の大きさや立地条件などにもよりますが、約2万円程度です。
登記申請を司法書士に委託した場合に支払う報酬は、約2万~3万円です。
そのため、合計で5万円程度を見込んでおくとよいでしょう。
借地権を譲り受けたときに必要な費用と手続き
借地権を譲り受けたときに行う登記は「所有権移転登記」です。
必要な書類は下記になります。
- 不動産売買契約書・贈与契約書
- 登記識別情報通知書(登記済権利証)
- 固定資産税評価証明書
- 登記原因証明情報
- 登記申請書
- 住宅用家屋証明書
- 印鑑証明書(譲渡人)
- 住民票の写し(譲受人)
- 委任状(司法書士に委託する場合、譲渡人・譲受人どちらも)
このうち、譲受人の方で準備が必要な書類は住民票の写しと委任状のみです。それ以外の書類は譲渡人が準備します。
売買であれば売買契約書を交わして、物件の引き渡しがあったときに法務局へ登記申請します。
贈与の場合は、贈与契約書を交わしたときです。
そして、所有権移転登記で必要な費用は下記です。
- 住民票の発行手数料
- 登録免許税
- 司法書士報酬
所有権移転登記での登録免許税率は所有権保存登記とは異なります。
所有権移転登記での登録免許税率は、固定資産税評価額の2%で、住宅用家屋証明書がある場合は、軽減税率が適用されて固定資産税評価額の0.3%です。
たとえば、譲り受けた建物の固定資産税評価額が1,000万円で、住宅用家屋証明書があれば、登録免許税は3万円です。
所有権移転登記を司法書士に委託した場合に支払う報酬はおおむね5万~8万円になります。
そのため、所有権移転登記に必要な費用の合計は、8万~11万円程度です。
借地権を相続で取得したときに必要な費用と手続き
借地権を相続で取得したときには「相続登記」をおこないます。
ただし、登記申請の中身は借地権を譲り受けたときと同じ所有権移転登記です。
ただし、必要な書類や手続きは異なります。
遺言書があれば、その内容に従って相続財産を分配し、建物と借地権についても誰が相続するかが決定します。
もし、遺言書がなければ法定相続分に従って財産は相続されます。
このとき、相続人が1人であればそのまま所有権移転登記の手続きに進みます。
しかし、相続人が複数人いる場合、誰が建物と借地権を相続するのか、共有名義で相続する場合は、誰がどのような持ち分で相続するのかを決定するために、遺産分割協議を行う必要があります。
そして、相続登記で必要な書類は以下のとおりです。
- 被相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票の除票
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 遺言もしくは遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 借地権を相続する方の住民票の写し
- 委任状(司法書士に委託する場合)
- 固定資産税評価証明書
- 登記簿謄本
- 登記申請書
- 登記原因証明情報
亡くなられた被相続人の戸籍謄本は、法定相続人を確定させるために、出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。法定相続人の戸籍謄本は現在のもののみで大丈夫です。
また、相続登記で必要な費用は下記になります。
- 必要な書類の発行手数料
- 登録免許税
- 司法書士報酬
相続登記は所有権移転登記なので、登録免許税は所有権移転登記と同じです。
通常は、固定資産税評価額の2%で、住宅用家屋証明書がある場合は、軽減税率が適用されて固定資産税評価額の0.3%となります。
司法書士報酬は、売買や贈与で譲り受けたときよりも高いことが多く、約7万~10万円です。
申請だけでなく必要書類の取得まで委託すると、上記金額から1万円~1.5万円ほど上がります。
そのため、相続登記にかかる費用の合計は10万~15万円程度になります。
借地契約を解消して更地で返還するときに必要な費用と手続き
建物を取り壊して、更地にして借地を返還するときには「滅失登記」をおこないます。
滅失登記は、現在登記されている建物が存在しなくなったことを示すための登記なので、現在の登記簿に記載されている情報を正確に記入することが重要です。
滅失登記の申請書の内容が現在の登記簿の情報とわずかでも差があれば、修正しなければならず、余計な手間がかかるからです。
そして、法務局の担当者が現地調査を行い、何も問題なければ滅失登記の手続きは完了で、登記完了証が交付されます。
滅失登記で必要な書類は下記のとおりです。
- 登記申請書
- 建物滅失証明書
- 解体業者の印鑑証明書
- 解体業者の登記事項証明書
- 住宅地図
- 委任状(土地家屋調査士に委託する場合)
建物滅失証明書、解体業者の印鑑証明書、登記事項証明書は、建物を取り壊したときに業者から発行してもらいます。
住宅地図は、建物が建っていた場所を確認するために添付を求められる場合があります。
必須ではないので、登記申請する法務局に確認してください。
また、滅失登記にかかる必要は下記のとおりです。
- 登記簿謄本の取得費
- 土地家屋調査士報酬
登記簿謄本の取得は、現在の登記情報を調べるために必要な費用で、1通1,000円程度です。
滅失登記の申請を専門家に委託する場合、委託する相手は土地家屋調査士で、支払う報酬は4万~5万円程度です。
その他の登記申請と異なり、登録免許税はかかりません。
そのため、滅失登記にかかる費用の合計はほとんど土地家屋調査士に支払う報酬のみで、約4万~5万円になります。
以上、4つの登記の手続きと費用について解説してきました。どの登記もご自身で行うことはできますが、慣れていなければ分からないところや不安なところが出てきます。
安心して手続きを完了させるためにも、司法書士や土地家屋調査士などの専門家に委託することをおすすめします。
「相続」と「遺贈」では借地権の取り扱いが異なる

通常、亡くなった方の財産は法定相続人に受け継がれ、分配されます。
しかし、事情によっては法定相続人以外の方に財産を渡したいと思われることもあるでしょう。
そのときに利用される制度が遺贈です。
遺言によって、法定相続人以外に財産を贈ることをいいます。
遺贈は現金や物だけでなく、不動産も可能です。つまり、借地権も遺贈によって相続人以外に贈ることができます。
ただし、相続と遺贈では、借地権の取り扱いが異なっていて、その大きな違いは地主承諾の必要性です。
「相続」であれば地主の承諾は不要
借地権が法定相続人に受け継がれる「相続」であれば、地主の承諾は必要ありません。
地代や借地権の存続期間もそのまま相続人に承継されます。
そして、相続であれば、誰が借地権を相続するか決まったあとで、地主に通知するだけで問題ありません。
もちろん承諾が不要なので、承諾料や名義書換料といった費用も不要です。
「遺贈」であれば地主の承諾が必要
一方、借地権が相続人以外に受け継がれる「遺贈」となる場合、地主の承諾が必要になります。
遺贈は第三者への譲渡と同じにみなされるからです。
そのため、遺贈となればまず、地主に連絡し、譲渡の承諾を求めます。
その後、承諾があって遺贈は完了します。
このとき、承諾料の支払いも必要です。承諾料は借地権価格の10%程度が相場です。
また、もし地主の承諾を得られなかった場合は、通常の譲渡と同じように裁判所へ地主の承諾に代わる許可(代諾許可)を申し立てることになります。
ここで代諾許可を得られれば問題なく遺贈となります。
しかし、申立てが却下となると遺贈はできず、法定相続人に借地権が相続されます。
このように借地権の遺贈となると、地主との交渉が必要になるなど相続よりも手続きが複雑で大変なので、専門の不動産会社や弁護士へ手続きを委任することがおすすめです。
相続人が未成年者の場合、相続登記の申請方法が異なる
最後に、相続人が未成年者だった場合の相続登記の申請方法について解説します。
未成年者は法律行為ができないと民法で規定されています。そして、相続登記の申請は法律行為です。
そのため、相続人が未成年者だった場合、代理人を立てる必要があります。
このときの代理人は通常、親権者である親が務めます。
法定相続分・遺言に基づく相続登記であれば、親が代理人となり手続きを進められます。しかし、相続時に遺産分割協議が行われる場合、親は未成年者である子どもの代理人になれません。その理由を詳しく説明します。
親も相続人だった場合、遺産分割協議で未成年者の代理人にはなれない
親と未成年者の子どもが相続人だった場合、お互いに利益相反の関係になります。
たとえば、父・母・未成年者の子どもの3人家族で、父親が亡くなった場合で考えてみましょう。
もし、母親が子どもの代理人を務められる場合、母親は自分が有利になるように遺産分割協議を進めることができてしまいます。
それでは、子どもが不利益を被るかもしれません。
そのような状況になることを避けるために、子どもの代理人として親が遺産分割協議を行うことができません。
親と子どもが相続人の場合、子どもの代理人には「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
特別代理人の選任手続きに必要な書類と費用
特別代理人の選任のための手続きは、利益相反関係にある親と子どもが申立人となって、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
このときに必要な費用は子ども1人につき800円分の収入印紙です。そして、必要な書類は以下のとおりです。
- 申立書
- 未成年者の戸籍謄本
- 親権者または未成年後見人の戸籍謄本
- 特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票
- 遺産分割協議書案
特別代理人候補者についての条件は利益相反の関係でないこと、つまり、相続人でなければ誰でもよいということになっています。ただし実際には、子どもの祖父母やおじ・おばなどの親族を特別代理人にして遺産分割協議を行うことが一般的です。
親族への依頼が難しい場合は、司法書士などの専門家を特別代理人候補者にすることも可能です。
家庭裁判所は申し立て時に提出された遺産分割協議書案も確認します。
このとき、親が借地権を含む不動産を単独で相続する場合は、
「その不動産に対する子どもの法定相続分の価格に相当するその他の財産が子どもに相続されるようになっている」
など、遺産分割協議の内容が全体として子どもの不利になっていないかを慎重に判断し、特別代理人の選任を受理するか決めます。
遺産分割協議書案の内容が子どもに不利益なものである場合、特別代理人の選任は認められません。
また、特別代理人の選任申し立てのときには、遺産分割協議書案も作成しておく必要があり、申し立てが受理されたあとで遺産分割協議書の内容を変更することはできない点にも注意が必要です。
まとめ
借地権は、地上権と賃借権に分かれており、タイミングに応じて必要な手続きが異なるため注意しましょう。
借地権の登記とは、地主が代わったときでも借地を使い続けるために必要な手続きで、借地権の登記費用は最大でも15万円程度かかります。
一応、自分で登記することもできますが、申請情報に不備があると正しくなるまで繰り返し修正しなければなりません。
その手間と時間を考えれば、専門家である不動産業者に相談することをおすすめします。