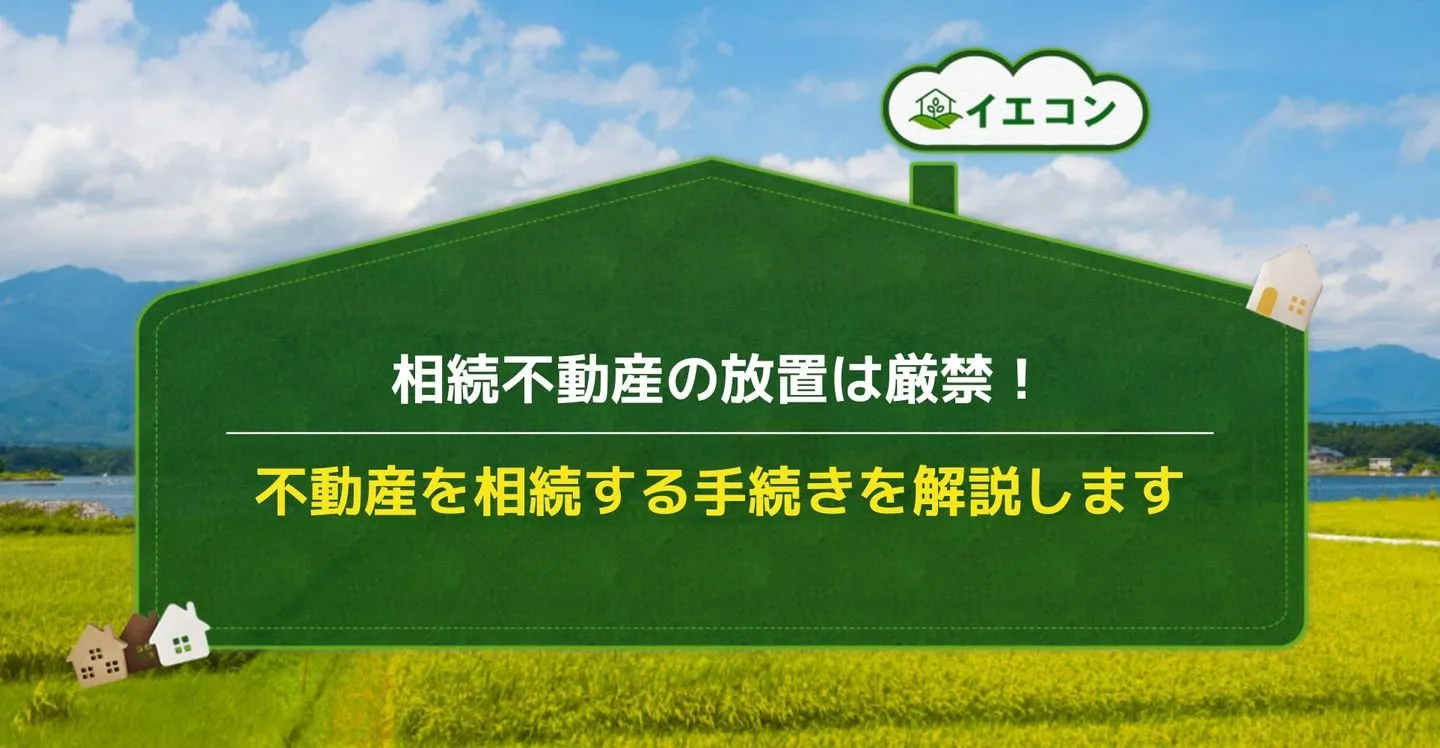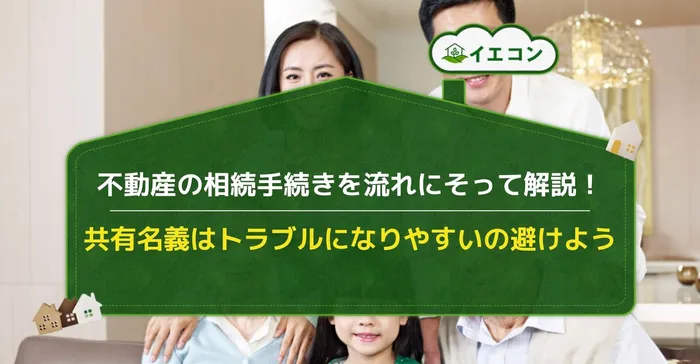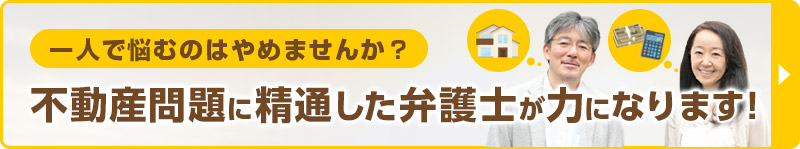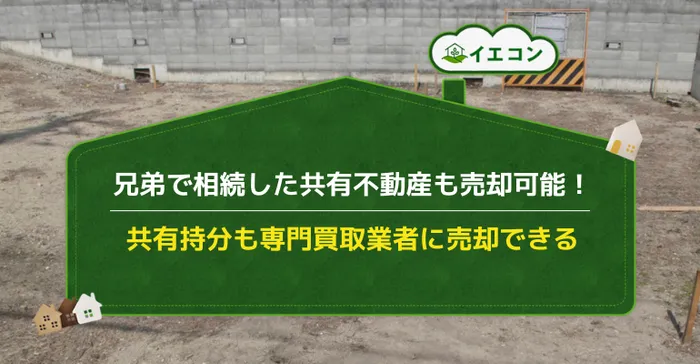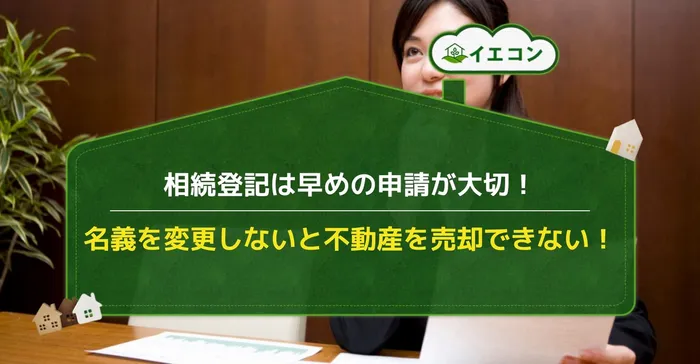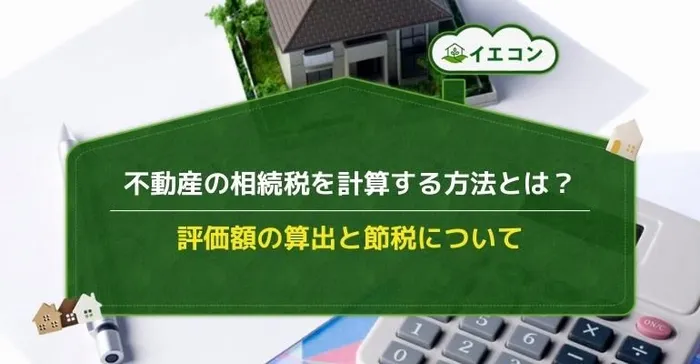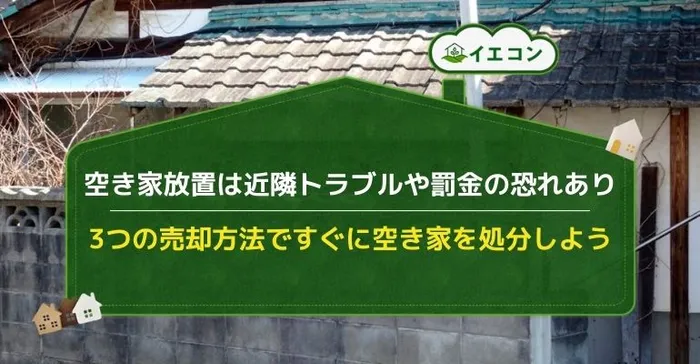実家の相続などで、住んでいる場所から遠方にある不動産を取得することもあります。
「相続手続きや売却のために現地へいくのが面倒」と思う人も多いでしょう。
しかし、相続不動産を放置しておくと、大きなリスクを抱えてしまうことになります。
不動産は放置せず、速やかに相続を済ませましょう。
また、相続不動産が不要という場合や、相続人同士でトラブルとなっている場合、弁護士と連携している買取業者に相談することもおすすめです。
不動産の相続手続きの流れ

まずは、不動産相続時の手続きを確認しておきましょう。
相続の基本的な流れは以下の通りです。
- 遺産分割をおこなう
- 不動産の相続方法を決定する
- 相続登記の手続きをおこなう
- 不動産にかかる相続税を計算する
相続の方法・手続きは、近くにある物件でも遠方にある物件でも違いはありません。
以下の記事でも不動産相続の基本的な流れを解説しているので、合わせて読んでおくことでより理解が深まるでしょう。
1.遺産分割をおこなう
遺産分割の方法は、相続人の数や遺言書の有無によって異なります。相続人が1人だけで遺言書もなければ、財産はすべてその相続人のものです。
相続人が複数人であり、遺言書がある場合、原則その内容に従います。遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割の内容・方法について話し合う「遺産分割協議」をおこないます。
遺産分割の方法・内容について相続人全員が同意したら「言った・言わない」のトラブルを避けるために「遺産分割協議書」を作成することが大切です。
遺産分割協議がまとまらなかったり、トラブルに発展してしまった場合は、相続問題に精通した弁護へ相談するとよいでしょう。
2.不動産の相続方法を決定する
不動産を相続する方法には、次の4つがあります。
代償分割・・・不動産を相続する人が他の相続人に代償金を支払う
換価分割・・・不動産を売却して代金を分配する
共有分割・・・不動産を複数の相続人(相続人全員)で共有して相続する
いずれの分割方法にも長所・短所があるため、なかなか結論が出せないかもしれません。
それぞれの分割方法については、以下の記事も参考にしてみてください。
3.相続登記の手続きをおこなう
不動産を相続したら「相続登記」の手続きをおこないましょう。
不動産の相続登記は法務局でおこないます。
相続登記の申請には、申請書の他に下記の書類を揃えなくてはいけません。
- 被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票(もしくは戸籍の附票)
- 相続人の住民票
- 相続人全員の印鑑証明書
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
- 固定資産税評価証明書
- 遺言書もしくは遺産分割協議書
相続登記の必要書類や申請方法については、以下の記事を参考にするとよいでしょう。
4.不動産にかかる相続税を計算する
不動産を相続したら、相続税を税務署に申告・納税する必要があります。不動産にかかる相続税を計算する際は「不動産の評価額」を算出し、あわせて適用できる「控除の特例」を調べましょう。
ちなみに、相続税の申告・納税は相続開始から10カ月以内におこなわなければいけません。もし期限を過ぎてしまうと、加算税や延滞税がかかってしまうケースもあります。
不動産相続における相続税の計算は複雑です。以下の記事では計算方法をわかりやすく説明しているので、ぜひ参考にしてみてください。
遠方の不動産を相続するときの注意点

遠方の不動産を相続するときは、下記の点に注意しなければいけません。
- 1.放置せず速やかに相続登記をおこなう
- 2.相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局へ申請する
- 3.空き家の場合は管理を怠らない
次の項目からそれぞれの注意点について解説していきます。
注意点1.放置せず速やかに相続登記をおこなう
2021年現在、相続登記は「いつまでに手続きをしなければならない」という期限は設けられていません。
そのため「不動産がある地方に足を運ぶのが面倒」などの理由によって、相続登記をおこなわず放置してしまう人も見受けられます。
しかし、相続登記をせずに放置しておけば、次のようなリスクを抱えることになります。
・次の相続が発生すると手続きが複雑になってしまう可能性がある
また、政府の方針として、2023年を目処に相続登記の義務化が決まっています。義務化された後は、期限や罰則の規定が設けられるので注意しましょう。
詳しいリスクや具体的な相続登記の方法は、下記の関連記事も参考にしてください。
注意点2.相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局へ申請する
不動産の所在地を管轄している法務局(もしくは登記所)でなければ、登記申請はできません。そのため、窓口申請するのであれば不動産のある法務局まで足を運ぶ必要があります。
ちなみに、管轄地域については法務局のホームページで確認できます。
遠くて現地まで出向くのが難しいという場合、郵送申請やオンラインシステムによる申請も可能です。
参照:法務局「管轄のご案内」
参照:法務省「不動産登記の電子申請(オンライン申請)について」
相続登記は司法書士に依頼するのが便利
平成17年より登記の郵送申請・オンライン申請が可能となったことで、遠方の不動産における相続手続きは比較的容易になったといえます。
しかし、申請や提出書類などに不備があれば、もう一度同じ手続きをやり直さなければならない可能性があります。
「申請方法がわからない」「書類に不備がないか不安」という人は、登記の専門家である司法書士に相談しましょう。
司法書士なら、必要書類の収集も含めてすべて任せることが可能です。そのため、手間をかけることなく登記を終わらせられます。
注意点3.空き家の場合は管理を怠らない
空き家は、管理を怠ると「老朽化により崩落で近隣住民がケガをした」「放火や空き巣などの被害に遭った」などのトラブルに発展する恐れがあります。
また、自治体から「特定空き家」に指定されるかもしれません。
特定空き家に指定されると「固定資産税の優遇措置が受けられない」「管理・修繕などの代執行がおこなわれ、多額の費用を請求される」ことがあります。
利用する予定のない不動産を相続したら、トラブルが起こる前に売却することをおすすめします。
遠方の不動産を売却する方法

遠方の不動産を売却するときの負担は「現地に行かなければならない」ことです。一般的に、売買契約の締結や決済・引き渡しなどは売主と買主が立ち会いのもとおこなわれます。
しかし、人によっては立ち会える日程を合わせられないケースもあるでしょう。
そのため、遠方の不動産売却を成功させるために何かしらの対策を考える必要があります。遠方の不動産を売却する主な方法は以下の通りです。
- 1.代理人を立てる
- 2.仲介業者と持ち回り契約を結ぶ
- 3.信頼できる買取業者に売却する
方法1.代理人を立てる
契約締結や引き渡しに立ち会えない場合、代理人に依頼するとよいでしょう。
例えば、相続した不動産の近くに住んでいる親戚や知人であれば、買主との日程を合わせやすいかもしれません。
また、弁護士に代理人を頼むことも可能です。弁護士に代理人を頼めば、法的な手続きをすべて任せられるので、手間なく不動産の売却が可能です。
方法2.仲介業者と持ち回り契約を結ぶ
持ち回り契約を利用することで、現地に行かなくても売買契約の締結や物件の引き渡しをおこなえます。
ち回り契約の流れは、以下の通りです。
- 仲介業者が重要事項説明書や売買契約書などの書面を作成
- 売主に契約内容を説明し、署名・押印をもらう
- 買主に契約内容を説明し、署名・押印をもらう
※2と3は順不同
ちなみに、手付金の授受については仲介業者が「預り証」を発行した上で受け取り、売主へ渡されます。
このように、持ち回り契約は非常に便利な契約のように思えます。しかし、全くリスクがないわけではありません。
持ち回り契約のリスクについては次の項目で解説します。
持ち回り契約のリスク
持ち回り契約ではお互いの顔を一度も見合わせることなく手続きが進んでしまうこともあります。そのため、売主も買主も不安を抱くことが少なくないでしょう。
信頼関係が築けないまま売買を進めたとしても、成約に至らない可能性が考えられます。
また、売主と買主が直接話し合う機会が少ないため、契約内容における認識のズレが生じてしまう恐れもあります。
電話やメールで売買契約に関する意向をうまく伝えられなかったり、細かい売買条件を口頭のみでおこなってしまうと「言った・言わない」のトラブルに発展しかねません。
持ち回り契約を利用する際は些細なことでも書面に書き起こし、仲介業者と綿密にコミュニケーションを取ることが大切です。
方法3.買取業者に売却する
「遠方の不動産売却を任せられる親戚や知人がいない」「手間をかけず早めに売りたい」という場合は、買取業者に売却することも検討しましょう。
とくに、弁護士と連携した買取業者なら、面倒な手続きも丁寧なフォローが可能で、スムーズに不動産を現金化できます。
遺産分割などの相続トラブルがあっても、一括で相談が可能です。
当サイトを運営するクランピーリアル・エステートも、弁護士と連携した不動産買取業者です。買主がなかなか見つからない不動産でも積極的に高額査定をおこなっているので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
不動産を現金化
売却したいなら
共有持分買取専門の
当社にお任せください!

海外在住中に不動産を相続したときの手続き

海外在住中に日本の産を相続した場合、相続や売却の手続きは非常に困難です。
時差などの関係で手続きの時間調整が難しいだけでなく、手続きをおこなうための必要書類等を揃えるのも大変でしょう。
海外在住中に不動産を相続したときは、以下の手続きが必要です。
- 住民票の代わりに在留証明書を発行する
- 印鑑証明書の代わりに「署名証明」をおこなう
- 納税管理人を選任する
住民票の代わりに在留証明書を発行する
不動産の相続・売却には被相続人と売主の住民票が必要です。海外に住みながら手続きをおこなう場合、住所を証明するための書類として「在留証明書」を発行しましょう。
在留証明書の発行手続きは、現地の日本領事館で取り扱っています。発行の際は以下の書類および手数料(日本円で1200円相当額)が必要です。
- 日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(有効なパスポートなど)
- 住所を確認できる文書(現地の官公署が発行する滞在許可証,運転免許証など)
- 滞在の開始時期や期間を確認できるもの
- 本文
発行にかかる日数や開館日、申請受付時間は、現地の事情によって異なります。詳しくは、発行の申請先である在外公館に問い合わせるとよいでしょう。
参照:外務省「在留証明」
印鑑証明書の代わりに「署名証明」をおこなう
不動産の相続・売却においては、印鑑証明書も必要です。
しかし、日本以外のほとんどの国では印鑑証明書という制度がありません。海外在住中に印鑑証明書が必要になったときは「署名証明(サイン証明)」を用いて手続きを進めます。
署名証明の手続きは、サインが必要となる書類や日本国民であることを証明できる書類(有効なパスポートなど)を持参した上で、領事館に直接出向く必要があります。
参照:外務省「署名証明」
納税管理人を選任する
相続によって財産を得た場合や、不動産を売却して利益を得た場合、海外在住中だとしても相続税、もしくは不動産の譲与所得税を申告しなければいけません。
海外に住みながらだとこれらの申告は困難であるため、納税管理人を選任して、代わりに申告してもらう必要があります。
納税管理人は、個人でも法人でも構いません。一般的には、税の専門家である税理士に依頼します。
納税地を管轄する税務署に、届出書を提出して申請します。届出書を作成する際は国税庁が雛形を公表しているので、参考にするとよいでしょう。
参照:国税庁「海外転勤と納税管理人の選任」
参照:国税庁「所得税・消費税の納税管理人の届出書」
まとめ
利用価値のない遠方の不動産を相続した場合、なかなか現地に出向けないなどの理由で、管理を怠ってしまうこともあるでしょう。
しかし、管理をせずに放置していると、老朽化による建物の崩落で近隣住民にケガをさせたり、放火や空き巣などの被害に遭う恐れもあります。
相続不動産が不要であれば、売却も検討するとよいでしょう。代理人や持ち回り契約を利用すれば、売却時の立ち会いも不要です。
また、弁護士と連携した買取業者に相談すれば、相続から不動産売却まで、総合的なサポートをしてもらえるのでおすすめです。