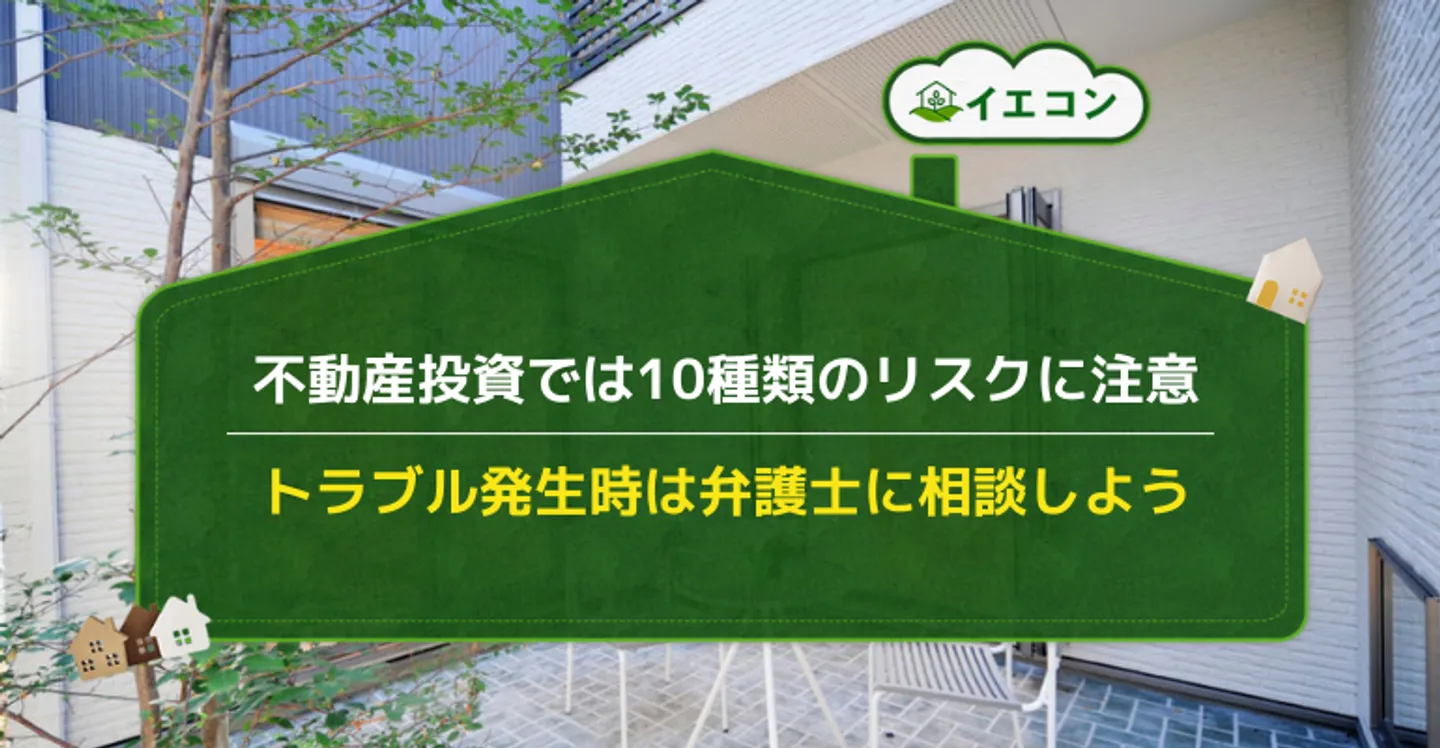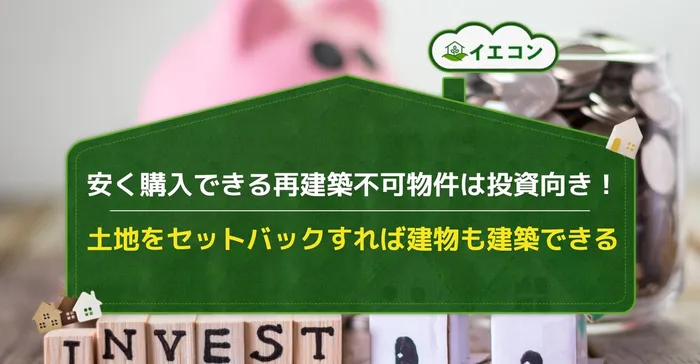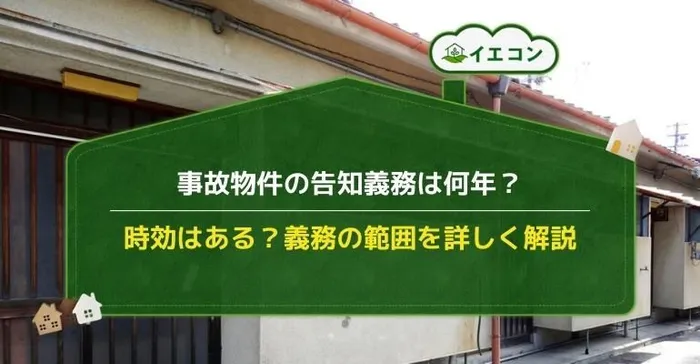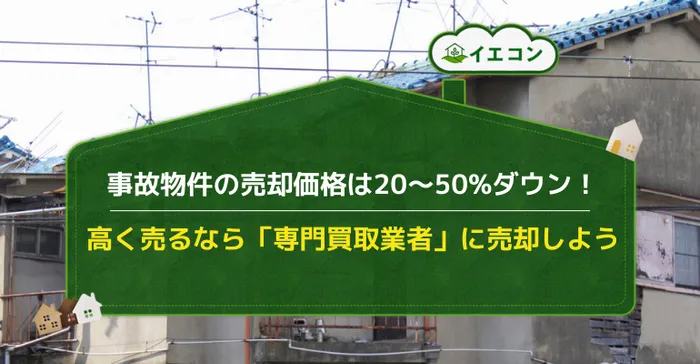どんな投資も、リスクなくしてリターンを得ることはできません。
しかし不動産投資は注意するべきリスクの種類が多く、リスクの程度も大きい傾向にあります。
不動産投資で考えられるリスクと、その対策として実践できることをご紹介します。
不動産投資に関係するリスクは多い

投資にも様々な種類がありますが、不動産投資は多方面にリスクのある投資です。まず言えることとして、他の投資と比較して一口の投資金額が大きくなりがちです。
そのため粗悪な物件をつかまされたり、身の丈に合わない物件を購入したりしてしまうと、自己破産に追い込まれてしまう可能性もあります。
投資対象が建物などの不動産となるため、失敗や損失が発生した場合も容易には撤退できません。手仕舞いが難しいという面でも、不動産投資のリスクは大きいと言えるでしょう。
不動産投資は、景気や入居者、周辺環境の変化など、投資家自身がコントロールできない要因でリターンが左右される特質も持っているため、リターンの幅は常に大きく変動する可能性があることを覚悟しておく必要もあります。
不動産投資の前に理解するべき10のリスク

ここからは、不動産投資の前に確認しておくべき主要な10のリスクと、対策としてできることの例を解説します。
リスク1:多額の借金
不動産投資はまず、投資物件を購入することから始まります。少なくとも数百万円、高ければ億単位にもなる物件購入費用を、現金で用意できる人は少ないでしょう。たいていの場合は、借金をして物件購入することになります。
高額の借金ですから、誰もが融資をしてもらえるわけではありません。お金を貸す金融機関にとってもリスクがあるため、審査は非常に慎重に行われます。そのため、審査を通過すると安心し、自分の投資計画に太鼓判を押してもらったように思えてしまうかもしれません。
しかし、自分にはどうにもできない理由で物件の価値が下落し、家賃収入が減額する可能性はあります。収支がマイナスになる期間もあるかもしれません。変動金利で借金をするなら、将来金利が上昇すれば返済するべき金額も増えます。
借りたからには、どんな状況になろうとも返済する義務があります。不測の事態によって収入が大きく変動する不動産投資において、多額の借金を負うことはリスクとなります。
対策としてできることは、できるだけ自己資金の割合を高め、借金の額を抑えることです。借金でまかなう割合が多ければ多いほど、リスクも高まると言えるからです。収入が安定してきたら、可能な限り繰り上げ返済を行うのもリスク回避になります。
金利がどのタイミングで上昇するかは予測しがたいものです。早め早めに返済を進めておくなら、将来の金利上昇で返済するべき金額が膨れるリスクを回避できます。
リスク2:空き室による無収入
不動産投資は、家賃収入から諸経費を差し引いたものが利益となります。どんな物件でも、空き室になるタイミングは必ずあります。物件に空き室があれば、空き室分の家賃収入は途絶えてしまい、利益は減ります。
空き室が多くなり、なかなか次の入居者が決まらないと、収支がマイナスになってしまうかもしれません。
対策としてできることは、できるだけ空き室の期間が少なくなるような物件を選ぶことです。
例えば、アパートではなく建物の質やセキュリティが優れているマンションにすることや、駅近、または商業施設や学校・病院などが近隣にある利便性の良い土地で、将来的にも賃貸物件のニーズが継続しそうな立地の物件を選ぶことができるでしょう。
家賃設定を相場よりも少し抑え目にすることで、入居者が決まりやすく、なおかつ退去しにくいように工夫することもできます。
空き室のリスクを抑えるためには、物件の管理を任せる管理会社の選定も重要です。たとえ物件自体の価値が高くても管理会社の質が低ければ、空き室率は上がります。
建物の維持管理や清掃のレベルが高い管理会社を選び、入居者にとって住み心地が良く、内見者にとって印象の良い状態に整えてもらえるようにしましょう。
管理料の安い管理会社には要注意
管理会社を選定する際には、さまざまな点を確認する必要がありますが、なかでも月額管理料が安い管理会社には要注意です。不動産の管理会社は星の数ほど存在しており、日夜物件の取り合いとなっています。
そのため、不動産を所有していると、さまざまな管理会社から管理を任せて欲しいという内容のダイレクトメールや営業電話が頻繁にかかってくるようになります。
初心者投資家の中には、管理料が少しでも安い管理会社に任せて、その分利回りを良くしようと考える人がいますが、これは大変危険です。
管理会社が物件の取りあいをする際に、サービスに自信がない管理会社は管理料を安くして営業するしかメリットがないため、とにかく管理料を下げて営業をしてきます。
ただ、あまりに安すぎる管理料では適切な管理はできません。一部の悪質な管理会社は、安い管理料をエサに解除する際の違約金を高額に設定した管理委託契約を結び、その後適切な管理をしないというケースもあるようです。
管理料の目安は、家賃の5%程度です。それを下回るような金額を提示してくる管理会社は、まともな管理をしてくれない可能性もありますので、契約を結ぶ際には十分注意しましょう。
リスク3:賃料滞納による無収入
物件に入居する人が、家賃の支払いを滞納することもあります。滞納があると当然、収入は減ってしまいます。滞納が何カ月も続けば強制退去などの法的手続きも視野に入れなくてはならなくなり、そのための費用も基本的にはオーナーの負担となります。
対策としては、入居審査を慎重に行うことが挙げられます。収入や勤務先だけでなく、できれば直接会ってその人の人柄を見ておくこともできるでしょう。親や子、兄弟など、近親者が保証人や緊急連絡先となっているかどうかも重要です。
管理会社の中には、賃料滞納があった場合に賃料の一部または全額を保証しているところもあります。万が一に備えて、賃料保証を実施している管理会社を選ぶこともできます。
家賃滞納を回避する方法
入居審査を厳しくすることも大切ですが、あまり厳しくしすぎると却って不動産会社から紹介を敬遠されてしまう恐れもあります。
終身雇用が崩壊している現代においては、入居時の勤務先や年収はそこまでの安心材料ではありません。入居中に転職する人も多いため、あまり入居時の属性にこだわり過ぎるのも問題です。
そこで重要になってくるのが、滞納が発生した際の対応です。家賃滞納者は、まったく支払う能力がないわけではなく、支払う能力はあるけれども、ほかの借金を優先して支払っているケースが多いのです。
滞納が発生した際に、すぐに督促連絡をせずに、数日放置したりすると賃借人としては「多少家賃が遅れても大丈夫なんだ」と勝手に都合よく解釈をします。
すると、次回以降、カードの支払いや何らかの返済が発生した際に、家賃の支払いを後回しにされてしまうのです。
そのため、家賃滞納が発生したらすぐに督促して入金を促すことが重要です。「1日たりとも遅れてはならない」と賃借人に意識づけることが何よりの家賃滞納予防になります。
また、連帯保証人についても躊躇してなかなか連絡をしない投資家が多いのですが、連帯保証人については、通常の保証人とは違い、「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」という権利がないため、滞納が発生したら連帯保証人にも督促することが可能です。
家賃滞納者は対処の仕方次第でかなりの率で予防することができるということを、ぜひ覚えておいてください。
リスク4:経年劣化や環境変化による物件価値の下落
新築の物件も、経年劣化によって価値は下落していきます。物件の周辺環境の変化によってニーズが減少してしまい、価値が下落することもあります。
経年劣化による価値の下落はどんな物件でも避けられないものです。少しでも価値を維持するためにできる対策は、できるだけ新しい物件を選ぶこと、頑強な構造の建物を選ぶこと、またメンテナンスにおいて信頼のおける管理会社を選ぶことなどです。
物件の周辺に大規模なマンションなどの建設予定はないか、人口が増加する見込みか減少する見込みか、利便性が良い立地か、利便性が増す要素はあるかなど、周辺環境に注意することも重要です。
経年劣化対策と併せて環境についても考えるなら、年数が経っても価値が下がりにくい優良物件を選ぶことが大切です。
修繕する場合は費用対効果に注意
物件価値を下げないためには、適切な修繕は必要ですが、あまりにも修繕費用をかけすぎてもマイナス効果となります。
とくに投資用マンションの場合は、定期的な大規模修繕のために修繕積立金を各オーナーから徴収して積み立てています。ただ、過剰な修繕は修繕積立金の値上がりの原因となります。
修繕積立金が値上がりすると、利回りを圧迫するため結果として売却する際の価格が下がってしまう可能性があります。修繕についてはただやれば良いというものではなく、適切な金額の範囲内で、適切な修繕を行うことがとても重要です。
管理会社によっては、大規模修繕を行って利益を上げるために、年々修繕積立金の値上げを打診してくるケースもありますので、十分に注意しましょう。
リスク5:災害による物件の損傷
経年劣化と並んで防ぐのが難しいのは、災害による物件の損傷というリスクです。地震や土砂災害、台風による浸水、地域によっては雪害や津波、竜巻による被害などが挙げられます。
日本は地震大国です。どの地域の物件であれ、地震保険に加入しておくべきでしょう。また、できるだけ地盤が強く、耐震性能の高い物件を選ぶこともポイントです。
土砂災害警戒区域で河川の近い物件は、地震や台風によって甚大な被害を受ける可能性が高まります。そのような区域は水場が近いことにより地盤も緩くなっている可能性があるため、極力避けることがリスク回避になります。
豪雪地帯であれば、雪への備えを万全にした建物を選ぶことが重要です。海が近く津波が心配される地域であれば、しっかりと防波堤の設置がなされている地域か、もしくは高台に位置している物件を選ぶことが大切でしょう。
リスク6:犯罪による物件の損傷
空き巣や強盗、放火、物件内での殺人事件などの犯罪も、物件の価値を大きく下げかねないリスクです。
対策としてできることは、建物の周囲や共用部分に防犯カメラを設置し、警備会社のセキュリティシステムを導入するなどして常時監視し、物件内外での犯罪を予防することでしょう。
物件の選定時には、警察や行政が公表している犯罪情報マップなどを参照して、検討している物件の周辺の治安を確認しておくこともできます。治安に問題がありそうな物件であれば、厳重なセキュリティを施して入居者を安心させる必要があるでしょう。
しかし、殺人事件や暴力事件などの犯罪に巻き込まれそうな人を、入居審査の段階で見極めることはほぼ不可能です。そこで、物件自体の価値やニーズに自信が持てるのであれば相場よりも少々家賃を高く設定し、高級賃貸住宅として募集することもひとつの手段です。
ひとつの傾向として、殺人や暴力に発展するような大きな犯罪に巻き込まれる人の中にはいわゆる低所得層の人も多く、家賃の安い物件に住んでいる人が多く見られます。
対して、ある程度の家賃を支払うことができる人というのは、社会的にしっかりとした立場を築いていて常識があり、人間関係も正常にこなしている可能性が高いとも言えます。
物件が「事故物件」と呼ばれてしまう原因となるような犯罪の発生を予防したいと思うのであれば、自信を持った家賃設定にしてみるのもひとつの方法でしょう。
リスク7:火災による物件の損傷
人が生活する以上、火災が発生するリスクは常にあります。物件からの出火でないとしても、近隣の住戸から飛び火して火災になってしまうこともあるでしょう。まれなことではありますが、放火による火災の可能性もあります。
火災への対策としてできるのは、補償の手厚い火災保険や損害保険に加入しておくことです。補償範囲は保険会社によって大きく異なるため、保険料だけで決めずに補償内容をよく比較検討する必要があります。
保険への加入は、入居者にも義務付けることが大切です。火災を出してしまった場合には、少なくても数百万円、時には数千万円の修復費用が必要になります。
その費用を自分の財産からすんなり支払える入居者は少なく、保険加入をしてもらわなければ「ない袖は振れぬ」という状態になってしまうかもしれません。
保険料は2年間で1万~2万円程度と、それほど高額ではありません。現在はほとんどの賃貸物件で損害保険への加入が必須となっているため、保険料の負担を理由に入居をやめる人はほとんどいないはずです。
対策としてできるもうひとつの点は、耐火構造の物件を選び、延焼しにくい建具や設備を導入することです。そうするなら、火災が起きたとしても被害を最小限に食い止めることができるでしょう。
投資家も火災保険は必ず加入する事
賃借人に火災保険に加入してもらうことはとても重要ですが、実はそれだけでは不完全です。というのも、賃借人の加入している火災保険では、損害の全額の賠償を受けることが難しいからです。
仮に室内で賃借人が火事を起こした場合、賃借人の火災保険の「借家人賠償」を適用して、損傷した室内の設備関係の復旧を行います。ただし、この際保険金として支払われるのは、復旧に必要な工事費用全額ではなく、損傷した設備関係の「時価」となります。
つまり、新品に交換する費用すべてが補償されるわけではなく、経年に応じた分が控除されてしまうということなのです。法律上、賠償責任があるのは時価が基本なので、工事費用全額を賃借人に負担させることができません。
そこで必要になってくるのが、投資家側でも火災保険に加入することです。投資家も火災保険に加入していれば、工事費全額と借家人賠償で補償される時価の「差額」について、保険会社から賠償を受けることができます。
火事自体は投資家に非はありませんが、保険に加入していないと大きな出費を伴いますので十分注意しましょう。
リスク8:シロアリによる物件の損傷
建物は、シロアリによる浸食被害に遭う可能性もあります。
シロアリのリスクがより高まるのは木造の建物ですが、鉄筋コンクリート造りなどの建物でも地中のわずかな隙間からシロアリが侵入し、断熱材などの壁材を食い荒らすことがありますので油断はできません。
シロアリ被害によって物件の基礎や支柱は弱くなり、もろくなってしまうため非常に危険です。軽度の地震や台風で大きく損傷するリスクも高まりますし、害虫の発生という現象は衛生面を考えても望ましくありません。
シロアリの被害は、室内でシロアリを見かけるなどして異変に気が付いた時には、すでにかなり浸食が進んでしまっていることが大半です。
シロアリのリスクを抑えるための対策は、定期的な点検と、予防のための薬剤散布などを怠らないことです。少しでもシロアリの浸食被害を確認したなら損傷部分の補修とシロアリ駆除を早急に行い、被害の拡大を防ぎます。
シロアリは木造だけの問題と考えず、木造以外の構造の物件でも抜かりなく対策を講じておきましょう。
リスク9:入居者の迷惑行為、自殺・孤独死
入居審査をどんなに慎重に行ったとしても、入居者による迷惑行為は起こりえます。入居者やその家族が騒音などの迷惑行為を起こしたり、反社会的勢力の一員であったりするかもしれません。
近年増えている「ゴミ屋敷」も、入居者によって物件の価値が下げられてしまう要因のひとつです。美観を損なうだけでなく、悪臭や害虫の大量発生などによって他の優良な入居者が退去してしまうようでは、オーナーにとっては踏んだり蹴ったりです。
入居者が物件内で自殺、孤独死してしまうリスクもあります。必ずしも入居者の悪意によるものではないとは言え、自殺や孤独死のあった物件は事故物件となり、なかなか次の入居者が決まりにくくなります。
遺体が発見されるまでに時間が空けばあくほど、原状回復のための清掃費用や補修費用も高額になり、オーナーに重くのしかかってきます。
対策としてできることはそう多くはありませんが、やはり入居審査を慎重に行い、迷惑行為の心配が少ない人を厳選することが大切です。身元がしっかりしており、何かあった際に連絡できる近親者がいることも条件の一つにするとよいでしょう。
何カ月、あるいは何年も自殺や孤独死の遺体が発見されないという事態を防ぐためには、日頃から物件内のコミュニティを確立しておき、何か異変があればいち早く察知することのできる環境をつくっておくことも有効です。
可能であればオーナー自身が物件を定期的に見回り、郵便物や新聞が異様に溜まっている部屋はないか、騒音や悪臭などの異変が感じられる部屋はないかを自らの目で確認することもできるでしょう。
リスク10:管理会社の倒産
物件の管理を任せていた管理会社が倒産してしまう、というリスクもあります。多くの場合、管理会社が家賃を代理で回収しているため、倒産されてしまうと回収済みの家賃がオーナーのもとに戻ってこなくなるリスクもあります。
空き室期間の家賃保証や滞納保証を設けている管理会社であっても、倒産されてしまっては何にもなりません。
対策としては、できるだけ営業実績の豊富な管理会社を選ぶことができるでしょう。管理会社としての営業実績が長いということは、顧客を満足させる管理サービスを長期間に渡って提供し続けているという証拠でもあります。
そのような管理会社は、簡単に倒産することはないでしょう。優良な管理会社に管理してもらうには、ある程度の手数料を支払うことを覚悟しなければなりません。手数料の安さにひかれて「安かろう、悪かろう」の管理会社を選ぶことのないようにしましょう。
家賃保証に頼りすぎると危険
初心者投資家にとって、家賃保証はとても魅力的なため、利用する人も多いと思います。ただし、家賃保証に頼りすぎると大きな痛手を負う可能性もありますので注意が必要です。
家賃保証については長期的な契約となるケースが多いのですが、保証される家賃額については定期的な見直しが行われます。そして殆どの場合、見直しのタイミングで保証額が値下がりしていきます。
購入当初は、投資家に購入を決断してもらうために相場よりも高めの保証額を提案してくれますが、購入したあとの見直しのタイミングで現実的な保証額を突きつけて値下げを要求してくるケースがとても多いのです。
家賃保証を利用する場合は、自分自身でよく周辺相場を調べた上で、不動産会社が提示してきている保証額が現実的な金額なのか、それとも相場よりも高いのかをよく認識し、相場よりも高い金額で提示されている場合は、将来的に値下がりすることも念頭に置いて資金計画をたてることが重要です。
また家賃保証契約は、不動産会社に部屋を貸す賃貸借契約の側面もあるため、投資家側から簡単には解除ができないケースがあります。家賃保証契約を締結する際には、解除する場合の手順や違約金の金額などについて、十分確認しておくようにしましょう。
まとめ リスク回避やトラブル解決は弁護士に相談を
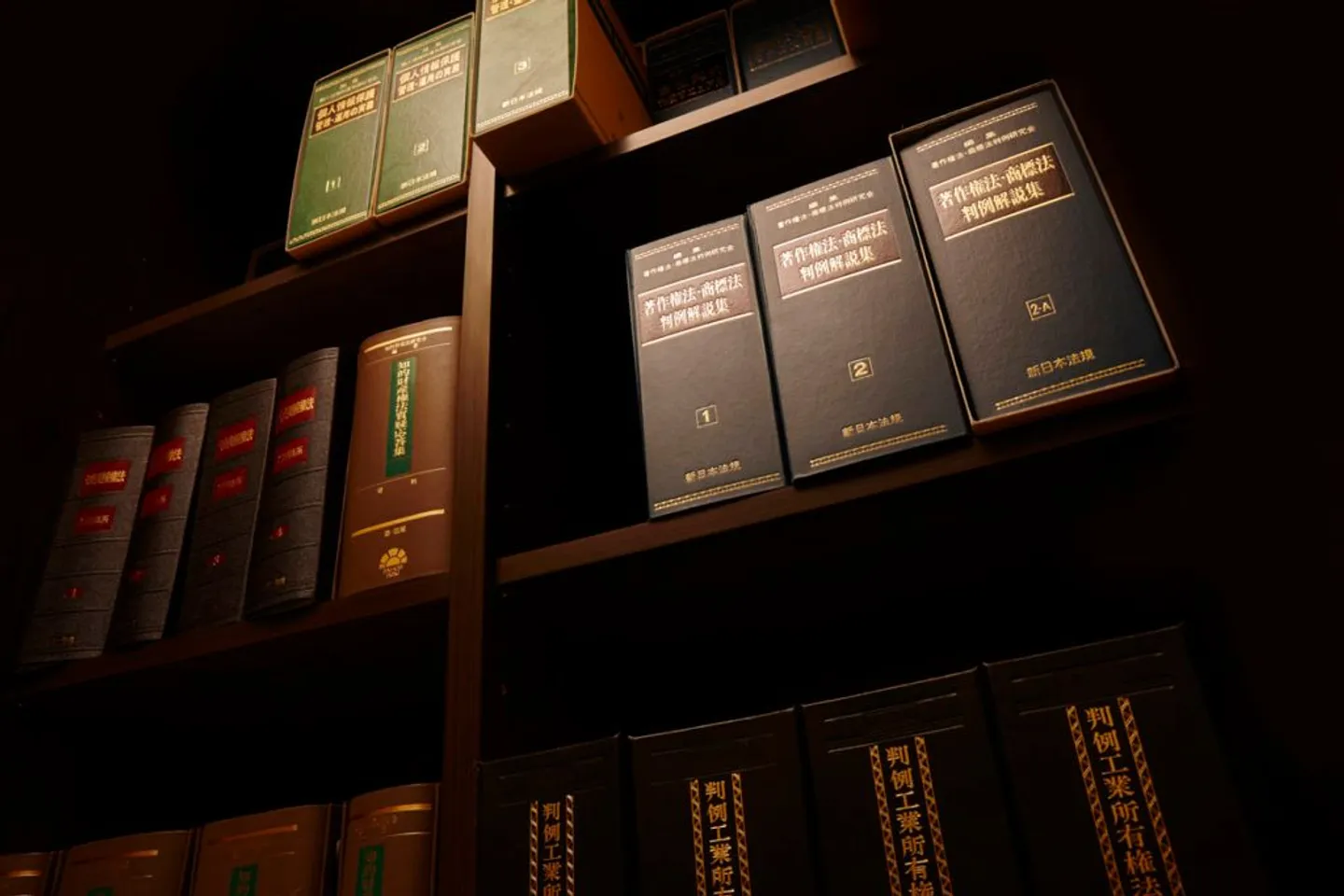
不動産投資に関するトラブルが起きたなら、早めに弁護士へ相談しましょう。
弁護士費用をかけずに自分で何とかしたいと考えて、下手に手を打ってしまうと裏目に出てしまうこともあります。トラブルをより大きくしてしまう前に、トラブル解決の専門家である弁護士に助言を求めましょう。
一人で、もがくよりも遥かにスムーズに、あっさりと解決できることでしょう。