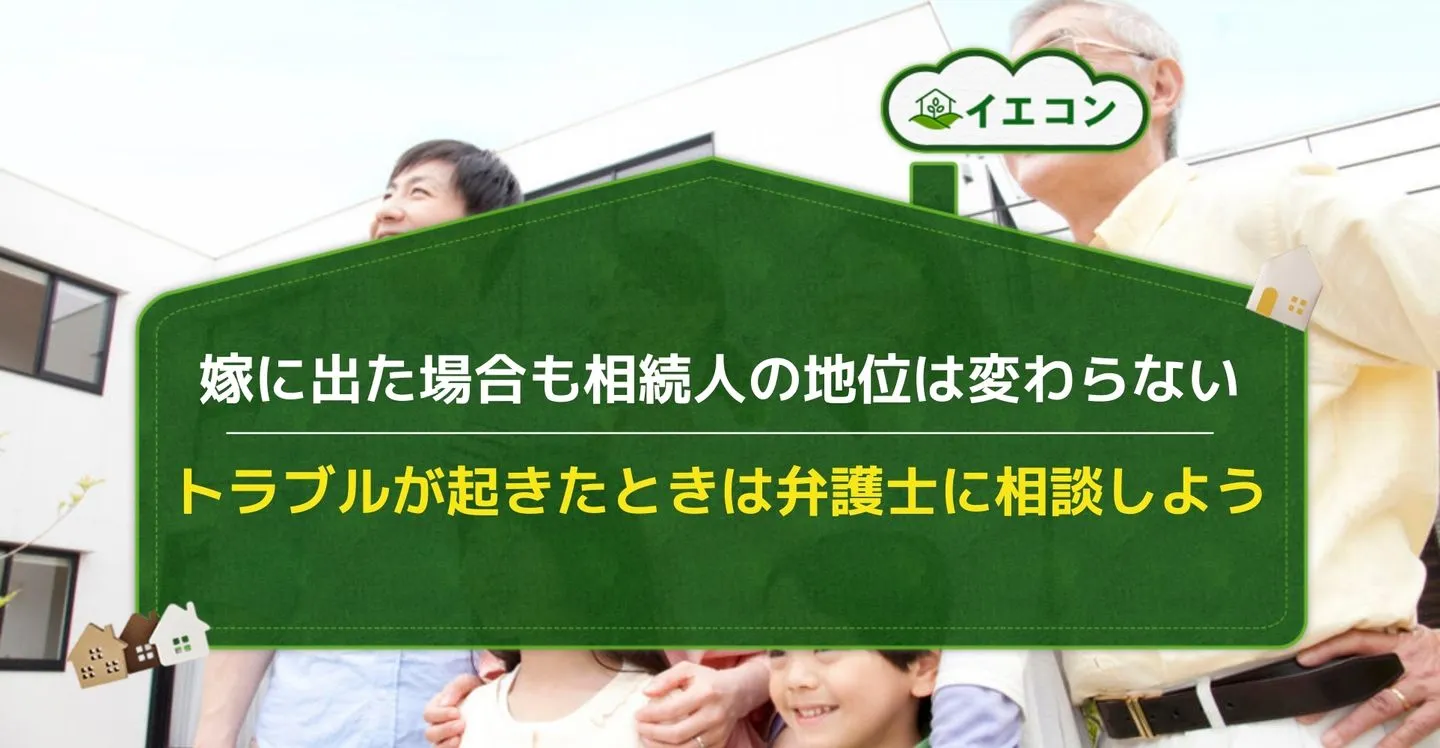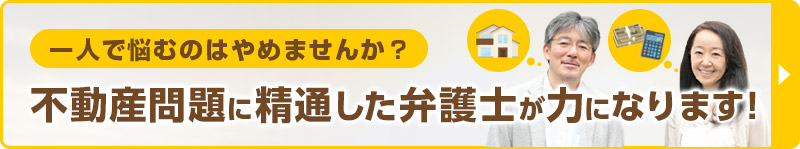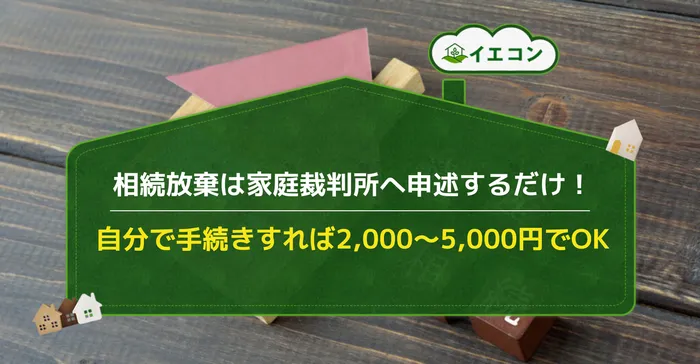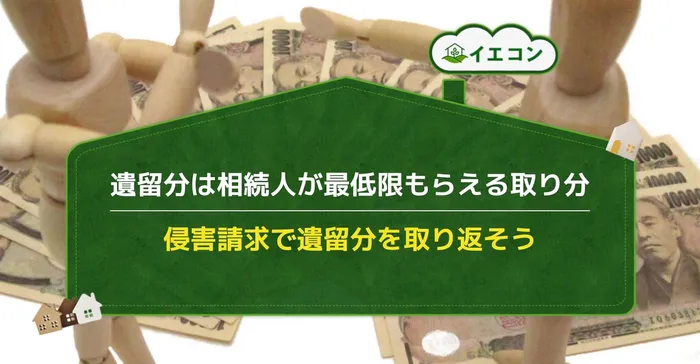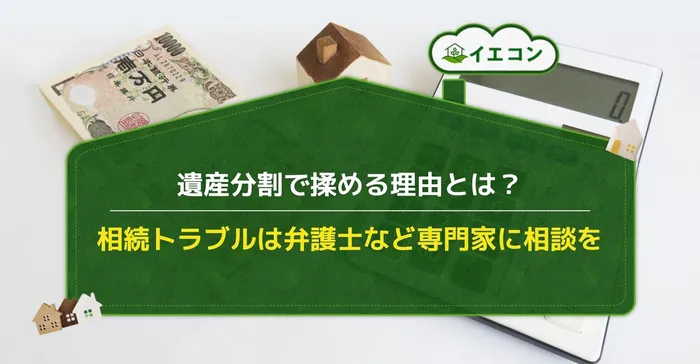嫁に出れば、実家の戸籍からは抜けることになります。
そのため、人によっては「実家の相続に加われないのでは?」と不安に思う場合もあるようです。
しかし、嫁に出て実家の戸籍から抜けていても、相続人の地位に変わりはありません。
実家の親が亡くなったときは、嫁に出ている・出ていないに関わらず、相続に参加する権利があります。
実家の相続でトラブルになったときは、弁護士に相談するとよいでしょう。当事者では感情的になってしまう状況でも、弁護士を挟めば冷静な話し合いが可能です。
嫁に出た場合でも実家の相続に加われる2つのケース

結婚をして家を出た場合であっても、次の2つのケースでは、相続人としての権利を有します。
- 両親が亡くなった場合
- 兄弟姉妹が亡くなった場合(条件あり)
相続人の権利があるということは、遺産分割協議など「相続に必要な手続き」に参加する義務があるということです。
相続放棄をしない限り、相続手続きに関わらる必要があります。
ケース1.両親が亡くなった場合
実家の両親が亡くなった場合、嫁に出た娘も当然その遺産を相続できます。
「嫁に出た人間は相続に関係ない」と思い込んでいる人もいますが、その理由は戦前の「家督相続」という考え方が一因です。
戦前の日本は「家制度」という仕組みを採用していたため、実家の遺産は家長の地位を受け継いだ長男がすべて相続することになっていました。
「嫁に出ることは、他人の家の人間になること」という考えは、家制度時代のなごりといえるでしょう。
ケース2.兄弟姉妹が亡くなった場合
実家の両親が亡くなった場合以外でも、相続人になる可能性があります。
ただし、亡くなった兄弟姉妹に子供がおらず、親・祖父母も他界しているという条件があります。
また、亡くなった兄弟が他の者にすべての相続財産を贈与するという内容の遺言を残していた場合には、一切の相続が認められません。
相続における基本ルール

相続手続きをスムーズに進めるためには、基本的なルールを押さえておくことが重要です。
とくに、下記のポイントは重要なので、しっかりと把握しておきましょう。
- 被相続人の子供は常に相続人となる
- 法定相続分は「相続人の組み合わせ」で変わる
- 一部の相続人には「最低限の取り分」がある
- 相続は「マイナスの財産」も対象となる
- 遺産分割の方法は「遺言どおり」が原則
被相続人の子供は常に相続人となる
相続人は民法で定められており、これを「法定相続人」といいます。遺言や遺産分割協議で特別に取り決めない限り、法定相続人で遺産を分け合います。
| 相続の順位 | 相続人になる人 | 相続人になる条件 |
|---|---|---|
| - | 配偶者 | 常に相続人となる |
| 第一順位 | 子(あるいは孫) | 胎児も含めて常に相続人となる |
| 第二順位 | 直系尊属(父母・祖父母) | 第一順位の相続人がいないとき |
| 第三順位 | 兄弟姉妹 | 第一・第二順位の相続人がいないとき |
子は、嫡出子だけでなく、非嫡出子(婚外子)であっても当然に相続人となります。今の民法では、家(苗字)ではなく、被相続人との血のつながりを重視して相続人の範囲を定めているからです。
被相続人の子であれば、嫁に出て苗字が替わったという場合であっても、相続人としての地位を失うことはありません。
ただし、嫁に入った家の両親(義両親)の相続人にはなれないので注意しましょう。
法定相続分は「法定相続人の組み合わせ」で変わる
相続が生じた場合、相続人それぞれの取り分を相続分といいます。
法律で定められた相続分の目安(法定相続分)は、下記のとおりです。
| 相続人となる人 | 相続人それぞれの法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者と子 | 配偶者1/2 子(全員で)1/2 |
| 配偶者と直系尊属 | 配偶者2/3 直系尊属(全員で)1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4 兄弟姉妹(全員で)1/4 |
なお、被相続人に配偶者がいない(同じ順位の相続人しかいない)場合には、相続財産の全額を相続人の人数で均等割した分が、それぞれの相続分となります。
例えば、父親の遺産相続で相続人が子供3人しかいないケースでは、1/3ずつ遺産分割することになります。
一部の相続人には「最低限の取り分」がある
実際の相続では、法定相続分と異なる割合で遺産分割を行うことも可能です。法定相続分に強制力はなく、相続人全員の合意や被相続人の意思(遺言)によって相続分を自由に定めることができます。
ただし、配偶者と第一・第二順位の相続人には「遺留分」が定められています。
遺留分とは、法律によって相続人に保証される最低限の取り分です。遺留分を無視した遺言や遺産相続は無効となります。
上記のとおり、遺留分は配偶者~第二順位までの相続人にしかありません。兄弟姉妹は法定相続人ですが、遺留分はないので注意しましょう。
相続は「マイナスの財産」も対象となる
相続の対象となる財産は、不動産や預貯金だけでなく、他人への貸付金・売掛金といった債権も相続の対象となります。
さらに、借金や買掛金、住宅ローン、滞納している税金や社会保険料の債務といったマイナスの財産も相続の対象です。
実際の相続では、マイナスの財産についての調査が不十分だったことで、相続放棄する機会を失ってしまうことも少なくありません。
相続が発生したときには、財産調査に漏れがないようにしなければなりません。
自分たちでは財産をうまく調査できない、十分な調査をするだけの時間がないというときには、弁護士等の専門家に財産調査を依頼すとよいでしょう。
相続財産とならないもの
被相続人の財産のうち、下記の財産は、例外として相続財産の対象とはなりません。
・生命保険金
・墓、位牌、家系図など
一身専属権とは「その人固有に発生した、他人に引き継がせることが相当とはいえない権利」のことをいいます。一身専属権の例としては、扶養請求権、慰謝料請求権、親権、国家資格者としての地位などがあります。
生命保険金は、受取名義人固有の権利と考えられるため相続財産の対象とはなりません。
ただし、被相続人の死亡を原因に発生する財産取得であることから、相続税の計算では課税対象として取り扱われる(みなし相続財産)ことに注意しましょう。
意外に思われるかもしれないのは、一族の墓や位牌、家系図といったものが相続財産の対象とはならないことです。これらの財産は、その後の祭祀(さいし)を執り行う者が引き継ぐことになります。
遺産分割の方法は「遺言どおり」が原則
遺産分割は、被相続人の作成した遺言書のとおりにおこなうのが原則です。
ただし、遺言書がない場合、もしくは遺言書とは違う内容で遺産分割をおこなう場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって分割方法を決定します。
遺産分割協議は相続人全員の参加が必須です。分割内容も、全員の同意がなければ成立しません。
そのため、相続発生時はまず相続人の調査・確定が重要となります。
実家の相続でトラブルになりやすい3つのケース
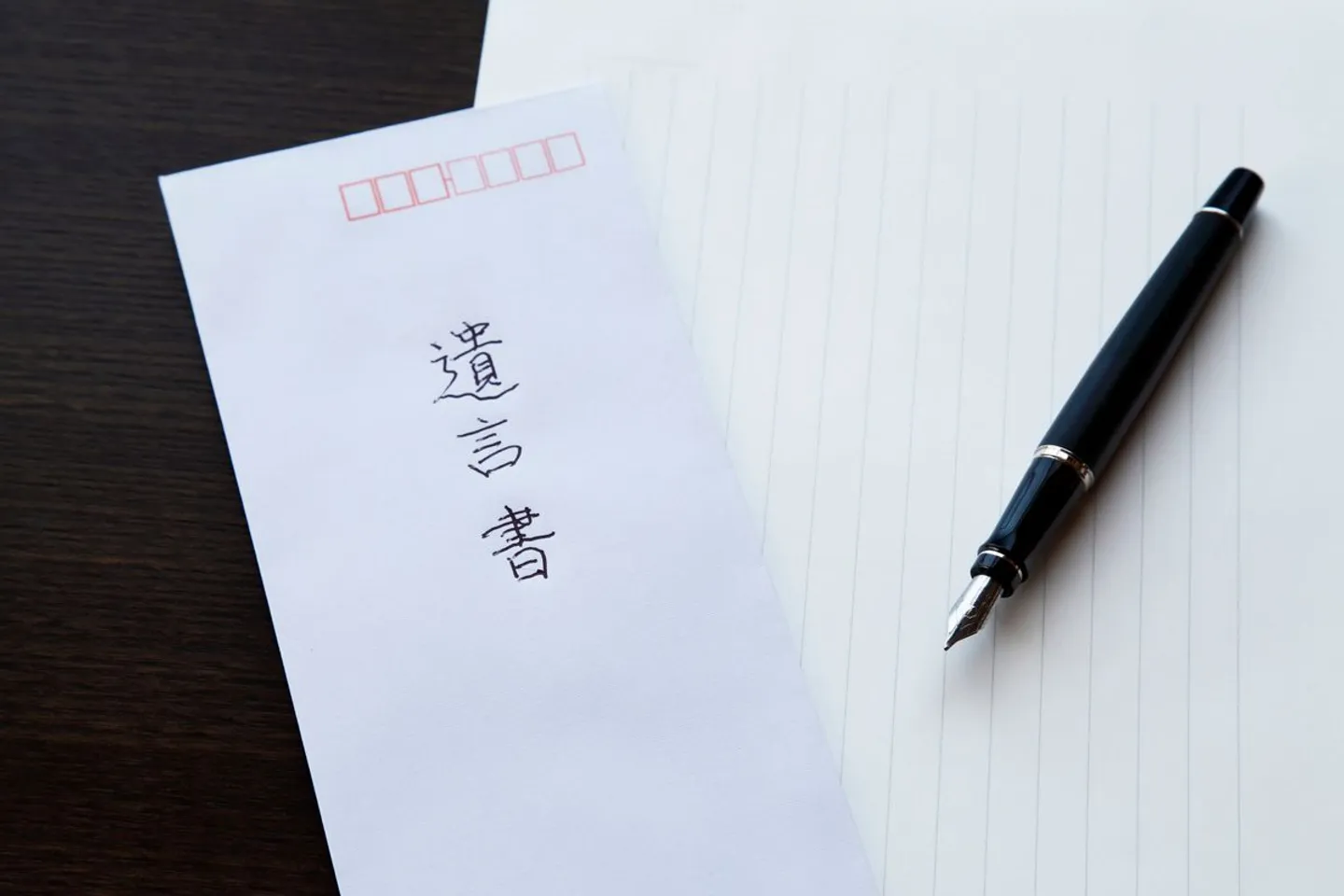
相続争いは、どこの家にでも起こりうるトラブルです。「わが家には争うほどの財産もない」と考えている人も多いかもしれませんが、裁判所に持ち込まれる遺産分割事件は、資産家の相続争いばかりではありません。
裁判所が毎年まとめている司法統計でも、遺産分割事件の多くは、ごく一般的な家庭の相続争いであることが見てとれます。
以下では、実家の相続においてトラブルになりやすい3つのケースを紹介します。
参照:裁判所「家事編第52表」
ケース1.特定の相続人だけ優遇されていた場合
例えば、兄弟が3人いるにもかかわらず、被相続人である父母が長男にだけ特別の贈与(住宅購入の援助など)をしていたという場合には、そのことが相続の場面で問題となることがあります。
法律では、被相続人による特定の相続人のみへの「特別の利益供与」があった場合には、その分を相続財産に持ち戻して配分を計算し直すのが原則です。
これを「特別受益の持ち戻し」といいます(なお、被相続人は遺言書などの意思表示で特別受益の持ち戻しを免除することもできます)。
ケース2.特定の相続人だけが被相続人の世話をしていた場合
例えば、被相続人の老後の介護を長男夫婦だけが負担していた場合や、被相続人の家業を次男だけが手伝っていたというような場合も、相続争いが起こりやすいといえます。
上記のように、特定の相続人による介護・家業手伝いが、相続財産の維持・増加に貢献があった場合には、その貢献分を上乗せして相続する「寄与分」が認められます。
しかし、寄与分の判断は非常に難しいため、どの程度の負担がどれくらいの寄与分になるかは弁護士に聞いてみましょう。
ケース3.不動産以外にめぼしい相続財産がない場合
「相続財産が被相続人の自宅だけ」というように、不動産以外にめぼしい財産がない場合も相続争いは起きやすいといえます。不動産は、各相続人の価値観で対立が起きやすく、分けるとしても方法が難しいからです。
「生まれ育った家だから残したい」「売却して現金化すべきだ」というような主張が食い違い、話し合いがまとまらないケースは少なくありません。
不動産を公平に分割したい場合、売却して現金で分割するのがおすすめです。
相続で争いになったら早めに弁護士へ相談する
相続争いは、相続人それぞれの価値観の違いが原因となることも多く、感情的なしこりを残しやすいトラブルでもあります。
家族だからこそ、お互いに冷静な話し合いができないこともあるでしょう。
そのため、話し合いが進まない場合は、弁護士を代理人に立てて相続の手続きを進めることをおすすめします。
弁護士であれば、他の相続人とも冷静かつ適切な交渉が可能です。
相続不動産の売却も検討するなら「弁護士と連携した買取業者」に相談しよう
相続における不動産は、そのままだと分割がしにくいため、トラブルになりやすい資産です。
そのため、相続にあわせて売却し、売却益で遺産分割をおこなうのがおすすめです。
弁護士と連携した買取業者なら、不動産の売却だけでなく、相続問題のサポートも可能なので相談してみましょう。
不動産を現金化
売却したいなら
共有持分買取専門の
当社にお任せください!

まとめ
相続は家単位ではなく、血のつながりを基準に相続人の範囲を考えます。
したがって、嫁に出た場合でも、被相続人の子供であれば実家の相続が可能です。
しかし、古いしきたりが強く残っている地域では「嫁に出たのだから相続は放棄すべき」といわれる人もいるかもしれません。
相続でトラブルになったときは、できるだけ早い段階で弁護士に相談するとよいでしょう。