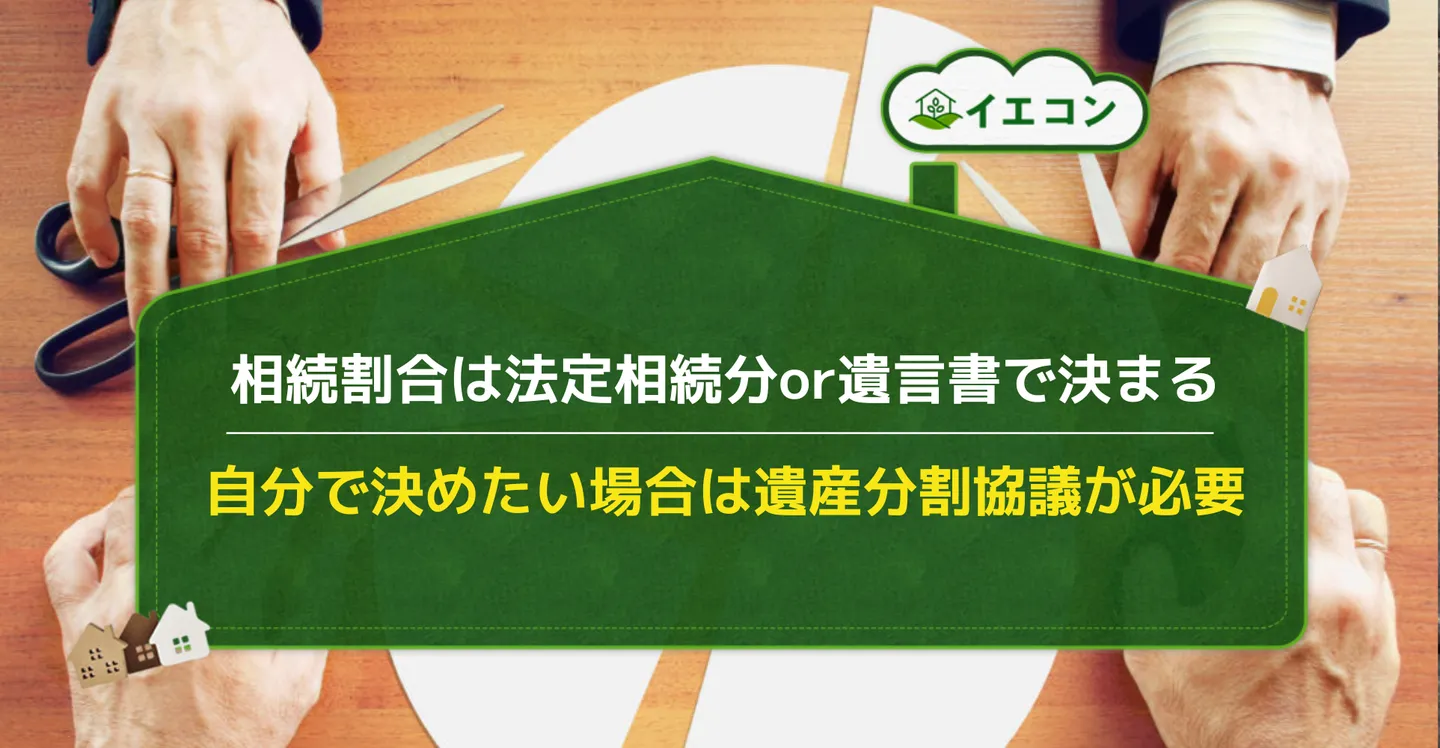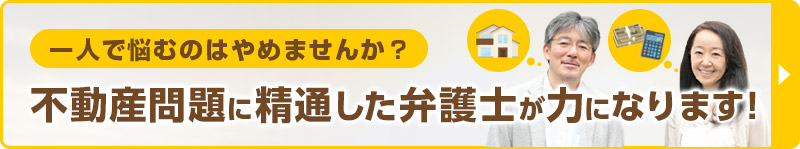相続割合を決める方法には「法定相続分」「遺言書」「遺産分割協議」の3種類があります。
原則として、遺言書がある場合はその内容どおりに相続しますが、遺言書がない場合は法律で定められた法定相続分どおりの割合で遺産を相続します。
また自分たちで相続割合を決めたい場合、遺産分割協議という話し合いをおこって、そこで決定した内容どおりに遺産相続することも可能です。
ただし、遺産分割協議で相続割合を決める場合、相続人同士の意見が合わずにトラブルが起こりやすいため注意が必要です。
もし遺産分割協議で揉めてしまったら、いますぐ相続問題に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。
【方法1】法定相続分に従って割合を決める
1つ目の方法は、法定相続分に従って割合を決める方法です。
法定相続分とは民法で定められた相続割合のことで、この法定相続分が認められている人を「法定相続人」といいます。
法定相続人には範囲と順位が定められているため、相続が発生したらまずは「誰が法定相続人か?」を調査しましょう。
法定相続人の人物さえわかれば、あとは法定相続分どおりに相続すれば基本的に問題ありません。
まずは法定相続分に従って割合を決める方法について詳しく解説します。
法定相続人の範囲と順位は決められている
まず法定相続人の範囲は原則「婚姻関係を結んでいる配偶者」と「子ども・両親・兄弟姉妹などの血縁関係にある人」です。
相続発生時に配偶者が生きているのであれば、必ず法定相続人に選ばれます。
一方で、子ども・両親・兄弟姉妹には相続できる順位(順番)が定められています。それが以下の通りです。
第2順位:親
第3順位:兄弟姉妹
つぎに、子どもも親もいない場合は兄弟姉妹に相続権が移動します。
ちなみに、法定相続人が1人もいないケースでは被相続人の財産は最終的に国庫に帰属します。
法定相続人の範囲と順位については以下の記事でも詳しく解説しています。
法定相続人は何人いるのか調査する
法定相続人の調査・確定をおこなわなかった場合、トラブルに発展してしまう恐れがあります。
なぜなら、思わぬ人が相続権を有しているケースもあるからです。
例えば、被相続人が離婚した前の配偶者との間に子どもを設けていた場合、その子どもは被相続人と親子関係にあるため法定相続人として認められます。
また、内縁の配偶者との間に子ども(非嫡出子)がいて、その事実を被相続人が認知している場合も、その子どもは実子と同じ立場として扱われるため法定相続人となります。
被相続人の置かれた状況によっては、会ったこともない法定相続人が現れる可能性もゼロとは限りません。
不動産を現金化
法定相続分に納得できないときの対処法
法定相続分で決められた相続割合に、納得できないこともあるかもしれません。
例えば「親である被相続人の介護を1人で負担していた」「他の相続人は被相続人から、住宅の購入費用として多額の贈与を受けていた」ことも考えられます。
このような事情を考慮しないまま、同等の相続財産を分割することに不満があれば、以下のような対処法があります。
- 寄与分を主張する
- 生前贈与分を差し引く
それぞれの対処法をわかりやすく解説していきます。
寄与分を主張する
介護にかかった費用や負担を加味した上で、遺産分割をおこないたいのであれば「寄与分」を主張しましょう。
被相続人を介護したり受け継いだ会社の業績を伸ばすことで寄与分が認められるケースがあります。
その場合は相続財産から寄与分を差し引いたものが分割対象となります。
例えば、以下のようなケースで遺産分割をおこなうとします。
「相続人は長男・次男・三男の3人」
「長男に300万円の寄与分が認められている」
まず、分割対象となる相続財産は「3,000万円-300万円=2,700万円」です。
よって、これを3人で分け合う場合、1人あたりの相続財産は「2,700万円÷3人=900万円」です。
しかし、長男に寄与分が認められているため「900万円+300万円=1,200万円」を相続できます。
一方、次男と三男はそれぞれ900万円ずつ相続することになります。
生前贈与分を差し引く
兄弟姉妹の誰かが被相続人から、生前贈与を受けていたのであれば「特別受益」として相続財産の調整が可能となります。
その調整方法は以下の通りです。
2.分配後の相続財産を分割する
例えば、以下のようなケースで遺産分割をおこなうとします。
「生前贈与額が300万円」
「相続人は長男・次男・三男の3人」
「受益者は長男」
まず、長男のみが300万円の生前贈与を受けているため、分割前に次男と三男に300万円ずつ分配して、分配後の相続財産は「3,000万円-300万円×2人=2,400万円」となります。
これを3人で分け合うとそれぞれ800万円ずつとなりますが、実際には長男が生前贈与で300万円、次男と三男は分割前に300万円ずつ受け取っています。
そのため、全員が1,100万円ずつ受け取ったことになり公平な分割になるというわけです。
【方法2】遺言書の内容に従って割合を決める
相続割合は、原則的に遺言書の内容に従って決められます。
相続において基本的に遺言書の内容が優先されるため、被相続人が遺言書を作成しているケースでは、その分割内容に従って相続がおこなわれます。
しかし、あまりにも不公平な内容だとしたら、そのまま従わなくてはならないのか不安になることもあるでしょう。
このような場合であれば「遺留分侵害請求(遺留分減殺請求)」が可能なケースもあります。
次の項目から遺言書があるときの相続についてわかりやすく説明しますので、被相続人の意思を尊重しながら相続割合を決めていきましょう。
遺言書の分割内容は優先される
法律では、法定相続分が決められています。
しかし、遺言書があればその内容が優先されます。
なぜなら「私的自治の原則」や「所有権絶対の原則」が作用されると考えられているからです。
所有権絶対の原則・・・所有する財産の扱いは誰にも干渉されずに自由に決定できるというものです。
これらの原則によって、遺言書で「遺産を誰に相続させるのか」という指定は個人の自由であるとされるため、法定相続分よりも優先されることになります。
分割内容があまりにも不公平な場合は「遺留分」が認められている
「遺言書の分割内容があまりにも不公平だった」というケースも珍しくありません。
先程も説明した「私的自治・所有権絶対の原則」が働くことで、分割内容を覆せないのではないかと心配になる人もいるでしょう。
結論から述べると、法定相続人の「遺留分」が侵害されている場合であれば、一定割合の相続財産を請求できるケースがあります。
遺留分の割合は簡単にいうと法定相続分の半分であるといえます。前の項目でも使用したケースを用いて具体的に解説します。
②配偶者と親・・・配偶者は2/6(1/3)、父母は1/6の遺留分が認められます。父母2人であればそれぞれ1/12です。
③配偶者と兄弟姉妹・・・配偶者のみ1/2の遺留分が認められます。被相続人の兄弟姉妹に遺留分の権利はありません。
被相続人の兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由は、子どもや親に比べて関係が希薄であると考えられているからです。
遺留分侵害請求をおこなう
もし遺留分よりも相続財産が少ない場合や遺産を一切相続できないような状況であれば「遺留分侵害請求」をおこないましょう。
例えば「相続財産が3,000万円」「相続人が長男・次男・三男の3人」「長男にすべての財産を相続させる」という内容の遺言書が残されているとするとします。
このようなケースでは次男・三男は一切相続できないため、遺留分を侵害されているということになります。
まず子どものみの場合、1/2の遺留分が認められています。この1/2をさらに分け合うため、それぞれの遺留分は「1/2÷3人=1/6」です。
したがって、次男と三男が遺留分侵害請求をおこなって受け取れる相続財産は「3,000万円×1/6=500万円」となります。
その結果、長男は2,000万円、次男と三男は500万円ずつ相続するというわけです。
自筆証書遺言は取り扱いに注意する
自筆証書遺言が見つかったとしても、その場で開封してはいけません。なぜなら、家庭裁判所で「検認」してもらわなければ「5万円以下の科料」が課せられてしまうからです。
万が一、検認せずに開封してしまったとしても遺言書の内容は無効にはなりません。誤って開封してしまった後は速やかに家庭裁判所で検認を申し立てることが大切です。
遺言書の検認における申し立てについては裁判所のホームページで必要となる書類や費用などを確認しておきましょう。
参照:裁判所「遺言書の検認」
【方法3】遺産分割協議をおこなって割合を決める
3つ目の決め方は「遺産分割協議」という話し合いをおこなって割合を決める方法です。
「遺言書が書き残されていない」「一部の財産しか分割内容が記載されていない」などのケースであれば「遺産分割協議」をおこなって割合を決めることがあります。
遺産分割協議の場合、基本的に相続割合は相続人同士で自由に決定できますが、相続人全員で話し合いをおこなわなければなりません。
また協議を終えた後は、話し合いの内容がわかるように「遺産分割協議書」を作成することが大切です。
最後は、遺産分割協議による割合の決め方について詳しく解説します。
遺産分割協議は相続人全員でおこなう
相続人が1人でも欠けた状態で遺産分割協議をおこなうと、その協議は無効になってしまいます。
なぜなら、協議に参加できなかった相続人の権利が侵害される恐れがあるからです。
連絡が取れない相続人がいるからといって、その人を参加させないまま遺産協議をおこなうとトラブルになりかねません。
協議終了後に参加できなかった相続人から連絡が来ることもあるかもしれません。
そのような場合は協議をもう一度おこなわなければならず、余計に時間や労力もかかってしまうでしょう。
割合や分け方は自由に決定できる
遺産分割協議において相続人全員が同意すれば、相続の割合や財産の分け方を自由に決定できます。
そのため、必ず法定相続分に従う必要はありません。
このようなケースで「長男に2,500万円」「次男・三男に1,250万円ずつ」という分割内容でもよいわけです。
ただし、先程も述べたように相続人全員が同意しなければ認められないので、注意しましょう。
また、不公平な相続にならないように寄与分や特別受益を加味した上で割合を決定するとトラブルも起きにくくスムーズに相続を終えられるかもしれません。
遺産分割協議が終わったら「遺産分割協議書」を作成しよう
相続人全員が遺産分割協議の内容に同意したら「遺産分割協議書」を作成しましょう。
様式に決まりはないため、パソコンでの打ち込みでも手書きでもどちらでも構いません。
正確な協議内容が記載されていれば基本的に自由に作成できます。
ちなみに、遺産分割協議書の書式や記載例は法務局が公表しているので、参考にしてみてください。
本来、遺産分割協議書を作成していなくても法律的な罰則などはありません。
ただし、作成したほうがよい理由については以下のような目的があります。
- 協議後のトラブルを防止する
- 相続手続きの必要書類となる
次の項目からそれぞれの目的について詳しく説明します。
参照:法務局「遺産分割協議書」
協議後のトラブルを防止する
もし遺産分割協議書を作成していなかった場合、心変わりした相続人が分割方法の変更を求めてくる可能性があります。
「実は分割内容に納得していなかった」「やっぱりその財産を相続したい」などのように意見を変えるかもしれません。
また「言った・言わない」のトラブルに発展してしまう恐れもあります。
しっかりと協議書を作成し合意を証明する署名押印がされていれば、身勝手な主張に対抗することが可能です。
遺産の分割方法を決める話し合いは時間も労力もかかることが多いため、早めに協議書を作成してこのようなトラブルを未然に防ぐことが大切です。
相続手続きに必要な書類となる
相続手続きをおこなう際に必要書類として遺産分割協議書の提出を求められることがあります。
例えば、遺産の中に不動産が含まれているのであれば相続登記をおこなわなければなりません。
相続登記をおこなう際に「誰が相続したのか」を証明するために遺産分割協議書を添付する必要があります。
遺産分割協議書があることで正式に所有権が移動したことを第三者に証明できます。
その結果、他の相続人が勝手に相続登記や払い戻しをおこなうことも防げるというわけです。
遺産分割協議がまとまらないときの対処法
遺産分割協議は相続手続きの中でも最もトラブルになりやすいといわれています。
「少しでも多くの財産を相続したい」などの気持ちを抱いていることで、お互いの意見がぶつかり協議が全くまとまらないケースも珍しくありません。
もしどれだけ話し合っても協議が進まないのであれば、以下の対処法を実施することで解決できるかもしれません。
- 法定相続分を主張する
- 遺産分割調停を申し出る
- 相続問題に詳しい弁護士に相談する
それぞれの対処法についてわかりやすく解説するので、状況に応じた選択をするとよいでしょう。
法定相続分を主張する
遺産分割協議は相続割合を自由に決められることが利点といえます。
しかし、自由に決められるからこそ自分の相続割合を優先してしまい、協議が泥沼化してしまうこともあります。
前の項目で説明した「寄与分」や「特別受益」であれば割合を決める上で妥当な理由として扱われるでしょう。
もしも、話し合いがまとまりそうにないなら「法定相続分での相続を主張する」ことも検討しましょう。
法律で定められた相続割合である以上、平等な相続であると考えられるので、法定相続分による相続が妥協案として折り合いがつく可能性もあります。
遺産分割調停を申し出る
法定相続分による相続の主張が拒否されてしまったとしても「これ以上対処のしようがない」と諦める必要はありません。
その理由は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し出ることで裁判官や調停委員などの第三者に介入してもらい話し合いをまとめてもらえるからです。
遺産分割調停を申し立てる際は所定の手続きをおこなう必要があり、申立先や費用・必要書類などは裁判所のホームページで確認可能です。
ちなみに、遺産分割調停も不成立に終わってしまった場合は「遺産分割審判」がおこなわれ、権利や相続人の事情などを考慮した上で強制的に分割方法が決められます。
参照:裁判所「遺産分割調停」
相続問題に詳しい弁護士に相談する
遺産分割で揉めてしまい家族や親族の間でトラブルに発展してしまうケースも少なくありませんが、相続人同士が協力・尊重し合えばトラブルを解決できるでしょう。
しかし、相続人の誰かが感情的になってしまうと、話し合いがまとまらず関係も悪化してしまい、遺産相続を巡って仲の良かった兄弟が絶縁状態になってしまう可能性もゼロではありません。
このような悲しい結果にならないためにも、早めに相続問題に詳しい弁護士に相談することが大切です。
相続に関する法律や相続人との交渉を得意とする弁護士に依頼することで、平和的な相続を実現できるかもしれません。
まとめ
相続割合は「法定相続分」「遺言書」「遺産分割協議」の3種類いずれかの方法で決めます。
法定相続分は法律によって割合が決められている以上、相続人全員が納得できる平等な相続を実現しやすいでしょう。
遺言書が残されている場合は基本的にその分割内容に従いますが、あまりにも不公平な内容だとしたら「遺留分侵害請求」ができるケースもあります。
また遺産分割協議をおこなえば、相続人同士で割合や分割内容を自由に決めることも可能です。
ただし「話し合いの折り合いがつかない」「泥沼化してしまって協議が進まない」といった揉め事も起こりやすいため、遺産相続に関するトラブルが起きた際は相続問題に詳しい弁護士に相談しましょう。