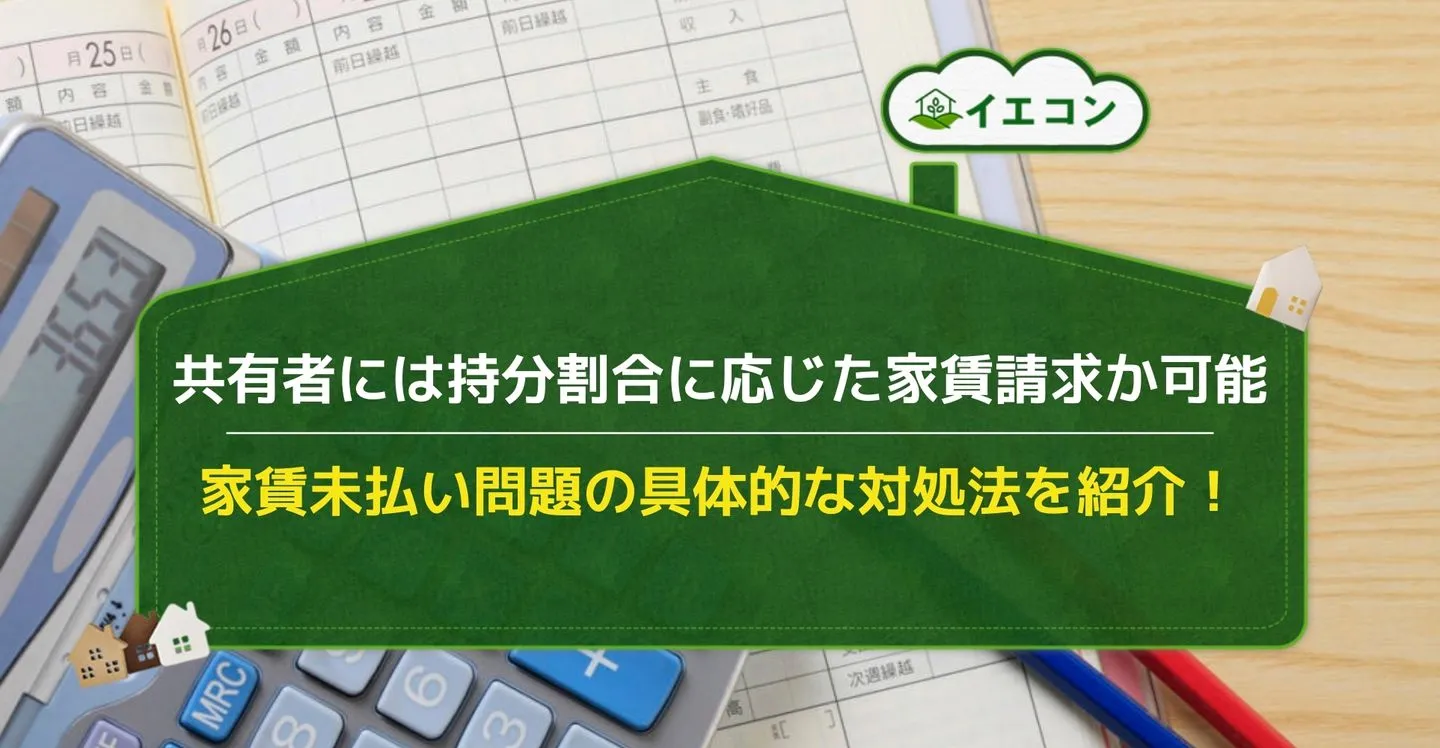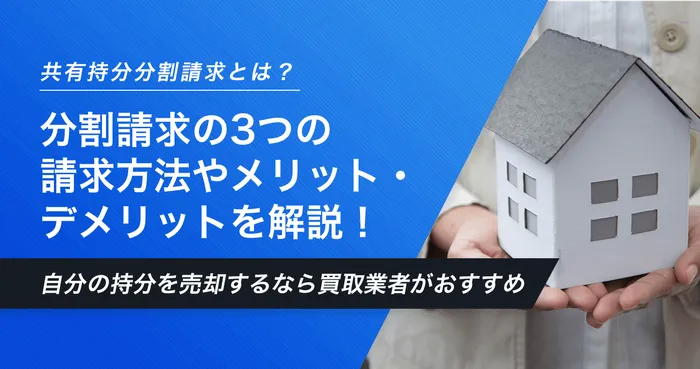共有名義の不動産は、すべての共有者に「使用する権利」があります。
しかし、住宅の場合は共有者のうち1人だけが居住し、他の共有者は実際に居住することも、家賃収入を得ることもできないという状況が少なくありません。
そのような状況で悩んでいる人に伝えたいのは「共有不動産を占有している共有者に対して、持分割合に応じた家賃を請求できる」ということです。
過去にさかのぼって請求することも可能なので、まずは弁護士に相談しましょう。
また、家賃トラブルを根本的に解決したい場合、共有持分を処分するのも1つの手です。共有者が使用している状態でも、共有持分の売却は可能です。
共有持分の売却について疑問があるときは、一度共有持分専門の買取業者へ相談してみるとよいでしょう。
相手が共有者でも家賃請求はできる

共有不動産において、共有者の1人が居住し占有状態になっているケースは少なくありません。
例えば、兄弟2人で不動産を共有していて、実際に住んでいるのは兄のみというパターンです。
上記の例だと、弟は不動産を利用できず、兄より損をしている状態です。言い方を変えれば、弟の権利が兄に侵害されているといえます。
そこで、共有不動産に住んでいない共有者は、住んでいる共有者に対して、持分割合に応じた家賃の請求ができます。
共有者に請求できる家賃は「家賃相場×持分割合」で計算する
家賃の金額は厳密に決まっているわけではなく、あくまで合理的な価格とされており、当事者の合意で決定します。
一般的には、近隣物件の家賃相場を参考に、持分割合をかけて算出します。
共有不動産の持分割合が「Aが2/5、Bが3/5」であり、実際に居住するのはAだけの場合、Bは月3万円(5万円×3/5)をAに請求可能です。
家賃に関する取り決めは、契約書を作成しておきましょう。身内だからと口約束だけにしておくと、トラブルになる恐れがあります。
共有者からの得た家賃も課税される
共有者から家賃を受け取った場合、税法の観点では所有している物件を賃貸した場合と同様に扱われます。
つまり、一般的な家賃収入と同じように、年間20万円以上の収入があれば確定申告をしなければいけません。
家賃収入は、確定申告において「不動産所得」に分類されます。年間の家賃収入から経費を差し引いた金額が、課税対象額です。
「使用貸借契約」が成立していると家賃請求できない
使用貸借契約とは無償でものを貸し借りする契約で、民法にも規定があります。
民法第593条
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。出典:e-Govポータル「民法第593条」
一般的に、どんな不動産の貸し借りでも家賃や地代といった対価が発生します。しかし、身内での貸し借りでは、無償で不動産を貸し出している状態も珍しくありません。
使用賃借契約がある場合、家賃請求はできないので注意しましょう。
使用貸借契約は口約束で結ばれているケースも多く、期限など詳しい条件を設定しなかったためにトラブルとなるケースが多くあります。
「共有者の家賃未払い」が起きたときの具体的な対処法
使用貸借のときを除き、共有者に対しても家賃の請求ができると解説しました。
しかし、共有者の家賃未払いトラブルが発生したとき、具体的になにをすればよいのでしょうか?
主な対処法は下記の3つなので、それぞれ具体的に解説していきます。
- 不当利得返還請求をおこなう
- 「共有物分割請求」で共有名義を解消する
- 自分の持分を売却して共有名義を解消する
対処法1.不当利得返還請求をおこなう
不当利得返還請求とは、他人に侵害された自分の利益を返還してもらう手続きです。
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。出典:e-Govポータル「民法第703条」
不当利得返還請求をおこなえば、最大で過去10年間の未払い家賃を請求できます。
ただし、共有者間の協議で使用貸借が成立している場合、不当利得返還請求はできません。「無償で使用する」という取り決めがあるので、返還を請求すべき利益がそもそも存在しないためです。
不当利得返還請求は弁護士に相談すべき
不当利得返還請求は、当事者間で直接交渉することもできます。しかし、強引な請求は自分の立場を不利にするので注意しましょう。
家賃を支払わないかどうかと、不動産に居住する権利は別問題です。家賃請求がエスカレートして嫌がらせのような行為をすれば、取れるはずの家賃が取れなくなる可能性もあります。
家賃請求は法的な手続きにのっとっておこなうことが大切なので、まずは不動産問題に詳しい弁護士へ相談しましょう。
不当利得返還請求で家賃以外に取り返せるもの
不当利得返還請求で取り返せるものは、家賃だけではありません。
例えば、共有不動産の固定資産税は持分割合に応じて分担すべきものです。しかし、共有者が分担を拒否し、他共有者が立て替えているケースは少なくありません。
不当利得返還請求をおこなえば、立て替えていた固定資産税を取り返せます。
また、賃貸物件として貸し出している共有不動産において、一部の共有者が賃料収入を独占しているケースもあります。
賃料収入も持分割合に応じて分割すべきものなので、不当利得返還請求によって取り返すことが可能です。
過去にさかのぼって不当利得返還請求をおこなう場合は税金に注意
不当利得返還請求は、時効である過去10年までさかのぼって請求できます。しかし、過去にさかのぼって請求する場合、税金の処理に注意が必要です。
10年分の家賃をまとめて返還してもらった場合、その年にまとめて不動産所得が発生したとみなされます。10年分が1度に課税されるため、税額が高くなってしまいます。
また、過去10年の減価償却や修繕費を算出するなど、複雑な計算をしなければいけません。
適切な税申告と、最大限の節税をおこなうためには、税理士に相談するとよいでしょう。
対処法2.「共有物分割請求」で共有名義を解消する
家賃トラブルがこじれた場合、無理に家賃を請求するより、共有名義を解消してトラブルから抜け出すという考え方もあります。
共有名義を解消できる制度に「共有物分割請求」というものがあります。他共有者に対して、協議や訴訟によって共有名義の解消を請求する制度です。
具体的には、下記の方法で不動産を分割します。
| 現物分割 | 不動産を持分割合に応じて切りわけ、それぞれ別名義の不動産とする方法。 |
|---|---|
| 代償分割 | 共有者間で、持分と金銭を交換(売買)する方法。 |
| 換価分割 | 不動産を売却し、売却益を持分割合にそって分割する方法。 |
共有物分割請求は、共有者なら持分割合に関わらずだれでも請求できます。請求があった場合、すべての共有者は分割に向けた話し合いをしなければいけません。
対処法3.自分の持分を売却して共有名義を解消する
共有名義の解消方法としては、自分の共有持分を売却するのもよいでしょう。
共有持分の売却に、他共有者の同意は不要です。自分の意思で、いつでも売却できます。
共有持分を売却すれば共有関係を解消できるので、家賃トラブルからも抜け出すことが可能です。
しかし、通常の不動産業者では共有持分を取り扱っていなかったり、安値で叩かれる恐れがあります。
そこで、共有持分専門の買取業者へ売却するのがおすすめです。共有持分専門の買取業者なら独自のノウハウを活かし、トラブルなく共有持分を高額買取をしてくれます。
当社、クランピーリアルエステートも「共有持分専門の買取業者」です。共有持分についてお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
不動産を現金化
売却したいなら
共有持分買取専門の
当社にお任せください!

まとめ
共有不動産を共有者の1人が占有している場合、持分割合に応じた家賃請求が可能です。
しかし、共有者間の話し合いで「使用貸借」が成立している場合、家賃請求はできないので注意しましょう。
また、請求は法的に正しい手続きを踏むことが重要なので、まずは不動産問題に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。