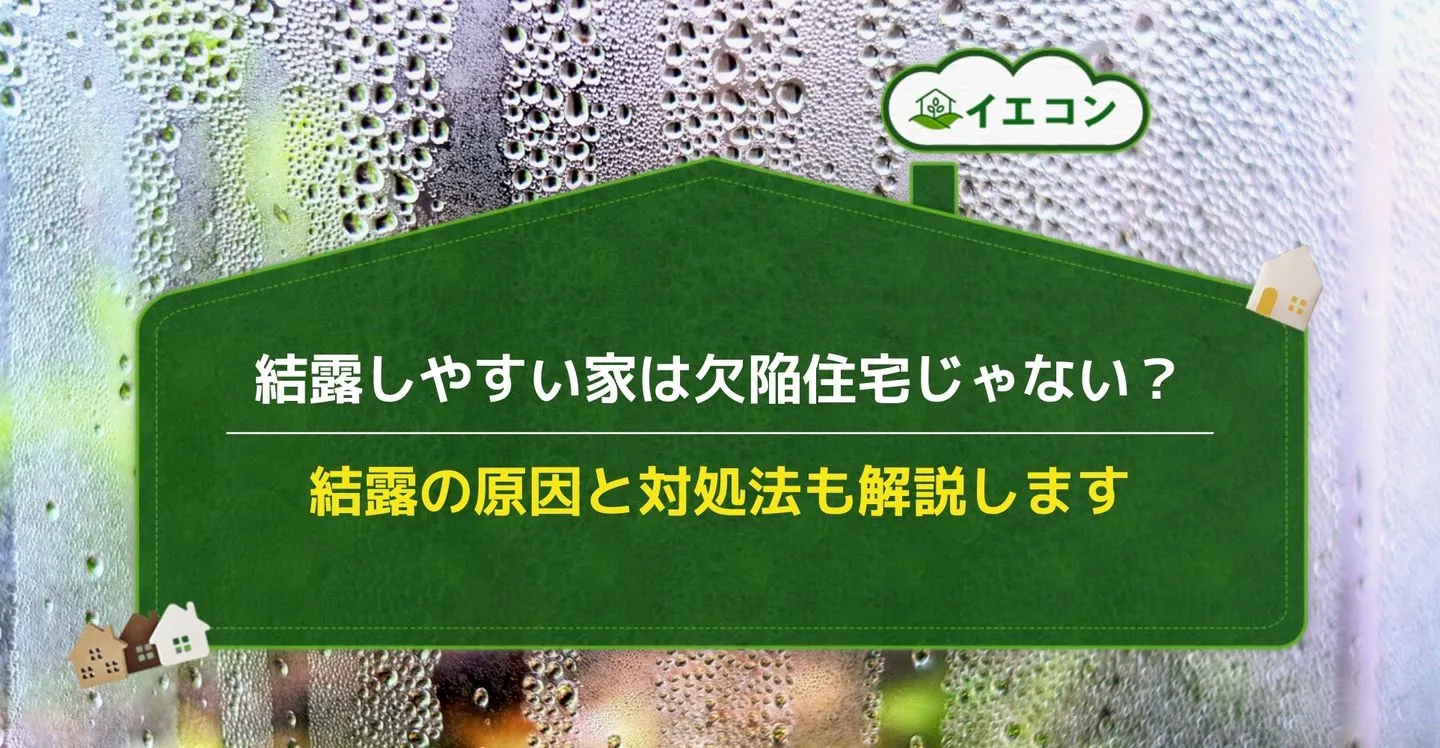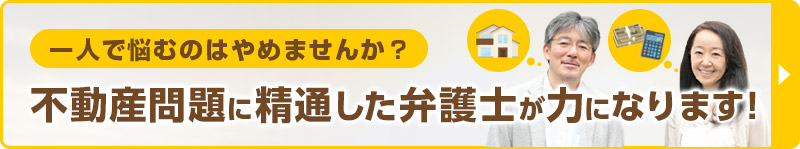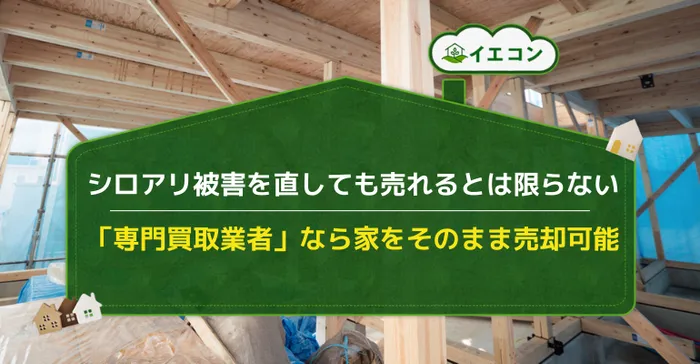家の中と外で温度差が発生すると、窓ガラスや壁に結露が発生します。
結露が多い家だと「欠陥住宅なのでは?」と思う人もいますが、室内の温度を保つために気密性を高くした家でも結露は発生しやすく、結露の多さだけで欠陥住宅とはみなせません。
しかし、窓ガラスや壁だけでなく「家の柱や土台」にまで結露が発生しているときは、欠陥住宅であるかもしれません。
また、結露が多いと家の腐敗やシロアリ被害も起きやすくなります。結露が多い家や腐敗・シロアリ被害が進んだ家を売却したい場合は、一般的な不動産仲介業者ではなく、訳あり物件専門の買取業者に買い取ってもらいましょう。
欠陥住宅であっても、訳あり物件専門の買取業者なら活用ノウハウがあるため、高額かつ最短数日での現金化が可能です。無料査定を利用して、具体的な価格や売却に向けたアドバイスを聞いてみましょう。
結露しやすい家であっても欠陥住宅とみなされるケースは少ない
もしも、購入した新築が結露しやすければ、欠陥住宅を疑うかもしれません。
ですが「結露しやすい」という理由だけでは、欠陥住宅とみなされるケースは多くありません。
結露が起きてしまう家のほとんどが「高気密高断熱住宅」というものです。
高気密高断熱住宅は冷暖房の効果を高められますが、気密性の高さから湿気をこもらせてしまう性質があります。
そのため、高気密高断熱を意図して設計されている家は、結露が多くても欠陥住宅とはされません。
もし欠陥住宅であれば損害賠償請求できる
先ほども説明した通り「結露しやすい」という理由だけでは、欠陥住宅とみなされる可能性は低いです。
ただし、住宅が「欠陥住宅」であった場合は、設計や工事をおこなった会社に対して損害賠償請求が可能です。
例えば、購入した住宅で窓付近だけでなく「家の柱や土台」にまで、結露が発生しているときは欠陥住宅とみなされるケースがあります。
目に見えるところだけでなく、柱や土台に結露が発生することを「内部結露」といいます。
もしも、欠陥住宅を疑うほど結露が発生してしまっている場合は、不動産問題に詳しい弁護士や訳アリ物件専門業者に相談してみましょう。
結露が発生してしまう主な原因は2つ
最近の住宅は、高気密高断熱住宅が主流になってきています。
高気密高断熱住宅は、室内の温度を一定に保てるため、夏は涼しく冬は暖かい住宅です。
しかし、一方で湿度がこもりやすく、それを原因に結露を発生させてしまうデメリットもあります。
以下の項目から、結露が発生してしまう主な原因を解説していきます。
室外と室内の寒暖差(温度差)が大きい
結露が発生する原因は「空気中の水分が外気と触れ、急激に冷やされることにより水滴が発生する」ことにあります。
つまり、室外と室内の寒暖差(温度差)が大きいとき、結露が発生してしまいます。
例えば、室外の気温が低い冬に室内で暖房器具を使用し、室温が高いときに結露が発生しやすいです。
室温と外気温の寒暖差が激しい冬に、結露が多く発生します。
人のいる部屋といない部屋で温度差が大きい場合も結露が発生する
結露は外気と室内の空気が触れることで発生するので、寒暖差の大きい窓際で発生しやすいです。
ただし「結露は窓際でしか発生しない」わけではなく、部屋と部屋の間でも結露は発生するので、注意が必要です。
とくに、人のいる部屋といない部屋で温度差が大きい場合は、壁の中に結露が発生してしまいます。
壁の中に結露が発生してしまうと、見えないところから柱や梁が腐ってしまいます。
人がいる部屋もいない部屋も、温度差を作らないようにすることが大切です。
室内の湿度が高い
結露が発生する原因は、外気との寒暖差だけでなく、室内の「湿度の高さ」にもあります。
結露は空気中の水蒸気が急激に冷え、液体化することで発生します。
ですので、空気中の水蒸気が多ければ多いほど、寒暖差があったときに結露(水滴)が発生しやすいです。
結露の対処法3つ
すでに説明しましたが、結露しやすい家であっても基本的に、欠陥住宅とはみなされません。
ですので、損害賠償請求はできません。引っ越しができないのであれば、住み続けることになるでしょう。
結露を放置するとカビ繁殖などのリスクに繋がり、住宅の価値が下がってしまいます。
そこで、結露への対処法を知れば、所有している家を結露の被害から守れるでしょう。
結露の発生を抑えるための方法は
- 換気して空気を入れ替える
- 外気温と室温を近づける
- 加湿器の過剰使用を控える
の3つです。以下の項目から、それぞれの方法を詳しく解説していきます。
換気して空気を入れ替える
室内で発生した水蒸気や湿度を外気と入れ替えるため、こまめに換気をおこないましょう。
窓を開けるのはもちろん、台所やお風呂にある換気扇の利用も効果的です。
とはいえ、寒い冬に窓を開け放しておくのは大変不便かと思います。
そんなときは、5~10分だけでも窓を開けて換気をするとよいでしょう。壁や天井がもとの熱を持っているので、短時間窓を開けただけでは大幅に室内の温度が下がることはありません。
外気温と室温を近づける
結露は室内と室外の寒暖差が原因で発生します。
ですので、外気温と室温を近づければ結露を防げます。
冬になると、暖房器具を使用しますが、設定温度を上げすぎず適切な温度に保つことが大切です。
また、先ほどの項目でも紹介しましたが、窓を開けて外気を取り入れることも、やはり重要です。
加湿器の過剰使用を控える
冬になると空気が乾燥するため、加湿器を利用する方も多いでしょう。
しかし、必要以上に加湿器を使用すると、室内の湿度が高くなってしまいます。
室内の湿度が高ければ高いほど、結露は発生しやすくなってしまいます。必要以上に加湿器を使用することは控えたほうがよいでしょう。
結露を放置することで発生するリスク
もしも、結露を放置してしまうと、以下のようなリスクがあります。
- 結露で濡れた部分にカビやダニが繁殖する
- 窓のサッシや住宅の木材部分が傷んでしまう
- シロアリ被害を引き起こしてしまう
カビやダニが繁殖すると、居住する方が喘息や肺炎を罹患してしまうなど、健康面でも悪影響を及ぼす恐れもあります。
また、シロアリの住処になると柱や梁が傷つき、建物が不安定になってしまいます。
ですので、結露が発生してしまった場合は、早めに対処を心がけましょう。
結露で濡れた部分にカビやダニが繁殖する
カビやダニは、湿度が「およそ60%以上」で活動をすると言われています。
もしも、結露で濡れた箇所を放置していると、すぐに湿度は60%を超えてしまうでしょう。
結露を放置していると、家にカビが発生して見た目が悪くなることは避けられませんし、建物を腐らせてしまいます。
また、カビの胞子やダニを吸い込んでしまうと、喘息や肺炎を発症する恐れもあります。
シロアリ被害を引き起こしてしまう
シロアリは水分を多く含んだ木材などを好むので、結露の発生を放置すると家の内部が、シロアリの住処になってしまうかもしれません。
シロアリが住居に住みつくと、柱や梁などの建材が傷ついてしまい、建物の耐久性を下げてしまいます。
カビもシロアリも、水分の多い箇所を好むので、結露は早めに対策することが大切です。
窓のサッシや住宅の木材部分が傷んでしまう
窓付近や住宅内部で結露が起きている場合、放置してしまうと水滴がたまり続けます。
サッシや木材が濡れたままだと傷み、建物が歪む原因になってしまうでしょう。
また、結露で発生した水滴を放置すると、サッシや木材だけでなく、周りの家具やカーテンなどにも被害が広がってしまいます。
結露しやすい家の売却を検討しているなら訳あり物件専門業者に相談しよう
結露のしやすい家は「欠陥住宅」というわけではありません。
ですので、家を売却する場合も、相場価格通りに売却できるでしょう。
ただし、結露が原因でカビが発生していたり、シロアリ被害にあっていると、通常通りの売却は困難です。
また、自分が認識していなくても、建物の内部で結露が発生し建物を傷つけている可能性もあります。
建物の一部が傷ついていたり、カビが発生していると「訳アリ物件」とみなされます。
大手の不動産会社などでは、そういった訳アリ物件を取り扱うことは多くありません。
ですので、結露しやすい家の売却を検討しているなら、訳あり物件専門業者に相談するのが一番です。
結露しやすい家の売却は当社にご相談ください!
先ほども解説しましたが、結露しやすい家の売却は「訳あり物件専門業者」に任せることが一番です。
当社クランピーリアルエステートも、訳あり物件を専門買取している専門業者の1つです。
物件の資産価値を高めるノウハウや実績があり、訳あり物件に詳しい専門家も多数在籍しています。
そのため、結露しやすい家や、結露を原因にシロアリ被害が発生してしまった家でも、高く買取いたします。
不動産を現金化
売却したいなら
訳あり物件買取専門の
当社にお任せください!

まとめ
一般的に「結露しやすい家」というだけでは欠陥住宅とみなされません。
ですので、結露の対策をしながら居住を続けることになるでしょう。
もしも、結露が発生したら、そのまま放置することはやめるべきです。換気や暖房器具・加湿器の調整を見直して、結露が発生しにくい環境をつくることが大切です。
結露が解消できず、建物が傷ついてしまった場合は、訳あり物件を専門に扱う不動産業者に売却することを検討してもよいかもしれません。
物件の資産価値を高めるノウハウや実績がある不動産会社なら、結露のトラブルが発生した家でも高く売却できます。