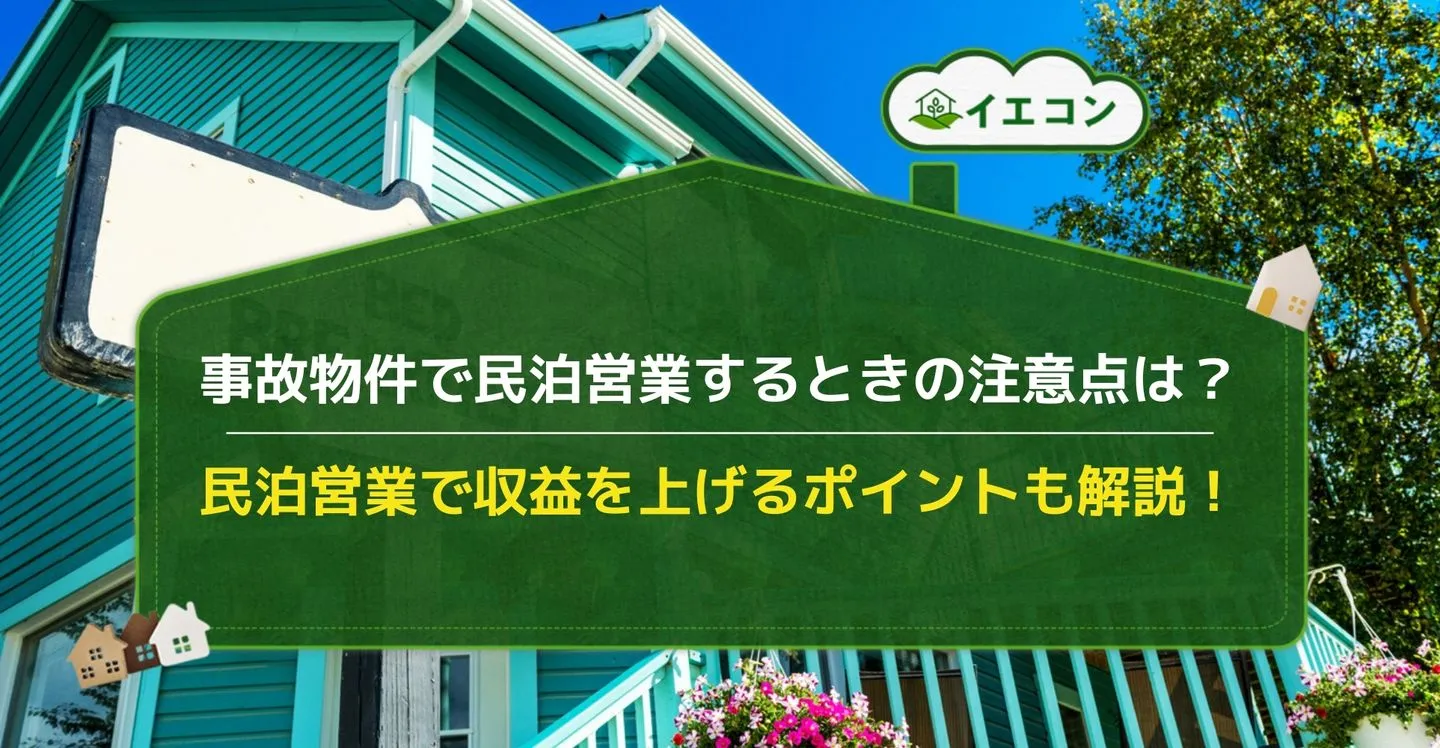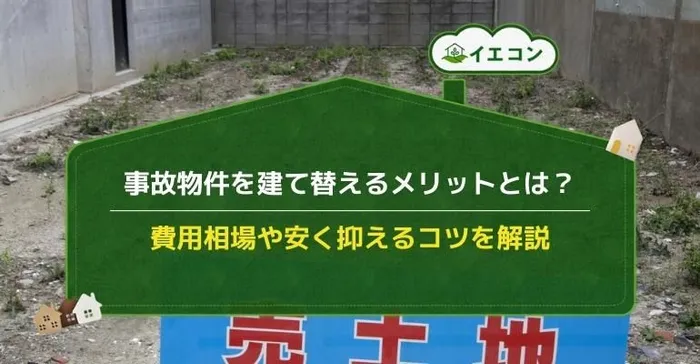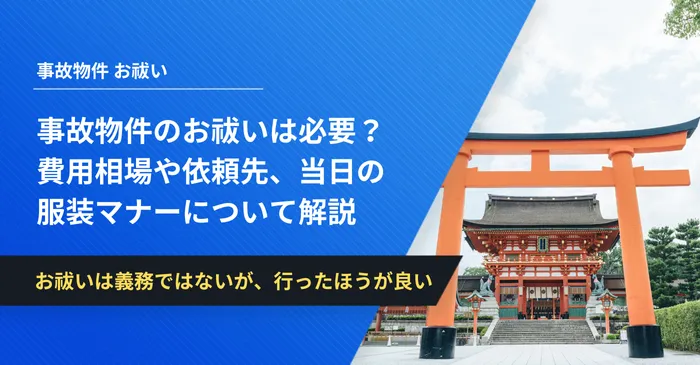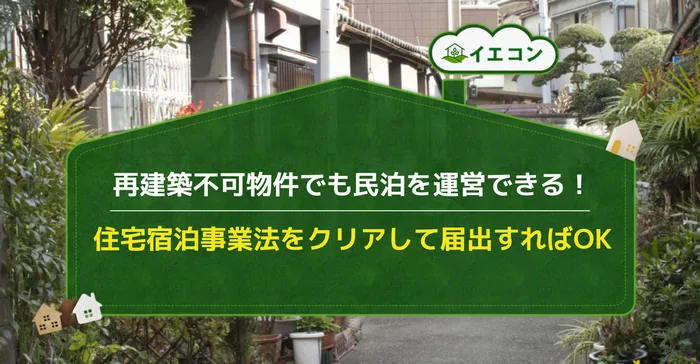不動産で自殺や殺人などの事件が発生すると、その物件は心理的瑕疵物件、いわゆる事故物件になってしまいます。
事故物件を民泊運営することで、利益を上げようと考える人もいることでしょう。
たしかに届出を提出することで、事故物件でも民泊運営可能です。
しかし、実際に事故物件を民泊として運営することは非常に困難です。
そこで、事故物件に居住しないのなら、売却することをおすすめします。訳あり不動産専門の買取業者であれば、事故物件をリフォームせずそのままの状態でも買い取ってくれます。
事故物件を民泊運営する際の注意点
所有している事故物件を民泊として営業することを検討している人もいるでしょう。
しかし、事故物件を民泊運営する際は以下のことに注意しなくてはなりません。
- 心理的瑕疵があることを必ず告知する
- リフォームだけではなくお祓いもしておく
次の項目から、具体的に見ていきましょう。
心理的瑕疵があることを必ず告知する
事故物件とは、その物件内で事件や事故などがあり「その事実を知った人が居住・宿泊することを避けたくなる」物件を指します。
そして、事故物件を売却・貸出するときは告知義務があります。
告知義務とは、物件について知り得る情報を売主から買主へ告知しなければならない義務のことです。
たとえ一泊のみの宿泊施設だとしても、その物件で過去に事件があったことは、必ず告知しなければいけません。
告知義務を果たさなければ、損害賠償請求される恐れもあります。心理的瑕疵物件であることを隠さず、トラブルを避けましょう。
リフォーム・お祓いをしておく
事故物件を事故当時の状況で利用する人は、まずいないでしょう。
遺体の血痕や体液が染み付いた状態の部屋は、見た目に不気味な印象を与えるだけでなく、感染力の高いウイルスが発生するなど、衛生面や健康面でも問題があります。
民泊物件を営業するには、役所の許可が必要ですので、そのような状態では、民泊物件として認可が下りることはまずありません。
ですので、事故物件を民泊物件に転用するには、リフォームやリノベーションは必須です。内装の入れ替えだけではなく、神職の方に頼んでお祓いもしておきたいところです。
お祓いをすることで安心する人はまだ多くいます。
きちんとお祓いをして、亡くなった人を供養した事実を伝えれば、心理的な不安が減るため、納得して多くの人が泊まってくれるでしょう。
民泊営業に必要な手続きと流れ
つづいて、事故物件を民泊に転用して営業するために、必要な手続きを説明します。
じつは「民泊」に法律上の明確な定義はありません。
一般的には「住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して、宿泊サービスを提供すること」とされています。
この表記にしたがい「民泊」を営業する際に必要な手続きを確認してみましょう。
民泊には3つの形態がある
民泊には、3つの形態があります。
②国家戦略特区法による認定を受ける方法
③住宅宿泊事業法(民泊新法)による届出を行う方法
①の「許可」は行政機関から許可が降りて、初めて営業可能になります。
これに対して、②の「認定」は法律が定める要件を満たせば営業できます。ですので「認定」の方が「許可」よりもハードルは低いです。
③の「届出」は、要件を満たした上で行政機関に届出すれば、すぐに営業可能です。
届出の場合、認定よりもハードルは低くなります。
以上から、もっとも手間なく民泊営業するなら、③の民泊新法による方法がベストです。
なお、民泊を営業するには所定の手続きが必要となり、手続きせずに民泊を営業した場合、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金を課される恐れがあります。
次の各号のいずれかに該当する者は、これを六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項の規定に違反して同項の規定による許可を受けないで旅館業を営んだ者
二 第八条の規定による命令に違反した者出典:旅館業法第10条
①旅館業法による簡易宿泊所営業許可
旅館業法によれば、都市計画法上の住居専用地域や工業地域等では、宿泊施設の営業が認められません。
また、設備などの要件も他の形態と比べて、もっとも厳格です。
一方で、営業許可さえ下りれば、他の形態のような営業上の制限はありません。
- 法律の定める要件を物件が満たす(用途地域の制限、床面積、消防設備、その他の設備)
- 許可申請書に必要書類を添えて都道府県へ所定の手数料を納めて許可を申請する(保健所を設置する市、特別区では市または特別区)
- 申請に許可が下りると、申請内容や設備などの現地調査がおこなわれる
これらの手続きを経た上で、問題無いと判断されると、許可が下りて営業可能になります。
②国家戦略特区法による認定
国家戦略特区法による認定の条件は、次の通りです。
- 特区として認められた自治体であること
- その地方自治体が条例を定めていること
国家戦略特区でも、都市計画法上の用途地域による制限があり、住居専用地域、工業地域での民泊営業は認められていません。
また建築基準法の都合上、民泊施設の用途は住宅・共同住宅でなければなりません。
国家戦略特区法の場合、戦略特区における民泊営業の条件にも注意が必要です。
国家戦略特区法による民泊では、2泊3日以上の施設滞在が必要で、1泊だけのお客さんは宿泊できません。
また手続きに際し、施設の所在地が戦略特区内にあり、条例が定められていることを確認する必要があります。
具体的な方法については、条例を確認する必要があります。
- 所定の書類を添付した申請書を作成して、手数料を都道府県に納めて申請する(保健所を設置する市、特別区では市または特別区)
- 申請が認められると、書類審査がおこなわれる
- 書類審査に通過すると、現地調査が入る
要件を満たすことが確認されると認定となり、民泊施設として営業可能になります。
③住宅宿泊事業法(民泊新法)による届出
この届出は、2018年6月から施行された住宅宿泊事業法によって認められた形態です。
旅館業法や特区民泊とは異なり、原則として用途地域による制限はありません。(例外的に条例で制限されている場合もあるため、事前確認が必要です)
最大の特徴は、営業日数が物件単位で年間180日以内に規制されている点です。
また営業者が常駐しない場合、管理業者に管理を委託する必要があります。
住宅宿泊事業法で定められている、民泊営業できる対象物件は以下のとおりです。
- 現に人の生活の本拠として使用されている家屋(自宅の空部屋)
- 入居者の募集が行われている家屋(賃貸物件・分譲物件として入居者等を募集中の物件)
- 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋(セカンドハウス・別荘等)
つまり、当初から民泊営業する目的で建てられた物件は、住宅宿泊事業法では営業が認められません。
消防設備については、自宅の空部屋を利用する場合には原則として必要ありませんが、それ以外は一定の設備を備える必要があります。
営業への手続きですが、営業開始日の前日までに所定の方法で、各都道府県に必要書類を添付して届出します。
添付書類は大きく分けて以下の3種類に分かれます。
- 届出者が欠格事由に該当していないことを証明する書類
- 物件が民泊営業するために必要な要件を満たしていることを証明する書類
- 民泊事業の営業が許された物件であることを証明する書類
届出は、所定の届出書を紙面で提出する方法と、オンラインシステム(民泊制度営業システム)から行う方法の2つがあります。
届出に手数料は必要なく、届出のみで足りるため、その後の許可や認定などを待つ必要はありません。
参照:民泊制度営業システム
民泊営業で収益を上げる3つのポイント
民泊物件は民泊新法の施行により、ビジネスモデルが大きく変わりました。
民泊新法では日本全国で民泊物件の営業ができますが、年間の営業日数が180日以内と制限されています。
空室が発生する中、半年間しか営業できない状況で、どうすれば収益を上げられるのか、そのポイントをお伝えします。
1.他の民泊物件との差別化を図る
半年の間しか稼働できない以上、収益を上げるには稼働率を高めるのではなく、宿泊料と客単価を上げる必要があります。
客単価を上げるには価格競争に参加するのではなく、自分の物件でしか味わえない体験を提供するなど、競合する民泊施設との差別化を図らなくてはいけません。
客単価を高めるには、初期投資で内装に力を入れたり、オプションサービスを設けたりと、工夫を凝らす必要があります。
2.観光地でアクセスのよい場所に物件を持つ
民泊物件を利用する人は、外国人観光客がほとんどです。
そして、外国人観光客が日本に訪れる理由は、ずばり観光のためです。
観光地でアクセスのよい場所に民泊物件を持てば、観光に訪れた人の宿泊先として十分な需要が見込めます。
ただし、事故物件の立地が悪ければ、収益をあげることは困難でしょう。
3.他の店舗や施設との併合型にする
差別化の一環ですが、民泊物件内のすべての部屋を宿泊施設にするのではなく、店舗などの複合施設型の民泊物件として営業することもひとつの手です。
半分を宿泊施設、もう半分を体験型店舗などにして営業することを考えてみましょう。
観光客は色々な場所に向かわずに、一箇所で文化を満喫できます。
事故物件を活用するなら売却がおすすめ
ここまでは事故物件を民泊運営する方法や収益をあげるポイントを説明しました。
しかし、実際には事故物件を民泊として運営することは非常に困難です。
リフォーム・リノベーションなどの初期費用をかけたとしても、民泊運営によって初期費用を回収できるとは限りません。
そこで、事故物件に居住しないのなら、売却することをおすすめします。
訳あり不動産専門の買取業者であれば、事故物件をリフォームせずそのままの状態で買い取ってくれます。まずは以下のフォームから、相談してみるとよいでしょう。
不動産を現金化
売却したいなら
訳あり物件買取専門の
当社にお任せください!

まとめ
事故物件を民泊物件に転用して、営業するのは決して容易ではありません。
物件にリフォームやリノベーションを施して、お祓いをしてから役所での手続きが必要となるため、費用も時間も掛かります。
一方で、そのコストに見合う収益を得られることが、民泊営業の最大の魅力です。
もしも、事故物件の扱いに困っているなら、売却することも検討すべきです。
訳あり不動産専門の買取業者であれば、事故物件であっても高値で売却可能です。