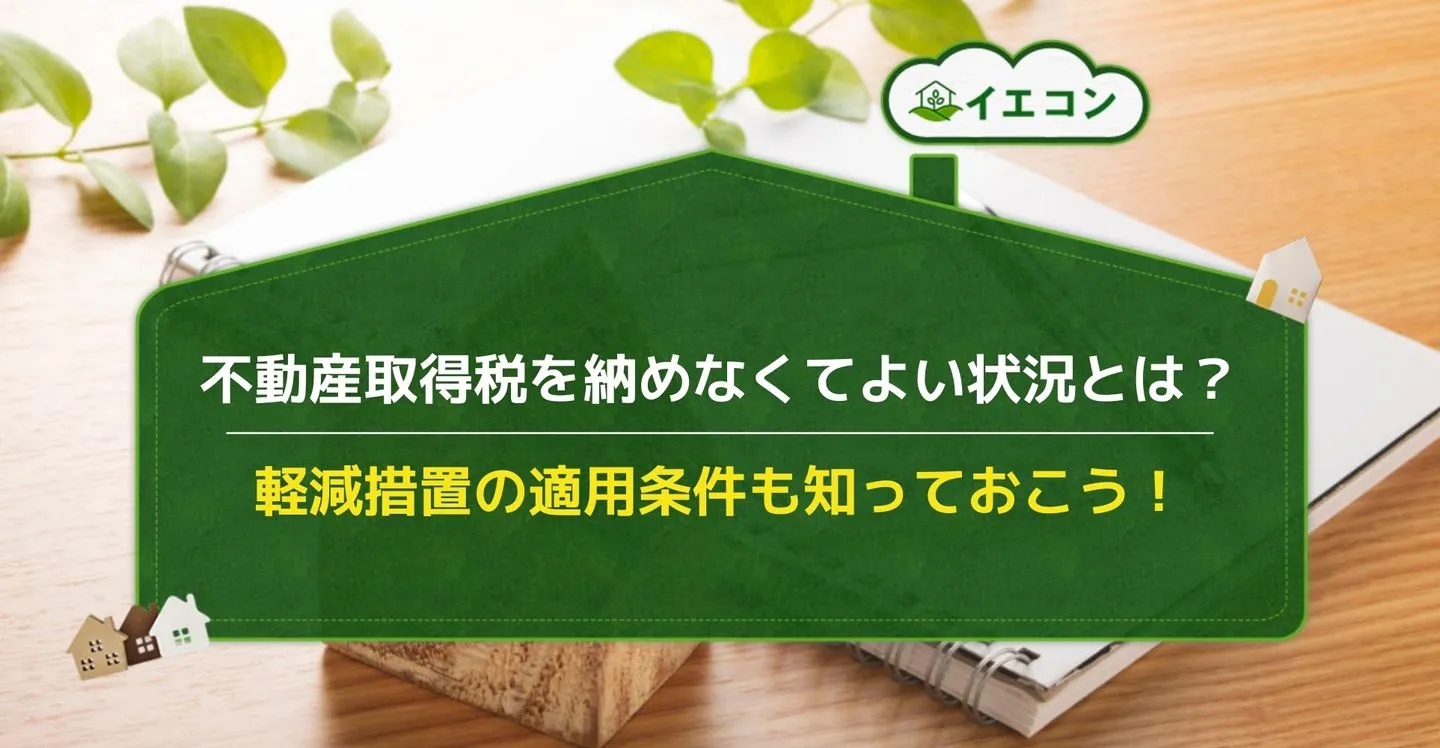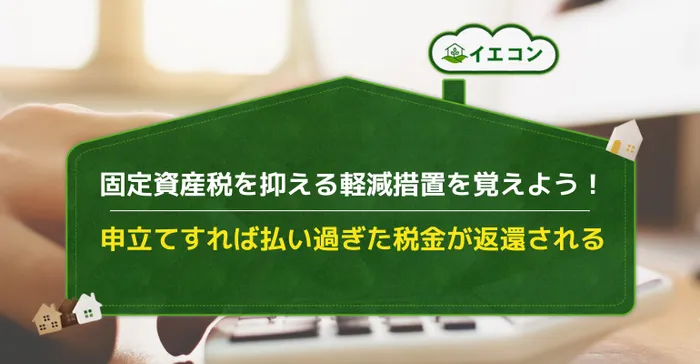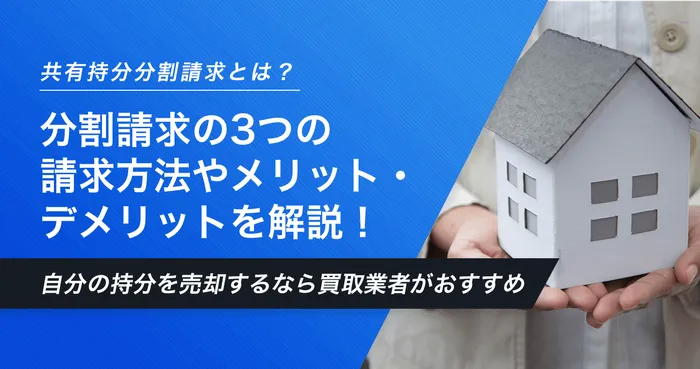不動産の売買や贈与には、数々の税金が発生します。
「不動産を取得する」という行為にも税金が課され、その税金を「不動産取得税」といいます。
不動産取得税には様々な軽減措置や控除・特例が設けられており、上手に活用すれば不動産取得税を0円にすることも可能です。
税額を少しでも抑えるためには、税制度の把握と適切な手続きが大切です。
一般の人では難しい判断が必要となるので、専門家である税理士の力を借りましょう。税理士なら、適切な節税方法についてアドバイスが可能です。
不動産取得税の節税に使える軽減措置

不動産取得税は、課税標準額(固定資産課税台帳に登録されている価格)に、税(標準4%)を乗じて計算します。ただし、宅地や宅地に類する土地に関しては、課税標準額を1/2で計算する特例が適用されます(2021年現在)。
取得した建物や土地が一定の条件に当てはまる場合、不動産取得税を軽減できる制度があります。具体的な軽減措置の例を見ていきましょう。
1.課税標準の控除および税率の軽減措置
不動産取得税において、一律で適用される軽減措置です。課税標準の控除および税率の軽減を受けられます。
課税標準は、新築住宅の場合は1戸につき1200万円、中古住宅の場合は「当該住宅の新築時に地方税法で規定されていた金額」を控除可能です。
税率は標準の4%ですが、新築または中古住宅を取得し、次の要件を満たす場合には3%に軽減されます。
| 新築住宅の場合 | ・住宅の床面積が50㎡(共同賃家住宅の場合は40㎡)以上、240㎡以下であること |
|---|---|
| 中古住宅の場合 | ・住宅の床面積が50㎡以上、240㎡以下であること ・耐火建築物は築25年以内、木造等は築20年以内 ・昭和57年1月1日以降に新築されたもの ・一定の耐震基準を満たしていること |
2.認定長期優良住宅に係る軽減措置
認定長期優良住宅に該当する住宅を新築したときに適用され、課税標準からの控除額を100万円増額し、1300万円の控除とするものです。
ここで言う長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための処置が、構造や設備に取り入れられている優良な住宅のことです。
具体的には、次のような機能を備えた住宅を指します。
| 劣化対策 | 数世代に渡って住み続けられるような構造の住宅であること |
|---|---|
| 耐震性 | 免震構造、あるいは耐震等級2以上の耐震性を備えていること |
| 省エネ性 | 断熱性能などの省エネルギー性能が備わっていること |
| 住戸面積 | 75㎡以上であり、一つの階層が40㎡以上あること(地域により規定に相違あり) |
| 計画的な維持管理 | 内装・設備の清掃や点検、補修、更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること |
| 居住環境 | 景観などについて配慮された建物であること |
長期優良住宅として認定されるためには、建物の着工前に建築および維持保全に関する計画を所管行政庁へ申請する必要があります。
申請する計画が満たしていなければならない基準は、次の4点です。
- 住宅の構造および設備について、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられていること
- 住宅の面積が、良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること
- 地域の居住環境の維持・向上に配慮されたものであること
- 維持保全計画が適切なものであること
3.買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置
この特例は、不動業者(宅地建物取引業者)向けの特例です。直接的に税額軽減の恩恵を受けるのは事業者ですが、消費者にとっても良質で安心な住宅が提供されるなどの、間接的な恩恵がもたらされることになります。
既存の建物(住宅)を取得し、住宅性能の向上のためにリフォーム工事を行ってから居住用住宅として販売する場合、建物の取得に際して課される不動産取得税の課税標準から一定額を控除するという特例措置です。
控除額は、当該住宅の築年月日に応じて次のように異なります。
- 平成9年4月1日以降:1,200万円
- 平成元年4月1日~平成9年3月31日:1,000万円
- 昭和60年7月1日~平成元年3月31日:450万円
- 昭和56年7月1日~昭和60年6月30日:420万円
- 昭和51年1月1日~昭和56年6月30日:350万円
- 昭和48年1月1日~昭和50年12月31日:230万円
- 昭和39年1月1日~昭和47年12月31日:150万円
- 昭和29年1月1日~昭和38年12月31日:100万円
この軽減措置によって、不動産業者がリフォームした一定以上の品質を備えた住宅の販売が促進されることが期待されています。
参照:国土交通省「買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置 不動産取得税の特例措置について」
「安心R住宅」に該当すればさらに減額される
「安心R住宅」とは、耐震性が確保され、インスペクション(建物状況調査等)がおこなわれた住宅をいいます。また、リフォームなどについて下記の情報提供がおこなわれている必要もあります。
具体的な要件としては、下記のものがあげられます。
- 耐震性などの基礎的な品質を備えている
- リフォームを実施済み又はリフォーム提案が付いている
- 点検記録等の保管状況について情報提供が行われる
「安心R住宅」に該当する住宅もしくは「既存住宅売買瑕疵担保責任保険」に加入する住宅の場合、4万5,000円または「土地1㎡あたりの評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(上限200㎡)×3%」の、いずれか多い方が不動産取得税から減額されます。
中古住宅の検査と保証が合わさった保険です。加入できるのは、保険法人に登録された宅地建物取引業者または住宅の調査をおこなった登録検査事業者です。
中古住宅の購入後に主要部分で欠陥が見つかった場合、宅地建物取引業者または検査事業者に保険金が支払われます。
業者はその保険金を使って、欠陥の修繕をおこないます。
※業者が倒産している場合、住宅の買主に直接支払われます。
参照:国土交通省「買取再販で扱われる住宅の取得等に係る不動産取得税の特例措置について」
申請することで不動産取得税が減免される2つのケース

不動産取得税は一般的な税金と異なり、納税義務者が申告することで課税されるものではありません。
課税される場合のみ、都道府県から納付書が送られてきます。
しかし、納税義務者となり得る人が自ら申請することで、不動産取得税の軽減や免除の特例を受けらる場合があります。
1.災害などによって不動産が滅失した場合
災害などによって不動産が滅失した場合、次の要件のどちらかにあてはまれば、被災の程度に応じて不動産取得税が減免されます。
- 不動産取得税の納期限までに、該当不動産が災害などで滅失または損壊した場合
- 災害などにより滅失または損壊した不動産があり、その代わりに他の不動産を災害などの発生後3年以内に取得した場合
ただし、土地については、崖崩れや地滑りなどによって実際に地積が減じたことが認められる場合に限ります。また、家屋の床上および床下浸水については減免の対象外です。
参照:東京都主税局「災害などにより被害を受けた方には都税を減免する制度があります」
2.土地区画整理事業に関連して移転した場合
土地区画整理事業などの公共事業で移転を余儀なくされ、その補償金で代わりの建物を取得した人に対しては、当該建物の不動産取得税相当額が減免されます。
ただし、移転前に所有していた建物を除却した日から2年以内、もしくは仮換地を引き渡した日から2年以内に代わりの建物を取得した場合に限っての特例です。
また、移転前の建物所有者と新たに建築する建物の所有者が同一であることも要件です。
不動産取得税が非課税になる2つのケース

そもそも、不動産取得税が課されない状況というものがあります。下記の2つは、不動産取得税の課税対象になりません。
- 法定相続人が相続・遺贈を受けることによる不動産取得
- 共有物の分割による不動産取得
それぞれの状況について、詳しく見ていきましょう。
1.法定相続人が相続・遺贈を受けることによる不動産取得
1つ目のケースは、法定相続人が相続・遺贈を受けることによる不動産取得です。
相続による不動産取得は予測のできない事であり、取得者の意思によるものではないケースがほとんどです。
また、相続は「不動産を取得した」というより、当然受け継ぐべき人へ所有権が移動したという表現の方が適切でしょう。
そのような事象に対して税金を課すということは不合理と言えるため、不動産取得税が非課税になっています。
遺言書による指示(遺贈)であっても、受贈者が法定相続人であれば非課税となります。
法定相続人以外は課税される
法定相続人でない人が遺贈によって不動産を取得する場合、不動産取得税は課されるので注意しましょう。
法定相続人でない人には「当然に不動産を取得する権利」はなく、その義務もないことから、偶発的に得た利益と見なされるため課税されます。
また、生前贈与や死因贈与による不動産取得は、法定相続人であっても課税されます。
2.共有物の分割による不動産取得
2つ目のケースは、共有物の分割による不動産取得です。
共有名義にある不動産は、持分割合に応じて分割(共有状態の解消)をおこなう場合があります。
この「共有不動産の分割」で取得した不動産については、不動産取得税が非課税となります。
ただし、分割後に取得した不動産が、共有していたときの持分割合より増えた場合は、不動産取得税が課税されるので注意しましょう
まとめ
不動産取得税は、軽減措置や特例を活用することで、0円にすることも可能です。
しかし、税金の制度は複雑なうえ、頻繁に改正されます。そのため、不動産取得時は最新の情報を確認することが大切です。
税金について不安や疑問があれば、専門家である税理士に相談しましょう。税理士なら、個々のケースにあわせて最適な節税方法を提案できます。