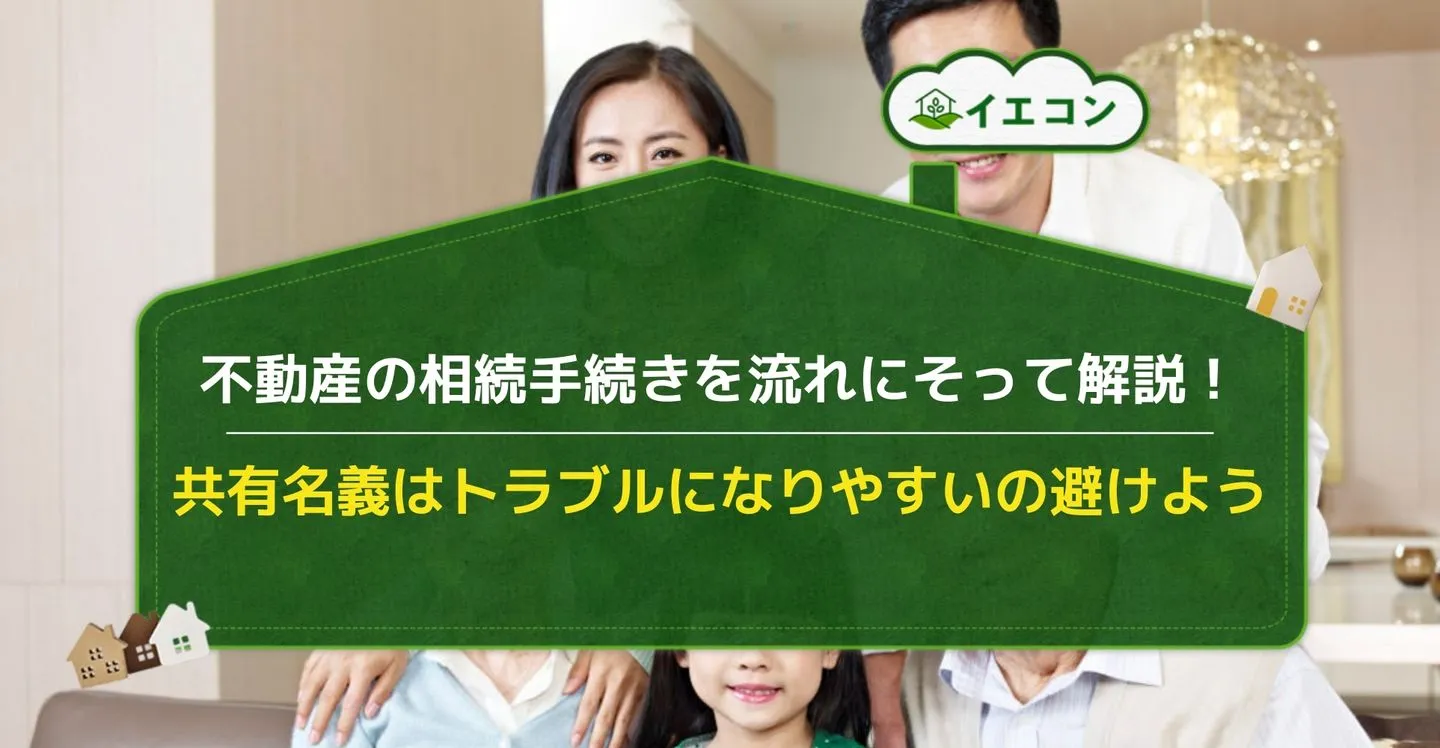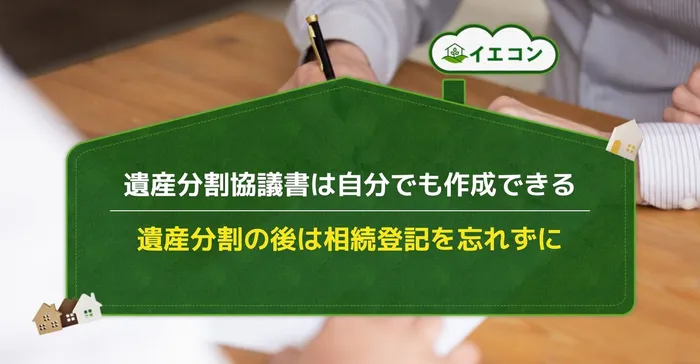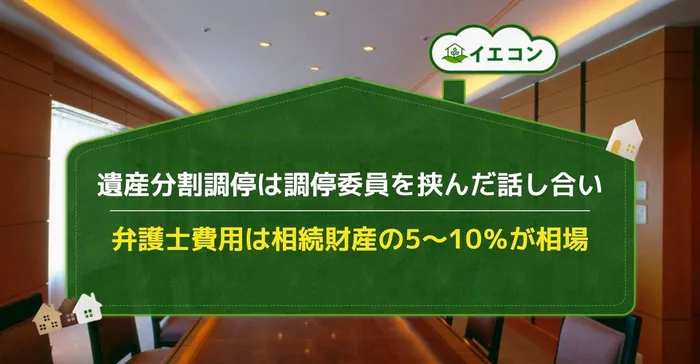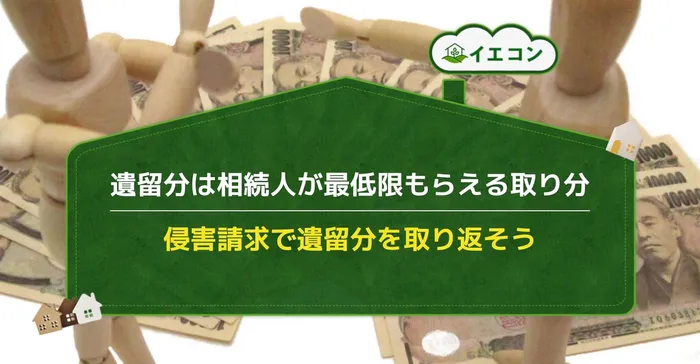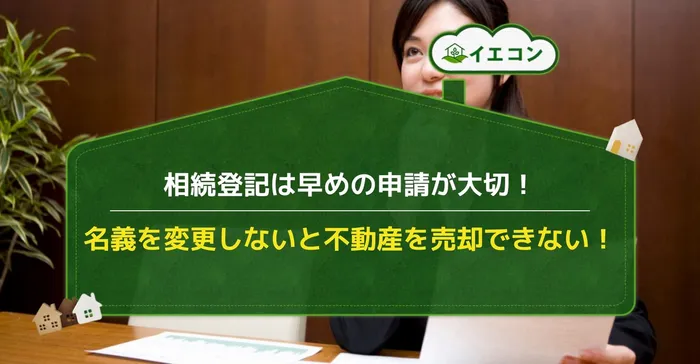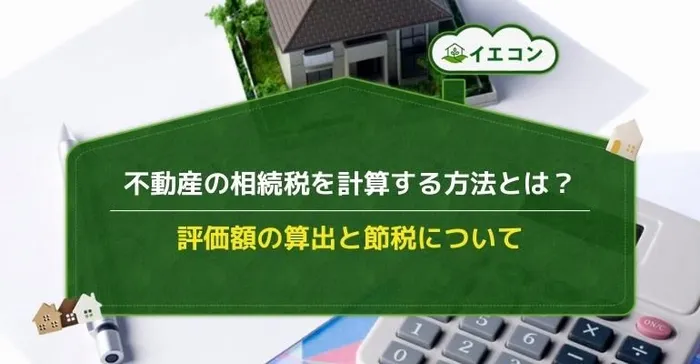家族や親族が亡くなったとき、考えなければいけないのが相続手続きのこと。
葬儀の準備に追われたり、気持ちの整理ができていなくても、さまざまな手続きをおこなわなければなりません。
不動産の相続手続きをスムーズに終わらせるためには、正しい手順の把握が必要です。
また、弁護士や司法書士といった、各専門家の力も積極的に借りましょう。
相続不動産の処分まで考えるなら、弁護士と連携した不動産買取業者に相談するとよいでしょう。不動産売却だけでなく、相続に関する悩みまで一貫したサポートが受けられます。
不動産相続の基本的な流れ

まずは、相続が開始されてから不動産の相続が終わるまでの基本的な流れを、時系列順に整理しておきましょう。
不動産相続の流れは以下のとおりです。
- 死亡届を提出する
- 遺言書の有無を確認する
- 必要書類を準備する
- 遺産分割協議を実施する
- 相続登記をおこなう
- 相続税を申告する
1.死亡届を提出する
被相続人が亡くなったとき、最初におこなうことは「死亡届の提出」です。
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません。
ただし、国外で死亡が確認されたのであれば、その事実を知った3カ月以内でも大丈夫です。
死亡届の提出先は、死亡者の死亡地もしくは本籍地、または届出人の所在地の役所です。
また、死亡届の届出人になれる対象者は、次のとおりです。
- 親族
- 同居者
- 家主や地主
- 家屋や土地の管理人
- 後見人や保佐人・補助人
上記のとおり、必ずしも相続人が届け出る必要はありません。
参照:法務省「死亡届」
参照:法務省「死亡届の記載例」
2.遺言書の有無を確認する
相続においては、遺言書の内容が最も優先されます。そのため、被相続人が遺言書を残していないか確認が必要です。
公証役場や法務局に預けている場合があるので、まずは問い合わせてみることをおすすめします。
また、自宅で保管している場合もあるため、家のなかも丁寧に探しましょう。
「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の違い
遺言書には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つがあります。
| 公正証書遺言 | 公証人の助言のもと作成された遺言書。内容や書式に間違いのないことが保証される。 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | 被相続人が自分で書いた遺言書。 |
公正証書遺言は「被相続人の意向にそって、正しく作成された遺言書」であることが保証されます。公証役場で保管され、改ざんのリスクを防げるのも特徴です。
一方、自筆証書遺言は偽造のリスクもあるため、家庭裁判所の「検認」のもと開封しなければいけません。
検認を受けずに自筆証書遺言を開封した場合、過料が課されます。また、遺産分割においても偽造・改ざんを疑われ、相続トラブルに発展するでしょう。
ただし、2020年7月からはじまった「自筆証書遺言保管制度」を利用していれば、自筆証書遺言でも検認は不要となります。
自筆証書遺言保管制度とは、法務局で自筆証書遺言を保管・管理する制度です。
参照:法務省「遺言書の検認」
参照:法務省「法務局における自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度について」
3.必要書類を準備する
不動産相続の手続きでは多くの書類が必要になります。なるべく早いうちに準備をはじめましょう。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 不動産の固定資産税評価証明書
- 不動産を相続する人の住民票
これらの書類収集は時間もかかるため、不動産の相続手続きのなかでも負担の大きい作業です。
自力で書類を集めるのが難しい場合、弁護士・司法書士などの専門家に代行してもらうことを検討しましょう。
「相続関係情報証明制度」とは?
相続手続きにおける書類収集の負担はとても大きなものです。とくに、財産や相続人が多ければ多いほど、手続きのたびに多くの書類を提出する必要があります。
収集漏れやミスも起こりやすく、書類不備のせいで手続きをやり直すケースも珍しくありません。このようなリスクを防ぐために、法務局の「相続関係情報証明制度」を利用しましょう。
登記官の認証を受けた「法定相続情報一覧図」の写しを提出するだけで手続きを進められるようになり、書類収集・管理の手間を軽減できます。
4.遺産分割協議を実施する
遺言書が残されていなかった場合、相続人同士の話し合いによって相続財産の分割方法を決定しなければなりません。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
また、遺言書が残されていても相続人全員の合意があれば、遺産分割協議によって異なる配分での遺産分割が可能です。
遺産分割協議の結果は「遺産分割協議書」という文書に記録します。遺産分割協議書は不動産や預貯金の名義変更に必要なので、忘れずに作成しましょう。
遺産分割協議書の書き方に法的なルールはありませんが、記載すべき内容はある程度決まっています。
下記の関連記事を参考にするか、弁護士・司法書士に作成を依頼しましょう。
遺産分割協議がまとまらない場合は調停や審判を申立てる
遺産分割協議は「相続人全員の同意」がなければ成立しません。
そのため、各相続人の意見が対立して話し合いが進まないケースも少なくありません。
協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停・審判を利用して遺産分割を決めることも可能です。
相続トラブルが起きたときは、弁護士に相談することも大切です。調停・審判をおこなう場合も、各種手続きを一任できます。
不動産を分割する方法は4つある
不動産を複数の相続人で分割するには、下記の方法があります。
- 現物分割:不動産を分筆する(切り分けて個別の名義にする)方法
- 代償分割:代表者が単独で相続し、他の相続人に代償金を支払う方法
- 換価分割:不動産を売却し、売却益を分割する方法
- 共有分割:不動産を共有名義にして相続する方法
現物分割で切り分ける方法もありますが、基本的には代償分割・換価分割など現金による精算のほうがトラブルは少ないでしょう。
また、実際の相続では、不動産に限らずさまざまな種類の財産を分割します。全体で公平となるよう分割することが大切です。
各相続人の「遺留分」を無視した遺産分割はできない
遺留分とは、法定相続人が最低限もらえる「相続の取り分」です。
被相続人の遺言においても、遺産分割協議においても、遺留分を無視した分割は無効となります。
遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害請求によって、侵害額を取り返すことが可能です。
5.相続登記をおこなう
遺産分割の方法が決まったら、法務局で相続登記をおこないます。相続登記とは、財産の名義を被相続人から相続人へ変更する手続きです。
相続した不動産を売却・活用したいのであれば、相続登記は必ず済ませる必要があります。
なぜなら、登記上の所有者になっていなければ、その不動産における権利を主張できないからです。
相続登記の必要書類
上記の「必要書類を準備する」でも触れましたが、相続登記に着目して整理すると、下記の書類が必要です。
- 被相続人の戸籍謄本や戸籍の除票
- 被相続人の住民票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明
- 不動産を相続する人の住民票
- 遺言書または遺産分割協議書
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 固定資産税評価証明書
被相続人の戸籍は、最新(死亡時)の戸籍だけではなく、過去に転籍した分も取り寄せなければいけません。
なぜなら、被相続人の戸籍は死亡を確認するためだけでなく、相続人の範囲を調査するためにも必要となるからです。
もし被相続人が転籍を繰り返しているのであれば、過去の戸籍をすべて集めましょう。
相続登記の費用
相続登記をおこなうときには「登録免許税」と呼ばれる手数料を納付しなければいけません。登録免許税の金額は「固定資産税評価額の0.4%」です。
なお、固定資産税評価額は1000円未満の端数を切り捨てて計算し、100円未満の登録免許税も切り捨てとなります。
例えば、固定資産税評価額が500万900円だった場合の登録免許税額は「500万円×0.4%=2万円」です。
また、相続登記の手続きを司法書士に依頼した場合、司法書士に支払う報酬も必要となります。
司法書士の報酬額は個別のケース次第で異なりますが、数万円~10万円程度が相場です。
参照:日本司法書士会連合会「報酬に関するアンケート(平成25年2月実施)第1 所有権移転登記-4 相続」
6.相続税の申告をする
相続開始から10カ月以内に、相続税の申告をおこなう必要があります。期限に間に合わないと延滞税が発生するため、早めに申告しましょう。
申告は、被相続人の死亡時における住所地を管轄する税務署でおこないます。
相続税の計算は非常に複雑です。適用できる控除を見落とさず、正確な申告ができるよう、税理士に相談しましょう。
不動産相続の注意点
不動産の相続において、とくに注意すべきポイントを3つ解説していきます。
- 共有名義にするとトラブルが起こりやすい
- 自宅の相続では「配偶者居住権」が設定されている場合がある
- 空き家を放置していると倒壊などのリスクがある
スムーズかつトラブルのない不動産相続をおこなうために、上記の3点は押さえておきましょう。
【注意点1】共有名義にするとトラブルが起こりやすい
不動産を分割することはむずかしいため、相続人の共有名義で相続するケースは少なくありません。
しかし、共有名義の不動産は、利用や管理・処分に共有者との話し合いが必要です。そのため、意見の対立や維持費の負担でトラブルになりやすいといえます。
相続にあわせて不動産を売却するなど、共有名義を避ける方法で相続するとよいでしょう。
共有名義にするより売却したほうがトラブルを防げる
不動産を売却し、売却益を分割すれば、遺産分割をスムーズかつ公平に済ませられます。
ただし、売却に時間がかかると相続手続きにも支障があります。そのため、相続不動産を売却したい場合は、短期間で売却できる買取業者がおすすめです。
とくに「弁護士と連携した買取業者」なら、不動産の売却だけでなく相続トラブルまでサポートできます。
当サイトを運営するクランピーリアルエステートも、弁護士と連携している不動産買取業者なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
不動産を現金化
売却したいなら
共有持分買取専門の
当社にお任せください!

【注意点2】自宅の相続では「配偶者居住権」が設定されている場合がある
2020年4月から「配偶者居住権」という制度が設けられました。配偶者居住権とは、遺された配偶者が「亡くなった人の所有していた建物」に居住する権利を保護する制度です。
従来、配偶者が単独で自宅を相続すると「他の財産を相続できなくなる」「他の相続人に代償金を支払う必要が生じる」などのデメリットがありました。
しかし、自宅の「所有権」と「居住権」を分けて考え、居住権を「遺産分割の対象とせず配偶者が必ず得られる権利」とすることで、配偶者がその他の財産も相続しやすくしたのです。
被相続人が生前に配偶者居住権を登記している場合があるため、登記情報を確認しておきましょう。
【注意点3】空き家を放置していると倒壊などのリスクがある
相続不動産を利用する人がおらず、空き家のまま放置されるケースは少なくありません。
しかし、空き家の放置はさまざまなリスクがあります。
- 建物が老朽化で倒壊する
- 放火や不法投棄などの犯罪に巻き込まれる
- 維持や管理にコストがかかる
建物が倒壊し、近隣の住民に被害が出た場合、損害賠償を請求される恐れがあります。
また、「保安上もしくは衛生上の危険が高い」「景観・近隣の生活環境に悪影響がある」などと判断されると、自治体から特定空き家に指定されます。
特定空き家に指定されると、固定資産税の軽減措置がなくなったり、過料が課されたりします。「行政代執行」で空き家を解体され、高額な解体費用を請求される可能性もあるのです。
空き家の放置はリスクが高いため、なるべく早く処分できるよう行動しましょう。
まとめ
不動産相続は、葬儀や故人の身辺整理などと並行して、さまざまな手続きをおこなう必要があります。
手続きに不安があったり、時間が取れないような場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。
また、不動産は所有しているだけでも多くのコストが生じます。資産価値よりもコストの方が高くなってしまうケースは珍しくありません。
相続不動産が不要であれば、相続にあわせて売却することも検討しましょう。弁護士と連携した不動産買取業者なら、総合的なサポートが可能です。