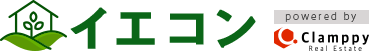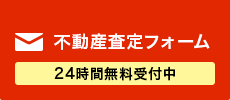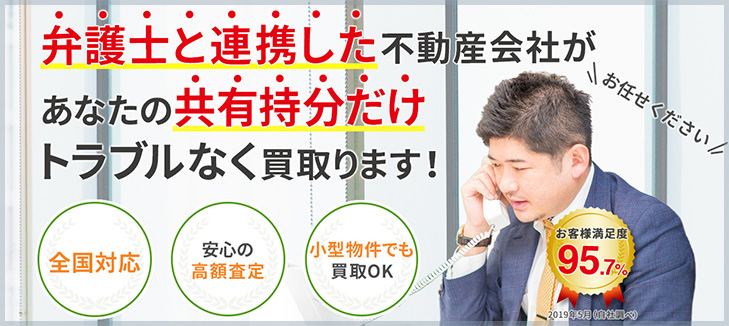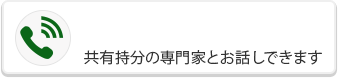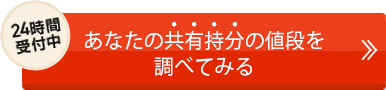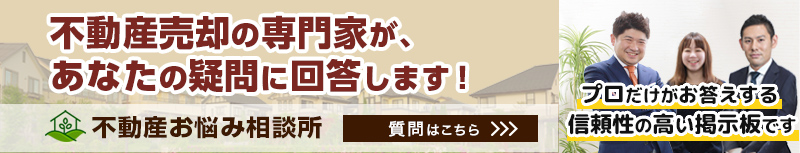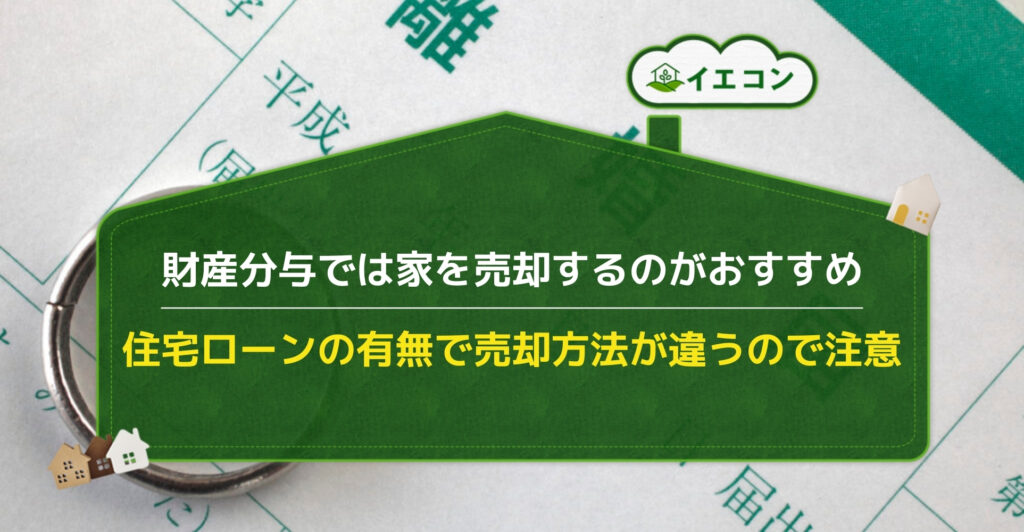
離婚する際、不動産の財産分与で悩む夫婦は多いでしょう。
財産分与は、夫婦で財産を1/2に分けるのが原則です。不動産のままでは1/2にわけられないので、売却して現金で分割したり、どちらかが単独で取得する代わりに金銭を支払うといった方法があります。
離婚時に不動産を財産分与するなら、後からトラブルになりにくい「売却」がおすすめです。売却して現金で分割すれば、1円単位で公平な財産分与ができます。
ただし、離婚時の家売却は、スムーズに進めないと離婚手続きも遅れてしまう可能性があります。不動産会社のなかでも、自社で物件を直接買い取る「買取業者」に相談するのがおすすめです。
弁護士と連携した買取業者であるクランピーリアルエステートなら、最短48時間での現金化も可能なので、迅速な売買を希望するときはぜひお問い合わせください。
【無料で査定!】財産分与でスムーズな家売却をしたい方はこちら
目次
財産分与とは離婚時に財産を1/2に分配すること
民法では、離婚の際、相手に対して、財産の分与を請求できると定められています。これを「財産分与」といいます。
結婚している間に夫婦で協力して築き上げた財産は、どちらか一方だけのものではなく、お互いの所有物です。
そこで、離婚する際には、それぞれの貢献度(一般的には、1/2ずつ)に応じて分配することになっています。
離婚時の財産分与の方法については、以下の記事でさらに詳しく解説しているので参考にしてください。
夫婦共有名義の家を財産分与する方法!住宅ローンがある場合の解決法も紹介
財産分与の対象にならない家
家は夫婦にとって大きな資産のひとつでしょう。
しかし、以下の家は財産分与の対象となりません。財産分与の対象とならない家とは、夫婦で協力して手に入れたものではない物件のことです。
具体的には、次の3つの方法で取得した家が、一般的に財産分与の対象外となるものです。
- 結婚前から所有していた家
- 結婚前から所有していた財産で購入した家
- 相続により取得した家
次の項目から、それぞれ詳しくお伝えしていきます。
結婚前から所有していた家
結婚前から所有していた家は、どちらか一方の努力により取得したものとなるので、財産分与の対象とはなりません。
結婚前から所有していた財産で購入した家
例えば、婚姻直後に、夫が独身時代から積み立てていた定期預金により、家を購入した場合、その家は夫婦で協力して築き上げた財産にならないので、財産分与の対象になりません。
※財産の状況などによっては、財産分与の対象になる可能性もあります。
相続により取得した家
夫婦どちらか一方の親族(父や母など)が亡くなり、相続で取得した家は、夫婦で協力して築き上げた財産とはいえないので、財産分与の対象になりません。
離婚時に家を財産分与する3つの方法
結婚している間に購入した家やマンションは、基本的に財産分与の対象になります。
しかし、お互いの貢献度で分けるといっても、家やマンションは簡単に2つにできるものではありません。では、どのように分けたらよいのでしょうか。ここでは、一般的な3つの方法を紹介します。

現物によって分与する方法
もっとも簡単な方法は、家やマンションのすべてをどちらか一方に分与する方法です。財産分与では、すべての財産の価値を求め、例えば半分ずつになるように、分与します。
そこで、家やマンションをどちらか一方に分与し、その他の財産を他の一方に分与します。
例えば、所有している財産が、3,000万円の価値を持つ家と現金・預金3,000万円である場合、妻に家を、夫に現金・預金を分与することにより、家のすべてを妻に分与できます。
相手に金銭の支払いをする方法
財産分与で家やマンションを分ける方法の1つに、一方(例えば夫)に家やマンションを全て分与する代わりに、他方(例えば妻)に金銭の支払いをする方法があります。
これは、他の財産の価値に比べて、家やマンションの価値が高い場合に用いられることが多いです。
例えば、所有している財産が、3,000万円の価値を持つ家と現金・預金1,000万円の合計4,000万円である場合、夫婦で半分ずつ分けるとなると、1人2,000万円ずつ分けることになります。
夫が3,000万円の家の分与を受けた場合、妻は現金や預貯金の1,000万円しか分与されず、不公平です。そこで、夫から妻へ1,000万円の金銭を渡し、1人2,000万円ずつ分与されたのと同じ状態にします。
売却し現金を分与する方法
夫婦どちらも、離婚後に家やマンションを引き継ぐ意思がない場合の分与の方法が現金化です。家やマンションを売却して得た金銭を、2人で分けます。
現金化することで財産の分与はしやすくなりますが、売却がなかなかできなかった場合、分与が完了するまでに時間がかかるなどの注意点もあります。
売却に時間がかかると、財産分与も終わりません。スムーズな売却をおこなうためには、不動産買会社のなかでも物件を自社で直接買い取る「買取業者」に相談しましょう。
当サイトを運営するクランピーリアルエステートも買取業者であり、豊富な売買経験や弁護士との連携を活かして、迅速な売買取引を実現します。家を売却する際は、お気軽にお問い合わせください。
>>【最短48時間で買取!】クランピーリアルエステートの無料査定はこちら
離婚時に家を売却する方法
家を売却する方法には「通常売却」と「任意売却」があります。
通常売却か任意売却かは、住宅ローン残債によって異なります。
そこでこの項目では、住宅ローン残債の状況と、それに合わせた売却の方法を解説しますので参考にしてください。
住宅ローン完済済みなら「通常売却」
住宅ローンを完済している場合は、問題なく売却に進めます。売却の際には、いくらで売却するかを不動産会社と相談します。ここで注意したいのが、業者によって売却価格の相場が異なるということです。
それは、不動産業者にはある地域に強い業者や、マンションの販売に強い業者など、強みの異なる様々な業者がいるからです。
アンダーローンなら「通常売却」
次に住宅ローンが残っている場合について、見ていきます。実は、住宅ローンが残っているケースには、住宅の売却価格より住宅ローンの残高が少ない場合と多い場合があります。
住宅の売却価格より住宅ローンの残高が少ない場合のことをアンダーローンといいます。アンダーローンの場合は、通常売却ができます。
住宅の売却価格から住宅ローンの残高を差し引いた残りが、金銭として受け取る金額です。
実際には、不動産業者や司法書士への手数料などの諸経費がかかるため、その分は受け取る金額から差し引かれます。
オーバーローンなら「任意売却」
家を売却する場合、気をつけなければならないのが、住宅の売却価格より住宅ローンの残高が多いケース、いわゆるオーバーローンの場合です。
オーバーローンの場合は、売却しても負債が残る、いわばマイナスの財産です。実は、マイナスの財産であるオーバーローンの場合は、財産分与の対象外になります。
そのため、オーバーローンになっている家の売却は通常できません。
この場合に用いる方法が「任意売却」です。任意売却とは簡単にいうと、融資を受けている金融機関の許可を得て、家を売却する行為のことです。
原則、売却代金は、住宅ローンの返済に充てられます。ただし、任意売却の場合は、家の売却ができても、ローン残高の返済を免除されるものではありません。
売却代金を返済に充てても、残っているローン残高部分については返済していく必要があります。
ローン残高は財産分与の対象にならず、ローン名義人が支払う必要があります。ただし、窓口がローン名義人であるというだけなので、返済方法はきちんと夫婦で話しあっておくことが大切です。
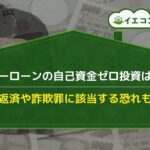
離婚時の家売却は弁護士と連携した不動産会社に相談しよう
離婚時の家売却は、離婚手続きや家の名義など、さまざまな法的知識が求められます。また、オーバーローンで任意売却をおこなうのであれば、金融機関との交渉が必要です。
そのため、離婚時の家売却は普通の不動産会社ではなく、弁護士と連携した不動産会社に相談することをおすすめします。弁護士によるサポートのもと、権利問題の解消や任意売却の交渉を任せられます。
当サイトを運営するクランピーリアルエステートも弁護士と連携した不動産会社なので、必要に応じて連携弁護士の紹介といった法的支援が可能です。
「不動産」と「法律」2つの専門家の観点から、あなたの家売却を的確にサポートするので、お気軽にご相談ください。
売却したいなら
共有持分買取専門の
当社にお任せください!
離婚で家を売却した場合の税金について

離婚で家を売却した場合、住宅ローンの取り扱いなどに気を取られがちですが、同じように注意しなければならないのが、税金のことです。
支払いが遅れると、延滞税などのペナルティがかかることもあります。
そこで、離婚で家を売却する場合は、どの税金がかかるのか、あらかじめ理解しておく必要があります。ここでは、離婚で家を売却する場合の税金について見ていきましょう。
財産分与では贈与税や不動産取得税はかからない
家だけでなく、離婚で財産を分与する場合に気になるのが、贈与税のことです。
例えば名義が夫の財産を妻に分与する場合、贈与ではないのかと考えがちですが、財産分与とは、名義にかかわらず、夫婦で協力して築き上げた財産を分ける行為のため、これは贈与には該当しません。
そのため、贈与税もかかりません。同じ理由で、不動産取得税もかかりません。
家の取得後に支払う税金がある
家を財産分与しても、不動産取得税はかかりませんが、家を取得した後に支払いが生じる税金があります。それが登録免許税と固定資産税です。
登録免許税は、法務局で所有権移転登記をする際に支払う税金のことです。税率は固定資産税評価額の2%となっています。
固定資産税は家を持っていることに対して課される税金です。固定資産税の税率は、原則、固定資産税評価額の1.4%です。
家のある地域によっては、0.3%程度の都市計画税がかかることもあります。
贈与税や譲渡所得税がかかるケースもある
財産分与では、贈与税はかかりません。ただし、貢献度を換算しても、明らかに多くもらっている場合や贈与税逃れのための偽装離婚と判断された場合などでは、贈与税がかかることになります。
財産分与する際には、明らかに多すぎにならないように気を付ける必要があります。
次に、家を売却した場合に注意したいのが、譲渡所得税です。購入価格より高く家を売却できた場合など、家の売却で利益が出た場合には、その利益に対して譲渡所得税が課されます。
譲渡所得税は、家を何年所有していたかによって、税率が異なります。
この場合は、利益に対して20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)です。
◾️譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の場合(短期譲渡所得)
この場合は、利益に対して39.63%(所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%)です。
贈与税や譲渡所得税は、場合によってはかなり高い税額となることがあるため、資金計画をきちんとしておく必要があります。
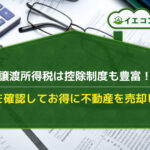
まとめ
離婚時に財産分与で家を分ける方法には「現物によって分与する方法」「相手に金銭の支払いをする方法」「売却し、現金化したものを分与する方法」の3つがあり、自分達に合った方法を選ぶ必要があります。
家を売却する場合にも、住宅ローンの状況などで売却方法が異なります。そのため、1人ですべてをこなすことは難しいと思われます。
離婚時に財産分与で家を分ける場合には、弁護士や専門の不動産会社に相談しましょう。
弊社クランピーリアルエステートは、弁護士や司法書士、税理士などの専門家と連携しています。財産分与の手続きや家の売買だけでなく、その後のトラブルや交渉までサポートしますから、安心してご相談いただけます。財産分与で家を売却したいがどうしたらよいかわからないとお悩みの方は、ぜひ一度お声がけください。
財産分与での家の取り扱いについてよくある質問
売却して、売却代金を分割する方法がおすすめです。財産分与の方法や割合について揉めることなく、スムーズかつ公平にわけられます。
いいえ、それらの不動産は財産分与の対象になりません。結婚前に購入した家や、結婚前に築いた財産で取得した家、相続により取得した家は「特有財産」とみなされ、財産分与をする必要はありません。
持分の過半数をもっていても、離婚時に不動産全体を必ず取得できるとはいえません。婚姻期間中に築いた財産はすべて「夫婦双方の貢献」が等しくあったとみなされるので、財産分与においては1/2ずつでわけるのが原則です。共有不動産全体を自分の単独名義にするには、他の財産と相殺するか、偏った割合での財産分与に双方が合意しなければいけません。
はい、自分の持分だけを売却することは可能です。ただし、離婚時の持分売却はタイミングや手続きに慎重な判断が必要なので、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
はい、あります。一般的な物件を扱う大手不動産会社よりも「共有持分を専門としている買取業者」へ売却したほうが高額となる可能性があります。また、離婚などで共有者どうしがトラブルになっている共有持分は、弁護士と連携している専門買取業者への売却がおすすめです。→ 共有持分専門の買取査定はこちら