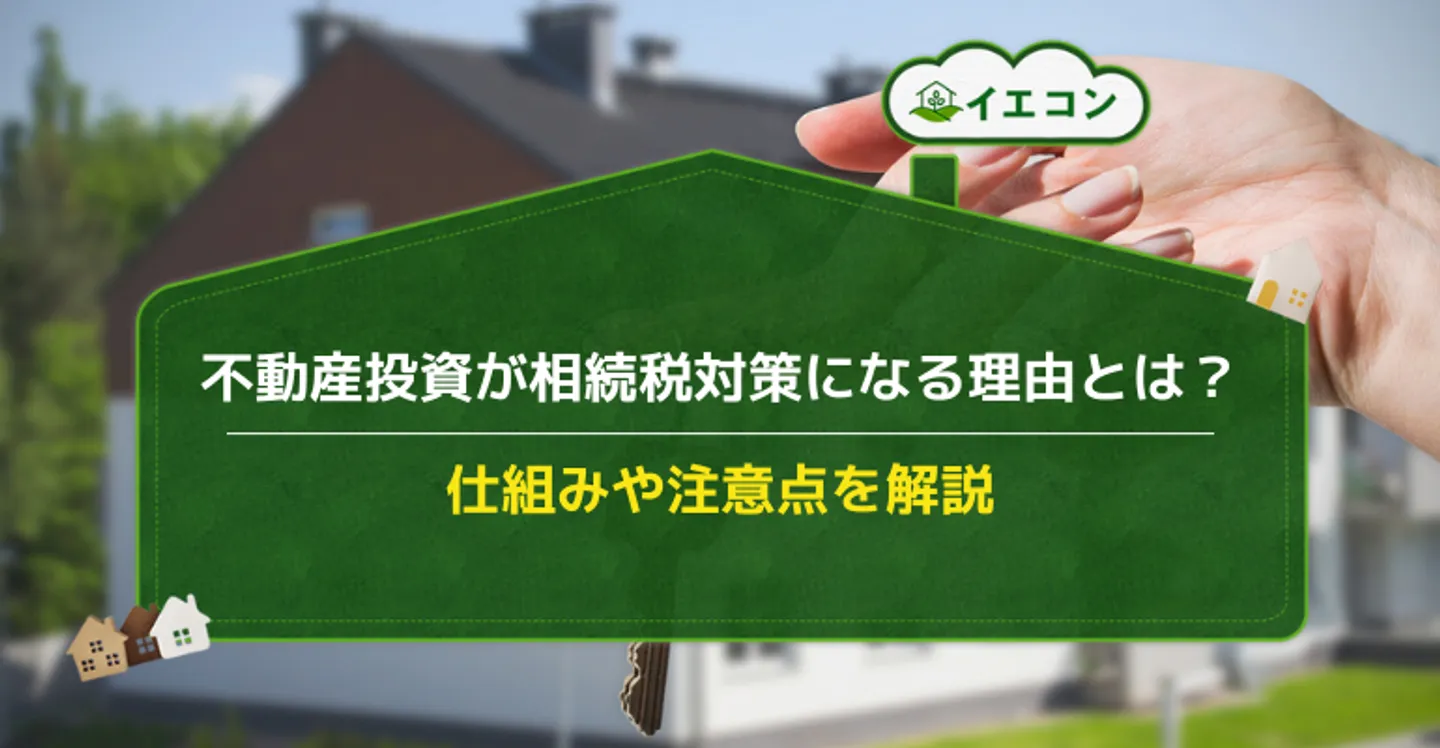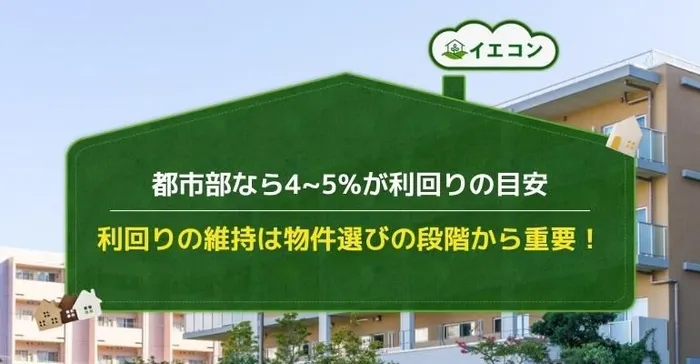2015年の相続税制改正によって課税対象になる人が大幅に増え、相続税が課税された人の割合は4.4%から8%台に増加しました。
相続税対策に不動産投資が向いていると聞いたことがあると思いますが、実際にどのような方法でおこなって、効果はどのくらいあるのか気になりますね。
この記事では、不動産投資による相続税対策をお考えの方向けに、節税の具体的な仕組みや方法について解説します。
不動産投資の相続税対策に失敗しないポイントや、注意点についても説明しますので、ぜひ最後までお読みください。
不動産投資が相続税対策になる仕組み
相続人の財産は、現金から不動産に帰ることで評価額が下がるため相続税を引き下げ効果もあります。
評価額がどのくらい下がるかというと、土地や建物に変えた場合は不動産の実勢価格の7〜8割程度に下がります。
現金の場合は金額そのままの評価額となります。
また、不動産を賃貸しているとその評価額をさらに下げることができるのが、不動産投資の大きなメリットの一つです。
現金を投資用の不動産に変えることで、相続税評価額を最大40%以上圧縮できます。
なぜこのようにできるのでしょうか?
現金を不動産に変換することで相続税評価額が下がる
まず土地は市街地では路線価(国が定めた土地1㎡当たりの単価)、市街地以外は評価倍率方式で評価され、時価の8割程度の金額となります。
相続税評価額は、土地の形状や接道状況で細かな加算や低減はありますが、以下で概算できます。
地域ごとの路線価は、以下の国税庁のホームページで確認できます。
財産評価基準書路線価図・評価倍率表|国税庁
路線価が時価の8割に設定されている理由は2つあります。
1つは不動産は売却するためには多くの時間とエネルギーを要し、株など他の換価が簡単な財産と同じように評価するのが不公平であることです。
2つ目は、路線価は年に1度しか改定されない一方、時価は1年の間でも大きく変動する可能性があるため、割安な評価にして納税者を保護しています。
建物は固定資産税評価額で評価され、固定資産税評価額は時価の7割程度となるので、5,000万円の建物で3,500万円程度の評価になります。
固定資産税評価額は、不動産の所有者に毎年届く納税通知書に記載されています。
不動産を賃貸に出すことでより相続税評価額が下がる
購入した不動産が投資用であることで、相続税の評価額はさらに下がります。
現金1億円を土地と建物に変えることで7,500万円の評価となりましたが、賃貸されている土地は「貸家建付地(かしやたてつけち)」という扱いになり、評価がさらに2割ほど下がります。
建物においては賃貸することで、さらに評価が3割下がり、評価額は以下のようになります。
→評価額4,000万円の土地を賃貸に出す→4,000万円×0.8=3,200万円
→評価額3,500万円の建物を賃貸に出す→3,500万円×0.7=2,450万円
→3200万円(土地)+2450万円(建物)=5,650万円
土地売買の手間や諸費用も考慮する必要があるため、単純な比較にはなりませんが、現金を不動産に換えるだけでも相続税の減少になることは確かです。
投資物件として貸し出せば、さらに相続税を節税でき、家賃収入も得られます。
小規模宅地等の特例で相続税評価額が下がる
相続税の評価を下げる制度はまだあります。
「小規模宅地等の特例」は配偶者などの遺族が、相続税の納付の負担で住居を手放さなくて済むように設けられた制度で、小規模な宅地が一定の要件を満たせば、土地の評価額を最大80%分減額できるものです。
この特例は居住用だけでなく事業用の宅地に対しても適用され、200㎡まで最大50%減額されます。
小規模宅地等の特例対象土地
| 土地の種別 | 適用 |
|---|---|
| 特定居住用宅地等 (住んでいる土地) |
限度面積330㎡ 減額割合80% |
| 特定事業用宅地等 特定同族会社事業用宅地等 (事業している土地) |
限度面積400㎡ 減額割合80% |
| 貸付事業用宅地等 (貸している土地土地) |
限度面積200㎡ 減額割合50% |
つまり、この制度を上記の例に適用できた場合、1億円の資産評価は最終的に4,450万円にまで下げられることになります。
相続税の計算方法
続いて、評価額をもとに相続税を計算する方法をご案内します。
基礎控除
基礎控除によって、相続税の評価額も減額されます。
相続税の基礎控除は、資産額に関わらず以下です。
たとえば相続人が配偶者のみの場合は、3,000万円+(600万円×1名)=3,600万円が基礎控除額となります。
相続税
上記の例の評価額で相続人1人の場合、課税標準は以下となります。
不動産5,650万円 - 基礎控除3,600万円 = 課税標準額2,050万円
法定相続人となる人と、それぞれの法定相続分は、以下の表のとおりです。
法定相続分は相続人の意志で割合を変更できますが、法定分の半額は「遺留分」として、相続人の権利として保証されます。
また、相続人の間での遺産分割協議で割合を決めることもできます。
| 相続人 | 法定相続分 | |
|---|---|---|
| 子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
| 子 | 2分の1(人数分に分ける。3人きょうだいはひとり6分の1) | |
| 子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
| 父母 | 3分の1(人数分に分ける。両親はひとり6分の1) | |
| 子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
| 兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける。3人きょうだいはひとり12分の1) | |
参考元:財産を相続したとき|国税庁
また、相続税の個人の税率と控除額は以下です。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
参考元:財産を相続したとき|国税庁
取り分や相続税率などをあてはめて相続税額を算出します。
相続人(妻一人):2,050万円 × 15% - 50万円 = 相続税額257.5万円
相続人が複数の場合、相続税額を合計して相続税の総額を算出し、実際に各人が相続した財産の割合で相続税額を割り出します。
今回は配偶者1名で全て相続するため、相続税の総額も257.5万円となります。
しかし配偶者には配偶者控除という特例があり、これを適用すると納税額は0円となります。
配偶者控除とは、配偶者が相続した遺産のうち課税対象となるものが1億6千万円までは相続税が課税されない制度です。
相続税対策が不要なケース
このように、最終的には相続税の納税額が0円=納税が不要となるケースも多くありますが、どのような例で納税不要となるかを整理しましょう。
相続税評価額が基礎控除額以下である
まず、相続税の評価額が基礎控除額以下であれば、相続税対策は不要となります。
基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)でしたので、法定相続人が2人なら4,200万円までの評価額なら、相続税対策は不要となります。
特例で相続税評価額の減額が認められる
また、前述した小規模宅地の特例で50%から80%の控除を受け、相続税評価額を基礎控除額以下にできる人も相続税対策が不要です。
配偶者控除を受けられる
相続人の配偶者の場合は、課税対象となる相続遺産のうち1億6千万円までの額面であれば、やはり相続税は課税されません。
配偶者控除を受けるためには内縁関係や事実婚などではなく、戸籍上の配偶者であることが求められ、相続税の申告期限までに遺産分割が完了していることも要件です。
ただしこれらの条件は現行の税法によるもので、今後相続税が増税されたり、特例などの条件が変更された場合はこの限りではありませんので、最新の情報には注意しましょう。
また、不動産投資を遺産に活用すべき理由として、もしもの際の生命保険がわりになるという機能も挙げられます。
投資物件の購入の際に融資を受けている場合、団信(団体信用生命保険)に加入していますが、相続人が亡くなって保険金でローンが完済された場合、ローンの残債分が保険金がわりとなります。
毎月の返済分だけ家賃収入が増える形となるため、保険金が月額で入金される収入保証保険のような役割も果たします。
不動産投資で相続税対策をする際の注意点
相続税対策を狙う場合、せっかくの不動産投資の効果が無にならない、あるいは最大になるように、以下のような注意点があります。
- 不動産を購入できるだけの資金の準備
- 被相続人の意思で不動産を購入する
- 配偶者や子の合意で不動産投資する
- 遺産分割を見越した投資をする
- ローンの残債を意識する
- 不動産経営の継承準備をする
不動産を購入できるほどの資金が必要になる
投資物件は、運用状態が良く相続する側に継承の意志があれば、相続に適した資産です。
しかし相続税対策として効果を挙げるだけの相続資産となると、数千万~数億円の物件を購入する必要があり、そのためのまとまった資金が必要となります。
購入のために融資を受けるとしても、自己資金は頭金(10~20%)と諸費用(新築:4~7%、中古7~10%)で合計物件価格の15~30%程度は必要と考えられます。
老後に残す生活資金や、お孫さんの学資贈与などと併せて、よく検討をしましょう。
自分の意志で不動産を購入する
これは相続人の注意点にもなりますが、被相続人(亡くなった人)が自らの意思で物件を購入しなかったと税務署がみなした場合は、貸家建付地・賃貸用建物としての相続税評価が無効となってしまう可能性が高いです。
その場合、相続税は物件の時価での評価となり節税もできないため、以下のようなケースは要注意です。
- 被相続人が認知症などにより、自ら意思決定できる状態になかった場合
- 代筆や代理で契約を行った場合
被相続人の意思能力に不安が出てきた際に、介護費用の捻出のためなどで物件の購入や賃貸借をおこなう場合もあるでしょう。
しかしその際には、相続の際の資産額が節税を要するレベルなのか、税務署と話し合える材料=実情の説明はできるかなどを意識する必要があります。
似たケースで、親の生きているうちに親名義の実家を賃貸に出す場合、相続後にいざ売りたいとなったときに困る点が2つあります。
1つは入居者と普通賃貸借の契約を結ぶと、貸主の意志で退去をしてもらうのが非常に困難になることと、2つ目は譲渡所得税の控除が使えなくなることです。
入居者との契約は定期建物賃貸借にして年限を設定すればそこで契約終了にできるのですが、税控除の特例には対策がありません。
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例、いわゆる「空き家特例」の3,000万円特別控除の要件は以下です。
- 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
- 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
出典:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
賃貸した場合に問題になるのは3つめの「相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと」です。
このような制度は「思い出の実家」を売りあぐねているうちに、たくさんの空き家が老朽化している現状に対応するためのものです。
空家となる公算の強い実家は関係者で話し合いのうえ、所有者の意志ありきで早めに売却を決めるか、賃貸に出す場合は、収益物件として運用していくよう決めるのが良いでしょう。
上記のほかに、持ち家を一時的のつもりで賃貸した場合のメリットとデメリットをご覧ください。
持ち家を貸し出すメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・家賃収入を得られる ・実家を活用できる ・投資のノウハウが少し得られる ・人が住むことで建物が傷みにくくなる ・放火や空き巣から実家を守れる ・不審者の侵入がない ・賃料収入で植栽や建物の管理状態を保てる |
・貸主の都合で途中解約するのが難しい ・苦情や滞納、入金管理など賃貸管理が必要(委託可能) ・定期借家契約の場合家賃は安めの設定になる ・賃貸時のリフォーム、設備修理や入居者の入れ換え時の原状回復などの費用が必要 ・売る際に空き家特例が使えなくなる |
配偶者や子の合意を取る
相続人のためを思い、税負担を軽減するように不動産投資を始めるのですから、「生前からあてにしないように」「大げさにしたくない」などの理由で、陰ながら進めようという気持ちもお有りかと思います。
しかし、投資物件の場合はゆくゆくトラブルになりかねないので、相続することになる人たちの合意をとっておきましょう。
配偶者や子が不動産投資を良く思っておらず、物件購入後にすぐ売却をするということがないように、メリットやリスクを含めて良く話し合いを持つことが、節税を含めた成功のために必要です。
遺産分割で相続人が揉めないようにする
不動産は相続人が均等に分けるのは難しいうえ、共有名義にするとのちに売却するなどの際に全員の同意が必要となり、非常に面倒なことを招きます。
そのため、換価分割と言って売却のうえで相続を実行することがあります。
それでも節税は可能なのですが、分け方をめぐって相続人が揉めるのは本意ではないでしょう。
遺言を書いて公正証書とするなどのほか、相続人の誰かが賃貸経営を受け継いで行ける方向に配慮するのが理想です。
ローンの残債が残らないようにする
融資を受けて不動産を購入する場合、のちに相続した人が賃貸経営がうまくいかず赤字になることも想定しておきましょう。
場合によっては物件を売っても清算しきれないオーバーローンの状態になり、任意売却で苦労をすることもあり得ます。
もしもの際に、遺族が残債を払えるだけの生命保険か、前述のように不動産融資にともなう団体信用生命保険に加入しておけば安心です。
不動産経営の継承準備をする
現在賃貸業の経営がうまくいっていたとしても、相続人にそのノウハウを伝えていなければ、良い状態を継続できるとは限りません。
資産だけではなく、経営ノウハウや物件を維持していくための人脈などの継承もしておく必要があるのです。
これから物件購入をお考えの場合、頼れる不動産会社は必要ですが、並行して継承できるだけの勉強を怠らないようにしましょう。
また、こうした経営の伝承は、意思能力がしっかりしているうちに行う必要があります。
現在65歳以上の約16%が認知症と推計され、80歳代の後半で男性の35%・女性の44%、95歳以上で男性の51%・女性の84%が認知症であると明らかにされています。
出典・ご参考:
認知症と共に暮らせる社会をつくる|独立行政法人・東京都健康長寿医療センター研究所
被相続人の方も、もし「投資物件を持っているのは知っているが、詳細は知らない」という場合は、早急に収支などの経営状態を確認し、引き継ぐかどうかの方向性を相続人の間で話し合っておく必要があります。
不動産投資が相続税対策としてみなされかねないケース
違法性があるというわけではありませんが、以下のようなケースで不動産購入が相続税対策としてあまりに不公平な「税金逃れ」とみなされてしまうと、相続税対策が無効になる場合があります。
- 過剰な相続税対策とみなされた場合
- 不動産購入目的が明らかに相続税対策である場合
- 相続税申告後の3年以内の売却である場合
過剰な相続税対策とみなされた場合
最近印象的なニュースとして、タワーマンションの相続税算出ルールが変更になりました。
- 築年数や階数などに基づいて、評価額と市場価格の乖離率を計算する
- 実勢価格と固定資産税評価額の乖離率が1.67倍以上の場合、通常の評価額に乖離率と0.6を掛ける
つまり、実勢価格が固定資産税評価額の1.67倍という危険水域の基準が示されたことになります。
この新ルールができた理由は、現金をタワーマンションに換え、相続税を大幅に減額できる「タワマン節税」が富裕層の間で流行ったためです。
この実勢価格と相続税評価額の差が開き過ぎる点が問題視されているのです。
実勢価格と相続税評価額の差額の利用で、相続税を大幅に抑えることが適切なのかが争点となった訴訟があり、2022年4月19日、最高裁で国税側が勝訴し、3億円を超える追徴課税が課されました。
この訴訟の例では、90歳を超えた被告が短期間に合計13億円ものマンション購入をしたこと、実勢価格との乖離率が3.2倍に達していたことなどが問題視されました。
これまでタワマン節税によって相続税負担が数十万円ほどで済んでいたケースも、数百万円単位の税負担にはね上がるという試算もあります。
最高裁判例は法制化されたルールと同じように機能しますし、不動産業界ではこのような事件をきっかけに、法令の締め付けが厳しくなるのはよくあることです。
今後行き過ぎた節税目的での対策は、上記のような算定基準によって認められなくなる可能性があります。
不動産購入目的が明らかに相続税対策である場合
現在明確な基準はありませんが、明らかに相続税対策と見られる物件購入をすることで、相続税対策が無効と判断されることがあるようです。
上記のように時価と相続税評価額の乖離が大きい場合だけでなく、融資審査の際に、購入目的を相続税対策と記入したり、高齢者が急に不動産を購入するといったケースは、チェックが入る可能性があります。
不動産投資自体が目的であるという形で、大家さんを営み、それを継承する体制を作るのが理想と言えるでしょう。
相続税申告後の3年以内の売却である場合
税務調査は、過去3年にさかのぼって調査が行われます。
税務調査が入った時点で物件を売却し、さかのぼって3年以内に相続税の申告が行われているような場合は、一連の行為が相続税対策とみなされる可能性が高くなります。
相続した不動産は5年以内の短期譲渡でも長期譲渡扱いとなるため相続後すぐに売却しても、譲渡所得税の税率が低いです。
しかし上記のようなことがあるので、相続税節税のメリットが出ている場合には、相続税申告後3年以内には売却しない旨を事前に相続人と共有しておくことが良いでしょう。
相続税対策に向いている不動産
ここまでのお話とは逆に、税務署に不当とみなされない範囲でなるべく節税をしたい場合に購入する不動産は以下のような特徴があります。
- 時価と相続税評価額に差がある
- 利回りが良い
- 買い手がつきやすい
時価と相続税評価額に差がある
タワーマンションの項で触れたように、時価と相続税評価額の差が大きい物件は、相続税対策に向いていることになります。
その差は一般的に地価の高い都心部で大きくなり、都市部の物件の方が安定して収益を得やすいこともあるため良いです。
都市部の方が物件価格も高いため、相続税対策の効果を挙げるのにも好都合です。
利回りが良い
相続税対策とは言え、毎月の返済額や物件の管理費、固定資産税や修繕積立金を上回る収益を期待できる物件であることも求められます。
利回りは物件価格を想定年間賃料で割った表面利回りではなく、運用のための経費を差し引いた実質利回りで計算し、家賃下落率なども加味して堅めにシミュレーションすることが大切です。
安定した運用のしやすい物件の目安は、少々厳しめですが表面利回りで5~8%と言われています。
これを超える高利回り物件をうまく運用するには、集客のヴィジョン、低コストで修繕できる、計画的な物件のメンテナンスなどのノウハウが必要になってくると考えましょう。
しっかりした経営をしておくのは、引き継ぐ方のためにも必要ですが、もうひとつ大きな理由があります。
相続税申告の時点で「賃貸割合」は入居率として計算されるため、例えば8室のうち4室空室=入居率が50%では「賃貸割合」が0.5となり、賃貸物件としての評価額の圧縮率が半減します。
相続税対策の物件でも、入居率を高める経営の工夫をしましょう。
実質利回りについて詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてください。
買い手がつきやすい
立地なども加味しながら相続後の出口戦略を取りやすい物件を選ぶことで、それ自体が資産価値にもつながります。
売りやすい物件の条件は人口が多い場所、駅近、接道の条件が良い、地形が良い、既存不適格や再建築不可などではないこと、隣地との境界が確定していることなどです。
いい物件を購入するには、パートナーとなる不動産投資会社選びが大切です!
>>【プロが最適な投資をアドバイス!】不動産投資会社の一括比較はこちら
不動産投資以外の相続税対策
個々の金額は大きくはありませんが、不動産投資以外にも以下のような相続税対策があります。
暦年贈与
贈与税は、贈与される人1人に対して年間110万円の基礎控除があるため、年間110万円内で贈与する分には贈与税がかかりません。
この年間110万円というのが王道の贈与方法ですが、毎年同じ時期に同じ額を同じ人に贈与していると連年贈与とみなされ、贈与税を課税されます。
この場合、贈与の時期や金額を毎回ずらすなどの対応をしましょう。
贈与は相続よりも高税率で、たとえば親族間で物件売買をする際に、不当に安い金額設定をすると実勢価格と売買価格の差額分に対して贈与税がかかり、売主には譲渡所得税が課税されます。
ただし暦年贈与以外に、賃貸物件の建物を生前贈与するために相続時精算課税制度を利用する手段もあります。
相続時精算課税制度は、推定相続人に財産を贈与した場合に基礎控除額が2,500万円まで設けられる贈与制度で、相続税評価額が2,500万円以下ならば、贈与の時点での贈与税は非課税となります。
そのかわりに相続時精算課税で贈与した財産は、相続時が発生した時点にその贈与財産を相続財産に加算して相続税が計算されます。
贈与税より相続税の方が税率が低い点も、メリットでしょう。
相続税評価額が2,500万円以下のアパートなら非課税枠内で建物を贈与してしまい、相続が予定される人は納税資金を蓄えておきます。
注意点は、相続時精算課税は一度選択することで途中で暦年贈与が使えなくなることです。
墓地など非課税財産の購入
墓地、墓石、仏壇、神棚などは相続税が非課税なのでこれらを生前に購入すれば、それだけ相続財産を減らせることになります。
ただしお墓や仏壇なども今後どうしていくか、誰が守っていくかは相続後に話し合いの対象となるため、生前に自分の意志をはっきり伝えておくのが良いでしょう。
生命保険
生命保険で降りる保険金は、500万円×法定相続人の人数が「非課税」となり、相続税の対象にならないため、保険金から保険料の総額を概算し、相続財産に換えることができます。
法定相続人が3人であれば、1,500万円までの保険金を非課税で分配できる計算です。
前述の投資物件による生命保険効果も得られますので、相続税対策でなくとも、お買い得で利回りのよい中古の一棟アパートを複数準備するのも良いかもしれません。
まとめ
不動産投資による相続税対策の具体的な仕組みや、注意点について解説しました。
相続税は、資産額が相応にある人が収めるものでしたが、各分野で大増税が進む今、相続税も賢く節税をおこなうことの必要性が増してくる可能性は十分にあります。
また、不動産投資は老後の生活手段や、家族の資産を守るうえで数々のメリットのある方法です。
早い段階で物件購入を検討し、ご家族の中でも賃貸業の継承についてよく話し合っていくことをおすすめします。