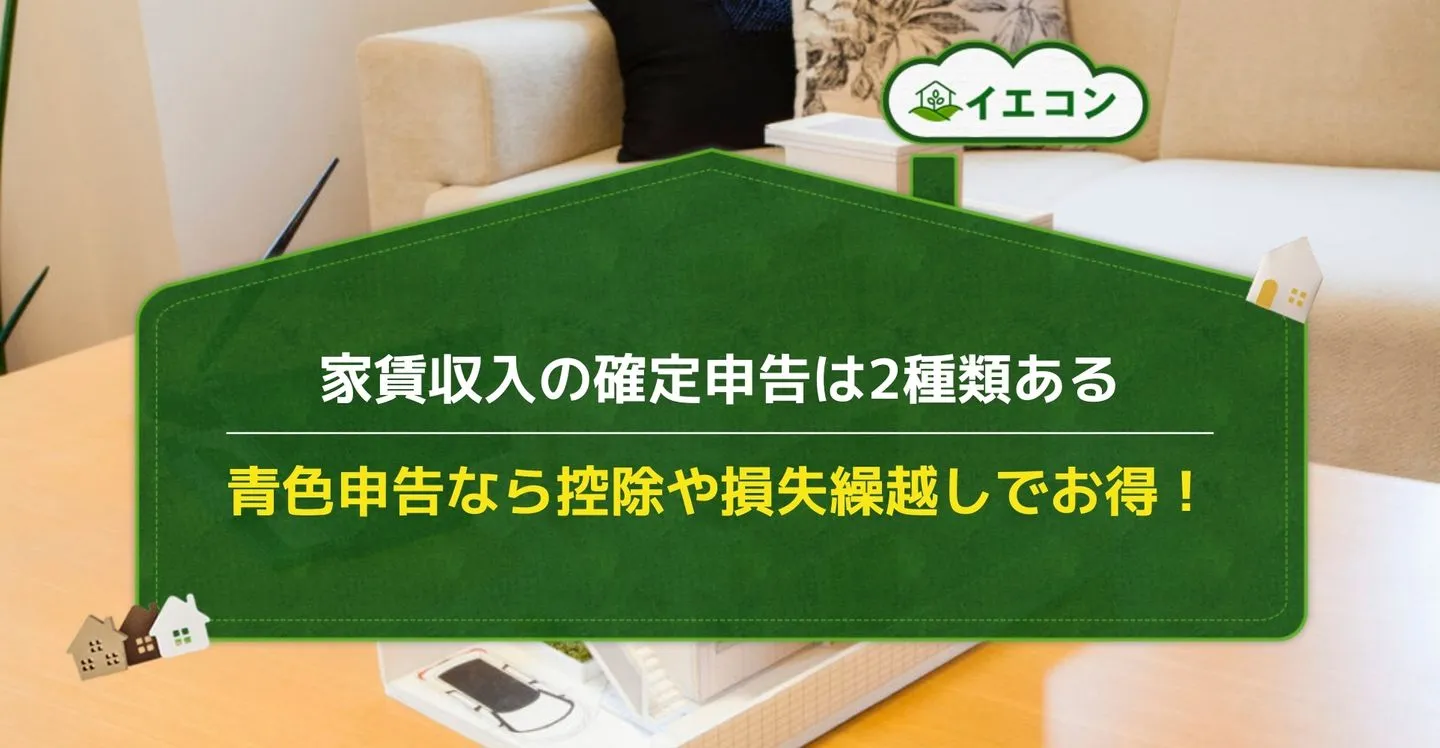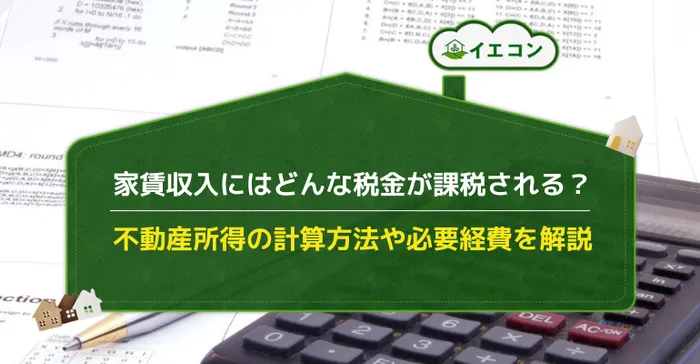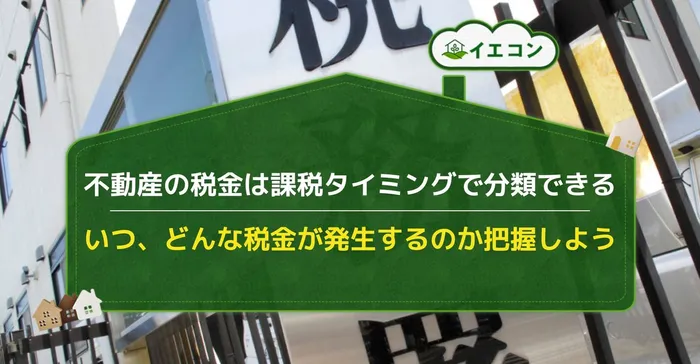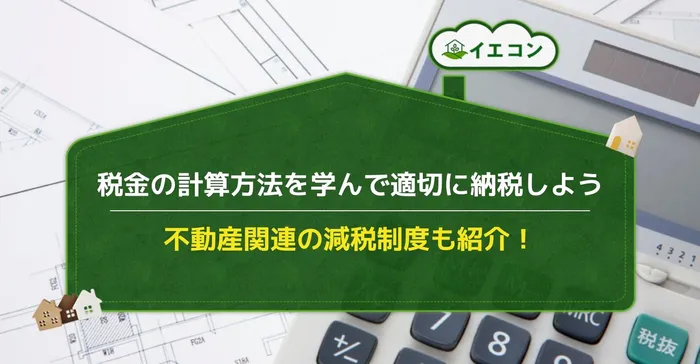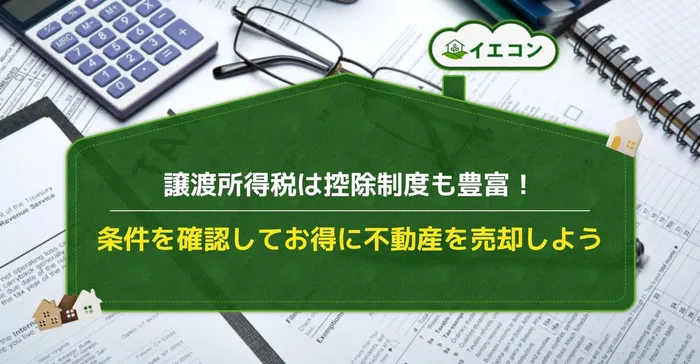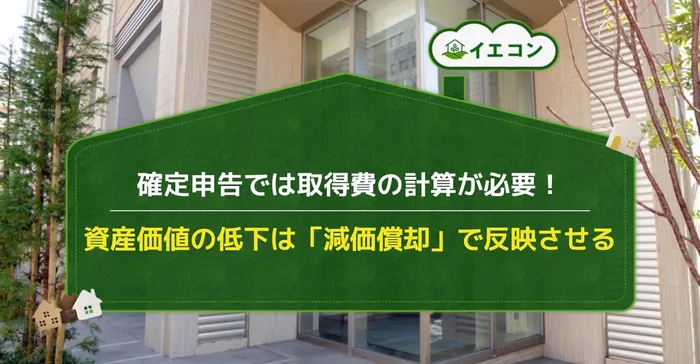大家として家賃収入を得る場合、忘れてはいけないのが確定申告です。
確定申告は申告時期が来てから準備をはじめるのではなく、事業を開始したときから事前の届け出が必要なので注意しましょう。
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
節税の観点からいえば青色申告がおすすめですが、手続きや経理作業は煩雑となります。
節税や税申告で疑問や不安があれば、税理士に相談してアドバイスをもらいましょう。必要であれば、申告の手続きも代行してもらえます。
家賃収入の確定申告をおこなう前に必要な準備

賃貸経営をスタートしてから初めての確定申告を迎えるまでには、いくつか必要な準備があります。
例えば、税制の優遇措置が受けられる青色申告は、事前に承認申請書を提出しなければ利用できません。
賃貸経営を開始したら、下記の申請を忘れずおこないましょう。
- 開業届を提出する
- 青色申告承認申請書を提出する
- 減価償却資産の償却方法の届出書を提出する
- 給与支払事業所等の開設届出書を提出する
確定申告は、毎年2月16日から3月15日にかけて行われます。ギリギリになって慌てないよう、早めに準備をしておきましょう。
開業届を提出する
確定申告の準備は、賃貸経営をスタートする時から始まります。まずは、税務署で「個人事業の開廃業等届出書」いわゆる開業届を提出しましょう。
開業届は、事業を開始してから1カ月以内に提出することが望ましいとされていますが、義務ではないので罰則もありません。
しかし、スムーズな確定申告をするためには、期限内に提出しておいた方が良いでしょう。
青色申告承認申請書を提出する
開業届の提出と同時に「青色申告承認申請書」も提出しておきましょう。確定申告において、のちほど解説する「青色申告」をおこなうために必要な申請です。
青色申告承認申請書は、事業を開始してから2ヶ月以内、もしくは事業を開始した年の3月15日までに提出しなければいけません。
青色申告は義務ではありませんが、税制優遇などメリットが多数あります。
実際に青色申告をおこなうかどうかは、確定申告のときに決められます。青色申告承認申請書は提出だけでもしておいたほうが、後々の選択肢が増えるためおすすめです。
減価償却資産の償却方法の届出書を提出する
初回の確定申告書に間に合うよう「減価償却資産の償却方法の届出書」も提出しましょう。
この届出は、減価償却資産について、定額法と定率法のどちらで償却するのかを申告するものです。青色申告を希望する場合には、提出しておくべき書類です。
定額法と定率法、どちらの計算方法が有利なのかは、事業形態などの諸条件によって異なります。
給与支払事業所等の開設届出書を提出する
賃貸経営に伴って従業員を雇用するなら「給与支払事業所等の開設届出書」の提出が必要です。事業のために事務所を開設したことを、税務署に届け出る手続きです。
事務所を開設してから、1か月以内の提出が期限となります。
なお、従業員が10人以下の場合は「源泉所得税の納期の特例の承認申請書」を同時に提出するのがお勧めです。
これにより、源泉所得税の納期が翌月の10日ではなく、年2回の納期に変更されるので、資金繰りにいくらかゆとりが生まれるでしょう。
確定申告をおこなう所得は「総収入金額-必要経費」で計算する
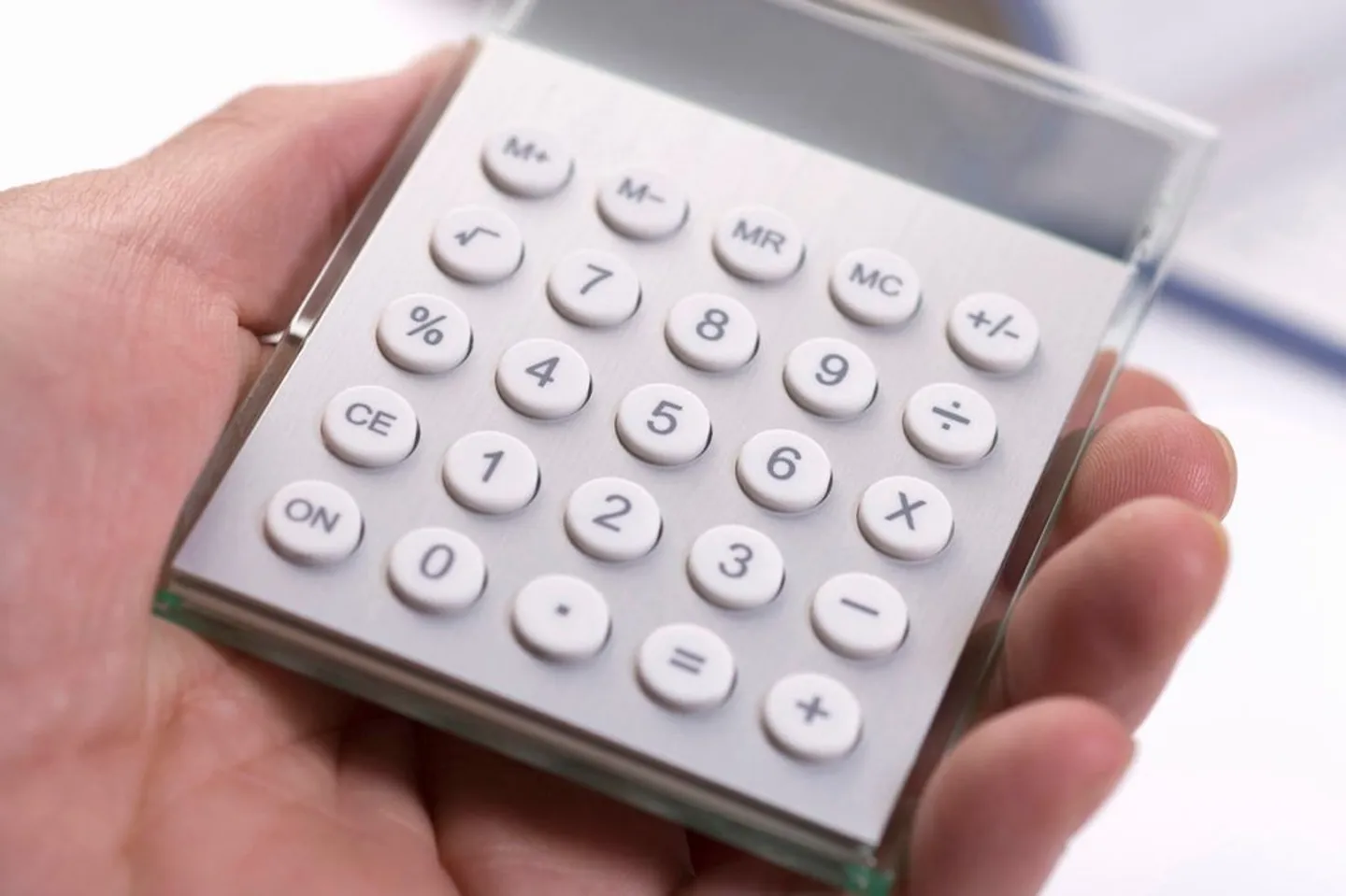
確定申告とは、自分の所得を申告することで、納めるべき税額を明らかにするための手続きです。
賃貸経営をしている大家の場合は、確定申告によって所得税や住民税(規模によっては事業税も課税される)の税額が決まることになります。
申告した所得が実際のものより多ければ、余分な税金がかかります。逆に、少なく申告してしまえば追徴課税が課されるので、注意が必要です。
正しい税額を計算するためには、正しい所得金額を申告することが基本です。
不動産所得を割り出すには、次の式を用います。
収入と所得の違い
「収入」と「所得」という言葉はどちらも似通った意味に感じますが、実際は別の意味をもちます。
収入とは、賃貸経営に際して手元に入ってくるお金すべてを表しています。一方で、所得は収入から経費を差し引いて最終的に残ったお金、いわば純利益のことです。
給与所得でいえば、総支給額が収入、手取り額が所得とイメージすれば理解しやすいでしょう。
賃貸経営で得た家賃収入は税務上「不動産所得」と呼ばれます。
賃貸経営における収入の内訳
賃貸経営における収入は、下記にあげるお金です。
- 家賃収入
- 共益費収入
- 礼金
- 保証金
- 更新料
不動産所得における収入の計上基準は「権利確定主義」です。つまり「お金を得る権利が確定した年に収入があった」とみなして計上します。
権利確定主義で考えると、これは今年度の収入となります。「翌月分の家賃は前月の末日までに支払う」という決まりであるなら、翌年1月分の「家賃を受け取る権利」は今年度中に確定しているからです。
礼金は「賃貸物件を引き渡した日の収入」として、更新料は「更新手続きを行った日の収入」として計上します。
保証金に関しては、物件や大家ごとに扱いが異なるケースも少なくありません。預り金として将来返還する場合もあれば、返還せず収入とする場合もあるでしょう。
保証金を預り金として受け取った場合、収入に計上する必要はありません。しかし、返還しない前提で受け取った場合は、その受け取り日の収入となります。
ちなみに、敷金は原則として返還されるべきお金なので、収入にはならないと考えられます。
賃貸経営において計上できる必要経費
賃貸経営において必要経費に含められるのは、下記のとおりです。
- 入居者の募集にかかった費用
- 管理費
- 各種保険料
- 修繕費
- 税理士費用
- 固定資産税、事業税、消費税など
必要経費として認められるのは、所得を得るために支出したお金です。賃貸経営の場合は「家賃収入を得るために直接的に必要となったお金」といえるでしょう。
修繕費については、通常使用の範囲における維持管理や、原状回復に必要な修繕費が必要経費となります。
建物の取得費用は減価償却で計上する
建物の取得費用や、付帯設備(電気設備や給排水設備など)は減価償却で経費計上をおこないます。
固定資産の取得にかかった支出を、その資産の耐用年数で配分して経費計上すること。例えば、250万円の資産において耐用年数が5年であれば「1年目に50万円、2年目に50万円・・・」と何年かに分けて計上する。
ただし、例外として取得価額10万円以上20万円未満の資産については、取得価額の1/3を3年にわたり分散して必要経費とします。
また、少額の減価償却資産(取得価額が10万円未満のもの、もしくは使用可能期間が1年未満の資産)については、事業に使用し始めた年度に全額を必要経費として計上できます。
参照:国税庁「少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」
耐震補強工事やリフォーム・リノベーション工事も減価償却扱いになる
修繕費は当年中に経費計上するのが基本ですが、耐震補強工事やリフォーム・リノベーション工事は減価償却扱いとなります。
耐震補強工事やリフォーム・リノベーション工事などは、物件の価値を高める目的で行われるため「資本的支出」とみなされるからです。
ただし、資本的支出でも20万円未満の費用で行われたものや、3年以内に周期的に行われるもので総費用が60万円未満の場合、修繕費として当年の必要経費にできます。
確定申告は2種類ある
大家が行う確定申告は、大きく分けると「白色申告」と「青色申告」の2種類に分類されます。
かつて、申告用紙の色が白や青に分かれていたことから、これらの呼び名が付きました。現在は、実際に色分けしているわけではありません。
白色申告は手続きがシンプルであり、青色申告と比べて難しくありません。ただし、青色申告のほうが税制度における数々の特典を受けられます。
1.単純明快な「白色申告」
白色申告の特徴は、帳簿付けの手軽さです。
単式簿記での記録を付けていればよいため、簿記の知識が乏しくても簡単に帳簿作成ができます。単式簿記とは、1つの収支について1つの記録を残す簿記のことです。
収入から支出を差し引けば、手元にいくら残ったのかわかります。シンプルな仕組みで、家計簿などもこの単式簿記で出来ています。
白色申告での確定申告は、単式簿記で記録した帳簿を参照しつつ、昨年中の収入から必要経費を差し引いて所得を申告します。
所得計算のプロセスが簡単で、日々の経理作業や確定申告時の手続きに時間がかからないというメリットがあります。
特別控除や赤字の繰越ができない点はデメリット
一方で、白色申告にはデメリットもあります。青色申告にあるような特別控除や、赤字の繰越しなどが認められていないことです。
特典を受けられないため、青色申告より税額が高くなるケースもあります。
賃貸経営の規模を拡大していく予定なら、早めに青色申告に切り替えた方が節税になるでしょう。
2.手続きは面倒でも様々な特典がある「青色申告」
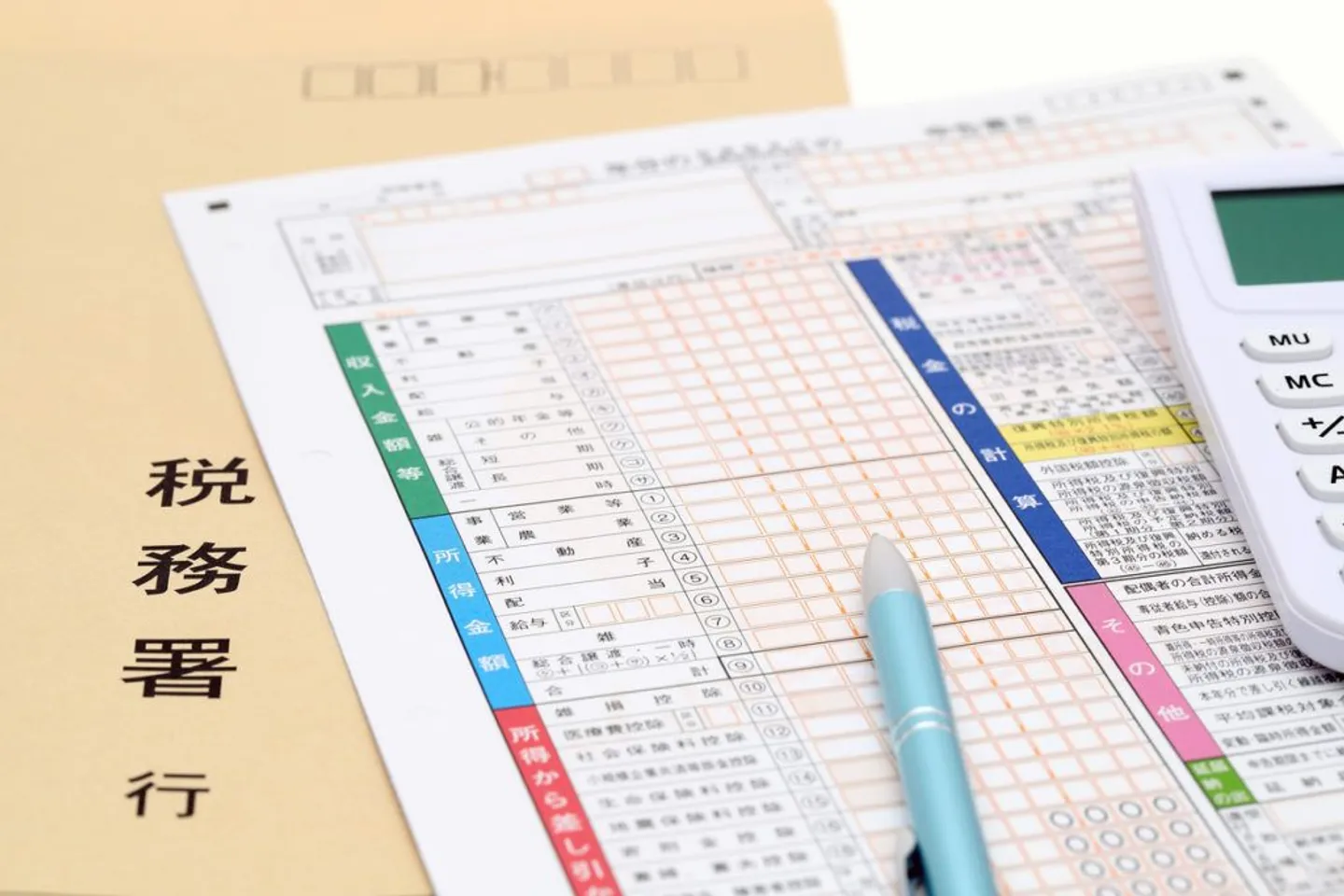
青色申告では、複式簿記での詳細な帳簿付けが求められます。複式簿記とは、1つの収支について複数の視点から記録を残す方法です。
「修繕費の5万円は現金5万円を支出して支払った」という詳細な記録ができる代わりに、経理作業が煩雑になります。
先に解説したように、青色申告による確定申告は、事前に「青色申告承認申請書」などを提出しなければいけません。
また、複式簿記によって日々の取引記録を付け、確定申告時には損益計算書と貸借対照表を作成して提出する必要があります。
加えて、青色申告のために記録した帳簿類は、原則として7年間保管する義務があります。
上記のとおり、面倒なことも多くある青色申告ですが、白色申告にはない税制上の特典を受けられます。
【特典1】青色申告特別控除
不動産所得または事業所得のある青色申告者には、65万円の特別控除が適用されます。
条件は下記のとおりです。
- 複式簿記で帳簿付けをしていること
- 確定申告の期限内に、損益計算書および貸借対照表を確定申告書に添付して提出していること
上記のどちらか1つでも満たしていないと、控除額は10万円に引き下げられてしまうので注意しましょう。
【特典2】純損失の3年間繰越し
青色申告をおこなっている個人事業主は、純損失を3年間繰り越すことが認められています。
■1年目・・・300万円の赤字
■2年目・・・150万円の黒字
■3年目・・・200万円の黒字
1年目は300万円の損失なので、所得税はかかりません。
2年目の確定申告では、150万円の利益から、1年目の損失を差し引けます。「150万円-300万円=-150万円」となって利益が相殺されるため、所得税はかかりません。
3年目は、前年で相殺しきれなかった損失を差し引きます。「200万円-150万円=50万円」となり、50万円に対してのみ課税されます。
【特典3】少額減価償却資産の特例
この特例は、「取得価額が30万円未満の減価償却資産について、取得して事業に使用し始めた年度の必要経費としてその全額を計上できる」という特例です。
ただし、特例を受けられるのは中小企業者であり、従業員の数が1,000人以下(令和2年4月1日以後には500人以下)であることが条件です。
また、各年度分において少額減価償却資産の取得価額の合計が300万円以下であることも条件になっています。
国税庁:「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
まとめ
大家として家賃収入を得る場合、確定申告は必須です。
さまざまな特典を受けられる青色申告を利用する場合、事業を開始してすぐに事前準備をはじめる必要があるため、注意しましょう。
税金のことで不安があれば税理士や、税理士と連携した賃貸管理会社に相談しましょう。個々のケースにあわせて、最適な節税方法をアドバイスしてくれます。