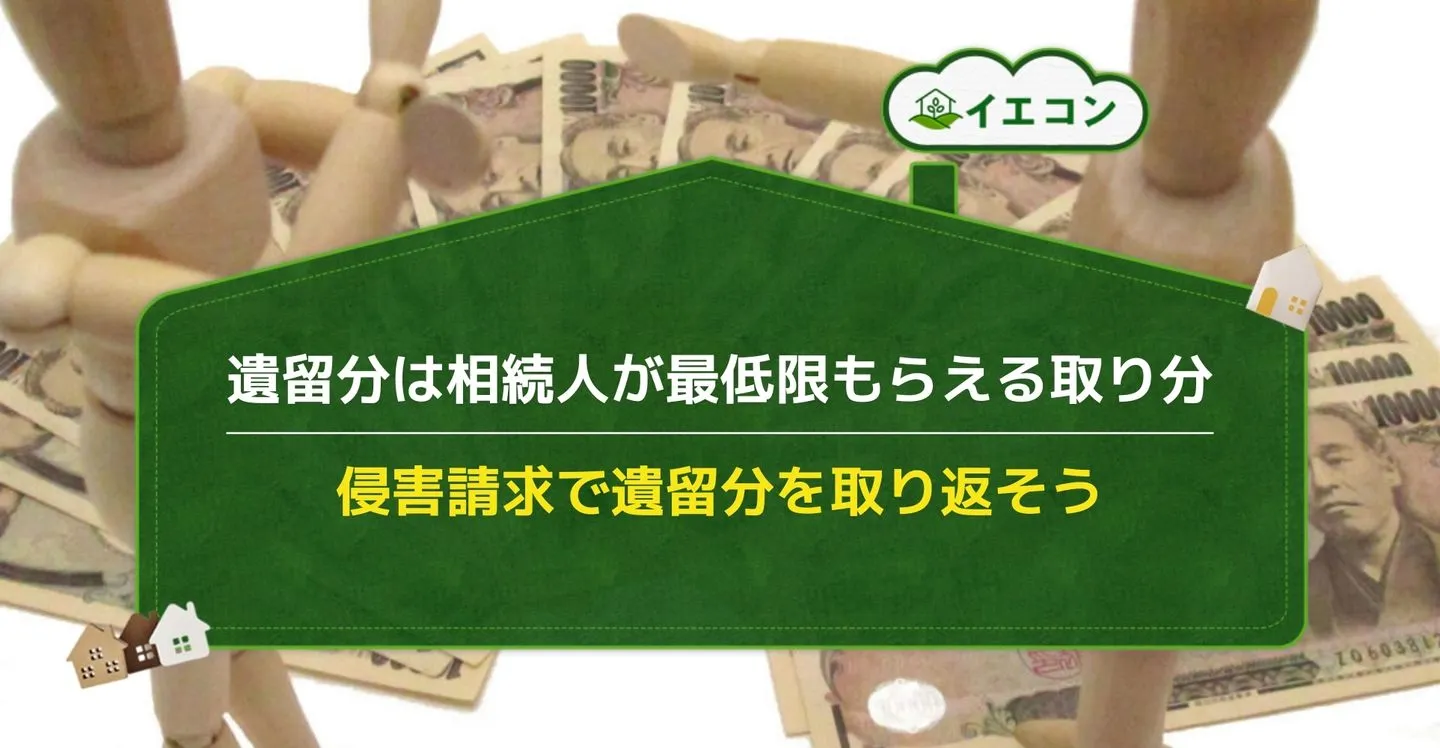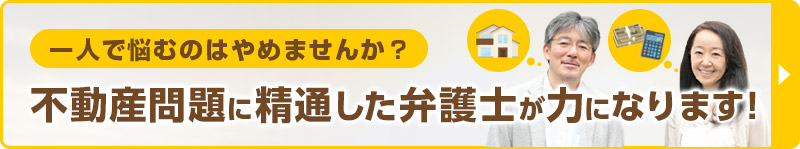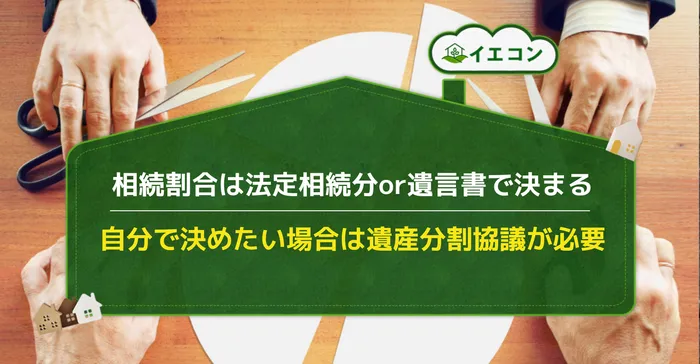相続が発生したとき、相続人が最低限取得できる「遺留分」。
相続で遺留分を無視した遺産分割がおこなわれたとき、遺留分侵害額請求によって取り返すことが可能です。
遺留分侵害額請求は、他の相続人と話し合って和解するのが基本です。
しかし、話し合いでの解決がむずかしいときは、裁判所に調停や訴訟を申し立てなければいけません。
弁護士に相談すれば、相手方との交渉から裁判所の手続きまで一任できます。不動産問題に強い弁護士へ相談し、遺留分侵害額請求の適切なアドバイスを聞いてみましょう。
遺留分とは「相続人が最低限もらえる財産の取り分」
被相続人の遺言があっても、その内容どおり相続されるとは限りません。
法定相続人には「遺留分」というものがあり、相続時に最低限受け取れる財産の割合が決まっています。
例えば、遺言で相続割合が指定されており、遺留分の半分しか相続できなかった場合、残りの半分を他の相続人などに請求できるのです。
本来受け取れるはずだったにも関わらず、なんらかの理由で受け取れなかった遺留分の金額を「遺留分侵害額」といいます。
遺留分はどの相続人まで認められる?
遺留分が認められる相続人は、以下のように被相続人との続柄によって決められています。
- 配偶者
- 子供(子供がすでに死亡している場合は孫)
- 直系尊属(父母、父母がどちらも亡くなっている場合は祖父母)
被相続人の兄弟姉妹や甥姪には、遺留分が認められないため注意しましょう。
遺留分を求める計算式
各相続人に認められている遺留分は以下の式で計算できます。
・ただし、相続人が直系尊属しかいない場合は「遺留分=相続財産×1/3÷相続人の人数」
法定相続分とは、民法で定められている遺産分割の目安です。
上記の計算式だけでは、具体的に「相続財産の何割が遺留分になるか」がわかりにくいと思います。
そこで、下記の表で「相続財産全体に対する遺留分の割合」をまとめました。
下記の表にある遺留分の割合を相続財産にかけ合わすことで、各相続人の遺留分がわかります。
| 相続人 | 配偶者の遺留分 | 子供の遺留分 | 直系尊属の遺留分 |
|---|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1/2 | - | - |
| 配偶者と子供 | 1/4 | 1/4 | - |
| 配偶者と直系尊属 | 1/3 | - | 1/6 |
| 子供のみ | - | 1/2 | - |
| 直系尊属のみ | - | - | 1/3 |
仮に相続財産が5,000万円で、相続人が配偶者と子供なら、遺留分は配偶者・子供のどちらも1/4である1,250万円です。
ただし、子供や直系尊属は、遺留分を同順位の相続人の数で割らなければなりません。
つまり、相続人が配偶者と子供2人ならば、遺留分は配偶者1,250万円、子供はそれぞれ625万円になります。
遺留分と法定相続分の違い
遺留分と似た言葉として「法定相続分」があります。法定相続分とは、民法による相続財産の分割目安です。
遺留分と法定相続分の違いは「法的な強制力」です。
法定相続分は、遺言や遺産分割協議による合意があれば無視しても大丈夫です。
しかし、遺留分は遺言や遺産分割協議で無視することはできません。
法定相続分の割合については、下記のとおりです。
| 相続人 | 配偶者の遺留分 | 子供の遺留分 | 直系尊属の遺留分 |
|---|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1/1 | - | - |
| 配偶者と子供 | 1/2 | 1/2 | - |
| 配偶者と直系尊属 | 2/3 | - | 1/3 |
| 子供のみ | - | 1/1 | - |
| 直系尊属のみ | - | - | 1/1 |
法定相続分について、詳しくはこちらの記事もご覧ください。
相続できなかった遺留分は「遺留分侵害額請求」で取り返せる
遺留分は、法律で保障された「各相続人が最低限確保できる相続の取り分」です。
被相続人の遺言や遺産分割協議による合意などで遺留分を無視された場合、侵害された遺留分を金銭で請求できます。
また、相続財産だけでなく、被相続人が生前贈与した財産についても「遺留分を侵害された」と主張できるケースがあります。
遺産そのものではなく金銭を請求する
遺留分侵害額請求では、遺産そのものではなく遺留分を金額に換算して請求します。
相続財産が現金だけとは限らず、不動産や車、証券など、現物では分割しづらいケースも少なくありません。
また、相手がすでに相続不動産を売却している場合、現物請求だと不動産の購入者と交渉が必要になり、手続きが複雑になってしまいます。
遺留分侵害額請求では上記のようなケースも考慮し、精算方法を平等に分割しやすい現金のみとしています。
生前贈与された財産への遺留分侵害額請求も可能
被相続人の遺言でも無視できない遺留分ですが、被相続人生前贈与をおこなっていた場合はどうなるのでしょうか?
結論をいうと、被相続人が本人の意思で生前贈与した財産に対しても、遺留分が認められる場合があります。
具体的な事例としては、下記のケースがあげられます。
- 相続の1年以内になされた贈与
- 故意に相続人の遺留分を侵害する贈与
- 過去10年でおこなわれた特別受益にあたる贈与
【ケース1】相続の1年以内になされた贈与
相続発生時、つまり被相続人が亡くなった日から過去1年以内に贈与した財産に対して、遺留分を請求できます。
受贈者(贈与を受けた人)が相続人であるかどうかは問われません。
つまり、相続とはまったく関係のない人が贈与を受けた場合でも、遺留分を請求できます。
【ケース2】故意に相続人の遺留分を侵害する贈与
被相続人と受贈者が、遺留分をもつ人に対して損害が発生することを知りながら贈与をおこなった場合も、遺留分侵害額請求の対象にできます。
つまり、贈与者と受贈者が「遺留分の侵害になると知っていた」ケースも遺留分侵害額請求が可能です。
遺留分の侵害になると知っていたかどうかの判断は、次の点から総合的に判断されます。
- 贈与時における贈与者の全財産と贈与した割合
- 贈与時における贈与者の年齢や健康状態
- 贈与の後に贈与者の財産が増える可能性
なお、このケースについては期限の定めはなく、相続発生から1年以上前の贈与でも遺留分侵害額の請求が可能です。
また、このケースでは贈与だけではなく、不当な金額での売買取引も遺留分侵害額を請求できます。
ただし「被相続人と受贈者が遺留分を侵害することを理解していた」という事実は、請求側が証明しなければいけません。
【ケース3】過去10年でおこなわれた特別受益にあたる贈与
特別受益とは、相続人の誰かが被相続人から特別に受けた利益をいいます。
具体的には、次のいずれかに当たるものが特別受益です。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 婚姻のための贈与 | 結婚生活をサポートするための贈与など |
| 養子縁組のための贈与 | 実親からの持参金など |
| 生計の資本としての贈与 | 開業資金や住宅購入費用など |
相続発生から過去10年以内にあった特別受益は、遺留分侵害額請求ができます。
また、遺言書によって法定相続人以外が相続人となる場合も特別受益とみなされるため、遺留分侵害額請求が可能です。
遺留分侵害額の請求には優先順位がある
生前贈与や遺贈が複数回おこなわれている場合、次のように遺留分侵害額を請求する順序が決められています。
- 遺贈
- 死因贈与
- 生前贈与(相続日に近いものから)
・死因贈与:「死亡したときに贈与する」と当事者間で結ぶ贈与契約。契約であるため、贈与を受ける側の合意も必要。
複数の遺贈・贈与があった場合は、相続発生日に近い遺贈・贈与の受取人から順次請求していきます。
請求金額と請求順序の具体例
遺留分侵害額の請求金額と請求順序について、具体例を見ていきましょう。
例えば、遺留分侵害額が500万円あったとします。そして、遺贈や贈与がそれぞれ次のようにあったとしましょう。
- Aへの遺贈が200万円
- Bへの死因贈与が800万円
- Cへの生前贈与が1,000万円
まずはAに対して遺留分を請求しますが、500万円-200万円で300万円が足りません。Aへの請求で足りない300万円は、次のBへ請求します。
Bへの請求で残りの300万円も取得できるので、遺留分侵害額の請求はここで完了します。Cへの請求はおこないません。
また、A・Bへの請求を飛ばして、Cに請求することもできません。
遺留分侵害額請求権は時効で消滅する
遺留分侵害額請求権には時効があります。請求せずに放置していると、本来もらえるはずだった遺留分がもらえなくなってしまうので注意しましょう。
相続の開始および遺留分の侵害となる行為を認識したときから、1年以内に請求をしなければ権利が消滅します。
また、相続の開始や遺留分の侵害行為を知らない状態でも、相続開始から10年間が経過すると同じく消滅してしまいます。
相続が発生したときは、なるべく早く遺留分が侵害されていないか確認する必要があるでしょう。
遺留分を請求できないケースもある
本来は遺留分をもっているはずの人でも、下記のケースに該当すれば、遺留分を請求できなくなります。
| 相続欠格になった人 | 相続するために殺人や脅迫など不正な行為を起こして、相続人の権利を失った人 |
|---|---|
| 相続廃除になった人 | 虐待や精神的苦痛などを与えたとして、被相続人の意思により相続権を剥奪された人 |
| 相続放棄をした人 | 自分の意思で相続する権利を放棄した人 |
上記に該当する人は、例え配偶者や子供であっても遺留分を主張できません。
遺留分侵害額を請求する方法
遺留分侵害額の請求は、次の順序で進めていきます。
- 相手と話し合いで和解をする
- すぐに和解できなければ内容証明郵便を送付する
- 当事者間での解決ができなければ調停・訴訟をする
当事者同士の話し合いで解決できればよいのですが、話し合いがまとまらない場合、裁判所へ調停の申立てや、訴訟を起こす必要も出てきます。
遺留分が実際に侵害されているかどうかの判断も含めて、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
方法1.相手と話し合いで和解をする
親族同士など、話し合いですぐに支払ってもらえそうな相手であれば、連絡をとって遺留分を払ってほしいと申し出ましょう。
相手が納得さえしてくれれば、時間をかけずに解決できます。
遺留分の支払いを受けるときには、トラブル防止のために必ず「遺留分侵害額についての合意書」を作成しましょう。
方法2.すぐに和解できなければ内容証明郵便を送付する
相手がすぐに遺留分を支払ってくれなさそうなときは、内容証明郵便を使って「遺留分侵害額請求書」を送りましょう。
内容証明郵便の通知書を送れば、遺留分侵害額請求権の時効を止められます。
「相続と遺留分侵害を知ってから1年以内」で時効が成立してしまうので、少しでも時間がかかりそうだと感じたら速やかに送付しましょう。
方法3.当事者間での解決ができなければ調停・訴訟をする
相手がどうしても支払ってくれず、話し合いでの解決がむずかしいと感じたら、調停や裁判に進みます。
遺留分侵害額請求では、基本的に調停からおこないます。明らかに話し合いが困難といえる状況でもない限り、裁判からはじめることはありません。
まずは調停を裁判所に申立てます。調停は裁判所の調停員が話し合いを進行しますが、あくまでも当事者たちの和解を目的とした手続きです。
調停で和解が成立しなかった場合は、訴訟を起こすことになります。裁判では、自分の遺留分が侵害されている事実を証明しなければなりません。
調停や訴訟は法律的な知識が非常に重要になるので、弁護士と相談しつつ、確実に遺留分をもらえるように準備を進めましょう。
2019年の法改正前に発生した相続は「遺留分減殺請求権」が適用される
遺留分侵害額請求権は、近年の法改正で内容に変更がありました。
改正前は「遺留分減殺請求権」とよばれており、遺留分の精算方法や請求期限に違いがあります。
改正法の施行日が2019年7月1日なので、2019年6月30日以前に発生した相続は、遺留分減殺請求権の対象です。
具体的にどのような違いがあるか、確認してみましょう。
【違い1】現物返還が原則
遺留分減殺請求権では、侵害した遺留分は現物で返すのが原則でした。
相続財産が不動産なら対象の不動産を、証券なら対象の証券を個別に返還されていました。
仮に不動産が現物で返還されれば、当事者たちの共有状態になります。
しかし、一度トラブルになった人同士が共有状態になるのは、当事者としても好ましくありません。
そこで、遺留分侵害額請求権への法改正によって、相続財産そのものではなくお金を請求する権利(債権的権利)に統一されました。
【違い2】特別受益の請求期限がない
法改正でもう一つ変更されたのが、遺留分侵害額の対象となる生前贈与の範囲です。
遺留分減殺請求権では、相続人への特別受益の対象となる生前贈与に期間の定めがありませんでした。
そのため、数十年前の贈与であっても遺留分を請求可能だったのです。
これが法改正によって、過去10年以内という時効が定められました。
まとめ
遺留分侵害額について、金額の計算方法や請求方法を解説しました。
遺留分をもっているのは、被相続者の配偶者・子供(もしくは孫)・直系尊属(父母もしくは祖父母)です。相続人の続柄や人数によって遺留分の割合も変わります。
請求するときは、まずは遺留分を侵害している人と話し合いましょう。話し合いによる解決がむずかしいときは、内容証明郵便で遺留分を請求したうえで、調停や裁判に進みます。
遺留分侵害額の成立や金額の判断は専門的な知識が必要なため、少しでも「遺留分が侵害されているかも?」と感じたときは、早めに弁護士へ相談しましょう。