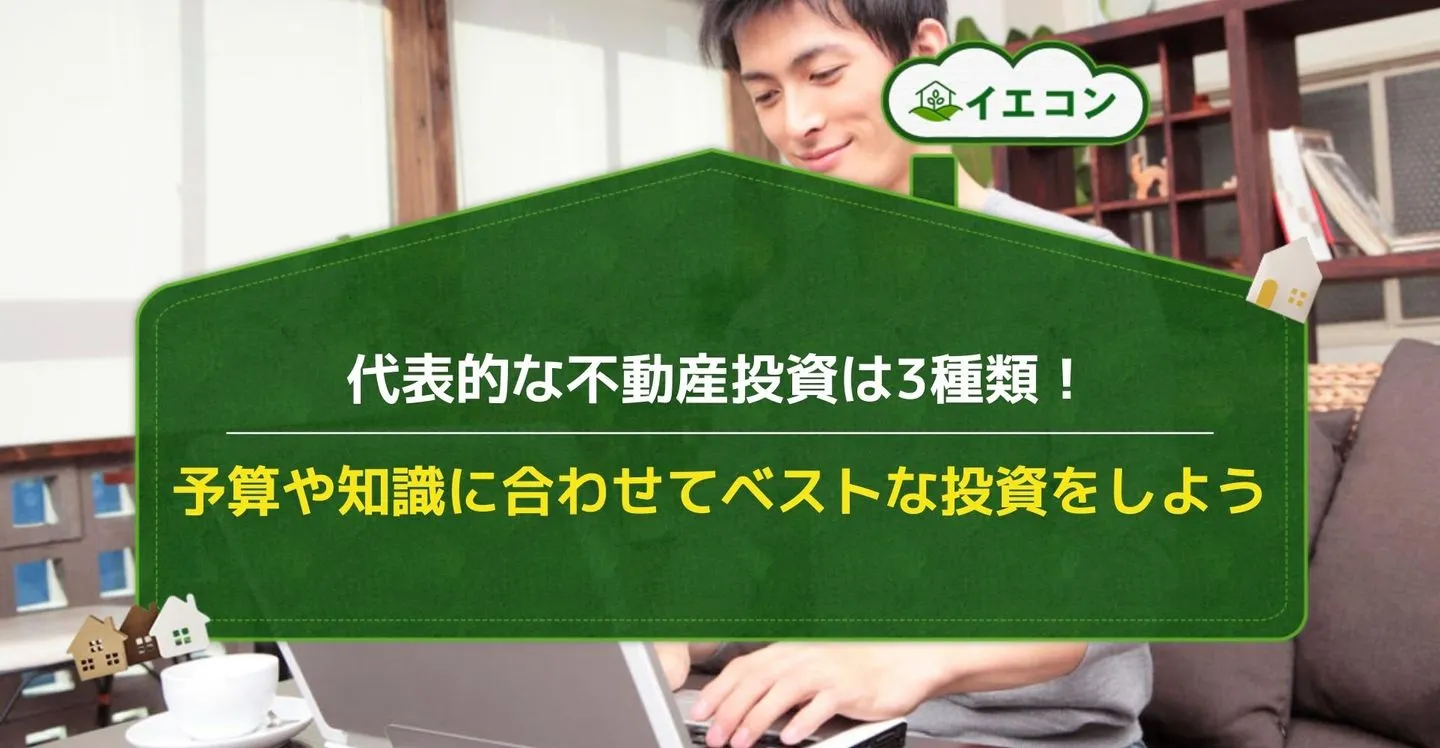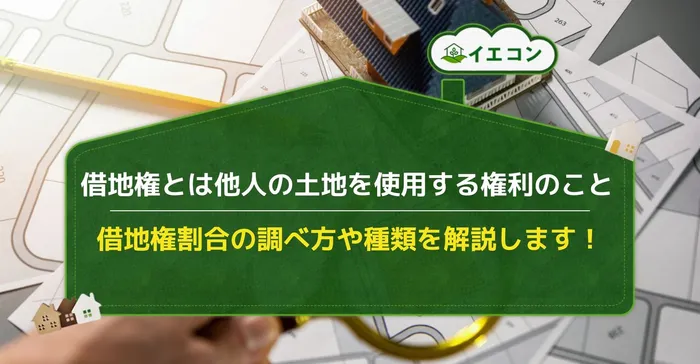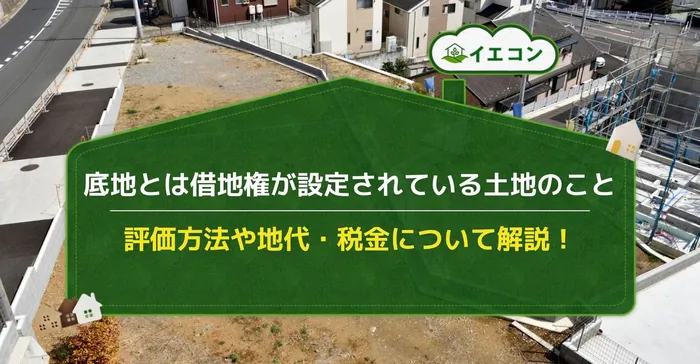いざ不動産投資を始めようと思っても、具体的にどんな方法があるかわからない人も多いでしょう。
主な不動産投資は「区分マンション投資」「戸建て投資」「一棟アパート投資」の3つがあり、自己資金や融資の上限額に応じて自分に合ったタイプを選ぶのが基本です。
また、民泊やシェアハウスのように一般的な賃貸とは違った物件や、1万円程度の自己資金からできる少額投資などもあります。
また、自分に合った投資方法を選ぶのに不安があるときは、専門家に相談してみることもおすすめです。不動産投資を専門とする会社に相談すれば、物件選びから運営計画の立案までアドバイスしてもらえます。
下記のリンクから、複数の不動産投資会社を一括で比較することができます。専任のコンシェルジュがつくので、安心して不動産投資を始めることが可能です。
代表的な3種類の不動産投資とメリット・デメリット

一口に不動産投資といっても土地や建物によってさまざまな方法があり、人によって向き・不向きがあります。
まずは代表的な不動産投資の方法として、下記の3つを紹介します。
- 区分マンション投資
- 戸建て投資
- 一棟アパート投資
これらは基本的な不動産投資の方法なので、物件も運用手法も探しやすいのが特徴です。
これから不動産投資を始めるなら、ぜひこの3つから取り組んでみましょう。
1.区分マンション投資
マンションを一部屋ごとに分けて販売しているものを「区分(分譲)マンション」と呼びます。
区分マンションの一部屋(もしくは複数)を購入し、賃貸として貸し出すのが区分マンション投資です。
区分マンションは基本的な不動産投資のなかでもっとも始めやすく、初心者にもおすすめできる方法です。
投資効率が低いため資産形成まで時間がかかる点はデメリットですが、経験を積むためには最適な投資方法といえるでしょう。
次の項目から、より具体的に区分マンション投資のメリットとデメリットを見ていきましょう。
区分マンション投資のメリットは「始めやすく流動性が高い」こと
区分マンション投資の主なメリットは以下の通りです。
- 1,000万円程度の少額の投資資金から始められる
- 投資額が比較的少ないため、管理や融資のハードルが低い
- 複数の地域に分けて分散投資をすればリスク分散ができる
- 市場が大きく流動性が高いので売却しやすい
単価が安く、管理の手間も少ないため、初心者でも始めやすい点が大きなポイントです。
また、少額の資金で始められるため失敗したときのリスクも低く、売却のしやすさから損切りもしやすい方法といえます。
区分マンション投資のデメリットは「投資効率や自由度が低い」こと
区分マンション投資の主なデメリットは以下の通りです。
- 他の投資と比べて入ってくる賃料が少なく、投資効率が低い
- 万が一空室になると無収入となり、利回りが低下する
- 空室・家賃滞納があった場合に収入がなくなる
- 建物の管理は管理組合に任せることになるため、管理費・修繕積立金が必要になる
- 土地の権利割合が低いため、年数が経つにつれて担保評価額が低下する
- 共有部分に関しては自分だけでは決められないため、物件管理の自由度が低い
とくに大きなデメリットは、他の投資方法と比べて得られる賃料収入が少ない点です。投資資金を回収するまで時間がかかるため、その間に物件自体の資産価値が下がってしまいます。
また、戸建てや一棟アパートならリフォームで資産価値を高めたり、更地化して売れやすくしたりといった工夫を自己判断でおこなえますが、区分マンションではそういった工夫がむずかしくなります。
マンション全体のルールといったしがらみが発生するため、自分で積極的に物件を管理したい場合は向いていないといえるでしょう。
2.戸建て投資
戸建て住宅を貸し出す方法が「戸建て投資」です。一般的には中古住宅を購入して貸し出すケースが多くなります。
区分マンションに比べて利回り(投資した金額に比べてどれだけ利益を得られるかの数値)が高い物件が多く、長期間に渡って安定した収入を期待できます。
一方、建物の修繕が必要になったときは都度お金がかかるため、自分で計画的に積み立てておくことが大切です。
修繕を怠ると建物の劣化が進み、入居者がつきにくくなるため注意しましょう。
戸建て投資のメリットは「高利回りと長期の賃貸収入が期待できる」こと
戸建て投資の主なメリットは以下の通りです。
- 地価の安い郊外なら高めの利回りが期待できる
- 長期間の入居になる場合が多い
- 土地部分は値下がりしにくい
- 実需目的(マイホーム利用)の人も購買層となるため投資家以外にも売却しやすい
中古住宅は安く買えて高利回りの物件が多く、投資資金を回収しやすいのが特徴です。
また、子育て世帯などが入居しやすく、子どもが自立するまで住み続けるケースが多いため、入居期間も長くなる傾向にあります。
一度入居者が決まれば、継続して安定した賃料収入を期待できるでしょう。
戸建て投資のデメリットは「資産価値が下がりやすく維持コストが高い」こと
戸建て投資の主なデメリットは以下の通りです。
- マンションやアパートより設備が多いため修繕費用が高くなる
- 地域によっては賃貸需要が低く入居者を見つけにくい
- 築年数が進むと担保評価額が下がる
- 自分で修繕計画を組む必要がある
- リフォームの専門知識が必要になる
とくに注意したいのが、家の修繕費用です。 鉄筋コンクリートなどが主体のマンションと比べ、木造建築がほとんどの戸建ては建物が劣化しやすくなります。
万が一シロアリや雨漏りなどの被害があった場合、修繕費は100万円を超える場合もあります。
入居者から修繕や設備の入れ替えを求められるケースも多く、維持コストがかさみやすいといえるでしょう。
3.一棟アパート投資
アパートを一棟購入して運用する方法を「一棟アパート投資」といいます。
物件価格が高くなるため多くの資金が必要ですが、軌道に乗れば効率的に資産を増やすことが可能です。
ただし、投資資金が高額な分、失敗したときのリスクも高いといえるでしょう。
ハイリスク・ハイリターンになるので、他の投資方法である程度経験を積んでから取り組むのがおすすめです。
一棟アパート投資のメリットは「賃料収入が安定し投資効率がよい」こと
戸建て投資の主なメリットは以下の通りです。
- 一度の投資で大きな資産を形成できるので投資効率がいい
- 部屋数が多いため空室リスクを抑えられる
- 土地割合が大きいため金融機関から高い担保評価が得られる
- 一棟すべてが自分の所有物であるため、建物の修繕・建て替えなどの自由度が高い
一番のメリットは、複数の入居者から賃料を得られるため、収入が安定しやすいことです。仮にいくつかの部屋で空室が出ても、収入がゼロになることは少ないでしょう。
1つの物件で得られる利益が大きいため、効率的に資産形成をおこなうことが可能です。
一棟アパート投資のデメリットは「投資金が多くリスクが高い」こと
戸建て投資の主なデメリットは以下の通りです。
- 建物一棟を所有することになるため高額の投資資金が必要になる
- 投資実績がないうちは金融機関の融資が受けにくい
- 自分で修繕計画を組む必要がある
- 投資金額が大きいため失敗した場合の損害が大きい
必要な投資資金が高額になるため、そもそも一棟アパート投資を始めること自体がむずかしくなります。
うまく入居者が集まらないと赤字も膨れ上がり、大きな損失を抱えてしまうかもしれません。
これらのことから、一棟アパート投資は他の投資方法で実績を積み、一定の知識と資金を得た人に向いているといえるでしょう。
物件選びや運用方法に不安があるときは専門家のアドバイスを聞こう
主な不動産投資の種類を解説しましたが、実際に物件を選ぶときや融資の申し込み、購入後の運用計画など、不安の大きい人も多いでしょう。
動かす金額が大きいため、可能な限り失敗の芽を摘み成功確率を上げたいものです。
そこでおすすめなのが、投資を専門とする不動産会社に相談することです。プロの観点から、収益性の高い物件を紹介してもらえたり、物件運用のサポートを受けられるなどのメリットがあります。
下記のリンク先では、あなたの状況に合わせて最適な不動産投資会社を一括比較することが可能です。専任のコンシェルジュについてもらえるので、不動産投資を始める際はぜひ活用してみましょう。
その他の不動産投資の種類

代表的な3つの不動産投資について解説しましたが、他にも下記のような投資の種類があります。
- テナント系投資
- 借地権投資
- 底地投資
- 民泊
- シェアハウス
- サービス付き高齢者向け住宅
- コインパーキング
- トランクルーム
- コンビニ土地活用
- 太陽光発電
物件によっては上記の投資方法が向いているケースもあるので、選択肢1つとしてそれぞれの方法を把握しておきましょう。
1. テナント系投資
オフィスや店舗などテナント系の物件は、マンションやアパートの家賃と比べて高くなるため、高利回りが期待できます。とくに、市街地や駅前などの商業エリアは投資効率が高いでしょう。
保証金や敷金が高いのもテナント系物件の特徴で、一般的に住居の敷金は家賃の1~2カ月分ですが、オフィスや店舗は3~6カ月分というケースが多くなっています。
保証金や敷金は最終的に借主に返還するものですが、賃料の滞納があった場合はそこから補填できるため、多く預かれる分にはメリットだといえるでしょう。
ただし、テナント系の物件は一度退去があると、次の入居まで時間がかかることも少なくありません。
景気に左右される傾向も強いため、コロナ禍のような特殊な状況などで需要が大きく落ち込む恐れもあります。
2.借地権投資
借地権とは「土地を借り、土地の借主名義の建物を建てることができる権利」を指します。借地権付きの土地を購入し、そこにマンションなどを建てて貸し出すのが借地権投資の主な方法です。
借地権投資のメリットとしては、土地を取得・使用するための費用や税負担が抑えられること、そして土地を所有するより利回りが高くなることが挙げられます。
土地の所有者から土地を借りて地代(賃借料)を払うわけですが、借地権なら所有権の相場の6~8割程度(地主によって異なる)で土地を使用できます。
さらに、固定資産税や都市計画税などは土地の所有者が支払うため、税負担も軽減され土地にかかるコストを全体的に抑えられるというわけです。
ただし、借地権投資の場合土地自体は地主のものであるため、土地を担保として融資が受けられないというデメリットもあります。
また、借地権には以下の3種類があり、少しずつ内容が異なるので注意が必要です。
- 旧法借地権(借地借家法施行前に結んだ借地契約。建物の構造によって契約期間が変わる)
- 普通借地権(期間満了とともに原則更新する借地契約)
- 定期借地権(期間満了後は更新しない借地契約)
- 一時使用目的の借地権(建設現場や一時的興行に伴い短期間だけ結ぶ借地契約)
借地権については下記の記事で詳しく解説しているので、気になる人は参考にしてみてください。
3.底地投資
底地投資とは底地(借地権がついている土地)を取得し、地代や更新料・各種の承諾料を収入とする投資方法です。
底地投資のメリットとしては空室リスクが低いこと、そして貸し出すのが建物ではなく土地であるため滅失リスクも低く、管理におけるコストもあまりかからないことが挙げられます。
その一方で、マンション・アパート経営ほどの収入が得られない、流通性が低く売却が難しいといったデメリットもあります。
一度購入したら簡単には手放せないため、投資物件とするには需要の高い地域にある土地であるか、土地の価格に見合う地代が設定されているかなど、しっかりと見極める必要があります。
底地については下記の記事でも解説しているので、よろしければ参考にしてください。
4.民泊
民泊とは、マンションの一室や一軒家を観光客などに向けて貸し出す利潤目的のサービスを指します。
アメリカのAirbnb(エアビーアンドビー)という企業が貸したい人と借りたい人を繋ぐWebサービスを提供し始めたことから、日本でも都市部を中心に浸透しつつありました。
しかし、新型コロナウイルスの影響で観光客需要が激減し、事業廃止が増加しています。業界の先行きも不透明で、2021年時点ではあまりおすすめできない投資方法です。
もしも民泊を運営するとしても、住宅宿泊事業法にもとづいた届出や、年間180日以内の提供日制限、最低床面積の確保など、さまざまな規則を守る必要があります。
また、マンションの場合は管理組合によっては民泊を禁止しているところも少なくないため、事前の確認が必要です。
「民泊を始めたい」という人は、まず住宅宿泊事業法の細かい規則と、提供予定の物件が民泊として適切かどうかをしっかりと見極める必要があります。
5.シェアハウス
シェアハウスとは、自分の部屋以外のキッチンや浴室などを共有スペースとし、他の居住者とシェアする形の賃貸住宅です。
通常の賃貸アパート・マンションを借りるより初期費用や月ごとの費用を抑えられることから、若者向けを中心に今後も一定の需要が見込めます。
シェアハウスは比較的高利回りを狙いやすく、収益性が高いことが特徴です。入居者の人数が多いので家賃収入総額が増えますし、空室リスクも低いため一棟アパートと同じようなメリットがあります。
反面、複数の居住部屋に対しトイレや浴室・キッチンは共有なので、一棟アパートより設備コストが大幅に抑えられます。
ただし複数人の共同生活であるため、トラブルを回避するための対策が必要になるなど一般の賃貸住宅より管理の手間がかかります。
そのため、管理会社に管理を任せる場合でも、一般的な賃貸不動産より管理費用がやや高くなるケースが少なくありません。
6.サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅とは、バリアフリー賃貸住宅に安否確認と生活相談サービスが付帯したものです。有料老人ホームとは異なり、介護の必要がない・軽度の要介護高齢者向けに提供されています。
本格的な介護サービスは付帯しないのが一般的ですが、有料老人ホームと同等の介護サービスを独自につけて、高齢者が安心して暮らせる環境を整えるケースもあります。
日本には有料老人ホームやデイサービスは多くあるものの、介護の必要がない比較的健康な高齢者向けの住宅は不足傾向にあります。
そのため政府もサービス付き高齢者向け住宅を積極的に増やそうとしており、一定の条件を満たせば建設のための補助や融資が利用できる、固定資産税が軽減されるといった優遇措置が受けられます。
アパートやマンションなどの一般的な不動産物件は、高齢者人口が増えていくと空室リスクや家賃下落のリスクが高まりますが、高齢者向けの住宅の需要は今後も高まっていくと考えられるでしょう。
ただし、地域によってはすでに多数の介護福祉施設があって利用者がなかなか見つからず、空室が目立つ可能性もゼロではありません。サービス付き高齢者向け住宅を成功させるには、医療や介護事業、不動産賃貸業など多岐にわたる知識とノウハウが必要になります。
まずは地域のニーズや入居者のターゲットを十分に考え、サービス付き高齢者向け住宅の運営経験が多い不動産会社を探すところから始めてみるとよいでしょう。
7.コインパーキング
初期費用が少なくランニングコストもほとんどかからないコインパーキングは、すでに土地を持っている方には始めやすい投資方法です。コインパーキングには、自営で行う方法と専門業者に貸し付ける方法があります。
自営の場合は利用率に応じて収入が増えるというメリットがある一方で、機械の設置など初期費用がかかることがデメリットとして挙げられます。
貸し付けの場合は毎月一定の収入が得られる、メンテナンスなど手間がかからないといったメリットの一方で、賃料以上の収入は得られないというデメリットがあります。
自営・貸し付けに共通したコインパーキングの大きなメリットとしては、狭小地や変形地であっても立地がよければ経営できることが挙げられますが、近年はすでに駐車場経営をしている人も少なくなく、競争が激しくなる可能性も考えられます。
土地探しから始める場合、場所によってはコインパーキングに適した土地を見つけるのが難しいこともありますし、税制面で優遇が受けられない点や初期費用が少なくて済む分アパート経営などと比べると収入額が少ない点もデメリットとして挙げられます。
コインパーキングを始める際は、まずは近所や各地のコインパーキングを実際に見に行ってみたり、インターネットを駆使して研究するなど、どんなエリアのどんなコインパーキングが成功しているのかを調べてみましょう。
8.トランクルーム
荷物の保管スペースを貸し出す「トランクルーム」投資は、コンテナなどを設置すれば始められるためリスク・コストを抑えられるメリットがあります。
現代では核家族化が進み、住む家も一軒家ではなく収入スペースの少ないアパートやマンションなど移り変わってきていることから、季節家電や衣類、たまにしか使わないものなどをトランクルームに預ける人が増えてきています。
少子高齢化により今後も核家族化が進むと予想され、トランクルームの需要も高まると考えられるでしょう。
ただし、一般的な不動産投資同様、空室リスクもあるということには留意が必要です。たとえば引っ越しが多い3~4月頃は満室でも、それ以外は空室が目立つというケースが少なからずあります。
また、ローリスクで誰でも始めやすいというメリットは、参入者が多くなり価格競争が激しくなるというデメリットにもなり得ます。始める際には立地などをしっかりと見極め、競合が少ない場所を選ぶ必要が出てくるでしょう。
需要が伸びているとはいえ日本ではまだまだ認知度が低いため、稼働率が上がるまでにある程度時間がかかることも考えられます。まずは地域人口などの基本的なデータ収集、トランクルームの需要、もしすでに近場にトランクルームがある場合はその料金なども詳しく調べてみましょう。
9.コンビニ土地活用
コンビニ経営は、マンション・アパート経営などと比較すると収益を生み出しやすいともいわれている投資方法です。郊外で住居を建設するには向いていないような広い土地も、郊外型の駐車場が広いコンビニを建てれば、土地の有効活用が可能となります。
コンビニ土地活用には、土地だけを貸す方法(事業用定期借地方式)と、土地に建物を建設して両方貸す方法(リースバック方式)とがあります。
事業用定期借地方式は初期費用がほとんどかからない、相続税評価額が減額される点がメリットとして挙げられますが、収益性は後者よりも低くなるといえるでしょう。
リースバック方式は建物を自分で建てる必要があるため初期費用がかかりますが、コンビニ側が建設代金を無利息で貸してくれることが多くなっています。初期費用がかかる分リスクは高くなりますが、収益性は大きくなるでしょう。
ただし、コンビニ自体の業績が不振となれば、すぐに撤退となることも少なくありません。
コンビニ土地活用を検討する際には、まず近隣にコンビニができそうな土地がないか確認する、コンビニ業界の動向を把握するといったところから始めるといいでしょう。「ビジネスとして真剣に取り組む」という心構えも念頭に入れておきましょう。
10.太陽光発電
太陽光発電投資は、建物の屋根の上や使用していない土地にソーラーパネルを設置し、そこで発電した電力を電気事業者に売却する方法です。2012年に再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT制度)が始まって以来、宅地としての需要がない地方の土地活用の選択肢として注目を集めています。
太陽光発電ではFIT制度により電力が20年間固定価格で買い取ってもらえるため、継続して安定した収入が得られる点がメリットだといえるでしょう。それ以外に電気の専門知識がなくても運用できる、ソーラーパネル設置費用が安くなってきているといったメリットから、初心者でも始めやすい投資です。
デメリットとしては、設置費用が安くなってきているのと同時に電力の売却価格も年々下落傾向にあること、さらにFIT制度の適用終了後は買取価格がどうなるかわからないといった問題が挙げられます。
自然を相手にするものなので、悪天候が続いて思うように収入が得られず初期費用回収までに時間がかかることも考えられますし、太陽光発電設備のメンテナンスや自然災害で被害を受けた場合の損害保険の加入など、ランニングコストについてもある程度考えておく必要もあります。
太陽光発電を始める際には、まず太陽光発電について基本的な情報・知識を仕入れておきましょう。今は複数のメーカーから太陽光発電の装置が出ているので、それらを比較してそれぞれの特徴を把握しておくことも大切です。
1万円~の少額で始められる不動産投資の方法

ここまででご紹介した不動産投資の方法は、ある程度まとまった資金がなければできない方法でした。
しかし、なかには「不動産投資に興味はあるけど、まとまった資金を作るのが難しい」という方もいるでしょう。
そういった人におすすめな「少額融資で始められる不動産投資」として、下記の3点を紹介します。
- REIT(リート)
- 不動産クラウドファンディング
- 不動産ソーシャルレンディング
1.REIT(リート)
REIT(リート)は1960年にアメリカで生まれたシステムで、「Real Estate Investment Trust:不動産投資信託」の頭文字を取ってREITと呼ばれています。日本ではJapanのJをとって『J-REIT』と呼ばれることもあります。
REITの仕組みとしては、まず投資法人が投資家から資金を集め、マンションやオフィスビル・ホテルなど複数のさまざまな不動産を購入し、購入した不動産の賃貸収入・売却利益を配当金として投資家に還元します。
また、配当を得る権限を証券化することで、株式のように証券市場で売買できるのも特徴です。気軽に現金化できるので、不動産投資でありながら資産の流動性が高くなります。
REITのメリット
REITの具体的なメリットは次の通りです。
- 株よりも利回りが高い
- 10万~100万円程度の少額から投資ができる
- 分散投資でリスクが軽減できる
- 株と同じように取引でき、流動性・換金性が高い
- 不動産の選定や運用などはプロが行うので手間がかからない
- NISA(少額投資非課税制度)を利用すれば年間120万円まで非課税となる
実際の不動産を購入して賃貸経営を行う不動産投資の場合、大きな費用が必要となります。しかし、REITは1万円程度から始められるため、敷居が低く誰でも始めやすいということが一番の特徴だといえるでしょう。
REITのデメリット
一方、REITのデメリットとしては次のものがあげれられます
- 実物の不動産の所有ができない
- 賃料の変動などで元本割れする恐れがある
- 上場廃止になる可能性がある
- 投資法人が倒産する可能性がある
- 金利の変動などで配当金が減ることがある
- 自然災害などで土地・建物が損害を受けるとREITの価値にも影響する可能性がある
- 法制度の変更がREITの価値にも影響する可能性がある
REITは「投資信託証券」を購入するので、不動産そのものの所有者になれるわけではありません。
そのため、実物の不動産を自由に使えない点は大きなデメリットといえるでしょう。
REITの選び方
REITはどの銘柄を選ぶかによって収益結果も変わってきます。銘柄を選ぶときは、下記のポイントをチェックしましょう。
| NOI利回り | ネット・オペレーティング・インカムの頭文字をとったもので、配当金から諸経費を差し引いた実質利回りのこと。 |
|---|---|
| 目論見書 | 投資法人の運用方針や体制、投資リスク、申込み方法などを記したもの。 |
| 資産運用報告 | 運用状況の推移や分配金等の実績、保有資産などが記載されたもの。 |
これらの情報は、各銘柄を取り扱っている証券会社から入手可能です。
とくに重要なのはNOI利回りで、REITでは5.5%以上が推奨されます。また、現時点では数値が低くても、今後上がるかどうかを予測することも大切となります。
2.不動産クラウドファンディング
不動産クラウドファンディングは、インターネットで出資者を募って不動産を購入し、運用や売買で得られた利益を出資者に分配する不動産投資です。
REITと似ている部分もありますが、不動産クラウドファンディングの場合は物件ごとに出資をおこなうという違いがあります。そのため、築年数や管理状態などから自分の判断で投資物件を選択できます。
対象となる物件はマンションや商業ビル、ホテルなど多岐にわたるため、普通は個人での投資がむずかしい物件にも出資が可能です。
必要資金もREITと同じように少なく、1万円から投資できる場合もあります。
ただし、REITのように証券化されていないため、資産の流動性は低くなる点はデメリットです。
3.不動産ソーシャルレンディング
不動産ソーシャルレンディングもインターネットを介した不動産投資ですが、仕組みとしては「不動投資運用業者への貸付」になります。企業が個人から資金を集める仕組みなので、クラウドファンディングの一種に分類されることもあります。
貸付契約に基づく返済金利が投資家の収益となるため、不動産運用の状況に関係なく配当金を得られます。
1万円からでも始められるほか、投資期間が数ヶ月~1年程度でできるため、短い期間で運用をしてみたい人にはおすすめの方法です。
ただし、不動産投資業者の経営が傾いたりすると配当が滞る恐れもある点がデメリットとなります。
まとめ
不動産投資を始めるときは、どの方法にもメリットだけでなくデメリットがあるということを踏まえ、その上で土地や物件ごとに適切な投資方法を見極めることが大切です。
一定の資金を用意できるなら区分マンションなどの現物投資、資金が少ないならREITなどの少額投資をおこなうなど、自分の経済状況に合わせた不動産投資の種類を選択しましょう。
また、投資方法の選び方に不安があれば、専門家のアドバイスを聞くことも有効です。とくに初心者の場合は、専門家のアドバイスをもとに確実な不動産投資をおこないましょう。