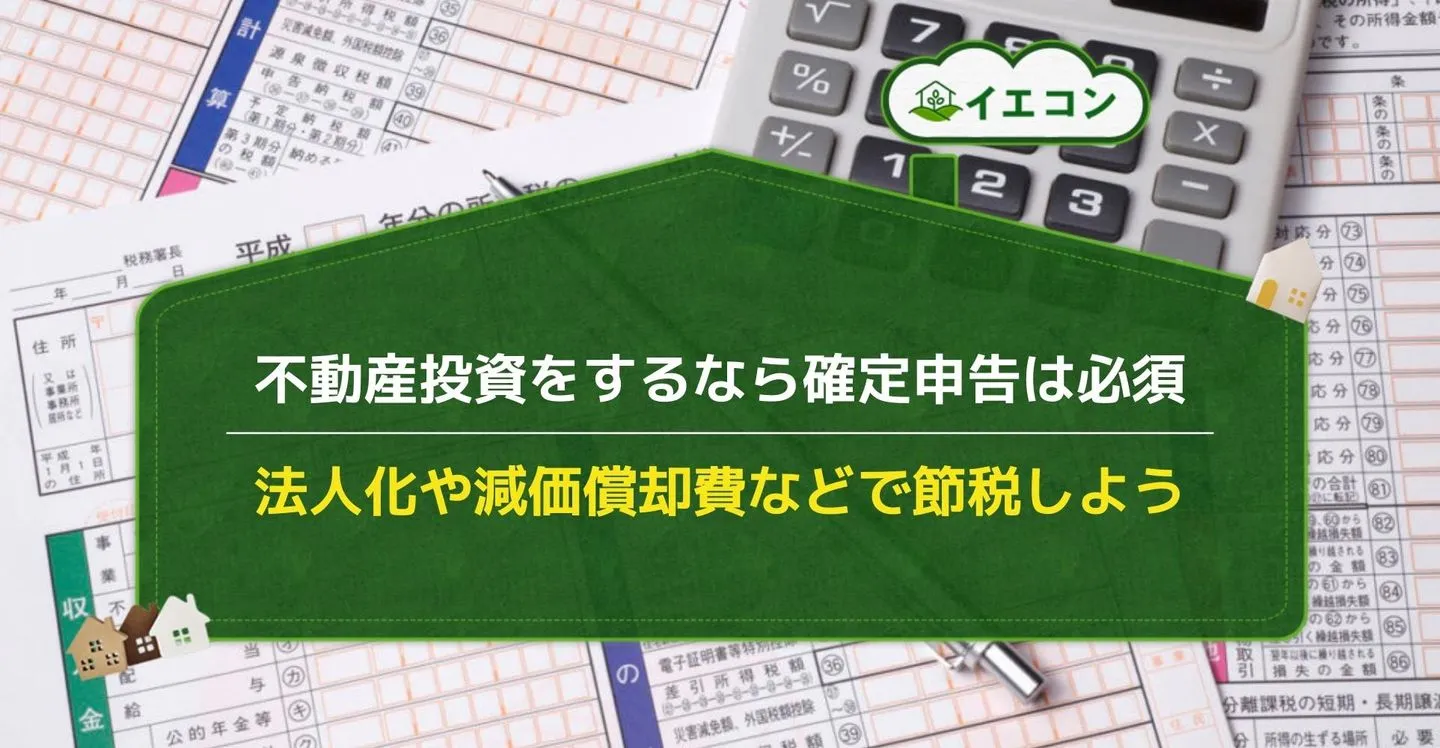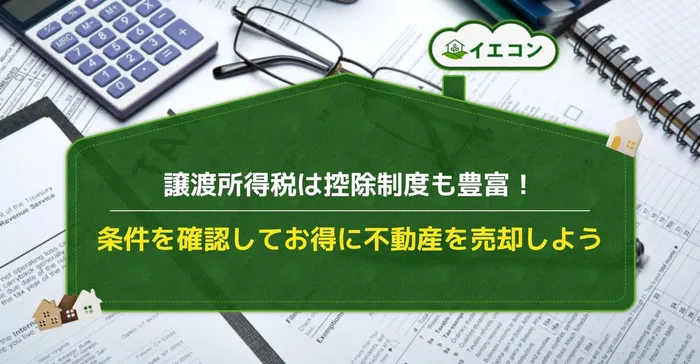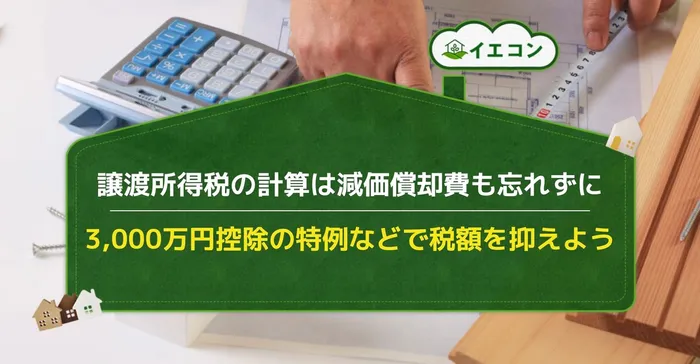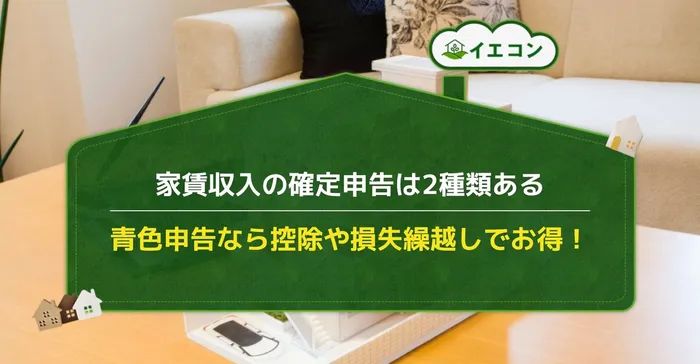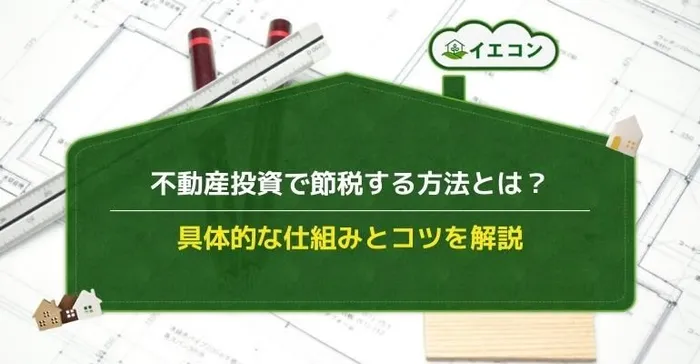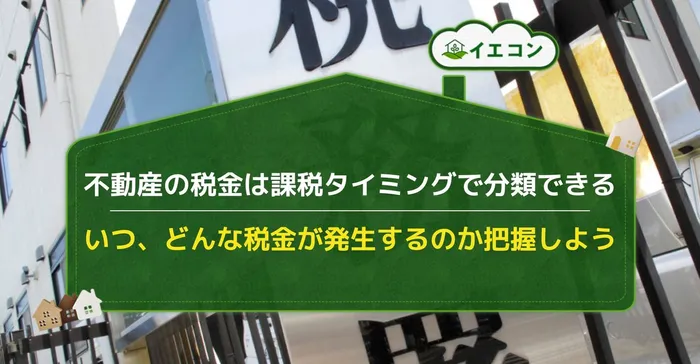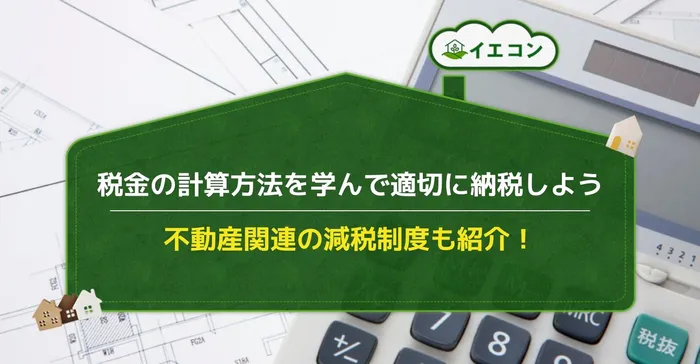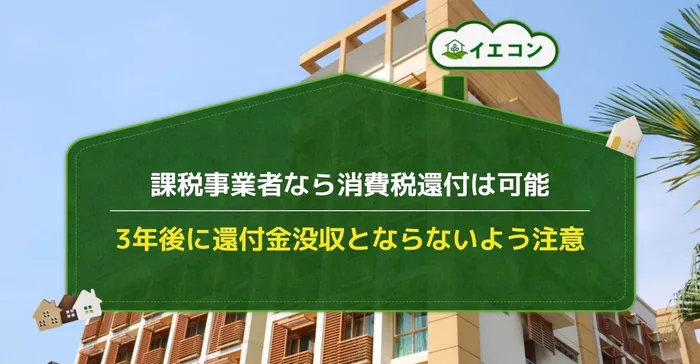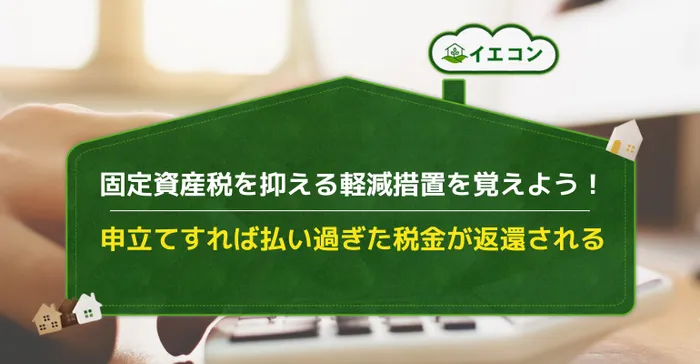不動産投資家にとっては義務である確定申告。
毎年面倒な思いをしている人も多いと思いますが、正確に申告をしないと追加で課税されたり、脱税を疑われて懲役や罰金などの刑罰を科される恐れがあります。
副業で不動産投資をしている場合でも、不動産所得が年間20万円を超すと申告義務があるので注意しましょう。
とはいえ、確定申告は申告方法の選択や帳簿の作成など、複雑な作業が多くあります。手っ取り早く、かつ正確に確定申告をするなら、税理士に相談するのがおすすめです。
また、日常の賃貸管理から「税理士と連携している賃貸管理サービス」を利用すれば、賃貸経営のコンサルティングから節税まで総合的なサポートを受けられるので、ぜひ活用してみましょう。
不動産投資をしている人には確定申告の義務がある

年度末になると、所得に応じた課税額を計算する確定申告。申告書や決算書を用意し、税務署に納税しなければいけません。しかし、確定申告とは「税金を支払う」というだけでなく「還付金を受け取れる」「住民税や所得税の軽減措置が受けられる」というメリットもあります。メリットを上手に活かすためには、申告書の中身を理解することが大切です。
不動産所得には確定申告の義務がある
家賃収入や地代などのような、不動産所得を受け取っている人は、確定申告を行わなければいけません。不動産所得は以下のように算出されます。
では、不動産所得とは具体的にどのような収入を含むのでしょうか。国税庁が指定する不動産所得とは、以下のものを指します。
・不動産上に存在する権利貸し
・船や航空機のレンタル料
このように不動産所得とは、マンションやアパート、駐車場経営などの賃料から得られる収入です。個人や事業者であることを問わず、単に個人で不動産を貸し付けている場合も不動産所得に該当します。例えば、自宅を一時的に他人に貸し付けているケースなども確定申告が必要です。
不動産所得は事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く
ただし、ここで注意しておくべきことがあります。それは、不動産収入のすべてが不動産所得ではないという点です。そもそも「所得」は、国税庁により10種類に区分されており「どのように収入を得たか」「どこから利益がでたのか」によって区分先が異なります。確定申告では、収入の発生源を確定させ、申告書に記載することが必要なのです。
しかし、これらの基準は少し曖昧になっているため、不動産所得か事業所得なのかハッキリ理解できている人は多くはありません。不動産所得の中でも、多くの人が不動産所得と間違ってしまうのは「事業所得」と「譲渡所得」です。なぜ間違う人が多いのか、それぞれ具体例と理由をみていきましょう。
事業所得とは
事業所得とは、事業から生じる利益のことを指します。営利目的でサービスを行った場合、または従業員を雇い継続して所得を増やす行為が事業所得です。事業所得に該当する例は、以下の事業となります。
・漁業
・製造業
・卸売業
・小売業
・サービス業
マンション経営をして得られる賃料は不動産所得に該当しますが、ウィークリーマンション経営は事業所得に該当するケースもあります。ウィークリーマンション経営で、食事を提供したり室内清掃したりするなど、不動産事業のほかにサービスを提供している場合は、事業所得と判断されるので注意しましょう。
譲渡所得とは
譲渡所得とは、不動産を譲渡(売却)したときに発生する所得です。長期的な賃借契約を締結したときには譲渡所得となります。例えば、以下の事業で得た収入は譲渡所得です。
・株式を譲渡したとき
・ゴルフ会員権を譲渡したとき
上記の資産を譲渡して利益を得ると、その収入は譲渡所得です。例えば、企業などに長期間土地を貸し付けて多額の利益を出した場合、実質、資産を譲渡したと判断されるため、不動産所得ではなく譲渡所得になってしまうケースもあります。
サラリーマンでも不動産所得が年間20万円を超すと申告義務が発生する
サラリーマンが副業として不動産収入を得ている、いわゆる「サラリーマン大家」も不動産所得が20万円を超えると申告義務が発生します。会社員は、会社で年末調整してくれているため、基本的に個人としての確定申告はほぼ必要ありませんが、年間で20万円超の不動産所得を得ていた場合は、確定申告が必要です。しかし、家賃収入から経費を差し引き、20万円以下の収入しかなければ、確定申告は不要となります。
ところで、サラリーマン大家は、上手に申告すると以下のような節税効果があるとご存知でしょうか。
・青色申告の10万円控除が利用できる
上記の制度は意外と節税効果があるのです。不動産所得でマイナスの損失があった場合、給料と損失を合算できるという特徴があります。合算した場合は、給料所得を減らし還付金を受けることも可能です。また、青色申告控除のひとつである10万円の控除制度を活用できます。ただし、このお得な控除制度を利用するためには、青色申告が必須です。青色申告の便利なシステムについては、後ほど詳しく解説していきます。
不動産投資に掛かる税金
不動産は、保有・購入・売却すべての行為に税金がかかります。不動産投資においてかかる税金は以下の通りです。
| 状況 | 税金の種類 | 概要 | 納税時期 |
| 保有 | 固定資産税 | 不動産の所有権者にかかる税金 | 毎年(年度末) |
| 都市計画税 | 都市計画区域内の土地・建物にかかる税金 | 毎年(年度末) | |
| 所得税 | 1年間の所得に課税される税金 | 毎年(年度末) | |
| 住民税 | 居住している地域に納める税金 | 毎年(6月頃) | |
| 購入 | 印紙税 | 契約書などの課税文書にかかる税金 | 1回(契約時) |
| 登録免許税 | 所有権など登記した際に納税する | 1回(登記時) | |
| 不動産取得税 | 不動産を購入すると発生する税金 | 1回(登記後半年) | |
| 売却 | 譲渡取得税 | 不動産を売却し利益が出た分にかかる税金
※所得税と住民税のこと |
1回(年度末) |
上記が不動産投資において深くかかわる税金の一覧です。不動産に関する税金には「毎年支払うもの」と「1回きりのもの」とに分かれます。毎年納税義務がある税金のほとんどは、確定申告時に支払うことになるのです。
確定申告期間
確定申告の期間は、毎年2月中旬~3月中旬までの約1カ月間です。2019年度の確定申告期日は、2020年2月17日(月)~3月16日(月)までとなります。よく「15日まで」と断言する人もいますが、正確な日付は毎年異なりますので、詳しくは国税庁のウェブサイトで毎年確認してみましょう。
ちなみに、源泉徴収や予定納税で税金を支払い過ぎたときに行える「還付申告」は、上記の日付以前から受付できます。税務署が混雑する前に還付申告したい人は、ぜひ足を運んでみましょう。
『白色申告』『青色申告』の違い
不動産所得がある人の申告方法は「白色申告」と「青色申告」のいずれかです。この2種類の申告では、記載項目や用紙、適用となる控除制度が異なります。白色と青色の違いを一言でまとめると「特段申請しなければ白色申告になり、節税対策をしたいのであれば申請して青色にできる」ということです。つまり「白色申告<青色申告」と考えてもらうと想像しやすいと思います。
もっと具体的に違いを比較するために、白色申告と青色申告ではどんな特徴やメリットがあるのか、わかりやすく表にまとめました。
| 特徴 | ||
| 白色申告 | ・一般的な申告方法
・青色申告よりも納税額が多い ・青色申告よりも簡易的 |
・事前承認が不要
・複式帳簿が不要 |
| 青色申告 | ・開始するには事前に承認が必要
・不動産所得や事業所得者が対象 ・帳簿の記帳義務が生じる
|
・65万円の特別控除
・10万円の特別控除 ・一定の範囲内で事業者給与を経費にできる ・純損失は翌年3年間の繰り越しが可能(個人) ・欠損金は翌9年間の繰り越し控除が可能(法人) ・在宅ワーカーの場合、自宅の光熱費も経費計上できる |
上記の表をみてわかるように、青色申告は承認や細かい帳簿作成が必要なものの様々な控除制度が利用できます。一方で、白色申告は複雑な記述は不要なものの控除制度がほぼありません。つまり、節税対策をしたいのであれば、少々面倒でも青色申告の承認をとり、控除制度を受けた方がお得になるのです。
必要経費の範囲・対象
不動産投資において節税対策とは、青色申告で必要経費を申告して税金を控除してもらうということがお分かりいただけたと思います。では、不動産経営ではどこからどこまでが必要経費に該当するのでしょうか。こちらも経費計上できるものと、できないものを以下にまとめます。
| 経費計上できるもの | |
| 租税公課 | 固定資産税・不動産取得税・登録免許税・印紙税など |
| 減価償却費 | 建物の購入費を耐用年数で割った額 |
| 修繕費用 | ハウスクリーニング・リフォーム代・設備交換費用など |
| 管理費用 | 賃貸管理会社の業務委託費用など |
| 保険料 | 火災保険・地震保険など |
| 広告宣伝費 | 入居者募集のために使用した宣伝費用 |
| 光熱費 | エントランスや街灯など共有部分に使用した光熱費 |
| 借入利子 | 投資物件を購入したローンの利子 |
| その他 | 管理会社の接待費用や投資セミナーへの交通費など |
| 経費計上できないもの | |
| 譲渡所得に該当するもの | 住民税や所得税など |
| ローンの元金 | 投資物件を購入したローンの元金 |
| 自宅部分の修繕費 | 賃貸兼住宅に住んでいる場合の自宅部分の修繕費用 |
| 生活費 | オーナーの生活費 |
投資物件の運営にかかる費用は、基本的に経費計上ができます。入居者のために捻出した費用は経費、オーナー自身のために使用したものは自己負担になると覚えておきましょう。ちょっとややこしいのが、投資物件を購入するために組んだローンです。利子は経費になりますが、元金は経費計上できません。なぜならば、投資物件を購入するための元金部分は減価償却費として計上しているため、元金も含めるとダブルで計上することになるからです。
赤字計上だった場合
不動産投資で利益が出せず赤字計上した場合、赤字を繰り越すことが可能です。不動産経営で、赤字計上となることは決して珍しくありません。建物を購入した年は経費計上する額が大きいため、赤字になるケースが多いのです。さらに、赤字計上には大きなメリットが隠されていることはご存知でしょうか。不動産投資で利益を上げる人は、この赤字計上を上手に利用しています。
赤字を繰り越すと、以下の2つのメリットがあります。
・前年の所得と相殺して還付を受ける(純損失の繰戻還付)
損失分と利益を相殺すると、前後の年の所得を減らすことができます。まず、純損失の繰越控除の具体例をあげて解説しますので、参考にしてください。
| 純損失の繰越控除 | |
| 1年間 500万円の赤字の場合 | 所得税はかからない |
| 2年目 600万円の黒字の場合 | 100万円(所得額)=600万円(黒字額)-500万円(赤字額) |
このように、前の年の赤字を翌年の黒字と相殺することで、所得を減らすことができます。純損失の繰り越し控除は翌3年間有効になりますので、これにより大きな節税効果が期待できるという仕組みです。一方、純損失の繰戻還付は控除された所得分を計算し直して、差額分を請求できます。前年度で所得税を支払ったけど、翌年に損失を出した場合は「支払った税金を返してくれ」と請求することが可能です。
確定申告をしないと追徴課税が発生する
いくら節税効果があるとはいっても、やはり面倒な確定申告。できることなら、申告せずに投資を続けていきたいと考える人も多いのではないでしょうか。しかし確定申告を怠ると、納税額がかなり増えてしまうこともあるので要注意です。
確定申告期日を過ぎてしまっても、確定申告自体は可能ですが、期限を過ぎると「期限後申告」となり、ペナルティとして追徴課税が発生してしまいます。追徴課税とは、加算税または延滞税のことです。どの程度違反したかによって、ペナルティ額が異なります。
加算税
| 名称 | 概要 | ペナルティ額 |
| 過少申告加算税 | 申告書に記載された納税額が少ない | 本来の税額+10~15%
(正当理由がある場合を除く) |
| 無申告加算税 | 確定申告をしなかった場合 | 本来の税額+10~15%
(正当理由がある場合を除く) |
| 不納付加算税 | 源泉所得税を納めなかった場合 | 本来の税額+10%
(正当理由がある場合を除く) |
| 重加算税 | 納税額を仮装や隠ぺいした場合 | 本来の税額+35~40% |
上記の4つの加算税のうち、重加算税は非常に金額が大きいことが分かります。また、重加算税以外は、正当な理由がある場合はペナルティを受けずに済みますが、重加算税はいかなる理由でも正当性が認められることはありません。「確定申告の提出が間に合わない」「申告し忘れた」のであれば少額なペナルティで済みますが、節税対策と称して不当な申告を行うと、大きな罰則を受けてしまいます。
延滞税
延滞税とは、税金の利息です。滞納すればするほどペナルティ額が増えていきます。延滞税の計算額は、国税庁のウェブサイトに記載されており、計算式は以下の通りです。
確定申告時に納付すべきだった税額に延滞料と遅延日数をかけ、365日で割ります。延滞税の割合は、「年7.3%」か「特例基準割合+1%」のいずれか低い方で計算されます。滞納期間が長くなればなるほど延滞税も増えていき、最大で14.6%の延滞税となるため、早めに申告しておきましょう。
申告書を作成・提出するまでの流れを解説

ここまで、確定申告のための知識について紹介してきましたが、ここからは申告書の作成から提出するまでの流れについてみていきましょう。確定申告書の作成から提出までの流れは、以下の7ステップです。書類の書き方さえ理解すれば、意外と簡単に納税まで進みます。
必要な書類を揃える
申告に必要な書類を揃えましょう。不動産所得を申告するための必要書類は、大きく分けると以下の3種類です。
| 本人確認書類 | 身分証明書
住民票(マイナンバー) |
| 所有不動産証明書 | 登記権利証
不動産売買契約書 |
| 経費関係の書類 | 固定資産税通知書
現金出納帳 管理費用領収書 借入金の支払明細 保険料領収書 |
申告では、不動産投資にどのくらいの経費がかかったか証明する以外にも、控除を受けるための本人確認も行われます。そのため、身分証明書は忘れずに持参していきましょう。
申告書を準備する
必要書類を揃えたら申告書を準備します。申告書はどれも同じ様式ではありません。確定申告の用紙には「A様式」「B様式」とあり、不動産所得の申告に使用するのは「B様式」と呼ばれる書式です。
| 確定申告書A(A様式) | 使用対象者:会社員やアルバイト、パート従業員など
記載項目:給与所得や公的年金、雑所得などに限られる |
| 確定申告書B(B様式) | 使用対象者:誰でも使用可能
記載項目:制限なし |
A様式と呼ばれる確定申告書Aは、使用者が給与所得者で記載できる項目にも制限がある簡易的な申告書です。一方で、B様式と呼ばれる確定申告書Bは、誰でも利用することができ、様々な経費を記載できます。
決算書を準備する
決算書は、投資状況を報告するために作成します。4枚で1部となりますので、該当項目は全て記載しましょう。
| 決算書内訳 | 記載事項 |
| 損益計算書(1〜3枚目 ) | 1年間に発生した収益(家賃収入など)
1年間に支払った経費(減価償却や修繕費など) 従業員がいる場合の賃金 利子の内訳 |
| 貸借対照表(4枚目 ) | 資産や負債の残高 |
簡単に説明すると「どれくらいの収益があり、どの程度の経費を支払ったのか」をまとめて記載する用紙になります。日々帳簿を作成しているのであれば、書き写せばそのまま提出可能です。ちなみに「付表の添付は必要か?」という質問がみられますが、付表は相続時に必要な書類です。被相続人の職業や経済状況などを記載する書類であるため「今回の申告は相続とは関係ない」「相続人がひとりしかいない」という状況のときには、作成は不要です。
申告書を作成する
必要書類を準備したら、いよいよ申告書を作成していきましょう。申告書の作成方法は、以下の4つの方法があります。
・国税庁のウェブサイト「e-tax」で作成し電子申告する
・会計ソフトを使い申告する
・税理士に依頼する
いずれの方法でも申告書を作成できますので、やりやすい方を選んでいきましょう。税務署に出向いても、結局e-taxコーナーに並んで自分で入力していくため、自宅のパソコンから入力するのとさほど変わりはありません。しかし税務署では、税務員に入力方法や記載項目などわからないことを相談することが可能です。申告書の入力に不安がある人は、税務署での作成をおすすめします。
提出する書類を確認する
税務署に提出する必要書類を、再確認していきましょう。ここまで紹介してきた書類を一覧にしてまとめました。
・住民票(マイナンバー)
・登記権利証
・不動産売買契約書
・固定資産税通知書
・現金出納帳
・管理費用領収書
・借入金の支払明細
・保険料領収書
・確定申告書B
・決算書
たまに、提出書類に記載している内容が前年度のものだったり、別の不動産の内容だったりすることがあります。慌てずに確認してください。ちなみに、控えが欲しい人は自分でコピーをとる必要があります。税務署ではコピーをとってくれませんので、税務署でコピー機を借りるか自宅でプリントアウトしておきましょう。
申告書を提出する
申告書の提出方法は、2通りです。
・国税庁のウェブサイト「e-tax」でデータを送信する
税務署に提出する場合は、年度末の2月中旬~3月中旬の確定申告期限内に申告書と必要書類を管轄の税務署に持っていきます。e-taxから申告する人は、書類の提出は必要ありません。代わりに、e-taxに必要項目を入力すること、税務署から内容確認があった場合は、5年間提出に応じることが義務付けられています。
納税
申告書を提出したあと、所得の額に応じて納税します。納税方法は以下の通りです。
・コンビニで支払う
・振替制度を登録する
・e-taxで支払う(ダイレクト納付)
・ネットバンキングで支払う
・クレジットカードで支払う
納税は申告期限である3月中旬までです。振替納税を選択した場合は期限内に預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を提出すれば、後日自動で引き落としがかかるシステムです。以上が、確定申告書を提出する流れです。
確定申告時に節税できる方法とやり方

正しく確定申告を行えば、控除制度を利用できたり追加徴税を支払わなくて済んだりするため、節税効果があると解説してきました。
「節税対策はしたいけど、何をすればいいのかわからない」という人は、「間違えずにきちんと申告する」という方法で十分な節税効果は得られるでしょう。しかし「この他に税金を安くする方法はないのか」という人のために、もう少し節税できる方法とやり方を下記にまとめました。さらにワンランク上の節税対策の知識を学びたい人は、こちらも併せて参考にしてください。
法人化する
法人化というと「会社設立」「経費がかかる」というイメージを抱く投資家も多いのではないでしょうか。現在、法人税の税率が引き下げられているため、法人を設立するメリットが高まってきているのです。そこで、不動産投資で法人化するメリットとデメリットを以下の表にまとめました。
| 法人化のメリット | 法人化のデメリット |
| 所得が増えても税率が変わらない
所得を分散できる 譲渡所得税が一定 計上できる経費が増える |
青色申告65万円特別控除が利用できない
利益分を勝手に使用できない 設立費用に30万円程度が必要 |
上記の表をみてわかるように、法人化の最大のメリットは税金が安くなるという点です。収益が増えても所得税率は変わらないうえ、譲渡所得税も一定なため短期のキャピタルゲインを実現させたい人に有利となります。
しかし、法人化は青色申告65万円制度や投資で得た収益を勝手に使えないというデメリットもあるため注意しなければいけません。法人組織で得た収益は、会社のものとなり社長が勝手に使うことができないのです。法人化にして得た収益は役員報酬という形で振り分けた後で、経営者の報酬を決めていく必要があります。また、サラリーマン大家の場合は本業の規定で副業を禁止しているかどうか確認しなければいけません。
法人するかどうか見極めるポイントは「投資物件をどのように運営するか」「会社が兼業を許可しているか」などです。出口戦略のことまで考え、個人所有がいいのか法人所有がいいのか考えていきましょう。
減価償却費を計算する
経費計上の項目でも少し触れましたが、長期間に渡って減価償却費を計上することで節税効果が得られます。減価償却は、建物の購入費用を耐用年数で割り長期間に渡って経費計上できる便利な会計処理方法です。長期間経費計上できるため、節税対策に繋がることになります。
ただし、減価償却費の要である耐用年数は「構造」「用途」「建材」によって細かく定められていますので、事前に確認することが重要です。減価償却費のための耐用年数は、国税庁の確定申告作成コーナーにて細かく記載されているので、確認してみましょう。国税庁で指定されている耐用年数の一例を以下に記載します。
| 構造と用途 | 耐用年数 | |
| 木造 | 事務所用 | 24年 |
| 住居用 | 22年 | |
| 鉄筋 | 事務所用 | 50年 |
| 住居用 | 47年 | |
| レンガ | 事務所用 | 41年 |
| 住居用 | 38年 | |
このように、構造や用途によって建物の耐用年数が異なります。そのため投資物件を選ぶときは、建物の価格だけでなく「減価償却がどれだけとれるのか」という点にも注目していきましょう。
固定資産税が減税できないか調べる
投資物件を保有すると、毎年かかる固定資産税。固定資産税は、建物と土地それぞれに課税され、評価の高い不動産は納税額が高く、反対に評価の低い不動産は固定資産税が少なくなるという仕組みです。固定資産税は以下の式で、算出されます。
評価額は3年に1度、再評価が行われます。建物の年数が経過すればするほど評価額は減少するため、年々固定資産税は安くなります。そして、この固定資産税には、減税措置があり一定条件を満たせば税率が低くなるのです。固定資産税の減税措置をまとめます。
| 種類 | 構造 | 減税措置 |
| 住宅 | 戸建て住宅 | 税率1.4%を1/2に(3年間) |
| マンション | 税率1.4%を1/2に(5年間) | |
| 土地 | 小規模住宅用地 | 評価額を1/6 |
| 一般住宅用地 | 評価額を1/3 |
要件を満たした場合、住宅用の建物は税率が1/2に減額されます。また土地においては、評価額が1/3~1/6になるため、かなりの節税効果がみられます。
この減税措置を受けるための一定条件は以下の通りです。
・耐震性や耐久性の基準を満たしていること
上記の軽減税率の適用要件は一例です。現在の投資物件が軽減税率の対象になるかどうか、自治体に問い合わせてみてください。
損益通算して減税する
損益通算とは、所得の利益分と損失を相殺する方法です。損失分が出た場合は、利益分から差し引いた額を申告することができます。これを「損益通算の減税」と呼びます。
損益通算に関しては、このページの上部の「赤字計上」の項目にて詳しく解説していますが、もう少し掘り下げて解説していきます。損益通算は、収益が少なく経費が多い場合に節税効果を発揮する減税対策です。しかし、すべての所得に損益通算ができるわけではありません。
| 損益通算できるもの | 損益通算できないもの |
| 不動産所得
事業所得 山林所得 |
別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付け
土地を取得するために要した負債の利子 組合契約に基づいて営まれる事業から生じたもの |
損益通算は、赤字が出た年だけでなく最大で3年間損失を繰り越しできます。数ある所得の中でも、不動産所得は損益通算が認められているため、赤字が出た時は節税対策のチャンスと捉えておきましょう。ただし、適用条件には要注意です。例え損失が出たとしても、生活に必要ではないものと判断された不動産は、損益通算できません。
まとめ
不動産投資で年20万円超の利益をあげている人は、会社員であっても確定申告を行わなければいけません。正しく確定申告を行わないと、節税にならないどころか無駄に納税額を増やしてしまいかねません。
税金や会計の知識は、不動産投資で利益をあげるための強い武器にもなります。面倒でもしっかりと税金のことを理解し、きちんと期間内に確定申告を行いましょう。