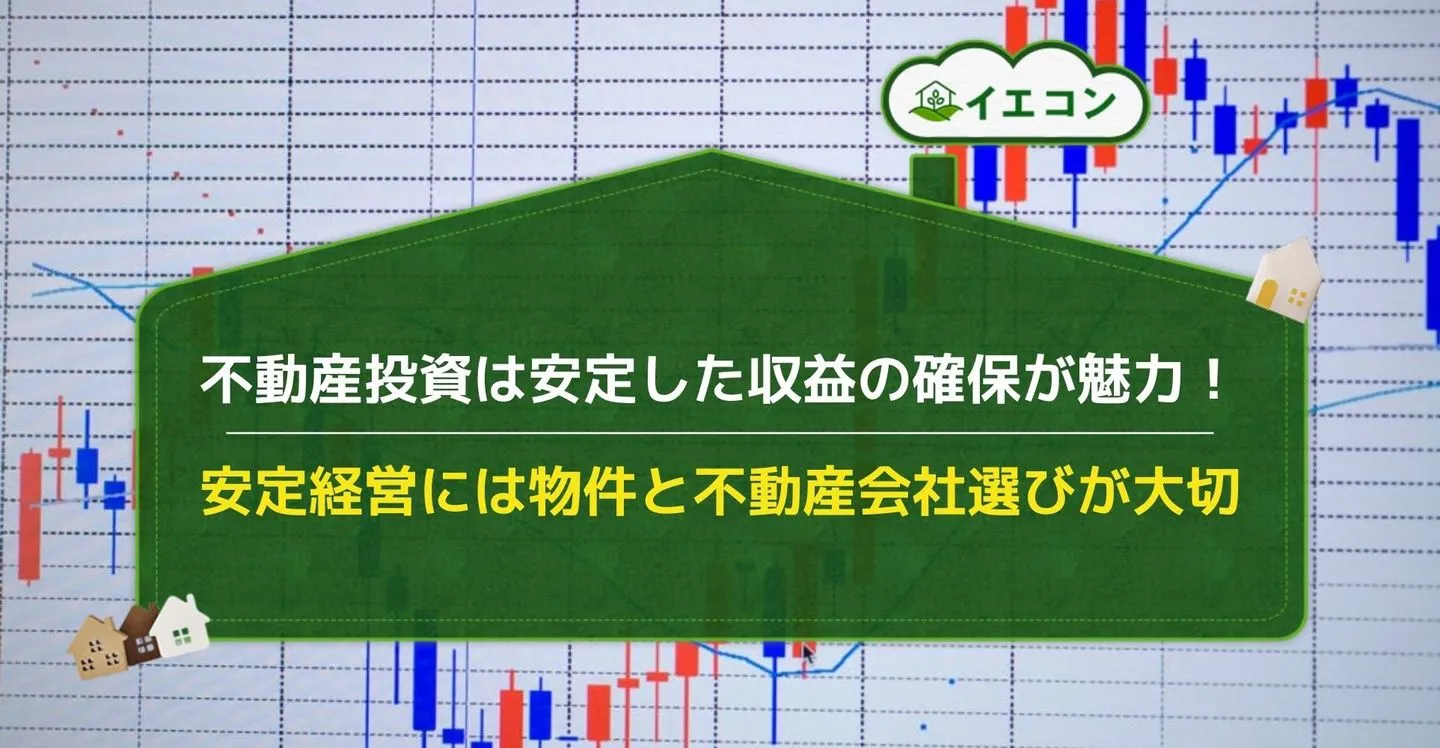資産運用の一環として、不動産投資を検討する人が増えています。株式投資やFXなどと比べて、不動産投資は賃料による安定した収入が期待できます。
しかし、不動産投資も知識が不足していたり、現実的に無理のある投資戦略を取ったりすると、損をしてしまう恐れがあるので注意しましょう。
初心者が不動産投資で成功するためには、不動産投資で利益を得られる仕組みを理解し、メリットとデメリットを把握した上で取り組むことが大切です。
また、物件選びや運用方法について、なんでも相談できる専門家との繋がりを作っておくことも重要となります。
下記のリンクから、あなたに合った不動産投資会社の一括比較を申し込めます。厳選された不動産投資会社に直接相談できるので、ぜひ活用してみましょう。
初心者が最初に知るべき不動産投資の仕組みや基礎知識
なにか物事を新しく始めるなら、最初にある程度の知識を入れておくことが大切です。まずは不動産投資がどういう投資方法なのか、その仕組みと基礎知識を把握しておきましょう。
利益が出る仕組みと基礎知識を知ることで、他の投資方法と比較が可能になり、不動産投資が自分に向いているかわかります。
不動産投資で利益が出る2つの仕組み
不動産だけに限らず、投資で得られる利益は「キャピタルゲイン」と「インカムゲイン」という2種類に分けられます。
この2つの利益を不動産投資にあてはめたものが、次の通りです。
| キャピタルゲイン | 物件の売買によって得られる利益 |
|---|---|
| インカムゲイン | 物件の賃料収入によって得られる利益 |
不動産投資では、基本的にインカムゲインによる収入を狙います。
それぞれの具体的な内容を見ていきましょう。
キャピタルゲインは物件の売買によって得られる利益
キャピタルゲインとは、資産を売買し、その差額によって得られる利益のことです。
具体例としては、以下のような投資の利益がキャピタルゲインに該当します。
- 不動産の売却益
- 株式投資の売却益
- 投資信託の売却益
- FXの売却益
キャピタルゲインは、高額商品ほど得られる利益も高くできる点が特徴です。購入時より10%高く売れるだけでも、元の資産価値が1億円なら利益は1,000万円を得られます。
ただし、不動産投資においてキャピタルゲインを狙うのは難しいといえます。土地は価格変動の少ない資産ですし、建物は経年劣化で資産価値が減少するからです。
物件の所在エリアや間取り、売却時期など条件によっては値上がりすることもありますが、不動産投資で大きなキャピタルゲインは狙いにくいといえるでしょう。
インカムゲインは賃料収入によって得られる利益
インカムゲインとは、資産を保有し続けることによって得られる利益です。
例えば、以下のようなものがインカムゲインに該当します。
- 不動産投資の賃料収入
- 株式投資の配当金
- 投資信託の分配金
- FXのスワップポイント
インカムゲインは、資産を保有し続ける限り継続的に安定した利益を得られることがメリットです。
不動産投資では、不動産を貸し出すことで得られる賃料収入がインカムゲインに該当します。入居者さえ確保できれば、ほとんど何もすることなく収入を得られます。
不動産投資ではインカムゲインを主に狙い、長期スパンでコツコツ稼ぐ手法が基本的な考えになります。
必要資金はケースバイケースで変わる
不動産を購入するにあたって、どれくらいの自己資金を貯めるべきなのか不安に思っている人もいるかと思います。
不動産投資で必要な自己資金の内容は「ローンの頭金」と「不動産購入にかかる諸費用」の2つです。
ローンの頭金は、多く出せるほうが金融機関の審査で有利になりますが、頭金ゼロで借入できる場合もあります。一般的にいわれるのは「購入する物件価格の10~20%」ですが、申込者の年収や勤務先によって変わります。
諸費用については合計で「物件価格の8~10%程度」といわれますが、こちらも状況次第で大きく変わる可能性があるため、あくまで目安程度に考えましょう。
諸費用の具体的な内訳として、次の通りです。
| 種類 | 内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 不動産登記費用 | 登録免許税や司法書士報酬など | 物件評価額の0.4~2%程度と、司法書士報酬として10万円程度 |
| その他税金 | 不動産取得税や印紙税など | 物件評価額の3~4%と、印紙代数万円 |
| ローン事務取扱手数料 | 金融機関へ支払う手数料 | 金融機関による |
| ローン保証料 | ローン保証会社へ支払う保証料 | 金融機関による |
| 火災保険料・地震保険料 | 保険会社に支払う保険料 | 物件による |
| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う手数料 | 物件価格の3~5%程度 |
| 清算金 | 売買した年の固定資産税や管理費などを日割りで売主に支払う清算金 | 物件による |
不動産管理は委託できるので時間がない人も始められる
初心者が不動産投資に対して感じる不安の1つに、物件の管理があります。
入居者選びや家賃回収、クレーム処理に大規模修繕の計画など、不動産管理には多くの手間がかかるものです。
しかし、すべてを自分で管理する必要はなく、管理会社に委託することもできます。委託費として賃料収入の5%程度を支払う必要はありますが、面倒な作業を丸ごと任せられます。
一度物件を購入した後は管理会社に任せることで、収入を得ながら自由な時間を作ることが可能です。
委託する管理会社を選ぶときのポイントは?
管理会社選びは客付けなどに影響するため、不動産投資において非常に重要です。とくに、次のポイントには注目しましょう。
- 管理実績が豊富である
- 担当者との連絡がスムーズにとれる
管理実績が豊富であるということは、それだけ管理のノウハウを持っているということを意味しています。Webサイトなどで過去の管理実績や、不動産投資エリアの実績について調べましょう。
担当者との相性も重要で、連絡がスムーズに取れないとトラブル時に素早い対応を期待できません。問い合わせなどに迅速な対応をしてもらえるかチェックしましょう。
不動産投資を始める5つのメリット
不動産投資の仕組みや基礎知識を理解したものの、いまだに始めるかどうか迷っている人もいるでしょう。
そこで、不動産投資を始めるメリットとして次の5つを紹介します。
- 安定した収入を継続して得られる
- 死亡保険代わりになる
- 所得税や住民税の節税になる
- 相続税の節税になる
- インフレ対策になる
どんなメリットがあるか把握して、不動産投資を検討するための判断材料としましょう。
安定した収入を継続して得られる
不動産投資では、入居者がいるかぎり安定した収入を得られます。賃貸は数年単位で入居するケースが大半なので、一度入居者が見つかれば長期間の収益を見込めるでしょう。
安定した収入があれば、仕事を辞めたときや、入院などで一時的に休職するときでも収入源を確保できます。
老後の私的年金代わりにするという考えもあり、経済的な不安をなくすことが可能です。
死亡保険代わりになる
不動産投資ローンは、団体信用保険を付帯させるのが一般的です。
ローン契約者が死亡や高度障害を負ったときなどに、その時点での残債をすべて支払う保険。
団体信用保険に入っておけば、自分が死んだとき「ローンの残っていない不動産」を遺族へ遺すことができます。
保険料はローン金利に含まれるので、負担を抑えて死亡保険代わりにすることが可能です。
所得税や住民税の節税になる
不動産投資で赤字が発生した場合、給与所得と合算する「損益通算」が可能です。トータルで所得額が減るため、所得税や住民税を節税できます。
「不動産投資で赤字が出たら結局損しているのでは?」と思うかもしれませんが、減価償却費を計上することで、現金の支払いがない経費を計上できます。
減価償却とは、不動産の購入費用を、法律で定められた耐用年数で分割して経費計上する制度のことです。
※実際の減価償却期間は、不動産の種類や築年数などに応じて決まります。
相続税の節税になる
相続税は、現金として相続するより、不動産として相続するほうが課税評価額は低くなります。
現金は相続人が自由に使えるのに対し、不動産は用途が限られるため、その分だけ評価が下がるようになっているのです。
おおむね70~80%の評価額になるため、相続税対策として不動産を購入する人も少なくありません。
インフレ対策になる
インフレとは、物価が上がり現金の価値が下がっている状態です。
社会全体で「前まで100万円で買えた商品が150万円になっている」という状態なので、インフレ時には保有している現金の価値が低くなります。
一方、土地や建物の価値が上がるため、インフレ前から資産を不動産に変えることで資産防衛に繋がります。
近年は世界的にインフレが進んでいるといわれているので、資産の一部を不動産に変えて備えることを検討してみましょう。
不動産投資を始める4つのデメリット
不動産投資のメリットをいくつか紹介しましたが、デメリットについても気になるところだと思います。
どんな投資にもデメリットはあるので、事前にしっかりと把握して対策まで考えておくことが大切です。
ここでは、不動産投資を始めるデメリットとして次の4つを見ていきましょう。
- 空き室リスクがある
- 家賃滞納リスクがある
- 流動性が低い
- 老朽化で資産価値が下落する
空き室リスクがある
不動産投資では、入居者がつかないと収入を得られず、維持費や税金ばかりがかかってしまいます。
入居者がいなくても各種費用は発生するため、賃料収入がなければ本業の給与などから補填しなければいけません。
2~3ヶ月程度ならまだしも、数年単位で入居者が現れない場合、資産を形成するどころか大きく減らす結果になってしまいます。
空き室リスクの低い物件選びのポイント
空き室リスク対策としては、常に賃貸需要の見込める物件を選ぶことが大切です。
- 都市部や人口が増加傾向にある地域
- 駅やバス停などに近い場所
- 大学や工場など人が集まる施設の近く
上記のような条件を満たせば、空き室リスクを下げられるでしょう。
家賃滞納リスクがある
入居者がついても、家賃を滞納されてしまうと賃料収入が減ってしまいます。うっかり払い忘れただけなら問題ありませんが、収入がなくなったなど、支払い自体ができない状態だと回収は困難です。
滞納を理由に立ち退き請求することも可能ですが、訴訟が必要になるなど手間がかかるため、入居者を選ぶ段階で滞納リスクの対策をしておくことが大切です。
すぐに新しい入居者を入れられない分、普通の空き室リスクより厄介といえるでしょう。
家賃滞納リスクを避けるためのポイント
家賃滞納を避けるためには、管理会社に入居審査を厳しくしてもらうのが一番です。また、自分で審査することも検討しましょう。
入居審査では、次の項目を重視すれば家賃滞納リスクを下げられます。
- 入居希望者の職業や年収
- 連帯保証人の職業や年収
- 入居希望者の人柄(態度や言葉遣いなど)
また、家賃保証会社との契約を入居条件にするのも有効です。保証会社がついていれば滞納時の家賃は保証会社から弁済されるため、賃料収入がストップする心配はなくなります。
資産の流動性が低い
不動産の売却には数ヶ月程度、場合によっては1年以上かかるケースもあり、資産の流動性(現金化の容易さ)は低いといえます。
まとまった現金が必要なときや、空き室が続いて処分したいと思ったときでも、売却できずにそのままの状態が続いてしまうかもしれないのです。
また、メリットの解説で「インフレ対策になる」といいましたが、逆にいえばデフレ時には物件の資産価値も下がります。
そうした状況になっても、流動性の低さから換金できずに資産を減らしてしまうというリスクが想定できます。
流動性を重視した物件選びのポイント
同じ不動産でも、物件の種類によって流動性に違いがあります。流動性を重視するなら、それに見合った物件を選ぶことが大切です。
例えば、区分マンションであれば価格帯の低さから購買層も多く、売却しやすいといえるでしょう。
逆に、一棟アパートやビル全体といった高額物件は、購入希望者が限られるため売れにくくなります。
ほかには、先に解説した「空き室リスクの低い物件」であれば、安定した収益が見込めるため流動性も高くなります。
老朽化で資産価値が下落する
建物の場合、年月とともに老朽化が進み、資産価値が下がっていきます。
築年数が古いほど修繕の回数が多くなったり、入居者がつきにくくなったりします。数十万から数百万円の修繕費がかかる場合や、家賃の値下げが必要になる場合もあるでしょう。
「最初の想定より賃料が下がって赤字になってしまう!」という事態を防ぐためには、10年後や20年後のことまで考えて物件を選ぶ必要があるのです。
老朽化による資産価値下落を避けるポイント
老朽化による資産価値の下落を遅らせるためには、定期的な点検とこまめな修繕が大切です。
また、10年程度で大規模な修繕をおこなうことを想定し、あらかじめ修繕費を積み立てておくようにしましょう。
あまりにも老朽化が激しければ、丸ごと建て替えるといったことも検討が必要です。
実際に不動産を購入するまでの手順
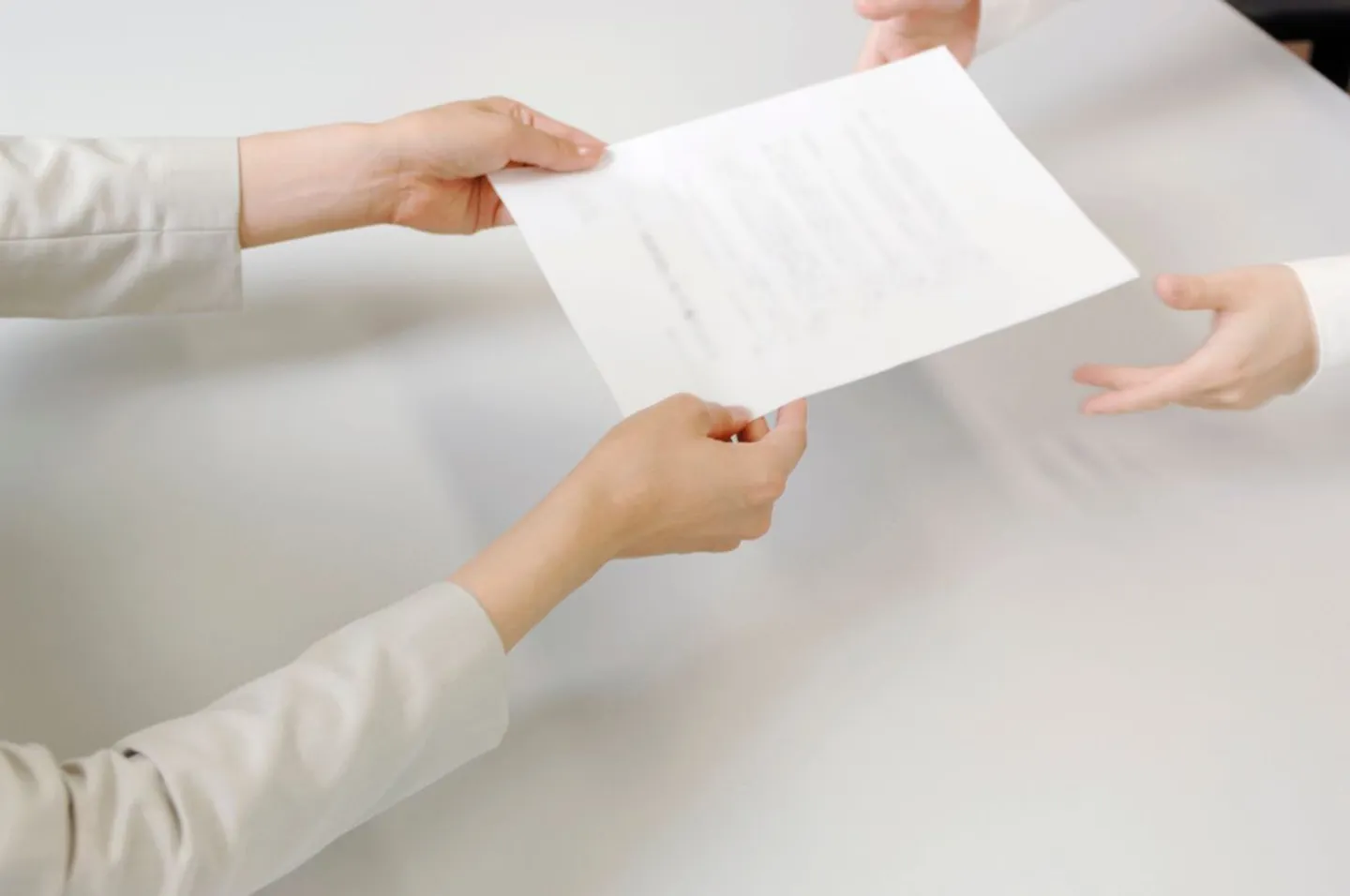
投資用不動産を購入するまでにいくつか手順を踏む必要があるため、スムーズに不動産投資を始めるためにもそれらを事前に把握しておくことが重要です。
投資用不動産を購入するまでの主な手順は以下の4つです。
- 物件探しと買付
- 融資審査を受ける
- 売買契約を締結する
- 管理会社を選定する
1.物件探し
まずは予算やエリアを決めて、投資用物件を探します。投資用物件を探す方法は以下の3つです。
- 不動産ポータルサイトで検索する
- 不動産会社に相談する
- 不動産投資セミナーに参加する
不動産ポータルサイトでの検索は、気になる物件を好きな時に好きなだけ検索できるというメリットがある一方、自分で調べるので得られる情報が乏しいというデメリットがあります。
不動産投資初心者の場合には、自分で検索するのではなく、不動産会社などの専門家を頼ったほうがより良い物件に出会えるでしょう。
そのため、不動産会社に直接相談したり、不動産投資セミナーに参加するのがおすすめです。場合によっては、不動産ポータルサイトに載っていない非公開物件を紹介してもらえる場合もあります。
ただし、詐欺物件を掴まされないよう、相談する不動産会社やセミナーの主催者はしっかりと調べるようにしましょう。
物件は現地視察をするのが失敗しないコツ
気になる物件があっても書類だけで購入せず、実際に現地で視察をおこないましょう。
できれば室内を内見し、使用状況や日当たり、周囲の騒音などを確認しておくべきです。実際に自分が入居者となる場合、入居をためらう要因がないかチェックしておくことをおすすめします。
内見だけでなく、周辺環境を見ておくことも大切です。駅までの距離や坂道の多さ、車の通行量などは入居者にとっても気になるポイントなので、デメリットがないか確認しておきましょう。
2.融資審査を受ける
物件を決めたら、金融機関で融資審査を受けます。不動産会社に物件探しを依頼している場合、連携している金融機関を紹介してもらえるケースもあるでしょう。
紹介がない場合、自分で銀行にアポを取って融資の相談を行わなくてはなりません。
断られることも想定して、1行だけでなくいくつか候補を選んでおき、スムーズに融資を受けられるように融資審査を進めていきましょう。
3.売買契約を締結する
融資を受けられることが決まってから、売買契約を結びます。売主と買主、不動産会社と金融機関の担当者、司法書士が集まって契約を結ぶことが一般的です。
売買契約の締結では、不動産会社から重要事項説明がおこなわれます。細かい売買条件や、後から問題が発覚したときの補償はどうなるのかをしっかりと確認しましょう。
売買条件に問題がなければ、書類にサインをして契約成立となります。
その場で融資が実行され売主への支払いを済まし、司法書士が名義変更の登記申請をおこなうことで不動産を取得できます。
4.管理会社を選定する
従前の管理会社にそのまま物件管理を委託することができれば、物件のことをよく知っているため安心して任せられます。
しかし、元々自己管理の物件である場合やきちんと管理する不動産会社を選びたい場合には、引き渡しまでに管理会社を選定しなければなりません。
不動産投資が成功するかは、入居者募集などを行う管理会社が鍵を握っていると言えるため、時間をかけてしっかり管理会社を選びましょう。
初心者が不動産投資を成功させる3つのコツ

不動産投資の仕組みや物件の選び方を理解するだけでは、不動産投資で安定した利益を得るには不十分です。
不動産投資初心者が不動産投資で安定した利益を得るには、以下の3つのコツに気を付ける必要があります。
- 融資も借金であることを忘れない
- 専門家の相談先を作っておく
- 出口戦略まで考える
1.不動産投資の勉強や情報収集を欠かさない
不動産投資は、条件を満たしていれば銀行から融資を受けながら始められるため、自己資金が少なくても問題なく始められます。
しかし、融資を受けるということは、自分の所持金が増えたというわけではなく、借金であるということを忘れてはなりません。
先述した通り、空き室などで家賃収入が得られない場合には、貯金を崩すもしくは給与所得から返済しなければならないということを覚えておきましょう。
2.専門家の相談先を作っておく
不動産投資は、物件の管理だけでなく権利関係の把握や税金の計算など、多くの作業が発生します。
ときには法律の専門的な知識が必要な場合もあるので、トラブルがあったときや疑問があるときの相談先を作っておきましょう。
すでに解説した通り、管理会社に委託すれば作業の大部分を任せられるので、初心者はとくに活用しましょう。
また、弁護士や司法書士、税理士など、不動産に詳しい士業の事務所を調べておくことで、トラブル時に迷いなく相談することができます。
3.出口戦略まで考える
最終的に不動産をどうしたいのかも、あらかじめ決めておくことが大切です。
売却する予定があるなら、いつまでなら資産価値を下げずに売却できるか予測し、売却活動をいつから始めるか考えておく必要があります。
また、家族に相続させたいなら、だれにどの物件を相続させるのか決めておいたり、相続税を抑える方法はないか税理士に相談することも考えておきましょう。
まとめ
この記事では、不動産投資の仕組みや不動産投資を始めるメリット・デメリット、物件の選び方について解説しました。
不動産投資は継続的に安定した賃料収入を期待できますが、物件選びを間違ってしまうとローン返済だけが残ることになるので注意が必要です。
また、どのような投資用物件を選ぶかだけでなく、管理を委託する不動産会社(賃貸管理会社)選びも重要となります。
不動産投資は「不動産を購入すれば終わり」というわけではなく、継続的な運用が重要となります。不動産投資で失敗しないためにも、専門家のアドバイスを聞きながら運用をおこないましょう。