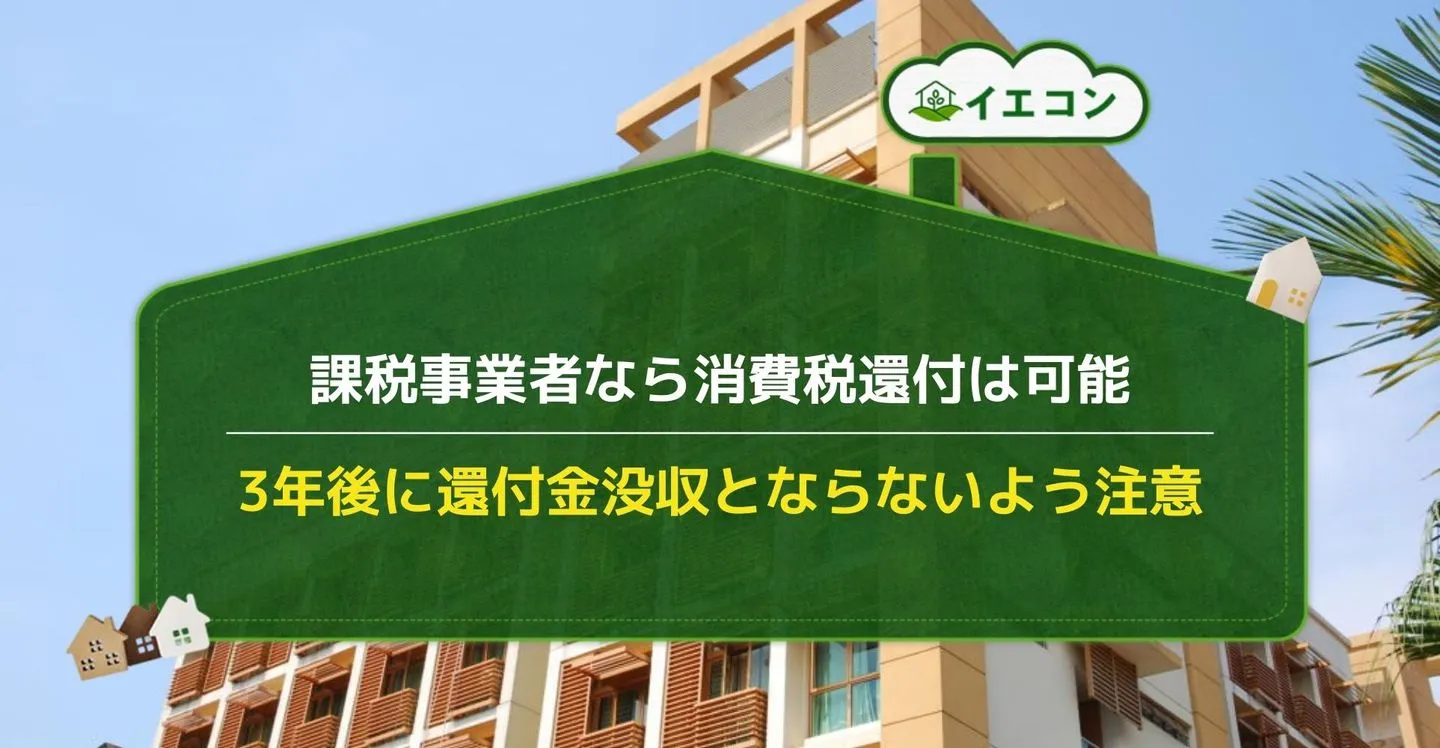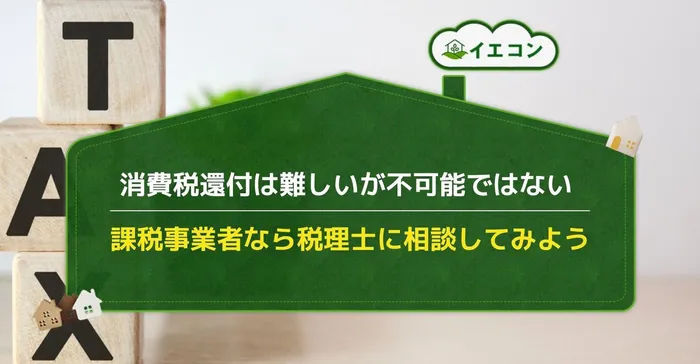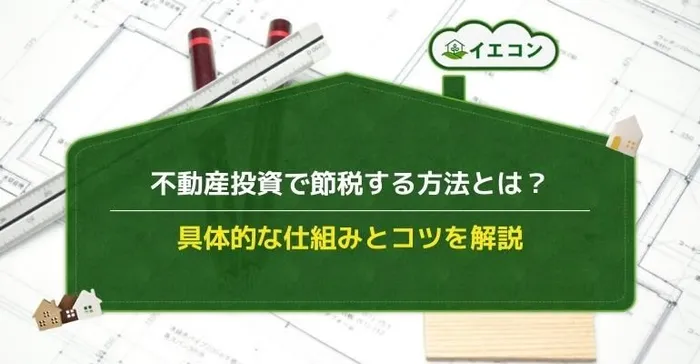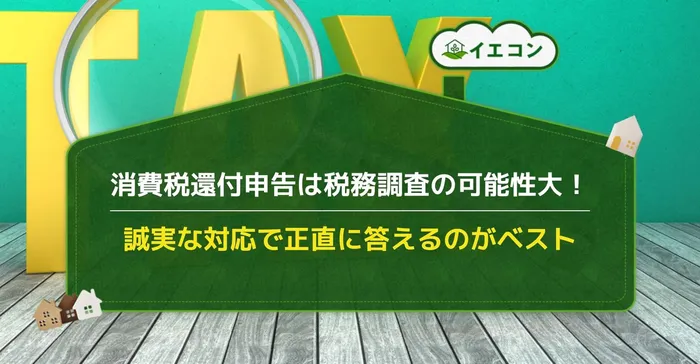ひと頃より難しくなったとは言え、現在でも不動産の消費税還付は可能です。不動産が法人の所有になっていれば、消費税還付の可能性はさらに高まります。
ここでは消費税還付の具体的な方法に加え、法人所有の不動産にしかないメリットについてもご紹介します。
課税事業者になると、不動産の消費税還付が可能になる

消費税還付を受けるためには、まず課税事業者になっていなければなりません。課税事業者とは、消費税を納める義務を負う事業者のことです。消費税という税金は、課税事業者が消費者から一時的に預かり、その後税務署へ納付するものです。課税事業者には、消費者から預かった消費税から、仕入れ先などに対して支払った消費税を差し引いて納めることが許可されています。そのため、預かった消費税よりも支払った消費税の方が高額であるなら、多く支払った消費税は還付してもらえます。これが消費税還付の基本的な仕組みです。
商品代金が数千万、数億円と巨額になる不動産取引においては、支払う消費税の金額も高額になります。ですから不動産の消費税還付について理解しておくことは、キャッシュフローにゆとりを持たせるためにも非常に重要です。しかし、入居者が支払う家賃には消費税が含まれていません。そのため不動産における家賃収入は非課税であり、売上のすべてが家賃収入の場合には課税事業者になっていたとしても消費税の申告・納税の義務は発生しません。納税義務がないということは、還付も受けることができないということです。この点をクリアするためには、いくらか工夫を凝らす必要があります。具体的にどうしたら良いのかについては、後半で詳しく解説します。
今後の消費税還付は、個人より法人が有利
消費税還付に関連する税制改正は度々行われてきましたが、平成28年の税制改正後は今までになく消費税還付のハードルが高くなっています。特に個人の不動産投資家にとっては、必要条件をクリアすることが非常に困難となっています。しかし法人所有の不動産については、個人に比べて消費税還付の条件を達成しやすい状況です。
平成28年の税制改正で大きく変化した点として、個人の不動産投資家が消費税還付を受けようとする場合は、還付申告年を含めた3年間は課税売上割合の推移に注意しつつ、合法的な「課税売上」を上げながら調整計算を適用されないように売上をコントロールしなくてはならなくなりました。
課税売上とは、次の4つの条件をすべて満たしている取引の売上のことです。
2. 事業者が事業として行う取引であること
3. 対価を得て行う取引であること
4. 資産の譲渡、資産の貸付け又は役務の提供であること
商品・製品の販売代金や請負工事代金、サービス料等のほか、機械の賃貸収入や機械・建物等の業務用資産の売却代金なども課税売上に含まれます。他方、消費税の課税対象ではない取引による売上は「非課税売上」と呼ばれます。例えば、受取利息や土地(借地権等を含む)の売却代金、家賃収入や金券類の販売代金、また社会政策的な配慮から課税することが適当でない取引が非課税売上に該当します。ちなみに、保険金や消費税の還付金なども非課税売上です。資産の譲渡・資産の貸付けおよび役務の提供の対価として受け取るものではないためです。
不動産の消費税還付を受ける場合は、家賃収入などの非課税売上を上回る額の合法的な課税売上を3年間に渡って計上しなくてはなりません。これは個人にとっては難しいことです。課税売上は事業者が行う取引によるものでなければならないという規定はありますが、合法的な課税売上を上げるための具体的な方法については何の規定もありません。投資物件の取得後に個人事業を始めれば3年間課税売上を上げることはできるかもしれませんが、会社勤めで副業が制限されている不動産投資家や、年齢や持病で労働のできない不動産投資家にとっては不可能なことでしょう。
仮に個人事業を始められたとしても、消費税還付において合法的と認められるような事業形態を取りつつ、合法的と認められる内容の課税売上を上げることは、それほど簡単なことではありません。消費税法基本通達5-1-1では、個人が事業者と定義される条件について「同種の行為を反復、継続、独立して行う者」としています。特殊な業種でない限り、上記の定義に当てはめる事業形態を取ることはできるかもしれません。しかし、税制改正以後、個人の不動産投資家が消費税還付申告を試みた事例や還付が認められた事例は非常に少なく、個人が消費税還付を受けることは極めて困難になったと言わざるを得ません。
一方、法人の場合は合法的な課税売上を上げることが非常に容易です。法人の行うことは、消費税で規定されている非課税売上以外であればどんな行為であれ基本的には「事業」と見なされますから、合法的な課税売上を上げるという条件は簡単にクリアできます。法人特有のメリットは他にもあります。金融機関から融資を受ける際には、個人よりも法人のほうが信頼性があり、大きな金額の融資が決まりやすくなります。続く部分で詳しく取り上げますが、個人よりも法人の方が経費計上できる項目が豊富であり、認められやすくなります。結果として不動産関連の税金をスマートに節税し、効率の良いキャッシュフローを生み出すことができるということです。
不動産を法人所有にすることの節税メリット

個人ではなく法人で不動産を所有することは、節税面でも大きなメリットをもたらします。以前までは、個人の不動産投資家が自ら不動産管理法人を設立し、物件管理料を自社へ支払うことで節税しようとするスキームが流行しました。しかし、管理料をどれほどの割合に設定するかによっては大幅な節税につながってしまうため、税務調査においてしばしば税務当局と納税義務者の間の衝突原因ともなってきました。
適切な管理料の割合については、税法などを参照しても「これ以下なら安い・これ以上だと高い」などの明確な指針は見つかりません。かなり割合を低くしておけば指摘されないだろうと考えても、不動産管理会社の税務調査では必ずと言って良いほど問題視されます。その点、法人所有の不動産であれば管理料の割合についての規定はありません。多くの不動産所得を法人へ移動させておけば、税務当局に問題視されることなく大幅な節税をすることができます。
不動産を法人所有にしておくことは、相続が発生した時にも役立ちます。あらかじめ、固定資産税に相当する額の3倍程度の地代を支払って「土地の無償返還の届出書」を法人および被相続人の連名で提出しておけば、相続発生時には通常の貸家建付地に近い評価額に抑えることができ、所得税と相続税の同時節税が可能になります。さらに、不動産を購入する法人が一定の条件を満たしていれば、購入時に建物部分について消費税還付を受けることも可能になります。
個人と法人では、税率がどれほど異なるかも考える必要があります。富裕層を中心に、個人への課税は年を追うごとに強化されており、現在では個人への最高税率は55%(所得税45%・住民税10%)です。一方で法人においては、世界経済が不透明化する中で国際競争力を高めるという名目のもと、法人実効税率の引き下げが行われています。平成28年度には29.97%、平成29年度と30年度の標準法人実効税率は29.74%と、当初の予定よりも早めに30%を切っています。法人の優位性は、必要経費の計上の点でも顕著に表れています。
個人と法人が同じ事業を営んだとしても、経費として計上できる項目については次のような差が生じます。
| 経費の内容 | 法人税申告の場合 | 個人の確定申告の場合 |
| 家族を従業員とした場合の給料 | 会社としての内部資料があれば認められる | 事前の届け出が必要 |
| 自宅を事務所として登録し、家賃を自分へ支払う | 可能 | 不可能 |
| 本人と家族への退職金 | 場合によっては全額経費と認められる | 経費とは認められない |
| 自動車購入・維持費用 | 全額経費として認められる | 業務使用と認められる範囲に限り、経費と認められる |
| 家具・電化製品 | 減価償却費として経費が
認められる |
経費とは認められない |
| 水道光熱費 | 全額経費として認められる | 業務使用と認められる範囲に限り、経費と認められる |
| 通信費 | 全額経費として認められる | 業務使用と認められる範囲に限り、経費と認められる |
| 飲食・接待交際費 | 1人あたり5000円以内で
あれば「会議費」として経費が認められる 従業員がいれば、福利厚生費として経費が認められる |
経費とは認められにくい |
| 香典・御祝などの慶弔費 | 業務に関連のある場合は経費と認められる | 経費とは認められにくい |
| 別荘 | 従業員がいれば、保養施設扱いとなり経費として認められる | 経費とは認められない |
| 生命保険料 | 場合によっては全額経費として認められる | 経費とは認められない |
同じ内容の経費でも、個人か法人かによって扱いに大きな差があることがお分かりいただけると思います。ちなみに、法人だけが可能な生命保険料の活用術があります。法人であれば、全損(一部半損)型の保険を積み立てておき、不動産の大規模修繕が必要になったタイミングで解約し、解約返戻金を修繕費に充てるというプランも選択できるようになります。特に中古物件を購入した場合には、前オーナーがどれほど手をかけていたかを知ることができませんから、すぐに修繕が必要になることも考えられます。何年後に大規模修繕を行うかを購入時に決めておき、予定した年に一番解約返戻金が高額になるような保険プランを設定することで、節税しながら安定した資金繰りのもとで不動産投資や経営をすることができます。
経費の点でなぜこれほどの差があるのかについては、税務当局側の認識が大きく影響していると考えられています。個人の経費については、「事業に関係のない個人的な費用を計上しているのではないか」とか、「会社ではないので会計管理もおそらく適当なものだろう」という疑いや先入観が持たれているのが現実です。また、何かあっても個人の方が牽制しやすく、不服を訴えてきたとしてもかわしやすいという当局の思惑もあるでしょう。一方で法人の場合は、仮にもひとつの会社として申告している経費のため、「会社であればそれなりに信頼できるだろう」と受け止められる場合が多くなります。会社の規模や従業員の人数にもよるところがありますが、社会的な信用という強力な武器を手にすることができます。不動産を法人所有にすることは、消費税還付が認められやすいことに加えて、節税面での大きなメリットになります。今後、個人名義で投資用不動産を保有する人は少なくなるかもしれません。
今後、消費税還付を行うための4ステップとポイントについて

平成28年の税制改正以降、従来の消費税還付スキームは通用しなくなっています。今後は、次の4段階のステップによって消費税還付を試みましょう。
1.不動産の取得前に、課税事業者になっておく
冒頭でも述べた通り、まずは消費税を預かる立場にならなければなりません。不動産を取得する前に「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで課税事業者になります。不動産を取得後に提出しても消費税還付は受けられませんので、注意しましょう。
2.不動産の購入・完成月に課税売上を発生させ、非課税売上を発生させない
不動産の家賃収入は非課税売上に該当します。不動産の購入もしくは完成月に家賃収入が発生してしまうことのないよう、賃貸契約のタイミングに気を配りましょう。一方で、不動産の購入もしくは完成月には、自販機収入や駐車場収入、物販収入やコンサル収入などの課税売上をあげておく必要があります。
3.消費税の確定申告書(還付申告書)を提出する
課税事業者になると、消費税の確定申告が必要になります。消費税額および地方消費税額を計算し、納税地や屋号、マイナンバーや氏名などを記入して提出します。確定申告書および還付申告書の提出期限は、所得税などの提出期限とは異なりますので注意しましょう。
4.3年後の還付金没収を回避する
平成28年の税制改正後の消費税還付において、もっとも気を付けなければならない条件です。税制改正後は、消費税還付を受けようとする人全員が調整計算の対象となっています。調整計算が及ぼす影響は、還付金の没収です。還付を受けた初年度の課税売上割合と還付を受けた年を含む3年間の通算課税売上を計算した結果、課税売上割合の変動率が50%以上かつ変動差が5%以上になってしまうと、せっかく還付された消費税が没収されてしまうことになります。いったん消費税還付に成功したとしても、その後3年間は油断できないということです。不動産の家賃収入がある場合は、特に変動率が50%を超えてしまいやすくなります。課税売上割合とのバランスを常に意識し、還付後3年間の通算課税売上を完全にコントロールしましょう。
まとめ
消費税還付のスキームは、税制改正の度に複雑化しています。平成28年の税制改正によって、消費税還付の可能性は完全に閉ざされたと考える人も少なくありません。税理士であっても、消費税還付はもはや不可能に近いと考えて相談にのらない人も多くなっています。
消費税還付を受けるだけでも大変ですが、せっかくの還付金が3年後に没収されないようにしなければ本当の意味での成功とはなりません。少数ながら、税制改正後も消費税還付手続きを請け負っている税理士もいます。その道のプロに任せるなら、後々悔しい思いをしない消費税還付が受けられるでしょう。