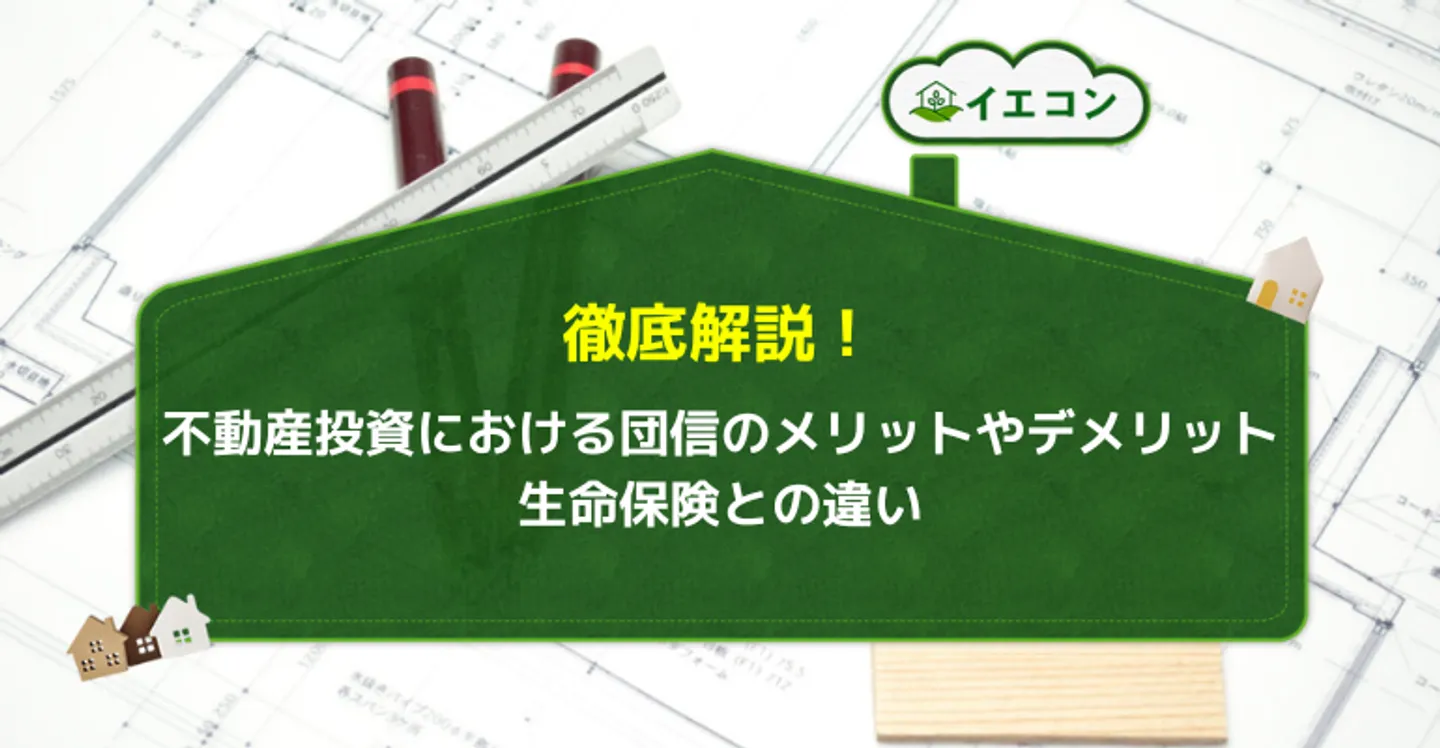不動産投資でローンを組むなら、団信の知識も重要です。なぜなら、団信は本人が死亡若しくは高度障害になったときの保障となる反面、金利が上がり返済額が増えることで不動産投資の収支に大きく影響があるからです。
団信とは、「団体信用生命保険」の略称でローン返済中に死亡若しくは高度障害になったときの保険となります。不動産投資ローンにおいて団信の加入は任意であることが多く、さらに加入すると金利負担が増えるので二の足を踏むケースもあるでしょう。また、団信は万が一のケースを保障するものであり、団信に入らない場合には将来にわたり大きなリスクを背負うことになります。
本記事では、不動産投資で団信に加入するメリットとデメリット、団信に加入する際の注意点や生命保険代わりになるのかについて解説していきます。
最後までお読みいただくと、団信の重要性について深く理解できることでしょう。また、団信に入らない場合の対策についてもわかります。
不動産投資における団信
団信(団体信用生命保険)とは、不動産投資ローンの債務者が返済期間中に死亡若しくは高度障害などの不測の事態に陥ったときに、ローン残債分相当の金額を保障する制度です。一般的に、長期に及ぶローン支払いのリスク低減になるのが団信と言えます。
仮に不動産投資を団信なしで行い、返済期間中に本人が死亡するなどの事態になると、ローン残債があるまま家族に引き継がれるリスクがあります。
また、団信には加入前に審査があります。過去3か月以内に医師の治療や投薬、若しくは過去3年以内に団信の告知事項に該当する病気を患っているとき、手足の欠損や機能障害がある場合には、審査のときに告知しなければなりません。
団信は告知することで加入が難しくなるケースが多いのですが、団信に入るために健康状態を偽ると団信の保険金は下りません。なお、現在では団信の審査に落ちてしまった人向けに、引受緩和型の団信(ワイド団信)を用意している金融機関もあります。
不動産投資で団信の加入は必須なのか
不動産投資で団信の加入は必須ではありません。なぜなら、団信の加入が必要かどうかは金融機関によるからです。もちろん、融資条件を団信への加入必須とする金融機関もあります。
また、団信が任意の場合、加入するかを迷うときもあるでしょう。例えば、以下のようなケースであれば団信加入の必要性は低いと考えられます。
- そもそも借入金が少ない(500万円程度の借入)
- 返済が短期間である(概ね5年以内)
- 生命保険のほうが保障内容が良い
- ローンを引き継ぐ家族がいない
そもそも借入額が少ないとき、団信のメリットがそれほど大きくありません。金利に加算される保険料とのバランスを見ながら加入するかを判断します。
次に、返済期間が短期間の場合も団信のメリットはありません。特に、年齢が若ければ団信に加入する必要性は低いでしょう。
続いて、既に加入する生命保険の保障内容が良いケースです。保障範囲を広げることや保障金額を上げることでカバーできます。
最後は、ローンを引き継ぐ家族がいないときです。一般的に配偶者や子などの法定相続人が全員死亡しているケースとなります。これらは被相続人が高齢者のケースで多くあります。
このように不動産投資での団信加入は状況により加入したほうが良いケースとそうではないケースがあるため、金融機関の担当者等に相談するのが良いでしょう。
不動産投資で団信に加入するメリット
不動産投資で団信に加入すると多くのメリットを享受できます。保険料分の金利を加算することで返済額は増えるものの、長期のリスク低減にはつながります。
不動産投資で団信加入のメリットは以下のとおりです。
- 返済能力がなくなった際のリスクが減少する
- 遺族にローンを残さないで済む
- 不動産投資に対しての家族の理解を得やすくなる
- 遺族に収益物件を残せる
- 他の保険の見直しのきっかけになる
- 保険金に所得税の納税義務がない
- 連帯保証人なしでローンが組める
返済能力がなくなった際のリスクが減少する
団信に加入すると返済能力がなくなった際のリスクが減少します。
通常の団信では、ローン契約者が返済期間中に死亡した場合、特約付きの団信では高度障害やガン、脳卒中や事故などで就業が難しくなったケースでも保険金が支払われます。
つまり、返済期間中に必ずしも健康でいられるとは限りません。就業不能などにより返済能力がなくなったときのリスクに備えて、団信への加入がおすすめです。
遺族にローンを残さないで済む
団信に加入すると遺族にローンを残さずに済みます。
ローン契約者が死亡しても、団信に加入していればローン残債を保険会社が全額支払うので遺族にローンが移行することはありません。
本人が万が一死亡したとしても、その後無借金の収益物件を家族に残すことができるので安心です。
不動産投資に対しての家族の理解を得やすくなる
団信に加入すると、不動産投資に対する家族の理解を得やすくなります。
本人が死亡や高度障害になった際にローンがなくなるので、遺された家族にリスクはありません。ローンがない投資物件であれば、相続後の売却もしやすくなるのもメリットと言えます。
遺族に収益物件を残せる
団信に加入することで、遺族に収益物件を残せます。
遺族はローンがない収益物件を相続できるので、入居率が安定している限り高い収益を得られます。また、前述で紹介したとおりに収益物件を売却して現金を得られます。
ローンがない収益物件を残せることは、遺族にとってメリットと言えるでしょう。
他の保険の見直しのきっかけになる
団信に入ることで、他の保険商品の見直しをするきっかけになります。
団信は、ローン契約者の死亡や高度障害を保障する生命保険の一種です。加入中の生命保険の内容と重複することがあります。ローンを組んで住宅を購入する際は、特に生命保険の見直しがおすすめです。
保険金に所得税の納税義務がない
団信においては、保険金に所得税の納税義務がありません。
生命保険の場合、満期返戻金などで得られた保険金は一時所得として所得税が課税されます。一方で、団信では所得税は課税されません。団信の実行によりローンがない不動産を受け取る人には経済的利益が発生しています。これを一般的に、債務免除益と言っています。
この債務免除益には、所得税の課税義務がないため、団信の保険金に所得税がかからないことになります。
参考元:国税庁 団体信用保険にかかる課税上の取扱いについて
連帯保証人なしでローンが組める
最後に団信へ加入すると、連帯保証人なしでもローンを組めます。
ローン返済中に不慮の事故や病気などで死亡した場合、ローン残債は保険料で清算されます。よって、連帯保証人は不要なので、連帯保証人なしでローンが組めます。
なお、ローンを組む際に収入金額が足らないケースは、団信に加入しても連帯保証人(ペアローン若しくは収入合算者)が必要です。
不動産投資で団信に加入するデメリット
団信への加入はメリットばかりではなく、デメリットもあります。不動産投資で団信に加入するデメリットは、以下に挙げたとおりです。
- ローン金利が上がる
- 基本的に解約できない
- 途中で契約内容を変更できない
- 生命保険料控除がない
ローン金利が上がる
団信に加入すると、ローン金利が上がり月々の返済が増えます。
不動産投資ローンでは団信が任意のケースが多く、通常金利に加算されるケースが大半です。団信の保険料は商品や加入者により異なりますが、年0.1%〜0.3%程度の金利が上乗せされます。
また、団信加入が必須で保険料が無料と謳っている場合でも、保険料は金利に含まれています(通常金利0.2%相当が保険料とされる)。
不動産投資ローンは、そもそも金利設定が高い商品です。仮に数千万円の多額の資金借入をする場合には、金利が0.1%〜0.3%上がるだけでも返済額はかなり上がります。
下記は借入金額5,000万円、返済期間30年、金利3%と3.3%の場合の返済シミュレーションです。
| 金利 | 月々の返済額 | 年間の返済額 |
|---|---|---|
| 3% | 210,802円 | 2,529,624円 |
| 3.3% | 218,977円 | 2,627,724円 |
※ボーナス返済なし
これにより、利回りの悪化や毎月の収支が赤字に陥ることも懸念されます。
よって、団信に加入するとローン金利が上がり返済額が増えるので、団信加入に否定的な投資家もいます。
基本的に解約できない
団信は、基本的に解約ができません。
団信が終わるのは、ローン完済したときや保障期間が終了したとき、死亡や高度障害などで団信を適用したときです。「団信、やっぱり必要ない」「金利の見直しをしたい」と思っても、保険料分の金利は上乗せされ続けます。借入金額が少なく返済期間が短いなど、健康リスクが低いケースでは、団信への加入は慎重に判断するのが良いでしょう。
途中で契約内容を変更できない
団信は、一度加入すると途中で補償内容の変更もできません。
例えば、通常団信を選択してローン実行を受けたあとに、疾病保障付など特約型の団信に変更はできないということです。仮に団信をどうしても変更したいのであれば、ローン自体の借り換えとなります。
よって、団信加入時は途中で契約内容を変更できないことを踏まえて商品を選択します。
生命保険料控除がない
団信の保険料は、生命保険料控除の対象にはなりません。
団信は、金融機関が保険会社に保険料を支払う形式です。ローンを借入れしている本人は保険の直接契約者ではないため、団信の保険料は年末調整時の生命保険料控除の対象になることはありません。
団信(団体信用生命保険)とは
団信とは、団体信用生命保険の略称です。ローン返済中に債務者(ローン契約者の本人)が死亡したケースや、高度障害状態(必ず保険金が支払われるとは限らない)になったときにローン残債相当の金額が弁済される生命保険の一種となります。
マイホーム用の住宅ローンを組む際には、フラット35を除き団信加入が融資条件となっておりますが、不動産投資ローンでも団信への加入ができます。
なお、不動産投資ローンでも一部金融機関では団信加入を必須としているところや、加入を勧める金融機関があります。
なお、団信は過去3か月以内の投薬や診察を受けた人など健康状態が悪い人、過去3年以内に告知事項に該当する病気を患っている場合に加入できないケースがあります。健康状態に不安がある人は、ローンの仮審査時に先行して団信の審査も受けることがおすすめです。
団信の仕組み
ここでは、団信の仕組みについて理解していきましょう。下記は、団体信用生命保険の仕組みを簡単に図でまとめたものです。
団信は、債務者が返済期間内に死亡または所定の高度障害になった際に、金融機関が加入する保険会社からローン残債相当額の保険金が支払われる仕組みになります。よって、団信に加入すると遺族がローン返済義務を負うリスクが低減されます。
また、団信は住宅ローンを組む債務者が被保険者、生命保険会社が金融機関と保険契約を行います。加入には被保険者(債務者)の健康状態が所定の条件を満たしていることが必要です。過去の病歴や健康状態によっては加入できないケースもあります。
なお、団信加入が任意の金融機関であれば融資自体に影響はありませんが、本人やその家族(法定相続人)は、団信に加入できないことでリスクを負うことになります。
団信の保険料は金利に含まれる
団信の保険料は、金利に含まれるケースが大半です。
団信の保険料が無料と謳っている場合でも、保険料は金利に組み込まれています。およそ金利の0.2%分が保険料です。
また、死亡や高度障害以外に保険の適用範囲を広げる場合には、特約付き団信の選択もできますが年0.2%〜0.3%ほどの金利がさらに上乗せされます。
団信加入が任意の金融機関の場合には、団信加入で保険料相当分の金利の上乗せとなります。
団信の種類や保証範囲
団信は、通常の団信の他にどのような種類があるのでしょうか?また、通常の団信の保障範囲についても改めて熟知しておきたいところです。
また、特約付き団信を選ぶことで保障範囲は広がりますが、金利が上乗せとなるので利回りや返済額と月々の収支とのバランスも気になります。債務者(ローン契約者)本人の健康状態や年齢などを鑑みて、どの団信に加入するかを判断していきます。
基本的な団信
基本的な団信(通常の団信)は、債務者(ローン契約者)が死亡または高度障害で就業不能状態などに陥ったときに保険料が支払われます。
なお、高度障害とは、病気やケガなどが原因で身体機能が重度に低下している状態を言います。例えば、住宅金融支援機構では、以下8つの状態を高度障害と認定しています。
-
- 1、両眼の視力を全く永久に失ったもの
-
- 2、言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
-
- 3、中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
-
- 4、胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
-
- 5、両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
-
- 6、両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
-
- 7、1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 8、1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
引用元:住宅金融支援機構 「債務弁済される場合、債務弁済されない場合」
以上を見ると高度障害を言い換えると、就業が難しく相当な重度の障害状態です。
また、基本的な団信では三大疾病や事故で負ったケガなどは保障範囲外です。将来的にガンや心筋梗塞などの病気になるリスクをカバーするには、特約付きの団信を検討しておきましょう。
三大疾病特約付団体信用生命保険
三大疾病特約付団体信用生命保険とは、債務者(ローン契約者)の「死亡または高度傷害状態」に加えて「三大疾病(ガン・脳卒中・心筋梗塞)」により所定の条件になったときに保険金が下りる特約です。
この保険に加入することで、以下のようなメリットがあります。
- 保障範囲を三大疾病までに広げられる
- 病気を患えば治療に専念できる
- ローン残債がなくなることで家族の生活が守られる
なお、この保険が規定する所定の状態とは、一般的には医師よりガンの診断(診断書が必要)確定がされたときとなります。ただし、返済開始日以前に羅漢したものや返済開始日から90日以内に診断確定した場合は、適用外になるケースもあるので注意します。
また、この保険に加入するとさらに0.2%〜0.25%程度の金利が上乗せされます。返済額は上がるので利用には慎重な判断が必要です。
八大疾病特約付団体信用生命保険
八大疾病特約付団体信用生命保険とは、三大疾病に加えて「糖尿病・高血圧性疾患、肝硬変、慢性腎不全、慢性すい炎」に保障範囲を広げた団信です。
これら8大疾病を患ったときに所定の状態(医師から確定診断を受けたとき)となれば、ローン残債務相当の金銭が補償されます。また金利の上乗せは金融機関により異なりますが、おおよそ基本的な団信の金利に+ 0.3%程度です。
がん診断特約付団体信用生命保険
がん診断特約付団体信用生命保険とは、がんと診断された場合にローン残債が0円になる団信です。基本的な団信の金利に0.1%〜0.3%程度が上乗せされます。
この保険では、上皮内がんや皮膚がんなどは対象外になるケースや過去3年以内にがんの病歴があると加入できないことがあります。
なお、ここまで紹介した特約付き団信の加入年齢は、概ね50歳未満になっているケースが多いので注意します。
ワイド団信
ワイド団信とは、基本的な団信への加入が難しい人向けの団信です。引受緩和型の団信と呼ばれることもあります。
ワイド団信では、通常団信では引き受けが難しい「高血圧・糖尿病・肝機能傷害」、さらに保険会社によっては脳卒中や心筋梗塞などの病歴があっても加入できるケースがあります。金利は、基本的な団信の金利に年0.2%〜0.3%程度の上乗せになるケースが多いです。
なお、ワイド団信は特約という扱いではなく、基本的な団信と保障内容に変わりはありません。健康上の理由から通常団信の加入ができない人は、検討するのが良いでしょう。
団信の加入条件
団信の加入条件は明確に開示されていませんが、債務者(ローン契約者)の状態によっては団信に加入できないことがあります。主な加入条件は、健康状態、年齢、職業です。
各金融機関により加入条件は異なりますが、一般的な事例としてご紹介していきます。
健康状態
団信を申し込む際に、債務者の健康状態は最も重要な要素です。以下に挙げた病名に該当する治療や入院、投薬履歴などがある場合には、加入時の審査が厳しくなる傾向があります。
| 心臓・血圧 | 狭心症・心筋こうそく・心臓弁膜症・先天性心臓病・心筋症・高血圧症・不整脈 |
|---|---|
| 脳・精神・神経 | 脳卒中(脳出血・脳こうそく・くも膜下出血)・脳動脈硬化症・精神病・神経症・てんかん・自律神経失調症・アルコール依存症・うつ病・知的障害・認知症 |
| 肺・気管支 | ぜんそく・慢性気管支炎・肺結核・肺気腫・気管支拡張症 |
| 胃・腸 | 胃かいよう・十二指腸かいよう・かいよう性大腸炎・クローン病 |
| 肝臓・すい臓 | 肝炎(肝炎ウイルス感染を含む)・肝硬変・肝機能障害・すい炎 |
| 腎臓 | 腎炎・ネフローゼ・腎不全 |
| 目 | 緑内障・網膜の病気・角膜の病気 |
| 新生物 | がん・肉腫・白血病・しゅよう・ポリープ |
| その他の病気 | 糖尿病・リウマチ・こうげん病・貧血症・紫斑病 |
| 身体障害状態 | ・身体障害手帳の交付経験か申請中 ・矯正しても左右いずれかの視力が0.2以下 ・聴力、言語、そしゃく機能の障害 ・手、足、指の欠損や機能の障害 ・背骨(脊柱)の変形や障害 |
参考元:新機構団信・新3大疾病付機構団信 ご加入にあたって
団信を申し込む際には、団体信用生命保険制度申込書兼告知書などに現在の健康状態や持病、治療歴や投薬歴などを記載します。過去3か月以内の治療歴や投薬歴有無、3年以内に手術や2週間以上に渡る治療や入院、投薬の有無などです。また、手足や視力などの機能障害の有無も申告します。
つまり、長期間のローン返済を継続できる十分な健康状態であるのかがポイントです。
なお、団信は該当する病気があると必ず団信に加入できないわけではなく、保険会社が現在の状況を鑑みながら総合的に判断します。仮に特定の疾病に該当していたとしても、現在の身体の状態や投薬の量、羅患したときからの治療履歴などにより審査結果は変わります。
年齢
年齢も加入条件の一つです。
一般的に基本的な団信は、65歳〜70歳以下で加入申し込みをして、保証期間終了時の年齢を80歳未満に設定しています。また、特約付きの団信であれば、加入時の年齢が50歳未満のケースが殆どです。
通常団信の加入で35年ローンを組むなら、44歳までに実行できるローンを組み団信に加入します。また、30年ローンなら49歳までです。
なお、団信は健康状態が悪くなると、加入しづらくなります。一般的に40代に突入すると病気を患う確率が高くなるため、20代後半から30代のうちにローンを組むのが理想的です。
職業
一部職業には、団信の加入条件に影響があります。
一般的な会社員や公務員などの職業であれば、職業が加入条件に影響することはありません。一方で、死亡リスクが高い職業については、団信に加入しようと思っても審査に通らない可能性があります。
例えば、自動車やバイクのレーサーや世界最高峰の山々を登る登山家、競技中に接触が多いアイスホッケー選手やラグビー選手、格闘技の選手やサーカス団員、スタントマンなどが該当します。
これらの職業に従事する人は、ローンを組む際の団信加入には注意する必要があります。
団信と生命保険の比較
団信は生命保険代わりに使えると言われますが、本当なのでしょうか?本章では、団体信用生命保険と一般的な生命保険について比較していきましょう。
| 団信 | 生命保険 | |
|---|---|---|
| 保険加入期間 | ローン契約期間内 | 定期または終身保険、年数や年齢、終身など選べる |
| 保険料の支払い | ・住宅ローンの金利に含まれる ・年齢や性別による金利や保険料率の差がない ・掛け捨て型 |
・月や年、一括など支払い方法が様々 ・加入時の年齢が上がると保険料が上がる ・性別による差もある |
| 保険金支払い条件 | 死亡・高度障害・余命6か月の診断 ※その他条件は特約による | 死亡・高度障害 ※その他条件は特約による |
| 保険金の受取り | 保険会社が金融機関に支払う | 被保険者が指定した受取人(配偶者や子)が受領 |
| 保障額 | ローン残高相当 | 自分で保障額を決める |
| 現物資産の必要性 | 不動産 | 不要 |
| 途中解約・途中加入 | 基本的にできない | 途中解約可能 |
| 生命保険料控除 | 対象外 | 対象(新制度の場合は最大4万円) |
保険加入期間
保険加入期間についての比較です。
団信の加入期間は、返済開始日からローンの返済終了日、若しくは被保険者の死亡や高度障害になったときまでになります。一方で生命保険は、定期または終身保険が選択できるので加入期間は自由に選べます。
保険の加入期間については、両者に明確な違いがあります。
保険料の支払い
次に、保険料の支払いについての比較です。
団信の保険料は、ローン金利に含まれるケースが多くなります。
また、実際に保険料の支払いは金融機関が行い、ローン契約者(被保険者)は保険料相当分の費用を金利で負担しています。さらに、年齢や性別による金利や保険料の差はなく、掛け捨て型です。
一方で生命保険の保険料は本人が支払います。支払方法は、毎月、一括年払いなどさまざまです。また、加入する年齢により保険料が上がることや、性別により商品の内容自体が変わります。
保険金支払い条件
最後は保険金の支払い条件の比較ですが、条件はほぼ同一となります。
保険料が支払われるのは、本人の死亡や高度障害になったときです。他、特約で保障された病気を患い医師の診断確定があったときになります。
なお、死亡は病死の他に自殺(ただし保険開始から1年〜2年以内の自殺は適用外)や他殺も適用されます。殺人は保険金の受取人が事件に関わっていないことが条件です。
また、保険開始日前より生じていた障害や疾病を原因とするものは保険の対象外となります。他にも高度障害の状態は細かく規定されています。仮に働けない身体であっても、高度障害の規定に合致していなければ保険金が支払われないケースがあります。
参考元:住宅金融支援機構(高度傷害とは?)
参考元:公益財団法人 生命保険文化センター
保険金の受取り
保険金の受け取り方法の比較です。
団信は保険金が下りると、保険会社が金融機関に対してローン残債分の金額を支払います。ローン契約者が保険料を受け取ることはありません。
一方で生命保険は、予め指定された保険金の受取人に支払われます。よって保険金の受け取り方法は、両者で全く異なります。
保障額
保障額の比較です。
団信が保障する範囲は、ローンの残債額相当になります。ローン残債は毎月減少していくので都度保障額が変わります。
一方で生命保険は、予め選択した商品で自らで保障額を決められます。保障額が多ければ、年間の保険金の支払いが高くなります。
現物資産の必要性
現物資産の必要性です。
団信は住宅ローンに付帯する生命保険であるため、必ず土地や建物などの現物資産が必要となります。つまり、団信のみで加入することはありません。
一方で、生命保険は自らの身体に対する保険であるため、現物資産は不要です。
途中の解約や加入
途中の解約や加入に関する比較です。
団信は、加入後の途中解約はできません。またローン返済開始後の団信途中加入も不可です。一方で、生命保険は途中解約ができることや他の生命保険に入り直すなど、自由に加入や解約ができます。
生命保険料控除
生命保険料控除に関する比較です。
前述でも紹介していますが、団信の保険料は生命保険料控除の対象ではありません。実際に保険料を支払うのが金融機関であるからです。
生命保険は、自らで生命保険料の支払いを行っているため生命保険料控除の対象となります。なお、一般的な生命保険料控除では、最大4万円が所得から控除されます。
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 20,000円超~40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
| 40,000円超~80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
参考元:国税庁 生命保険料控除
団信があっても生命保険が必要なケース
団信が生命保険代わりと言っても、実際団信が生命保険を全てカバーしているわけではありません。つまり、団信があっても生命保険が必要なケースがあります。
特に、団信はローン残債に対する保障となり家族に直接保険金が支払われるわけではないので、以下のようなケースでは生命保険が必要です。
- 家族に保険金を残したい場合
- 家賃収入のみでは家族の生活が困難になることが想定できる場合
- 大規模修繕の費用などを残す場合
収益物件をローン無しで残すことは、将来的に家賃収入や売却で資金が得られることから、残された家族にとっては安心です。
しかし、まとまった資金を予め残したいケースや家賃収入だけでは収入が足りないと思われる場合、収益物件の修繕費用を工面する費用として考える場合には、生命保険が必要となるでしょう。
団信で保険金が支払われる流れ
実際に団信が実行される場合、保険金はどのように支払われるのでしょうか?団信で保険金が支払われる流れは、以下に挙げたとおりです。
- 融資を受ける際に、金融機関が団信に加入する
- 団信の金利を含んだローンの支払いがスタートする
- 返済期間中に死亡、高度障害によって返済能力がなくなる
- 生命保険会社から金融機関に対して保険金の支払いがある
- 金融機関は生命保険会社から支払われた保険金でローンの残債を清算する
団信で保険金が支払われる大まかな流れは、上記に示したとおりです。団信を扱う保険会社は数多くありますが、基本的な流れは同一となります。
なお、ローン返済中の滞納による団信の失効、免責事由に該当する告知義務違反を行った場合には、保険金が支払われることはありません。
不動産投資で団信加入を検討する際の注意点
不動産投資で団信に加入するかは、金利面や返済面、利回りの面から悩むケースは多いでしょう。ここでは、不動産投資で団信加入を検討する際の注意点をご紹介します。
- 支出は許容範囲かを確認する
- ローン返済途中からは加入できない
- 告知義務違反をしない
- 団信で保障されない事態を想定しておく
- 生命保険を見直す
支出は許容範囲か確認する
団信加入時の注意点は、支出が許容範囲かを確認することです。
団信に加入すると、保険料はローン金利として上乗せされます。金利が高くなれば毎月の返済額が増え、賃貸経営の収支にも大きく影響します。
保険料が負担となり、不動産経営が難しくならないか(赤字にならないか若しくは薄利にならないか)を確認しておきます。
ローン返済途中からは加入できない
二つ目の注意点は、ローン返済途中からは加入できないことです。
団信は、ローン返済開始前までに所定の手続きを行い加入するので、物件購入前に団信に加入するかを具体的に決めておきます。 ローン返済開始後に、団信の加入はできないので注意しましょう。
告知義務違反をしない
三つ目は、告知義務違反をしないことです。つまり、告知書に虚偽の内容を記載しないことになります。
生命保険であれば医師の診断書の提出が必要ですが、団信加入時には申込書兼告知書の提出だけのケースが多くなります(金融機関によっては借入金額により診断書の提出が必要なケースもある)。
健康状態が悪く持病がある場合、団信を通すために虚偽の内容を記入してしまうと保険金が支払われないリスクがあるので注意しましょう。
団信の保険金請求時には健康状態や生活環境などの調査があり、申請内容が虚偽と認められれば告知義務違反となります。
団信で保障されない事態を想定しておく
最後は、団信で保障されない事態を想定しておくことです。
通常団信で保障されるのは、返済期間中の死亡と高度障害のみとなります。しかし、それ以前にさまざまな病気で就業不能状態に陥ることはあります。これらを要因に、ローン返済が困難になるケースも長期間であれば十分可能性はあるでしょう。
よって、ガンや心筋梗塞などと診断されたときにも保障される特約型の団信を付けることも検討します。特に、病気を患う可能性が高い40代の人や大病はないものの健康診断の数値が悪い場合には、加入がおすすめです。
なお、特約付き団信をつけたとしても保険会社が指定する所定の状態でなければ、保険金の支払いはありません。また、団信に加入直後によく検討せずに他の生命保険を解約するのも危険です。
団信は生命保険代わりとはいえ、遺族に保険金が支払われる形式ではありません。遺族にまとまった資金を残す意向であれば、団信とは別に就労不能になったときに備えた生命保険の加入を検討しておきます。
生命保険を見直す
団信に加入したら、生命保険の見直しを検討します。
生命保険と団信は、商品によっては一部保障内容が重複する点もあります。重複する保障内容は縮小、縮小して保険金額が下がった分で他の保障内容を拡充するなどを検討してみましょう。
団信に加入したら、併せて生命保険会社の担当者への相談がおすすめです。
団信に入れない場合の対策
団信は、健康状態によっては加入できないケースもあります。
団信に加入できないことで、本人が返済期間中に死亡した場合に遺族にローンを残す事態になり不安です。よって、団信に入れない場合には、リスク回避するための対策が必要となります。
本章では、団信に入れない場合の対策について解説します。
- 不動産経営の継承や売却までの計画を立てる
- 生命保険に加入しておく
- ワイド団信に加入する
不動産経営の継承や売却までの計画を立てる
団信に入れないときの対策として、不動産経営の継承や売却までの計画を予め立てることがあります。
団信に加入せずローン契約者が死亡すると、残された遺族が不動産経営とローン返済を行います。何も予備知識や経験がないままで不動産経営を継承しても、健全な経営ができるはずはありません。
そこで、本人が存命中に相続人に対して不動産経営に関わらせておく方法があります。いつでも経営を引き継ぐ態勢を作るだけでなく、売却する基準や売却の流れも共有しておきましょう。
以上を行うことで、団信に加入せずとも残された家族が急に収益不動産を継承することになっても、対処しやすくなります。
生命保険に加入しておく
団信に入れないときの対策として、生命保険への加入があります。
本人に万が一のことがあっても、生命保険に加入していれば家族は保険料をローン返済に充てられます。また、生命保険であれば通院や入院費など幅広い保障も選べます。
団信に加入ができなければ、死亡時に保険料が支払われる商品や病気による通院なども幅広く保障する生命保険への加入を進めておきます。
ワイド団信に加入する
通常団信に入れないときは、ワイド団信に加入する方法もあります。
ワイド団信は、引受緩和型の団信とも言われます。つまり、持病や過去の病歴等で通常団信に加入できない人向けの団信です。
ワイド団信の審査基準は、通常団信よりも緩く設定されていますが、保険会社により引受基準は異なります。よって、ワイド団信を検討するなら取り扱う金融機関を複数ピックアップし、保険会社が異なることを確認してから保険会社に申し込むのが得策です。
なお、ワイド団信に加入すると、0.2%〜0.3%程度金利の上乗せがあります。ローン返済額が増えるので加入には慎重な判断が必要です。
不動産投資家が団信以外にも入るべき保険
不動産投資家は、団信に加入していれば安心というわけではありません。長期間の不動産経営では、死亡リスク以外にも多くのリスクが存在します。本章では、不動産投資家が入るべき保険を紹介していきます。
- 火災保険に加入する
- 地震保険に加入する
- 家賃保証会社と契約する
例えば、建物が不審火や放火、火の不始末などの要因により火災に遭うリスクを回避するために火災保険に加入しておきます。併せて火災保険加入時にオプションとなる地震保険にも加入します。
火災保険と地震保険はセットで加入すると覚えておきましょう。なお、地震保険は火災保険期間中の加入や地震保険のみの加入はできません。
続いて、家賃滞納に備えて家賃保証会社と契約します。家賃滞納は、不動産経営の根幹を揺るがす事態となります。家賃保証会社と契約することで、万が一の家賃滞納時にも安心です。
まとめ
不動産投資にローンを用いるなら、団信への加入がおすすめです。団信に加入することで金利負担が増えるケースはあるものの、万が一のときに家族に安心して財産を残せます。
また、団信の加入には審査があるため、健康状態が良くないケースでは団信に加入できないこともあります。このようなときには、ワイド団信の検討や他の生命保険に加入するなどの対策が必須です。
不動産投資は長期間行うものであり、その間多くのリスクが考えられます。団信以外にも火災保険の加入や家賃保証会社との契約等、起こりうるリスクに備えて他の保険等にも加入しておくことも、健全な不動産経営を行うコツと言えるでしょう。
「不動産投資における団信のメリットデメリット」に関してよくある質問
団信とは何か?
仮に不動産投資ローンを団信加入せず組むと、返済期間中に本人が死亡若しくは高度障害になると、ローン残債が家族に引き継がれるリスクがあります。
また、団信の加入には審査が必要です。過去3か月以内に医師の治療や投薬、若しくは過去3年以内に団信の告知事項に該当する病気を患っているとき、手足の欠損や機能障害がある場合には、審査のときに告知しなければなりません。
仮に告知義務違反をすると、死亡時に団信が適用されないので注意します。
不動産投資で団信の加入は必須なのか?加入の必要性が低いときとは?
また、団信加入の必要性が低いときは以下のようなケースです。
・そもそも借入金が少ない(500万円程度の借入)
・返済が短期間である(概ね5年以内)
・生命保険のほうが保障内容が良い
・ローンを引き継ぐ家族がいない
不動産投資で団信に加入するメリットとデメリットとは何か?
・返済能力がなくなった際のリスクが減少する
・遺族にローンを残さないで済む
・不動産投資に対しての家族の理解を得やすくなる
・遺族に収益物件を残せる
・他の保険の見直しのきっかけになる
・保険金に所得税の納税義務がない
・連帯保証人なしでローンが組める
一方で、団信加入のデメリット以下に挙げたとおりです。
・ローン金利が上がる
・基本的に解約できない
・途中で契約内容を変更できない
・生命保険料控除がない
団信にはどのような種類があるのか?
・基本的な団信
・三大疾病特約付団体信用生命保険
・八大疾病特約付団体信用生命保険
・がん診断特約付団体信用生命保険
・ワイド団信
基本的な団信以外は、金利の上乗せがあります。疾病特約付団信は、死亡と高度障害(基本的な団信とワイド団信の保障範囲)の他に、該当の病気と医師から診断されたときに適用されます。
不動産投資で団信加入を検討する際の注意点とは何か?
・支出は許容範囲かを確認する
・ローン返済途中からは加入できない
・告知義務違反をしない
・団信で保障されない事態を想定しておく
・生命保険を見直す
詳細は本編にてご紹介しています。