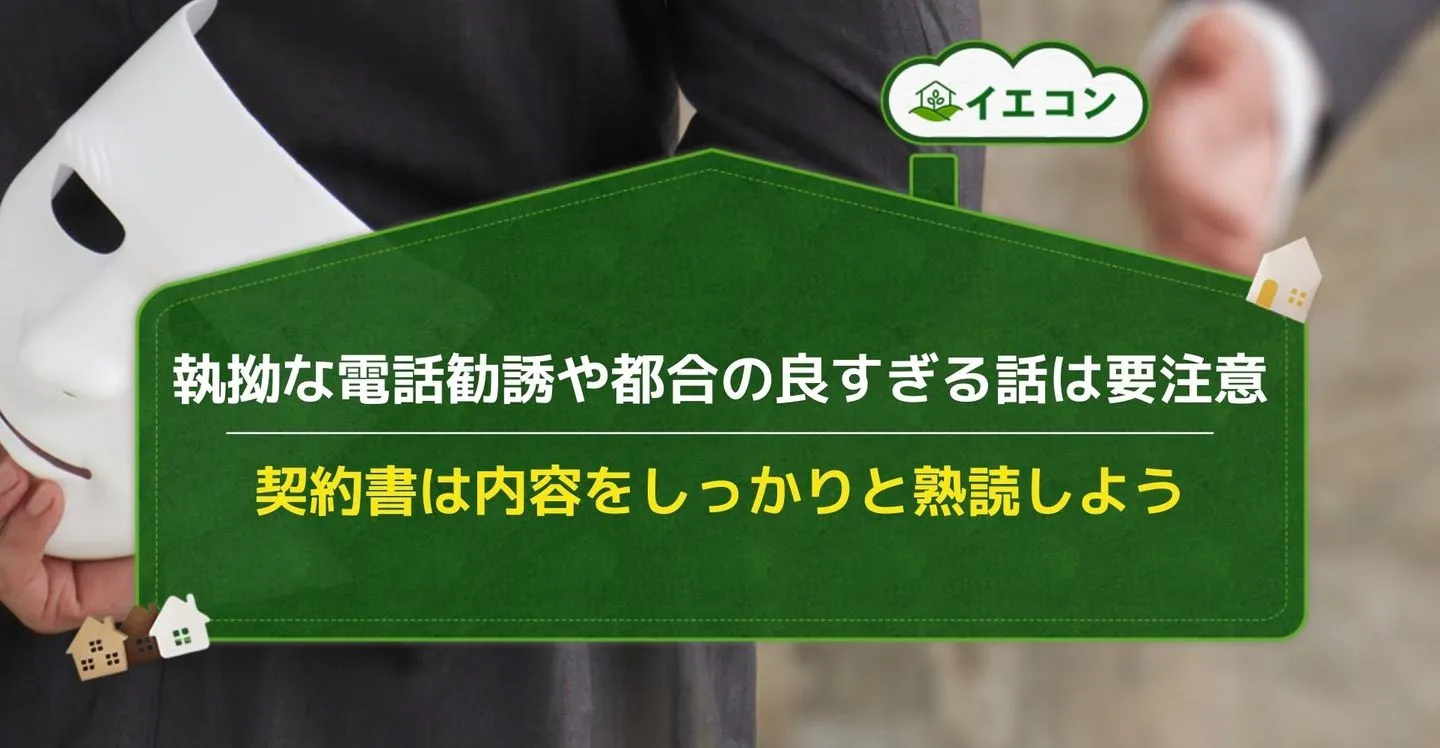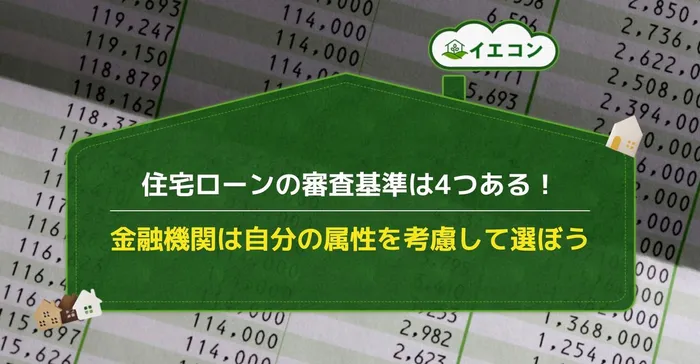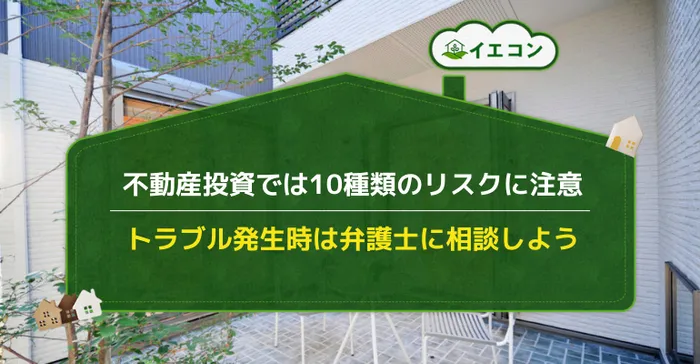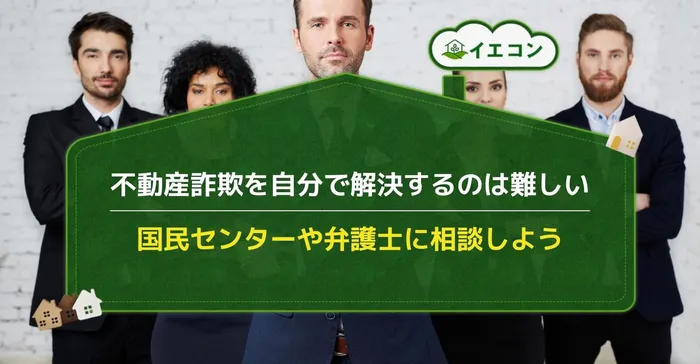副収入や年金代わりの老後資金として、マンション投資を検討する人が増えています。
しかし、マンション投資の人気につけ込んで、詐欺行為または詐欺すれすれの行為をはたらく悪質な業者もいるため注意しましょう。
この記事では、マンション投資で失敗しないために、悪質な業者を見分けるためのポイントや対処方法を解説していきます。
以下のリンクから、信用できる不動産業者へ無料相談もできるので、アドバイスをもらいたい人は利用してみてください。
【悪徳業者が心配な人へ】安心して不動産投資を無料相談できる業者はこちら
悪質業者を見分けるための特徴

まずは、マンション投資における悪質業者の特徴をいくつかご紹介します。
このような場面に遭遇したら、悪質業者と思って警戒するべきです。
- 執拗な電話勧誘をおこなう
- 都合の良すぎる話を持ち掛ける
- マンション投資のリスクに一切触れない
- 手付金の支払いや契約をやたらと急かす
- 強引に新築ワンルームマンションを勧める
- 恋愛感情や婚活に便乗した誘いを持ちかける
執拗な電話勧誘をおこなう
世の中には、本物の掘り出し物といえる優良物件も少数ながら存在しており、その場合は営業担当者も顧客のためを思い、善意から熱心に勧めてくる場合があるでしょう。
それでも、こちらがはっきりと断れば、すぐ見切りをつけて他の顧客に話を持っていくのが普通です。なぜなら、1人の顧客相手に粘らずとも、本当に優良物件ならばすぐ売れるはずだからです。
悪質な業者を見分ける簡単な方法のひとつは、執拗な電話勧誘です。
不動産投資を検討していて資料請求をした人や、すでに不動産投資を始めている人の電話番号を何らかの方法で入手すると、毎日または日に何度も架電し、資料送付や物件内覧を執拗に勧めることがあります。
なぜなら、不動産投資を始めている人は一般人よりも成約見込みが高いとみなされているためです。
ひどい場合は自宅の固定電話や勤務先に昼夜問わず架電し、相手を辟易させることで契約に持ち込もうとして、切ろうとすると、脅迫まがいの言葉で脅すことさえあるでしょう。
電話勧誘がしつこい場合は通報しよう
宅地建物取引業法施行規則第16条では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際した電話による長時間の勧誘、その他の私生活または業務の平穏を害するような方法により相手を困惑させるような行為を禁止しています。
断っているのに何度も執拗に電話してくる業者は宅地建物取引業に違反している悪質業者と考えられるので、勧誘電話に対しては「まったく検討していません」「二度とかけてこないで下さい」といった断固たる態度で応対しましょう。
すでに何度も電話されていて迷惑している場合は「断っているのにしつこく勧誘するのは宅建法違反だとご存知ですよね?電話をやめないならしかるべき措置を取ります。」と伝えて、県土整備局事業管理部建設業課へ通報しましょう。
ただし、以下のような情報がないと、通報してもほとんど意味がないので、必ず保存しておくようにしましょう。
- 相手の会社名
- 担当者名
- 勧誘内容
- 電話があった日時・頻度
- 電話の音声録音
県土整備局事業管理部建設業課に通報すれば、悪質業者に対する指導や勧告をしてくれますが、身の危険を感じるような場合は、すぐ警察に相談しましょう。
都合の良すぎる話を持ち掛ける
マンション投資において、都合の良すぎる話は一度疑ってかかるべきです。
例えば、30年家賃保証、固定金利でしかも低金利なローン、異様に高い利回り、といった好条件過ぎる話です。
- 好条件すぎる家賃保証
- 好条件すぎるローン金利
- 好条件すぎる利回り
好条件すぎる家賃保証
家賃保証というシステム自体は実在しますが、実際は物件の経年劣化に合わせて保証額も下がっていったり、保証を受けるためには年数に応じて手数料が割増になるのが普通で、最悪の場合は保証が一切なくなることもあります。
こうした注意事項について一切説明してくれない場合、何かおかしいと考えて良いでしょう。
好条件すぎるローン金利
不動産投資のためのローンはほとんどが変動金利で、固定金利といっても最初の数年間のみの話で、その後は金利が数倍に膨れ上がる場合もあります。
変動金利型不動産投資ローンの金利はどんなに低くても1%台ですし、そのような低金利で融資をしているのは年収1000万円クラス以上の人を顧客とするメガバンクくらいです。
一般的な金利は2~5%程度であるということを念頭に置き、なぜ固定でなぜ低金利なのかを問いたださなければならないでしょう。
好条件すぎる利回り
マンション投資の物件選びにおいて、利回りも重要な判断材料です。
もちろん利回りが高い物件ほど収益を上げやすいのですが、都心の物件であれば平均して3~5%の実質利回り、郊外の優良物件でも実質利回りは10%に満たないくらいが平均値です。
20〜30%など、相場をかけ離れて異様に高い利回りの場合、いったん立ち止まって冷静に考える必要があります。
マンション投資のリスクに一切触れない
投資にはリスクがつきもので、マンション投資にも数多くのリスクがあります。
- 入居者の家賃滞納
- 事故物件となった場合の原状回復費用
- 建物を維持するための費用
- マイホームのローンに通過しづらい
こうしたリスクの説明が一切無い場合、こちらから問い質してみましょう。
問い質した結果、話をそらしたり「リスクなど無い」と否定するのであれば、怪しい業者と思ったほうが良いでしょう。
入居者の家賃滞納
どんなに入居審査を厳しくしたとしても、家賃滞納の可能性はゼロにはなりません。
一定期間を超えて滞納が続くようなら出て行ってもらうほかありませんし、追い出すための手続きにかかる費用も基本的には家主である投資家の負担となります。
事故物件となった場合の原状回復費用
善良な入居者であっても、事件や事故あるいは突発的な病気によって物件内で死亡し、遺体が長期間発見されない事態になるかもしれません。
世間一般に事故物件と言われる状態になれば、原状回復のための費用は家主持つことになります。
建物を維持するための費用
建物は必ず経年劣化するため、定期的にメンテナンスが必要で、そのための費用も基本的に家主が負担することになります。
さらに、建物の築年数が増すにつれ修繕箇所は増え経費がかさんでいきますが、家賃は値下がりしていくため収入は下がります。
年数を追うごとにキャッシュフローは悪くなるのが普通で、それも計算に入れた綿密な事業計画を練らなければなりません。さらに、不動産を所有する人は毎年、固定資産税と都市計画税という税金を支払う義務があります。不動産の価値が高ければ高いほど税負担は重く、甘く見ることのできない費用です。
マイホームのローンに通過しづらい
マンション投資のためのローンを組むと、マイホームのローンに通るのは難しい点もリスクのひとつです。
投資用物件のローンが邪魔になってマイホームのローンが組めないとなれば、マイホームを楽しみにしていた家族との間で摩擦が生じて、投資そのものがやりづらくなる場合もあります。
手付金の支払いや契約をやたらと急かす
他の詐欺でも共通している点ですが、考える時間を与えないことは人を騙す際の鉄板手法です。
以下のような発言で投資を焦らせる場合、悪質業者の可能性が高いでしょう。
- 「今日中に手付金を払ってくれないなら、あなたよりも属性の良い他の顧客に話を持っていく」
- 「もう何件も内見希望者からの問い合わせが集まっている。会社に無理を言ってあなたのために何とかおさえている状況で、今日決めてくれないなら二度とこんな優良物件は紹介できない」
もちろん、売買にせよ賃貸にせよ不動産の契約が早い者勝ちなのは本当のことで、本当に問い合わせが殺到している優良物件もあり、そのような物件は実際にすぐ買い手が決まります。
しかしそうであれば、購入に向けた具体的なアクションを起こしていない人にわざわざ連絡していることはないはずです。
特に前向きな返事をしていないのに、やたらと急かしてくる場合は、悪質業者かもしれないと考えましょう。
悪質業者の場合、内見時や事業所での面談などでも、その場で契約書に署名捺印をするよう急かされることがあります。
しかし、よく考える時間を取らないままに契約をするようなことは絶対にあってはなりません。
強く押せば言うことを聞く人物と思われれば、圧力はさらに強くなるので、どれだけ急かされても、動揺したり怯んだりしてはいけません。
強引に新築ワンルームマンションを勧める
非婚化や晩婚化、高齢化などに伴い、国内の単身世帯数は年々増加しているため、都心を中心にワンルームマンションのニーズは低下しにくいと考えられています。
しかし、この状況を利用して、経験の浅い投資家に新築ワンルームマンションを勧める悪質業者もいます。
「ニーズがある上に新築の物件なら、利回りも相当高くなりそう」と考えてしまうかもしれませんが、新築ワンルームマンションは、ある程度知識や経験のある人なら決して手を出したがらない投資物件です。
新築ワンルームマンションは駅に近い場所や都心、生活に便利な好立地に建つことが多く、往々にして取得価格が高額になります。
新築であるという強みがあるため、不動産業者も強気の価格設定をしていますが、高額なローンを組んで投資を始めても、最初の入居者が入った時点で中古物件になり、市場価格は20~30%減となります。
しかも、単身者の場合は自分の一存で引越しを決められてしまうため、空室になる可能性も高くなります。
再度募集する時にはもう新築ではなく中古物件なので、新築当初の家賃よりも値下げしなければ入居者は入りにくくなる上、家賃を値下げしてやっと入居者が決まったとしても、税金や毎月かかる維持管理費などの費用は下がりません。
むしろ年数が経てば、維持費用は増えていくため、利益は下がるのに支出は増えていくという状態になります。
空室に困って売却しようとしても、5年程度経てば物件の流通価格は新築時の約70%前後となるため、大きな損失となり、投資失敗となるでしょう。
つまり新築マンションの場合、取得するための費用は高額になるのにその後の収益は下がりやすく、キャッシュフローが非常に悪くなりやすいです。
一方で、利幅の高い新築マンションを販売できれば不動産業者側のうまみは大きいため、何とかして新築後すぐに買い手を付けたいと考えます。
リスクを承知の上で挑むベテラン投資家ならまだしも、初めて不動産投資をおこなう人が新築ワンルームマンションを選ぶのはあまりに無謀なので、強引に新築ワンルームマンションを勧める業者には注意しましょう。
恋愛感情や婚活に便乗した誘いを持ちかける
悪質業者というよりは詐欺師になりますが、近年は婚活サイトやパーティーなどで知り合った異性をターゲットにし、強引にマンション投資の契約をさせるケースも増えています。
ターゲットになりそうな相手を見つけると、好意を持っている素振りを見せてデートに誘い、相手が気を許した頃、以下のようにマンション投資を持ち掛けるのが常套手段です。
- 「二人で余裕のある老後を過ごすための投資」
- 「子どもができたら何かとお金がかかる。結婚する前に準備しておこう」
拒むと執拗に勧めてきたり、突然激怒して怯えさせたりすることもありますが、もちろん、契約が終われば連絡が取れなくなることがほとんどです。
被害にあった人の中には、何かおかしいと感じた瞬間があった人もいますが、それでも騙されてしまったのは「この人を信じたい」や「この人を逃したらもう結婚のチャンスはないかもしれない」という気持ちになり、疑念を押し殺してしまったことが原因と考えられます。
契約後に行方をくらますのは本当の詐欺師のやり方ですが、悪質な業者の中にも似たようなことをする人間がいるのも事実です。
業者の人間自らが、高額の融資が下りそうな属性の高い異性と接触して丸め込み、結婚後に一緒に住むためなどと理由をつけて物件を買わせた後、別れ話をするといった手口です。
人間誰もが持つものである恋愛感情を利用した極めて悪質なこの行為は、老若男女問わず誰もがターゲットにされる可能性があります。
とくに、正社員として大企業に長年勤めている人や、公務員や士業、医療関係者など社会的属性の高い職業に就いている人は、詐欺師や悪質業者から狙われやすいので、他人事と思わず警戒しましょう。
悪質業者と取引しないために注意できること

マンション投資を、1棟目だけで終わらせる人は少なく、経営が順調になってくれば、2棟目3棟目と広げていくのが一般的です。
すると、どうしても、様々な業者と関わりを持つ機会が増えることになるため、悪質業者を避けるための術を身につけておくことが重要です。
ここからは、悪質業者を見分けるためにできることを解説します。
- 業者の所在・担当者の身元を確認する
- 「売買契約書」の内容を熟読する
業者の所在・担当者の身元を確認する
まず、取引しようとしている業者が本当に信頼できる不動産業者かどうかを確認しましょう。
具体的には、名刺やパンフレットなどに記載されている事業所所在地を調べて、本当に会社が存在しているかを確かめましょう。
代表電話番号が、番号変更も簡単で誰でもすぐに取得できる携帯番号や050から始まるIP電話になっているなら要注意です。
一方、固定電話やフリーダイヤルがあれば、信用できる不動産会社である可能性が高いです。
業者の名前をインターネットで検索して、ウェブサイトなどで確認する方法も有効で、悪質業者であれば、何らかの口コミが見つかる可能性もあります。
もし、業者の名前が誰もが知る大手不動産業者の名前だとしても、まずはその大手不動産業者の公式ウェブサイトを調べるのが賢明です。
一時期、大手不動産業者の名前を騙る悪質業者が横行した時期もあったため、業者の名刺やパンフレットに記載されている事業所所在地や電話番号が、大手不動産業の情報と同じであるかを確かめましょう。
免許証番号を信用するべきではない
「不動産業者の信用度は免許証番号の末尾にある( )内の数字が大きければ大きいほど高い」という情報もありますが、これは間違いです。
( )内の数字は、5年に1度行われる免許証更新を何回行っているかを示すもので、宅地建物取引業免許を受けて5年未満なら1、12年目なら3になっているはずです。
しかし、免許証番号は色々なタイミングでリセットされる場合があり、近隣県への業務拡大のため知事免許から国土交通大臣免許に切り替わる場合、以前の数字に関係なく(1)となります。
個人事業として長年不動産業を営んできた業者が法人登録した場合も、(1)にリセットされてしまうため「免許証番号の( )内の数字が1では信用できない」という認識は間違っています。
逆に( )内の数字が大きい業者でも、実績と信頼ある業者とは限らない場合があります。
「免許証番号の数字が大きい業者は信用できる」という誤解がいまだに根強く残っているため、免許証番号の大きい会社を買収する手段は悪質業者が用いる手口のひとつともなっています。
免許証番号の数字は、確かな信用度のバロメーターにはなりませんので、惑わされないように注意しましょう。
担当者の信頼性を確認する方法
マンション投資をする場合は、窓口となる営業担当者が付きますが、営業担当者個人も信用してよい人物かを確かめる必要があります。
話しやすい・相性があうなど人としての部分もある程度は大切ですが、不動産投資についての知識や理解の深さ・的確なアドバイスや忠告ができる人間かどうかが何よりも大切です。
高額のお金をつぎ込むマンション投資において、担当者はパートナーとしての大きな影響力を持っているので、マンション投資が成功するか失敗に終わるかは、担当者の力量によって大きく左右されると言っても過言ではありません。
担当者の能力が低かったばかりに、粗悪な物件を購入してしまった事例もあ流ため、あまりに知識不足であったり、物件のメリットばかり述べてデメリットや注意点をほとんど述べないような担当者は変更してもらうか、別の業者を探しましょう。
担当者の名刺には、担当者直通の携帯番号も記載されていますが、一度は不動産会社の固定電話にかけてみることをおすすめします。
その担当者が本当に在籍しているかを確認できますし、会社に電話がつながることが確認できれば一層安心できます。
勝手に大手不動産業者の名前を騙り、社員であるかのように振る舞い、詐欺同然の行為を働く人間もいるため、会社へ電話したこともない状態で契約をおこなうのは危険です。
何回か会ってしまうと「いい人そうだから大丈夫だろう」と表面上の人柄に気を取られて、確認する気持ちがなくなってしまう場合もあるので、業者と担当者の確認はできるだけ早い段階でおこなうのがベストです。
「売買契約書」の内容を熟読する
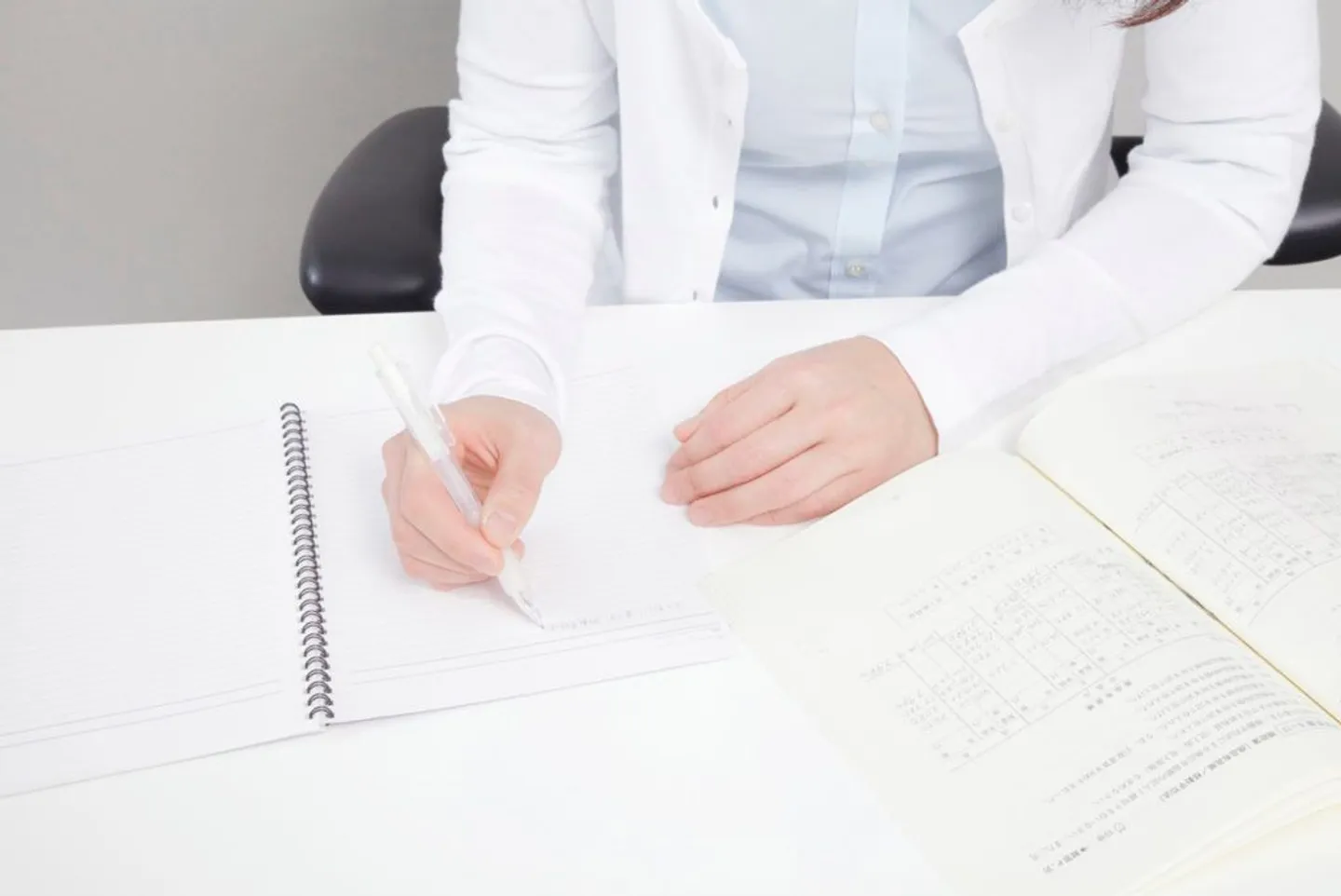
マンション投資のための物件を購入する時には、色々な契約書を交わしますが、とりわけ重要なのは、売買契約書です。
売買の条件、保証を受けるための条件、責任の所在や負担割合、トラブル時の対処手順など、投資をおこなう上で重要な情報はすべて売買契約書に記載されますが、契約書の隅々までくまなく目を通さない人もいます。
また、契約書を作成する側にとって不都合なことは、目立たない場所に小さく書いてあったり、分かりにくい言い回しで記載されます。
そのため、マンション投資の売買契約書は自身で熟読するか、弁護士や司法書士などの専門家に依頼して、自分に不利なことが書いていないかを確認しましょう。
内容チェックだけなら、専門家への依頼費用は1万~3万円程度で済むので、安全に取引をするための初期投資と思えば、決して高くない金額でしょう。
マンション投資で不動産業者とトラブルになった場合、裁判沙汰になる恐れがありますが、契約書は最重要事項とみなされ、じつに80%程度は契約書の内容を参考にして判決が下されると言われています。
マンション投資を巡ってトラブルになる人の中には、「契約書の内容がよく分からなかった」「勘違いしていた」「見落としをしていた」などと言う人がいますが、すべて言い訳にしかなりません。
署名捺印した以上、契約書のすべての記載事項を理解し承諾したことになるため、署名捺印という行為の意味と重大さをよく理解して、必ず売買契約書のすべての記載事項を確認しましょう。
【悪徳業者が心配な人へ】安心して不動産投資を無料相談できる業者はこちら
まとめ
マンション投資を巡る悪質業者の手口は、年々変化しており、効果的でグレーゾーンぎりぎりの訴えられにくい方法を編み出しています。
マンション投資をする以上、悪質業者と一切接触せずに済む保証はないので、自己防衛のために知識を身につけておくことが大切です。
日頃から不動産投資関連のニュースやウェブサイトなどをチェックしておくこともできますし、勉強会やセミナーに参加して同じようにマンション投資で大家業をしている人たちと交流を持つのも良い方法です。
悪質業者に騙されないためには、新鮮でリアルな情報を豊富に持っておくことが大切なので、いま実際にマンション投資の現場にいる人たちの輪に入って情報を共有することが、一番の対策といえるでしょう。