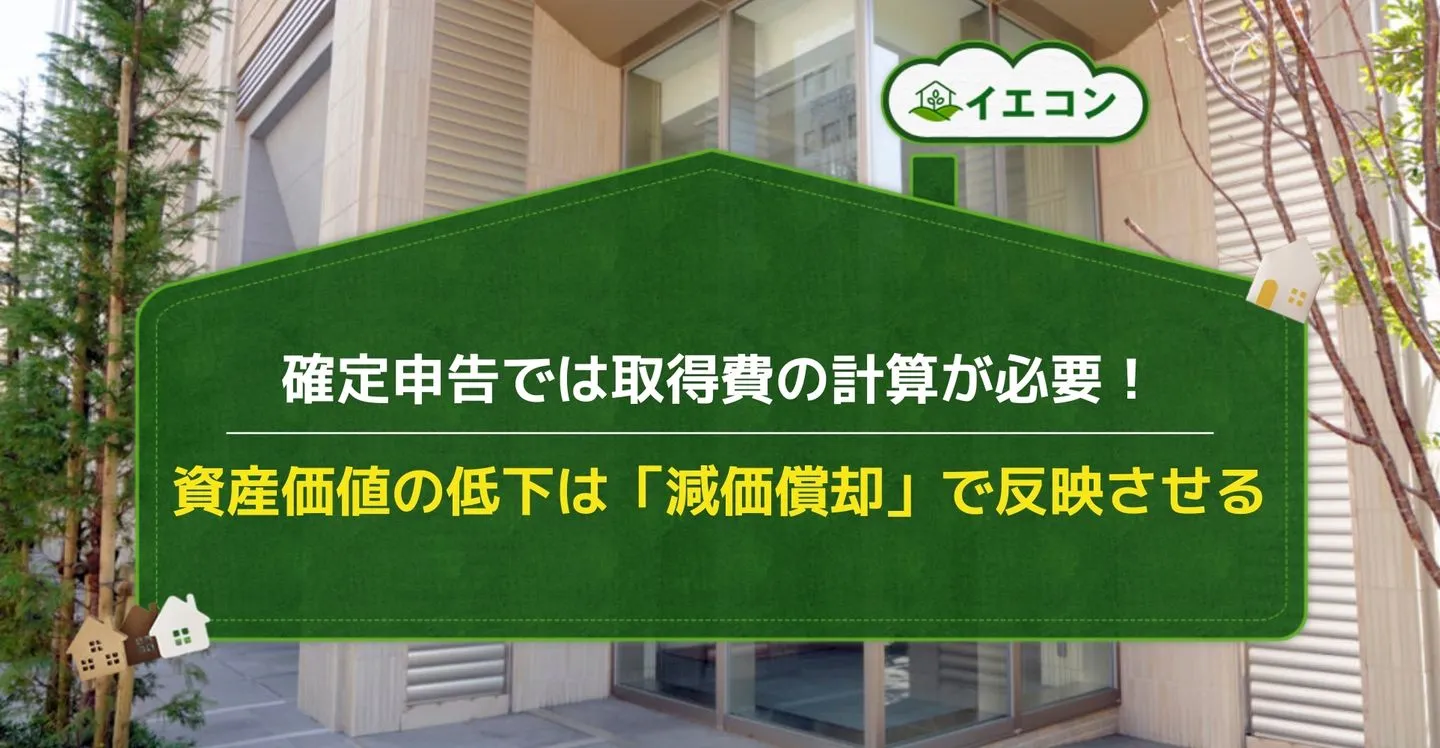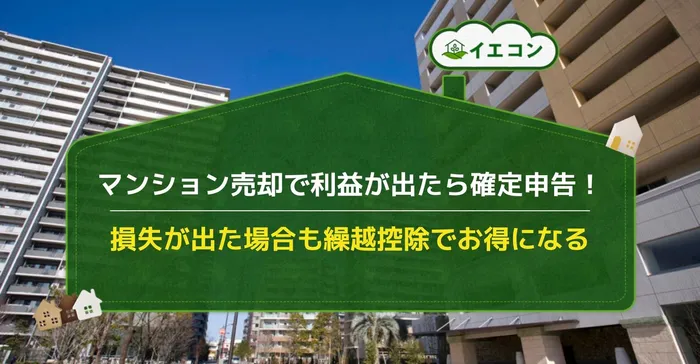マンションを売却すると、確定申告が必要となります。売却によって得た利益と、その利益に課される税金(譲渡所得税)を算出するためです。
そして、売却利益を計算する際に必要となるのが「取得費」です。
取得費とは、マンションを取得するときにかかった費用を指します。しかし、単純に売却利益から購入価額を差し引くだけでは不十分です。
取得費を計算するときは、減価償却によって「劣化による資産価値の低下」を反映させましょう。
取得費や減価償却の計算に不安がある場合は、税金の専門家である税理士に相談しましょう。必要であれば、確定申告の手続きも代行してもらえます。
マンション売却時の確定申告では「取得費の計算」が必要になる
取得費とは、文字どおり取得時にかかった費用を指します。
マンションの売却において取得費が関わってくるのは、確定申告です。譲渡所得の課税額を算出するために、取得費が重要な項目となります。
譲渡所得とは、言い換えれば「マンション売却で得られた利益」です。「譲渡価額-取得費-譲渡費用」で計算します。
- 譲渡価額・・・売却価格。買主から実際に受け取る代金。
- 取得費・・・マンションを取得したときにかかった費用。
- 譲渡費用・・・マンションを売却したときにかかった費用。
譲渡所得に控除や税率を適用して、譲渡所得税の税額を算出するのが確定申告の目的です。
取得費にあてはまるもの
取得費はマンションの購入代金だけでなく、仲介手数料など「購入に必要な費用」も含まれます。
取得費の具体例としては、下記のものがあげられます。
- 購入代金や建築代金
- 購入手数料(仲介手数料など)
- 設備費
- 改良費
- 登録免許税や登記費用
- 入居するまでに支払った住宅ローンの利子
- 所有権の確保に要した訴訟費用
上記以外にも取得費となるものがあるので、詳しくは国税庁のWebサイトで確認しましょう。
また、取得費が売却価格の5%未満であるときは、5%相当額として計算できます。
取得費が不明な場合は「売却価格の5%」で計算する
先祖伝来の土地であったり、購入時期が古かったりなどで、取得費がわからないケースは少なくありません。
上記のように取得費がわからない場合、売却価格の5%を取得費として計算できます。
取得費を0円で計算すると譲渡所得が高くなり、ひいては課税額も高くなります。そうした負担を軽減するために、取得費は「売却価格の5%」を下回らないようになっているのです。
減価償却はマンション取得費における「資産価値の低下」を反映させる

減価償却とは、年月によって低下する資産価値を計算するための手法です。
マンションのような固定資産は、建物の劣化による価値の低下を避けられません。10年、20年と経てば、資産価値は下がります。
そして、譲渡所得を計算するとき、低下した資産価値を取得費に反映させる必要があるのです。
10年間でマンションの資産価値が変動しない場合、譲渡所得は「3,000万円-3,000万円-譲渡費用」で計算します。つまり、譲渡所得は0円ないしはマイナスです。
しかし、実際は建物の劣化などがあるため「資産価値が変わらない」ということは原則ありえません。劣化による資産価値の低下を反映させるため、減価償却が必要となります。
ちなみに、税制における資産価値と、不動産市場における売却相場は、必ずしも比例するとは限りません。劣化した建物でも、需要があれば高く売却できるケースはあります。
減価償却は「耐用年数に応じて分割して経費を計上する」手法
減価償却をシンプルに説明すると、取得費を「資産を使える期間(耐用年数)」で分割して経費計上する方法です。
例えば、1,000万円の取得費を「取得した年」に全額計上するのではなく、10年間で100万円ずつ計上するという手法です。
「なぜ分割して経費計上をおこなうのか」は、会計制度における原則を考慮するとわかりやすくなります。
上記が会計制度の原則ですが、高額な固定資産を購入した場合、年間で利益と費用が対応するとは限りません。
取得年で全額を経費にすると「利益<経費」となり、その年の課税額は極端に低くなります。
反対に、売却した年には計上できる経費がないので「利益>経費」となり、税額が極端に高くなります。
そこで、取得費を分割して経費計上し、年間の利益と対応させるのです。こうすることで、売却した年度による課税額の偏りがなくなります。
不動産の減価償却は「建物」のみが対象
不動産の場合、減価償却できるのは建物と付帯設備(インフラ設備や空調設備など)に限られます。
土地は「劣化による価値の低下」がないため、対象とされていません。
また、使用可能期間が1年未満のものや、取得価額が10万円未満のものも、減価償却の対象外です。
取得費に減価償却を反映させる計算方法
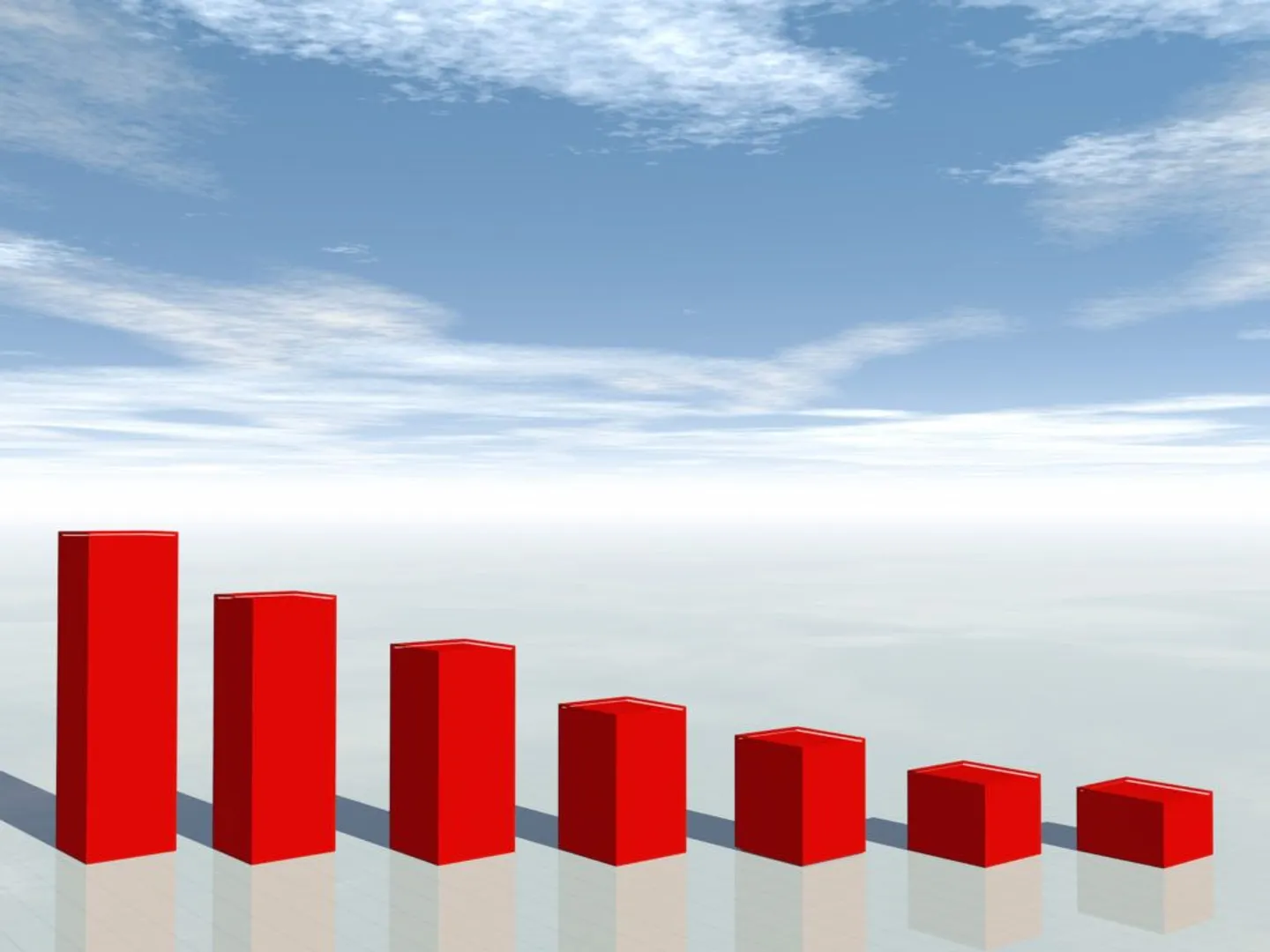
取得費に減価償却を反映させるには「減価償却費相当額」の算出が必要です。減価償却費相当額とは、所有期間中に減価償却された金額(劣化によって低下した価値の価額)です。
計算方法には「定率法」と「定額法」の2種類があります。マンションのような建物で適用されるのは「定額法」です。
マイホームなど「事業用途以外」の建物では、次の計算式となります。
経過年数とは、マンションを取得してから売却するまでの年数です。1年未満の月数は切り上げます。
取得費から減価償却費相当額を差し引くことで、減価償却を反映できます。
減価償却の計算で使われる「耐用年数」と「償却率」
減価償却の計算で使われる「耐用年数」と「償却率」は、法律で決まっています。
下記は「鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造の建物」の耐用年数を、一部抜粋したものです。
- 事務所用のもの・・・50年
- 住宅用のもの・・・47年
- 飲食店用のもの(木造内装部分が30%超の場合)・・・34年
- 飲食店用のもの(上記以外)・・・41年
- 店舗用のもの・・・39年
上記は基本的な耐用年数ですが、マイホームなど非事業用の資産は1.5倍にします。住宅であれば「47年×1.5」で70年です(1年未満切り捨て)。
償却率は、耐用年数に応じて決まります。耐用年数が70年の場合、定額法の償却率は0.015です。
参照:e-Govポータル「減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第1、第7、第8」
取得費の計算例
具体的な計算例として「マイホーム用のマンションを売却したケース」を見ていきましょう。
法定耐用年数:70年
償却率 : 0.015
経過年数:12年
このケースで実際の建物の取得費を計算すると、以下のようになります。
減価償却後の建物価格(取得費)=3,000万円-486万円=2,514万円
このケースでは、マンションの建物部分の取得費は2,514万円となります。
まとめ
マンションを売却した後は確定申告が必須であり、申告の際には「取得費」と「減価償却」の計算をしなければいけません。
ただし、税制は常に改正されるため、マンションの取得時期や売却するタイミングで計算方法が変わる恐れもあります。
最新の制度を反映し、適切な確定申告をおこなうためには、税理士に相談することをおすすめします。税理士なら、個々の状況に合わせて最適な節税方法も提案可能です。