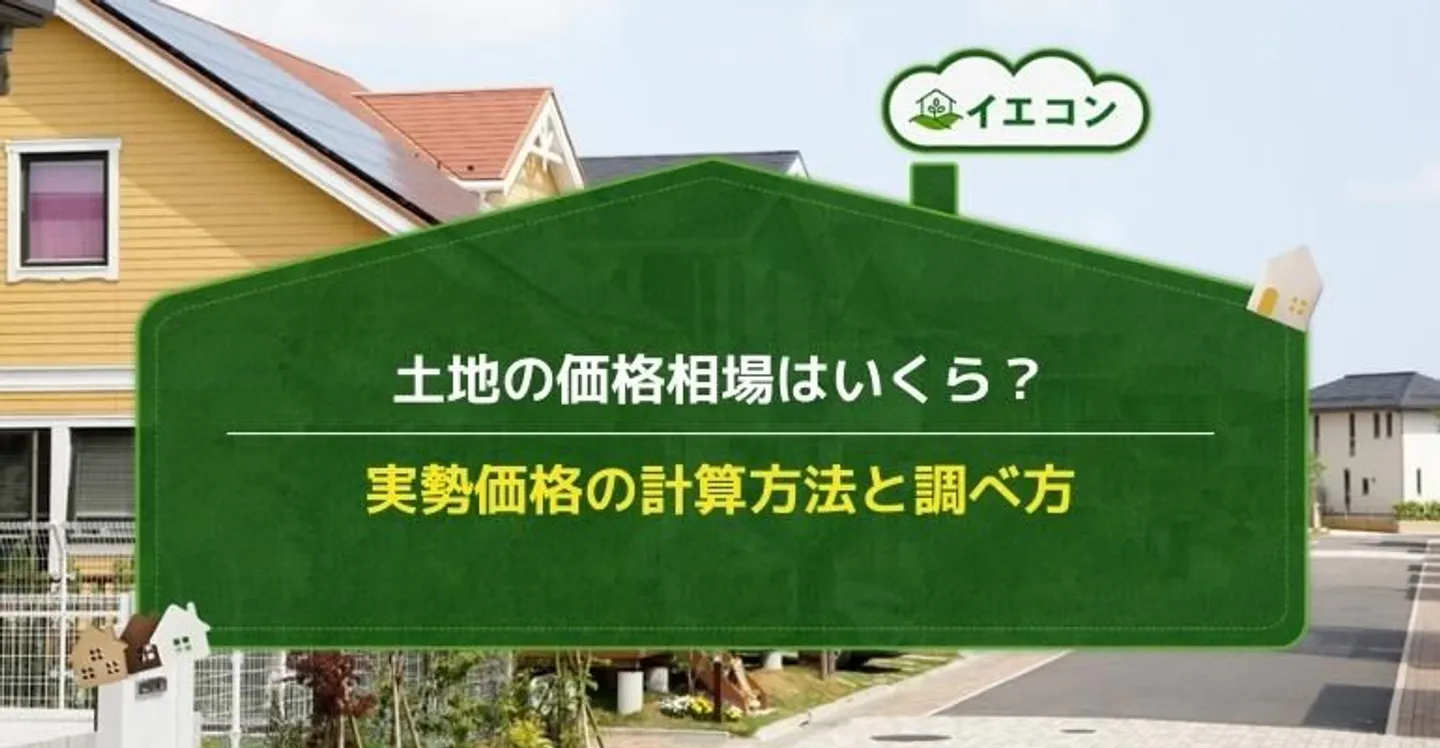土地の価格相場(実勢価格)は、不動産会社に査定してもらう方法が最も正確で早く売却金額を把握できる方法です。
「不動産会社に査定依頼する」など、土地の価格相場の調査方法がわからない場合、売却価格を決めきれずに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
土地の実勢価格は、過去の売買データから算出された価格なので市場価格として参考にできます。
一方で、不動産会社に査定依頼をしても「参考価格」に留めておかなければいけません。
本記事では、土地の価格相場の調べ方や実勢価格の注意点、売却の流れなどを解説します。
本記事を読むと、所有している土地の実勢価格や売却の流れがわかり、適切な価格で土地を売却できる可能性が高まるでしょう。
土地の価格相場(実勢価格)は過去の売買データから予測できる?
土地の価格相場は、過去の実勢価格のデータを目安にしておおまかな金額を予測できます。
土地の売却を検討している方は実勢価格を調べましょう。
国土交通省が運営する「土地総合情報システム」などで、過去に取引された土地の実勢価格を調べられます。
実勢価格とは土地の売却契約が成立した際の金額のことです。
不動産会社が売りに出していた金額ではありません。
不動産業者が土地を1,000万円で売りに出していても、交渉により最終的に900万円で売却されると実勢価格は900万円になります。
実勢価格は下記のようなさまざまな要因で価格が決まります。
- 立地
- 形状
- 面積
- 方角
- 接道状況
世の中に「全ての条件がまったく同じ土地」はないため、おおまかな参考価格であることを忘れないようにしましょう。
土地の売却相場を知りたいなら「不動産一括査定」も活用できる
土地の売却相場を知るためには、「不動産一括査定」は効果的な方法です。
不動産価格を一括査定できるサイトには、多くの不動産会社が登録しているため複数の企業から売却価格の情報を得て比較検討できます。
土地の情報などを入力するだけなので、容易に売却価格相場がわかります。
また、一括査定サイトを利用しても「必ず契約しなければいけない」というルールはなく、無料で使用できるためおすすめです。
ネットからの査定依頼なので24時間活用でき、日中は仕事で忙しく不動産会社を調べたり問い合わせたりする時間がない方にはうってつけです。
不動産会社に個別に依頼した場合、査定額に不満があったり担当者を信頼できなくなったりすると、別の不動産会社に再度査定依頼から始めなければいけません。
複数の不動産会社に一括で査定依頼ができれば時間や手間も省けます。
土地の価格相場(実勢価格)を調べる方法
土地の実勢価格を調べる方法は、以下の5つです。
- 不動産会社に土地価格を調べてもらう
- 国交省の「不動産取引価格情報検索サイト」で調べる
- 固定資産税評価額から土地の実勢価格を計算する
- 公示地価(基準地価)を調べて実勢価格を計算する
- 路線価(相続税路線価)を調べて実勢価格を計算する
| 実勢価格を調べる方法 | 利用する判断基準 |
|---|---|
| 不動産会社に土地価格を調べてもらう |
・路線価がないエリアを調べる場合 ・手間をかけずに正確な市場価格を知りたい場合 |
| 国交省の「不動産取引価格情報検索サイト」で調べる |
・路線価がないエリアを調べる場合 ・過去の成約事例を確認したい場合 |
| 固定資産税評価額から土地の価格相場(実勢価格)を計算する |
・路線価がないエリアを調べる場合 ・複数の実勢価格の参考例が欲しい場合 |
| 公示地価(基準地価)を調べて実勢価格を算出する |
・公的機関のデータを参考にしたい場合 ・複数の実勢価格の参考例が欲しい場合 |
| 路線価(相続税路線価)を調べて実勢価格を計算する |
・公的機関のデータを参考にしたい場合 ・複数の実勢価格の参考例が欲しい場合 |
「不動産会社に土地価格を調べてもらう」方法は、査定依頼だけであれば手間がかからず確実に相場がわかります。
また、国交省の「不動産取引価格情報検索サイト」で調べる方法は、過去の成約事例が見やすいため近隣の土地の参考価格がすぐに確認できます。
確定的な売却価格はわからないため、相場を知る段階で手間をかけるメリットはありません。
参考価格がわかればいいので、上記2つの方法は手間がかからずおすすめです。
1.不動産会社に土地価格を調べてもらう
不動産会社に土地価格を調べてもらう方法の特徴は、以下の表の通りです。
| 不動産会社に土地価格を調べてもらう方法 | |
|---|---|
| 調べる難易度 | 低 |
| 価格相場がわかるまでの時間 | 少 |
| 正確度 | 高 |
個別依頼や一括査定依頼で不動産会社に依頼するのは難しくありません。
オンライン上では、物件に関する情報を入力するだけです。
査定にかかる時間は時間は3日から1週間くらいですが、不動産会社によってはさらに早く結果が出ることもあります。
不動産を売買している会社が土地価格を査定するため、現在の具体的な市場価格がわかるでしょう。
また、不動産業者にしか閲覧できない過去取引事例が見られる以下のサービスがあります。
- レインズ(REINS)
- アットホーム(at home)の「不動産調査・成約事例」
- 不動産データクラウド
専門業者にしか得られない情報があるため、不動産会社に依頼することで的確な相場価格がわかります。
不動産会社ごとに査定金額に差が出るため、比較検討するために複数社に査定依頼することが大切です。
2.国土交通省の「不動産取引価格情報検索サイト」で調べる
国交省の「不動産取引価格情報検索サイト」で調べる方法の特徴は、以下の通りです。
| 国交省の「不動産取引価格情報検索サイト」で調べる方法 | |
|---|---|
| 調べる難易度 | 中 |
| 価格相場がわかるまでの時間 | 少 |
| 正確度 | 高 |
国土交通省の「土地総合情報システム」から土地の実勢価格を検索できます。
マップから調べたい地域や時期を選択するだけなので、調べるのは難しくありません。
不動産取引価格情報の一覧まで辿り着くと売買取引が行われた土地の詳細情報が確認できるため、特徴が類似した土地を参考にできるでしょう。
例えば、以下のような情報を確認できます。
- 実勢価格
- 最寄駅からの距離
- 土地面積
- 形状
- 建ぺい率
一方で、詳細な住所や個人情報に関わる内容は確認できません。
近隣の地域でも詳細な住所や現在の土地の状態によって価格が異なる可能性があるため、あくまでも類似した条件の土地を参考にする程度に留めておきましょう。
調べる手順
不動産取引価格情報検索サイトで調べる手順は、以下の通りです。
- 国土交通省の「土地総合情報システム」画面を開く
- 「不動産取引価格情報検索」を選択する
- 「宅地」「土地」など検索したい種類から「土地」を選ぶ
- 「地図」で探すか「路線」から探すかを選ぶ
- 探したい地域を絞り込んでいく
- マップ上に青色のマークで「不動産取引価格情報」が表示され、そのなかの「詳細を表示」をクリックする
- その地域の詳細一覧が表示される
- 近隣の物件や類似物件を参考にする
サイトの「不動産取引価格情報検索」まで辿り着けると、直感的に選択しやすいサイト画面になっています。
そのため、調べる難易度は高くなく、時間もあまりかかりません。
3.固定資産税評価額から土地の実勢価格を計算する
固定資産税評価額から土地の実勢価格を計算する方法の特徴は、以下の通りです。
| 固定資産税評価額から土地の実勢価格を計算する | |
|---|---|
| 調べる難易度 | 高 |
| 価格相場がわかるまでの時間 | 中 |
| 正確度 | 中 |
固定資産税評価額とは、土地や家などの「不動産」の価値を数値で表したものです。この数値は「固定資産税」を決める際の基準になります。
市区町村から送付される固定資産税課税明細書を確認することで固定資産税評価額がわかります。
売却したい土地を所有している方は、市町村から送付される固定資産税課税明細書を確認すると固定資産税評価額がわかります。
土地の実勢価格を求める計算式は以下の通りです。
例えば、固定資産税評価額が2,800万円の場合で計算します。
実勢価格は、2,800万円 ÷ 0.7 × 1.1 = 4,400万円になります。
土地の固定資産税評価額は、公示価格の約70%に設定されているため、計算式で割り戻すことがポイントです。
「公示価格」とは、不動産鑑定士が毎年1㎡あたりの正常な価格を判定して導き出している信頼できる価格です。
また、実際に土地が売買された価格(実勢価格)は、公示価格の1.1倍~1.2倍が目安となるため、1.1倍にする計算を入れることで計算式が完成します。
A:固定資産税評価額を0.7で割った数の1.1倍程度が実勢価格の目安です。
固定資産税評価額は市区町村から送付される固定資産税課税明細書で確認できます。
「書類に記載されている固定資産税評価額 ÷ 0.7 × 1.1」という簡単な計算で、実勢価格がすぐに算出できるのでおすすめの調査方法です。
固定資産税課税明細書は失くさないように注意しましょう。
調べる手順
固定資産税評価額から土地の実勢価格を計算する手順は、以下の通りです。
- 固定資産税課税明細書で固定資産税評価額を確認する
- 以下の計算式に当てはめて計算する
固定資産税課税明細書は毎年4月〜6月に、1月1日時点の土地所有者に送付されます。
送付される時期の詳細は、自治体によって異なるので各自治体に確認しましょう。
固定資産税納税通知書がない場合、以下の方法で情報が得られます。
- 各自治体の税務課に問い合わせる
- 固定資産税課税台帳の閲覧申請を行う
- 固定資産評価証明書を役所で取得する
固定資産税納税通知書がなければ時間と手間がかかってしまいます。
固定資産税納税通知書は、重要な書類で再発行ができないため気をつけて保管しましょう。
4.公示地価(基準地価)を調べて実勢価格を算出する
公示地価(基準地価)を調べて実勢価格を算出する方法の特徴は、以下の通りです。
| 公示地価(基準地価)を調べて実勢価格を算出する | |
|---|---|
| 調べる難易度 | 中 |
| 価格相場がわかるまでの時間 | 中 |
| 正確度 | 中 |
公示地価(基準地価)とは、公的機関が出している土地の価格です。
公的機関が発表している価格なので、土地売買の際に金額の参考にできます。
公示地価と基準地価は調べ方や内容はほとんど同じですが、調査日や公表時期などは以下の違いがあります。
| 公示地価 | 基準地価 | |
|---|---|---|
| 調査機関 | 国土交通省 | 都道府県 |
| 調査日 | 毎年1月1日 | 毎年7月1日 |
| 公表日 | 毎年3月下旬 | 毎年9月下旬 |
公示地価を調べた上で以下の計算式に当てはめて実勢価格を算出します。
例えば、公示価格が1㎡あたり30万円、売買したい土地の面積が100㎡の場合で計算します。
30万円 × 100㎡ × 1.1 = 3,300万円
上記計算では、実勢価格の目安は3,300万円になります。
実勢価格の目安を出す際に、公示地価が計算に含まれる場合は1.1倍してください。
公示地価は、国土交通省ホームページの「土地総合情報システム」から調べます。
シンプルなシステムなので、公示地価を調べることは簡単です。
周辺エリアの公示地価・基準地価を調べて実勢価格の目安を計算してみてください。
一方で、公示地価は調査日から公表日まで数ヶ月かかるため実勢価格が変わることも考慮しなければいけません。
そのため、実勢価格はあくまでも参考価格として考えましょう。
A:公示地価の1.1倍程度が実勢価格の目安です。
調べる手順
公示地価(基準地価)から実勢価格を調べる手順は以下の通りです。
- 国土交通省ホームページの土地情報総合システムにアクセスする
- 「地価公示都道府県地価調査」を選び、調べたい都道府県をマップから選択する
- 市区町村を選択する
- 地価や用途区分などの条件を指定して検索する
- 調べたい土地に近い地域や条件の価格を見る
- 計算式に当てはめて実勢価格の目安を計算する
物件の詳細情報から最寄駅までの距離や建物構造、周辺の土地の利用現況などの詳細情報も確認できます。
実勢価格は参考価格ですが、物件の詳細情報がわかるため売買を検討する際に役立つでしょう。
5.路線価(相続税路線価)を調べて実勢価格を計算する
路線価(相続税路線価)を調べて実勢価格を計算する方法の特徴は、以下の通りです。
| 路線価(相続税路線価)を調べて実勢価格を計算する | |
|---|---|
| 調べる難易度 | 高 |
| 価格相場がわかるまでの時間 | 中 |
| 正確度 | 低 |
路線価(相続税路線価)から実勢価格を算出する計算式は以下の通りです。
例えば、記載されている路線価が160、その道路上に面している土地が100㎡の場合で計算します。
記載されている路線価の数字は、1㎡あたり1,000円単位の路線価です。
路線価 = 160 × 1,000円 = 16万円
この路線価を計算式に当てはめると、2,200万円になることがわかります。
16万円×100㎡ ÷ 0.8 × 1.1 = 2,200万円
路線価は、公示地価の80%程度になるように定められているため0.8で割り戻し、公示地価の価格に戻して1.1倍します。
計算が少し手間な上に目安の実勢価格にしかならないため、参考程度に留めることが大切です。
路線価は、毎年7月初旬に国税庁が定める土地の価格で、相続税や贈与税の算出に使われています。
一方で、路線価は土地の価格を表しているため、実勢価格の計算にも応用できるのです。
A:路線価を0.8で割った数の1.1が実勢価格の目安です。
調べる手順
路線価から実勢価格を調べる手順は以下の通りです。
- 国税庁の路線価図・評価倍率表のページにアクセスする
- 日本地図から調べたい都道府県を選択する
- 「路線価図」を選択する
- 詳細な市町村を選択する
- 調べたい土地が面している路線価の価格を確認する
- 実勢価格の目安を計算する
市町村を選択し、路線価図ページ番号を選択すると地図画面が開きます。
地図の道路上に「数字のみ」もしくは「数字+A〜Gの記号」が記載されており、この数字にあたる部分が路線価です。
A〜Gの記号は借地権の割合を示しています。
| 記号 | 借地権割合 |
|---|---|
| A | 90% |
| B | 80% |
| C | 70% |
| D | 60% |
| E | 50% |
| F | 40% |
| G | 30% |
参考:路線価図・評価倍率表
実勢価格は土地売却時にどの程度参考にしていい?
実勢価格は参考価格として捉えて利用します。
この「参考価格」はどの程度参考にしていいのかを、以下の場合に分けて解説します。
- 土地売り出し時の「希望価格 or 相場価格の設定」で参考にする
- 購入希望者との交渉の末で実勢価格が決まる
- 土地の売り出し価格は、不動産会社に相談して決めるのが最善
土地売り出し時の「希望価格 or 相場価格の設定」で参考にする
実勢価格は、基本的に市場価格を反映しているため、希望価格や相場価格の参考とするのは問題ありません。
高すぎる価格は購入希望者を遠ざけ、低すぎる価格は想定以上に利益を減らしてしまう可能性があります。
相場価格として参考にすることで適切な範囲の価格設定ができます。
一方で、最低価格の参考価格にするのはおすすめできません。
「最低でも相場価格で売りたい」と考える方は多いですが、達成できるケースは多くありません。
当初の設定価格で売れない場合、相場価格より低い価格にしなければ売れなくなってしまいますので注意しましょう。
購入希望者との交渉の末で実勢価格が決まる
自分が売却する土地の価格は、最終的に購入希望者との交渉によって決まります。
そのため、過去の売買案件における実勢価格を参考にしても、自分の土地購入者と交渉内容が異なるため、売却価格が変わることもあります。
一方で、実勢価格を確認しておけば適切な価格の目安がわかるため、値引き交渉の末に売却価格が下がっても許容範囲内であれば損を感じにくくなります。
また、実勢価格を参考にすることで市場価格と比較して低すぎない金額設定が可能です。
土地の売り出し価格は不動産会社に相談して決めるのが最善
土地の売り出し価格は、過去の実勢価格を参考にするよりも不動産会社に相談して決めることがおすすめです。
不動産会社には市場の動向を知る術や土地価格を設定してきた経験、土地売買のノウハウがあるためです。
ほかにも、不動産会社は売主と購入希望者の間に立って交渉を進めてくれます。
そのため、不動産会社や担当者の技量によって交渉がうまく進むのか、適切な売却価格を設定してくれるのかが変わるので、実績があり信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。
一方で、悪徳な不動産会社に騙され、低い価格設定にされていないかを知るために実勢価格を参考にすることは重要です。
土地の実勢価格における注意点
土地の実勢価格について、以下の3点に注意しましょう。
- 過去取引の成約金額なので地価が変動しているケースがある
- 実勢価格の相場通りに売却できるとは限らない
- 不動産会社の査定金額 = 実勢価格とはならない
過去取引の成約金額なので地価が変動しているケースがある
実勢金額は過去のデータなので、地価が変わっている可能性があります。
また、国や自治体が公表する公示地価や基準地価・路線価は調査から発表までに数ヶ月時間がかかるため、時間経過で地価が変わっている可能性も考慮しましょう。
さらに、同じ地域にある土地でも、狭い土地や形がいびつな土地などさまざまな土地があるので、条件によって価格が変動することも把握しておきましょう。
実勢価格の相場通りに売却できるとは限らない
実勢価格を調べても、相場通りに売却できるとは限りません。
過去のデータや路線価、公示地価をもとに計算した実勢価格の参考値は、あくまで参考値です。
また、事情により、高く売るよりも早く売ることを重視している場合は、相場よりも安く売らざるを得ないこともあります。
実勢価格は、土地の状況や個人の条件によって価格に影響が出ることが多いです。
条件や立地を踏まえると1つとして同じ土地はないので、実勢価格を参考にしながらも相場通りの金額で売却できないこともあると理解しておきましょう。
不動産会社の査定金額 = 実勢価格とはならない
不動産会社の査定金額は、そのまま実勢価格にならないことがあります。
以下の理由から、査定金額を多めに見積もっている可能性も考えられます。
- 売主が他社と相見積もりした際に負けないようにするため
- 購入者側から値下げ交渉されて利益を残すため
上記のような事情があるため、土地の査定を依頼する際は、複数の不動産会社に査定を依頼しましょう。
不動産会社によって査定金額が違う上に、得意不得意な不動産分野があるためです。
例えば、不動産会社によっては、土地の売買が得意な会社もあれば、賃貸物件の取り扱いが得意で土地の扱いが不得意な会社もあります。
土地の価格相場(実勢価格)を調べた後に売却する流れ
土地の価格相場を調べた後、実際に売却していく流れは以下の通りです。
- 不動産会社に査定してもらう
- 不動産会社と媒介契約を締結
- 売却活動を開始
- 購入希望者との交渉
- 売買契約を締結
- 決済・引渡し
- 確定申告
1.不動産会社に査定してもらう
まず、不動産会社に査定してもらいます。
査定方法には以下の2種類があります。
- 机上査定(簡易査定)
- 訪問査定
机上査定(簡易査定)は、立地条件や過去の取引価格などの不動産データから査定価格を出す方法です。
不動産会社への一括査定依頼などは主にこの机上査定になります。
訪問査定は、不動産会社の担当者が実際の現場まで訪問し、土地の状態も含めて細かな調査を行った上で査定価格を計算する方法です。
詳細な査定価格を算出できますが、結果が出るまでに時間を要します。
不動産会社を選択して依頼し、担当者が訪問日を決める工程を経るためです。
時間と手間がかかるため、売却することが確定している方におすすめの査定方法です。
2.不動産会社と媒介契約を締結
次に、不動産会社の仲介で不動産売却を進める「媒介契約」を締結します。
媒介契約には3つの種類があります。
- 一般媒介
- 専任媒介
- 専属専任媒介
大きな特徴は以下の表の通りです。
| 一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 | |
|---|---|---|---|
| 複数の不動産会社と 媒介契約が結べる |
◯ | ✕ | ✕ |
| 複自分で探した購入者と 直接取引ができる |
◯ | ◯ | ✕ |
一般媒介
一般媒介の特徴は以下の2つです。
- 複数の不動産会社と媒介契約が結べる
- 自分で探した購入者と直接取引ができる
複数の不動産会社と契約可能なので認知を広げやすく、売却できる可能性が高くなります。
一方で、物件や不動産会社によっては積極的に販売活動をしてもらえない可能性もあるため、注意が必要です。
専任媒介
専任媒介の特徴は以下の2つです。
- 1つの不動産会社と媒介契約を結ぶ
- 自分で探した購入者との直接取引ができる
専任媒介契約を締結すると、1社の不動産会社からしか売却活動ができません。
しかし、土地の売却のために積極的な販売活動をしてもらえる可能性が高く、売却成功の確率も高まります。
さらに、不動産会社とのやり取りも1社のみで済むため状況を把握しやすく手間やコミュニケーションコストを抑えられます。
一方で、1社の販売力にしか頼れないため慎重に不動産会社を選ばなければいけません。
専属専任媒介
専属専任媒介契約の特徴は、以下の2つです。
- 1つの不動産会社と媒介契約を結ぶ
- 自分で探した購入者と直接取引ができない
売主にとって制約の多い媒介契約です。
しかし、不動産会社は売主に販売活動の報告を頻繁にしなければいけないため、積極的な販売活動をしてもらえる可能性が高いです。
売れにくい物件を所有している方や、早く売却したいという方におすすめの契約といえるでしょう。
不動産会社が土地を買取る場合は「売買契約」を締結する
不動産会社が土地を買取る場合は、売主は「売買契約」を締結して売却します。
売主にとっては以下のメリットがあります。
- 売却までの時間が短い
- 売却しにくい物件でも売却できる可能性がある
不動産会社は、売主と買主をつなげることはしないため「仲介契約」ではありません。
そのため、買主が現れるのを待つ必要がなく、売却までの時間が短くて済みます。
また、売主は仲介契約では売りにくい物件でも不動産会社に売却できる可能性があります。
不動産会社は、買い取った不動産をさまざまな方法で売却するノウハウがあるからです。
一方で、不動産会社への売却では、売却価格が市場価格の約70〜80%になってしまうデメリットがあります。
不動産会社は買い取った後に、再販売するまでの管理費や販売リスクを考慮して買い取るためです。
さらに、不動産会社は買い取った価格に利益を乗せて販売することも計算するため、市場価格より安く買い取られてしまいます。
3.売却活動を開始
媒介契約を締結すると、不動産会社が売却活動を開始します。
自社のホームページやレインズに物件を登録したり、チラシ・住宅情報雑誌などに広告を出したりして売却活動を進めていきます。
売却活動を開始すると、不動産会社から媒介契約ごとに定期的な活動報告から状況を把握しておきましょう。
- 一般媒介契約:報告の義務付けなし
- 専任媒介契約:2週間に1回以上
- 専属専任媒介契約:1週間に1回以上
どのような販売活動をしたのか、問い合わせが何件あったのかなどを活動報告から状況を把握しておきましょう。
一方で、報告義務に違反する場合、誠実な対応をしていない不動産会社となるので早めに契約を解除して、別の不動産会社と契約するのがおすすめです。
4.購入希望者との交渉
購入希望者が現れると、以下の内容について交渉が発生することがあります。
- 売買価格
- 手付金の金額
- 引渡しの時期
最も多い交渉は、「売却価格をもう少し値下げできないか」という価格交渉です。
条件交渉は不動産会社が間に入って代行するため、売主が直接行うことはほとんどありません。
購入希望者から価格交渉が発生しても売却できるチャンスなので、内容を吟味して譲れない部分は不動産会社にしっかりと伝えて妥協案を検討していきましょう。
5.売買契約を締結
条件交渉などがまとまると、売買契約書に署名押印を行って「契約締結」となります。
司法書士や行政書士、不動産会社に依頼して土地売買契約書を作成しましょう。
契約書に不明点を見つけた場合、署名捺印する前に必ず不動産会社に確認しましょう。
引渡し後にトラブルが発生すると、大きなトラブルに発展したり長引いたりする恐れがあるためです。
また、「言った・言わない」の水掛け論になることも防止できます。
「トラブルが発生しない契約書を作成できるかどうか」という点も不動産会社次第になるので、信頼できる不動産業者を選択することが重要です。
6.決済・引渡し
最後の工程として決済と引渡しを行います。
決済時に必要なものは以下の通りです。
| 決済・引渡し時に必要なもの |
|---|
|
決済や引渡しは基本的に平日の午前中に行います。
決済を行う前に司法書士が売主と購入者双方の書類を確認します。
その際に、書類の不備などのトラブルがあったとしても当日中に対応するために、平日の午前中に行います。
必要書類が揃っていなければ手続きを進められないため、事前にしっかりと確認して準備しておきましょう。
不備の内容によっては、引渡しを延期することになってしまうかもしれません。
例えば、抵当権抹消書類の準備です。
金融機関によっては書類の準備に2週間〜1ヶ月ほどかかる場合もあるため、早めに準備しておきましょう。
7.確定申告
土地を売却して利益が発生した場合、確定申告が必要です。
土地などの不動産を売却して得た利益を「譲渡所得」といいます。
譲渡所得は、給与所得などと分離して課税されるため確定申告が必要なのです。
以下の計算式で譲渡所得を算出します。
例えば、土地を3,000万円で売却した場合を考えます。
売却する際に手数料となる譲渡費用が300万円、土地の購入にかかった費用(取得費)が2,000万円だった場合は以下の計算になります。
譲渡所得 = 3,000万円 ー (2,000万円 + 300万円)
譲渡所得は700万円となるため、確定申告が必要になります。
確定申告に必要な書類は以下のものです。
- 確定申告書B
- 確定申告書第三表(分離課税用)
- 譲渡所得の内訳書
- 本人確認書類のコピー
- 売買契約書のコピー
- 譲渡費用の領収書のコピー
- 取得費の領収書のコピー
確定申告書第三表(分離課税用)は、土地売却で売却利益が出た場合に提出する書類です。
売買契約書のコピーは、土地売却時と購入時の分がそれぞれ必要です。
確定申告を初めて行う方は、難しく感じる可能性もあるため早めに書類などを準備して税理士に依頼することも検討しましょう。
一方で、確定申告が不要な場合は、売却額が「取得費 + 譲渡費用」よりも少なく、利益が出ない場合です。
売却にかかる譲渡費用に含まれる諸経費には、以下のようなものがあります。
- 仲介手数料
- 印紙税
- 登記費用
確定申告の際に税金の控除ができる制度もあるので、税金に関することは事前に確認しておきましょう。
まとめ
本記事では、実勢価格の調べ方や売却の際に実勢価格の注意点、実際に土地を売却するときの流れなどを解説しました。
実勢価格は以下の5つの方法で調べられます。
- 不動産会社に土地価格を調べてもらう
- 国交省の「不動産取引価格情報検索サイト」で調べる
- 固定資産税評価額から土地の実勢価格を計算する
- 公示地価(基準地価)を調べて実勢価格を計算する
- 路線価(相続税路線価)を調べて実勢価格を計算する
さまざまな方法がありますが、不動産会社に依頼するのが一番おすすめです。
市場相場を把握し、土地の価格設定を行ってきた経験とノウハウがあるためです。
参考になる適切な実勢価格や注意すべきポイント、流れを把握して土地を売却しましょう。
実勢価格に関するよくある質問
実勢価格と時価の違いは?
時価は、個別事情の影響を含まない現在の価格です。
しかし、ほとんど違いのない同じ意味として使用されていることが多いです。
土地の価格相場(実勢価格)は調べる必要がある?
買主は土地を購入する際に交渉に使えます。
また、割高な価格設定になっている土地の購入を回避できます。
土地以外の不動産でも実勢価格を調べることはできる?
・不動産会社に依頼する
・国土交通省の「土地総合情報システム」を使用する
・固定資産税評価額をもとに計算する
ただし、正確な価格は物件の特性や市場状況により変動するため、参考価格に留めておきましょう。