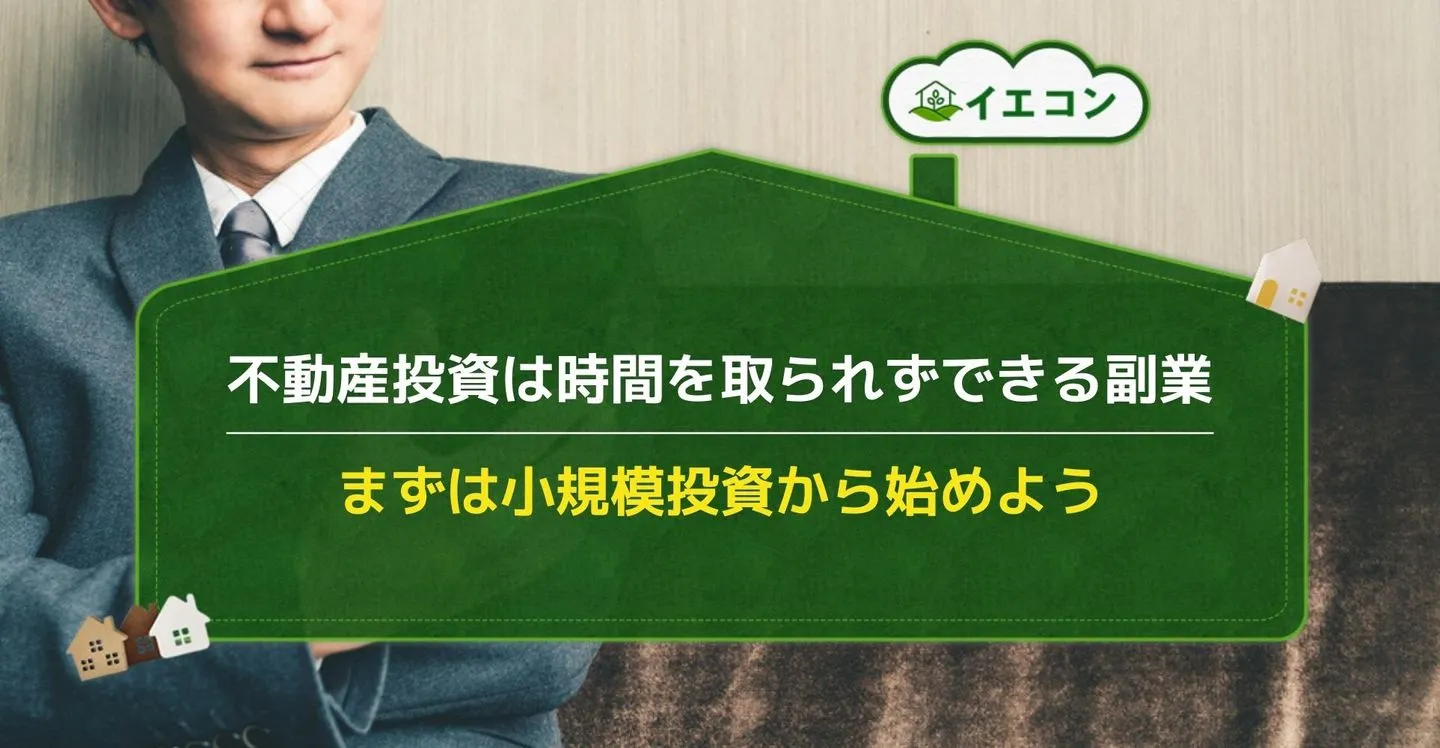不動産投資に興味があるものの、高額資産なので失敗するのが怖いと考えている人も多いと思います。
しかし、不動産投資は会社員が副業ではじめるのにぴったりの資産運用といえます。会社員なら借入もしやすく、節税効果も高いので、会社員にとってメリットの大きい投資方法なのです。
人によっては会社で副業を禁止されているという人もいるかと思いますが、不動産投資なら本業に支障を来しにくいので、勤務先で問題になることはほとんどありません。
ただし、副業で不動産投資をやるなら、時間をかけず効率的に運用をすることが重要となります。そのため、まずは不動産会社に相談して、物件選びや運用方法のアドバイスをもらいましょう。
下記のリンクからあなたにぴったりの不動産投資会社を診断することができるので、これから不動産投資をはじめる人はぜひ利用してみてください。
【会社員こそおすすめ】副業で不動産投資をする8つのメリット
国が副業を推進していることもあり、近年は会社員でも副業をする人が多くなってきました。副業をすることで収入が向上・安定し、効率的な資産形成ができます。
そして、不動産投資は会社員にこそおすすめできる副業です。副業として不動産投資をするメリットは、次の8つがあげられます。
- 会社員ならローンを組みやすい
- 時間を取られない
- 他の投資より安定した収入がある
- 退職や休職をしても収入源を確保できる
- 生命保険の代わりになる
- 所得税や住民税の節税効果がある
- 相続税の節税効果がある
- インフレ対策になる
各メリットを詳しく解説していくので、不動産投資をはじめるか悩んでいる人はぜひ参考にしてください。
1.会社員ならローンを組みやすい
不動産投資ではローンを組んで物件を購入する方法が一般的です。初期費用が少なくてもローンを組むことで高額な不動産を購入できるのが、不動産投資のメリットでもあります。
ローンを組むにあたって重要になるのが収入です。金融機関のローン審査では、申込者の信用力を測るために年収や雇用形態、勤続年数などが見られます。
会社員として正規雇用されている人は収入が安定しており、職を失うリスクが低いため、非正規雇用の人や個人事業主よりローンを組みやすいのです。
借入額の上限や金利などで優遇される場合もあり、不動産投資において会社員であることは大きなアドバンテージとなるのです。
2.時間を取られない
副業としておこなう場合、いかに本業やプライベートの時間を削らないかも重要です。副業に時間を取られると、本業がおろそかになったり、自由な時間がなくなってしまいます。
不動産投資の場合、不動産管理会社に依頼すれば面倒な作業はほとんど任せることができます。管理委託費を支払う必要はありますが、本業とうまく両立しながら取り組むことが可能です。
株式やFXなど他の投資では、利益を得るためには常に市場を見ている必要があるなど、時間を取られやすくなります。
これら他の投資と比べれば、時間を有効に使える不動産投資は効率的な稼ぎ方といえるでしょう。
3.他の投資より安定した収入がある
株式やFXと比較して、収入が安定するというメリットもあります。
株式やFXは主に売買の差益で収入を得ますが、値動きが予想と外れたり、経済動向など外的要因で損をしたりなど、収入が不安定です。
一方、不動産投資では入居者さえいれば継続的に家賃収入を得られるため、会社員が参入できる副業の中でも安定しているといえます。
4.退職や休職をしても収入源を確保できる
不動産投資をすることで、会社を退職したり、なんらかの理由で休職することになっても無収入になる事態を避けられます。
病気やケガをしたときの備えになりますし、会社が倒産したときや、転職活動をおこなうときに金銭的・精神的な負担を軽減できます。
また、老後の私的年金の代わりとしても不動産投資は有効です。入居者がいる限り継続的に収入を得られるので、物件をしっかりと管理・メンテナンスすれば、老後の収入確保につながります。
5.生命保険の代わりになる
不動産投資をすることで、生命保険の代わりになるという考え方もあります。
理由は不動産ローンに付帯する「団体信用生命保険」で、これは契約者が死亡したときや、高度障害を負ったときなどに、保険金からローンの残債が支払われるというものです。
つまり、ローン契約者が死亡した場合、遺された家族はローンの完済された不動産を取得できます。
保険料はローン金利に含まれるので、返済と別途に支払う必要がないのもメリットです。保険料で家計を圧迫することなく、万が一の事態に備えることが可能です。
6.所得税や住民税の節税効果がある
本業にしろ副業にしろ、収入があったときは1年ごとに所得税や住民税が課せられます。不動産投資では、収入から物件の購入費や固定資産税などの必要経費を引いた「不動産所得」が課税対象です。
しかし、入居者がつかなかったり修繕費がかさんだりなどで、不動産所得が赤字になることもあります。
不動産所得で生じた赤字は、他の所得と合算する「損益通算」ができます。つまり、不動産所得の赤字が発生すれば所得税や住民税は低くなるのです。
そして、不動産所得では経費として「減価償却費」を計上できます。減価償却を簡単に説明すると、不動産の購入費用を買った年にまとめて経費計上するのではなく、法律上の耐用年数に分けて計上するというものです。
減価償却をしない場合、物件を購入した年は3,000万円の経費計上ができるため税金はかかりません。しかし、翌年以降は通常通り課税されます。
一方、仮に5年に分けて減価償却をした場合は「3,000万円÷5年=600万円」が毎年経費計上されるため、5年間課税されないことになります。
減価償却をうまく活用すれば、所得税や住民税を大幅に節税できるでしょう。
なお、減価償却ができるのは建物やその付帯設備のみです(土地には法定耐用年数がなく、減価償却ができないため)。
また、構造や材質、用途によって法定耐用年数が異なり、財務省令の別表によって定められています。
参照:e-Govポータル「減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」
7.相続税の節税効果がある
資産を不動産にしておくことで、相続税の節税効果もあります。
相続財産が現金だと金額そのままが相続税評価額となりますが、不動産の場合は時価の70~80%程度になるよう調整されるのが一般的です。
また、投資用不動産として第三者に貸し出している場合、相続人が不動産を自由に使用できないことから、上記よりさらに評価額が下がります。
現金より不動産のほうが課税対象となる評価額を減らせるので、相続税を節税できるのです。
8.インフレ対策になる
インフレとは物価が上がり、お金の価値が下がる現象です。
インフレ時には不動産価格も上がるため、インフレ前に不動産を保有しておけば資産価値が上昇します。
また、お金の価値が下がるということは借入金の価値も実質的に下がることになるため、不動産ローンの返済負担が軽減されます。
世界的に見るとインフレ化が進んでおり、長らくデフレ(物価が下がりお金の価値が上がる状態)が続いた日本でもインフレに転じる可能性があります。
そのため、資産形成や資産防衛のためにも、早めに不動産投資をはじめるのがインフレ対策として有効といえるのです。
副業禁止の会社でも不動産投資は可能?
会社員として勤めている人のなかには、職場が副業を禁止している場合も多いと思います。
国が副業を推進しているとはいえ、いまだに就業規則で副業を禁止している企業は数多く存在します。
しかし「不動産投資は資産運用だから副業じゃない!」「会社にバレなければ問題ないのでは?」と考える人も多いでしょう。
次からは、不動産投資が副業禁止の就業規則に抵触するのかや、トラブルを避けるためのポイントを解説していきます。
基本的には副業禁止でも不動産投資はできる
結論からいうと、副業禁止の職場であっても不動投資は問題にならないケースがほとんどです。
そもそも、副業を禁止する理由の1つは「本業に支障が出るから」です。就業後の深夜や休日に副業をして長時間労働になり、本人の体調が崩れてしまうと会社にとって迷惑がかかります。
また、他の理由として「情報漏えいのリスク管理」もあります。副業を通して社内の情報を外部に流されたり、競合する事業を個人で起こされると会社の不利益になるため、リスク防止の観点から禁止にするのです。
しかし、不動産投資は管理会社に業務の大半を委託できるので、本業に支障が出るほど時間は取られません。
情報漏えいに関しても、不動産投資では会社に損失となるようなリスクは少ないため、容認されるケースが多いのです。
公務員は投資規模に注意が必要
同じ副業禁止でも公務員に関しては法律で規制されており、場合によっては懲戒などの罰則があります。
| 国家公務員法第103条第1項 | 営利企業の役員兼務や自営を禁止 |
|---|---|
| 国家公務員法第104条 | 103条第1項に定めた条件を除く、報酬を得る業務や役職の制限(内閣総理大臣および所轄庁の長の許可が必要) |
| 地方公務員法第38条 | 役員兼務やその他報酬を得る業務や役職の制限(自治体の長など任命権者の許可が必要) |
国家公務員も地方公務員も、原則として所轄庁などの承認が必要となります。
ただし、国家公務員に関しては人事院規則で「許可が必要な条件」が定められており、その条件未満の規模であれば承認を取らなくても不動産投資が可能です。
具体的には、下記の投資規模であれば自由に不動産投資が可能です。
- 賃料収入が年500万円未満であること
- 戸建てや集合住宅については、保有物件がおおむね5棟未満であること
- 集合住宅については、保有物件がおおむね10室未満であること
- 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件未満であること
- 駐車場賃貸については、駐車台数が10台未満で建築物や機械設備を設けていないこと
- ホテルや旅館など特定の業務に使用する建物でないこと
- 劇場、映画館、ゴルフ練習場などの娯楽・遊技等のための設備を設けていないこと
地方公務員に関しては統一された規則はなく、自治体ごとのルールに従うことになります。
参照:e-Govポータル「国家公務員法第103条、第104条」
参照:人事院「人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」
金融関係者はできないケースもある
銀行や証券会社などの金融関係者の場合、一般的な企業より厳しく投資を規制されている場合があるため注意が必要です。
なぜなら、金融関係者は企業の未公開情報に触れる機会が多いため、インサイダー取引とみなされると個人だけでなく勤務先全体の信用情報に発展してしまうためです。
具体的な規定は勤務先によるため、雇用契約書や就業規則で不動産投資が禁止されていないかしっかり確認しておきましょう。
トラブルを避けたければ事前に会社へ相談する
不動産投資で会社とトラブルを起こしたくなければ、事前に相談しておくとよいでしょう。
雇用契約書や就業規則で明確に認められていれば問題ありませんが、あいまいな表記の場合は念のために相談したほうが安全です。
問題ないことを確認しておけば堂々と不動産投資ができるようになり、「バレたらどうしよう」とストレスを貯めながら日々を過ごすこともなくなります。
会社員が副業として不動産投資をするときの注意点
会社員が不動産投資をするにあたって、押さえておきたい注意点は下記の3つです。
- 確定申告は毎年忘れずおこなう
- 不動産投資の規模を拡大しすぎない
- 本業に支障を出さないようにする
上記の注意点を押さえて、不動産投資の失敗リスクをなくしましょう。
確定申告は毎年忘れずおこなう
確定申告とは、1年間の所得などを申告し、所得税や住民税を確定する手続きです。会社員は勤務先で年末調整をおこなうため、確定申告をしたことがない人も多いと思います。
本業以外で20万円を超える所得を得た場合は、会社員でも確定申告をしないと延滞税などが課されるため注意が必要です。
また、不動産投資が赤字になっても、給与と合算する「損益通算」によって節税が可能なため、忘れず申告をおこないましょう。
住民税を「普通徴収」に変更しておこう
住民税の支払い方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があり、会社員は通常、給与から天引きされる特別徴収となっています。
しかし、不動産投資も特別徴収にしてしまうと、勤務先に不動産投資でいくら稼いでいるのか筒抜けになってしまいます。
そのため、不動産投資の所得は自分で納付する普通徴収に切り替え、勤務先に所得額がわからないようにしましょう。
確定申告書を書く際に、住民税に関する事項で「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に対する住民税」の欄で「自分で納付」に記入すれば、普通徴収に切り替えられます。
不動産投資の規模を拡大しすぎない
不動産投資を拡大しすぎて事業規模になると、勤務先で問題になる可能性が高くなります。
なぜなら、副業禁止にしている会社では「不動産投資が事業規模になっているかどうか」をボーダーラインにしている場合があるためです。
具体的には、確定申告で事業とみなされる「戸建ての保有数がおおむね5棟以上もしくは集合住宅の保有数がおおむね10室以上」の場合、勤務先で容認されない可能性が高くなります。
そのため、勤務先とトラブルを起こしたくなければ、規模を拡大させすぎないほうが安心して不動産投資をおこなえるでしょう。
本業に支障を出さないようにする
副業として不動産投資をおこなう場合、本業に支障が出ないよう、いかに効率的に運用をおこなうかも重要です。
物件の管理には入居者募集やクレーム対応、設備点検や修繕計画など面倒な業務がいくつもあるため、本業のある人にとっては大きな負担となってしまいます。
そのため、自分ですべて管理するのではなく、不動産会社に委託することをおすすめします。
委託管理なら運用業務のほとんどを一任できる上、専門家に投資計画の相談もできるため、初心者でも安心して不動産投資をはじめられます。
「不動産会社選び」が手間なく効率的に不動産投資を成功させるカギ
不動産投資を成功させるためには、物件探しから収支計画の立案、購入後の運用まで、さまざまなことを相談できる不動産会社を選びましょう。
専門家のアドバイスを聞きながら、リスクを抑えて利益を最大化するのが不動産投資を成功させるカギです。
ただし、不動産会社によって得意な物件の種類や地域に違いがあるため、まずはいくつかの不動産会社を比較してみましょう。
下記のリンクから、一人ひとりに合った不動産投資会社の診断・一括比較ができるので、不動産会社選びに迷っている人はぜひ利用してみましょう。専任のコンシェルジュも付くので、スムーズに不動産投資をはじめられます。
少ない資金で不動産投資をはじめるなら「小規模投資」もおすすめ
不動産投資に興味はあるものの、資金が足らず物件購入ができないという人もいるでしょう。
そんな人におすすめなのが「小規模投資」です。少ない資産ではじめられる不動産投資なら、初心者でもリスクを抑えた運用が可能です。
おすすめの小規模投資として、
- ワンルームマンション投資
- 中古の戸建て投資
- REIT(リート)
の3つを紹介していきます。
ワンルームマンション投資
ワンルームマンションは、ファミリータイプのマンションより規模が小さいことから初期投資を抑えることが可能です。
少子高齢化にともない単身者は増加傾向にあるため、安定した需要が期待できるということもワンルームマンション投資のメリットです。
入居者が付きやすいため空き室リスクも少なく、安定した収益を見込めます。
中古の戸建て投資
中古の戸建ては安価に売り出されていることが多く、初期投資を抑えて利回りの高い運用が期待できます。
また、戸建て投資は利用方法が豊富な点もメリットです。
例えば、
- 民泊として運用
- シェアハウスとして運用
- 更地にして売却
- 駐車場に転用
など、状況によって運用方法や出口戦略を柔軟に変えられます。
REIT(リート)
REITとは「不動産投資信託」のことで、投資家から集めた資金を元に不動産の運用をおこない、その収益を投資家へ分配する金融商品です。
投資家は1万円程度から出資可能であり、運用自体は専門家に任せることになるので、初心者でも気軽にはじめられます。
また、REITは株式などと同じように証券市場で売買ができるため、現物の不動産より流動性が高い点も大きな特徴です。
現金が欲しいときはすぐに換金できるので、不動産投資に限らず柔軟な資産運用をしたい人にはおすすめの投資方法です。
まとめ
不動産投資は、しっかりと知識を付けておこなえば安定した収益を見込める資産運用です。
会社員ならローン審査で有利な上に、委託管理にすれば時間を取られることもないので、本業が忙しい人でも効率的に運用ができます。
確実に不動産投資で成功したいのであれば、まずは不動産会社に相談して適切な運用方法を教えてもらいましょう。
専門家のアドバイスを聞きつつ自分で試行錯誤を続けることができれば、不動産投資で大きな利益を得ることが可能です。