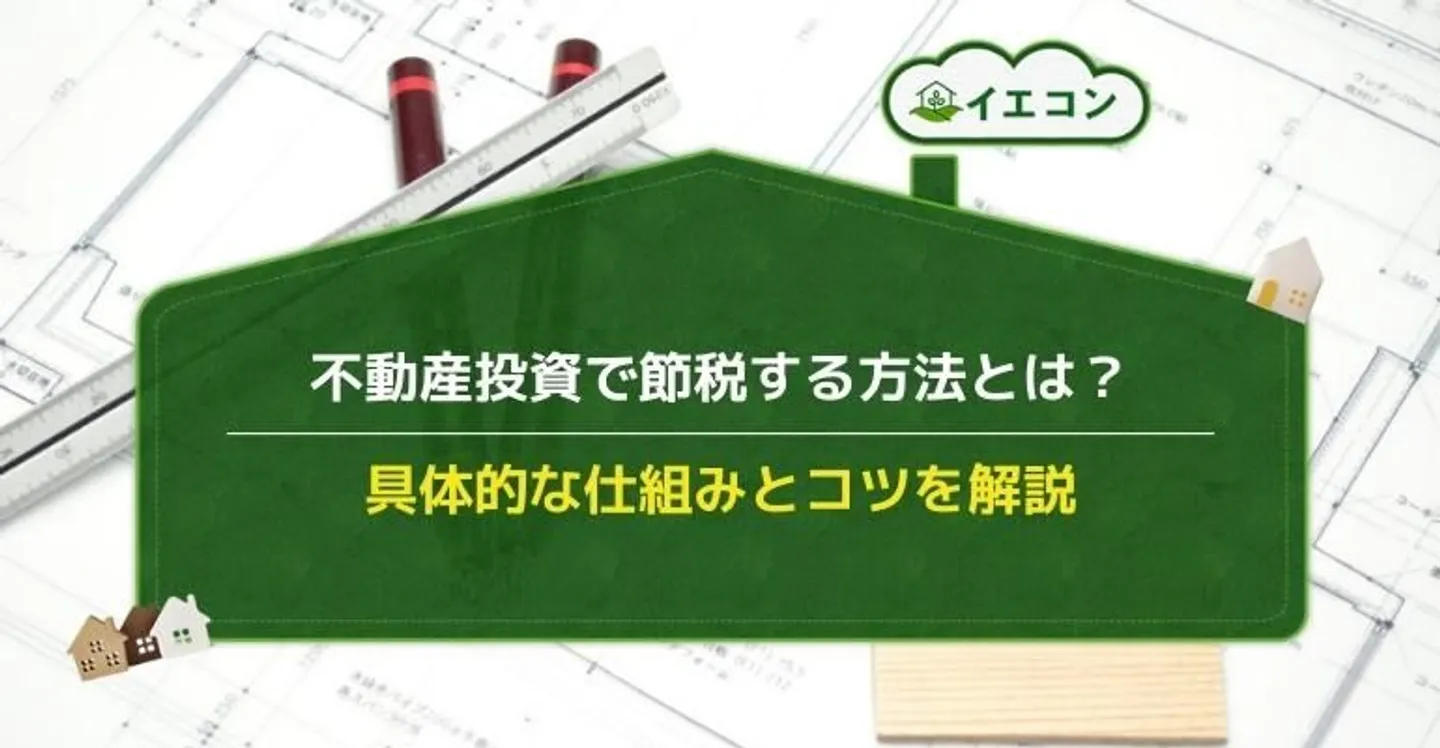不動産投資は、家賃収入や売却益によって利益を得るだけでなく、節税効果も期待できる投資方法です。
しかし、不動産投資による節税の仕組みは複雑で、適切に活用しないと逆効果になることもあります。
この記事では、不動産投資で節税するための基本的な知識や、節税を成功させるためのコツを分かりやすく解説します。これから不動産投資を始めようと考えている人は、是非参考にしてください。
なお、不動産投資を1人で始めるのが不安であれば、不動産投資会社に相談しましょう。節税に関するアドバイスはもちろん、優良物件の紹介や、運用開始後の管理代行まで、一気通貫のサポートを受けられます。
下記リンク先の「イエベスト」では、厳選された不動産投資会社の一括比較が可能です。自分と相性の良い不動産投資会社を見つけて、スムーズかつ的確な不動産投資をしましょう。
>>【プロが最適な投資をアドバイス!】不動産投資会社の一括比較はこちら
なぜ不動産投資が節税につながるのか?
不動産投資が節税につながる理由は、主に以下の2つです。
- 所得税や住民税の対象額を減らせる
- 相続税や贈与税の対象額を減らせる
所得税や住民税を減らせば、毎年の税負担が軽くなり、家計に余裕が生まれます。浮いた分をさらなる投資に使ったり、別の支出にあてたりすることが可能です。
また、相続税や贈与税を減らせば、配偶者や子供に資産を譲る際、相手の負担を軽くできます。
それぞれどのような仕組みで節税になるのか、詳しく見ていきましょう。
>>【プロが最適な投資をアドバイス!】不動産投資会社の一括比較はこちら
所得税や住民税の対象額を減らせる
不動産投資で得た収入は、経費や損失を差し引いた金額(不動産所得)として、所得税や住民税の課税対象となります。
さらに、「損益通算」という処理を行うことで、不動産所得がマイナスとなったとき、赤字分を他の所得から控除できます。
しかし、それだけでは大きな節税効果は生まれません。何より、支出が収入を大幅に上回るような状況では、投資としては失敗と言えます。
そこで重要となるのが、「減価償却」という会計処理です。減価償却をすることで、手元の資金を減らさずに、不動産投資による「会計上の赤字」を作れます。
「損益通算」と「減価償却」の2つが、不動産投資で所得税・住民税を節税するときのキーポイントとなります。
「損益通算」で赤字分を他の所得と合算できる
損益通算とは、所得金額の計算上発生した損失(赤字)を、一定の手順に従って他の所得から控除できる制度です。
例えば、給与所得500万円の会社員が、副業の不動産所得で200万円の赤字を出した場合、課税所得は「500万円-200万円」で300万円となります。これにより、所得税や住民税の納税額も減少します。
また、赤字額が所得額を上回った場合、控除しきれなかった分を翌年以降3年まで繰り越すことも可能です。
例えば、給与所得500万円で、不動産所得で1,200万円の赤字を出した場合、次のように控除されます。
- 損失が発生した年…500万円-1,200万円=-700万円→非課税
- 1年目…500万円-700万円=-200万円→非課税
- 2年目…500万円-200万円=300万円→300万円に課税
- 3年目…500万円-0万円(控除なし)=500万円→500万円に課税
損益通算と繰越控除の適用には、毎年の確定申告(確定損失申告)が必要です。確定申告は毎年2月16日から3月15日までに行う必要があり、居住地を管轄する税務署で申告します。
「減価償却」で手元の資金を減らさずに高額な経費計上ができる
減価償却とは、長期間にわたって使用する資産(不動産の場合は建物)の価値が経年劣化することを考慮して、その耐用年数に応じて毎年一定額を経費計上する会計処理です。
例えば、建物部分が5,000万円の新築アパート(木造)を購入した場合、耐用年数は22年と定められており、毎年約230万円(5,000万円÷22年)を減価償却費として経費にできます。
減価償却費は、実際にお金を支払っていなくても経費計上できるため、不動産所得を圧縮し、納税額を減らすことに繋がります。
また、減価償却費を計上した年度の不動産所得がマイナスになった場合は、前述した「損益通算」が適用されます。つまり、減価償却費が800万円、不動産所得が300万円であれば、差額の600万円をその他の所得から控除できますし、余った分は翌年以降に繰り越すことができるのです。
減価償却の期間を決める「耐用年数」とは?
耐用年数は、新築と中古の場合で設定方法が異なります。
新築の場合、建物の種類に応じて決められた「法定耐用年数」に従います。主な住宅における法定耐用年数は、以下の通りです。
| 木造 | 22年 | |
|---|---|---|
| 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 | 47年 | |
| 金属造(鉄骨造) | 骨格材の肉厚が4㎜超 | 34年 |
| 骨格材の肉厚が3㎜~4㎜以下 | 27年 | |
| 骨格材の肉厚が3㎜以下のもの | 19年 | |
一方、中古物件の場合は、上記の法定耐用年数を基準に、新築からの経年劣化を考慮して計算します。具体的な計算方法は、以下の通りです。
法定用年数×20%
例:木造住宅なら「22年×20%=4年」
(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%)
例:木造住宅で10年経過しているなら「(22年-10年)+(10年×20%)=14年」
「法人化」で税率を下げることも可能
不動産投資を個人で行う場合、不動産所得は総合課税され、所得金額に応じて最大45%(2023年3月現在)の所得税がかかります。一方、不動産投資を法人で行えば、法人税を納めることになり、税率は最大23%(2023年3月現在)となります。
参照:国税庁「法人税の税率」
参照:国税庁「所得税の税率」
つまり、不動産投資事業を法人化することで、最大で半分近くまで税率を下げられるということです。法人化に伴う金銭的負担と節税効果のバランスを考慮すると、年間利益が800万円以上になったあたりが、法人化の検討ラインとする考えが一般的です。
ただし、法人化にはメリットだけでなくデメリットもあります。例えば、会社の設立や運営に費用が発生しますし、減価償却費の計算方法が異なります。
そのため、法人化するかどうかは、個々の状況に応じた判断が必要です。
相続税や贈与税の対象額を減らせる
不動産を相続したときは「相続税」が、贈与したときは「贈与税」が、相手方(相続・贈与を受けた側)に発生します。
これらの税金を計算するときは、課税対象となる「不動産の評価額」が必要になりますが、評価基準の関係上、現金より不動産のほうが評価を下げられます。
つまり、現金より不動産で相続・贈与したほうが、課税対象額を減らせるということです。
具体的にどのような仕組みで、どのくらい低くなるのか、詳しく見ていきましょう。
「課税における不動産の評価額」は時価より下がる
相続税や贈与税の課税対象となる不動産の評価は、土地と建物で異なります。ただし、いずれの場合も、市場価格より低くなるよう定められています。
具体的な評価方法について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
土地の評価方法
土地の場合、「路線価方式」と「倍率方式」の2つの方法で算出されます。それぞれの違いは以下の通りです。
| 路線価方式 | 国土交通省が公表する路線価(1㎡あたりの土地価格)に面積を乗じて評価額を求める。ただし、形状等で補正がかかる場合もある。 例:路線価が10万円で、面積が200㎡なら、「10万円×200㎡=2,000万円」がその土地の評価額。 |
|---|---|
| 路線価方式 | 路線価が定められていない土地に用いられ、エリアごとに設定された倍率を固定資産税評価額に乗じて求める。 例:固定資産税評価額が3,000万円で、そのエリアの評価倍率が1.1の場合、「3,000万円×1.1=3,300万円」がその土地の評価額。 |
そして、路線価の決め方について、国税庁は「公示価格※等の80%程度にする」という方針を取っています。80%としているのは、バブル期に起こった地価高騰への対策という歴史的背景からくるものです。
※公示価格…国が毎年公表する、各地域の土地の適正価格
路線価等は、1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格(時価)の80%程度を目途に評価しています。
以上のことから、土地の相続・譲渡における課税対象額は、市場価格より低い価額になります。
建物の評価
建物(家屋)の場合、課税対象額は固定資産税評価額と同じ金額になります。
※再建築価格…「同じ建物を評価時点で再び新築する」と仮定した場合の費用
参照:国税庁「土地家屋の評価」
固定資産税評価額は各自治体が決めますが、建物の固定資産税は、時価のおおむね50~70%程度となるよう設定される慣例があります。なぜ50~70%なのか、条文などに明確な根拠はありませんが、以下のような理由が挙げられます。
- 「経年劣化による価格補正」と「実態の価格下落」に差異があるから
- 再建築価格に「不動産会社の利益」が乗らないから
- 市場の急激な変動で納税者に負担をかけないため
ただし、数値はあくまで一般的な目安であり、実際の評価基準は自治体によって異なります。
賃貸用物件はさらに評価額が軽減される
賃貸用物件の相続税・贈与税では、下記のような補正がかけられ、自己使用物件よりさらに評価額が軽減されるようになっています。これは、賃貸している物件は、自己使用できる状態と比べて「制限がある状態」とみなされるためです。
| 補正 | 内容 | 補正割合 |
|---|---|---|
| 借地権割合 | 借地権(建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権)にかかる補正 | 30~90%(路線価図により土地ごとに設定) |
| 借家権割合 | 貸家にかかる補正 | 30%(全国一律) |
| 賃貸割合 | 一棟アパート等、複数の独立部分がある物件で賃貸されている割合 | 各独立部分の床面積の合計÷賃貸されている独立部分の床面積の合計 |
| 貸家建付地の評価 | 貸家の敷地を評価するときの方法 | ※評価式 通常の評価額-通常の評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合 |
参照:国税庁「借地権の評価」
例えば、以下のような一棟アパートを相続したとします。
- 通常の土地の評価:3,000万円
- 建物部分の評価:6,000万円
- 借地権割合:50%
- 賃貸割合:100%(満室)
この場合、アパートの評価額は以下のように計算します。
3,000万円-3,000万円×50%×30%×100%=2,550万円
建物部分の評価額
6,000万円×30%=1,800万円
アパート全体の評価額
2,550万円+1,800万円=4,350万円
借地権割合と借家権割合を適用することで、不動産全体の評価額は9,000万円から4,350万円に減少しました。これにより、相続税や贈与税の納税額も減らすことができます。
具体的な節税効果とシミュレーション
不動産投資による節税効果は、具体的にどれくらいなのでしょうか?ここでは、一般的なケースをもとにシミュレーションしてみましょう。
所得税・住民税の節税効果
所得税・住民税の節税効果は、不動産所得が赤字であれば損益通算によって得られます。
例えば、給与所得500万円の会社員が不動産投資を始めて、以下のような物件を購入したとします。
- 物件種別:ワンルームマンション(鉄骨鉄筋コンクリート造、築20年)
- 購入価格:3,000万円
- 家賃収入:月額10万円(年間120万円)
- 耐用年数:(47年‐10年)+(10年×0.2)=31年
- 償却率:0.033
- 減価償却費:3,000万円×0.033=99万円
- 管理費:月額5,000円(年間6万円)
- 修繕費:年間12万円
- 租税公課:年間30万円
この場合、不動産所得は以下のように計算されます。
・不動産収入120万円
・経費:減価償却費99万円+管理費6万円+修繕費12万円+租税公課30万円=147万円
・不動産所得:120万円-147万円=-27万円
不動産所得が-27万円となったため、この金額を給与所得から差し引き、「500万円-27万円=473万円」が課税対象となります。
所得税が税率20%と42万7,500円の控除(330万円~694万9,000円の場合)、住民税はおおむね税率10%(自治体による)なので、計算すると次のようになります。
・節税前:500万円×20%-42万7,500円=57万2,500円
・節税後:473万円×20%-42万7,500円=51万8,500円
・節税効果:57万2,500円-51万8,500円=5万4,000円
・節税前:500万円×10%=50万円
・節税後:473万円×10%=47万3,000円
・節税効果:50万円-47万3,000円=2万7,000円
参照:国税庁「所得税の税率」
参照:総務省「個人住民税」
計算の結果、所得税と住民税を合わせて8万1,000円の節税となりました。このように、不動産投資が赤字であれば、所得税・住民税の節税効果が得られます。
相続税・贈与税の節税効果
相続税・贈与税の節税効果は、不動産の評価額が時価よりも低くなることで得られます。
ここでは、配偶者に不動産を贈与するケースを想定し、以下のような条件でシミュレーションします。
- 物件種別:一棟アパート
- 時価:1億円(土地5,000万円、建物5,000万円)
- 賃貸割合:100%(満室)
- 借地権割合:50%
この場合、贈与される不動産の評価額は以下のように計算できます。
・通常の評価額は時価の80%と仮定し、「5,000万円×80%=4,000万円」とする。
・貸家建付地の評価方式を反映すると、「4,000万円-4,000万円×50%×30%×100%=3,400万円」となる。
・固定資産税評価額は時価の60%と仮定し、「5,000万円×60%=3,000万円」とする。
・借家割合と賃貸割合を反映すると、「3,000万円×30%×100%=900万円」となる。
3,400万円+900万円=3,900万円
このように、贈与される不動産の評価額は3,900万円となりました。贈与税の計算式にあてはめると、以下のようになります。
・節税前:1億円-110万円(基礎控除額)×55%-640万円(控除額)=4,799万5,000円
・節税後:3,900万円-110万円(基礎控除額)×55%-640万円(控除額)=1,444万5,000円
・節税効果:4,799万5,000円-1,444万5,000円=3,355万円
結果、不動産の評価額が時価よりも低くなることで、贈与税を2,520万円節税できたことになります。このように、不動産の評価額が時価よりも低くなることで、相続税や贈与税の節税効果が得られます。
>>【プロが最適な投資をアドバイス!】不動産投資会社の一括比較はこちら
節税目的なら中古物件がおすすめ
ここまで、不動産投資による節税効果と、その仕組みについて解説しました。しかし、これから不動産投資を始める人が気になるのは、「結局どんな物件に投資すれば良いか?」だと思います。
物件選びには投資目的や予算なども影響しますが、節税を中心に考えるなら、中古物件を購入することをおすすめします。さらに言えば、「耐用年数がなるべく短い物件」です。
収益性を考えると、築古物件の購入は抵抗を感じるかもしれませんが、減価償却の関係上、中古物件のほうが節税効果は高くなります。
新築より中古のほうが「減価償却による節税効果」が高い
減価償却費は、単純に言えば「不動産価格÷耐用年数」で計算されます。3,000万円の物件で、耐用年数が10年なら、毎年300万円を経費計上できるということです。
そして、中古物件の耐用年数は「新築からの経年劣化を考慮する」と解説しました。つまり、中古物件の耐用年数は、必ず新築より短くなります。
耐用年数の長さによる減価償却費の違いを比較すると、以下のようになります。
- 耐用年数が10年の場合…3,000万円÷10年=300万円
- 耐用年数が20年の場合…3,000万円÷20年=150万円
耐用年数が長いと、毎年計上できる減価償却費が少なくなってしまうのです。
もちろん、耐用年数が何年であろうと、最終的な総減価償却費は変わりません。短期間に高く計上するか、長期間で細かく計上するかの違いです。
しかし、不動産投資は耐用年数を迎える前に売却することも少なくありません。早めに売却する場合、減価償却費も短期間で計上したほうがお得です。
また、経年による価格変動もあります。「耐用年数が切れてから売ろう」と考えたとして、10年後に売るより、20年後に売る方が、価格が下落している可能性は高いでしょう。
以上のことから、節税を目的として不動産投資では、新築より中古物件のほうがおすすめと言えます。
購入費用も安いので始めやすい
中古物件のもう一つのメリットは、購入費用が安いことです。中古物件は新築物件に比べて価格が安くなる傾向があります。
これから不動産投資を始める人にとって、必要となる資金は少ないほうが不安は少ないでしょう。また、価格下落が起こっても、大きな損失を抱えずに済みます。
また、投資を始めるにあたって、取り扱いやすい点もメリットです。賃貸物件としての実績がある分、空室率や現在の家賃などがはっきりしており、今後のシミュレーションも立てやすくなります。
>>【プロが最適な投資をアドバイス!】不動産投資会社の一括比較はこちら
節税目的で不動産投資を始めるときの注意点
不動産投資による節税効果は大きなメリットですが、知識不足で間違った不動産投資をすると、かえって損失を生んでしまうかもしれません。
そこで、節税目的で不動産投資を始める場合には、以下のような注意点を把握しておきましょう。
- 不動産の維持費がかかる
- 減価償却が終わると節税効果が小さくなる
- 売却するときには譲渡所得税がかかる
- 価格変動のリスクがある
- 収支計画通りにいかないリスクがある
不動産の維持費がかかる
不動産投資をすると、固定資産税や管理費、修繕費などの維持費がかかります。経費計上による控除が所得税節税のポイントですが、赤字が膨らめば損失に繋がります。
特に重要なのは、「キャッシュフロー」という現金の流れです。手元にどのくらいの現金があるのか、いつ収入や支出があるのか、常に収支を把握する必要があります。
収支をチェックしながら適切な運用を行い、損失が節税効果を上回らないよう気をつけましょう。
減価償却が終わると節税効果が小さくなる
不動産投資の節税で主な要因となるのが、建物の減価償却費です。減価償却費がなければ「会計上の赤字」を作るのは難しくなります。
しかし、減価償却費は建物の取得価額に達するまでしか計上できません。つまり、減価償却が終わると、節税効果も小さくなります。
キャッシュフローの悪化を防ぐためには、減価償却が終わる前に売却するなどの対策が必要です。運用開始前から、出口戦略(トータルでプラスになるような撤退方法)を考えて投資計画を立てるようにしましょう。
売却するときには譲渡所得税がかかる
不動産を売却するときは、譲渡所得税がかかります。譲渡所得税は、売却価格から取得価額や必要経費を差し引いた利益に対して課される税金です。
譲渡所得税の税率は保有年数によって変わり、最高で39.63%(所得税30.63%、住民税9%)にもなります。売却時に大きな利益を出すと、節税した分以上に税金がかかる恐れもあります。
一方、売却で損失が生まれると、その赤字分を他の所得から控除できますが、節税効果より損失分が大きければ意味がありません。
節税効果と売買損益のバランスを考え、タイミング良く売却する必要があります。
価格変動のリスクがある
不動産の評価額は市場価格によって変動します。相続税や贈与税の節税効果は不動産の評価額が時価に影響を受けるため、想定通りにいかない場合があります。
例えば、不動産市況が好調であれば、評価額も高くなり、節税効果も低くなります。物件の価値が上がるのは喜ばしいことですが、相続・贈与の相手方は税負担が重くなり、かえって迷惑に思うかもしれません。
逆に、不動産市況の悪化で評価額が下がれば節税効果は高くなりますが、物件自体の「資産としての魅力」は下がります。
このように、不動産の価格が上がっても下がってもリスクはあるので、相続・贈与のタイミングや市況の変化に注意が必要です。
収支計画通りにいかないリスクがある
不動産投資を始めるときには、収支計画を立てることが重要です。収支計画では、家賃収入や経費、収支バランスやキャッシュフローを予測します。
しかし、収支計画はあくまで予測であり、実際には想定外の事態が起こるかもしれません。例えば、以下のようなリスクが考えられます。
- 空室率が上昇する
- 家賃引き下げや滞納が発生する
- 修繕費や管理費が予想以上にかかる
- 金利が上昇する
- 火災や地震などの災害が発生する
- 入居者の自殺などで事故物件化する
これらのリスクが発生すれば、収支計画通りにいかなくなり、節税効果も減少する可能性があります。リスク対策をしっかりと行い、余裕を持った収支計画を立てましょう。
>>【プロが最適な投資をアドバイス!】不動産投資会社の一括比較はこちら
不動産投資による節税を成功させるコツ
不動産投資による節税は、知識や経験が必要です。理屈の上でも理解しても、実際に取り組むとなると困難が伴います。
不動産投資で節税を成功させるためには、以下のコツを押さえておきましょう。
- 不動産の維持費がかかる
- 減価償却が終わると節税効果が小さくなる
- 売却するときには譲渡所得税がかかる
- 価格変動のリスクがある
- 収支計画通りにいかないリスクがある
専門家のアドバイスを聞く
不動産投資は、法律や税制、市場の読み取り方など、さまざまな知識が必要です。自分で勉強することも大切ですが、専門家にも的確なアドバイスを聞くようにしましょう。
例えば、以下のような専門家に相談することができます。
- 不動産会社…不動産の選び方や購入方法、管理方法などについて
- 税理士…確定申告や節税対策、法人化のメリット・デメリットなどについて
- 弁護士…契約書やトラブル対応、相続手続きなどについて
- 司法書士…登記手続きや相続手続きなどについて
- 金融機関…融資の条件や返済方法などについて
専門家に相談することで、自分では気づかなかった投資方法や、運用上のリスクを知れるかもしれません。
特におすすめなのが、「不動産投資会社」という、投資関連を専門に取り扱う不動産会社への相談です。投資計画の立案から、物件の紹介、管理委託など、不動産投資に関する幅広い事柄をサポートしてくれます。
企業によってサービス内容や投資の方針に違いがあるため、まずは複数社に相談し、相性の良い不動産投資会社を探すことがおすすめです。下記リンクから利用できる「イエベスト」では、厳選された不動産投資会社を無料で一括比較できるので、ぜひ活用してみましょう。
>>【プロが最適な投資をアドバイス!】不動産投資会社の一括比較はこちら
「長期的な計画」と「定期的な見直し」を行う
不動産投資は、一時的な節税目的で行うものではありません。長期的な視点で計画を立てることが大切です。
不動産投資の収益性は、物件の選び方や購入時の条件だけでなく、市場の動向や税制の変更などにも影響されます。そのため、不動産投資を始めたら、定期的に収支状況や物件の評価額、税金の負担などを見直すようにしましょう。
見直しを行うことで、節税効果が低下したり、キャッシュフローが悪化したりするリスクを回避できます。また、見直しを通して、新たな節税対策や投資機会を見つけられるかもしれません。
「甘い話」には警戒する
不動産投資には節税効果がありますが、それだけで不動産投資を決めてしまうと、後悔するかもしれません。不動産投資は、節税だけでなく、収益性やリスクの考慮も必要です。
しかし、不動産投資は動くお金が大きい分、悪徳業者も数多くいます。特に、以下のような「甘い話」をしてくる業者には注意しましょう。
- 節税効果や収益などを強調し、リスクを説明しない
- 物件の評価額や家賃相場を過大に見積もる
- 物件の状態や立地条件を隠す
- 契約内容や手数料についての説明が不明瞭
- 「早く契約しないと物件がなくなる」と焦らせる
- 書類説明を行わずに署名・捺印を求めてくる
悪徳業者に騙されないためには、自分でも情報収集を行い、知識を持っておくことが重要です。疑問や不安があれば説明を求め、しっかりと納得できる条件でのみ契約しましょう。
>>【プロが最適な投資をアドバイス!】不動産投資会社の一括比較はこちら
まとめ
不動産投資は、所得税や住民税、相続税などの節税効果が期待できるメリットがあります。しかし、ただ税金のことだけ考えるのではなく、運用や売却タイミングなども考慮する必要があります。
自分の目的や予算に合った物件を選ぶためには、市場調査や物件比較をしっかりと行うことが必要です。また、不動産投資会社や税理士など、専門家の意見も参考にしましょう。
不動産投資で節税することは可能ですが、節税だけを目的にするのではなく、不動産投資全体のバランスを考えることが重要です。