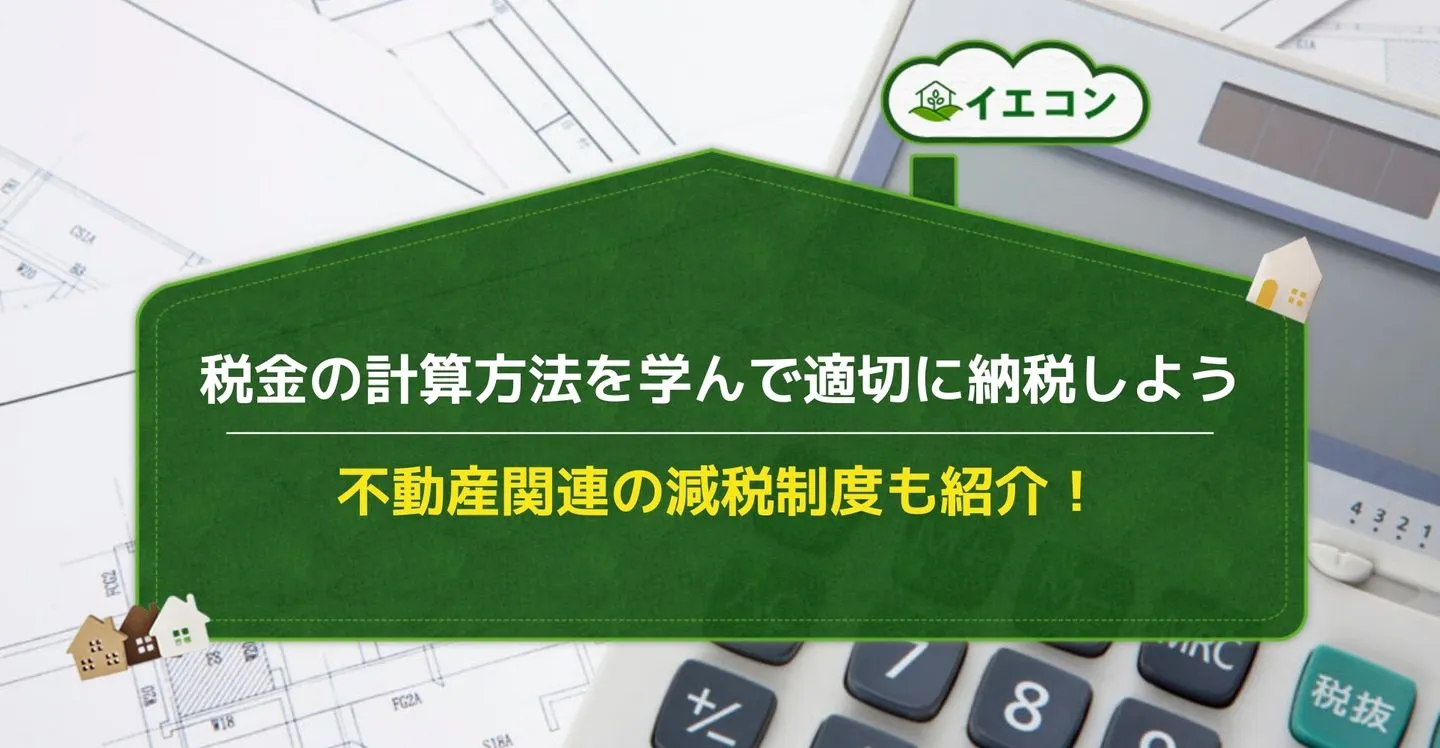不動産の取引には、じつに多くの税金が関係しています。
とくに重要なのは、不動産取得税・固定資産税・譲渡所得税の3つです。これらの税金は、不動産の取得・保有・売却でそれぞれ課税されます。
税金の計算は非常に複雑であり、些細なミスで課税額が大きく変わる恐れもあります。
税金のことで困ったら、税理士に相談しましょう。税理士なら、個々の状況にあわせて最適な節税のアドバイスも可能です。
税理士と相談しつつ、適切な申告をおこないましょう。
不動産を取得したときにかかる「不動産取得税」
売買や贈与で土地・建物を取得した人には、不動産取得税が課されます。中古住宅の購入や建売だけでなく、新築・増築なども課税対象です。
不動産の取得後、都道府県から納税通知書が届きます。不動産取得から4~6ヶ月程度で届くのが一般的ですが、1年以上かかる場合もあるため、忘れないよう注意しましょう。
支払期日は都道府県ごとに異なりますが、おおむね送付から1ヶ月程度で設定されています。
不動産取得税の計算方法
不動産取得税は、下記の計算で算出されます。
固定資産税評価額は、のちほど解説する固定資産税を算出するための評価額です。固定資産税評価額を調べるには、下記3つの方法があります。
- 自治体から毎年5~6月頃に送られる納税通知書を確認する
- 役所で固定資産税評価証明書を取得する
- 役所で固定資産課税台帳を閲覧する
新築の建物などでまだ固定資産税評価額が決定していない場合には、都道府県ごとに定める基準によって評価額が設定されます。
不動産取得税の軽減制度
不動産取得税の軽減制度として、代表的なものは下記のとおりです。
- 税率の軽減
- 新築住宅やその敷地の税額軽減
- 中古住宅やその敷地の税額軽減
状況によって使える軽減制度にも違いがあるので、実際に申告するときは各自治体の税事務所や、税理士に相談しましょう。
税率の軽減
2021年現在、不動産取得税の特例として税率が3%となっています。つまり、税額は「固定資産税評価額×3%」で計算します。
適用期限は2024年3月31日までです。ただし、その後も延長したり、反対に中止される可能性もあります。
税金については、常に最新の情報を調べることが大切です。
新築住宅やその敷地の税額軽減
新築住宅を購入した場合、課税標準額(固定資産税評価額)から1,200万円が控除されます。つまり、新築住宅の計算式は「(固定資産税評価額-1,200万円)×3%」となります。
要件として「課税床面積が50㎡(戸建て以外の貸家は40㎡以上)~240㎡」であることが必要です。
また、認定長期優良住宅(国指定の期間が認定する、長期間使用するための構造や設備を有している住宅)の場合は、控除額が1,300万円となります。
新築住宅の敷地については、課税標準額(固定資産税評価額)が半額となり、さらに下記のうち金額の多いほうが控除されます。
- 45,000円
- (土地1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2(200㎡限度))×3%
つまり、新築住宅の敷地は「(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額」で計算します。
中古住宅やその敷地の税額軽減
中古住宅を購入した場合、その住宅が建てられた年度に応じて、一定額が課税標準額(固定資産税評価額)から控除されます。つまり、計算式は「 (固定資産税評価額−控除額)×3%」となります。
要件としては、下記の3点のいずれかに該当しなければいけません。
- 1982年1月1日以降に建築された住宅であること
- 新耐震基準に適合しているか、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものであること
- 入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施する一定の中古住宅であること
控除される金額は、下記のとおりです。
- 1997年4月1日以降・・・1,200万円
- 1997年3月31日以前・・・1,000万円
- 1989年3月31日以前・・・450万円
- 1985年6月30日以前・・・420万円
- 1981年6月30日以前・・・350万円
- 1975年12月31日以前・・・230万円
- 1972年12月31日以前・・・150万円
- 1954年7月1日~1963年12月31日・・・100万円
中古住宅の敷地については、新築住宅の敷地と同じ控除・計算式が適用されます。
不動産取得税が発生しないケース
不動産取得税は文字どおり「不動産を手に入れたときの税金」ですが、非課税となるケースもあります。下記にあげるのはその一部です。
- 遺産相続や遺贈による取得
- 土地区画整理事業などでの換地の取得
- 譲渡担保による所有権移転
- 公共の用に供する道路の取得
- 宗教法人や学校法人の取得
また、各種控除などを適用した価額が一定の金額を下回ると、課税されなくなります。この一定の金額を「免税点」といいます。
- 土地を取得した場合・・・10万円以下
- 新築などで建物を取得した場合・・・1戸につき23万円以下
- 既存の建物を売買によって取得した場合・・・1戸につき12万円以下
ただし、下記の場合は前後の取得をあわせて「1つの不動産取得」とみなされるので注意しましょう。
- 土地を取得して、1年以内に隣接する土地を取得した場合
- 家屋を取得して、1年以内にその家屋と一構となるべき家屋を取得した場合
参照:e-Govポータル「地方税法第73条の4~第73条の7」
不動産を保有しているとかかる「固定資産税」
不動産を保有している間にも、定期的に課税されるのが固定資産税です。
毎年1月1日時点での不動産情報をもとに課税され、各自治体から毎年5~6月頃に納税通知書が送られてきます。
納税は一括払いか、年4回の分割払いのどちらかを選択できます。
固定資産税の計算方法
固定資産税の計算式は、下記のとおりです。
不動産取得税の項目でも触れましたが、固定資産税評価額は納税通知書を確認するか、役所に問い合わせるとよいでしょう。
また、固定資産税評価額は3年ごとに評価替えをおこないます。
建物に関しては「同じ建物を、評価時の物価で新しく建てた場合の費用」をもとに、経年による減価を差し引いて計算します。
土地に関しては、再評価時の地価が基準です。ただし、急激な高騰があったときは税負担を軽減するため、段階的に評価額を上げて変化を緩やかにする「負担調整措置」が取られます。
固定資産税の軽減制度
固定資産税の主な軽減制度としては、下記のものがあげられます。
- 住宅用地に対する固定資産税評価額の軽減
- 新築住宅の税額軽減
- 改修工事による税額軽減
固定資産税の軽減制度は申告不要で適用されるものと、申告が必要なものがあります。税理士に相談しつつ、申告できる軽減制度がないか確認しましょう。
住宅用地に対する固定資産税評価額の軽減
住宅用地(住宅の敷地として使用する土地)は、固定資産税評価額が軽減されます。適用に申告は不要です。
軽減率は住宅用地の面積によって異なります。
| 区分 | 面積 | 軽減率 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地 | 住宅1戸につき200㎡までの土地 | 固定資産税評価額×1/6 |
| 一般住宅用地 | 住宅1戸につき200㎡を超えた部分で、住宅床面積の10倍までの土地 | 固定資産税評価額×1/3 |
また、住宅が店舗などと併用である場合、住宅用地の面積は下記の住宅用地の率を敷地面積に乗じて計算します。
| 住宅の種類 | 住宅用地の率 |
|---|---|
| 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 |
・居住部分が1/4以上1/2未満の場合は0.5 ・居住部分が1/2以上3/4未満の場合は0.75 ・居住部分が3/4以上の場合は1 |
| 上記以外の併用住宅 |
・居住部分が1/4以上1/2未満の場合は0.5 ・居住部分が1/2以上の場合は1 |
ちなみに、建物を解体し、更地の状態で1月1日を迎えると、この特例は受けられないので注意しましょう。
新築住宅の税額軽減
2022年3月31日までに建てられた新築住宅には、税額が一定期間、1/2まで減額される制度があります。
要件や期間などは下記のとおりです。
| 床面積 |
・通常の住宅は50㎡~280㎡ ・一戸建て以外の貸家住宅は40㎡~280㎡ ・店舗などとの併用住宅は居住部分の床面積が50㎡~280㎡ |
|---|---|
| 減額される割合 | ・120㎡までの床面積相当分に相当する税額から1/2 |
| 減額期間 |
・3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅は新築後5年間 ・上記以外は新築後3年間 ・長期優良住宅の場合は上記に2年追加 |
原則として申告をしなくても適用されますが、認定長期優良住宅の場合は税事務所への申告が必要なので注意しましょう。
改修工事による税額軽減
下記の改修工事をおこなった場合、一定の税額が軽減されます。
| バリアフリー改修工事 | 100㎡の床面積相当分までの固定資産税額を1/3減額 |
|---|---|
| 耐震改修工事 | 対象となる家屋の住宅部分のうち120㎡を超える部分及び非住宅部分において、固定資産税を1/2減額 |
| 省エネ改修工事 | 当該住宅の一戸あたり120㎡の床面積相当分まで、固定資産税を1/3減額 |
それぞれに申告期限や適用条件が細かく設定されているため、税理士に相談してみましょう。
固定資産税が発生しないケース
固定資産税にも、不動産取得税と同じように免税点があります。
- 土地の場合・・・30万円以下
- 建物の場合・・・25万円以下
納税義務者の所有する土地や建物の課税標準額を集計し、合計額が上記の免税点以下と判定されれば、固定資産税は課税されません。
また、所有している不動産が公共の用に供するものである場合も、固定資産税は課税されません。
不動産を売却したときにかかる「譲渡所得税」
不動産を売却して利益(譲渡益)が出ると、譲渡所得税を課税されます。譲渡所得税は、給与所得や事業所得などの他の所得とは、分離して課税されることになります。
不動産を売却した年の翌年に、確定申告をしなければいけません。
確定申告は毎年2月16日から3月15日の間に、税務署で申告します。
譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税は「譲渡所得×税率」で求めます。譲渡所得については、次の項目で解説します。
税率は所有期間によって変わり、具体的な数値は下記のとおりです。
|
短期譲渡所得 (所有期間5年以下) |
39.63%(所得税30.63%、住民税 9%) |
|---|---|
|
長期譲渡所得 (所有期間5年超え) |
20.315%(所得税15.315%、住民税 5%) |
課税対象となる「譲渡所得」の計算
譲渡所得税を計算するには、最初に課税対象となる譲渡所得を求めなければいけません。
譲渡所得の計算式は、以下のとおりです。
取得費は、次の2通りの方法で算出される金額のうち、いずれか金額の多い方を選択できます。
| 実額法 | 不動産の購入代金と取得に要した費用を合計した金額から、減価償却費を差し引いた金額 |
|---|---|
| 概算法 | 譲渡収入金額の5% |
譲渡費用とは、不動産を売却するためにかかった費用を指しています。具体的には、不動産会社に支払った仲介手数料や、登記の際に支払った登録免許税などです。
譲渡所得税の軽減制度
譲渡所得税に関する軽減措置は、状況によってさまざまな制度があります。
下記は代表的な制度を抜粋したものです。個々の状況にあわせて適切な軽減制度を利用するには、税理士の力を借りることをおすすめします。
- 居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
- 特定居住用財産を買換え等した場合の譲渡益課税の繰延制度
居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
マイホームの買換えに伴って譲渡損失が生じた場合、譲渡損失をその年の他の給与所得や事業所得などから控除(損益通算)する制度です。
損益通算しても控除しきれなかった損失については、翌年以降3年間繰越控除できます。
過去に住んでいたマイホームについて申告するときは、引っ越してからから3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければいけません。
その他の条件については、国税庁のWebサイトを参照してください。
参照:国税庁「マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき」
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
住宅の譲渡に際して損失が出た場合、一定の要件を満たす場合に限り、譲渡損失を他の所得から控除(損益通算)する制度です。
「住宅ローンの償還期間が10年以上の残高であること」が条件となっています。
その他の条件については、国税庁のWebサイトを参照してください。
参照:国税庁「住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき」
特定居住用財産を買換え等した場合の譲渡益課税の繰延制度
住宅の買換えに伴い譲渡所得が生じた場合、譲渡所得税の課税を100%繰り延べることができるというものです。
耐火建築物については新築後25年以内のもの、または新耐震基準に適合していることが証明されたもの、または既存住宅売買瑕疵保険に加入しているものであることが要件です。
例外として、耐震基準適合証明書がある非耐火建築物に関しては、上記の要件に当てはまらなくとも適用可能とされています。
その他の条件については、国税庁のWebサイトを参照してください。
まとめ
不動産は、取得時・保有中・売却時と、あらゆる場面で税金が発生します。
それぞれの税金でルールや税率、適用される軽減制度が異なるため、計算は非常に複雑といえるでしょう。
少しのミスで課税額が増えたり、申告漏れで追徴課税があるかもしれません。税金の専門家である税理士と相談しつつ、適切な税申告を心がけましょう。