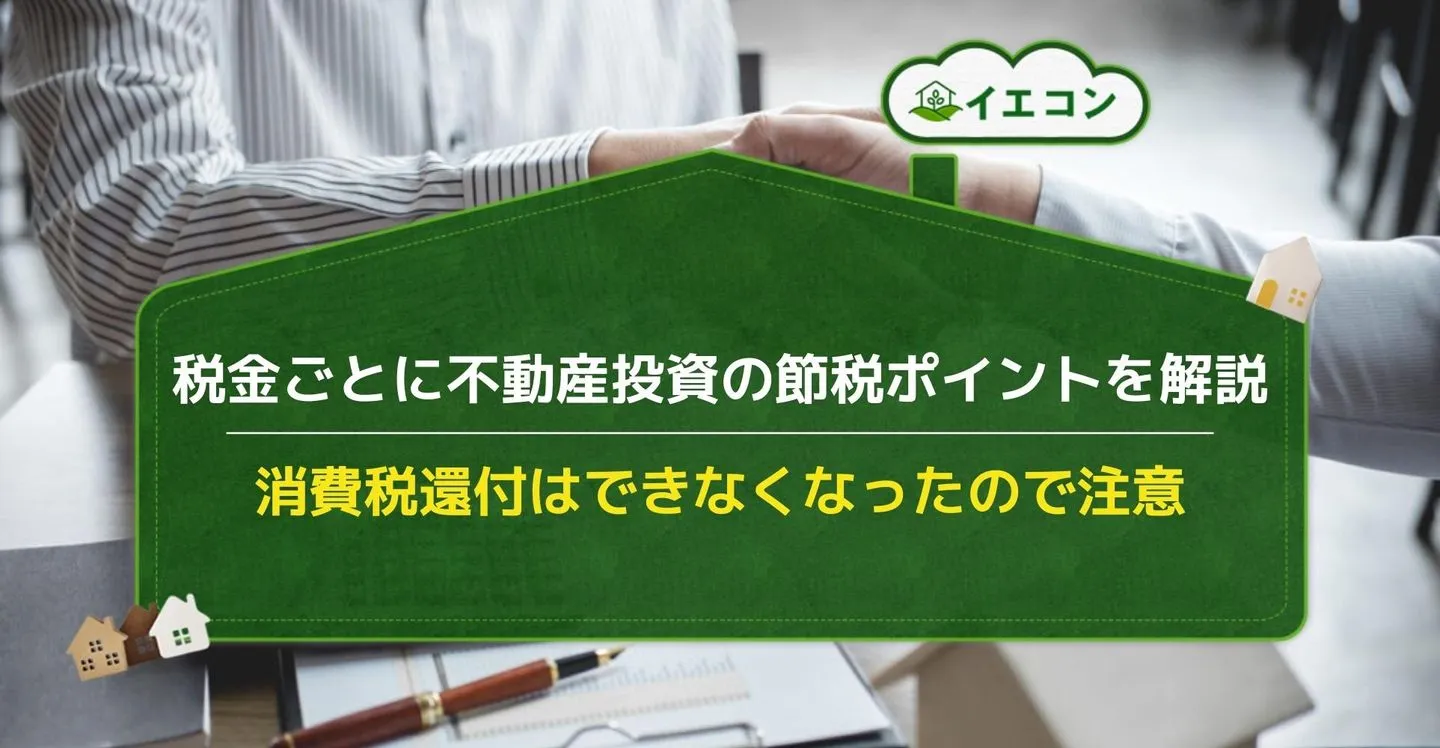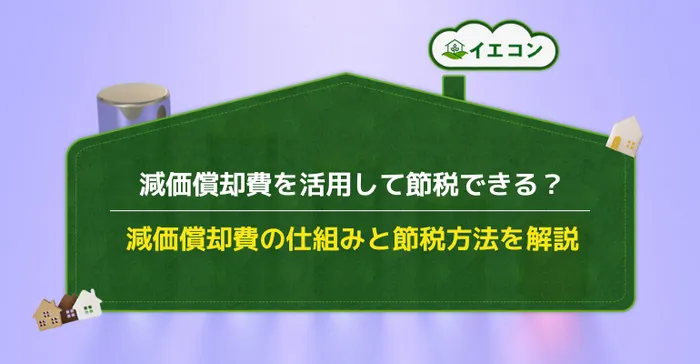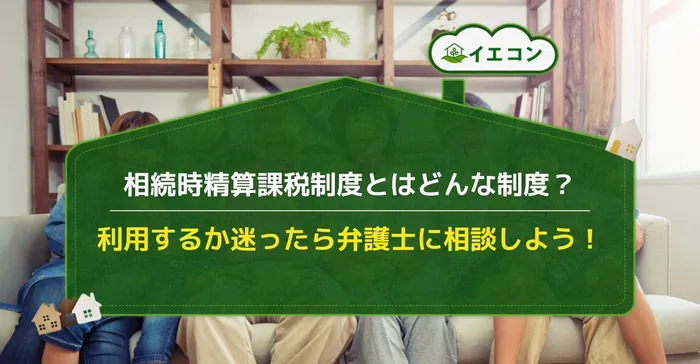「不動産投資は税金対策になる」といわれることがありますが、具体的にどんな仕組みで節税に繋がるのかわからない人は多いでしょう。
不動産投資に関する税金が複数あるため、それに伴う節税方法もいくつかの種類があります。
まずはどんな税金が課されるのか把握してから、それぞれの節税方法を理解しましょう。
ただし、税制は常に改正される可能性があるため、いつでも最新の情報をチェックすることが大切です。
「自分でチェックするのは大変だ」という人は、不動産や税金の専門家に相談してみましょう。自分であれこれ考えるより、的確な節税方法をアドバイスしてもらえます。
不動産投資で所得税・住民税を節税できる仕組み
不動産投資で節税できる代表的な税金が「所得税・住民税」です。
| 税金 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 所得税 | 国税 | 1年間の所得(収入から必要経費を差し引いたもの)に対して国から課せられる税金。 |
| 住民税 | 地方税 | 所得税と同様、1年間の所得額が課税の基準となるが、納付先は国ではなく市区町村や都道府県。 |
不動産投資の所得が赤字になった場合、給与所得などほかの所得と相殺して全体の所得金額を下げることが可能です。これを「損益通算」といい、不動産投資で節税できるといわれる根拠となります。
「赤字が出ているのであれば節税できても損しているのでは?」と思うかもしれませんが、会計上の制度をうまく活用することで、実質的な損もなく節税が可能です。
所得税・住民税の節税を可能にする「減価償却」とは?
減価償却とは、固定資産の取得にかかった費用の計上を、その固定資産の耐用年数に応じて配分する仕組みです。
簡単にいえば、不動産の購入費用を購入した年にまとめて経費計上するのではなく、数年に分けて少しずつ計上していくという手続きになります。
一方、10年間で240万円ずつの減価償却をおこなえば、毎年の課税所得が360万円となり、トータルで節税額が大きくなります。
※実際の減価償却期間や金額は、不動産の構造や用途、築年数などによって異なります。
減価償却については下記の記事でも解説しているので、よろしければ参考にしてください。
所得税・住民税の節税には「確定申告」が必要
所得税と住民税の節税を受けるには、毎年2月16日~3月15日におこなわれる「確定申告」をする必要があります。確定申告は、1年間の所得を申告し、課税額を確定させる手続きです。
サラリーマンで収入が本業の給与しかない場合、勤務先の年末調整によって確定申告は不要となります。しかし、不動産投資などで給与以外の収入がある場合、確定申告をしなければ延滞税や無申告税が加算されるので注意しましょう。
なお、所得税と住民税で課税のされ方が異なるため、確定申告後の流れも下記のように違いがあります。
| 所得税 | 給与所得がある場合、毎月の給与からおおよその所得税を差し引き、年末調整で当年の所得を確定させてから過不足を清算するのが原則。そのため、確定申告で損益通算をすると納め過ぎた所得税が還付される。 |
|---|---|
| 住民税 | 住民税は当年度の所得額から次年度の税額を算出するため、確定申告で損益通算をすると次年度の住民税が低くなる。 |
確定申告の流れ
確定申告は、次の流れで手続きをおこないます。準備に時間のかかるものもあるため、早めの準備が大切です。
また、自分で手続きするのが不安な場合、税務の専門家である税理士に相談するとよいでしょう。
- 添付書類の取得
- 決算書や確定申告書の作成
- 申告手続き
1.添付書類の取得
不動産投資の確定申告では、下記の書類が必要となります。
| 書類 | 取得先 |
|---|---|
| 入居者と交わした賃貸契約書 | 売買契約時に不動産業者から取得 |
| 家賃の送金明細 | 毎月、不動産業者から送付 |
| 固定資産税通知書 | 4~6月頃に役所から送付 |
| 不動産ローンの借入返済表 | 融資実行後、金融機関から取得 |
| 損害保険証券 | 損害保険契の約成立後、保険会社から取得 |
| 管理費・修繕積立金等の領収書やレシート | 各費用の支払い後 |
| その他の支出の領収書やレシート(交通費や交際費など) | 各費用の支払い後 |
| 源泉徴収票(サラリーマンの場合) | 毎年1月~2月頃に勤務先から取得 |
不動産を購入した年は、上記以外に不動産売買契約書や売渡精算書(どちらも不動産会社から取得)が必要です。
2.決算書や確定申告書の作成
確定申告にあたって作成しければならないのが、決算書と確定申告書です。
決算書は確定申告の種別によって、作成する書類も異なります。いずれの申告方法も、不動産投資収支の帳簿を作成しておく必要があります。
| 申告方法 | 作成する書類 | 内容 |
|---|---|---|
| 青色申告 | 青色申告決算書 | 記入項目は複雑だが、家族給与の経費計上や計上赤字繰り越し、最高65万円または10万円の特別控除などが適用される。月々の収支を複式簿記によって帳簿付けしておく必要がある。 |
| 白色申告 | 収支内訳書 | 手続きは簡単だが、家族給与の経費計上や計上赤字繰り越し、特別控除などが適用されない。月々の収支は単式簿記による簡易帳簿のみで済む。 |
なお、青色申告をする場合には、不動産投資の開始から2か月以内に税務署へ青色申告承認申請書を提出する必要があるため注意しましょう。
確定申告書については、青色申告も白色申告も「確定申告書B」という申告書を使用します。
参照:国税庁「青色申告制度」
申告手続き
各種書類の準備ができたら、税務署で申告をおこないます。申請は税務署の窓口や郵送、インターネットの電子申告が可能です。
確定申告の時期は税務署が大変混み合うので、なるべく早い時期に、時間に余裕をもって申告しましょう。
電子申告なら自宅からでも申告可能ですが、事前申請とICカードリーダライタの購入が必要になります。
不動産投資で「相続税・贈与税」を節税できる仕組み
不動産投資をすることで、相続税と贈与税を節税することも可能です。相続税・贈与税の節税では「相続税評価額のルール」がポイントとなります。
不動産の場合、相続税も贈与税も国税庁が定める「相続税評価額」によって算出します。しかし、この相続税評価額は不動産の時価に対して7~8割程度になるよう調節されます。
用途が限定されたり、入居者がいると明け渡し請求が困難といった理由から、不動産は現金と比べて自由度が低いとみなされ、評価額も低くなるのです。
そのため、単純に現金5,000万円を相続・贈与する場合は額面通りの金額で税金を算出しますが、時価5,000万円の不動産を相続・贈与した場合は3,500万円~4,000万円程度の評価額で課税されます。
「相続時精算課税制度」で贈与税を大幅に節税することも可能
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に対して贈与するときに使える制度です。
贈与時には課税せず、相続が発生した時にまとめて課税するという方法になります。基本的に贈与税より相続税のほうが控除額は大きい※ため、トータルで節税することができるのです。
※通常の贈与税は「年間110万円の基礎控除」と「10万円~400万円の税額控除」がある一方、相続税は「3,000万円+法定相続人×600万円」の基礎控除がある。
ただし、相続時精算課税制度を使えるのは2,500万円分の資産までで、それを超える資産を贈与したときは、超過分に対して一律20%の贈与税が発生するため注意しましょう。
相続時精算課税制度については下記の記事でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
「消費税還付スキーム」は2020年より原則として利用不可
不動産投資による節税として、過去に「消費税還付スキーム」という方法がありました。不動産投資を事業化することで、消費税を大幅に節税することが可能だったのです。
消費税を負担するのは消費者ですが、実際に納付をおこなうのは事業者です。一方、事業者は商品を仕入れる際、仕入先に消費税を支払っています。
そのため、事業者が実際に納付する消費税は「消費者から預かった消費税-仕入れ時にかかった消費税」ということになり、これを「仕入税額控除」といいます。
しかし、居住用賃貸建物の仕入れにかかる消費税は、上記の「仕入れ時にかかった消費税」として計算できないのが原則です。
そこで、不動産オーナーは「自動販売機スキーム」や「金地金スキーム」といった方法で物件取得時の消費税の還付を受けられるようにしていたのです。
しかし、これらの消費税還付スキームは、法の抜け穴を使って本来なら受けられない還付を受けている状態であり、度々問題視されていました。
そのため、2020年の法改正より、居住用賃貸建物の取得に係る課税仕入れ等については、仕入税額控除の適用から除外することを明確にされたのです。
そのため、現在は不動産投資における消費税還付スキームは事実上不可能となっています。
まとめ
ここまで不動産投資の節税方法について解説しましたが、実際に節税しようとすると多くの知識や税制上の手続きが必要です。
また、税制は改正を繰り返しているので、常に最新の制度を確認する必要があります。
節税について迷ったときや不安なときは自分一人で解決しようとせず、専門家の意見を聞いてみましょう。
不動産投資の専門家なら、自分では思いもよらない節税方法を提案してもらえる可能性があります。
適切なアドバイスのもと、効率的に不動産投資をおこないましょう。