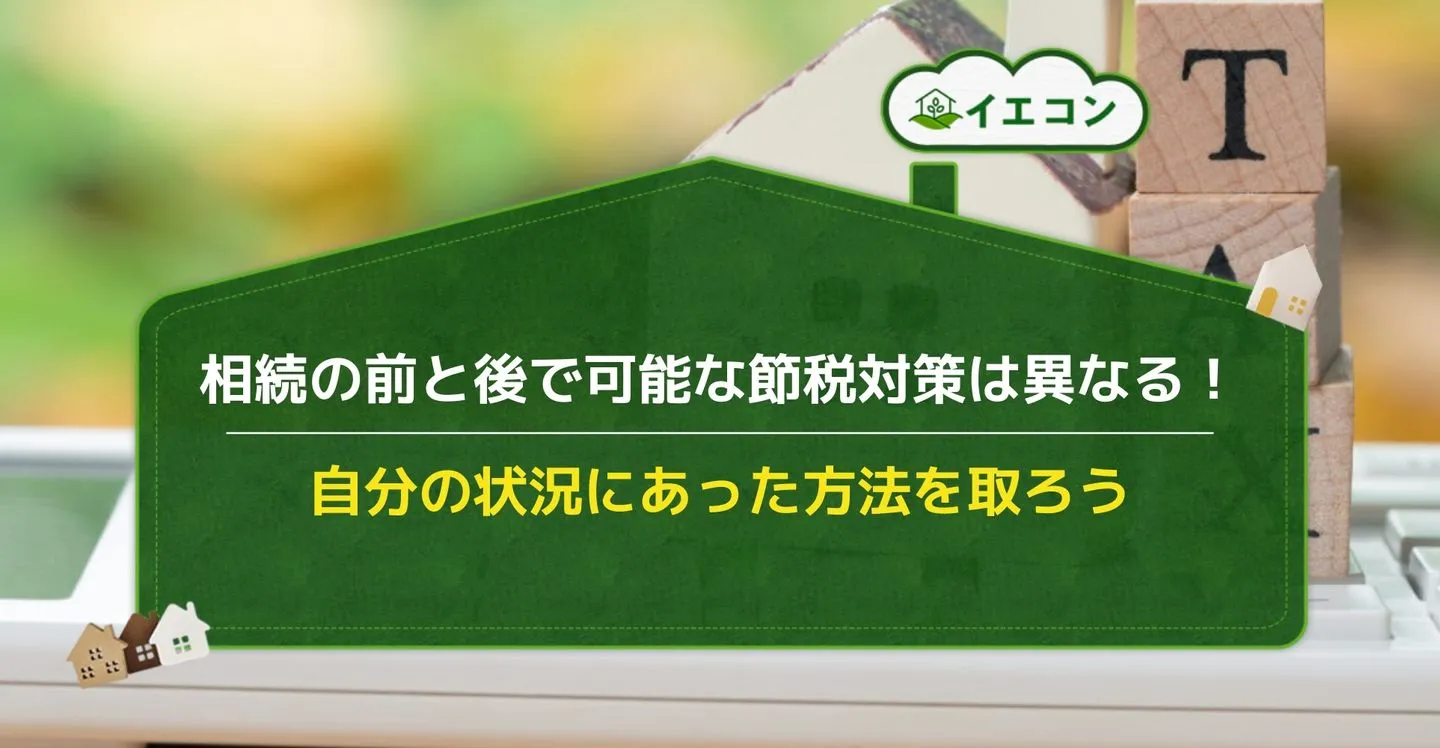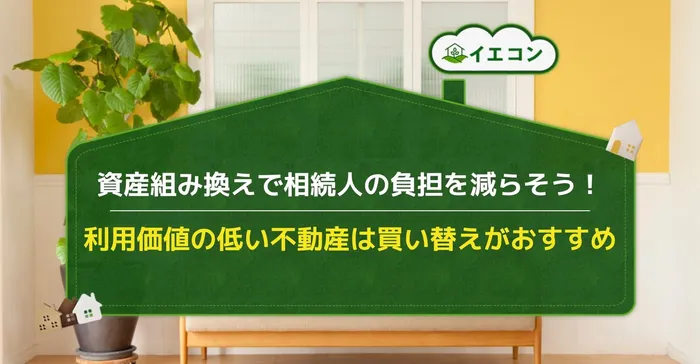相続財産の総額が多ければ多いほど、負担する相続税も大きくなります。「税金対策をおこなって、少しでも多くの遺産を残したい」という人も多いでしょう。
不動産の節税対策には、さまざまな方法があります。うまく組み合わせれば、大きな節税効果が期待できます。
節税のことや、税務署での手続きに不安がある場合、税理士に相談しましょう。税理士なら、税負担が軽くなる最大限の方法もアドバイスできます。
また、相続不動産の売却も検討している場合、弁護士と連携した買取業者に相談してみましょう。
弁護士と連携した買取業者なら、相続問題から不動産の売却・税金まで、総合的なサポートが可能です。
相続発生前の節税対策

まずは相続発生前、つまり被相続人ができる税金対策を紹介します。
具体的には、以下の通りです。
- 不動産を賃貸する
- 夫婦間で居住用不動産を贈与する
- 基礎控除を活用して毎年110万円分ずつ贈与する
どの節税対策が自分に合っているのか、慎重に選ぶことが大切です。次の項目から詳しく解説するので、参考にしてみてください。
【対策1】不動産を賃貸する
不動産を賃貸することで、評価額を下げて節税できるケースがあります。
評価額の計算における賃貸物件は「借地」「借家」「貸家建付地(賃貸用建物と一緒に敷地として貸し出している土地)」の3つがあります。
それぞれの評価方法が以下の通りです。
借家・・・建物の評価額-建物の評価額×借家権割合×賃貸割合
貸家建付地・・・土地の評価額-土地の評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合
賃貸物件を評価するときは「借地権割合」「借家権割合」「賃貸割合」が用いられます。これらの割合を計算に入れるため、賃貸物件の相続税は安くなるのです。
借地権割合は国税庁が公表している「路線価図・評価倍率表」で確認できます。A~Gで表されており、例えばCであれば借地権割合は70%です。
借家権割合は、ほぼすべての地域で30%と定められています。
賃貸割合は、入居率に比例します。満室であれば100%、部屋の半数が埋まっていれば50%です。
賃貸物件の評価例
下記の条件で、賃貸物件の評価額を計算してみましょう。
- 土地にアパートを建てて経営している
- 建物の評価額が3,000万円、土地の評価額が5,000万円
- 借家権割合30%、借地権割合70%、賃貸割合90%
建物部分の評価は、下記のとおりです。
続いて、土地部分(貸家建付地)は下記の評価額となります。
本来は土地と建物を合わせて8,000万円の評価額でしたが、アパートを経営することで6,245万円まで下がりました。
このように、賃貸することで不動産の評価額が下がり、相続税も抑えられるのです。
【対策2】夫婦間で居住用不動産を贈与する
婚姻期間が20年以上の夫婦は、居住用不動産または居住用不動産の購入資金の贈与に対して最高2,000万円の配偶者控除があります。
ただし、贈与された年の翌年3月15日までに、贈与された不動産または贈与された資金で購入した不動産に、贈与を受け取った人が住んでいなければなりません。
また、その後も継続して住み続ける見込みがないと判断された場合、特例が認められないケースもあります。
そのため、贈与された居住用不動産をすぐに売却すると、この特例は利用できないので注意しましょう。
参照:国税庁「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」
【対策3】基礎控除を活用して毎年110万円分ずつ贈与する
贈与税には、毎年110万円の基礎控除があります。年間で受け取った贈与額が110万円以内なら、課税されません。
この基礎控除を利用して、財産を少しずつ贈与する方法があります。つまり、相続予定の財産を年間110万円ずつ贈与し、課税を免れる方法です。
基本的には現金を贈与する方法ですが、不動産の共有持分(所有権の一部)を少しずつ譲ることも可能です。
ただし、例えば「1,100万円を10年に分けて贈与する」というように、最初から財産を分割して贈与する約束があった場合、課税される恐れがあります。
あくまで「110万円の贈与が、たまたま10年間続いた」という形でなければいけません。詳しくは、税理士に相談してみましょう。
相続発生後の節税対策

相続が発生した後、つまり相続人がおこなえる節税対策もあります。
相続後に使える、主な特例や節税対策は以下の通りです。
- 小規模宅地等の特例を利用する
- 土地を分筆する
次の項目からそれぞれ解説していきます。
【対策1】小規模宅地等の特例を利用する
自宅や店舗、事務所などのために使用していた宅地を相続する際に、敷地面積400㎡までの宅地における評価額を最大80%減額できる制度が「小規模宅地等の特例」です。
評価額を大幅に減額する特例が用意されている理由は、宅地は相続人の生活基盤になり得る財産だからです。
多額の相続税が課せられて宅地や家を売却しなければならなくなると、相続人が生活基盤を失ってしまうことになりかねません。このような事態を防ぐために、特例が設けられています。
ただし、適用するにはさまざまな要件があります。詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
参照:国税庁「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
【対策2】土地を分筆する
2つ以上の土地に分筆することによって、評価額を引き下げられるケースがあります。
原則として、土地の評価額は路線価を基準に計算します。例えば、200㎡の土地Aが「路線価1㎡あたり30万円の道路(30万円/㎡)」と「路線価1㎡あたり20万円の道路(20万円/㎡)」に接しているとしましょう。
2つの道路に接している土地を評価する場合、高い方の路線価が採用されます。そのため、土地Aの評価額は「200㎡×30万円=6,000万円」となります。
次に、上記の土地Aを土地B・土地Cに100㎡ずつ分筆したとしましょう。このとき、土地Bは2つの道路に、土地Cは路線価20万円/㎡の道路にのみに接するよう分筆します。
すると、土地Bを評価するときは「路線価30万円/㎡」が、土地Cを評価するときは「路線価20万円/㎡」が適用されます。それぞれの評価額は以下の通りです。
土地Cの評価額=100㎡×20万円=2,000万円
合計の評価額=3,000万円+2,000万円=5,000万円
このように、分筆する前の評価額に比べて1,000万円低くなります。その結果、相続税も減額することが可能というわけです。
相続税における控除の種類

相続税においてはさまざまな控除が用意されており、主な控除は下記の7種類があります。
- 相続税の基礎控除
- 配偶者の税額控除
- 未成年者の控除
- 障害者の控除
- 「前の相続から10年以内の相続」の控除
- 贈与税額の控除
- 外国で徴税された税金の控除
次の項目から、それぞれの控除を詳しく解説します。
相続税の基礎控除
相続税には、相続財産の基礎控除があります。基礎控除額の計算式は以下の通りです。
相続財産の相続が基礎控除額を下回る場合、相続税は一切かかりません。
法定相続人の人数次第では、課税されないということです。そのため、相続人の人数と相続財産の総額は、しっかりと確定しておくことが大切です。
配偶者の税額控除
配偶者の相続は「1億6,000万円までの相続分」または「法定相続分」のうち、金額の高いほうまで控除できます。
つまり、最低でも1億6,000万円、法定相続分が1億6,000万円を超えればそれ以上の金額が、相続財産から控除されます。
未成年者の控除
未成年者控除は、未成年の相続人が満20歳になるまでの年数1年につき、10万円が控除されます。
これを計算式に表すと、以下の通りです。
※1年未満の期間は切り捨て
例えば、相続人が10歳である場合、上記の計算式に当てはめると以下のようになります。
ちなみに、未成年者の相続税額よりも控除額が大きく、差し引いた後も控除額が余ることがあります。
余った控除額については、扶養義務者(被相続人の配偶者や兄弟姉妹など)の相続税額から差し引くことも可能です。
障害者の控除
相続人が障害者の場合、相続人が満85歳になるまでの年数1年につき10万円を控除できます。特別障害者(とくに重篤な障害をもつ人)の場合は、年数1年につき20万円です。
障害者控除額の計算式を表すと、以下の通りです。
※1年未満の期間は切り捨て
例えば、障害者の相続人が35歳だとすると、以下の通りになります。
また、未成年控除と同様に、控除額が余ってしまった分は扶養義務者の相続税から差し引くことが可能です。
「前の相続から10年以内の相続」の控除
相続税には「相次相続控除」という制度もあります。
控除額は、一次相続で納税した金額から1年につき10%の割合で減額されたものです。
一次相続で支払った相続税が100万円だとすると、1年目に二次相続をおこなった場合の控除額は90万円、2年目の場合は80万円と、控除額が小さくなっていきます。
参照:国税庁「相次相続控除」
贈与税額の控除
相続開始前の3年以内に被相続人から贈与された財産は、相続税の課税価格に加算されます。
ただし、贈与されたときに支払った贈与税は、加算される金額から控除されます。
例えば、300万円の贈与があった場合、贈与税を35万円納めたとしましょう。
贈与から3年以内に相続が発生した場合、相続税の課税価格には300万円が加算されます。しかし、贈与税35万円をすでに支払っているので、その分は控除されるというわけです。
外国で徴税された税金の控除
日本の税制度では、海外にある財産の相続も徴税されます。しかし、現地の税制度でも徴税されている場合は二重徴税になってしまうので、その分を控除することが可能です。
これを「相続税の外国税額控除」といい、控除できる金額は下記2つのうち少額になるほうです。
- 外国で徴税された「相続税に相当する税」
- 相続税の額×(海外の財産の額÷相続人の相続財産の額)
まとめ
不動産相続の節税には、基礎控除や特例などさまざまな制度があります。制度を最大限適用すれば、相続税を大幅に減額できるでしょう。
ただし、各種制度の適用や相続税の計算は複雑です。些細なミスで税務署に指摘され、追徴課税が発生するかもしれません。
不動産相続の節税は、税理士に相談することをおすすめします。
税理士なら税金の具体的な対策方法をアドバイスしてくれますし、税金の計算や申告といった実務も代行してくもらえます。