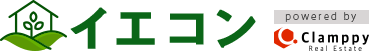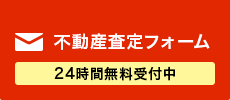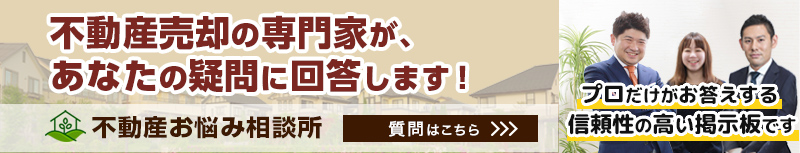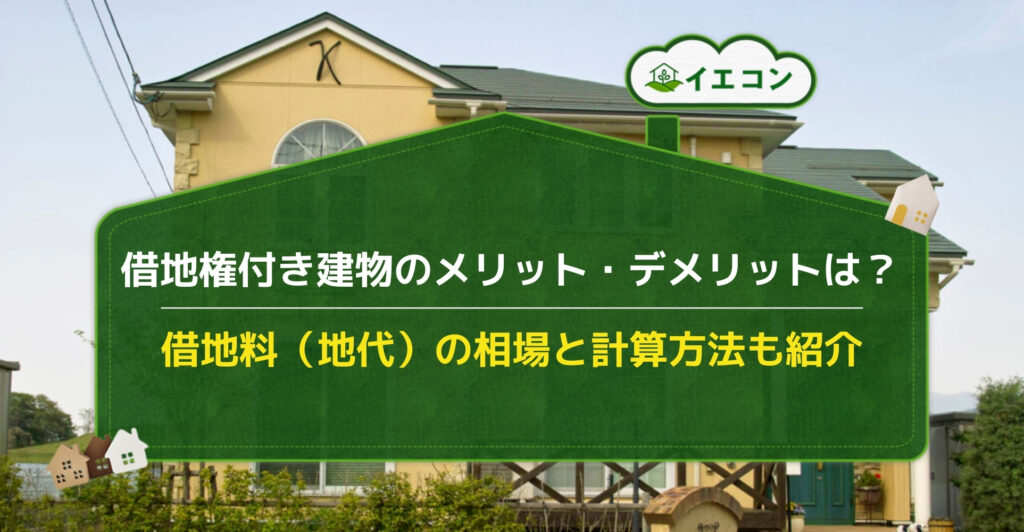
マイホームを購入しようと思って物件を探している時「借地権」と記載された相場より安い物件を見かけたことはないでしょうか。
借地権付き建物は価格が安いことが魅力ですが、価格が安い分のデメリットもあります。
とくに、購入時の融資が受けにくい、建物を自由に売却・改築できないといったデメリットは不便といえるでしょう。
もしも、借地権付き建物を手にした後、手放したいと考えているなら、借地権専門の買取業者に買取してもらうとよいでしょう。
専門買取業者なら、借地権付きの建物であっても最短48時間で買取できるので、まずは無料査定を受けてみることをおすすめします。
目次
借地権付き建物を所有するメリット・デメリット
借地権付き建物は、借地上に建てられた建物のことです。
借地権付き建物は、更地を購入するときと比べると、非常に安く購入できます。
ただし、借地権は土地に住む「権利」のみを借りている状態のため、土地を自由に利用できません。
次の項目から、借地権付き建物のメリット・デメリットを見ていきましょう。
【メリット1】価格が安い
建物の敷地が借地の場合、所有権を取得している土地に比べて利用の制限が多いです。
建物が古くなったからといって建替えなどの増改築をするにも、地主の承諾と一定の承諾料が必要です。
また、家を使わなくなったから売却したいと思ったときも、地主の承諾と承諾料が必要になります。
このように借地権付きの建物は、その借地上の建物を含めて自由に変更することができないデメリットが多いです。
そのため、借地権付き建物は、土地の所有権を取得している建物の価格よりも安く設定されることが多いです。建物の状態や立地にもよりますが、所有権を取得する場合の60~80%の価格が相場になっています。
【メリット2】税金がかからない
土地を購入して所有権を取得した場合、その時点で不動産取得税が課税されます。
さらに毎年の税金として固定資産税、建物が都市計画区域に建てられている場合は都市計画税も課税されることになります。
しかし、借地権付き建物であればその敷地は借地、つまり土地を取得していることにはならないので、土地の部分に対する不動産取得税はかかりません。
また、固定資産税や都市計画税も土地の部分についても課税されません。
土地の部分にかかる税金は地主が納めることになります。
【デメリット1】融資を受けにくい
通常、不動産を購入するときは土地と建物を担保に住宅ローンを組みます。
しかし、借地権付き建物の場合、借地への抵当権設定を地主が承諾することはほとんどありません。
そのため、抵当権を設定することになるのは建物のみとなり、担保価値が小さくなります。
借地上の建物に抵当権を設定すると、その効力は借地権にも及ぶというのが一般的な解釈ですが、それでも担保価値は小さいため融資可能額も低くなることが多いです。
借地権付き建物は融資を受けられる条件が厳しく、受けられたとしても通常の住宅ローンより少なかったり、金利が高かったりするというデメリットがあります。
【デメリット2】地代がかかる
借地権付き建物の場合、購入後、地主に毎月地代を支払う必要があります。
借地借家法に基づく普通借地権の存続期間である「30年間」地代を支払い続けたとしても、土地の所有権を取得するときに必要な金額に比べ、安くなることがほとんどです。
それでも、毎月の地代に抵抗を感じる方もいますので、その点が借地権付き建物を購入するデメリットといえます。
【デメリット3】増改築時に地主の承諾が必要
借地契約に増改築禁止の特約がある場合がほとんどです。
そして、借地権付き建物を増改築したいなら、地主の承諾を受ける必要があります。
もしも、許可なく増改築にあたるリフォームやリノベーションをしたときには借地契約を解除される可能性もあるので気をつけてください。
【デメリット4】建物を第三者に売却するときには地主の承諾が必要
建物を売却するときには、借地権もセットで売却することになります。
そして、借地権を第三者に売却するときには必ず、地主の承諾と一定の承諾料が必要です。
借地権付き建物について売買契約を結ぶときには、地主の譲渡承諾書といった書面の提出が求められ、承諾を得られない場合には売買契約も成立しません。
万が一、地主の承諾なく借地権付き建物を売却した場合には、契約違反となり借地契約解除の対象となります。
また、借地権の譲渡を地主から認められないときには、裁判所から地主の承諾に代わる許可を得ることができます。
このような場合、必要な手続きをすべて個人で進めるのは難しいので、借地権に詳しい不動産会社に相談するようにしましょう。
売却したいなら
底地買取専門の
当社にお任せください!
借地料(地代)の相場と計算方法
借地権付き建物を購入したら毎月、地代がかかるとお伝えしました。
そして、その土地の立地や利用状況によっても異なるため、借地料には明確な基準はありません。
ただし、一般的には、住宅地であれば固定資産税と都市計画税の合計額の2~3倍が相場と言われています。
借地料(地代)の計算方法は4つ
借地料を計算するときに用いられる方法は、主に4種類あります。
- 積算法
- 公租公課倍率法
- 収益分析法
- 賃貸事例比較法
次の項目から、それぞれの計算方法を詳しく見ていきましょう。
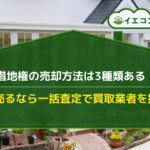
(1)積算法
積算法はその土地を貸したときに土地貸主が得たい利回りから逆算して計算する方法です。計算式は次のようになります。
期待利回りの算出は収益還元法という評価方法に基づいて出しますが、計算方法が複雑で専門的な知識が必要となるため、概算で2%程度として借地料を求めることが多いです。
また必要経費は、固定資産税と都市計画税の合計額と考えて問題ありません。
(2)公租公課倍率法
固定資産税と都市計画税など、その土地を所有していることでかかる税金を基準に一定の倍率を掛けて計算します。
一般的には2~3倍で計算します。
それぞれの税率は、固定資産税が固定資産税評価額の1.4%、都市計画税が固定資産税評価額の最大0.3%で合計1.7%です。
それの3倍とすると、年間に納める地代は固定資産税評価額の5.1%となります。
(3)収益分析法
収益分析法は借地上に建てられた建物が住居としてではなく、事業のために使われる場合に用いられる計算方法です。
賃借人が行う事業において、その土地が事業の利益にどれくらい貢献したかを基準に計算します。
ただし、利益を想定し、その中でもさらに土地の貢献度を求めるというのは一個人が行うにはほとんど不可能です。
そのため、収益分析法で計算するときには専門家へ依頼されています。
(4)賃貸事例比較法
賃貸事例比較法では、その土地の周辺地域で立地条件などが近い複数の賃貸事例から土地の形状、環境などの要素を比較して借地料を計算します。
しかし実際には、借地料の金額の情報が手に入ることは難しく、条件に合う賃貸事例そのものが少ないです。
そのため、あまり使われる計算方法ではありません。
まとめ
借地権はトラブルが発生することも多く、「借地権付き」の物件は購入時に避けられがちなのは事実です。
しかし、通常の不動産購入では手が出ないような人気の立地でも、手頃な価格でマイホームを持てるというメリットもあります。
借地契約の契約期間は、最低でも30年と非常に長い契約です。
だからこそメリットとデメリット、自分自身の将来計画など総合的な視点から考えて決めることが大切です。
また、借地権付き建物を購入しようか迷われている場合は専門知識を持ったプロである不動産会社へ相談することをおすすめします。
借地権のメリット・デメリットでよくある質問
「通常の土地に比べて価格が安い」「税金がかからない」といったメリットがあります。
「融資を受けにくい」「毎月、地代がかかる」「増改築時に地主の承諾が必要」「建物を第三者に売却するときには地主の承諾が必要」といったデメリットがあります。
「固定資産税と都市計画税の合計額」の2~3倍が相場と言われています。例えば、固定資産税と都市計画税の合計額が20万円だった場合、年間の借地料は40万~60万円です。
「積算法」「公租公課倍率法」「収益分析法」「賃貸事例比較法」といった方法があります。計算することが困難な場合は、税理士へ依頼してみましょう。
借地権付き建物はあまり需要が高くありません。そのため、借地権専門の買取業者へ売却するとよいです。【借地専門の不動産業者】借地の買取窓口はこちら