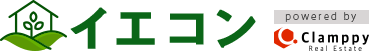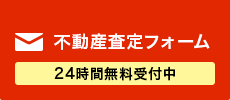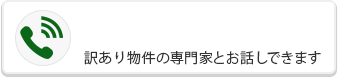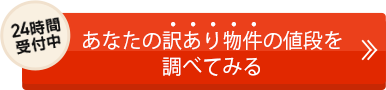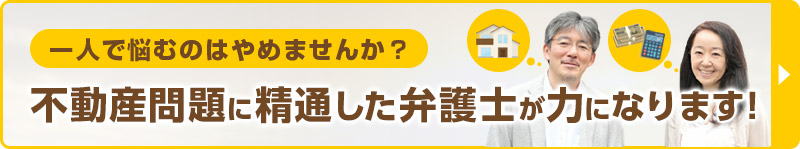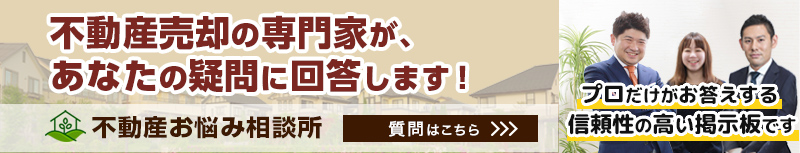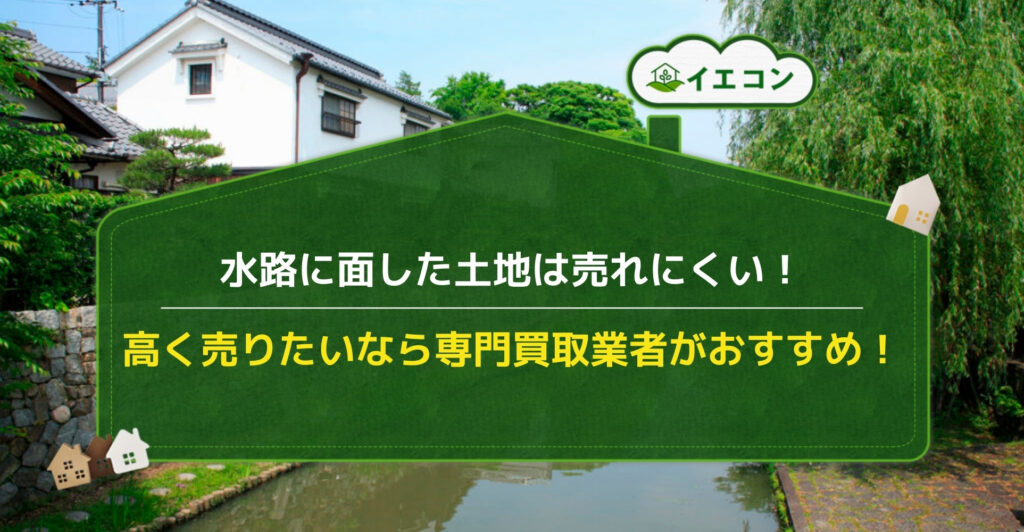
河川や用水路など、水路に面している土地は多くのデメリットを抱えています。
水害や地盤沈下のリスクに加え、建築・再建築不可の土地である可能性も高いといえます。
水路に面した土地の売却は、そういったデメリットを1つずつ調査し、売却前後でトラブルにならないよう慎重に対策することが大切です。
売却活動に手間や費用をかけられない場合、訳あり物件専門の買取業者に現状のまま買い取ってもらうことも検討してみましょう。
訳あり物件専門の買取業者なら、水路に面している土地のメリットとデメリットを熟知しているため、高額査定と最短数日のスムーズな買取が可能です。まずは無料査定を利用して、水路に面した土地の具体的な価格や、売却に向けたアドバイスをもらうとよいでしょう。
目次
水路に面している土地はデメリットが多く売れにくい
土地はいずれかの面が道路に面しているのが一般的です。
しかし、農地が広がるエリアでは、道路ではなく水路に面している土地もあります。
水路とは、用悪水路とも呼ばれており、かんがい用または排泄用の水路を指します。田畑を潤すための水路(用水)と使用後の水を排泄するための水路(悪水)の2つの水路があるのです。
使用後の水を排泄するための水路は、衛生上の観点から地下を通っているのが一般的です。
そのため、道路に面しているのは、ほとんどが田畑を潤すための水路といえます。
田畑を潤すための水路であれば、衛生上の問題もないため、土地を売却する際にもほとんど影響がないと思われがちです。
しかし、水路に面した土地にはデメリットが多くあるため、売れにくくなってしまいます。
水路に面した土地のデメリットについて、くわしく見ていきましょう。
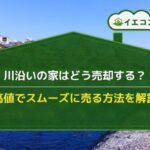
デメリット1.建築不可の可能性がある
土地が水路に面している場合、建物を建設できない恐れがあります。
水路に面している土地は、建築基準法の接道義務を満たしていないことがあります。その場合に建物を建設すると、建築基準法違反になるからです。
つまり、建築確認の際に許可が下りず、接道義務を満たしていない土地には建物を建設できません。
例えば、一般国道、都道府県道、市町村道などの公道は建築基準法の定める道路ですが、私道は建築基準法の定める道路ではないので注意が必要です。
接道義務を満たすには、建築基準法で定める道路に2m以上接している必要があります。
なお、水路に面していても、接道義務を満たした土地であれば、問題なく建物を建てることが可能です。
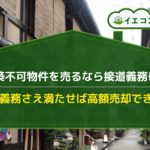
再建築不可の可能性がある
水路に面している土地で接道義務を満たしていなければ、建築不可になります。
しかし、既にマンションや戸建て住宅が建設されている場合もあるでしょう。
そのような物件は、建築基準法の改正前に建設されており、建物が建設された時点では建築基準法を満たしていたことから「既存不適格建築物」として扱われます。
既存不適格建築物であっても、すぐ「建物を壊さなくてはならない」というわけではありません。
ただし、既存不適格建築物を壊して新しく建て直そうとする場合には、最新の建築基準法が適用されるので再建築できません。
接道義務を満たしていない建物付きの土地を購入しても、建物を建て替えられないため、価値の低い不動産だと判断されます。買主がなかなか見つかりにくいともいえるでしょう。
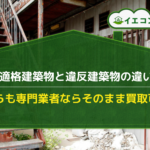
デメリット2.軟弱地盤の可能性がある
土地が水路に面していれば、土地の水分量が他の土地よりも多いです。
水分量が多い土地は地盤が弱くなるため、建物を建てる際には補強工事が必要になります。
土地の購入後には、補強工事の費用を買主が負担するため、買主の費用負担が大きくなります。
そのため、一般的な土地の相場よりも価格を下げないと、なかなか買主が見つからない可能性があるので注意しましょう。
また、契約後に軟弱地盤であることが発覚して、補強工事が必要になった場合、瑕疵担保責任を問われる可能性もあります。
買主とのトラブルを避けるためにも、売主は水路に面している土地であることをしっかりと告知しておいた方がよいでしょう。
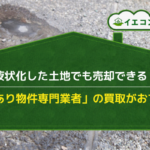
デメリット3.水路から水が溢れる恐れがある
水路は川からの分流であることが多く、雨が降って流量が多くなった場合は、水路から水が溢れる可能性もあります。
そうなると、建物に浸水被害が生じる恐れもあります。
こういったデメリットがあるため、水路に面した土地を売却することは困難だと言えます。

水路に面している土地の売却方法
水路に面している土地は売却価格が安くなりやすく、買主も見つかりにくいです。
しかし、売却方法を工夫すればスムーズに高く売却できるかもしれません。
水路に面している土地を売却する方法として以下の2つが挙げられます。
- 居住用ではない土地として売却する
- 橋をかけて住居用の土地として売却する
それぞれの売却方法について、具体的に解説していきます。
【方法1】居住用ではない土地として売却する
土地を求めている人が、必ずしも居住用の土地を求めているとは限りません。
田畑が隣接している場合は物置小屋を設置したり、駐車場として利用すれば、居住用以外の方法で活用できます。
そのため、居住用ではない土地として売却すれば、買主が見つかる可能性は高いです。
しかし、居住用ではない土地として売却する場合、買主が農家や駐車場オーナーなどに絞られてしまいます。
すぐ買主を見つけて売却したいと考えていても、なかなか買主が見つからず苦労するかもしれません。
【方法2】田畑として売却する
水路が残っているエリアは、田畑が残っている可能性もあります。
そのため、田畑が隣接している場合には、田畑として売却するという選択肢もあります。
ただし、現状が田畑の場合にはそのまま売りに出せますが、一度整地している場合に田畑として売り出すのは容易ではありません。
土地として売り出す際は、現状や需要などを考慮しながら決める必要があります。
橋をかけて住居用の土地として売却する
接道義務を満たしていない水路に面した土地は、建築基準法の要件を満たしていないため、基本的に建物を建設できません。
そこで、道路との間口が2m以上ある橋をかければ、接道義務を満たすため、建築基準法の要件を満たした土地として売却できます。
しかし、水路の所有権は土地所有者に付随しているわけではないため、橋は勝手にかけられません。
では、どのような手順で水路に橋をかければよいのでしょうか?橋をかけて住居用の土地として売却する手順は以下の3つです。
- 水路の占用許可を取得する
- 水路の占用許可を承継できるか確認する
- 建築時の条件について確認する
次の項目から、詳しく見ていきましょう。
水路の占用許可を取得する
水路は国や都道府県、市町村といった行政が管理しているため、橋をかけるには、水路の占用許可を申請しなければなりません。
市町村に水路の占用許可を申請しますが、占用料が発生する可能性もあるので注意が必要です。
例えば、京都市は水路の占用料として1㎡あたり年間750円支払わなくてはなりません。
自治体によっては占用料が変わってくるため、事前に確認しておきましょう。
水路の占用許可を承継できるか確認する
水路の占用許可を取得して、道路に2m以上接する橋をかけた場合、建築基準法の接道義務を満たした土地といえます。
ただし、買主に水路の占用許可が承継されるか、確認しておかなくてはなりません。
承継できない場合不法に水路を占用していることになるため、後で買主が自治体とトラブルに発展する可能性があります。
第三者に承継できない場合は、買主が次に水路の占用許可を取得するのにどんな手続きが必要か伝えておけば、買主も安心して土地を購入できるでしょう。
建築時の条件について確認する
水路に面している土地に、橋をかけて建築基準法の接道義務を満たしても、一般的な敷地と同様の建築条件が適用されるとは限りません。
宅地として認められても、容積率、建ぺい率、道路からのセットバックなど、何らかの制限が加わる可能性があります。
また、田畑が広がるような水路に面している土地は、都市計画区域内ではあるものの、用途地域の定められていない「市街化調整区域」で建物の建築に制限されていることもあります。
「建てられる住宅が制限されていると事前に知っていれば契約しなかった」いったトラブルを防ぐためにも、事前に土地に関する建築条件を確認しておきましょう。
水路に面した土地の建築条件が不明であれば、不動産に詳しい弁護士へ相談してもよいです。
水路に面している土地の売却における注意点
水路に面している土地の売却時には、以下の2点に注意しましょう。
- 橋をかけると費用がかかる
- 制限がある場合は告知義務と瑕疵担保責任がある
それぞれの注意点を1つずつ解説していきます。
橋をかけるには多大な費用がかかる
橋をかけると、道路と面することになるため、建築基準法の接道義務を満たせます。
しかし、橋をかけるには、水路を管理する行政の許可が必要になるだけでなく、橋をかける費用がかかります。
とくに、橋の上を車が通過するといったケースでは、橋の耐久性も上げなくてはなりません。
水路の幅や耐久性によって費用は大きく異なりますが、数百万円かかることが一般的です。
橋をかけることで水路に面した土地を売れたとしても、橋の工事費用で赤字になっては元も子もありません。事前に必要な費用を確認しておいた方がよいでしょう。
制限がある場合は告知義務と瑕疵担保責任がある
水路に面した土地を売却する際は「水路に面した土地であること」を買主に対して告知する必要(告知義務)があります。
水路に面した土地であることを告知しないまま売却した場合、売主は瑕疵担保責任を負うことになります。
瑕疵担保責任では、契約解除や損害賠償の請求が買主に認められています。ですので、売買契約が成立する前に必ず告知しましょう。
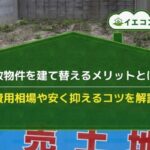
水路に面した土地の売却は「訳あり不動産専門の買取業者」がおすすめ!
これまで説明した通り、水路に面した土地を売却することは困難です。
一般的な不動産会社に査定を依頼しても、制限のある土地ということで査定結果が低くなる可能性が高いです。
買主がなかなか見つからないと、その間も固定資産税や都市計画税などを負担し続けなければなりません。橋をかける場合には、多額の費用がかかります。
そこで、水路に面した土地を売却するなら「訳あり不動産専門の買取業者」による買取がおすすめです。
買取業者に依頼すれば、最短数日で不動産を買取してくれるため、買主が見つかるまでの時間や手間を省けます。
売却したいなら
訳あり物件買取専門の
当社にお任せください!
まとめ
水路に面している土地は、建築基準法の接道義務を満たしていない土地が多く、売却時にトラブルに発展する可能性もあるため注意しましょう。
接道義務を満たすためには、建築基準法で定められている道路に2m以上接していなければなりません。橋をかけて接道義務を満たせば、建物の建築制限が解除されますが、水路は公共物なので勝手に橋をかけることはできません。
水路に橋をかける際は自治体の許可が必要になり、橋をかける費用として数百万円程度の費用がかかります。
水路に面している土地を売るのは容易ではないため、訳あり不動産の買取を専門とする不動産会社に相談することをおすすめします。
水路に面した土地の売却時によくある質問
「建築・再建築不可の恐れがある」「軟弱地盤である可能性が高い」といったリスクを抱えているため、通常の土地と比べて売却が困難です。
はい、売却可能です。「田畑や駐車場用の土地として売却」「水路の占用許可を取り、橋をかけてから売却」といった方法であれば、スムーズかつ相場に近い価格で売却できます。
告知義務と瑕疵担保責任に注意が必要です。「水路に面した土地」であることを伝えずに売却すると、損害賠償請求や契約解除される恐れがあります。
物件の瑕疵や欠陥をすべて説明する義務のことです。物件の取引時にかならずおこなわれます。
「訳あり物件専門の買取業者」へ売却するとよいです。契約不適合責任を負う必要がなく、最短数日で現金化も可能です。訳あり物件専門の買取業者はこちら→