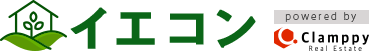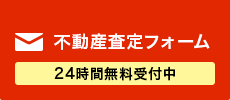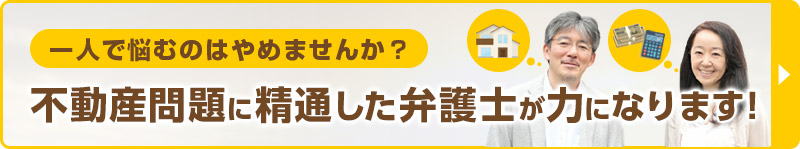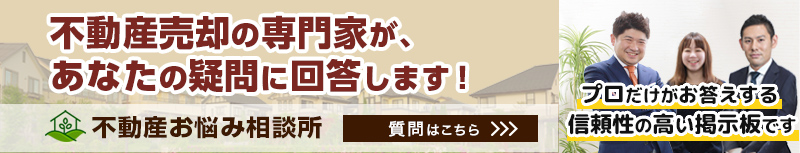土地を借り受ける権利「借地権」ですが、この借地権を売却することも可能です。
ただし、借地権を売却する場合、一般的な不動産売却と同様に譲渡所得税などの税金が発生する上、各種税金を収めなければ追徴課税が発生するので注意しましょう。
そもそも、借地権の売却は一般的な不動産売買よりむずかしいため、まずは専門の不動産業者に相談してみることをおすすめします。
なかでも、弁護士と提携した不動産業者なら、借地にかかる税金から確定申告の手続きまで、さまざまな法律的アドバイスを受けられます。
以下のリンクから、無料相談が受けられるので、借地権の売却方法から税金まで、気になる点を相談してみるとよいでしょう。
目次
借地権の税金は「取得時・取得後・売却時・相続時」に分けられる

借地権の税金は、4つのタイミングで課税されます。
- 取得時にかかる税金
- 取得後にかかる税金
- 売却時にかかる税金
- 相続時にかかる税金
借地権の売却における基礎知識として、それぞれの税金がどのように課税されるのか把握しておきましょう。
取得時にかかる税金
借地権の取得時にかかる税金は、次の3種類です。
- 印紙税
- 登録免許税
- 不動産取得税
印紙税は契約書類にかかる税金で、借地権取得時の契約書に課税されます。
登録免許税は不動産の権利について、法務局に登記する際にかかる税金です。
不動産取得税は、不動産を取得した人に課される税金で、借地権の場合も含みます。
各税金の内容を、次の項目から詳しく解説します。
1.印紙税
借地権を取得するとき、賃貸人を地主、賃借人を土地の借主とした土地賃貸借契約書を結びます。
土地賃貸借契約書は「地上権又は土地の貸借権の設定又は譲渡に関する契約書」である第1号文書の2にあたり、印紙税の課税対象です。
印紙税額は、記載された契約金額によって異なります。
例えば、契約金額が1億円以下の場合、印紙税は以下のとおりです。
| 記載された契約金額 | 課税額 |
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円〜10万円 | 200円 |
| 10万円〜50万円 | 400円 |
| 50万円〜100万円 | 1,000円 |
| 100万円〜500万円 | 2,000円 |
| 500万円〜1,000万円 | 10,000円 |
| 1,000万円〜5,000万円 | 20,000円 |
| 5,000万円〜1億円 | 60,000円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
「記載された契約金額」に、地代や敷金は含まないので注意しましょう。
印紙税は、土地の賃借権設定または譲渡の対価にあたる権利金が基準となります。
保証金や敷金、土地賃貸借契約成立後における使用収益上の対価である地代は記載金額に該当しません。
印紙税の軽減措置が受けられるケース
借地権付き建物を取得する場合などで、不動産譲渡契約書に「建物の譲渡価格」と「借地権の譲渡価格」があわせて記載されている場合は、印紙税の扱いが特殊になります。
不動産売買で使用する不動産譲渡契約書は、第1号文書の1にあたり、2022年3月31日までの間に作られた契約金額が10万円を超えるものは軽減措置の対象です。
下表のような軽減税率が適用されます。
| 記載された契約金額 | 課税額 |
| 10万円〜50万円 | 200円 |
| 50万円〜100万円 | 500円 |
| 100万円〜500万円 | 1,000円 |
| 500万円〜1,000万円 | 5,000円 |
| 1,000万円〜5,000万円 | 10,000円 |
| 5,000万円〜1億円 | 30,000円 |
そして、軽減措置の対象である建物譲渡に関する契約金と、軽減措置の対象外である借地権の譲渡に関する契約金が併記されているものについても、軽減措置の対象になると定められています。
この場合、契約書に記載された合計金額4,000万円に対して、軽減後の税率が課税されます。
そのため、印紙税は1,000万円〜5,000万円の10,000円になります。
このように借地権を取得する場合、軽減税率が適用されるケースもあるので、正しい金額の印紙を貼るように注意しましょう。
また、契約書の原本の数だけ印紙税が必要になります。
そのため、原本は1冊のみで地主が所有し、借主と連帯保証人は原本のコピーを保管するような場合、印紙は1冊分のみで大丈夫です。
地主、借主、連帯保証人がそれぞれ契約書の原本を所有する場合は、その数に合わせて印紙が必要になります。
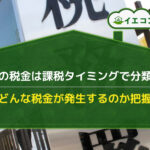
参照:国税庁 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
参照:国税庁 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
2.登録免許税
登録免許税は、登記簿に登記するときに必要な税金です。
一般的には、借地権を取得した場合、借地上の建物を登記します。
借地権が賃借権の場合、地主に登記への協力義務はないため、借地権を登記することはほとんどありません。
しかし、登記しなければ第三者に借地権を主張できず、底地の売却などで地主が変わった際にトラブルの原因になるからです。
そして、借地上の建物を登記する場合、2種類の方法があります。
| 新築の場合 | 所有権保存登記 |
|---|---|
| 中古住宅の場合 | 所有権移転登記 |
基本的な税額はそれぞれ、以下のようになります。
| 所有権保存登記 | 固定資産税評価額の0.4% |
|---|---|
| 所有権移転登記 | 固定資産税評価額の2% |
登録免許税の軽減税率が受けられるケース
個人が2020年3月31日までの間に住宅用家屋を取得して、自分が住むために登記した場合は軽減税率の対象となります。
ただし、軽減税率の適用を受けるには、以下のような一定の要件を満たす必要があるので、事前に確認することが大切です。
- 床面積が50㎡以上であること
- 新築または取得後1年以内の登記であること
建物の登記は義務ではないので、登記しなければ登録免許税はかかりません。
しかし、借地権を第三者へ主張できずにトラブルが起こりやすいので、借地権の取得時には、必ず建物の所有権登記をするようにしましょう。
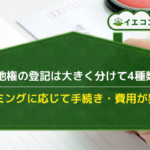
3.不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を取得した人に対して、都道府県が課税する税金です。
この税金は不動産を登記しているかどうかに関係なく、課税されます。
借地権は土地に対して設定する権利ですので、課税対象外ですが、借地権とともに取得した建物に対して不動産取得税がかかります。
借地上の建物にかかる不動産取得税の税額は、固定資産税評価額から控除額を除いた金額×3%です。
不動産取得税の軽減税率が受けられるケース
借地上の住宅取得時にかかる不動産取得税の軽減制度もあります。
軽減制度が適用されるには、必要書類を所管の都道府県税事務所に申告する必要があるため、要件を満たせば自動で適用されるものではないので、気をつけましょう。
具体的な手続きについては、所管の都道府県税事務所で相談することをおすすめします。
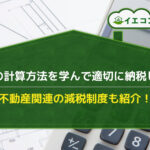
取得後にかかる税金
借地権を取得後、所有している間にかかる税金は「固定資産税」と「都市計画税」で、毎年1月1日時点での所有者に課税されます。
そのため、借地権の取得年では、売買契約成立日を境に、売主と日割で清算することが一般的です。
そして、固定資産税・都市計画税はどちらも不動産そのものにかかる税金で、土地を使用する権利である借地権には課税されません。
つまり、借地権の取得後にかかる税金は建物部分のみということになります。
借地権の取得後にかかる税金は、基本的に以下のとおりです。
| 固定資産税 | 固定資産税評価額の0.4% |
|---|---|
| 固定資産税 | 固定資産税評価額の2% |
取得後にかかる税金の軽減措置が受けられるケース
固定資産税は新築後3年間または長期優良住宅は5年間、120㎡以下の部分の税額が1/2に減額される軽減措置があります。
固定資産税の軽減措置については、特に申請する必要はありません。
市区町村から送られてくる納税通知書には、反映された税額が記載されているので、一括または年4回の分割で納税します。
また、固定資産税評価額は3年ごとに見直しが行われています。これを「評価替え」と呼び、2018年・2021年・2024年と続きます。
評価替え年度の合間にある年は、評価額が据え置きとなります。
そして建物は築年数が古くなるにつれて固定資産税評価額も落ちていくので、固定資産税・都市計画税の納税額も3年ごとに減っていきます。
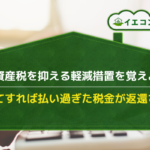
売却時にかかる税金
売却時にかかる税金は「印紙税」「譲渡所得税」の2種類です。
譲渡所得税とは、借地権付き建物を売却したときの利益に対してかかる所得税と住民税のことです。
譲渡所得税の税率は、譲渡した年の1月1日時点での所有期間によって、以下のように異なります。
| 所有期間 | 所得税 | 住民税 | |
|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下の場合 | 30% | 9% |
| 長期譲渡所得 | 5年超の場合 | 15% | 5% |
また2037年12月31日までは、復興特別所得税として短期譲渡所得の場合は0.63%、長期譲渡所得の場合は0.315%が課税されます。
譲渡所得の計算は、譲渡価格から取得費と譲渡費用、特別控除を除いて算出します。
譲渡価格-取得費-譲渡費用-特別控除
取得費とは、借地権付き建物を取得するためにかかった費用のことです。
借地権については権利金や更新料は取得費に分類されますが、敷金や保証のような借地権者に返還される性質のものは取得費とはみなされません。
建物については購入代金や建築代金、登記費用などが含まれます。
譲渡費用には、印紙税や不動産会社への仲介手数料、第三者へ売却するときに地主へ支払った譲渡承諾料が含まれます。
売却時にかかる税金の軽減措置が受けられるケース
売却した借地権付き建物がマイホームだった場合、一定の要件を満たすことで3,000万円特別控除の特例を受けられます。
敷地が借地権でも適用要件を満たすので安心してください。
3,000万円特別控除を適用できれば、実質3,000万円までは無税で手元に残すことができるので非常に重要なものです。
ただし、この特例を受けるには要件を満たしているだけでは十分ではなく、必要書類を揃えて確定申告する必要があるので注意しましょう。
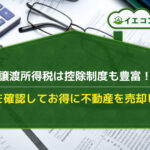
相続時にかかる税金
借地権を相続で取得した際にかかる税金は「相続税」「登録免許税」の2種類です。
- 相続税
- 登録免許税
登録免許税は、相続登記のときに必要で、固定資産税評価額の0.4%です。
ただし、借地権が登記されていない場合は借地権の登録免許税は不要で、建物の部分のみとなります。
相続税とは、借地権を含む相続財産すべてが基礎控除額を超えた場合にかかる税金で、借地権も相続税の課税対象なので、借地権価格という評価額で相続財産に加算されます。
そして、借地権価格の算出方法は、借地権の種類によって異なります。
まず、旧法借地権や普通借地権の場合は、路線価図や評価倍率表をもとに算出される更地価格に借地権割合を掛けることで求めます。
相続時にかかる税金の軽減措置が受けられるケース
定期借地権の場合は、単純に借地権割合を掛けるだけでなく、借地権の残存期間なども考慮して算出されることになっています。
また敷地が借地権であっても、小規模宅地の特例は一定の要件を満たすことで適用されます。
その場合、借地権の評価額を大幅に減額できて相続税も減らせるので、要件を満たしているか確認するようにしましょう。
「相続」と「遺贈」では借地権の取り扱いが異なる

借地権者が亡くなったとき、借地権は「相続」される他に、遺言によって法定相続人以外の方に「遺贈」される場合もあります。
相続も遺贈も、亡くなった方から特定の方に財産が移転するという点では共通ですが、借地権の取り扱いが異なるので注意が必要です。
その違いは、地主の承諾についてです。
借地権を相続によって取得する場合、地主の承諾は必要ありません。
遺贈によって取得する場合には、第三者への譲渡とみなされるので地主の承諾が必要になります。
遺贈で借地権を取得する場合は地主の承諾が必要
承諾を得るためには、遺言で指定された受遺者だけでなく、相続人全員の連署で遺贈があることを地主に通知して、承諾請求をおこないます。
また、遺言の内容を実現するために必要な手続きを一任された遺言執行者がいれば、受遺者と遺言執行者のみの連署で大丈夫です。
このとき、地主の承諾と合わせて承諾料や名義書換料の支払いが必要になる場合が多いので、受遺者はある程度の資金を準備しておいた方が安心でしょう。
そして、承諾を得られたら、速やかに建物の所有権移転登記をおこないます。
相続の場合は所有権移転登記をしていなくても、第三者へ借地権を主張できますが、遺贈の場合は登記していなければ権利を主張できなくなるからです。
また、もし遺贈となって、受遺者が新しく借地権者になることについて地主の承諾を得られない場合、裁判所へ地主の承諾に変わる許可を申立てします。
裁判所から許可を得られた場合でも、地主に承諾料として借地権価格の10%程度支払うことが一般的です。
そして、裁判所に申立てしても許可を得られなかった場合、遺贈はできないので、借地権は法定相続人に相続されることになります。
このように遺贈は相続に比べて必要な手続きが多く、手続きに漏れがあると借地契約を解除される恐れもあります。
そのため、借地権の遺贈を受ける場合には弁護士や税理士などの専門家へ相談するようにしましょう。
相続した借地権を売却したいときの手続き

相続した借地権を売却したいときには、自分で取得した借地権を売却するときとは異なる2つの手続きが必要です。
- 借地権が相続登記する
- 相続人全員の同意を得る
それぞれの手続きを順番に解説していきます。
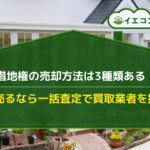
借地権を相続登記する
相続して何も手続きしなければ、借地権の名義は亡くなった被相続人のままですが、借地権を売却するときには、借地権の名義は自分である必要があります。
この場合、借地上の建物の名義を被相続人から自分名義に変えます。
所有権移転登記の申請をする際に、どのような形で記入すればよいのかは、法務局のホームページで確認できます。
具体的な手続きについても、管轄の法務局や司法書士などの専門家に相談すれば教えてもらえます。
また、相続人が複数いる場合には、遺産分割協議書も必要です。
このとき、借地権も特定の1人に相続させるのか、共有不動産として相続するのか考える必要があります。
もしくは、借地権を売却して代金を分ける換価分割をおこなう方法もあるでしょう。
どのように遺産を分けるのか、遺産分割協議書に書面という形でまとめます。
共有不動産として相続する場合には、相続人の共有名義で所有権移転登記をすることになります。
相続人全員の同意を得る
借地上の建物が共有名義になっていると、売却するときには相続人全員の同意が必要です。
そのため、実印や印鑑証明書、住民票の写し、本人確認書類といった書類は共有者全員が用意します。
さらに、契約締結時や売却代金の決済時には、共有者全員が立ち会う必要もあります。
このように共有不動産の状態で売却するときには手続きが大変です。
そこで、換価分割をする際には、共有名義に変更するのではなく、相続人から代表者を決めて、その人物が単独名義で登記した後に売却手続きをおこなう方法もあります。
ただし、単独名義で換価分割する場合、遺産分割協議書を作成しないと、分配した金額が贈与とみなされて贈与税の課税対象になってしまうことも多いです。
後々のトラブルを避けるためにも、単独名義で換価分割をするときには弁護士などの専門家に書類作成を依頼したほうが安心でしょう。
この2つの手続きを行ったあとは、通常の借地権の売却と同様の流れとなります。
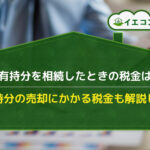
相続の手続きから借地権の売却まで当社にお任せください
相続した借地権を売却するには、いくつも手順を踏む必要があります。
遺産分割協議や相続登記、売却の手続きなど、不動産知識が少ない方にとっては複雑で考えるのも嫌になるほどです。
そこで当社クランピーリアルエステートは、不動産業者の専門知識と弁護士や司法書士と形成している独自ネットワークを活かして、借地の相続から買取まで一貫したサポートが可能です。
権利関係が複雑な物件や不動産トラブルで遺産分割が進まない相続などに対して、的確なアドバイスがおこなえるので、無料相談でぜひお気軽にご相談ください。
売却したいなら
訳あり物件買取専門の
当社にお任せください!
借地権の売買は消費税がかからない
日常、何かモノやサービスを売買するときには消費税がかかりますが、借地権の売買は消費税の課税対象ではありません。
国税庁の非課税となる取引にも「借地権などの土地の上に存する権利を含みます」と明記されています。
借地権付き建物を不動産業者などの事業者から購入する場合、建物部分には消費税がかかりますが、売主が個人であれば、建物の部分も消費税は不要です。
そのため、借地権付き建物を売却する時、消費税はかかりません。
参照:国税庁

まとめ
借地権に対する税金は、取得時・取得後・売却時・相続時の4つのタイミングで課税されますが、借地権を売却したときにかかる税金は印紙税と譲渡所得税の2種類です。
借地権を売却するとき、売却価格によっては多額の譲渡所得税がかかる恐れがあります。
しかし、特例を活用すれば納税額を大幅に減らせるので、借地権を売却する際には、税金関係にも詳しい不動産業者と相談しながら進めるようにしましょう。
すでに借地権を売却している場合、弁護士や司法書士に相談して、どのような税金の控除が受けられるかをアドバイスしてもらうことをおすすめします。
借地権の税金に関するよくある質問
「取得時」「取得後」「売却時」「相続時」という、4つのタイミングで税金が課税されます。
「印紙税」「登録免許税」「不動産取得税」の3種類です。
基本的には「固定資産税」「都市計画税」の2種類です。
「印紙税」「譲渡所得税」の2種類です。
「相続税」「登録免許税」の2種類です。